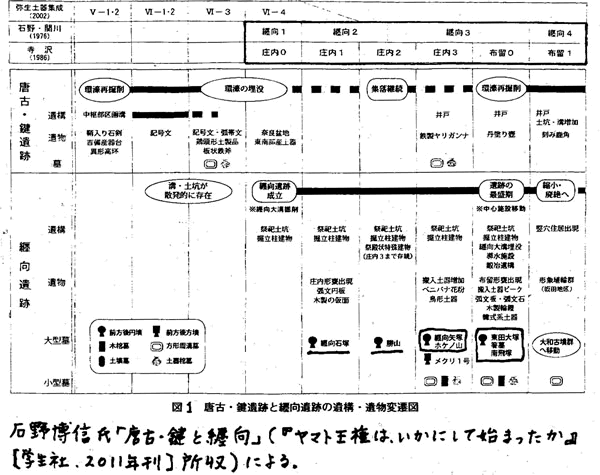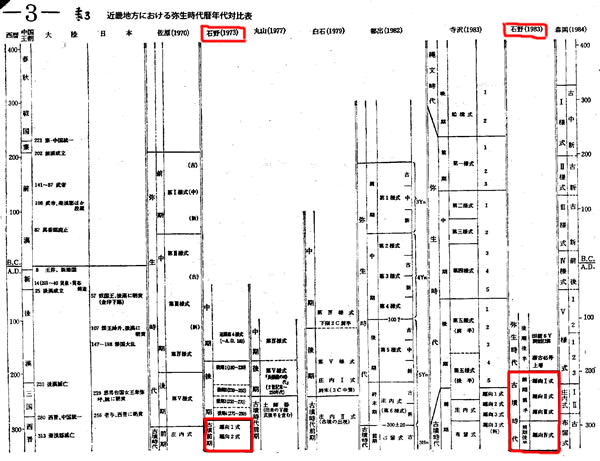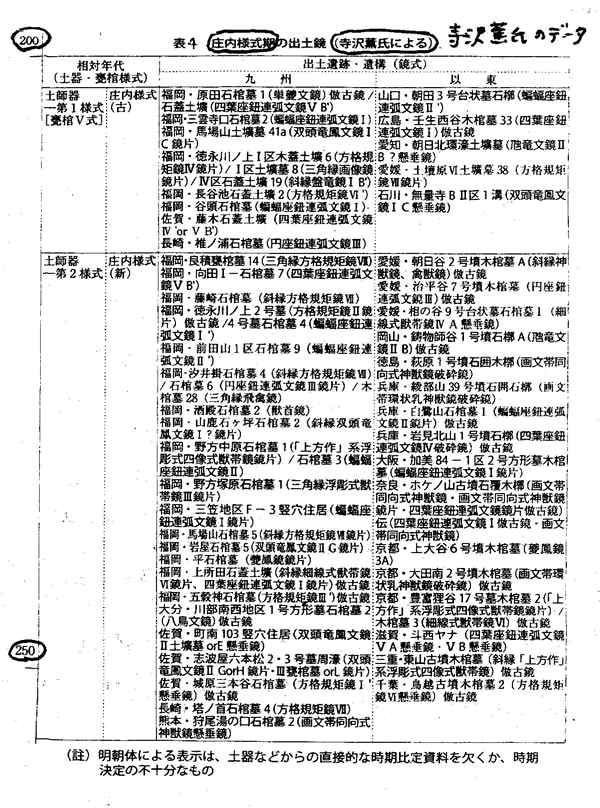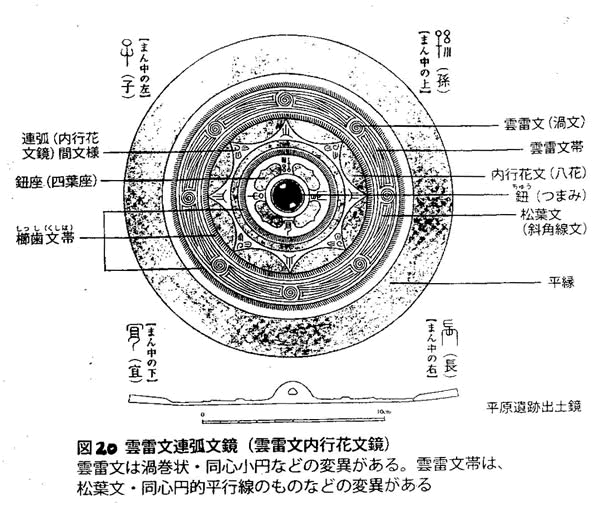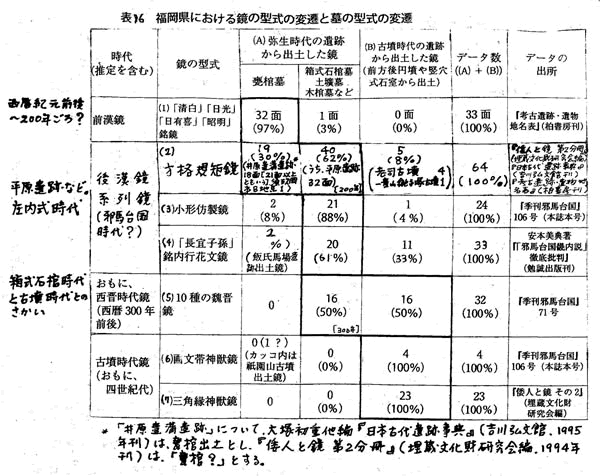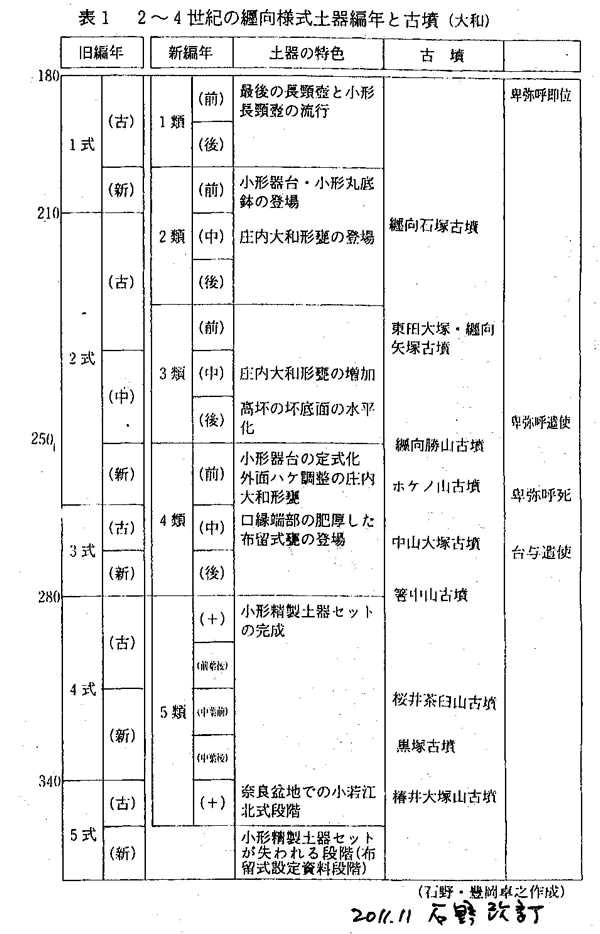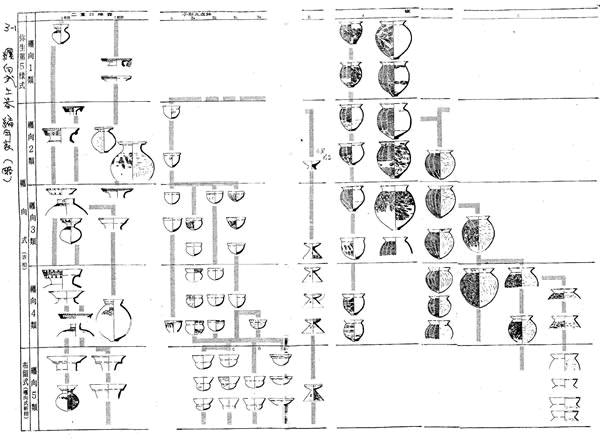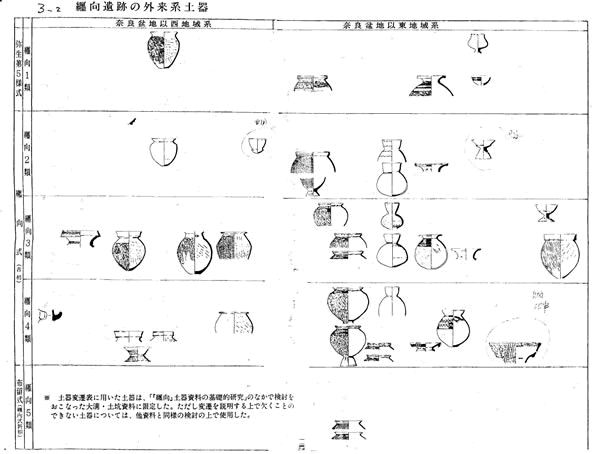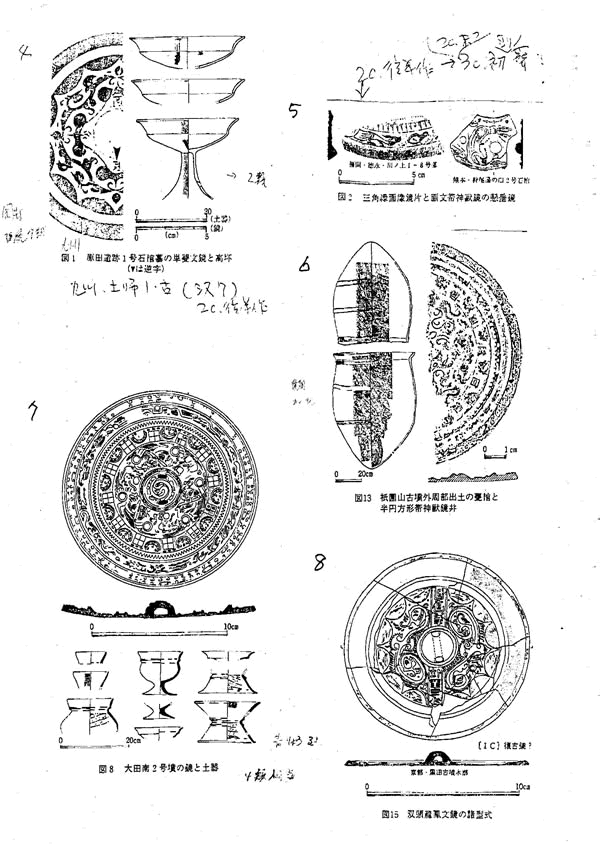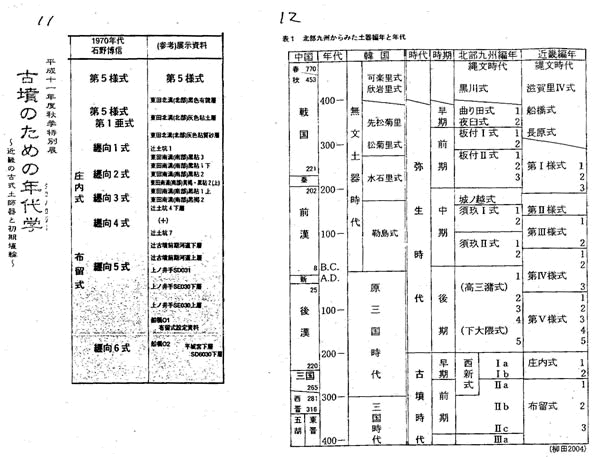| TOP>活動記録>講演会>第304回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第304回 邪馬台国の会(2011.11.27 開催)
| ||||
1.安本先生講演・纒向式土器の相対年代と歴年代
|
石野先生との議論はこれが4回目となる。 ■土器の編年
・近畿地方における弥生時代歴年代対応比表 石野先生は1973の時点では、表のように纒向1式など土器を比較的新しく編年していた。
1984ではだいぶ古い時代にシフトした。
・土器の絶対年代は確実ではない。 三世紀の終りごろ(西暦280年~300年ごろ) 三世紀の中ごろ(西暦250年前後) 新聞などで発表される土器の年代は、暫定的なものであって確実なものではない。 ■「再現性」の問題 2006年5月13日(日) ■「事実」と「意見」とについて 「美人」という言葉は、一義的ではない。意見としては「美人かどうか」であるが、客観的要素としては「二重まぶたかどうか・身長155センチより高いかどうか」である。 ■客観性や再現可能性 ・池田清彦著『科学とオカルト』(講談社文庫2007年刊) ・具体的に庄内式土器と一緒に出た、鏡のデータ どんな鏡が多いかについても、奥野氏、小山田氏、寺沢氏のデータは内行花文鏡、方格規矩鏡が多いことになる。 どのような墓から出るかについても、奥野氏、寺沢氏は同じで、箱式石棺から多く出る。 奈良県に圧倒的に多いのは前方後円墳、三角縁神獣鏡、画紋帯神獣鏡である。これらは布留式土器の時代となる。 ■中国考古学者たちの見解 また、王仲殊氏とならんで、中国を代表する考古学者である徐苹芳氏も、つぎのようにのべる。 寺沢薫氏の示された表のデータによるとき、福岡県から出土した30面の庄内期出土の鏡のうち、王仲殊氏、徐苹芳氏のあげる「方格規矩鏡」「内行花文鏡」「獣首鏡」「夔鳳鏡」「双頭竜鳳文鏡」のいずれかにあてはまるものは24面を数える。
王仲殊氏はのべている。 ■貨泉の問題 雲雷文連弧文鏡(内行花文鏡の一種)は190年を下限とする洛陽焼溝漢墓から出てくる、300年ごろの洛陽晋墓からも出てくる。日本では平原遺跡からも出てくるし古墳時代からも出てくる。これが日本で一番多く出てくるのはやはり福岡県である。
■墓制の変遷 (2)箱式石棺墓葬・石蓋土壙墓葬 (4)横穴式石室葬 (1)の甕棺墓葬と、(2)の箱式石棺墓葬・石蓋土擴墓葬は、おもに、北九州に分布する。
■福岡県における鏡の形式の変遷と墓の形式 前漢鏡から、古墳時代鏡までについて、どのような墳墓(甕棺墓、箱式石棺墓、前方後円墳)から出て来たものが多いかについての表から、西晋時代鏡は箱式石棺と前方後円墳で半分づづとなる。これが庄内式と布留式土器の境目となると考えられ、そのひとつ前の時代が邪馬台国時代のもではないか。つまり後漢鏡系列(方格規矩鏡、小形仿製鏡、長宜子孫銘内行花文鏡)である。
中国の社会科学院考古研究所楊氾氏は、つぎのように述べている。 寺澤さんのデータでも、200年~250年の鏡は圧倒的に北九州から出ている。 |
2.石野博信先生講演・纒向式土器の相対年代と歴年代
|
今日は邪馬台国がどこにあったは触れないで、土器の相対年代から暦年につないでいくことについて話したい。 纒向に幅5メートル、推定長さ2600メートルの水路があり、ここから何百個の土器が出てくる。この中でも少し、層位の乱れがある。 「庄内式土器」は大阪の豊中市の庄内という土地から出たので、布留式以前の土器として庄内式としたもの。この名前が一般的に通っているが、弥生5様式より新しく、布留式より古いとされたもので、邪馬台国時代ではないかと言われている。今回の話は「纒向式土器」として話す。 表1にあるように、纒向1式2式3式4式から5年前に、纒向1類2類3類4類と表記を変えた。しかしまだこの表記は浸透していないが、正しいのはこの「類」表記である。
唐子・鍵遺跡を中心とした弥生5様式が細かく5種類に細かく分けられているが、その最終期の分類に当たるのが纒向1類となる(纒向の始まる時期)。布留式になるのが纒向5類で、纒向の最終期となる。また纒向4類を寺沢氏は布留式の要素が出始めた庄内式なので、布留0式とした。 壷に波型、丸いボタンみたいなものが付いており石垣波状紋といわれている。これは加飾壷[かしょくつぼ](かざりかけた壷)で、加飾壷は弥生5様式には無く、纒向2類から現れ、3類、4類、5類へと続き、纒向5類になると無くなる。 小形丸底の土器(直径10センチ程度)が纒向2類から出てきて、3類、4類と5類の布留式まで続く。これはかけらでは4類では布留式と見分けが付かなくなってくる。 小形器台も纒向2類から出てきて、5類まで続く。そして形が微妙に変化して行き、4類では縁のところが変わってくる。 布留式土器の目安となる小形土器3種が纒向5類から出てくる。これが全国的に広がってくる(土器の斉一化)。近畿を中心として、文化が土器としても全国的に広がったといえる。これが前方後円墳の時代で、大和政権の全国制覇となる。 弥生5様式の甕が纒向4類まで使われる。専門家でも弥生5様式と纒向4類の甕の区別ができないくらいのものである。弥生的な煮焚きに使う甕が使い続けられるのである。 庄内甕と言われる薄甕は厚みが2mmから1mmである。この庄内甕が現れるのは纒向4類からで、纒向5類(布留式甕)まで続く。 纒向2,3,4類の土器の違いは、出土した土器の数が多くないと難しく、少なくとも5~6個は見つからないと難しい。
・纒向遺跡の外来系土器
邪馬台国畿内説では、狗奴国は東海地方との説があるが、大きな銅鐸を持っているのは東海であり、近畿と東海は仲がよいので、狗奴国ではないのではないかと思われる。これは土器の交流でもいえる。この交流は東海系の土器が近畿に来ており、近畿土器の東海への移動量は少ない。
・出土鏡 4番 7番 8番
・庄内式土器と布留式土器の出土層(「古墳のための年代学」から) 纒向2式土器の変化 纒向2・3式土器の変化 纒向3式(纒向4類)土器の変化 ・北部九州からみた土器編年と年代 九州の多々良込田遺跡から西新ⅠB期、纒向3類
このように九州と纒向の土器の関係を比較している。
・弥生~古墳時代初頭における中国鏡の出土状況 |
3.安本先生・石野先生対談
|
①岡村秀典氏の鏡の年代 ・石野先生回答
・石野先生回答 ③土器の共伴関係 ・石野先生回答 九州の庄内式土器と近畿の庄内式が同じ形でも一緒に使われたか分からないではないかということに対し、 九州の西新式土器が近畿でも30箇所くらい出ているし、数は少ないが近畿の庄内式土器が九州でも出ている。だから、九州に対し近畿の庄内式土器が20年~100年も開くことは考えられない。 九州から多くの鏡が出て、近畿から出て来ないことについては別問題である。 しかし、九州で掘っている箱式石棺、甕棺、に対し、近畿で庄内段階の纒向2・3・4類の方形周溝墓は少ない。同じ時期の土器を出している墓はホケノ山程度で、同時に中山大塚は盗掘を受けており中身はよく分からない。 ④邪馬台国問題は魏志倭人伝に書かれていることで議論すべき ・石野 ・安本 ⑤貨泉 ・石野 ⑥次回 ・石野 |
| TOP>活動記録>講演会>第304回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |