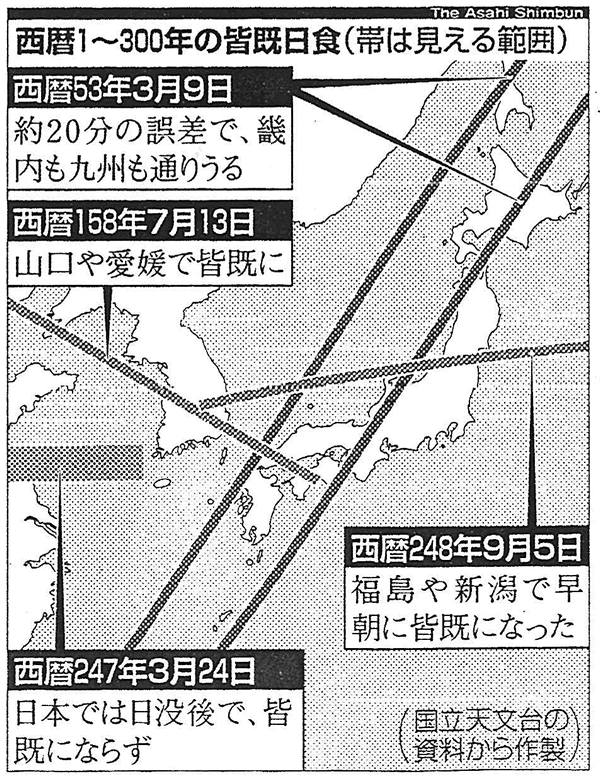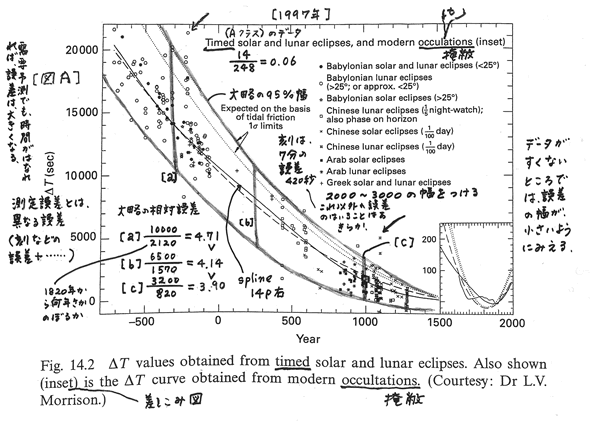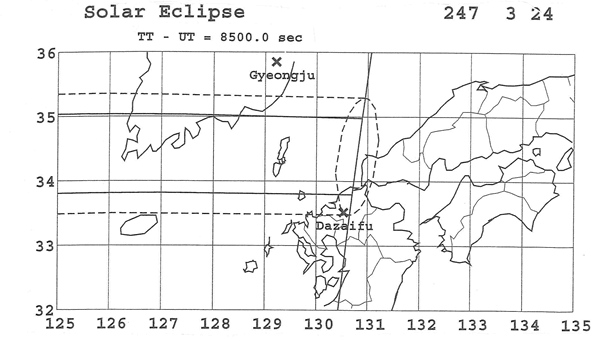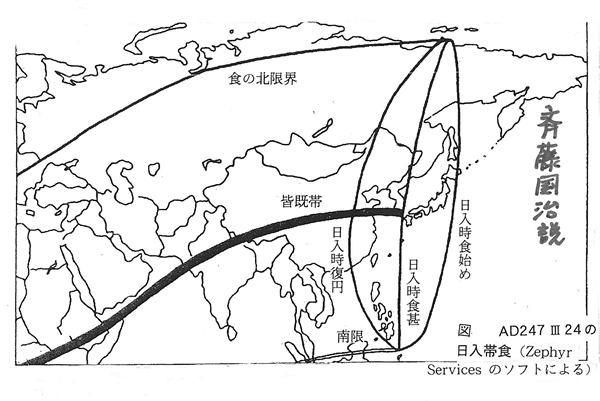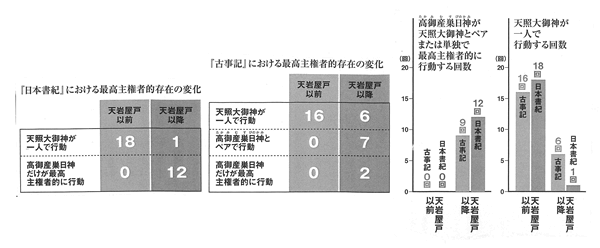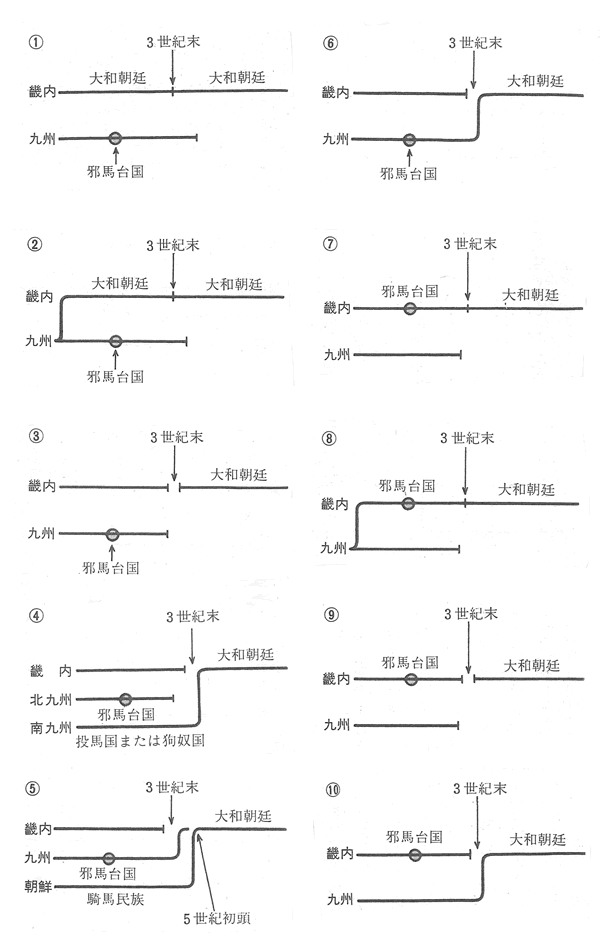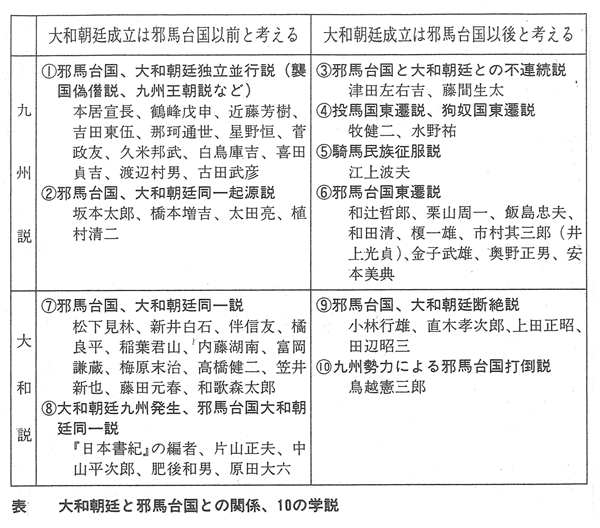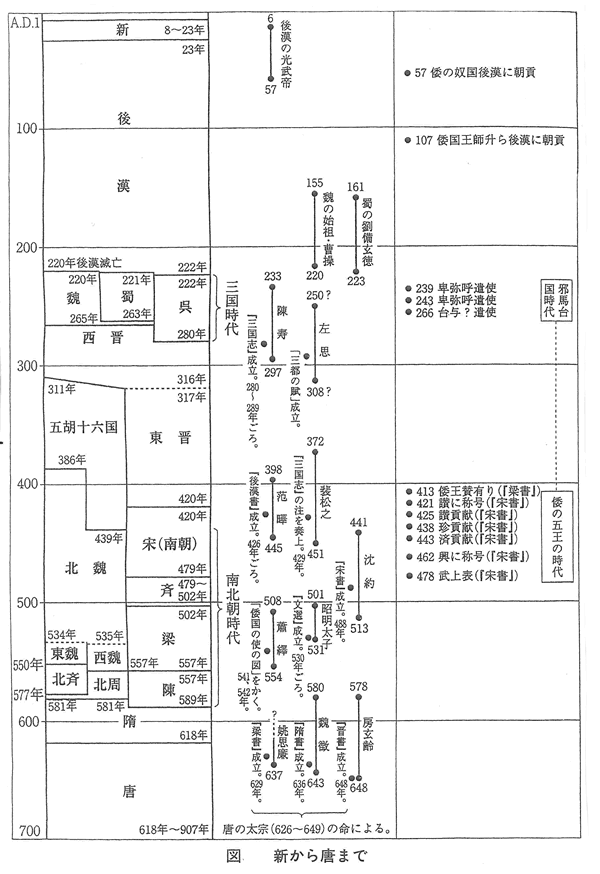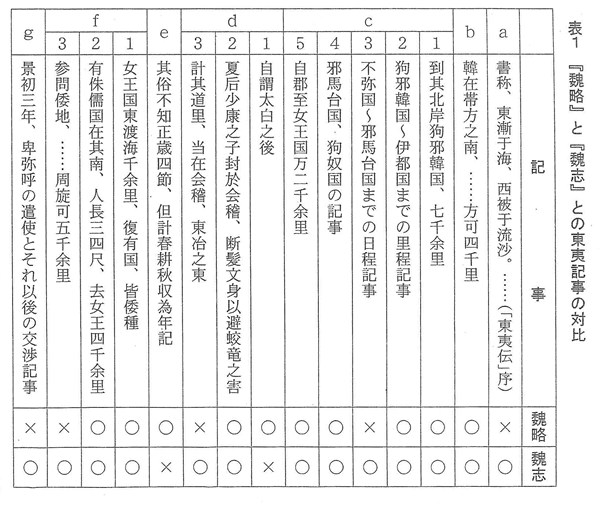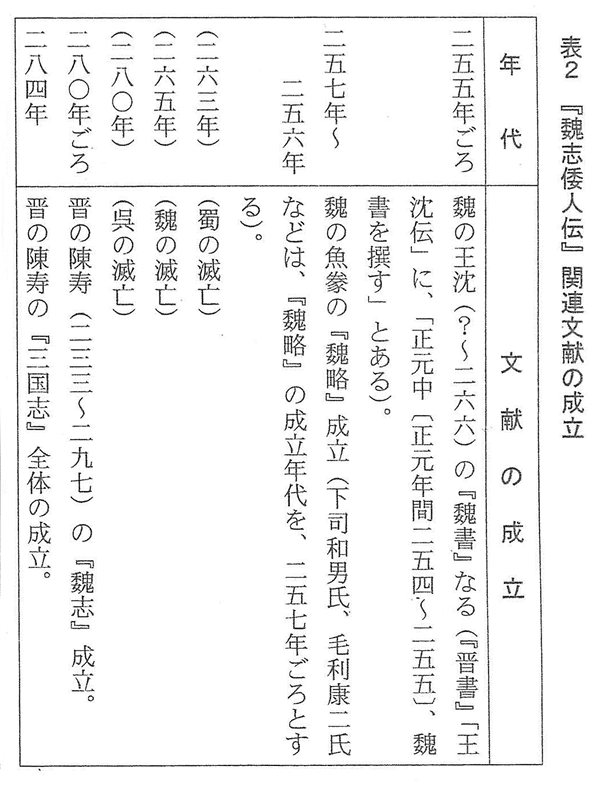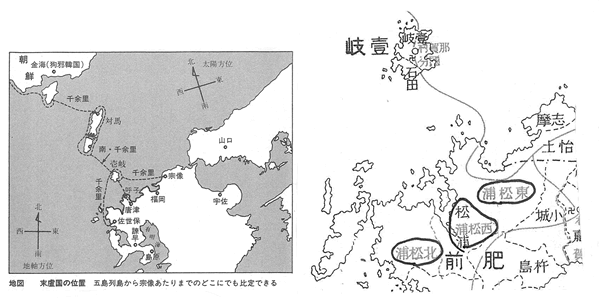| TOP>活動記録>講演会>第319回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第319回 邪馬台国の会(2013.5.26 開催)
| ||||
1.天岩戸事件と日食
|
『朝日新聞』の記事で「247年の日食は日本では日没後で、畿内、九州では皆既日食が見られなかった」とした。 『朝日新聞』2010年3月28日(日)朝刊の記事[参考] ①日食補正の計算の出発点の元になっている『三国遺事』延烏郎・細烏女の記事問題 延烏郎細烏女の話[参考で一部記載] この記事は何日間も太陽や月が消えている。これは皆既日食の話か?火山の可能性もある(朝鮮半島で白頭山の噴火なども考えられる)。 『三国史記』に阿達羅尼師今(アタルラニサコム)[アタルラ王]の時代4年(西暦157年)の記事に日食の記述がない。また、20年(西暦173年)5月倭国の女王、卑弥呼が使臣を遣わして修交したとあり、この年代は信頼性に乏しく資料として使われない。 この年代について、那珂通世は、「上世年紀考」のなかで、つぎのようにのべている。 このように西暦158年としている頃は日本も朝鮮も伝承の時代である。
②Stephenson(スティーブンソン)によるΔTについての取り扱い ΔTは重要なパラメータで、この計算で採用するデータはStephensonが注意を喚起している。 その結果のグラフが、下図となり、そのグラフから、時代が古くなると、誤差がだんだん大きくなる。西暦300年頃[b]で4.14の幅。統計的に処理することが重要となる。 また、『朝日新聞』の記事の元の論文で、延烏郎細烏女の話は日時の記載がないので、Stephensonによる「untimed」扱いとなる。その他でもStephensonの注意に反しているようだ。
■修正論文 ・西暦247年3月24日の日食について 『朝日新聞』の記事の元の論文において、谷川・相馬は「天の磐戸」日食の候補を探した。その際、『三国遺事』の「延烏郎細烏女」伝説が重要な役割を果たした。すなわち、伝説に「このとき新羅では、太陽と月の光が消えてしまった」とあるのを皆既日食と解釈し、『三国遺事』の作者が意図する時代を信用して紀元158年7月13日(ユリウス暦)の日食であるとした。当時の△Tを幅広く動かしても新羅の首都慶州(Gyeongju)において深い食であることは確かである。『朝日新聞』の記事の元の論文では、この日食の皆既帯が慶州を通るとして、 7692秒<△T<7933秒を得た。この値を信用するなら、 100年後の紀元247年前後に△T=8500秒に増えることは考えにくい。『朝日新聞』の記事の元の論文の記述を再録すると、「247年当時は△T=7300秒あたりなので、この日食も候補からはずれてしまう」これが谷川・相馬の結論であった。 朝鮮の古代史は過去に向かって引き伸ばされている可能性があると指摘する歴史学者がいる。すなわち、「韓史モ、上代ニ遡ルニ随ヒ、年歴ノ延長セリト覚シキ所アルコトハ、殆卜我ガ古史ニ異ナラズ」(那珂通世)。「延烏郎細烏女」伝説が日食について述べているにしても、紀元150年代ではなく、もっと現代に近いかもしれない。そうだとすると、『朝日新聞』の記事の元の論文の前提は崩れ、結論はあやしくなる。 正始8年春2月朔(西暦247年3月24日)の日食に関する直接の記録が三國志と晋書にある。とくに三國志巻十四と晋書巻十二の情報は、実際に日食を観察したことが読み取れて有用である。本論文は、この情報を考慮に入れて△Tの範囲、および当該日食が日本で皆既または皆既に近い日食であったかどうかを調べることを目的とする。三國志および晋書の記事をここに載録しておく。(注:三國志巻十四と晋書巻十二の原文表記省略) 『三国史』の記述要約: 晋書の記述もほぼ同様なので省略する。ただ、蒋濟(しょうせい)の上奏文の直後に以下の文章が続く。それによると、不吉な日食に正しく対処しないと国が亡びることもあり得ると歴史家は考えていたようだ。 『晋書』巻十二の一部訳: 『朝日新聞』の記事の元の論文と違って、紀元247年には△T>7750秒が得られた。上の限界は求めることができなかった247年3月24日の日食が北九州で皆既になるかどうかは興味深い。△T=8500秒,8900秒,9700秒の3つの場合に皆既帯および食分0.99帯を計算してみる。結果は下図に示した図に見られるように北九州市周辺は皆既になるが、福岡市や佐賀市は皆既帯からはずれ、いずれの場合も食分0.99ないし0.98となる。 天照大御神は卑弥呼のことが神話化・伝承化したものであり、天照大御神の天の磐戸伝承は卑弥呼の死と関係する、との見解がある。卑弥呼の死の前後と見られる紀元247年に北九州で、皆既または皆既に近い日食があったことは、注目に値する。下図参照
・
和辻哲郎は、次のように考えた。 ・天岩屋戸事件後、激変する
彼女の行動が意味すること 天照大御神が、須佐男之命の乱暴に怒って、天岩屋戸にこもったという神話は、太陽の神とされていた天照大御神(卑弥呼)の死の前後に、深い日食があったので、古代人にとっては、衝撃が大きく、それが、神話化したものであろうとする説がある。 ・ところで、『古事記』『日本書紀』に記されている日本の神話を、ていねいに読むと、次のようなことに気がつく。 ②『日本書紀』の本文では、天岩屋戸以前と後で、さらにはっきりと、一線を画しているようである。天岩屋戸の後、すべての命令などは、高御産巣日神(『日本書紀』では、「高皇産霊尊」と記している)ただ一人の名によって行われている。あたかも、天岩屋戸の事件以前においては、天照大御神が高天原の主権者であり、天岩屋戸から後においては、高御産巣日神が高天原の主権者であるかのような取り扱いである。
|
2.邪馬台国についての諸説
|
卑弥呼のことを神話化したものが天照大神とする。21代雄略天皇(倭王武)が478年に宋へ使いを出したことから天皇1代平均9.56あるいは9.6年で25代さかのぼると、天照大神の活躍時期は239または238年となる。そして『古事記』、『日本書紀』の記述から、250年~260年に出雲の国譲り、270年~280年に神武天皇の東遷の前に邇芸速日命などが大和に入り、280年代になって神武東遷となる。 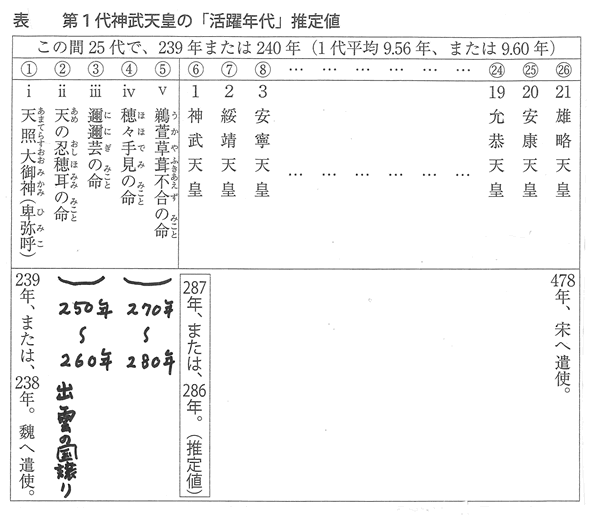 このように考えると歴史のつじつまがあうだろう。 しかし、これに対し邪馬台国について、いろいろな説がある。 ■邪馬台国と大和朝廷成立の関係の学説 ①邪馬台国、大和朝廷独立並行説 ②邪馬台国、大和朝廷同一起源説 ③邪馬台国と大和朝廷との不連続説 ④投馬国東遷説、狗奴国東遷説 ⑤騎馬民族征服説 ⑥邪馬台国東遷説 ⑦邪馬台国、大和朝廷同一説 ⑧大和朝廷九州発生、邪馬台国大和朝廷同一説 ⑨邪馬台国、大和朝廷断絶説 ⑩九州勢力による邪馬台国打倒説 |
3.『魏志倭人伝』はいつ、どこで、誰が書いたか |
『魏志倭人伝』とふつういわれているものは、晋の陳寿(233~297)の編纂した『三国志』のなかの、魏の国の歴史を書いた『魏志』(正確には『魏書』。『三国志』のテキストそのものでは、『魏書』『蜀書』『呉書』などと記されている)のなかの、「烏丸鮮卑東夷伝(うがんせんぴとういでん)」のなかの、「倭人の条」のことである。私たち日本人の祖先の1700年以上まえの姿が、そこに描かれている。 ■『魏志倭人伝』は、いつ書かれたのであろうか。 (2)『三国志』のなかの、『魏志(魏書)』の成立した時期を、『魏志倭人伝』の成立した時期と考える。『魏書』『蜀書』『呉書』は、もともと、別々に書かれたものであり、『魏書』の成立は、『三国志』全体の成立よりも早かったことが考えられる。 (3)魚豢(ぎょかん)の書いた『魏略』のなかに、『魏志倭人伝』と、共通する記事がある。『魏略』は、『魏志倭人伝』の先行文献であったとする説がある。また、王沈(おうしん)の『魏書』が先行文献で、『魏志倭人伝』も、魚豢の『魏略』も、先行文献である王沈の『魏書』の記事をうけついだものである、とする説がある。 いずれにしても、『魏志倭人伝』には、先行文献があったのである。先行文献の記事と、『魏志倭人伝』の記事とが、ほとんど同一であるとすれば(つまり、陳寿が、いろいろな資料を編纂して、『魏志倭人伝』を書いたのではなく、先行文献にすでにまとめられていた記事を、ほとんどそのまま写したのであるとすれば)、その先行文献の成立した時期が、「倭人伝」の成立の時期と考えられる。 ■『三国志』全体は、いつ成立したのか? いっぽう、陳寿は、297年になくなっている。 以上から、『三国志』の成立は、284年にほぼ確定できることになる。 ■『三国志』の『魏志』は、いつ成立したか? これに対し、『魏志』は、265年に魏が滅亡し、晋の国が成立したことまでしか記していない。 ■『魏略』は、『魏志』の先行文献である (1)唐の歴史家の劉知幾(りゅうちき)は、その著『史通』の「正史篇」で、つぎのようにのべている。 (2)信頼できる『魏略』の逸文(いつぶん)(他の文献に引用される形で、一部分だけ残存している文章。『魏略』の全体は、伝わっておらず、逸文の形でのみ存在する)のもっとも時代のあとのものは、高貴郷公(254~260)の甘露二年(257)のものである(江畑武「再び『魏略』の成立年代について」〔『阪南論集』人文・自然科学編、第26巻第1号、1990年6月。阪南大学刊〕参照)。『魏略』の成立は、この257年を、それほど大きくは降らないとみられる。 (3)『魏略』は、『魏志』にくらべ、司馬氏に対して厳しく、司馬氏の敵対者に対しては寛容な傾向がみられる。これは、『魏略』が、司馬氏のたてた国である晋になるまえの魏の時代(265年以前)に編纂されたためであろう。 (4)以上から、『魏略』の成立年代は、257年~265年の10年たらずのあいだのどこかと判断される。つまり、卑弥呼が死亡してから、10年ないし20年たらずのちには、『魏略』が成立していたことになる。 私は、魚豢の『魏略』のおよその成立年代(260年前後)と、陳寿の『魏志』のおよその成立年代(280年)ごろとの差からみて、魚豢と陳寿との年齢差は、15歳~25歳ていどとみる。陳寿は233年の生まれ、魚豢は、『魏略』を50歳前後で書いたとみれば、210年前後の生まれとなる。 なお、先に紹介した劉知幾の『史通』の文は、「これより先、魏の時代に、京兆の人、魚豢は、『魏略』を私撰した。帝紀は、明帝で終っている(先是、魏時、京兆魚豢私撰魏略、事止明帝)。」 ■『魏志倭人伝』の『魏略』によらない部分は? したがって、『魏志倭人伝』の全文の成立の時期に、さかのぼらせることはできない。よって、『魏志倭人伝』の成立は、早くみて280年ごろ(『魏志』の成立の時期)、遅くみて、284年(『三国志』の成立の時期)ということになる。
『魏志倭人伝』関連文献の成立の時期を表にまとめれば、表2のようになる。 北海道大学の津田資久氏は、論文「『魏略』の基礎的研究」(『史朋』第三一号。北海道大学東洋史談話会編集・発行)において、つぎのようにのべ、山尾幸久氏らの議論が、成立しがたいことをのべている。
■『三国志』は、どこで書かれたか? |
4.『魏志倭人伝』を徹底的に読む
|
■末盧国 まず、一支国から末盧国への道程は、里程記事だけがあって、方向記事がぬけている。 壱岐の対岸で、壱岐からもっとも近い松浦(まつうら)の地(肥前の国松浦郡)を、『万葉集』では、「麻都良(まつら)」「末都良(まつら)」「麻通良(まつら)」「麻通羅(まつら)」などと記している。『古事記』の「仲哀天皇記」では、「末羅県(まつらのあがた)」と記しており、『日本書紀』の「松浦県」も、「まつらのあがた」と訓むのがふつうである。『和名抄』の郡名では、「松浦(万豆良)」と記されている。 『魏志倭人伝』は、「末盧国」の条で、「好んで、魚や鰒(あわび)をとらえる。海の深い浅いを問わず、人びとはみなもぐってこれをとっている。」と記している。これに対応する記事が、『肥前の国風土記』の「松浦郡」の条にみえる。 すなわち、つぎのとおりである。 (2)「白水郎等(あまども)、此の島に就(つ)きて宅(いえ)を造りて居(す)めり。因(よ)りて大家郷(おおやのさと)といふ。廻縁(めぐり)の海に、蚫・螺・鯛・雑の魚、及(また)、海藻・海松多し。」[大家島(おおやしま)の条。大家島の所在は、明らかでない。平戸島、その北の大島、あるいは、呼子町、登望(とも)駅西北海上の馬渡島などが擬されている。] (3)「[値喜(ちか)の郷(さと)の土蜘蛛(つちぐも)の大耳(おおみみ)、垂耳(たりみみ)らが、景行天皇に]長蚫(ながあはび)・鞭蚫(むちあはび)・短蚫(みじかあはび)・陰蚫(かげあはび)・羽割蚫(はわりあはび)等(ども)の様(ためし)をつくりて、御所に献(たてまつ)りき。」(値嘉の郷は、五島列島の総称。長蚫・鞭蚫・・・は、あわびの肉を薄く長くのばして、さまざまな形につくり、乾燥した加工食品。『延喜式〔主計式〕』の、諸国からの貢物の名に、短鰒・長鰒・羽割鰒〔肥前の国〕、蔭鰒・鞭鰒〔筑前の国〕がみえる。) (4)「[値嘉の郷の]海には則(すなわ)ち、蚫・螺・鯛・鯖・雑の魚、海藻・海松・雑の海菜(もは)あり。彼(そ)の白水郎(あま)は、馬・牛に富めり。」 |
| TOP>活動記録>講演会>第319回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |