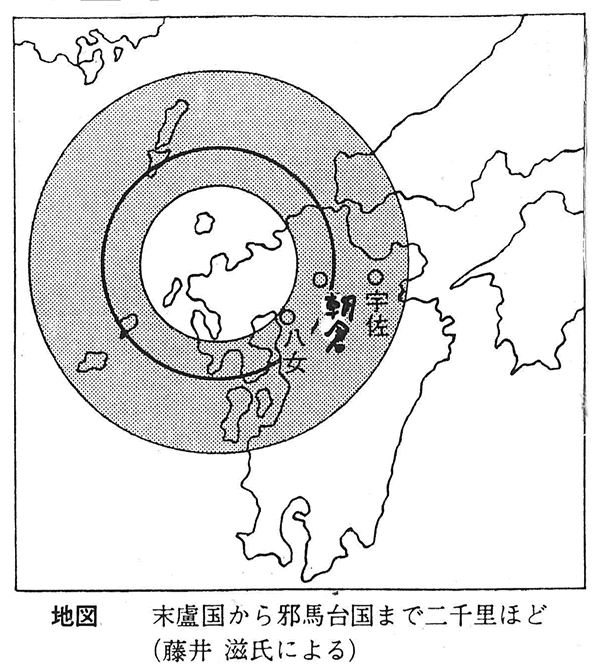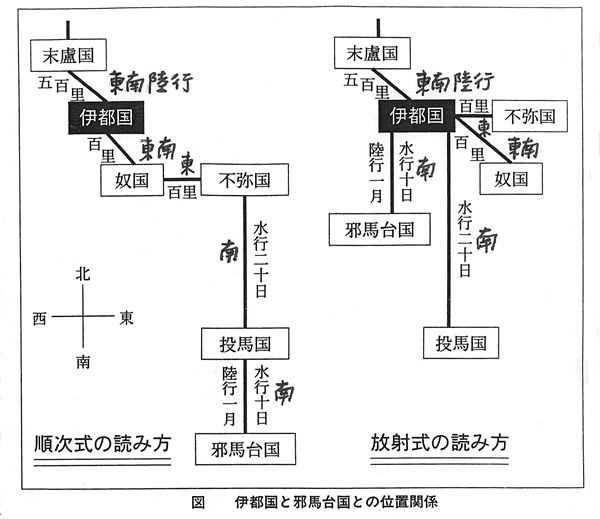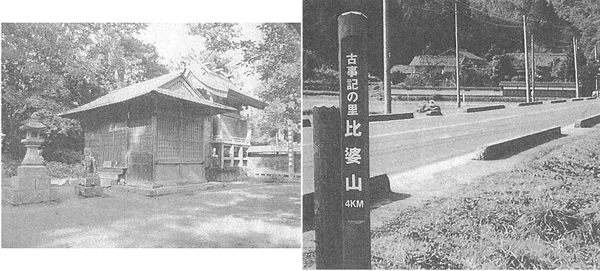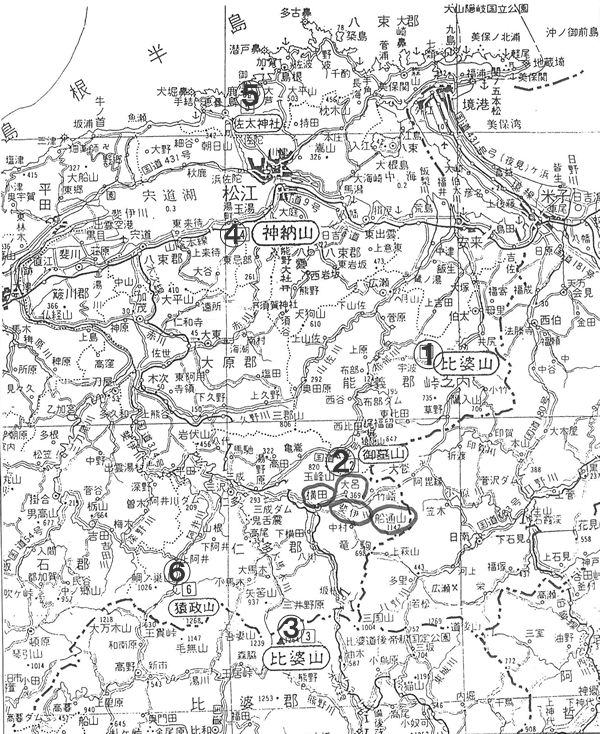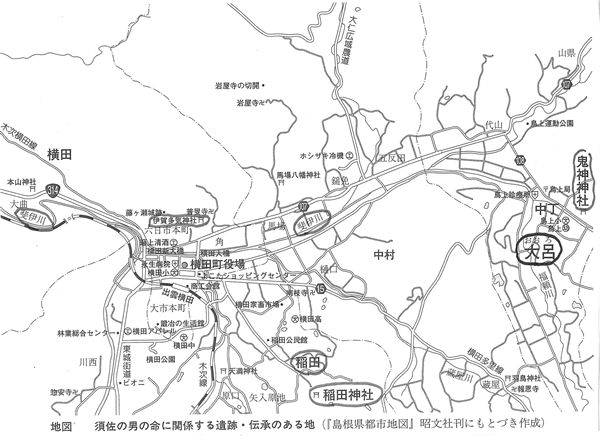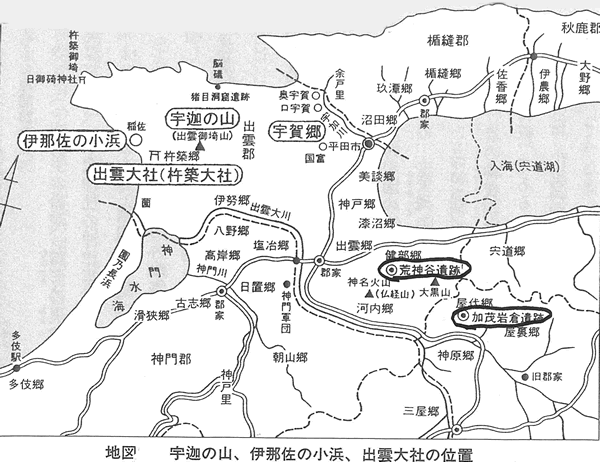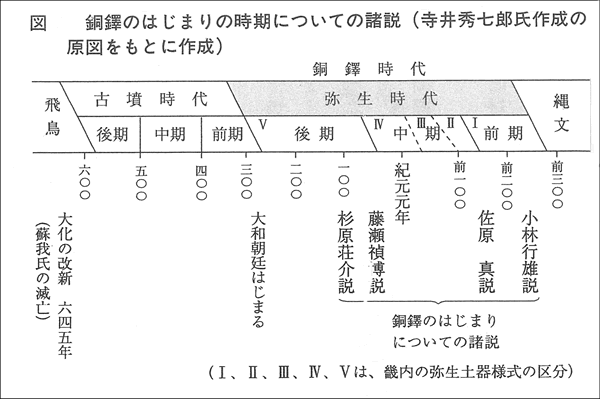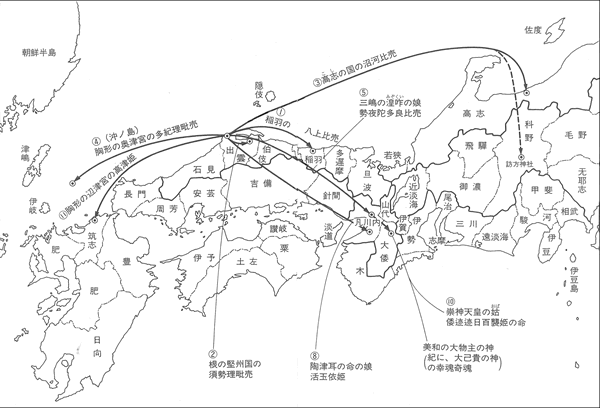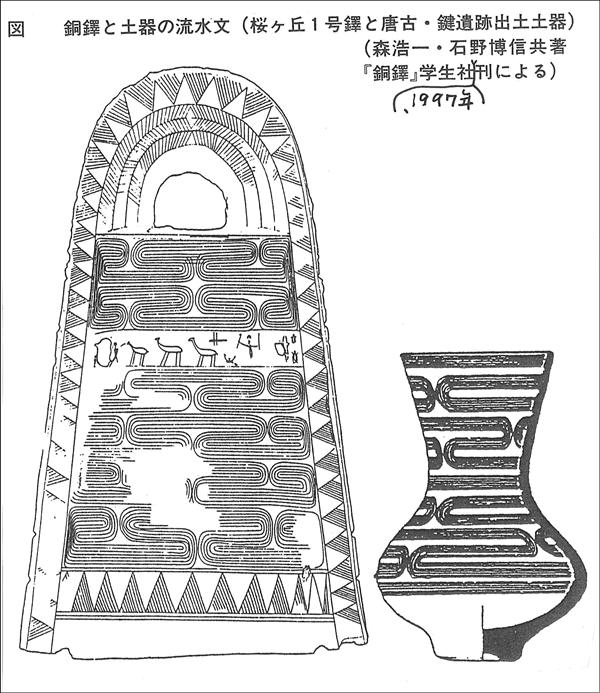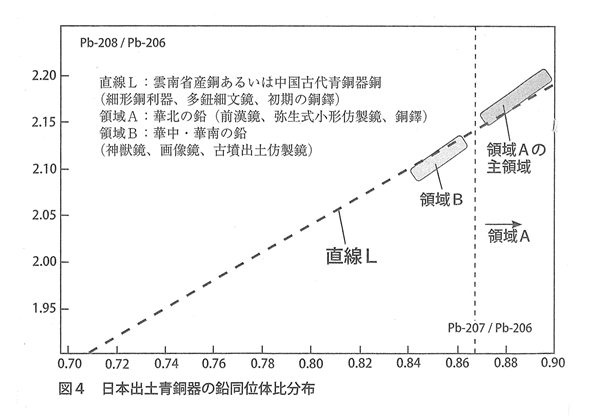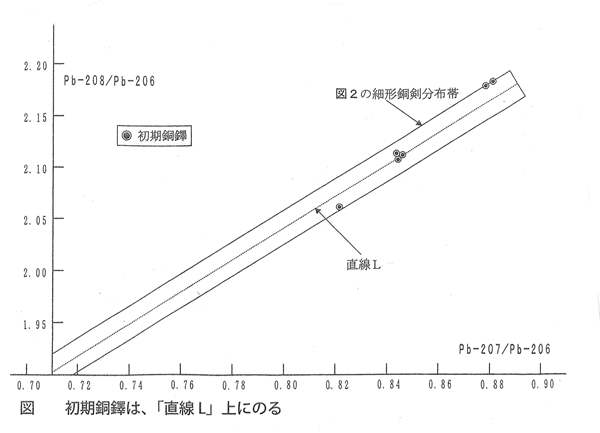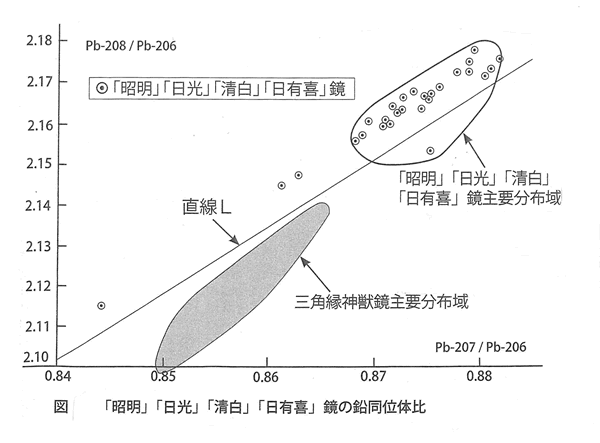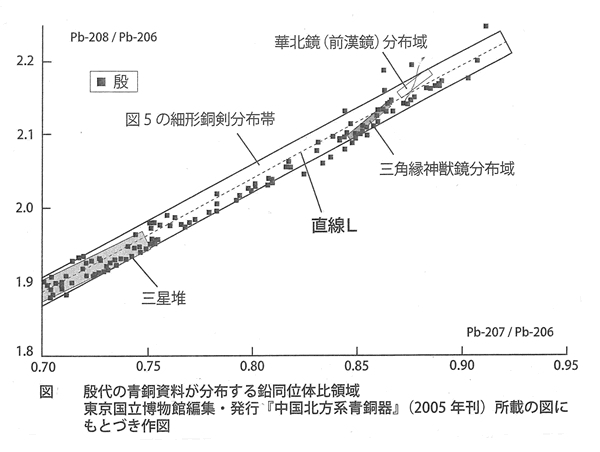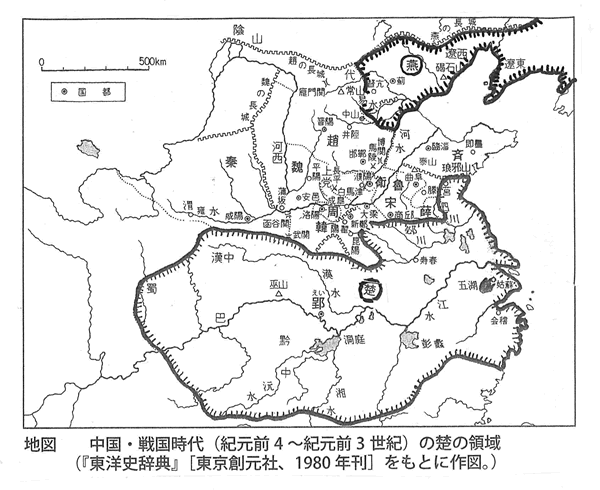■卑弥呼を神功皇后としている
・中国の文献
丙戌年。書紀紀年で266年。
起居注は、中国で天子の言行ならびに勲功を記した、日記体の政治上の記録。
従って歴朝に起居注があった。附書、経籍志には晋代についても晋泰始起居注二十巻(李軌撰)ほか二十一部をあげ、日本国見在書目録の起居注家には晋起居注三十巻をあげている。なお晋書にも類似の記事はあり、武帝紀には「泰始2年(266)、11月巳卯、倭人来献方物」といい、同四夷伝の倭条にも「泰始、初遣使重訳入貢」としるしてある。三種を比べて、入貢の主体を倭女王とするのは本条だけであるが、この倭女王は、おそらく、魏志、倭人伝に、卑弥呼が死亡の後、一たん立てた男王が廃され、ついでたった「卑弥呼宗女壹(臺の誤りか)与、年十三」にあたると考えられている。ただ書紀は、この倭女王も卑弥呼その人と考えたのであろうとおもわれ、そこで、卑弥呼すなわち神功皇后とみなしていた書紀は、皇后の死をこの年のあとにおくこととしたのであろう。
『魏志倭人伝』の記述から、卑弥呼が亡くなったのは248年頃と考えられ、その時13歳の壹与の年は泰始2年(266)には31歳か32歳だと考えられる。
『日本書紀』神功皇后紀に下記がある。
66年。是年、晉の武帝の泰初(たいしょ)の二年なり。晉の起居(ききょ)の注に云はく、武帝の泰初の二年の十月に、倭の女王、譯(をさ)を重ねて貢献せしむといふ。
■伊邪那岐、伊邪那美の命の話
神話の内容から、伊邪那岐は亡くなった伊邪那美に会いに黄泉の国へ行き、見てはいけない亡くなった伊邪那美を見たため、黄泉の国を追われ、「竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘の小門(をど)の阿波岐原(あわぎはら)で禊(みそぎ)をする。」とある。このようなことから、伊邪那岐は九州方面の人ではないか。
また、伊邪那美の命が死ぬと、出雲と伯耆国の国境の比婆山に葬られる。更に、須佐之男(すさのう)の命が母の国の根の堅州国に行きたいと言っている。そして出雲の国に天下る。
このことから、伊邪那美は出雲方面の人と考えられる。
伊邪那美の命の墓の伝承地は6ヶ所あるが、出雲と伯耆国の国境だとすると、①の「比婆山」が有力と考えられる。
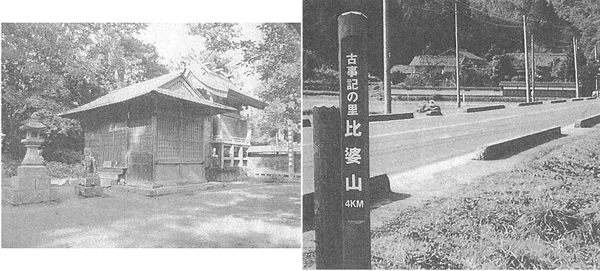
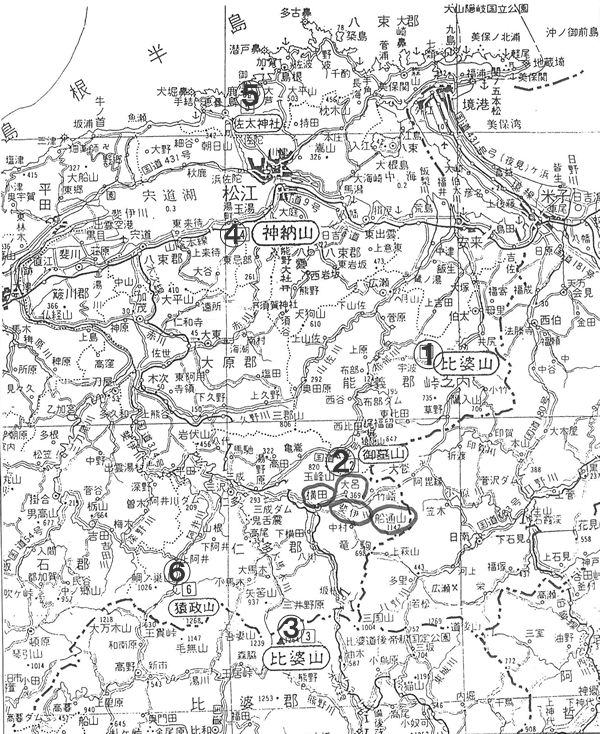
■須佐之男の命
・須佐之男の命は船通山(せんつうさん)[鳥上の峰(とりかみのたけ)]に天くだる。
そこで、大蛇の退治を行う。
下記の地図から、
斐伊川(ひいかわ)[肥の河(ひのかわ)]
鬼神神社[五十猛の命の陵]須佐之男の命の子
稲田神社[稲田姫を祭っている]
伊賀多気神社に天くだったとされる。
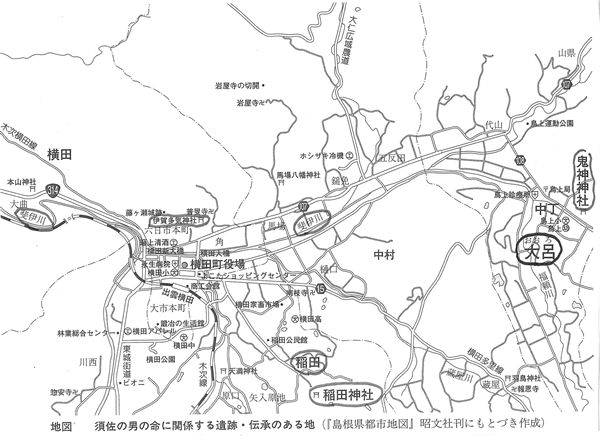
・須佐之男の命(『日本書紀』は素戔の嗚の尊)は鉄と関係している
『素戔の嗚の尊は、その子の五十猛の神をひきいて、新羅の国から埴土(はに)をもって舟とし、乗って東にわたり、出雲の国の簸(ひ)の川上にある鳥上の峰(たけ)に到った』と、『日本書紀』に見えている。
以前、鉄の専門家で、『鉄の考古学』(雄山閣出版刊)の著者である窪田蔵郎氏からおよそつぎのような話をうかがったことがある。
「鉄鉱石から鉄をつくるのには、高い技術を必要とすると考えられがちです。しかし、かならずしも、そうとばかりは、いえないのです。鉄鉱石を赤く熱して、酸素をとり、くだけて散らないように、そっと根気よくたたいて、石の部分をとばして行けば、900度ぐらいでも、鉄はできるのです。」
また黒岩俊郎著『たたら日本古来の製鉄技術』(玉川大学出版部、1976年刊)に、『たたら製鉄の復元とその鉧(けら)について』(たたら製鉄復元計画委員会報告)にのっているつぎのような文が紹介されている。
「京城の加藤灌覚氏の実見談を和田重之氏が記録したものによると、明治42年(1909年)5月7日のことであるが、朝鮮咸鏡北道富寧(ふねい)の南東にあたる沙河洞の村民が、輸域(ゆいき)川の河原できわめて原始的な製鉄をやっているのを目撃したそうで、その方法は河原によく乾いた砂鉄を60センチほど積みあげ、その上に大量の薪をのせて火をつけ一夜燃やし続け、翌日になって鉄塊を拾い集めていたとのことである。」
このように、原始的に鉄をつくることが、出来たとしたら弥生時代の末期に日本でも製鉄が行われ、出雲での製鉄として、須佐之男の命は鉄と関係していたのではないか。
八岐大蛇(やまたのおろち)から、草那芸(くさなぎ)の剣(つるぎ)[天(あま)の叢雲(むらくも)の剣(つるぎ)]が出てくる。
草那芸の剣は三種の神器の一つとして、熱田神宮にまつられている。
一方、大蛇を切った十拳(とつか)の剣(つるぎ)[斬蛇の剣]は奈良県石上神宮(いそのかみじんぐう)にまつられている。
■大国主の命
大国主の命は氏素性がはっきり分からないようにみえるが、須佐之男の命のところにきて、須佐之男の命の娘の須勢理比売と駆け落ちして、出雲の国のシンボルを持って逃げた。須佐之男の命は大国主の命に国を任せる。
その後、大国主の命の勢力が大きくなって、高天原勢力は大国主の命に国を譲れとして、
第三回目の使者、建御雷の神をつかわしたときの状況を、『古事記』は、つぎのように記す。
「建御雷の神と天の鳥船の神の二はしらの神は、出雲の国の伊那佐の小浜にくだり到着して、十掬(とつか)の剣を拔いて、さかさまに浪のさきに剌したて、その剣のまえに足をくんですわって、大国主の神にたずねてのべた・・・。(此の二はしらの神、出雲の国の伊那佐の小浜に降り到りて、十掬剣を抜きて、逆に浪の穂に刺し立て、その剣の前に趺み坐して、その大国主神に問ひて言(の)りたまひしく・・・。)」
このようにして、大国主の命は高天原勢力に国を譲る。

これらの、出雲神話は『古事記』の場合、全体の1/3は日本神話で、その1/3位が出雲神話の話である。
戦後、出雲神話はすべて作り話だ。なぜなら出雲地方からこれという考古学的なものが何も出てこないとされていた。しかし荒神谷遺跡、加茂岩倉(かもいわくら)遺跡が発見され、大量の銅剣、銅矛、銅鐸が出てきた。それが出雲神話と結びつくのかつかないのか。
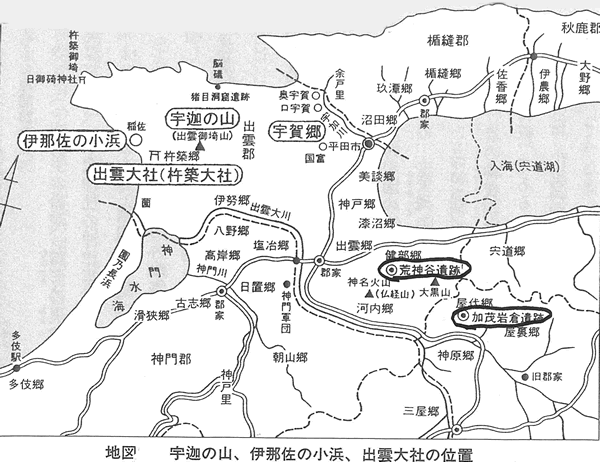
大塚初重・按井清彦・鈴木公雄共編『日本古代遺跡事典』(吉川弘文館、1995年刊)
・荒神谷遺跡(こうじんだにいせき)
弥生青銅器埋納遺跡。国史跡。簸川郡斐川町字神庭(現在の出雲市斐川町神庭西谷)に所在。農道開設にともない県教育委員会が1984年と85年に発掘調査。遺跡は宍道湖低地に向かってのびる丘陵間の南北に長い谷の最奥部に位置する。
埋納場所は小丘の南斜面中腹。 1984年発見の銅剣群は斜面をコ字状に切り込んで造成した上下2段の凹地の下段部に、等高線に並行して4列横隊で並べられていた。すなわち下段には浅い埋納坑(東西約4. 6m、南北約2.6~2.7m)が設けられ、底に粘土を敷いた後に銅剣を、鋒と茎を水平に、刃を立てて置く。列は段に向かって左からA列(34本を茎と鋒を差し違え)、B列(111本、手前の4本鋒西向き、他は差し違え)、C列(120本,鋒東向き)、D列(93本、鋒東向き)となる。
合計358本を並べ終えた後、上面を粘土で覆い、下段全体を埋めるという手順がとられている。銅鐸と銅矛は銅剣群の埋納坑より7m東(谷奥)で、ほぼ同レベルの個所に、やはり斜面を切り込み、前面に粘土を貼って埋納坑(東西約2.1m、南北約1.5m)を設け、向かって左に6個の銅鐸が3個2列で、鰭(ひれ)を立て、鈕を向き合わせて並べられ、右には16本の銅矛が鋒と袋部を交互に差し違えて横たえられていた。
埋納時には銅剣同様に刃部を立てて置いたものと考えられる。被覆した埋土は低いマウンド状をなしていた。出土した銅剣は全長51cmで、すべて中細形c類に属する。同型式の剣は山陰地方では4か所12本の発見であり、本遺跡での大量出土と絡めて中細形c類を出雲型銅剣とし、その分布の中心を当地方に求める見解がある。銅鐸は高さが約22~24cmの小型で、菱環鈕式(横帯文)が1、外縁鈕式(袈裟襷文)が5となっている。
山陰地方での菱環鈕式銅鐸は初出であり、重弧文や斜格子文を鋳出した1号鐸は類例がない。銅矛は中細形b類2本(全長約70cm)と中広形14本(全長約75~84cm)で、中広形には研ぎ分けを施すものがある。いずれも北部九州からの搬人品と考えられる。
当遺跡での弥生青銅器群の一括大量発見は、近畿と北九州の中間地帯にも青銅器の生産と保有・分配の拠点地域をうかがわせ、日本海域を含めた西日本の弥生時代の動向を探る上で重要な資料を提供したといえる。出土青銅器は国重要文化財。遺跡は整備、公開されている。
瀧音能之(たきおとよしゆき)『古代の出雲事典』(新人物往来社2001年刊)
・荒神谷遺跡
荒神谷遺跡の発見がなされる前の出雲は、実態の伴なわない神話の国というイメージが強かった。確かに記紀神話のなかで出雲系神話の占めるウェイトは大きく、量的にみても三分の一ほどが費やされ、内容的にもスサノオ神のヤマタノオロチ退治神話やオオクニヌシ神の国譲り神話など重要なものが多い。こうしたことから、出雲には大和に匹敵する政治勢力が存在したと想像されてきたのであるが、考古学的にみると、例えば古墳の規模などからしても大和とは比較にならないほど小さく、吉備と比べても見劣りがして、出雲勢力の実在を裏付ける物質的な資料は脆弱であった。ところが荒神谷遺跡の発見によって、その勢力の実在性が証明されたのである。
銅鐸は、高さ21~24センチ、重さ606~1116クラム、銅矛は、長さ69~84センチ、重さ980~2160グラムの大きさである。銅剣と異なり、銅鐸と銅矛の形式は単一ではない。銅鐸のうち五号鐸は菱環(りょうかん)鈕I式、その他の五個は外縁付(がいえんつき)鈕Ⅱ式である。銅矛は、一号矛と二号矛は中細形、他の14本は中広形である。
銅矛については、その形態や綾杉(あやすぎ)状の研ぎ分けの技術などを根拠として、16本とも北部九州で作られたとみられている。
◆これら多量の青銅器の埋納は、ほぼ同時期に一緒になされたと考えられているのであるが、いつ作られ、いつ埋納されたのかという具体的な時期の特定は難しい。年代の決めてとなる土器などの共伴物がまったくないためである。そこで、それぞれの青銅器の形態・形式を個別にそこから年代を推定する方法がとられている。
すなわち、銅鐸のうち菱環鈕式は、一般的に弥生前期末から中期初め、外縁式鈕式は弥生中期前半の製作とみられている。銅矛は弥生中期後葉以降。中期細形銅剣は弥生中期後葉から後期の製作とされている。したがって、青銅器の埋納時期は、これらを全体的にとらえると、弥生中期末もしくは後期の初め以降と考えてよいであろう。
・銅鐸がいつ始まったか。
佐原眞氏が銅鐸の編年の研究をされて来た。佐原眞氏の銅鐸研究では相対年代として立派な実績を残したが、絶対年代については疑問がある。
杉原荘介氏に対し300年位古くもってきている。佐原眞氏の説では銅鐸は古くなり、邪馬台国時代より前になる。
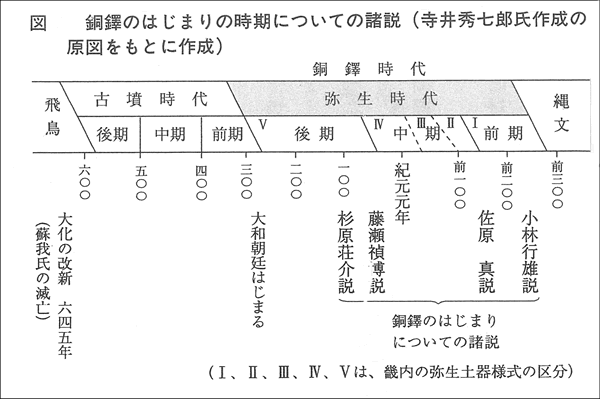
加茂岩倉(かもいわくら)遺跡
◆大原郡加茂町岩倉(現在の雲南市加茂町岩倉)。宍道湖の南西、国道54号線から西へおよそ2キロほど入った、細長い谷の奥に位置する弥生時代の遺跡。近くに金鷄(きんけい)伝説をもつ大きな岩がある。平成8(1996)年10月、農道工事によって偶然、銅鐸が掘り出され、その後の発掘調査によって合計39個の銅鐸が出土した。一遺跡からの出土数としてはこれまでのところ史上最多である。これらの銅鐸は一括して国の重要文化財に指定され、遺跡も周辺の山や谷を含めておよそ19,000平方メートルの範囲か国の史跡に指定されている。
南へ約1.6キロのところには景初三年銘の銅鏡を出土した神原神社古墳があり、銅剣をはじめとする多量の青銅器を出土した荒神谷遺跡とは、北側の山をはさんでわずか3.4キロの至近距離にある。
◆銅鐸は、謎の青銅器といわれている。農耕祭祀などの共同体の祭祀に用いられた祭器と考えられているのであるが、具体的にはどんな祭祀にどのように使われたのかは不明であるし、なぜ埋められたのかという謎も解明されていない。
そして、ある時期を境にしていっせいに姿を消してしまうのである。こうした謎に加えて、加茂岩倉銅鐸が発見され、さらに新たな謎をなげかけることになった。
◆銅鐸は標高約138メートルの丘陵斜面の中腹に埋納された状態で発見された。銅鐸を埋めた穴(埋納坑)は、推定約2×1メートルの長方形をしており、深さは約0.4メートル。丘陵斜面をカットして造り出した平坦面に掘り込まれていた。
出土した銅鐸は、高さ約45センチの大型銅鐸が20個、高さ約30センチの小型銅鐸が19個。銅鐸の身には、袈裟襷(けさだすき)もしくは流水の文様がほどこされている。このうち14組28個の銅鐸は、大きな銅鐸のなかに小さな銅鐸を収めた「入れ子」の状態で発見された。なぜ入れ子の状態で埋められたのかも謎であり、解明が待たれるところである。 銅鐸のほとんどは佐原真氏の分類方法によるⅡ式かⅢ式にあたり、弥生時代の中期に造られたとみられている。
ちなみに、荒神谷遺跡ではこれより古いⅠ式とⅡ式の銅鐸が出土した。
◆銅鐸の生産地については、発見当初は近畿とする説が強かったが、次第に地元の出雲で造られたものも含まれているといわれるようになってきている。特に袈裟襷文のうち18号鐸・23号鐸・35号鐸のように縱帯と横帯の界線が切り合っている文様は独特であり、これらは出雲で造られたのではないかといわれている。
生産地を考える上で大きなヒントになると思われるのが同茫品の存在である。39個のうち、15個8組が同茫とされ、そのなかには加茂岩倉遺跡内における同范関係もみられるし、他地域から出土した銅鐸と同范という場合もみられる。そして、その地域は、隣接する鳥取県をはじめとして、兵庫県・大阪府・和歌山県・奈良県・徳島県というように広がりをもっている。こうした同范関係をどのように理解したらよいのかという点も大きな謎である。一般的には、近畿から出雲へという伝播は想定するのであるが、逆に出雲から近畿へというルー卜を考えることはできないものであろうか。
◆加茂岩倉銅鐸のなかにはシ力やトンボ、あるいは人面などの線画をほどこしたものがみられる。10号鐸にはカメの絵が描かれている。手の形などからこのカメはウミガメであるといわれているのであるが、内陸部に位置する遺跡からなぜウミガメの絵をもつ銅鐸が出土したのであろうか。また、23号鐸には奇妙な四足の動物が描かれている。イノシシではないかともいわれているのであるが断定は難しく、この四足獣が一体、何であるのかという点も興味深い謎である。
さらに、12個の銅鐸の紐の中央部に「×」が刻されていることが確認されている。
この「×」は荒神谷遺跡の銅剣にもみられるものであり、「×」が同じ集団によって同じ時期に刻されたとすると、両遺跡の青銅器の少なくとも一部が、埋納されるまでのある時期いっしょに保有されていた可能性も出てくるのではないかとの指摘もある。
11号銅鐸の鈕。菱環(りょうかん)の部分に×印が刻まれている。加茂岩倉遺跡出土の銅鐸の13個にこのような×印がこれまで確認されている。
◆『出雲国風土記』の大原郡神原(かむはら)郷の条に、「古老の伝へて云はく。天(あめ)の下造らしし大神の御財(みたから)を積み置き給ひし処なり。則ち神財(かむたから)郷と謂ふ可きを、今の人、猶誤りて、神原郷と云ふのみ」とある。天の下造らしし大神(大穴持命)の宝物を置いたという伝承から神原の地名が生まれたというのであるが、この「大神の御財」を加茂岩倉銅鐸と結び付け、銅鐸の埋納伝承が『出雲国風土記』の記事に反映したのではないかとの見解も出されている。また、岩倉は「磐座(いわくら)」、すなわち「神の降りてくる岩」を意味すると考えられている。こうした地名起源説話と銅鐸の埋納行為との関わりも興味深い謎である。
・大国主の命の通婚範囲
大国主の命は艶福家といわれ、通婚範囲が広い。北は高志(越)の沼河比売と結ばれている。日本神話で、大国主の命と沼河比売の子の建御名方が高天原の建御雷の神と戦い、科野(信濃)の諏訪湖の方の諏訪神社で降伏するのも、母(沼河比売)の国の高志(越)の方へ逃げていったのではないか。
また、大国主の神は北九州の胸形(宗像)奥津宮の多紀理(たきり)毘売や奈良県と関係する。北九州では綾杉(あやすぎ)状の銅矛など共通点があり、奈良県は共通の銅鐸が出ている。
大国主の命はいろいろな土地の豪族の娘と結婚し、あまり戦争をせずに自分の勢力範囲を拡大したようにみえる。
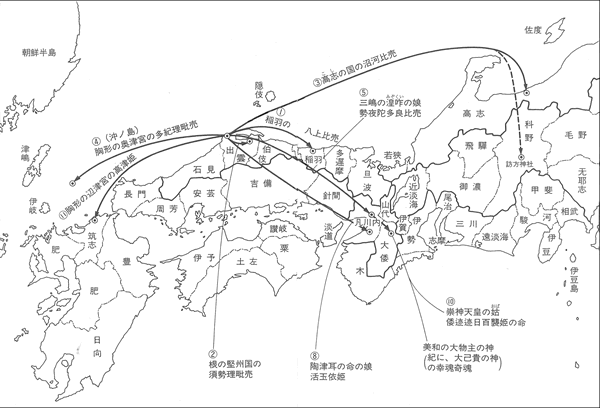
銅鐸の年代
加茂岩倉遺跡の銅鐸の「製作年代」については、『加茂岩倉遺跡・銅鐸の謎』(島根県加茂町教育委員会編・南川三治郎撮影・河出書房新社、1997年4月刊)のなかで、島根県教育委員会埋蔵文化財調査センター長の宍道正年(しんじまさとし)氏が、つぎのようにのべている。
「ふつう遺跡や遺物(遺跡から出土するさまざまな品物)の年代を決める有効な手がかりは、それがどんな土器と一緒に出たかというところにあります。
銅鐸が作られ、そして埋められたのが弥生時代であるならば、弥生土器が一緒に出てきてほしいわけです。
弥生時代の土器は、弥生時代全体のいわば『歴史年表』ともいうべき『土器編年表』がかなりしっかり出来上かっていますから、土器さえ一緒に出てくれば、年代を決めるのはむずかしくありません。
しかし残念なことに、現在まで全国で500個の銅鐸が出土していながら、弥生土器と一緒に見つかった銅鐸は一つもありません。加茂岩倉遺跡でも、弥生土器の破片すらまったく発見されなかったのです。
では、どのようにしていつ頃作られたのかを推定するのでしょう。
基本的には、一部の銅鐸についている『流水紋(りゅうすいもん)』(流水紋銅鐸)という模様が、紀元前2世紀頃の弥生土器についている『櫛描(くしが)き流水紋』を取り入れたものだという考えから割り出しています。
さらには、銅鐸と一緒に弥生土器は出なくとも、銅鐸を作った鋳型(いがた)と一緒に出土したり、銅鐸に描かれた絵と同じような絵が弥生土器にあったり、青銅製武器形祭器(銅剣や銅矛など)と比較して総合的に考えています。
そういうことから加茂岩倉の銅鐸の年代を考えると、およそ紀元前二世紀から紀元後一世紀の間に製作されたようです。」
注:これは佐原眞氏の絶対年代を参考にしたもので、古く考えられている。
・銅鐸と土器の流水文(桜ヶ丘1号墳と唐古・鍵遺跡出土土器)(森浩一・石野博信共著『銅鐸』学生社、1997年刊)
森:ぼくは、九州のほうがいまのところははるかに年代の基点になると思う。
たしかに近畿の場合、流水文との類似性とか、木の葉文と言いましたか、葉を四枚つないだ文様も一部銅鐸に出てくるからという議論が、直良[なおら](信夫)さんなどは銅鐸研究のなかで言われていたけれども、唐古・鍵遺跡の文様を研究した藤田(三郎)さんが、銅鐸に付いているような流水文は、古いほうの流水文じゃなくて、第Ⅳ様式(紀元後1世紀ごろ)にもあると言っている。だから、流水文があるからといって古いという証拠にはならない。そうすると、近畿の年代の出し方が、ぼくはいまのところ基盤が弱いような気がする。
石野:流水文があるから第Ⅱ様式だと言っていたら、明らかに同じ手のものが第Ⅲ様式にも第Ⅳ様式にもあるということが、遺構の土器の一括資料の中で言えるようになってきたわけです。
あれは唐古の報告書そのものを見直してもその可能性は高いんです。ですから、逆なんですね。流水文があるから第Ⅱ様式だというふうに型式学的に言われてきたが、現実に九州から出てくる材料がふえてくると、そうとは言えない。同じ手のものが中期の後半、第Ⅳ様式まであるんだということがわかってきましたから、基準としては修正すべきものだろうと思います。」
と述べている。
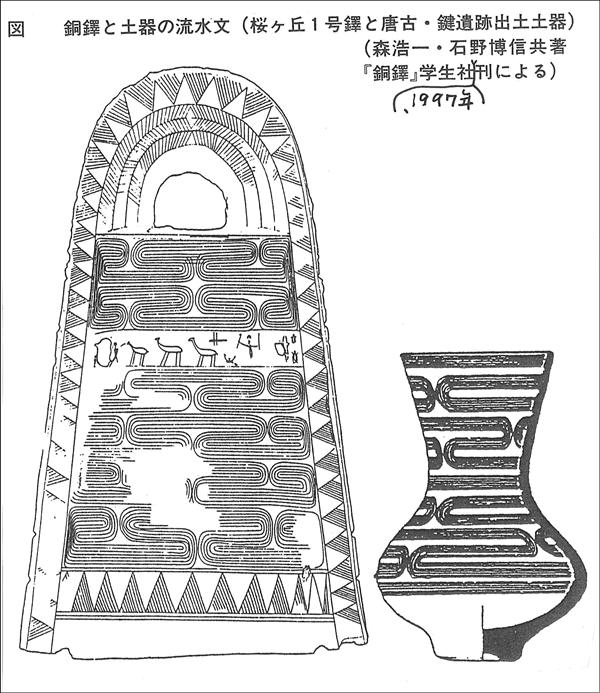
■鉛同位体比
別の観点から見ると、鉛同位体比がある。
銅の生産地や青銅器の製作年代を、あるていど知ることができる研究に、銅の中に含まれている鉛についての研究がある。
鉛には、質量の異なるものがある。鉛は、四つの、質量の違う原子の混合物である。その混合比率(同位体比)が産出地によって異なる。鉛には、質量数が、204、206、207、208のものがある。つまり、四つの同位体(同じ元素に属する原子で、質量の違うもの)がある。
鉱床の生成の時期によって、鉛の同位体の混合比率が異なる。いわば、黒、白、赤、青の四種の球があって、その混合比率が、産出地によって異なるようなものである。
鉛同位体比研究の重要な意味は、青銅器に含まれる鉛の混合率の分析によって、青銅器の製作年代を、あるていど推定する手がかりが与えられることである。
とくに、質量数207の鉛と206の鉛との比(Pb207/Pb206 Pbは鉛の元素記号をあらわす)を横軸にとり、質量数208の鉛と206の鉛との比(Pb208/Pb206)を縦軸にとって、平面上にプロットすると、多くの青銅器がかなり整然と分類される。
それによって、青銅器の製作年代などを考えることができる。
すなわち、古代の青銅器は、大きくつぎの三つに分類される(下図参照)。
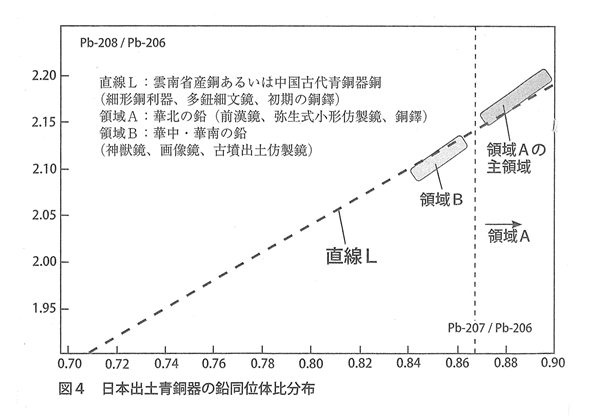
(1)「直線L」の上に、ほぼのるもの もっとも古い時期のわが国出土の青銅器のデータは、この直線の上にはほぼのる。「直線L」の上にのる青銅器またはその原料は、雲南省産銅あるいは中国古代青銅器の銅が、燕の国を通じて、わが国に来た可能性がある。細形銅剣、細形銅矛、細形銅戈、多鉦細文鏡などは、「直線L」の上にのるグループに属する。
「直線L」の上にのる鉛を含む青銅器を、数多くの鉛同位体比の測定値を示した馬淵久夫氏(東京国立文化財研究所名誉研究員、岡山県くらしき作陽大学教授)らは、朝鮮半島産の銅とするが、数理考古学者の新井宏氏は、くわしい根拠をあげて、雲南省産銅あるいは中国古代青銅器銅とする。(新井宏著『理系の視点からみた「考古学」の論争点』[大和書房、2007年刊]および、本誌74号の新井宏氏の論文「鉛同位体比による青銅器の鉛産地をめぐって」参照)。
「直線L」の上にのる形で、広い範囲に分布するものとしては、つぎのようなものがある。
①細形銅剣
②細形銅矛
③細形銅戈
④多鈕細文(たちゅうさいもん)鏡
⑤初期銅鐸
おそらく、これらは、ほぼ同時期に製作されたものであろう。
日本の細形銅剣は中国の三星堆(さんせいたい)遺跡の青銅と一致する。
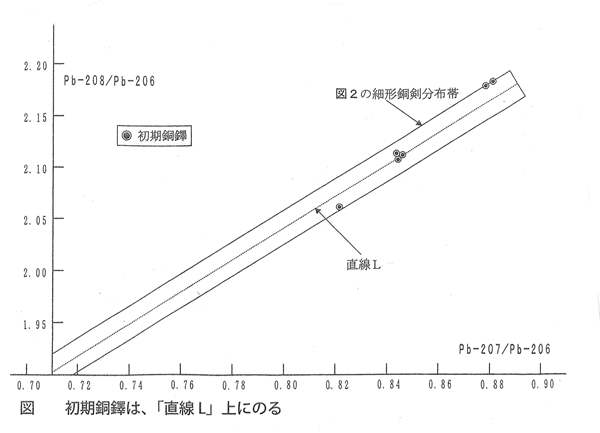

(2)「領域A」に分布するもの 甕棺から出土する前漢・後漢式鏡(「照明」「日光」「清白」「日有喜」)、箱式石棺から出土する「長宜子孫」銘内行花文鏡、小形仿製鏡第Ⅱ型、そして、広形銅矛、広形銅戈、近畿式・三遠式銅鐸などは、「領域A」に分布する。弥生時代の国産青銅器の多くも、この領域にはいる。
(3)「領域B」に分布するもの 三角縁神獣鏡をはじめ、古墳から出土する青銅鏡の大部分は「領域B」にはいる。ほぼ、西暦300年ごろから400年ごろに築造されたとみられる前方後円墳から出土する鏡の多くは、この領域にはいる。
客観的な事実は、以上のようなものとみられる。
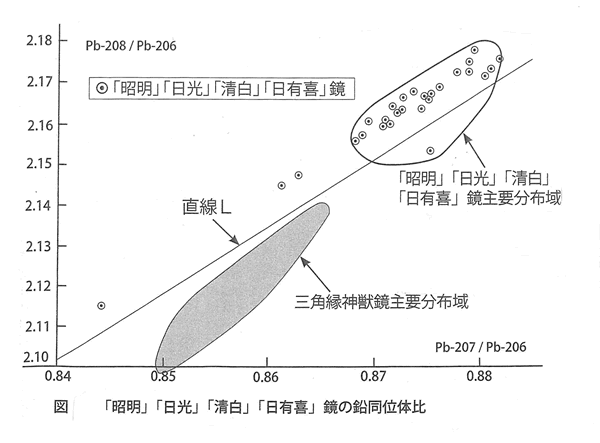
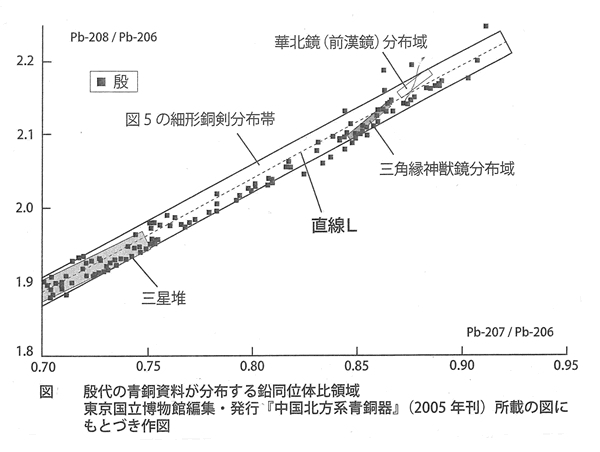
中国の戦国時代(BC403~BC221)に戦国七雄(韓、魏、趙、斉、秦、楚、燕)があった。
楚は揚子江の広い範囲を領有していた。
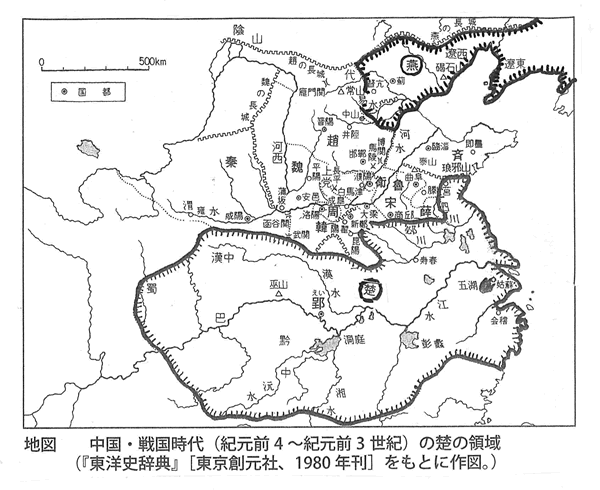
新井宏氏は、つぎのように述べる。
「燕国将軍・楽毅が斉から奪った宝物類が原料(このような現象が起きたのは、)おそらく中国の中原地方などで宝物類として伝世された青銅器が、なんらかの理由で再溶解された状況を想定するのが、最も理解しやすい。貴重な青銅器なら500年以上伝世された可能性が十分にあるのは、奈良時代の青銅器が多数残っているのをみればよくわかる。
そのように考えると、その入手時期として最も可能性の高いのは、『史記』が伝える燕の昭王28年(前284年)の斉・臨澑[りんし](蓄)の攻撃である。これは燕が楚と三晋(さんしん)と秦と連衡し、一時的に都臨澑を陥落させた事件であるが、その際に伝世の宝物類を戦利品等として入手している。
『史記』はその『楽毅列伝』において、燕国の将軍・楽毅が斉の首都臨澑を陥(お)とし、斉の宝物類を根こそぎ奪って昭王のもとに送り届けたことを『楽毅攻人臨蓄、尽取斉宝財物祭器輸之燕(楽毅は臨溜に攻めいり、斉の宝財物をことごとく取って、これを燕にはこんだ)』と伝えている。また同じく『史記』の『田敬仲完世家』も、莒に逃れた斉の湣王(びんおう)を救援にきた楚の淖歯(とうし)が、逆に湣王を殺した際に、燕の将(楽毅)と宝物を山分けにしたことを伝えている。おそらく、その前々年(前286年)に斉は安徽省・河南省にあった宋を滅ぼし併合しているので、そのときの戦利品もそこには含まれていたに違いない。
このような理解は、全体的にみて、整合的であり、無理がない。すなわち、貴重な伝世の青銅器の入手であるなら、この昭王の時以外を想定することは困難である。逆にいえば、商周期の鉛同位体比をもつ青銅器が、500年以上もたってから燕や朝鮮半島、日本に現れた現象を説明できる仮説は、現在のところ右記の想定以外には全く見出すことが困難なのである。」
・貨泉
「貨泉」が、新[前漢と後漢の間の(8~23年)の時代]の国ではじめて鋳造されたのは、『漢書』 の「食貨志(しょくかし)」によれば、西暦14年のこととされている。また、『漢書』の「王莽伝」によれば、西暦20年とされている。
貨泉は「照明」「日光」「清白」「日有喜」などの鏡と鉛同位体比が一致する。