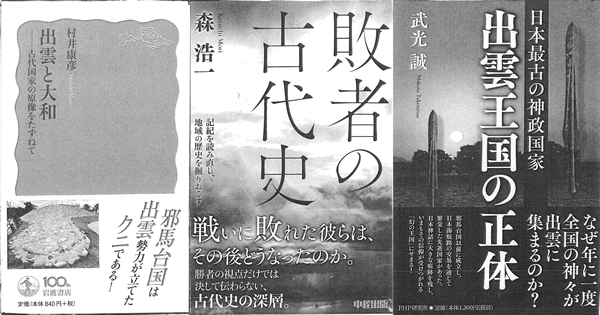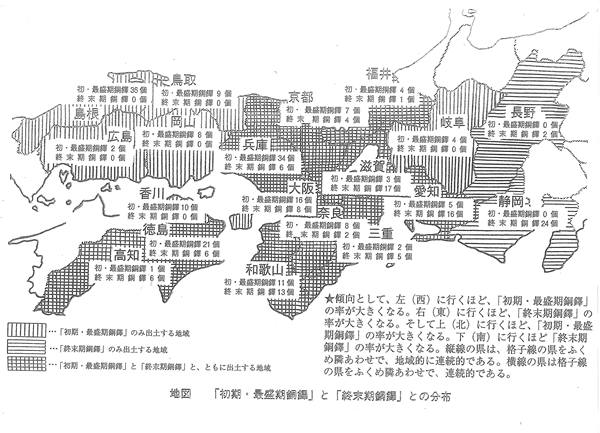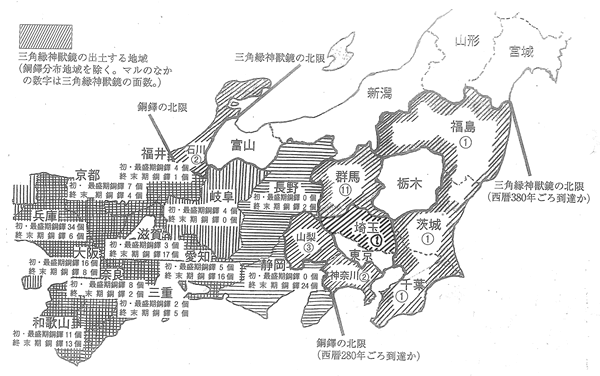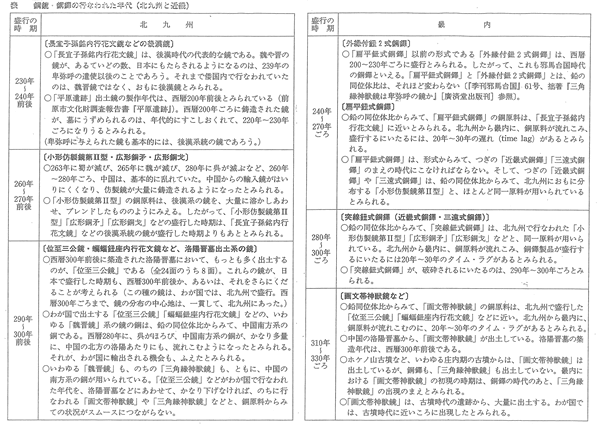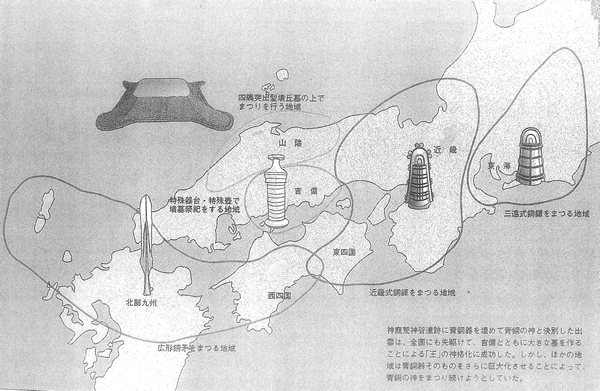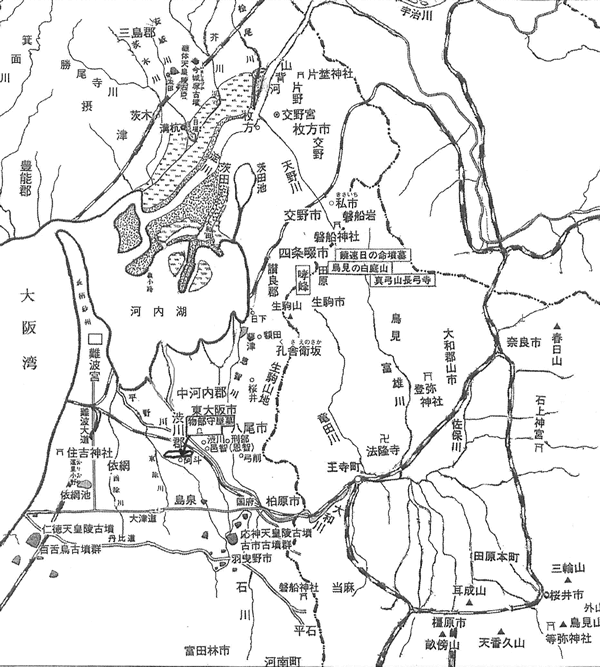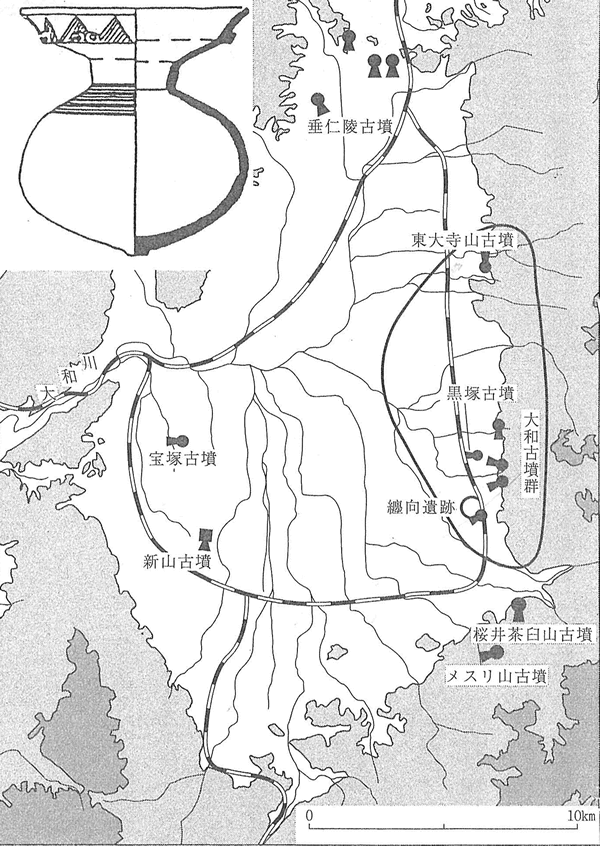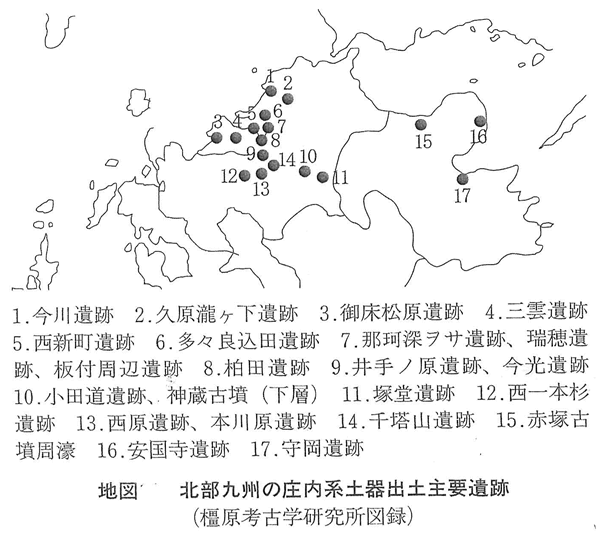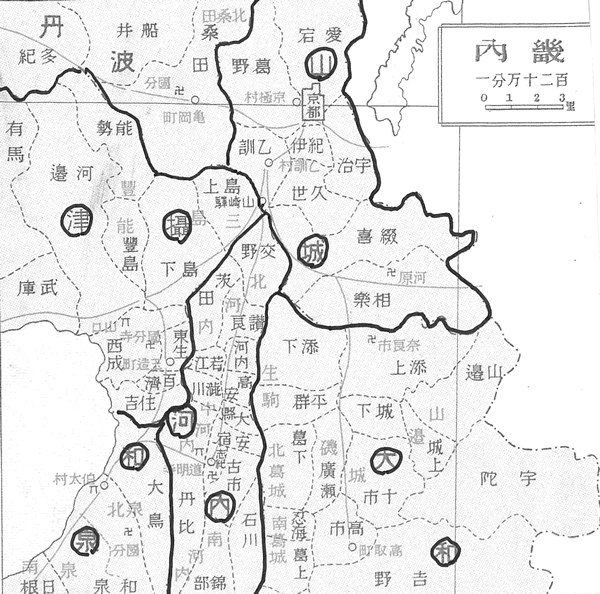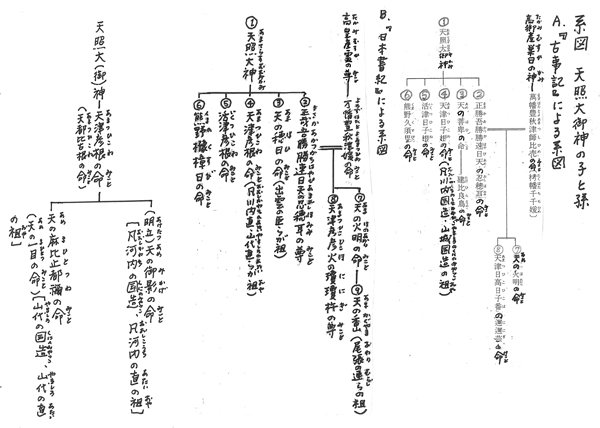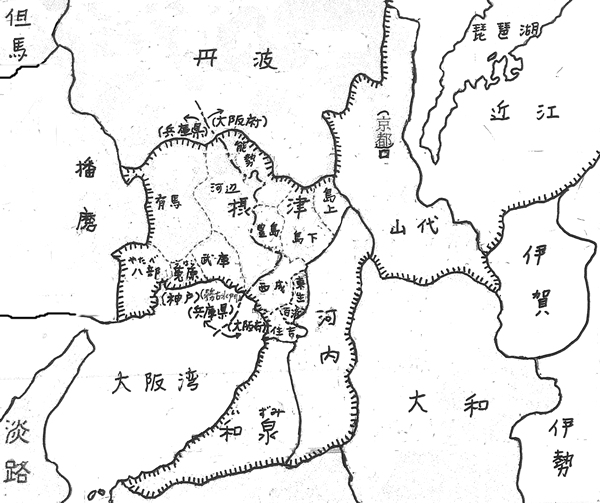| TOP>活動記録>講演会>第322回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
Rev.2 2021.1.30 |
第322回 邪馬台国の会(2013.9.15 開催)
| ||||
1.今年でた論者についての論評
|
今年でた下記の三つの本について論評を加える。 (1)出雲の大和(村井康彦)[2013年1月刊] 大和の中心にある三輪山になぜ出雲の神様が祭られているのか? それは出雲勢力が大和に早くから進出し、邪馬台国を創ったのも出雲の人々だったからではないか? ゆかりの地を歩きながら、記紀・出雲国風土記・魏志倭人伝等を読み解き、古代世界における出雲の存在と役割にせまる。古代史理解に新たな観点を打ちだす一冊。 本文からの引用 村井氏の考え とくに問題なのは、壱与が20人もの使者を立てて「台」(魏の都・洛陽)にまで派遣し、大量の品々を貢献した際、「張政らの還るを送らし」めたという表現がなされていることである。張政らが倭に来ていたとしても、朝鮮半島の陸路か沿岸海路を北上して帯方郡に至る間、壱与の使者集団を引率帯同するのは張政の役目であろう。間違っても、張政が倭国の使者たちに送られるような存在であるはずがない。それでは主客顚倒というものである。にもかかわらず、そうとしか読みとれない表現がなされているのはなぜか。この時張政の立場に劇的な変化をもたらす、深刻な事態が起きていたのではあるまいか。 安本先生の考え 村井氏の考え 長髄彦は生駒地域の首長だっただけでなく、饒速日命の率いる邪馬台国連合の総大将であったとみられる。神武軍の侵攻をまず生駒でくいとめた上、桜井への侵入にも立ち向かい、最後の戦いの指揮をとったのも、同じ理由による。 邪馬台国は外部勢力(神武軍)の侵攻を受けて滅亡したが、しかし戦闘に敗れた結果ではない。総帥・饒速日命が最後の段階で、戦わずして帰順したからである。饒速日命は、もっとも信頼のおける部下の長髓彦を殺してまでも和平の道を選んだのである。饒速日命の決断は正しかったどうか、その行為の意味を検討してみる必要があろう。 しかしこの天孫降臨の話で不可解なのは、葦原中国の統治権を得た天孫の降臨先が、なぜ大和ではなく、九州日向の高千穂の峯(鹿児島県霧島、又は宮崎県高千穂峡とする)であったのか、である。地上全土を譲られたのであれば一挙に本拠地の大和に降ってしかるべきではないか。 神武の后として、大物主神の巫女が選ばれたのは、出雲勢力の奉祭する出雲の神の力を取りこみ、大和に残る出雲族の服属を意図したものであったといってよいであろう。三輪山・大神神社のもった重みがしのばれる。 三つは、『魏志倭人伝』で知られる倭の女王、邪馬台国の卑弥呼の名が、『古事記』『日本書紀』に全く出て来ないことである。その辺りの検討は本文にゆだねるが、実は『日本書紀』の編纂者たちは『魏志倭人伝』の内容も卑弥呼の存在も熟知していたのである。にもかかわらず卑弥呼の名を出さなかったのは卑弥呼が大和朝廷と無縁の存在であり、大王=天皇家の皇統譜に載せられるべき人物ではなかったからである。したがって邪馬台国は大和朝廷にはつながらず、その前身ではなかったということになる。 以上の三つのデータを重ね合わせると何がいえるであろうか。それは、邪馬台国は出雲勢力の立てたクニであった--。 安本先生の考え a.『魏志倭人伝』の記す旅程では、伊都国を経て、終わりは、「南、邪馬台国にいたる。女王の都するところ」と記している。順路の読み方は、「順次式」「放射式」などがあるが、大略、「邪馬台国」は、「伊都国」の南にあったことになる。 ・女王国は伊都国、奴国、不弥国の大略南であり、『魏志倭人伝』の範囲では、90°方向が違っている例はない。
(2)出雲王国の正体(武光誠)[2013年3月刊] 「天下造(あめのしたつく)らしし大神命(おおかみのみこと)」の表現が九例、「天下造らしし大穴持命」が一例、「天下造らしし大神」が十例である。こういった表現は、大国主命が国作りの神であるから、朝廷は出雲の諸豪族を特別扱いすべきだという主張にもとづいて記されたものだ。 安本先生意見 (3)敗者の古代史(森浩一) 寛平5年(893)10月の『太政官符』によると、大和国城上郡の宗像神社が筑前国宗像郡の宗像大神と同神であることをわざわざ述べている。さらに筑前国宗像郡の金埼(かねざき)(鐘埼)の16人の正丁(せいてい)を大和の宗像神社の修理に派遣している。金埼は海女の多い海村で宗像大社の信徒圏である。宗像七浦のなかでも重要な土地である。 安本先生意見 ・両系相続
「初期・最盛期銅鐸」と「終末期銅鐸」の分布 島根県から大和にかけてきわめて広い範囲にわたって、出雲(大国主命)勢力があった。国譲りの結果、天菩比命が出雲の方に下り、邇芸速日命が近畿の方へ下った(260年から270年ごろ)。邇芸速日命勢力がその土地の伝統を引き継いで作ったのが終末期銅鐸であり、静岡県まで伸びている。この終末期銅鐸の銅の原材料は出雲地方の銅鐸とは違い、北九州の広型銅矛や広型銅戈、北九州の小形仿製鏡と同じである。つまり銅鐸の形式としては、その土地の伝統を引継いでいるが、銅の原料は北九州から持ってきた。北九州から銅の原料を持ってきたのが邇芸速日命勢力である。この大きい銅鐸を作った尾張氏という勢力は静岡県の方まで広がっている。
東大の和辻哲郎は邪馬台国東遷説を唱えた。北九州の勢力は鏡、玉、剣をシンボルとし、それに対し銅鐸の勢力があって、この銅鐸勢力を滅ぼしたとした。これは基本的にあっているのではないか。つまり下図のような勢力範囲になっていた。
・「ヒノキの年代」は」省略
|
2.邪馬台国の東遷と饒速日の命
|
いくつかの説を紹介する。 (1)『隠された物部王国』(情報センター出版局2008年刊)谷川健一 物部氏の出身は、現在の福岡県直方市、もしくは鞍手(くらて)郡あたりのようです。
(2)『日本古代氏族人名辞典』(吉川弘文館1990年)坂本太郎・平野邦雄監修 八尾市渋川にある渋川廃寺は、物部氏の氏寺と推測されている。 (3)『日本古代氏族事典』(雄山閣1994年刊)佐伯有清 なお、大阪府八尾市の旧跡部郷の地には、跡部遺跡があり、流水文銅鐸など、二つの銅鐸が出土している。 物部氏の祖先が饒速日命である。饒速日命は神武天皇に先立って畿内に天下たとされている。 何故なら、京都府、大阪府、兵庫県は饒速日命の地盤だからである。奈良県が大和朝廷のもとに入ったのは神武天皇以降である。奈良県で画紋帯神獣鏡や三角縁神獣鏡が出るようになるのは神武天皇以後となる。 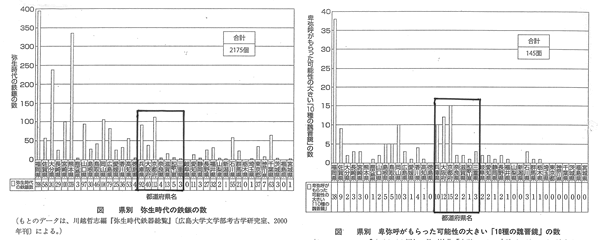 大阪の現在の真ん中付近には河内湖があった。その河内湖の下の渋川郡が物部氏の本拠地であった。現在物部の守屋の墓がある。その近くの亀井遺跡、跡部遺跡から銅鐸が出ている。この銅鐸が物部氏と関係する。
また、この渋川郡のあたりから、最も沢山の庄内式土器が出て来る。近畿でもう一つ庄内式土器がでてくるところが、下図に示す纒向遺跡を含む付近である。このあたりは後ちの磯城の県主の治める地域である。磯城の県主(あがたぬし)は物部氏の子孫である。 だから物部氏と庄内式土器は関係があると思われる。
■庄内式土器の出土する場所
石野博信氏はまた、『邪馬台国と安満宮山(あまみややま)古墳』(吉川弘文館、1999年刊)におさめられた「邪馬台国と大和」という文章のなかで、つぎのようにものべられる。 ■畿内の庄内式土器の出土地は、物部氏の根拠地であった
■凡河内(おおしこうち)氏[大河内氏] 河内湾は物部氏の根拠地があったところで、その現地マネージャは凡河内氏である。 前記の『日本古代氏族人名辞典』の大河内の項に下記がある。 また、『日本古代氏族事典』の凡河内(おおしこうちの)項にも下記がある 凡河内氏は和泉、河内、摂津を支配していた。山城も支配下である。 氏姓制度では臣(おみ)・連(むらじ)の下の直(あたい)で、更にその下が首(おびと)などである。
■凡河内氏の系図 『古事記』、『日本書紀』に記載されている系図から、天津彦根の命の子孫が凡河内直であるとされている。 『先代旧事本紀』は下図⑦の「天の火明(ほあかり)の命(みこと)」を「天照国照彦天(あまてるくにてるひこあま)の火明(ほあかり)櫛玉饒速日(くしたまにぎはやひ)の命」と記し、尾張(おわり)氏と物部氏の祖とする。天の火明の命を、饒速日の命と同神とする説を本居宣長は『古事記伝』で偽説とした。田中卓氏は同神とみてよいとする。 『新撰姓氏録』は火明の命の子の、天の賀吾山(かごやま)の命を、尾張の連、尾張の宿禰(すくね)の祖とする。 天津彦根の命の子の系図
天津彦根の命の後裔氏族が活動した地域を下記に示す。 この地図から、大和は空白となっている。 初めのところで述べた「出雲の大和(村井康彦)」の説の邪馬台国時代に奈良県に大きな勢力があったとは言えない。
|
| TOP>活動記録>講演会>第322回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |