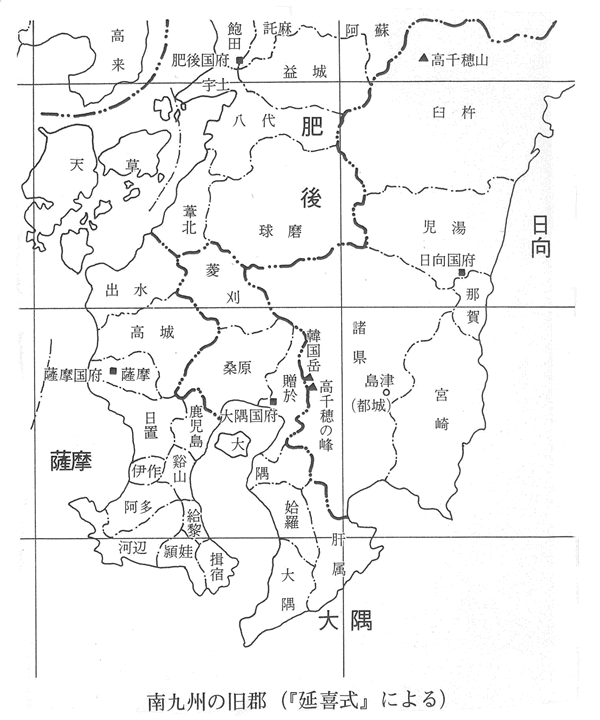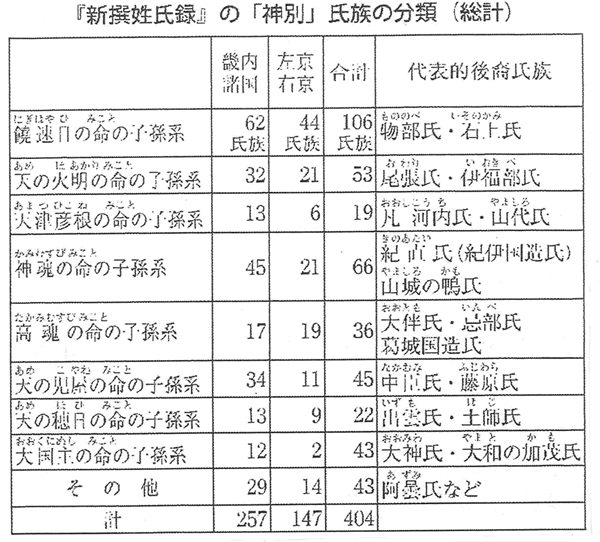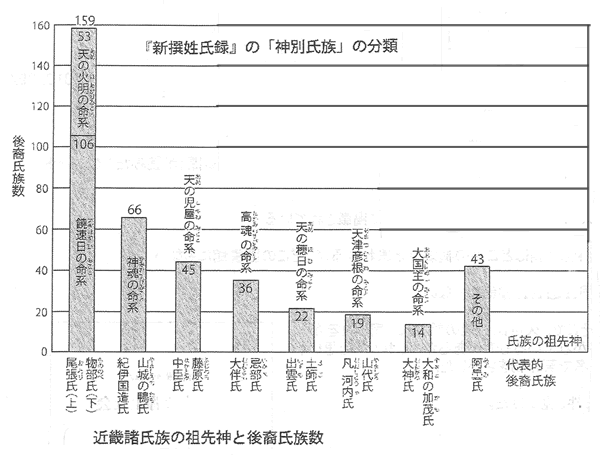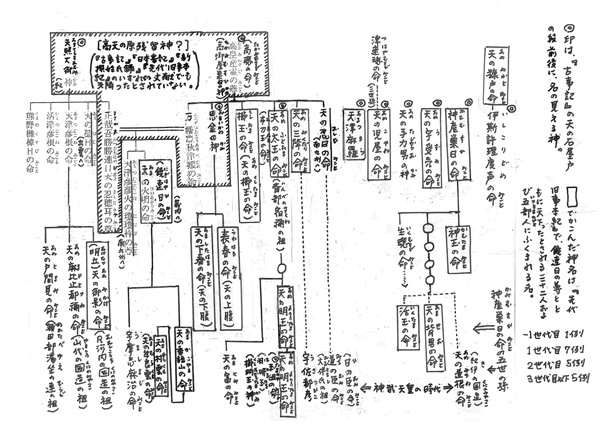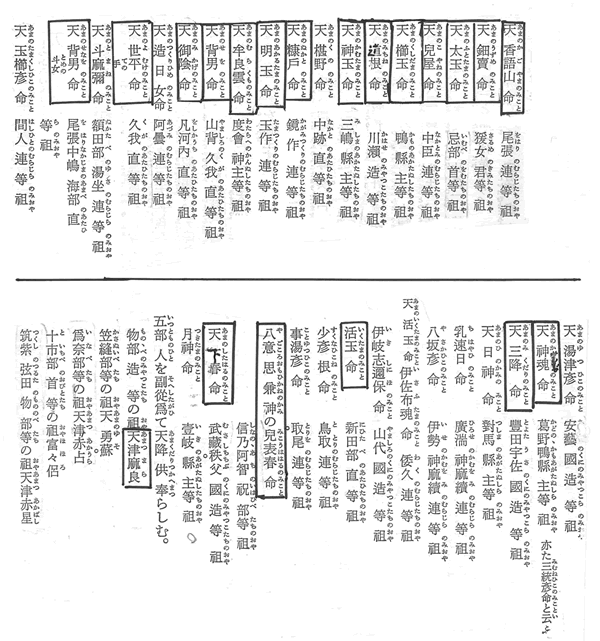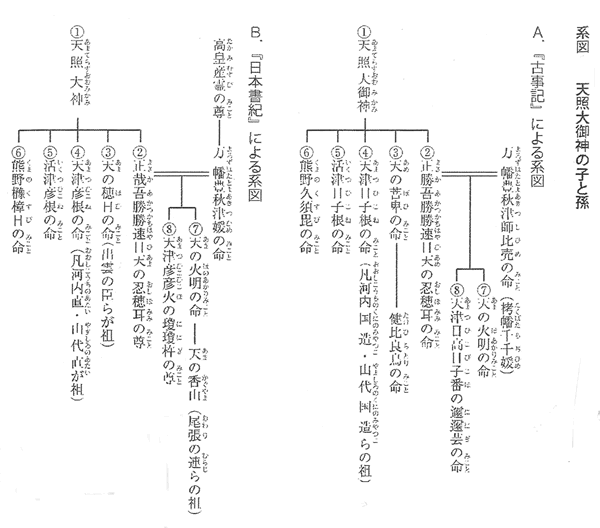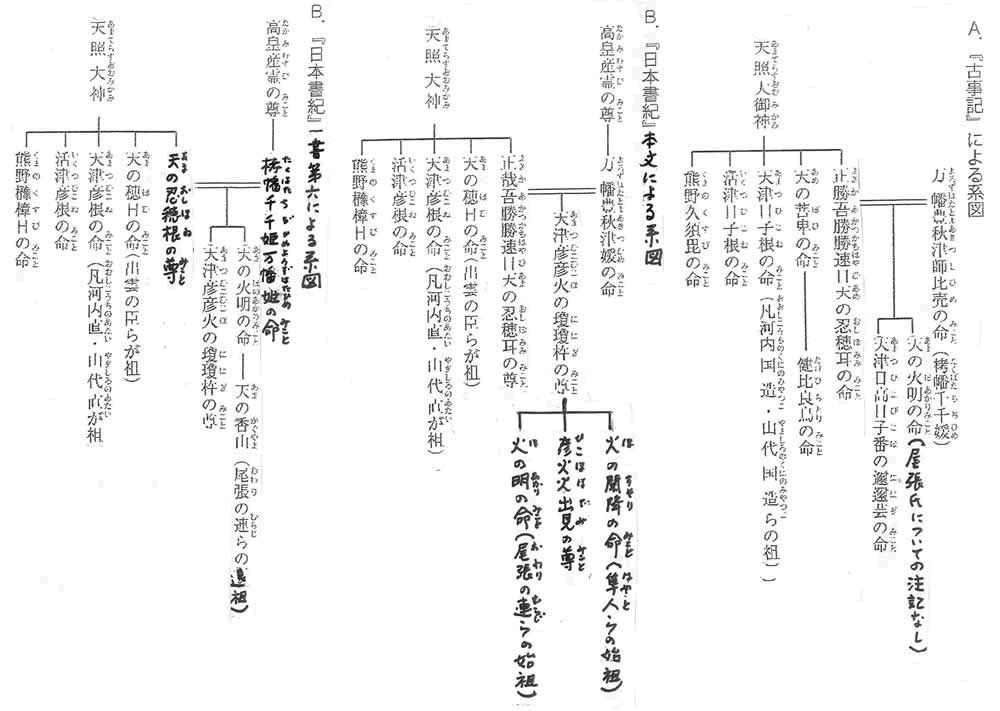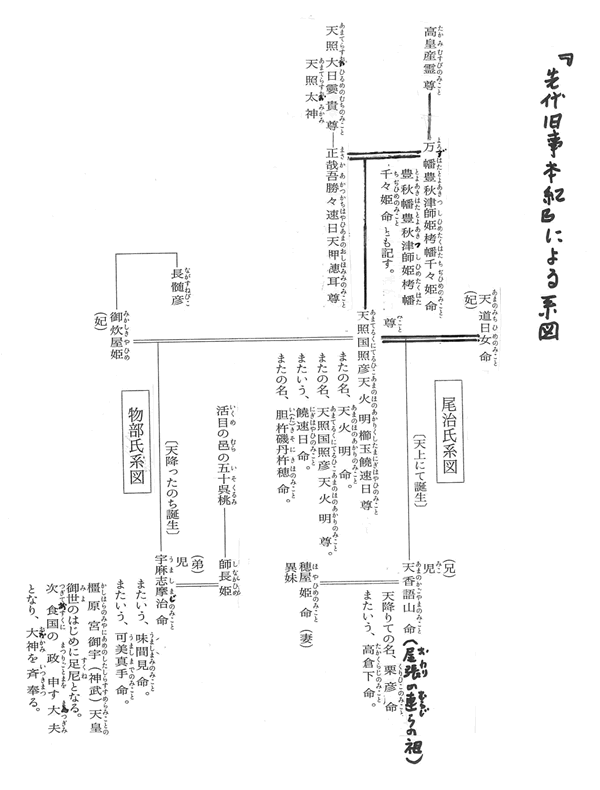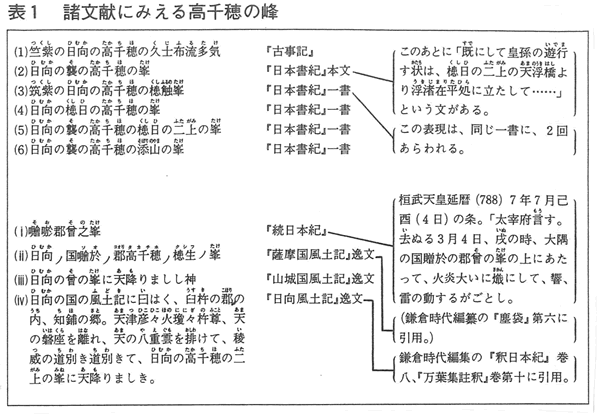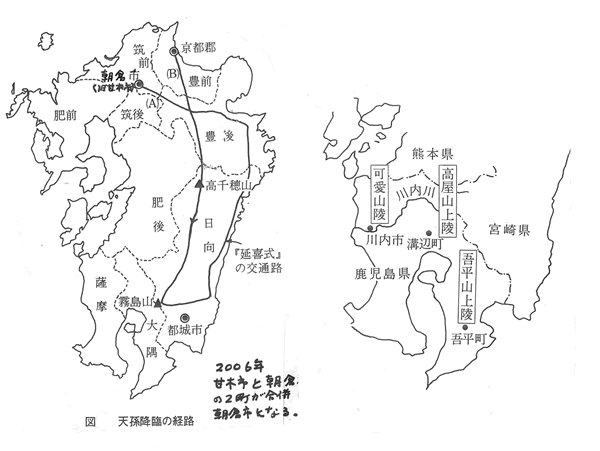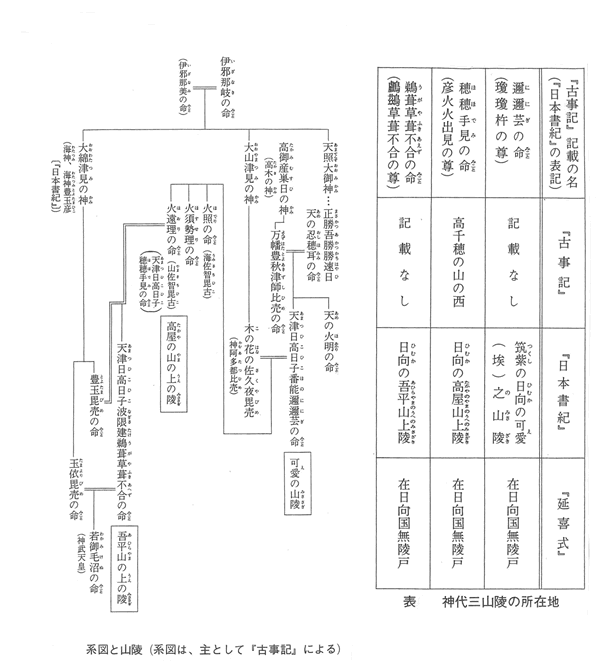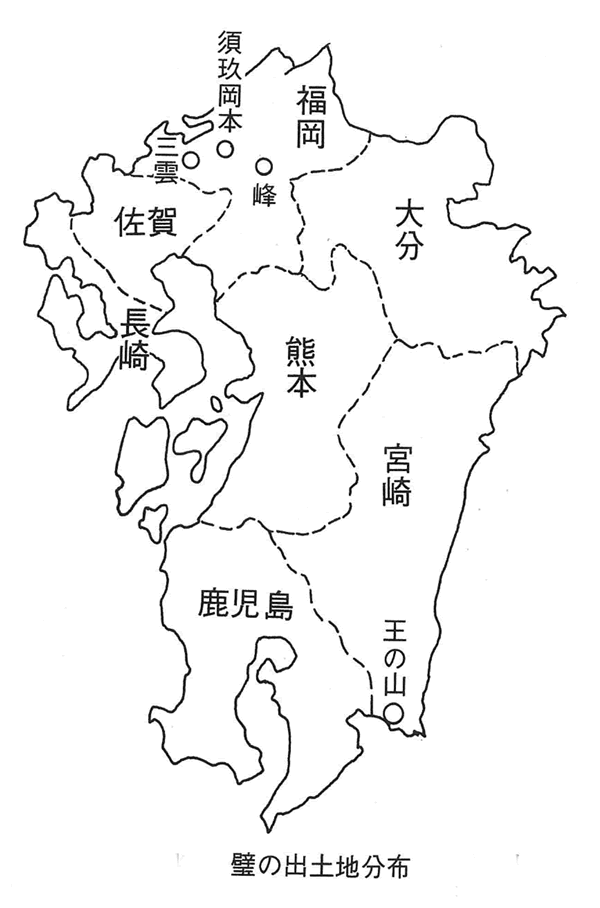■饒速日の命は実在したか
平安時代の系譜などの文献
・『新撰姓氏録』
『新撰姓氏録』は平安前期の系譜書。30巻、目録1巻(散逸)。嵯峨天皇の勅をうけて、万多(まんた)親王らが撰進。弘仁6年(815)成立。神武天皇の時代から弘仁期までの京畿の姓氏1182氏を皇別・神別・諸蕃・未定雑姓に分類、各系譜を記したもの。現存本は抄録本とされる。
・『先代旧事本紀』
『先代旧事本紀』は、「天の火明の命(ほあかりのみこと)」を「天照国照彦(あまてるくにてるひこ)天の火明櫛玉饒速日の命(あまのほあかりくしたまにぎはやひのみこと)」と記し、尾張氏と物部氏の祖とする。天の火明の命を、饒速日の命と同神とする『先代旧事本紀』の説を、本居宣長は『古事記伝』で偽説とし、田中卓氏は、同神とみとめてもよいとする(『日本国家の成立と諸氏族』(田中卓著作集2)
饒速日の命の子孫が多い
『新撰姓氏録』は「二田物部(ふたたもののべ)。神饒速日(かみにぎはやひ)の命、天降りまししときのときの従人(ともびと)、二田天物部(ふたたのあめのもののべ)の後(すえ)なり。」のような形で、神饒速日の命の天降り伝承をのせている。
・『新撰姓氏録』にのせられた1182氏の分類
皇別:335氏
神別・天神:265氏
神別・天孫:109氏
神別・地祗:30氏
緒蕃:326氏
未定雑姓:117氏
計:1182氏
| 分類基準 |
氏族数 |
% |
祖先となる天皇や神 |
| 皇別 |
335 |
28.2% |
神武天皇 |
| 神別 |
天神 |
265 |
404氏
(34.2%)
[265氏
(22.4%)
109氏
(9.2%)
30氏(2.5%)] |
饒速日の命、神魂(かみむすび)の命、高魂(たかむすび)の命、津速魂(つはやむすび)の命[藤原氏の祖神の天(あま)の児屋(こやね)の命は、津速魂の命の二世の孫] |
| 天孫 |
109 |
天の火明(ほあかり)の命、天の穂日(ほひ)の命、天津彦根(あまつひこね)の命[いずれも天照大御神の子孫] |
| 地祗 |
30 |
大国主の命 |
| 緒蕃 |
326 |
27.6% |
|
| 未定雑姓 |
117 |
9.9% |
|
| 計 |
1182 |
100% |
|
ここで、神別(しんべつ)に注目する。
①河内国神別
②摂津国神別
③和泉国神別
④山城国神別
⑤大和国神別
『新撰姓氏録』の「神別」氏族の分類、
河内・摂津・和泉・山城・大和の土着の氏族について、
饒速日の命の子孫が一番多く62氏族。次が天の火明の命で、32氏族である。もし『先代旧事本紀』の記述のように、饒速日の命と天の火明の命が同一人物であったなら、圧倒的に多くなる。
『新撰姓氏録』が書かれた時代は藤原氏が権力を持っていた時代である。しかし藤原氏の祖神の天(あめ)の児屋(こやね)の命の子孫は饒速日の命の子孫より少ない。
これは、何か歴史的事実を反映していたのではないか。

『新撰姓氏録』の「神別」氏族の分類(左京神別・右京神別)
これは都に本籍をおく氏族である。
これでも、饒速日の命の子孫が一番多く44氏族。次が天の火明の命で、21氏族である。
このように、饒速日の命が多いことは、簡単に饒速日の命が架空の人と言えないのではないか。

『新撰姓氏録』の「神別」氏族の分類(総計)
前の表の二つを合算すると下記の表となる。
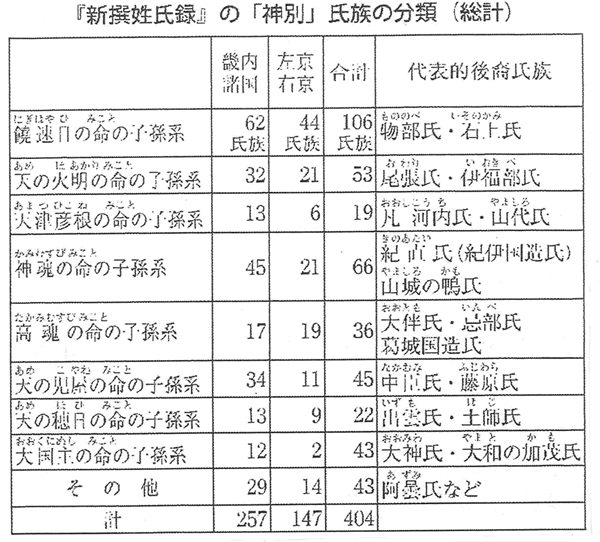
近畿諸氏族の祖先神と後裔氏族数
前の表で、饒速日の命と天の火明の命が同一として、書いたグラフである。
このように、饒速日の命と天の火明の命が同一とすると、圧倒的に多くなる。
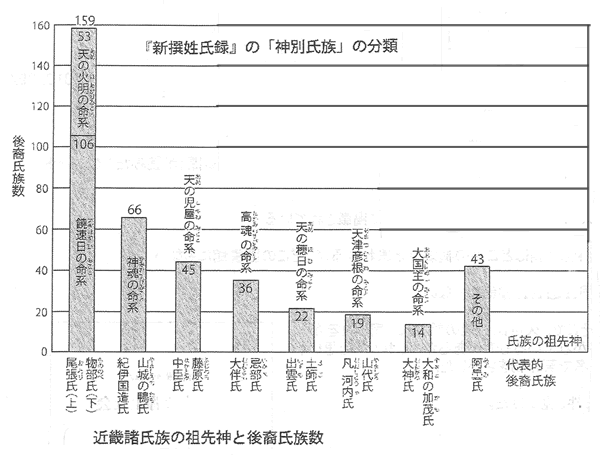
高天原の神の系図
古代では、兄弟姉妹などは同じような名前が多い。饒速日(にぎはやひ)の命と邇邇芸(ににぎ)の命は発音が近いので兄弟の可能性はある。
『記紀』で「出雲に天の穂日(ほひ)の命が天下り、近畿に饒速日の命に天下る。」となっている。
天の穂日の命は天照大御神の子の時代、饒速日の命は天照大御神の孫の時代となる。
◎を付けた神は『古事記』の天の岩屋戸の段の前後に名の見える神。
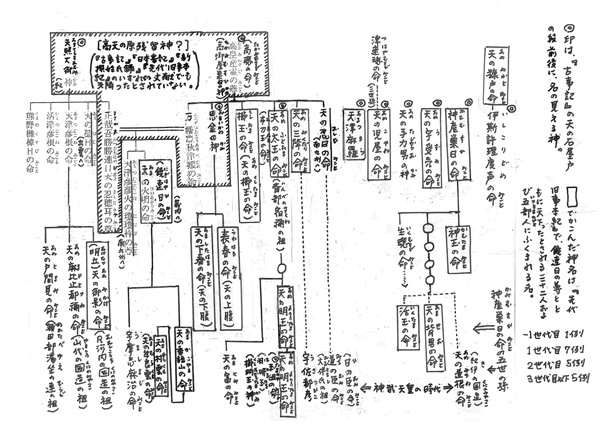
下記は『先代旧事本紀』から饒速日の命と一緒に天下った神々の表である。四角で囲んだのは、前の系図に表記している神々で、系譜が分かっている神々である。
例として、「天背男命(あまのせおのみこと)」は前の系図の「神産巣日(かむすひ)の命」の孫としてある。
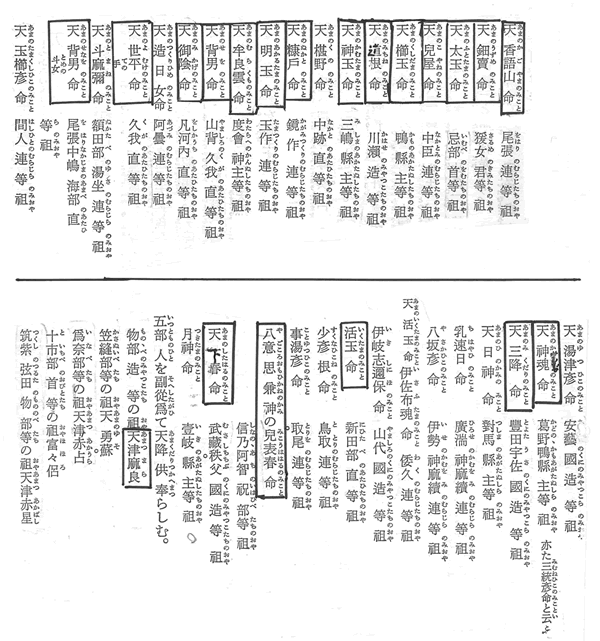
天照大御神の子と孫の系図について、『古事記』と『日本書紀』を比較して下記に示す。
天津彦根は国造(くにのみやつこ)クラスである。両方とも凡河内(おおしこうち)について、『古事記』は国造として、『日本書紀』では直(あたい)としている。これは両方とも、のちの郡長クラスを示すことになり、つじつまが合っている。
「天の火明の命」については、『古事記』は、邇邇芸(ににぎ)の命の兄であるとしている。『日本書紀』は、瓊瓊杵(ににぎ)の尊の子であるとする伝承と、瓊瓊杵の尊の兄であるとする異伝との両方を伝えている。
一度、南九州に天下った瓊瓊杵の尊の子が、饒速日の命といっしょに畿内に天下るのは、やや不自然である。
その意味では、瓊瓊杵の尊の兄弟とみたほうが無理がない。
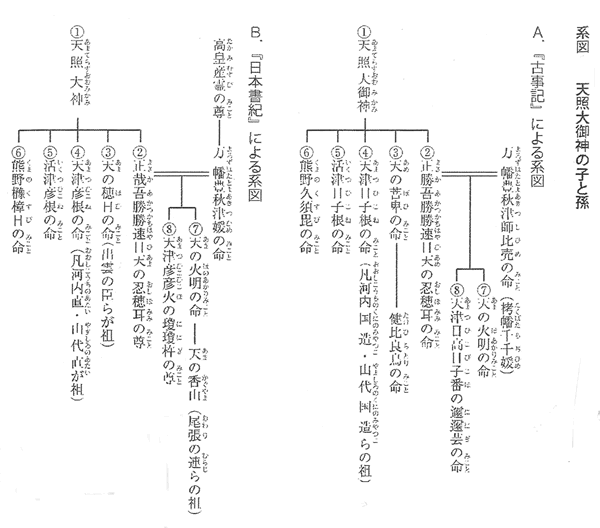
天の背男(せお)の命は『古事記』『日本書紀』に名がみえず。『新撰姓氏録』と『先代旧事本紀』とに名のみえる神である。
『先代旧事本紀』のばあい、饒速日の命といっしょに天降った人のなかに、京都府内の地域の現地支配者の祖先であるとされている人が何人かみえる。
たとえば、つぎのようなものである。
「天の背男(せお)の命 山背の久我(くが)の直(あたい)たちの祖(おや)」
「天背男命(あまのせおのみこと)」「阿麻乃西乎乃命(あまのせおのみこと)」両様の表記が『新撰姓氏録』にみえる。『新撰姓氏録』では、「神魂(かみむすび)の命の五世の孫、阿麻乃西乎乃命」などと記されている。
「久我」は、のちの山城の国の愛宕(あたご)郡久我村(京都市伏見区久我一帯)である。
■九州に残った邪馬台国の勢力はどうなったのか
『先代旧事本紀』の「国造(くにのみやつこ)本紀」において、九州の国造に「天孫」系の人は、ほとんどいない。わずかに「大隅国造」「薩摩国造」の「日佐(おさ)[長(おさ)か]」である。この国造となった「隼人」を火(ほ)の闌降(すそり)の命の後裔として、「天孫」とみなしうるか?
他に、豊の国造の祖が、天の穂日の命(出雲系)で、「天孫」となる。(宗像の君、宗形朝臣は大国主の命系で「地祗」)
・筑紫の国の場合について考えてみよう。
筑紫の国国造の後裔氏族と考えられる「筑紫の君」[君(きみ)は姓(かばね)]は第7代孝元天皇の皇子大彦の命を祖とする。
神武天皇よりもまえ以来の有力な天孫系氏族(天照大神の子孫とされる氏族が、この地とされる氏族が、この地に盤居(ばんきょ)していたようにはみえない)
・筑紫の君
筑後平野を本拠地とした豪族。筑紫国造の後裔氏族と考えられる。筑紫国造は孝元天皇の皇子大彦命を祖とし、継体朝に反乱して敗れた筑紫君磐井(いわい)は『日本書紀』に筑紫国造とみえるが、筑紫君氏の国造就任は磐井の乱後のことであろう。そして乱後も、一族は七世紀後半に至るまで在地の代表的首長として存続したらしく、その墳墓として八女市の八女古墳郡が比定されている。しかし氏人の名は上記磐井のほかに、磐井の子の葛子、斉明朝の百済救援軍に従い、唐軍の捕虜となって天智朝に帰国した筑紫君薩野馬(さちやま)が知られるだけである。(佐伯有清編『日本古代氏族事典』[雄山閣刊])
・筑紫の連(むらじ)
「筑紫連。饒速日の命の男(こ)、味真治(うましまぢ)の命の後(すえ)なり。(『新撰姓氏録』「山城国神別」
筑紫連氏の一族の人名は、他の史料にみえない。栗田寛は『旧事紀の天神本紀に、饒速日命五部の内に、筑紫弦田(つるた)物部等天津赤星(あまつあかほし)、また二十五物部の内に、筑紫聞(きく)物部贄田(にえた)物部あり、之をもて思ふに、筑紫連は、この筑紫の物部を掌る長なりと見ゆ』と述べているが、栗田の指摘のように、筑紫連氏は、『旧事紀』天神本紀の『副五部人為従天降供奉』条にみえる筑紫弦田物部、あるいは『天物部等二十五部人。同帯兵杖天降供奉』条にみえる筑紫聞物部・筑紫贄田物部の伴造氏族であったかもしれない。」
味真治命『古事記』は宇摩志麻遅命に作り、神武天皇段に「故、邇芸速日命、娶登美毘古之妹、登美夜毘売生子、宇摩志麻遅命。<此者物部連、穂積臣、婇臣(うねのおみ)祖也。>」とみえる。」(佐伯有清編『新撰姓氏録の研究』[考証編第三]吉川弘文館 1982年刊)
・筑紫君葛子(つくしのきみくずこ)
6世紀の北九州の地方豪族。磐井の子。磐井は、継体天皇が近江臣毛野(おうみのおみけの)に新羅遠征を命じた折に、新羅と結んで毛野の渡海をさえぎり反乱を起こした。継体22年(528)11月、継体が物部麁鹿火(あらかひ)らを送って磐井を討つと、その子葛子はその年の12月、父の罪に連坐することを恐れて糟屋(かすや)屯倉(みやけ)[福岡県粕屋郡・福岡市東区の付近]を献上して死罪をあがないたいと乞うて許されたという。 葛子の子孫筑紫君はかなりのちまで活躍している。(坂本太郎・平野邦雄監修『日本古代氏族人名辞典』吉川弘文館 1990年刊)
・大彦命の子孫の筑紫の君磐井は継体朝に反乱を起こし滅ぼされた。しかし、筑紫君葛子は土地を献上して、しばらくのちまで栄えたとある。
このように、九州方面で天照大御神や、高御産巣日や天の忍穂耳の命の子孫が豪族として栄えたように見えない。
邪馬台国の東遷現象があったとして、九州の邪馬台国の全体が動いたのか、それとも本体部分の一部が残ったのかと考えると。
本体部分の一部が残ったと見えるが、その後九州で豪族として栄えた形跡がないことから、近畿に移動したものが、その後勢力が大きくなり九州方面に残った子孫を吸収したことになったのではないか。
古代においては。都[宮処(みやこ)]が、しばしば移っている。
古代は都を移動したが、そうすると九州方面のかなりの勢力が邇芸速日命として畿内に移った。それは邪馬台国の本体が移ったようになったのではないか。
更に、神武天皇が南九州から畿内に移った。そして先に移って来ていた邇芸速日命の勢力と連合政権を造った。そのため畿内での邇芸速日命の子孫の勢力が栄えたのではないか。
■饒速日の命の子孫
饒速日の命の東遷も邇邇芸命の南遷も、基本的に、同一主体、同一勢力の東遷、南遷として描かれている。『日本書紀』神武天皇紀に、長髄彦が、饒速日の命が天神の子孫である証拠を見せる話がある。
この話から、饒速日の命が物部氏の祖先であることが書かれている。
・『古事記』、『日本書紀』、『先代旧事本紀』の系図
更に、天照大御神の子と孫の系図について尾張氏を示すため、『古事記』と『日本書紀』(本文系図と第六書による系図)を下記に示す。
尾張氏の祖先が「天の火明の命」となるように書かれている。また、尾張氏は三河・遠江から多く出土する三遠式銅鐸と関係していると考えられる。
「天の火明の命」の子孫が他でも国造となっている例が多い。更に、尾張氏は東方に伸びて行っている。
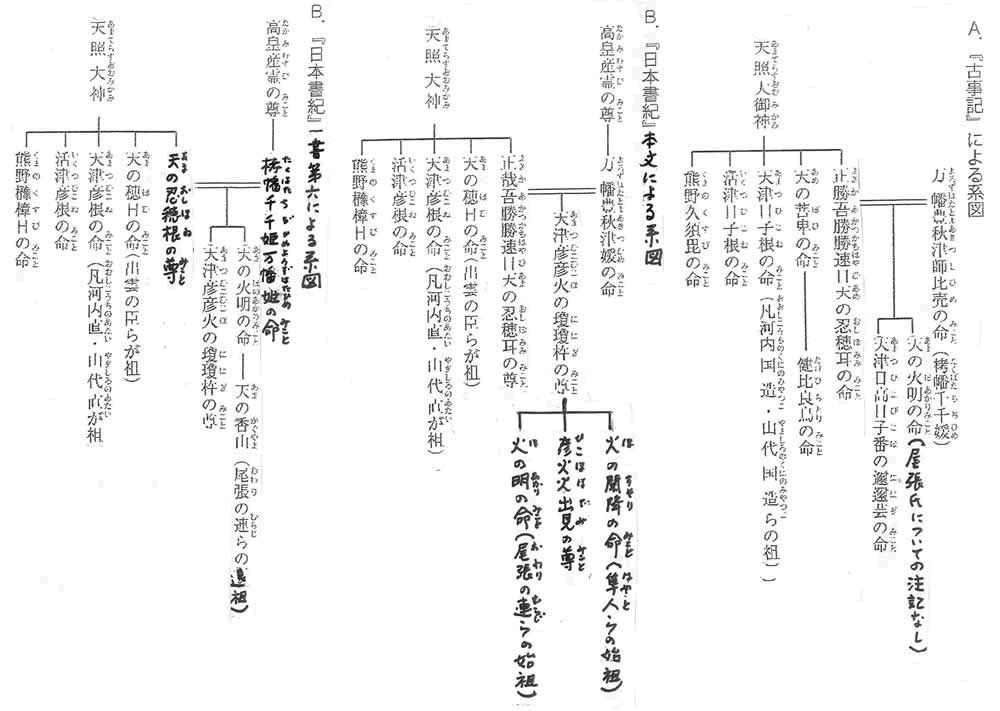
『先代旧事本紀』の系図を下記に示す。尾張(尾治)氏の系図が書かれており、「天香語山命(あまのかごやま)」の子孫とされている。
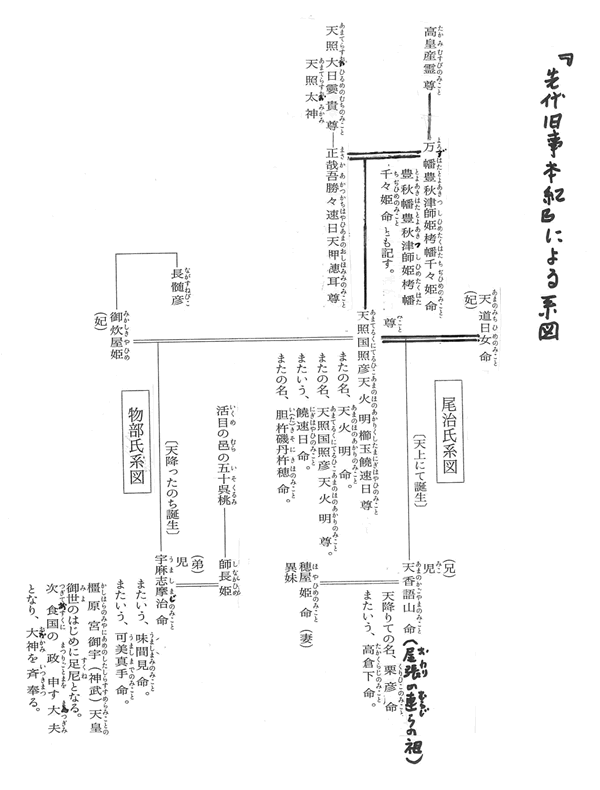
このように興味深い尾張氏については別途講演する予定。