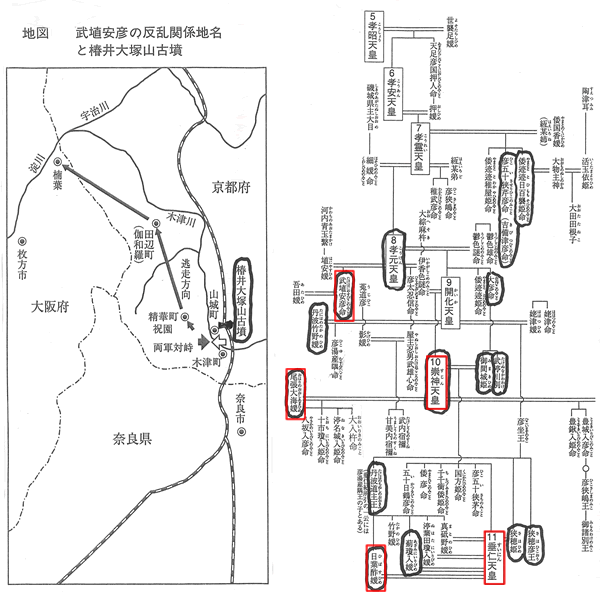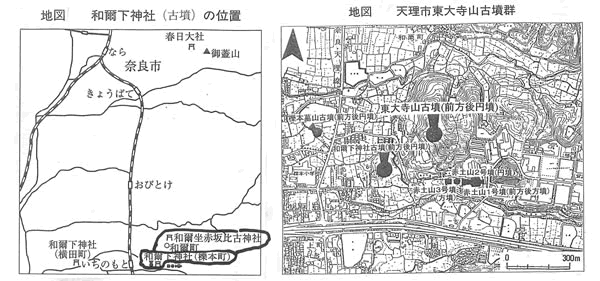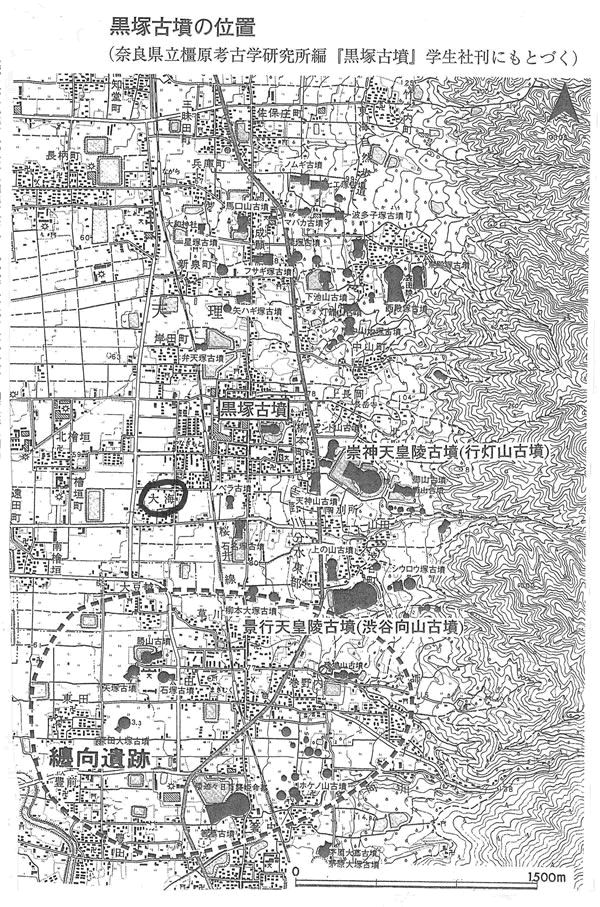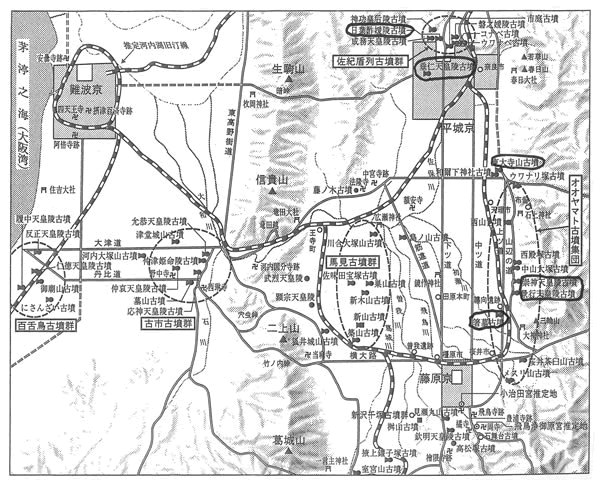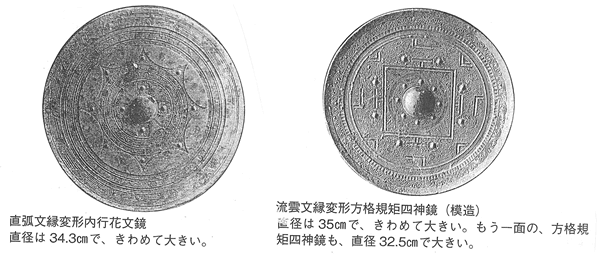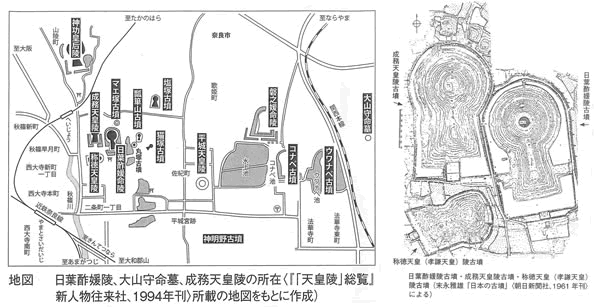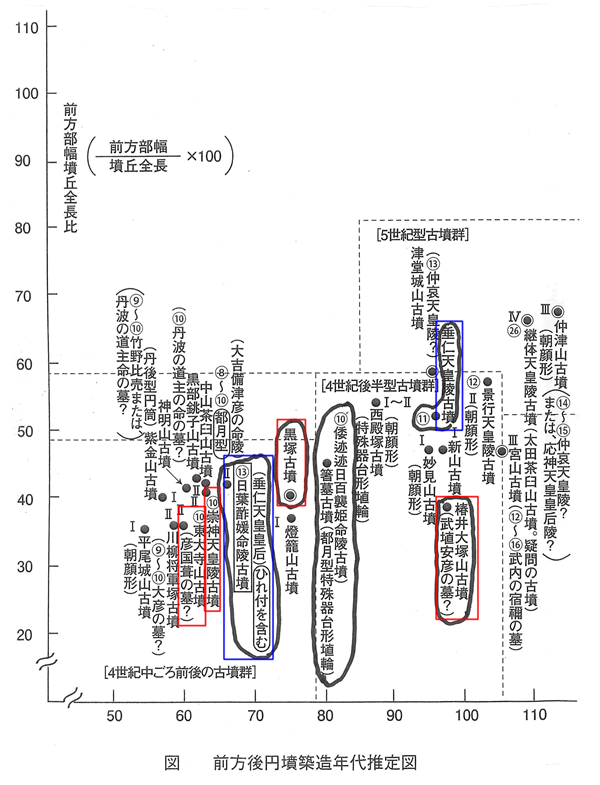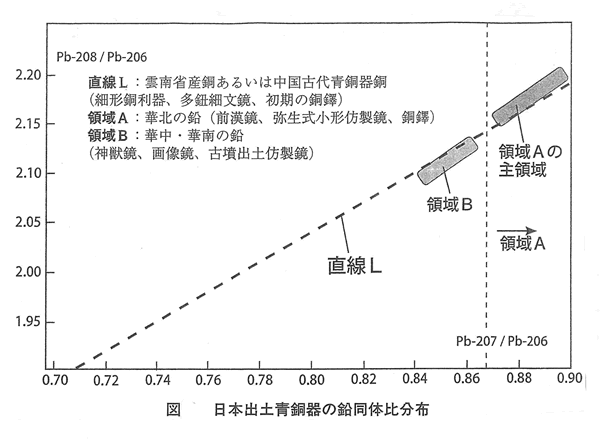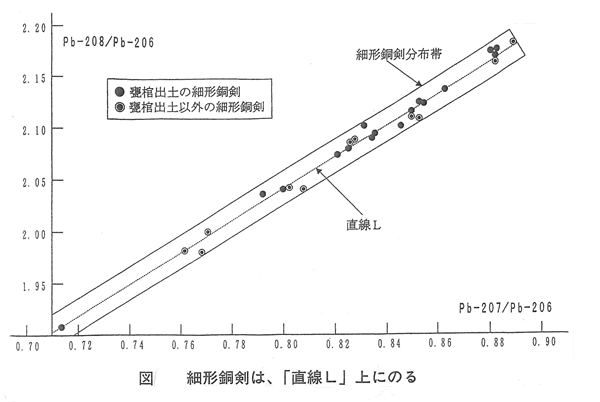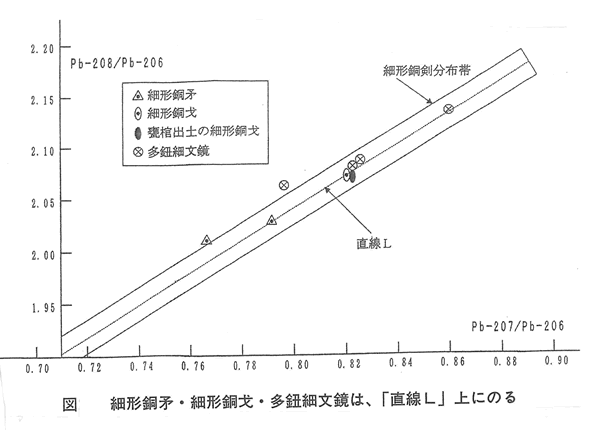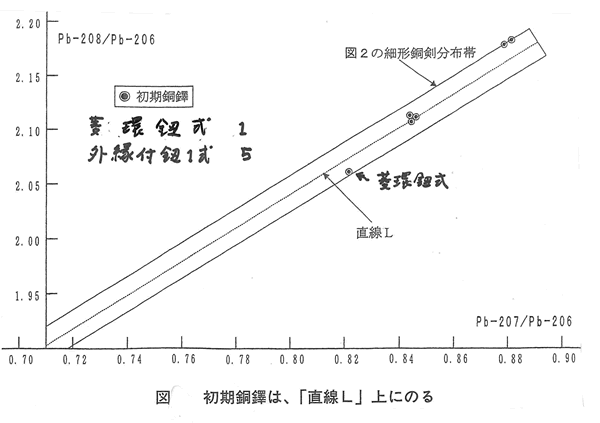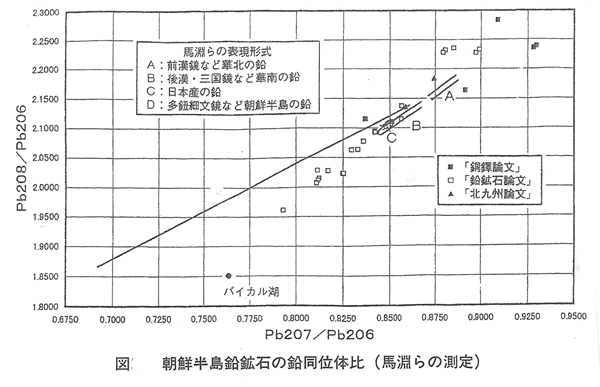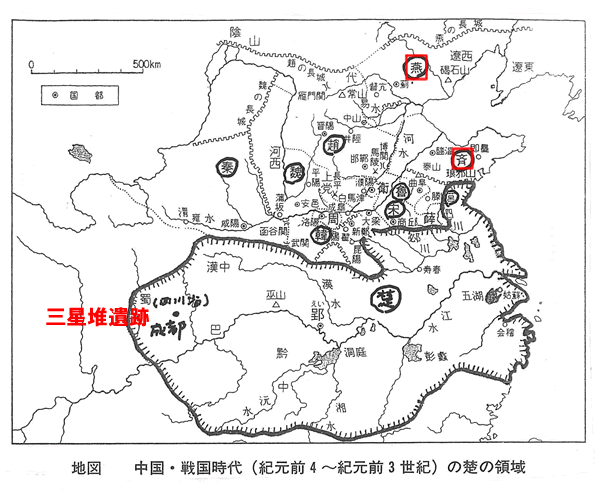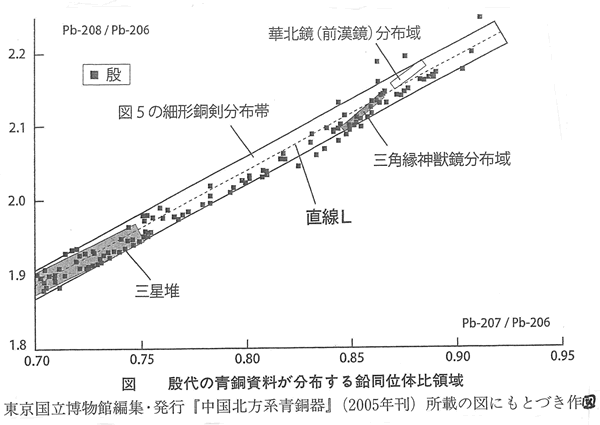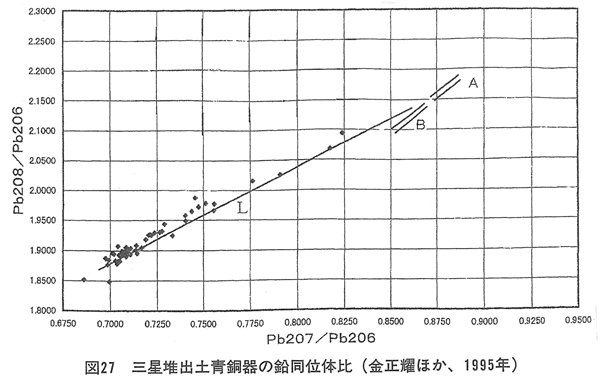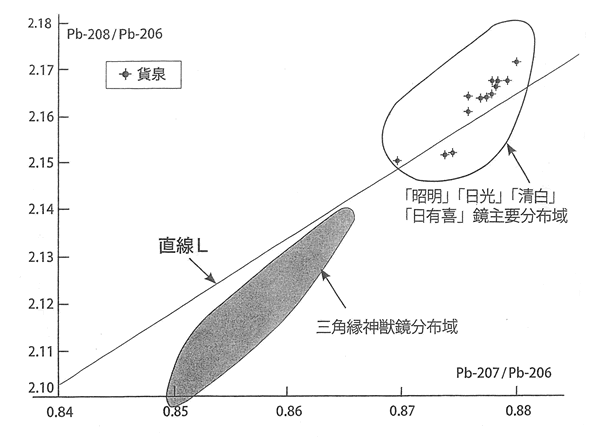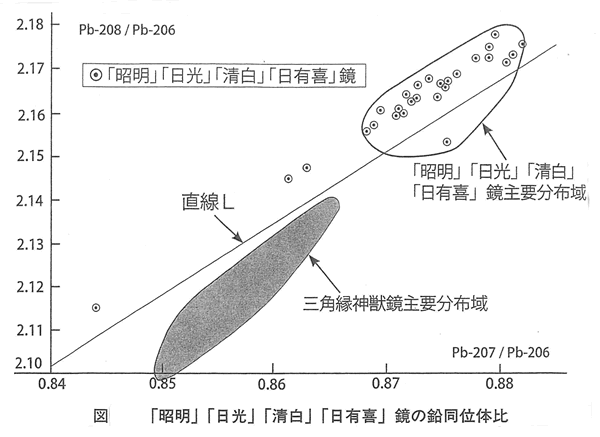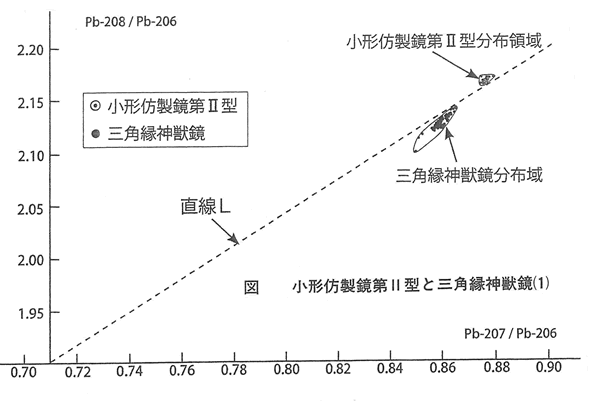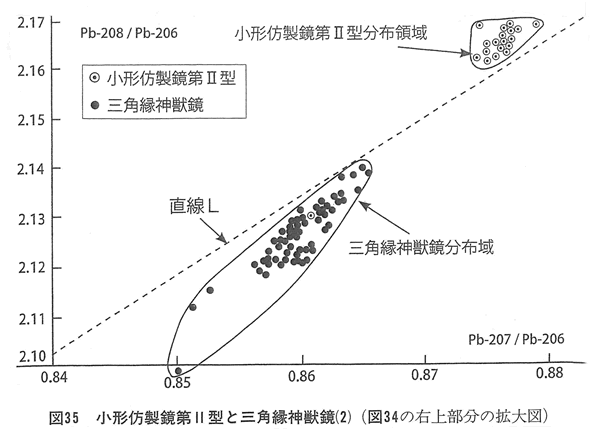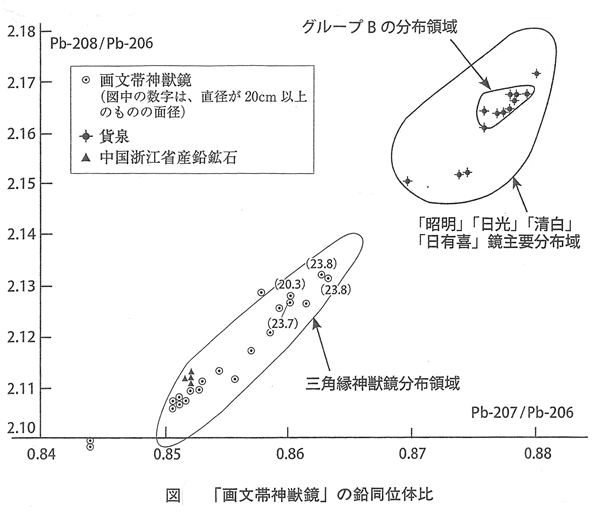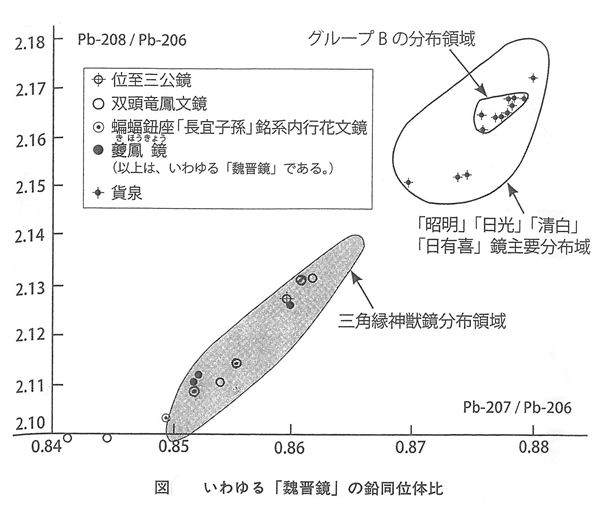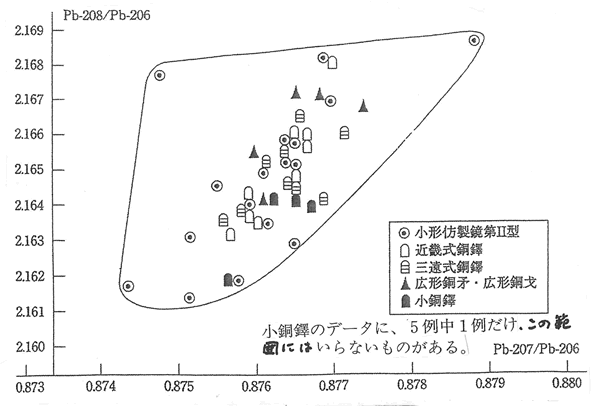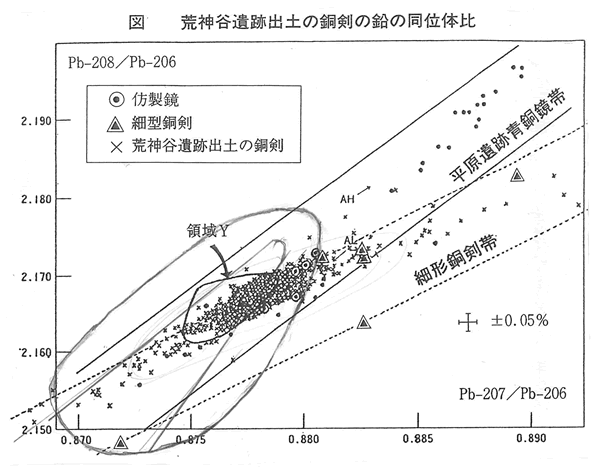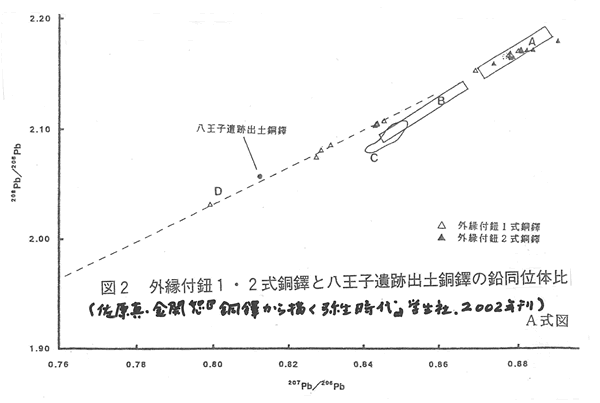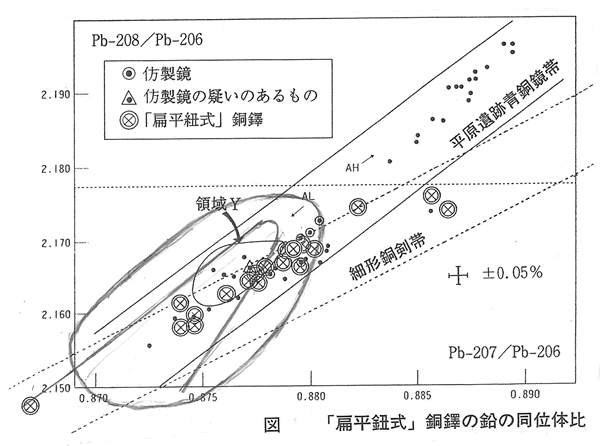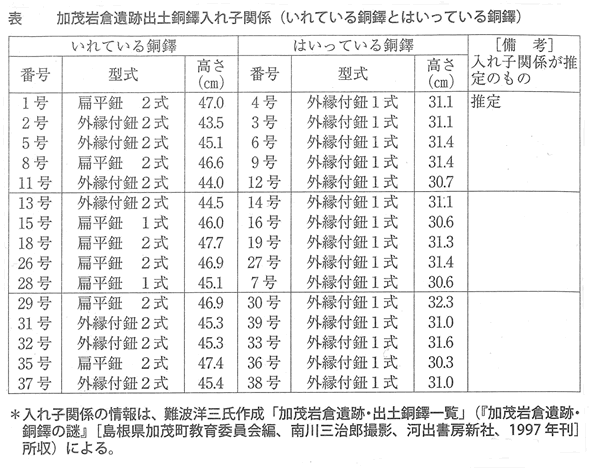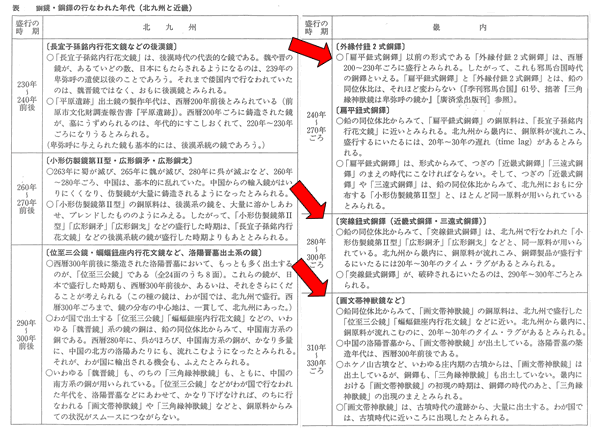| TOP>活動記録>講演会>第329回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第329回 邪馬台国の会(2014.5.25 開催)
| ||||
1.4世紀崇神天皇時代の諸古墳 |
2.4世紀垂仁天皇時代の諸古墳 |
3.鉛同位体比について |
銅の生産地や青銅器の製作年代を、あるていど知ることができる研究に、銅の中に含まれている鉛についての研究がある。 ■日本出土青銅器の鉛同位体比分布について下記の考え方がある。 (1)銅鐸の銅原料は、ほぼすべて、中国から来たとみられる。 (2)出雲系(大国主の命系?)銅鐸と、北九州系(饒速日の命系?)銅鐸とでは、銅原料にやや違いがみられる。 (3)出雲系銅鐸の銅原料は、中国古代殷代の銅に貨泉などのまじったものか。 (4)北九州系銅鐸の銅原料は、おもに貨泉を溶かしてまぜあわせたものか。 グラフの分析について 細形銅剣は直線L上にある。
この直線Lの青銅器について、昔は朝鮮半島産の銅だとされていたが、朝鮮半島の鉛鉱石の鉛同位体比は直線Lの上に乗らない。
■直線Lの青銅器について、新井宏氏は、つぎのように述べる。
このような理解は、全体的にみて、整合的であり、無理がない。すなわち、貴重な伝世の青銅器の入手であるなら、この昭王の時以外を想定することは困難である、逆にいえば、商周期の鉛同位体比をもつ青銅器が、五百年以上もたってから燕や朝鮮半島、日本に現れた現象を説明できる仮説は、現在のところ上記の想定以外には全く見出すことが困難なのである。 殷代青銅器資料が分布する鉛同位体比領域は直線L上にある。 三星堆出土青銅器の鉛同位体比は直線Lの上に乗る。燕が滅ぶのは紀元前222年で、楚が滅ぶのは紀元前223年であり、1年くらいの差である。そこで、燕の青銅器材料が日本に来たのならば、楚が滅んだことにより、三星堆出土青銅器が揚子江を渡って日本まで来たという仮説も考えられる。しかし、直線Lにのる多鈕彩細文鏡は燕から遼東半島、満州、朝鮮、日本と分布して出土する。このことから考えて、三星堆出土青銅器の可能性は低いと思われる。 ■北九州と畿内の青銅器材料の共通性 前漢鏡の鉛同位体比は貨泉と同じ分布となる。 北九州から出土する 小形仿製鏡Ⅱ型(箱式石棺とからの出土が多い)と、畿内を中心として広い範囲から出土する三角縁神獣鏡の鉛同位体比について、小形仿製鏡Ⅱ型は「昭明」「日光」「清伯」「日有喜」鏡主要分布の狭い範囲(たまご型)に集中し、三角縁神獣鏡もその下の比較的狭い範囲に集中する。
画文帯神獣鏡の鉛同位体比は三角縁神獣鏡と同じ分布の範囲となる。 北九州から中心に出土する西晋時代のいわゆる「魏晋鏡」の鉛同位体比について、位至三公鏡、双頭竜鳳文鏡、蝙蝠鈕座内行花文鏡、變鳳(きほう)鏡のいわゆる「魏晋鏡」は三角縁神獣鏡と同じ分布となる。 たまご型の領域は「昭明」「日光」「清伯」「日有喜」鏡などの前漢鏡、貨泉、雲雷文「長宜子孫」銘内向花文鏡が分布する。そしてグループB[注:領域Bとは別]は、たまご型の領域から更に狭い領域で、小形仿製鏡Ⅱ型、広型銅矛・戈、近畿・三遠式銅鐸、小銅鐸が分布する。 拡大図でグループBの狭い領域の小形仿製鏡Ⅱ型、広型銅矛・戈、近畿・三遠式銅鐸、小銅鐸の鉛同位体比の分布をみる。 国立歴史民俗博物館の館長であった考古学者の故佐原真は、その著『祭りのカネ銅鐸』(講談社、1996年刊)のなかで、つぎのようにのべている。 しかしこれらの青銅器は日本製と思われ、同じ鉱山とは考えられない。存在した青銅器を集めて溶かしたため、同位体比が狭い範囲なったのではないか。 小形仿製鏡Ⅱ型、広型銅矛、広型銅戈は北九州から出土し、近畿式銅鐸、三遠式銅鐸は近畿から静岡県の範囲で出土する。しかし同じ原材料が使われているということは、近畿式銅鐸、三遠式銅鐸の原材料は九州からもたらされたと考えられるのではないか。
外縁付鈕式1式銅鐸は直線Lの上に乗り、 外縁付鈕式2式銅鐸は領域Aの方に移っている。これは古い銅鐸は細形銅剣と同じ鉛同位体比であり、少し新しくなった銅鐸は貨泉や、前漢鏡と同じ鉛同位体比に移ったように見える。 更に新しくなった扁平鈕式銅鐸の鉛同位体比は、たまご型の領域に集まる傾向がある。
出雲系の青銅器は最初直線Lの上にあり、その後、グラフの上の方に移動して領域Aの範囲になり、更に、領域Y(グループB)の範囲にまとまるように移動して行くように見える。しかし、近畿式・三遠式銅鐸までは狭い範囲にはならない。 ■加茂岩倉遺跡出土銅鐸入れ子関係(入れている銅鐸とはいっている銅鐸)
■以上まとめると、古い順に記せば、 となり、北九州から20~30年遅れて近畿や出雲やその他にもたらされたと考えられる。
|
| TOP>活動記録>講演会>第329回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |