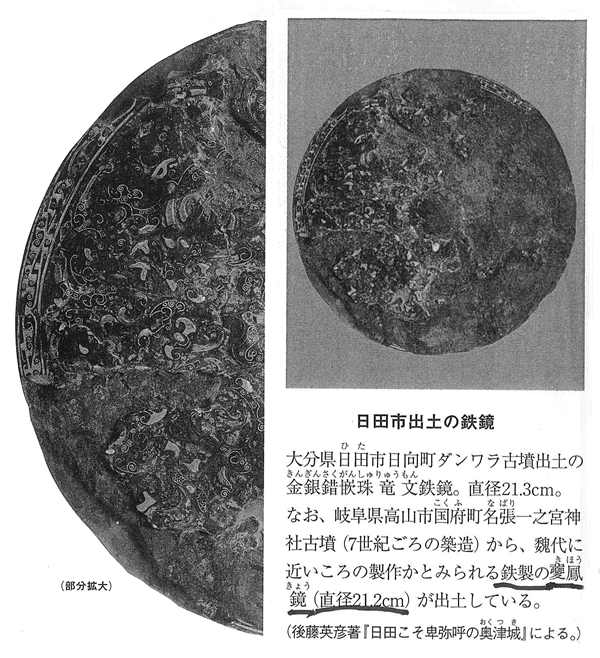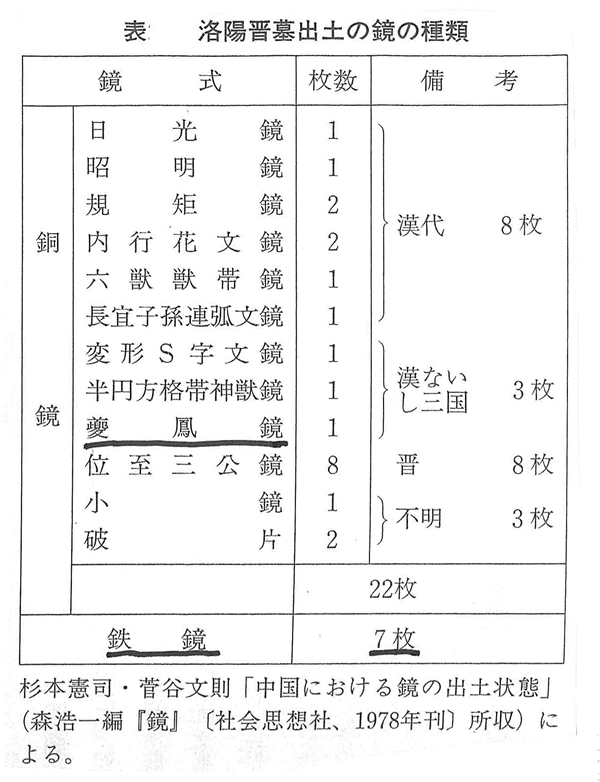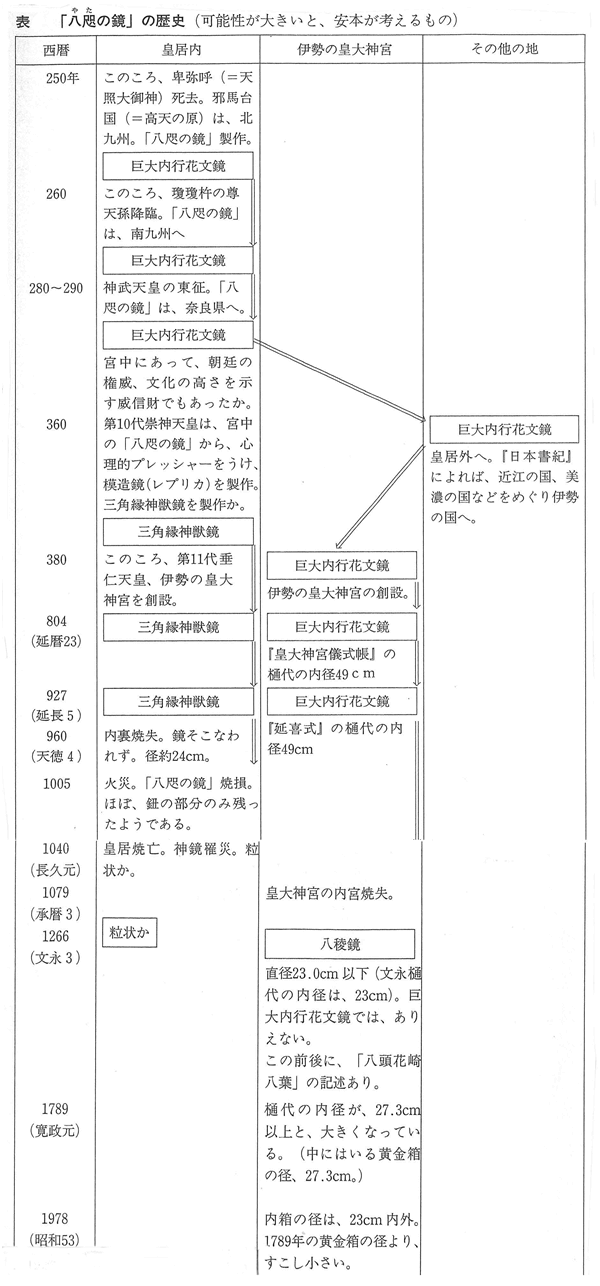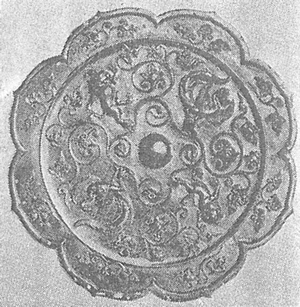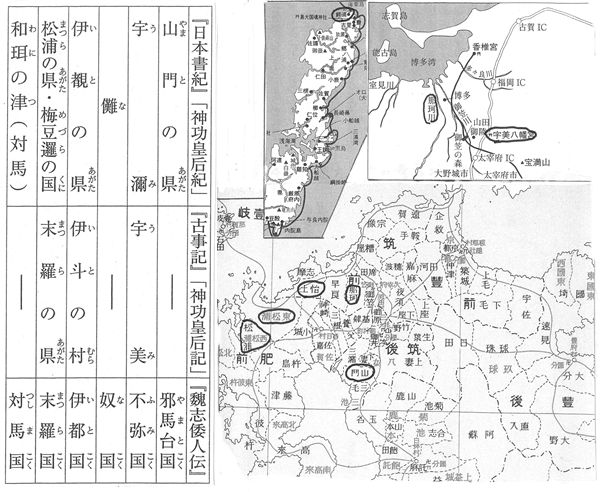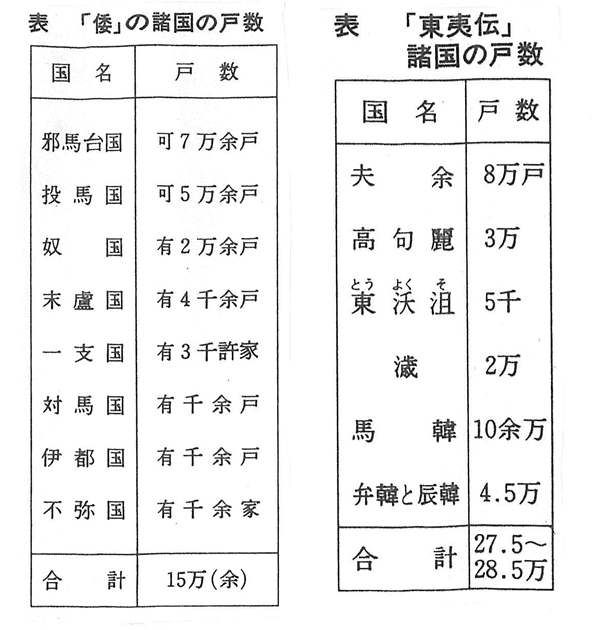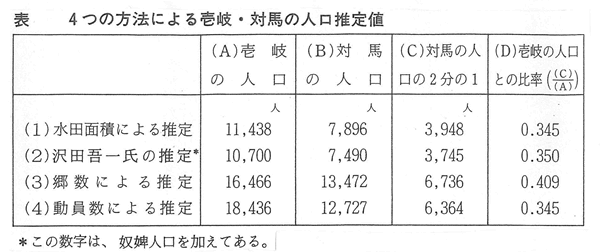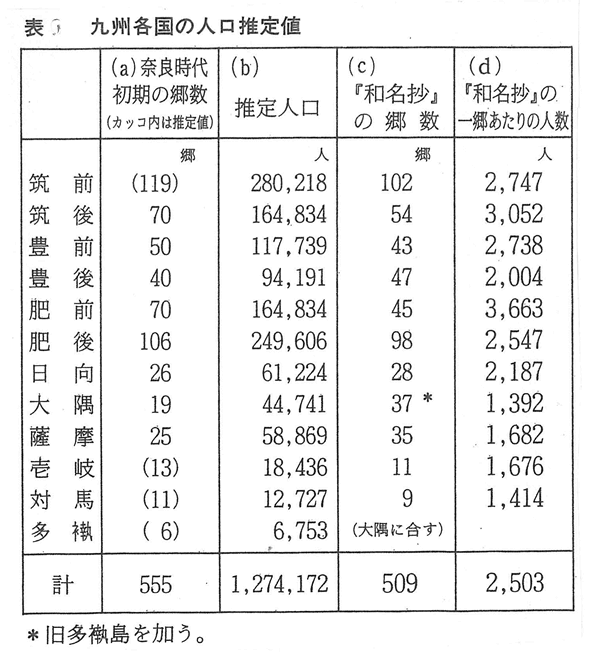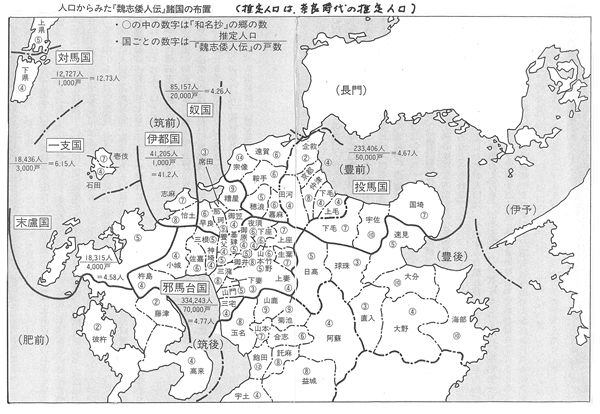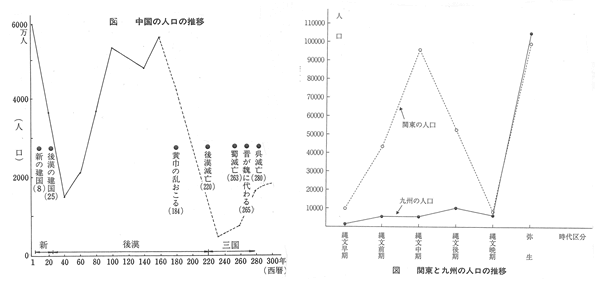伊勢神宮は三重県伊勢市にある皇室の宗廟(そうびょう)で、正称、神宮である。皇大神宮[内宮(ないぐう)」と豊受(とようけ)大神宮[外宮(げぐう)]との総称である。皇大神宮の祭神は天照大神、御霊代(みたましろ)は八咫鏡(やたのかがみ)で、豊受大神宮の祭神は大神である。20年ごとに社殿を造り加える式年遷宮の制を遺し、正殿の様式は唯一神明造(ゆいつしんめいづくり)と称す。
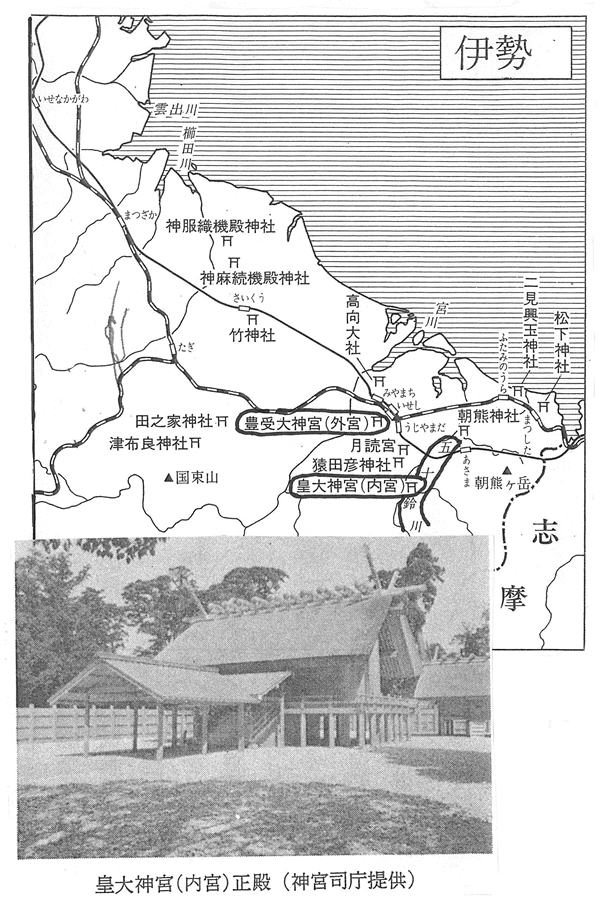
伊勢の皇大神宮(こうたいじんぐう)[内宮(ないくう)]の創建については、『古事記』の「垂仁天皇記」に、「(垂仁天皇皇女の)倭比売(やまとひめ)の命が、伊勢の大神の宮を祭った」という記事があり、『日本書紀』の「垂仁天皇紀」の25年3月の条に、倭姫の命の内宮創建の話がのっている。
記紀から、伊勢の皇大神宮は垂仁天皇の時代に創建されたことになる。
谷川健一郎編『日本の神々 神社と聖地(6)伊勢・志摩・伊賀・紀伊』(白水社 1986年刊)に八咫鏡について、下記の記事がある。
「内宮の御神体の八咫鏡(やたのかがみ)は、御樋代(みひろしろ)という小箱に入れたうえで、いろいろな衣と裳(も)・比礼(ひれ)・帯・おすひ・履(くつ)・鏡・御衾(おふすま)・櫛筥(くしはこ)・枕などとともに「御船代(みふなしろ)」という大きな櫃(ひつ)のなかに納め、正殿(本殿)の神座の床の上に置かれていた。南北朝時代の『貞和御餝記(じょうわおかざりき)』にある御船代の形状は、古墳時代前期に盛行した舟形石棺に似ており、たとえば、その時期にこそ御船代とさらには神宮が成立したのではないかと推定する説もある。」
「御船代」というのは、つぎのようなものである。
まず、「霊代(たましろ)」ということばがある。
「霊代」というのは、神や人の霊の代りとして祭るもので、「八咫(やた)の鏡」は、天照大御神の「御霊代(みたましろ)」である。
伊勢の皇大神宮は、天照大御神の「御霊代」である「八咫の鏡」をまつる。
つぎに、「樋代(ひしろ)」ということばがある。
「樋代」というのは、「霊代」をいれる容器のことである。伊勢の皇大神宮のものは、「御樋代(みひしろ)」とよばれ、円筒型をしている。
「樋代」などの大きさは、時代によって異なる。
文永樋代を下図に示す。
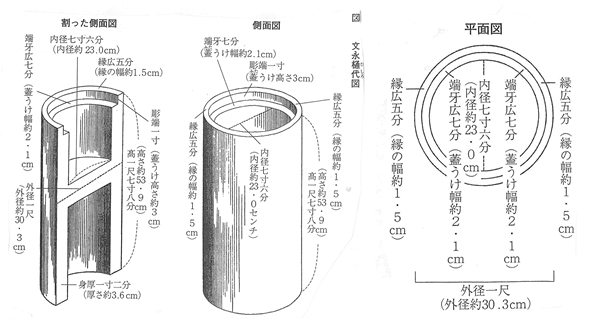
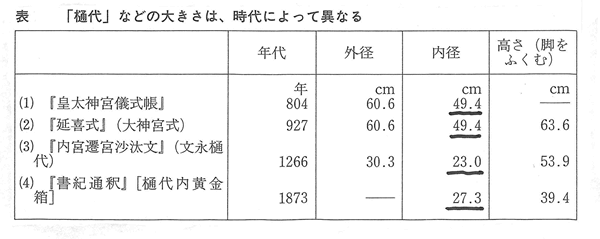
そして、「船代(ふなしろ)」ということばがある。
「船代」は、「樋代」をさらにおさめる容器である。伊勢の皇大神宮のものは、ふつう「御船代(みふなしろ)」とよばれる。
江戸時代の安永4年(1775)に成立した荒木田経雅(あらきだつねただ)の『大神宮儀式解(だいじんぐうぎしきげ)』に、「船代は、木を彫(え)りて船の形とす」とある。
「船代」という名のとおり、船の形をしている。
さて、伊勢の皇大神宮の「御船代」を模造した「船代」が、奈良県の石上(いそのかみ)神宮に存在する。
石上神宮の神剣[布都御魂大神(ふつのみたまおおかみ)]をおさめるために、明治7年(1874)8月、石上神宮の大宮司であった管政友(かんまさとも)が調整したものである。
「船代」の蓋と身の両方に丸い突起があるが、これは縄掛突起のように思われる。
縄掛突起は、石棺の蓋の縁部や身の上部の前後両端・側面につくられた短い棒状で方形の突起部。一般にくり抜きの割竹形石棺・舟形石棺などには蓋・身ともに前後両端にみられ、長持形石棺には蓋・身ともに前後・側面にもみられる。家形石棺になると形式化して蓋のみとなる。名称は突起部に縄をかけて運搬したと想定したことに由来する。本来は蓋と身の緊縛封鎖用施設であり、それが形式化して存続・残存したものと思われる。
下図の上のものは石上神宮の「船代」で、下のものは伊勢神宮の外宮の「船代」である。
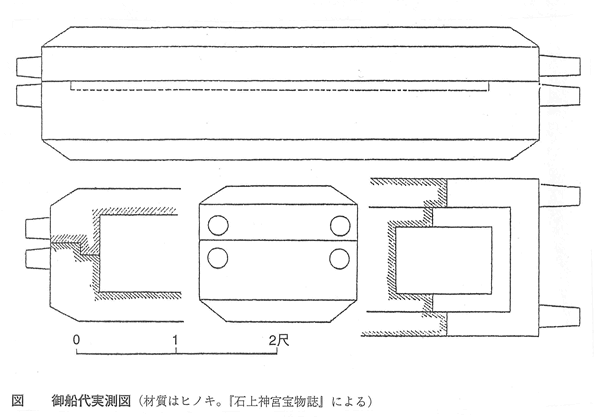
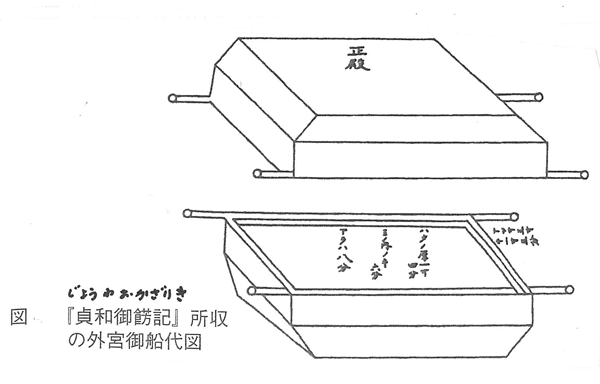
棺の形式と前方後円墳の形式から見て、「舟形木棺」「舟形石棺」は4世紀型古墳から出土する。
(下図はクリックすると大きくなります)
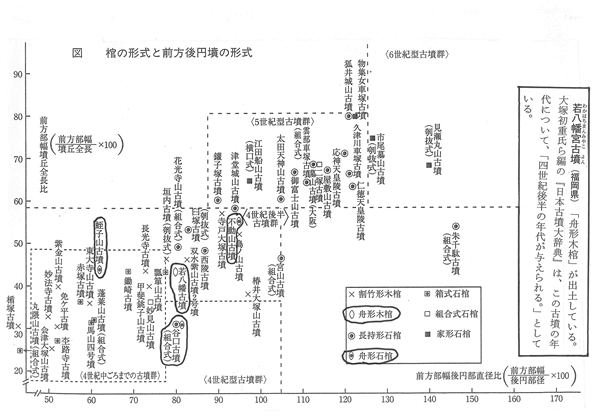
『古事記』『日本書紀』の記す皇大神宮の創建年代は、「舟形木棺」「舟形石棺」の行なわれる時期と、大略あっているようにみえる。すくなくとも、「御船代」の形は、5世紀後半や、6世紀、7世紀ごろに主流であった棺の形とは、結びつかない。4世紀後半から5世紀前半ごろの棺の形によって説明がつく。
「御霊代(みたましろ)」である「八咫の鏡」については、これを、「内行花文鏡」とみる原田大六氏や森浩一氏の説がある。
また、「三角縁神獣鏡」とみる出口宗和(でぐちむねかず)氏の説がある。これらの説は、いずれも、それなりの根拠をもっている。
そして、「内行花文鏡」は、おもに、3世紀、4世紀を主とする遺跡から出土するものである。「三角縁神獣鏡」は、おもに、4世紀代の古墳、つまり、崇神天皇、垂仁天皇ごろとみられる古墳から出土するものである。
話は、疑いすぎなければ、全体的には、よくあっている。
天皇の一代平均在位年数を約10年として推定すれば、垂仁天皇の活躍年代は、西暦360年~370年ごろとなる。伊勢の皇大神宮の創建も、その前後であろう。
八咫の鏡は、三種の神器の一つであり、『古事記』『日本書紀』によれば、天照大御神が天の岩屋にかくれたとき、石疑姥(いしこりどめ)の命が作ったという。現在も、伊勢の皇大神宮の内宮(ないくう)に奉斎されているとされ、その模造の鏡は、宮中の賢所(かしこどころ)に奉安されている。
八咫の鏡は、内行花文鏡であるとする説と、三角縁神獣鏡であるとする説と、鉄鏡であるとする説などがある。
(1)内行花文鏡説
福岡県前原市大字有田の平原遺跡から直径46.5cmの巨大な内行花文鏡が、5面出土している。日本最大のものである。八咫の鏡は、この種のものとする説がある。(原田大六著「平原弥生古墳」〔葦書房刊〕による。)
巨大内行花文鏡も、考えられる。
 鏡が小さいのに、無用に大きな樋代(ひしろ)をつくることはないであろう。
鏡が小さいのに、無用に大きな樋代(ひしろ)をつくることはないであろう。
「樋代」の外径60センチ内径50センチ近く(49センチ)といえば、かなりな大きさである。
日本神話にあらわれる八咫の鏡を内行花文鏡であろうとする見解を、最初に強く主張したのは、北九州の平原遺跡の発掘で著名な、原田大六(1917~1985)である。
原田大六は、その著、『実在した神話』(学生社、1966年刊)のなかで、およそつぎのようにのべる。
「『延喜式』の『伊勢大神宮式』でも、『皇太神宮儀式帳』でも、容器の内のりが一尺六寸三分(約49センチ)の径を持つと明記している。平原弥生古墳に副葬されていた八咫ある鏡は、径46.5センチであるから、2.5センチの手で持って納める余裕まで持っている。ということは伊勢神宮の『樋代(ひしろ)』の中にすっぽり納まる大きさであるといえる。
文永・弘安年代(1264~1288)の調進として『正中御飾記(しょうちゅうおかざりき)』に記されているのは、樋代の径高各一尺五寸(約46センチ)と記されている。この記載は詳しく記したものでない。しかし大略でも前記の寸法に近いものである。
つぎに、伊勢神宮の八咫の鏡の形態(文様)についての記録をあたってみよう。伊勢神道の経典である『御鎮座伝記』には『八頭花崎八葉形也(やたはなさきやはのかたちなり)』とある。
この文を『八頭花崎』と『八葉』に分けてみよう。『八頭花崎』とは平原弥生古墳出土の『内行八花文』にあたり、『八葉』はそのまま紐をめぐる『八葉座』に相当するのではあるまいか。(以下、写真 とみくらべながら読んでみていだきたい)。
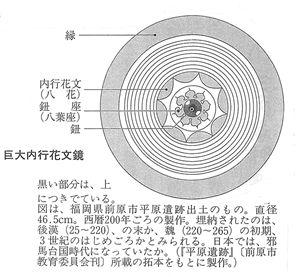
もう少し考えを前進させてみよう。もう少し考えを前進させてみよう。『八頭花崎』の『八頭』は日本語ではヤツガシラと読まれる。同じような頭だけが八個ある状態である。『花崎』とは(ナサキで、花弁の先端ということであろう。先端のみの八花弁を『八頭花崎』といったと考えられる。考古学でいう『内行八花文』も、花弁形なら外側に貼り出るのに、内側に向かっているのでつけたまでで、『八頭花崎』も『内行八花文』も、同じ意味であった。
『八葉』の意味は大きい。舶載鏡にしても、現在までに発見されていた彷製鏡にしても、内行花文鏡や方格規矩鏡などの四葉座というのは数多く見受けたが、八葉座というのは、平原弥生古墳の大鏡がはじめての出土である。すると八葉というのは特殊な鏡でなければありえなかったといえる。
わたしは、さきに、平原弥生古墳出土の大鏡を見て、印象にのこる文様は『内行八花文』と『八葉座』であると書いたが、『御鎮座伝記』が「八頭花崎八葉形也」と記したのは、実見した時の強烈な印象を書きしるしたのであろうと思う。」
(2)三角縁神獣鏡説
八咫の鏡は。天照大神から、瓊瓊杵の尊に授けられ、神武天皇の東征とともに、東にうったとみられる。
八咫の鏡は、その後、天皇の宮殿にまつられていたようであるすなわち、平安時代のはじめにできた『古語拾遺』の神武天皇の段に、つぎのように記されている。
「天の富(あめのとみ)の命は、もろもろの斎部(いんべ)をひきいて、天璽(あめのみしるし)の鏡・剣(八咫の鏡と草薙の剣)をささげ持って、正殿に奉安し、また玉をかけ、そなえものをおき、大殿祭(おおとのほがい)[宮殿に災厄のないように祈願する神事]の祝詞をのべた。」
 第10代崇神天皇のときに、天皇は、この鏡から心理的なプレッシャーをうけるようになる。
第10代崇神天皇のときに、天皇は、この鏡から心理的なプレッシャーをうけるようになる。
『日本書紀』は、つぎのようにのべている。
「これより先に、天照大神(神体は八咫の鏡)と倭(やまと)の大国魂(おおくにたま)の二はしらの神を、天皇の御殿のうちにお祭りしていた。ところが、崇神天皇は、神の威勢を畏(おそ)れて、ともに住みたまふことが不安であった。
そこで天照大神には豊鋤入姫(とよすきいりびめ)の命(崇神天皇の皇女)をお付けになって、倭の笠縫邑(かさぬいのむら)[桜井市三輪檜原(ひばら)神社境内、磯城郡田原本町新木、桜井市笠山荒神境内などの説かある。檜原神社境内説が有力]に祭られた。」
「崇神天皇の時代にいたって、崇神天皇は、神威を畏れ、同じ宮殿にすむことに不安をおぼえられた。
そこで、斎部氏をして、石凝姥(いしこりどめ)の神の子孫と、天の目一(あまのまひと)つの子孫との二氏をひきいて、さらに鏡て剣を鋳造させ、護身のしるしのものとされた。これは、今、践祚の大甞祭のさいに用いるところのしるしとなる鏡と剣である。」
八咫の鏡のレプリカ(複製品)のつくられたことがのべられている。そして、レプリカのほうは、宮殿におかれ、本物の八咫の鏡のほうは、場所をうつされることになったのである。
『日本書紀』によれば、第11代垂仁天皇の時代に、八咫の鏡を、豊鍬入姫の命から離して、垂仁天皇の皇女の倭姫(やまとひめ)の命に託す。倭姫の命は、八咫の鏡を鎮座させるところを求めて、菟田(うだ)の筱幡(ささはた)[大和の国宇陀(うだ)郡。今の奈良県宇陀市榛原(はいばら)]、近江の国、美濃の国(岐阜県)をめぐり、伊勢の国(三重県)にいたって、斎宮(いつきのみや)を、五十鈴川の川上にたてたという。
「八咫の鏡」のレプリカであるという伝承をもつ鏡に、三角縁神獣鏡があるという問題をとりあげよう。
奈良県の磯城郡田原本町八尾字ドウズに、鏡作坐天照御魂(かがみつくりにますあまてるみたま)神社がある。
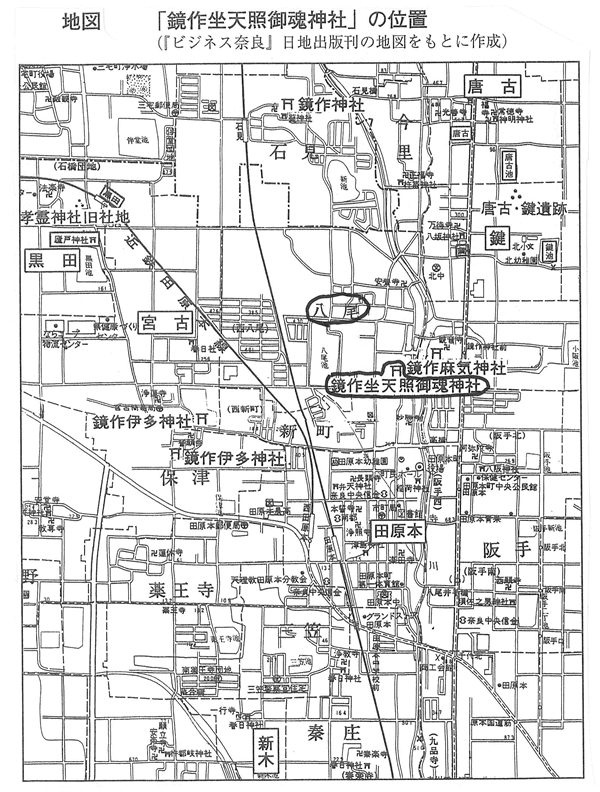
この神社については、『日本の神々 神社と聖地4大和』(谷川健一編、白水社、1985年刊)の「鏡作坐天照御魂神社」の項(大和岩雄氏執筆)にくわしい。
そこには、およそ、つぎのようなことがのべられている。
鏡作坐天照御魂神社の祭神は、現在は三座で、中央に、天照国照日子火明(あまてるくにてるひこほあかり)の命、向かって右に鏡作の遠祖石凝姥の命、左に、天の児屋根(あめのこやね)の命がまつられている(火明の命は、すでにでてきた海部の始祖でもあることは、やや留意される)。
天照国照日子火明の命は、試鋳の像鏡(みかたかがみ)のことであるという。
『磯城郡誌』には、つぎのように記されている。
「社伝に、本社は三座にして中座は天照大神の御魂なり。伝へ言ふ。崇神天皇6年9月3日、此地に於て日御像(ひのみかた)の鏡を改鋳し、天照大神の御魂となす。今の尚侍所(ないしどころ)[賢所(かしこどころ)のこと。宮中の神鏡を安置したところ)の神鏡是(これ)なり。本社は其像鏡(そのみかたかがみ)を、祭れるものにして、此地を号して鏡作(かがみつくり)と言ふ。
左座は麻気神即(すなわ)ち天糠戸神(あまのぬかとのかみ)なり。此神日の御像(みかた)を作る。今の伊勢の大神是(これ)[日の御像]なり。右座は伊多神即ち石凝姥なり。此神日像(ひのみかた)の鏡を作る。今の紀伊国日前(ひのくま)神社是なり。」
大神(おおみわ)神社宮司であった斎藤美澄(よしずみ)が、1890年~1894(明治23~27)に編纂した『大和志料』でも、崇神天皇6年9月3日に鋳造した日御象(ひのみかた)の鏡は、今の尚侍所の神鏡であり、そのさいの試鋳の鏡を、天照大神の御魂として斎(いつ)きまつってきた、とする。
すなわち、尚侍所の神鏡を鋳造するに先だって鋳造された試鋳の鏡が、天照大神之御魂(あまてらすおおみかみのみたま)[別号(別の名)火照の命]として、中座に祀られている、とする。
和田萃(あつむ)氏は、つぎのようにのべる。
「鏡作座天照御魂神社では、古来、御神体の鏡を天照御魂神として祀っていたと思われる。鏡作神社に御神体として伝えられている鏡は、中国製説のある三角縁神獣鏡で、型式は、単像式の唐草文帯三神二獣鏡である。」
 「(この鏡の)外区の欠失していることが注意される。こうした例は、他にほとんどなく、人為的になされたと考えざるをえない。完型でないこの舶載鏡を、鏡作り工人らが奉仕した理由が判然とせず、さらに本鏡が古来御神体であったことにも疑念が持たれている。」
「(この鏡の)外区の欠失していることが注意される。こうした例は、他にほとんどなく、人為的になされたと考えざるをえない。完型でないこの舶載鏡を、鏡作り工人らが奉仕した理由が判然とせず、さらに本鏡が古来御神体であったことにも疑念が持たれている。」
「鏡作神社近傍の古墳から出土した鏡に手が加えられ、ある時期からそれを御神体として奉仕したとの想像も、あながち無稽のことではないだろう。」
しかし、森浩一氏は、「八尾の鏡作神社には、三角縁神獣鏡の内区だけの遺品があって、鏡制作の原型(げんけい)[鋳物のもとになる型]と推定することができる。」(「古墳出土の小型内行花文鏡の再吟味」、橿原考古学研究所編『日本文化論考』所収)と書く。 三角縁神獣鏡では、既存の鏡のいろいろな部分を組みあわせて、新しい文様をもつさまざまな鏡が作られている。
八尾の鏡作神社の鏡は、新しい鏡をつくるための原型で、内区の部分のために利用されたものであろう。
なお、和田萃氏は、三角縁神獣鏡を、「御神体」とするが、神社では、「神体」ではなく、「神宝」としてあつかっている。
(4)鉄鏡説
『古事記』は、「鉄鏡」と記していいるが?
「八咫の鏡=鉄鏡説」は、あるていど有力な根拠をのべることができる。
「八咫の鏡=鉄鏡説」は、すでに、幕末から明治時代の国学者・飯田武郷(たけさと)が、『日本書紀通釈』のなかで説いているものであるが、今日あらたな資料によって、復活させうる余地がある。
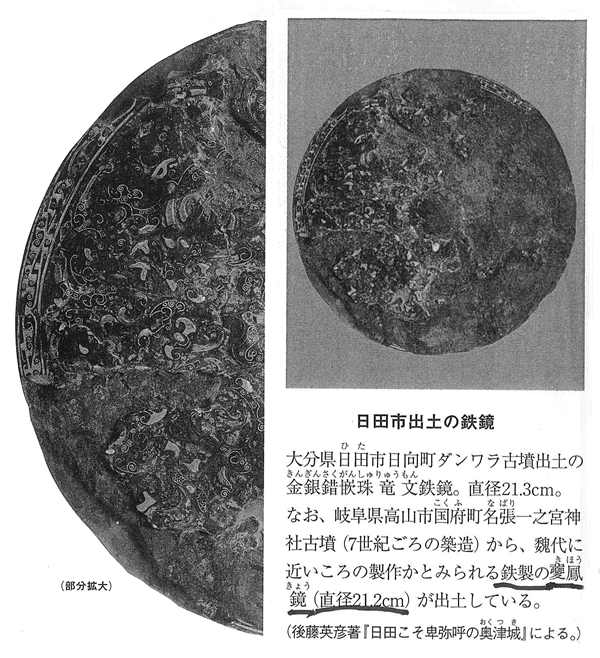
『古事記』をよく読むと、奇妙な記事がある。
天照大御神は、弟の須佐の男(すさのお)の命の乱暴に怒って、天の石屋(あまのいわや)にかくれる。そこで、八百万(やおよろず)の神は、天の安の河の河上の天の堅石(あめのかたしわ)[鉄を鍛える金敷(かねしき)の石か)を取り、天の金山(あめのかなやま)の鉄を取って、鍛人(かぬち)[鍛冶(かじ)職。鍛人(かぬち)は、金打(かなうち)の省略]の天津麻羅(あまつまら)をたずね求め、伊斯許理度売(いしこりどめ)の命に命(めい)じて、鏡を作らせた。・・・ この話によれば、このときに作られた鏡は、鉄の鏡であったことになる。
『古事記』に、「天の金山の鉄(くろがね)とあるものが、文献の編纂される時代とともに、つぎのように変化している。
①「天の金山(かなやま)の鉄(くろがね)」(712年成立の『古事記』)
②「天の香山(かぐやま)の金(かね) 」(720年成立の『日本書紀』のよう
③「天の香山(かぐやま)の銅(あかがね)」(807年成立の『古語拾遺』)
④「天の金山(かなやま)の銅(あかがね)」(830年ごろ成立かとみられる『先代旧事本紀』
⑤「天の香山(かぐやま)の銅(あかがね)」(830年ごろ成立かとみられる『先代旧事本紀』
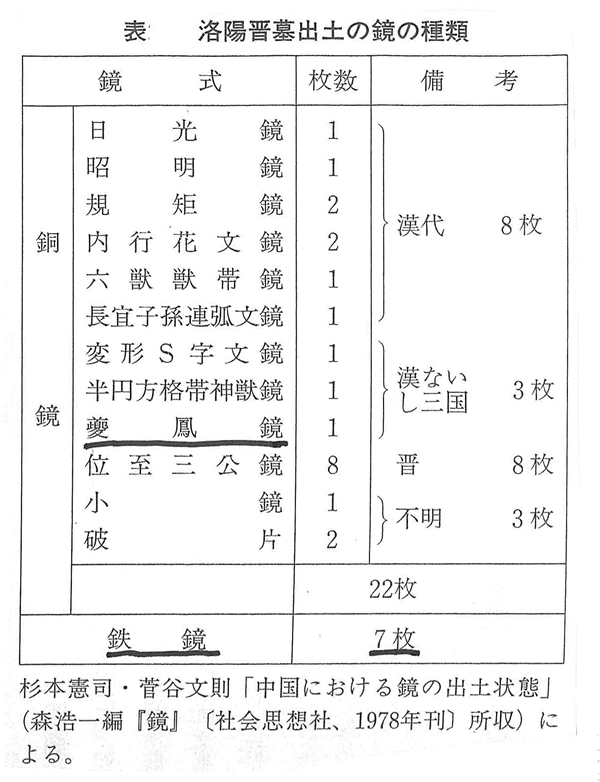
弥生時代の末から古墳時代では、銅鐸や銅鏡などの原材料の銅は中国から来たものとするのが定説になっている。
天の金山あるいは香山から銅は取れないのではないか。
その場合、天の金山あるいは香山からは銅はとれず。鉄であったそれは矛を造った。鏡を造ったのは別の話とする説がある。
■鏡の被災の記録
皇居では2回の被災記録がある。
①960年頃
平安京の御所の温明殿(うんめいでん)[賢所(かしこどころ)は、960年(天徳4)9月24日の火災で被災した。このときのことについて、『日本書紀』の最初の注釈書『釈日本紀(しゃくにほんぎ)』は、『村上天皇御記』(「御記」は、天皇の手に成った記録)のつぎのような文章を引用している。
「天徳年間に内裏が焼けうせたとき、内侍所(宮中の神鏡を安置したところで、女官である内侍が、鏡を守護した。賢所ともいう)の神鏡は、灰燼(はいじん)のなかにあったが、焼け損(そこな)われず。申時(さるどき)(午前3時~5時のあいだ)、源重光朝臣(みなもとしげみつあそん)が来ていう。瓦上に鏡一面あり。その鏡は、径八寸(約24センチ)ばかり、頭に小さな瑕があるが、ほとんど損われていない。円規と蔕(へた)[鈕(ちゅう)。ただし、この字が、帯(おび)になっているテキストがある。帯なら、たとえば、三角縁神獣鏡などの周帯(外区の鋸歯文帯など)や獣文帯をさすか]は、はなはだはっきりしている。これを見たものは、驚き感じいらないものはいなかった。神鏡は、縫殿寮(ぬいどのりょう)の高殿(たかどの)に安置した。」(安本注。この文は『扶桑略記』に、『村上天皇御記』天徳4年9月24日条を引用した同文がみえる。)
②1040年頃
1040年(長久元)9月9日。皇居の京極土御門殿(きょうごくつちみかどどの)が焼亡。神鏡が罹災(りさい)した。神鏡すでに焼け損じ、遺体わずかに、当日、焼けあとから「玉金如きもの数粒」、翌10日「金玉の如きもの二粒」を得たのみであった(参議・藤原資房(すけふさ)の日記『春記』による)。
このように、焼失したことも考えられ、「八咫の鏡」の歴史をまとめると下記となる。
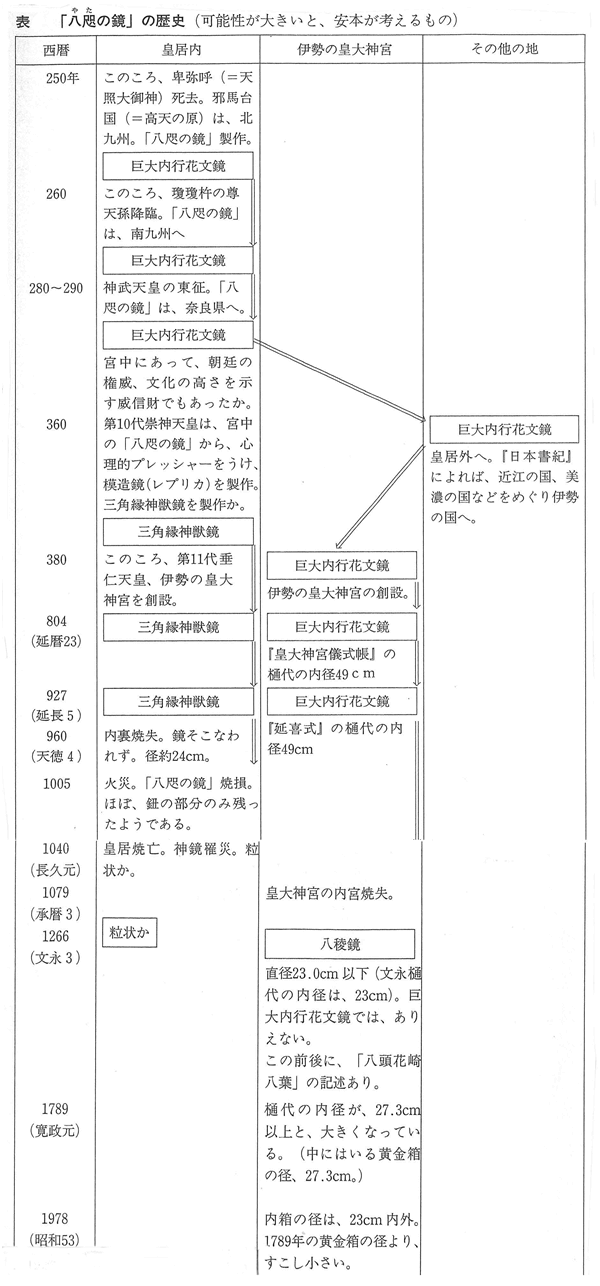
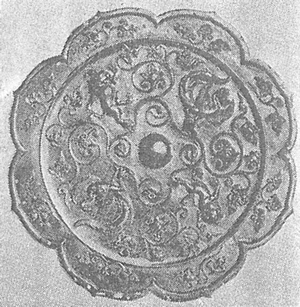
現在の「八咫の鏡」はどうなっているのだろうか?
宮中の鏡は「粒状」になってしまったままであろうか。
また、伊勢の皇大神宮のものは「八稜鏡」のような違う形の鏡になってしまったのであろうか。
八稜鏡(はちりょうきょう)は鏡の形式名である。外周が菱花鏡の八菱をなすもので六菱のものは六稜鏡といわれる。
本来八菱鏡とすべきものであるが「菱」でなく「稜」を用いている。稜は。『辞源』に「物体上的辺角式尖角」であり、稜角等に用いられ、必ずしも正鵠を射たものではない。この種の鏡は。奈良時代にさかんに用いら、唐鏡から和鏡への過渡的な形式をもつものとされている。




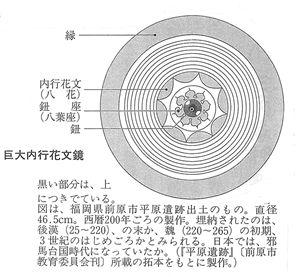 もう少し考えを前進させてみよう。もう少し考えを前進させてみよう。『八頭花崎』の『八頭』は日本語ではヤツガシラと読まれる。同じような頭だけが八個ある状態である。『花崎』とは(ナサキで、花弁の先端ということであろう。先端のみの八花弁を『八頭花崎』といったと考えられる。考古学でいう『内行八花文』も、花弁形なら外側に貼り出るのに、内側に向かっているのでつけたまでで、『八頭花崎』も『内行八花文』も、同じ意味であった。
もう少し考えを前進させてみよう。もう少し考えを前進させてみよう。『八頭花崎』の『八頭』は日本語ではヤツガシラと読まれる。同じような頭だけが八個ある状態である。『花崎』とは(ナサキで、花弁の先端ということであろう。先端のみの八花弁を『八頭花崎』といったと考えられる。考古学でいう『内行八花文』も、花弁形なら外側に貼り出るのに、内側に向かっているのでつけたまでで、『八頭花崎』も『内行八花文』も、同じ意味であった。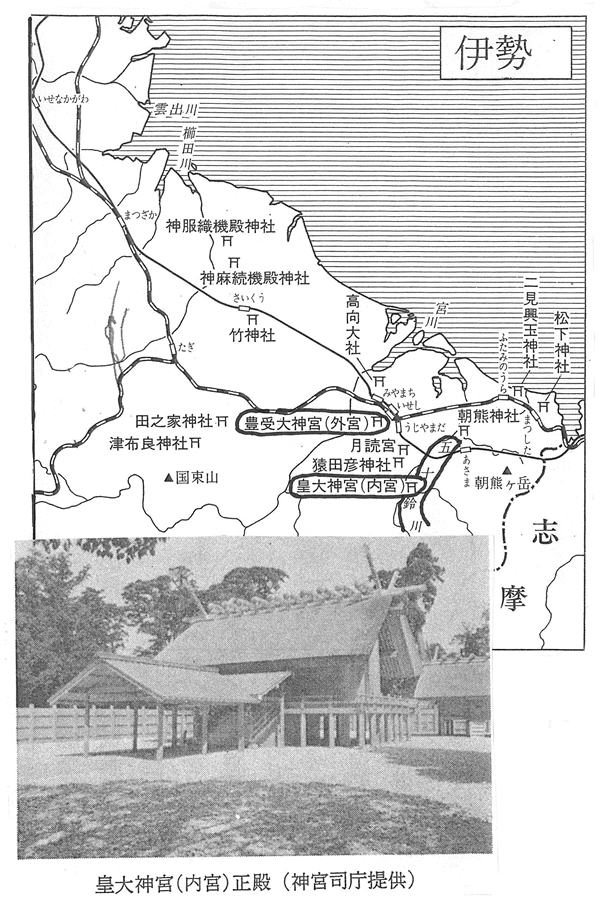
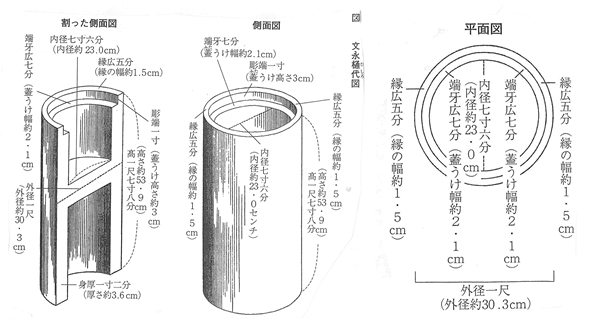
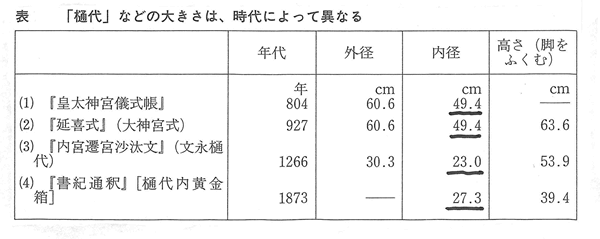
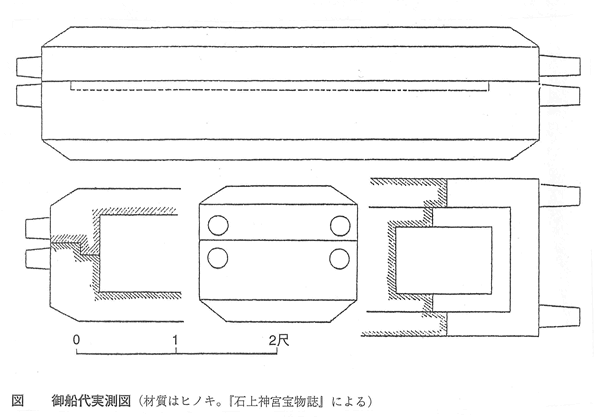
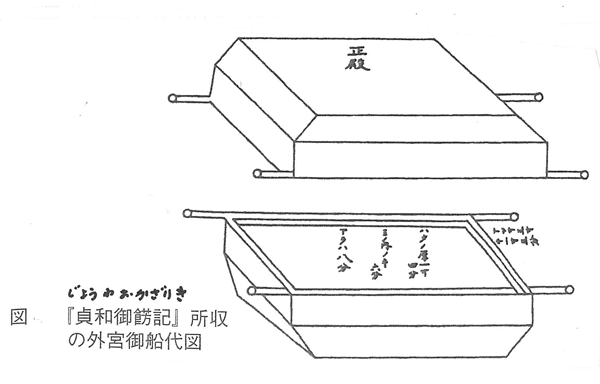
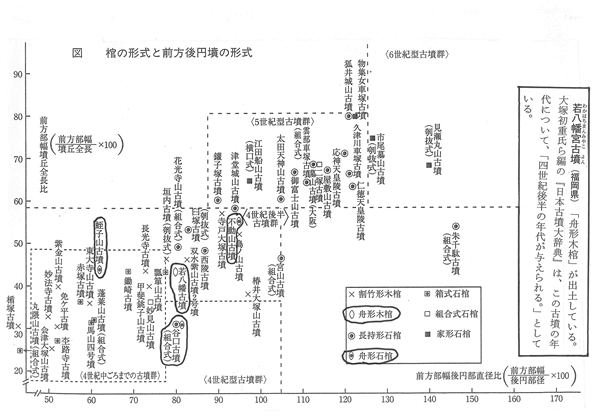
 鏡が小さいのに、無用に大きな樋代(ひしろ)をつくることはないであろう。
鏡が小さいのに、無用に大きな樋代(ひしろ)をつくることはないであろう。 第10代崇神天皇のときに、天皇は、この鏡から心理的なプレッシャーをうけるようになる。
第10代崇神天皇のときに、天皇は、この鏡から心理的なプレッシャーをうけるようになる。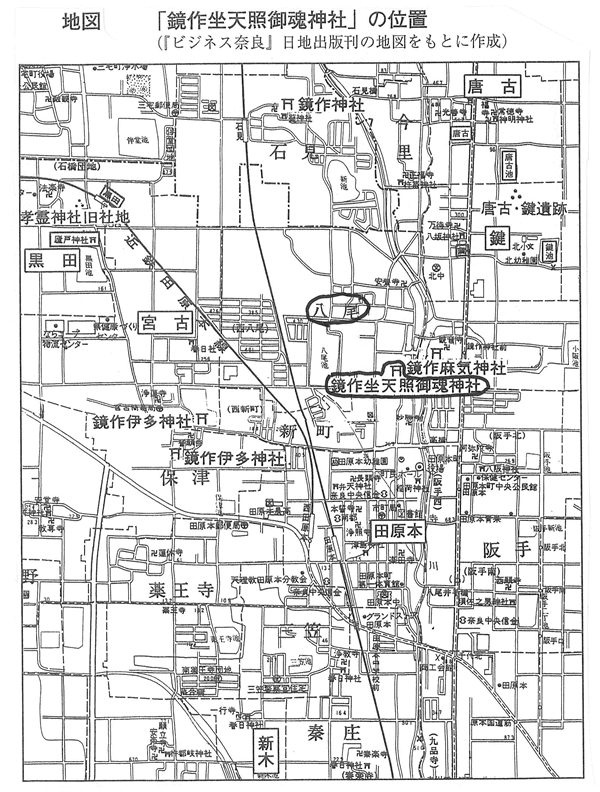
 「(この鏡の)外区の欠失していることが注意される。こうした例は、他にほとんどなく、人為的になされたと考えざるをえない。完型でないこの舶載鏡を、鏡作り工人らが奉仕した理由が判然とせず、さらに本鏡が古来御神体であったことにも疑念が持たれている。」
「(この鏡の)外区の欠失していることが注意される。こうした例は、他にほとんどなく、人為的になされたと考えざるをえない。完型でないこの舶載鏡を、鏡作り工人らが奉仕した理由が判然とせず、さらに本鏡が古来御神体であったことにも疑念が持たれている。」