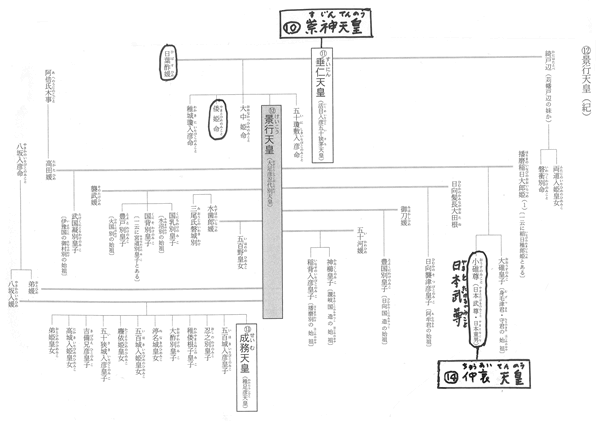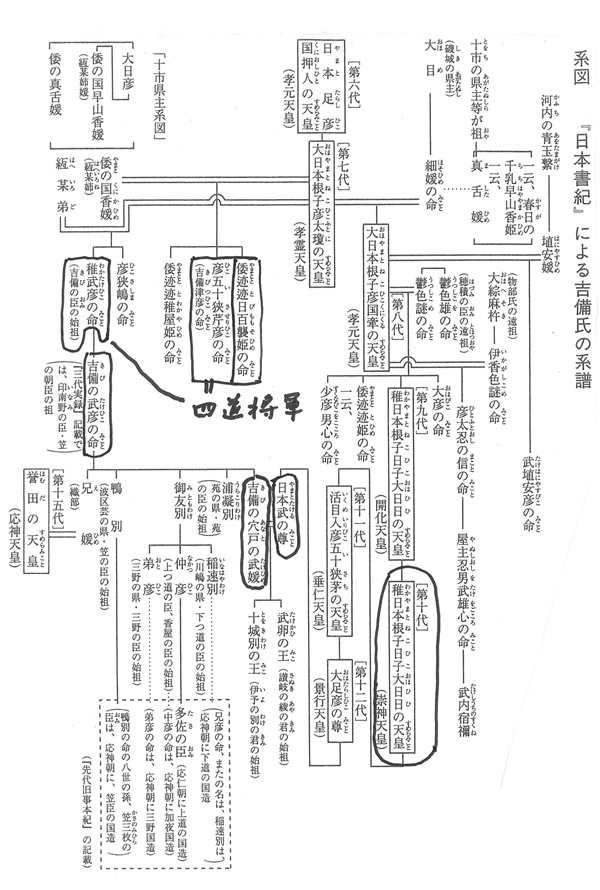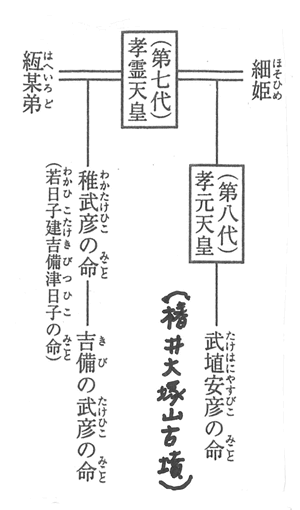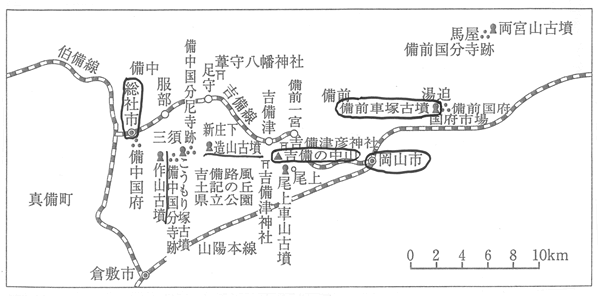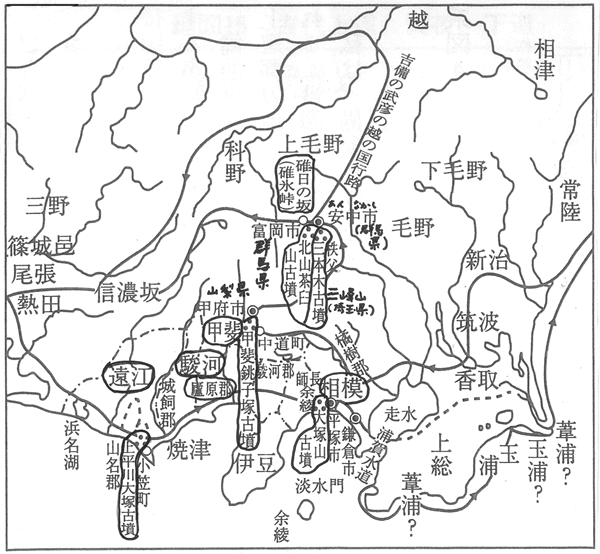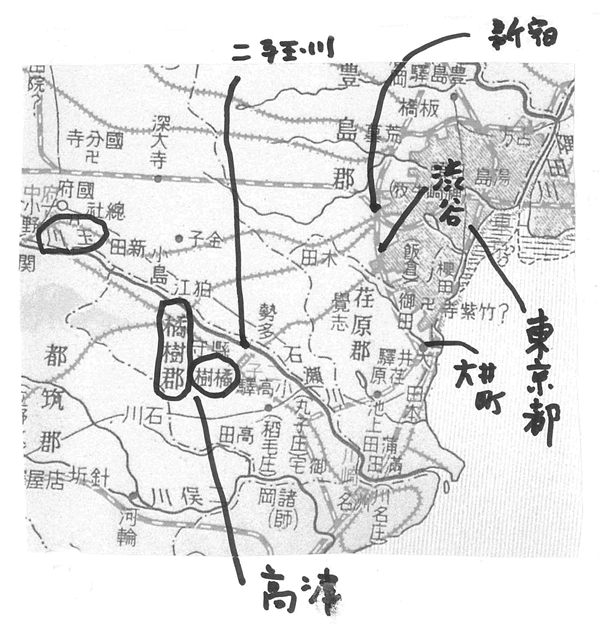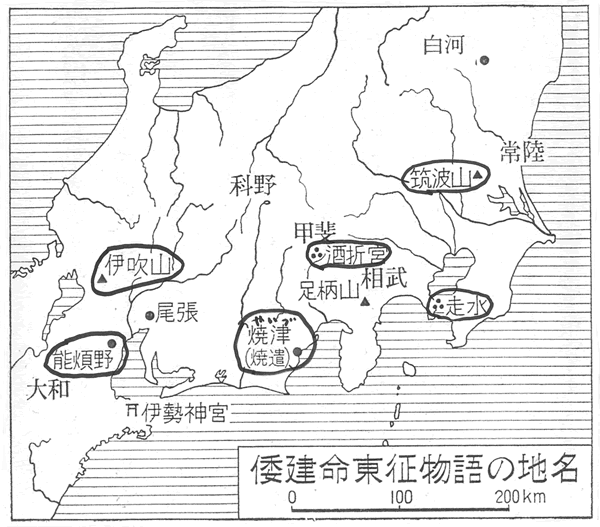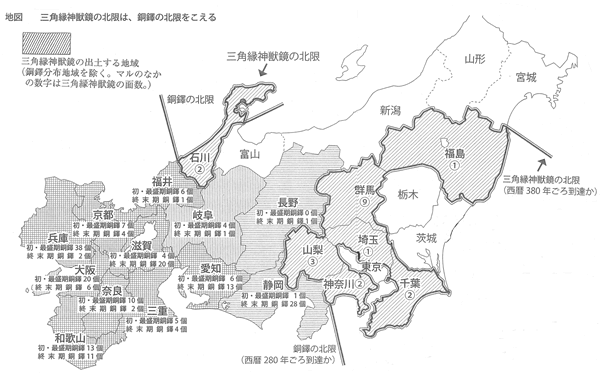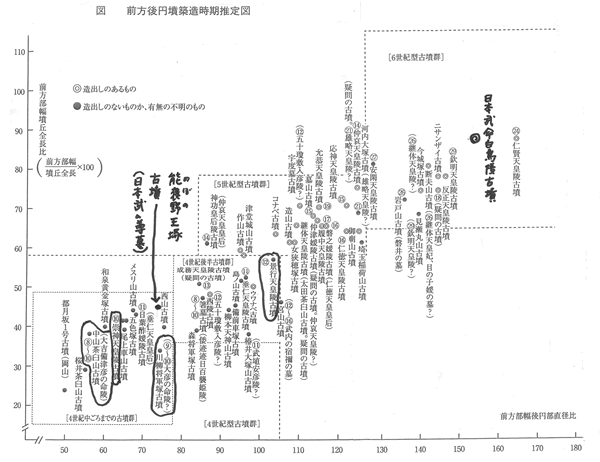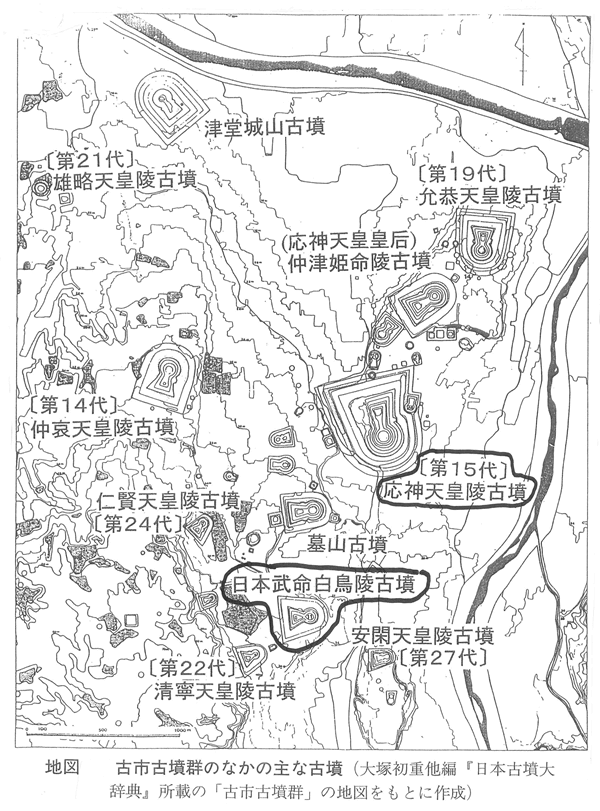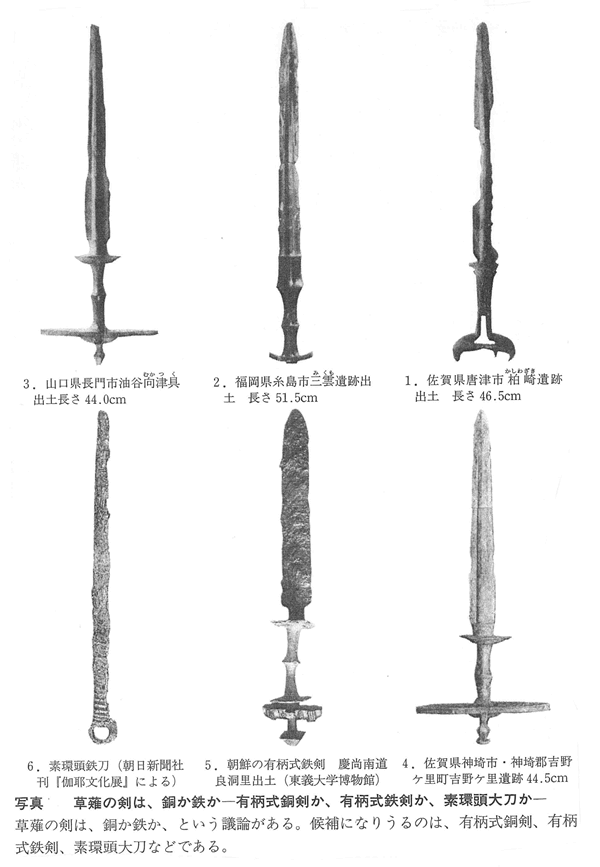| TOP>活動記録>講演会>第331回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第331回 邪馬台国の会(2014.7.27 開催)
| ||||
1.日本武の尊
|
2.弟橘姫(おとたちばなひめ)の話
|
3.日本武の尊の墓 |
■日本武の尊の死 『日本書紀』では日本武の尊は、東国からの帰途、近江の伊吹山の賊徒を征伐のさい、病を得て、伊勢の能褒野(のぼの)で没したという。『古事記』では伊吹の山神を討ちにいって病死したという。 また『古事記』では、日本武尊は能褒野(のぼの)で病死して亡くなる前に望郷から次のようなに歌っている。 このように、大和を祖国として、望郷の念を意識していたと考えられる。 ■日本武の尊の墓と思われる3古墳 ■能褒野王塚古墳 能褒野王塚古墳について、京都大学文学部史学科卒業の毎日新聞記者、岡本健一氏はのべる。 能褒野王塚古墳の周囲には、十数基の小円墳が存在している。 x座標[前方部幅/後円部径]×100=[40/50]×100=74 y座標[前方部幅/墳丘全長]×100=[40/90]×100=44 この値を図のうえにプロットすれば、能褒野王塚古墳は、崇神天皇陵古墳よりもごくわずか時代の下る特徴をもつ古墳で、四世紀中ごろから四世紀後半にかかる古墳とみてよい。
x座標[前方部幅/後円部径]×100=[165/106]×100=156 y座標[前方部幅/墳丘全長]×100=[165/190]×100=87 この値を、上図のうえにプロットすれば、この古墳はむしろ、「六世紀型古墳群」に属する。前方部がきわめて発達している。いずれにしても、この古墳は日本武の尊のものではないであろう。
|
4.草薙の剣はどのような剣か?
|
熱田神宮にまつられている草薙の剣とはどのような刀であったのか。鉄製であるのか銅製であるのか。
つまり、治部大輔季通が他の神官数名と草薙の剣を取り出して、それを収めていたお櫃を新たにつくった。そしてこの人々はのちに神罰をうけて懲罰を被ったというのである。残念ながら剣についてのことは何も書いてない。だが見た人かあるという推理はこの記事によって成立する。 さらに時代はずっと下って、明治30年(1897)、東京帝国大学の栗田寛教授が、『神器考証』という本を書いている。この本は後に発禁本となっているが、この中で栗田教授は、江戸時代において、垂加神道の学者・玉木正英(まさひで)[1736年没]がその著『玉籖集』の裏書(吉田家蔵)に、熱田大宮司社家四、五人が志を合わせて、草薙の剣を見たということを記した記事を引用して、そのことを紹介している。 彼らが最初に見たものは剣を収めた箱であった。その箱は、まわりが五尺ほどの木の箱になっていて、これを開けると次に赤土がある。その次には石の箱があって、これをあけるとさらに赤土になっている。 これを見た人たちは次々に病に倒れ、そのうちの一人だけがこのことを言い伝えたという注釈がついている。 そして、この記述によってはじめて、神剣草薙の剣の具体的な姿が浮かび上がってきた。この文を要約すると、剣は、次のような特徴をもっていることになる。 ところで今の記事から、明治大学の教授で、考古学の権威であった後藤守一さんは『日本古代史の考古学的検討』という著書のなかで、もし『玉籖集』に書かれていることが本当ならば、というまえおきを述べた上で次のような推理を行っている。それによると、刃先が菖蒲のようであったということは、両刃の剣だったということである。中程が厚くなっていたことは、鎬造(しのぎづく)り(刃の幅が広く、両刃の剣の両がわにある稜線の幅が狭いつくり)であったということである。それから本のほうが魚の骨のようになっていたことは、これは鉄剣には、まったくない形であって銅剣だけにある形である。色が白いということは、白色銅であって、これをそのまま土の中に入れると、銅は錆びて緑色になるか、黒っぽくなってしまうのである。以上を総合すると、九州、三雲遺跡から出土した有柄式細形銅剣が非常によく似ているといえる。ただし長さが二尺七、八寸というのは非常に長い。これはどうも銅剣には無理なようである。もしかしたらこれは剣ではなくて、鉾(ほこ)ではなかったか、と述べている。つまり、形態からすると三雲の有柄式銅剣によく似ており、長さを考えると銅鉾という推理をされている。 ではそのほかの文献では、神剣のことをどのように記しているのであろうか。 この記事は、『玉籖集』の記載とかなりの部分で一致しているが、御神体の長さが一尺八寸ほどで、『玉籖集』に記されているものより一尺ほど短い。 「・・・あくまでも推理の域を出ないのでございますが、文献的にはどれをお採りになりますか。 刀剣研究家の石井昌国氏は、一方で、つぎのようにものべている。 石井昌国氏は大蛇を切った刀を草薙の剣としているが、大蛇を斬ったのは石上神宮の神剣の布都御魂大神(ふつのみたま)である。 |
| TOP>活動記録>講演会>第331回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |