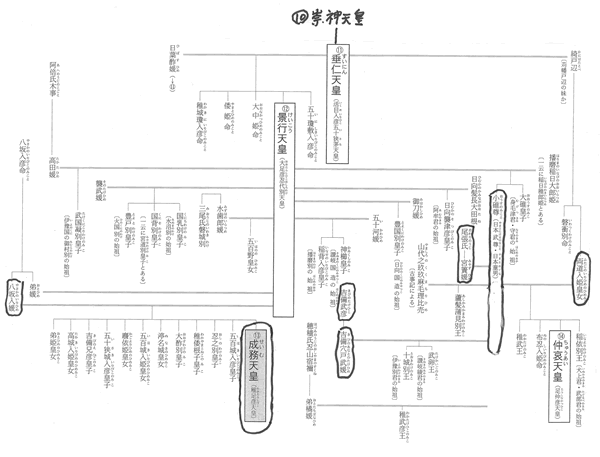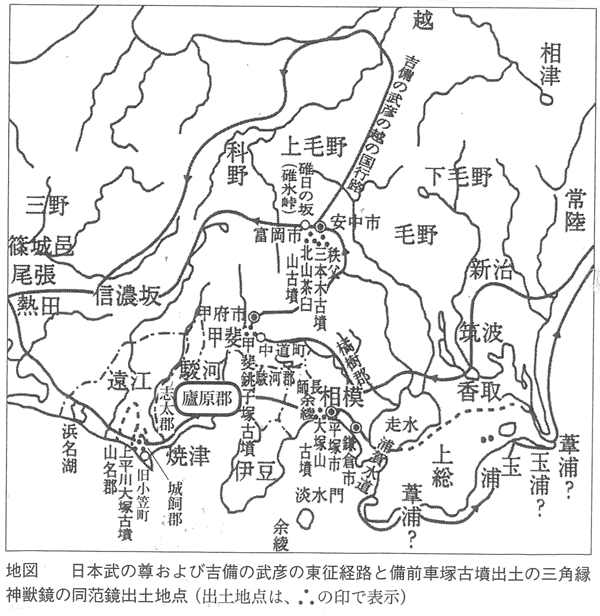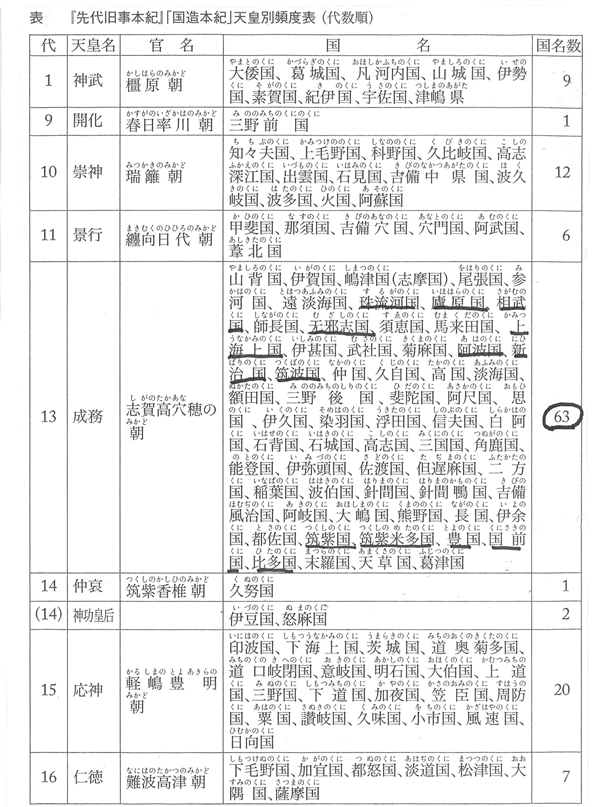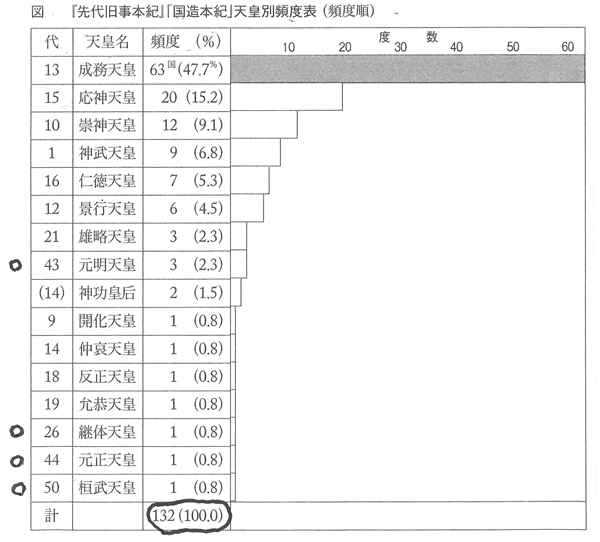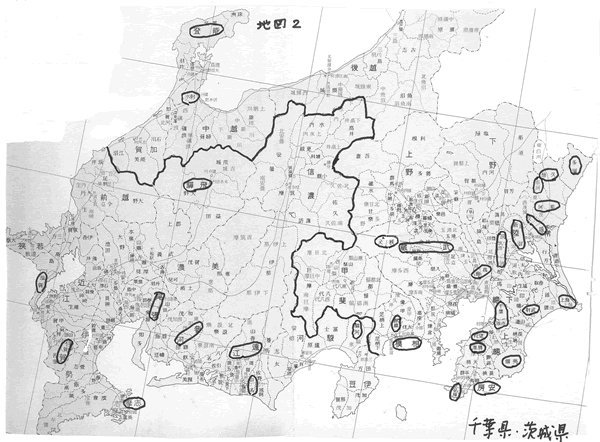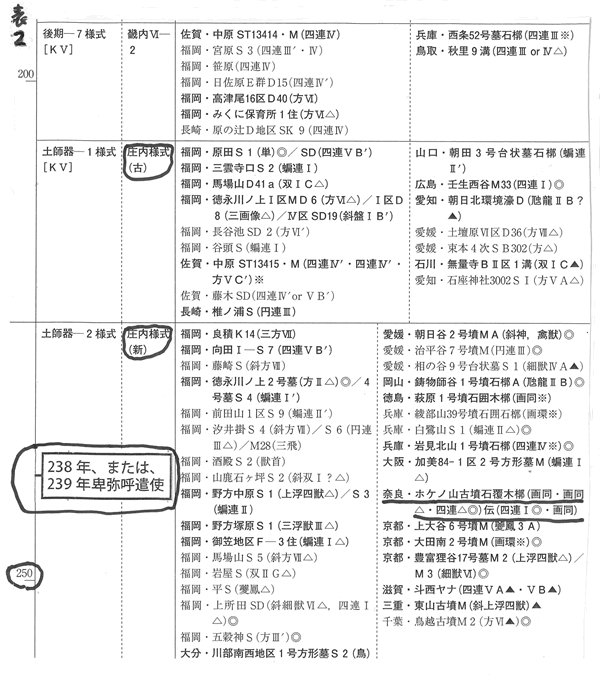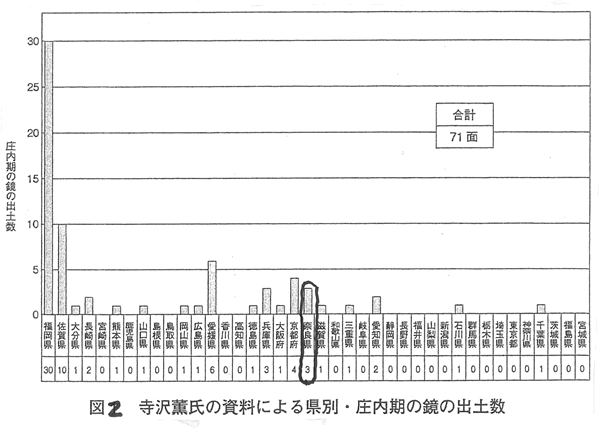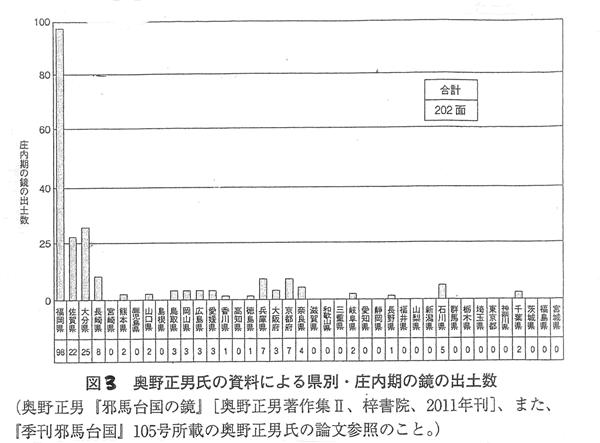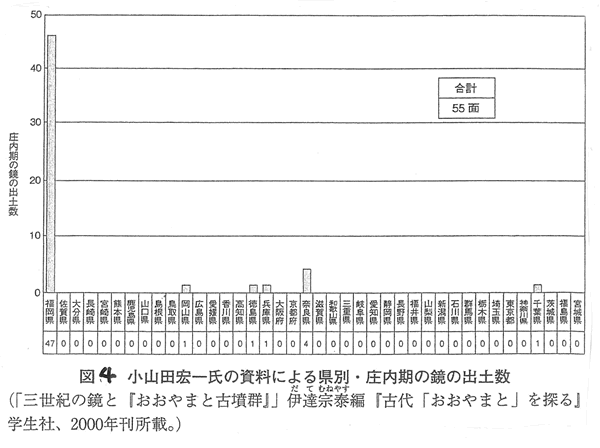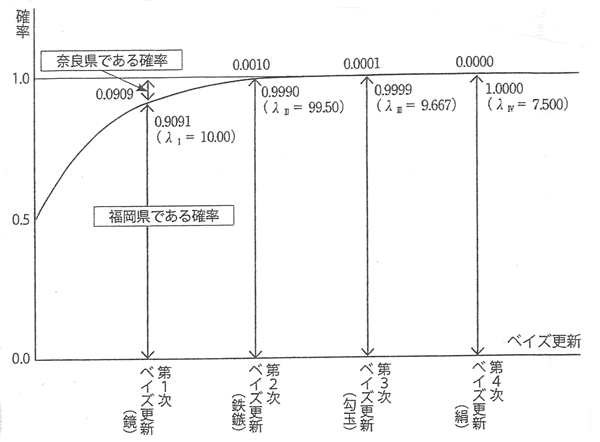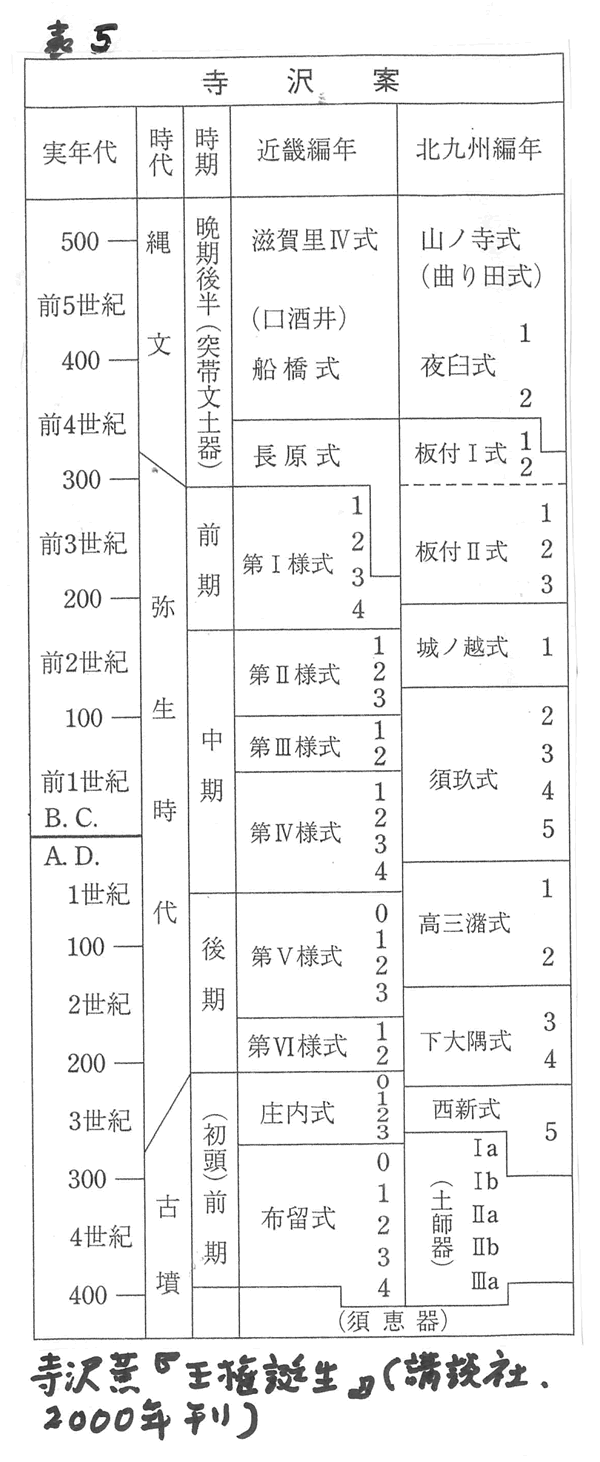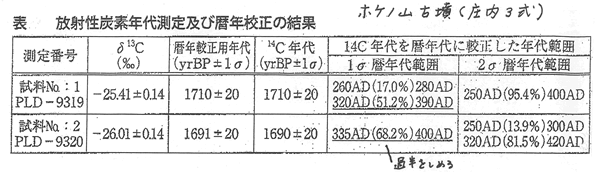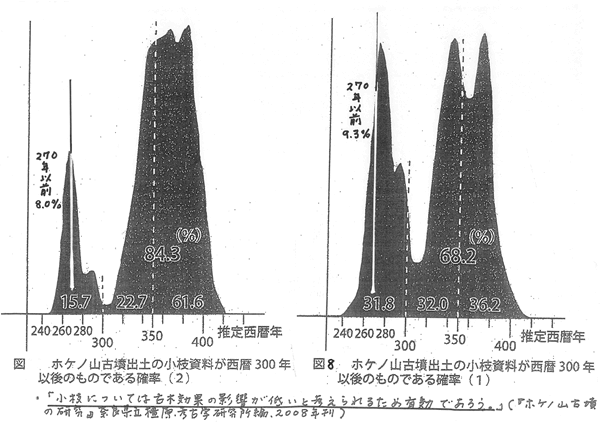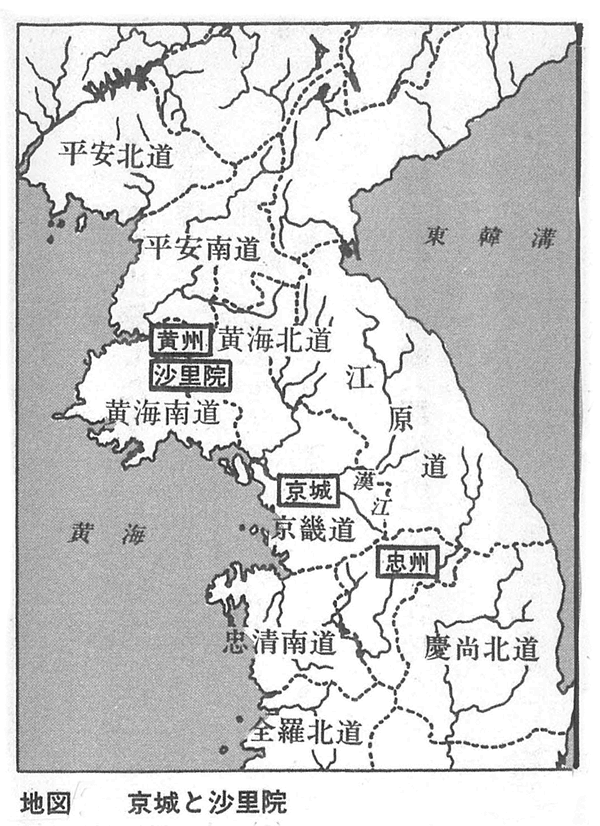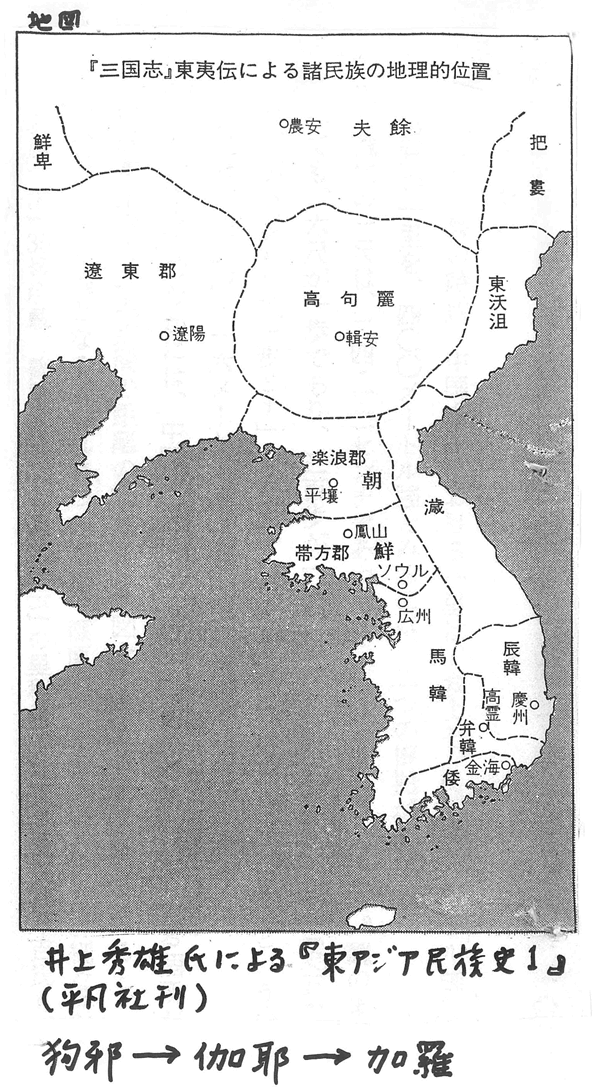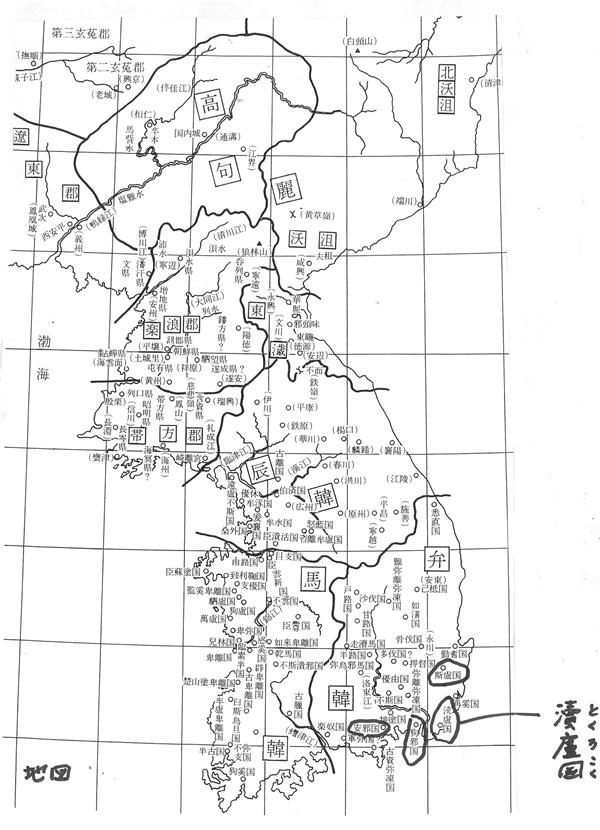| TOP>活動記録>講演会>第332回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第332回 邪馬台国の会(2014.9.21 開催)
| ||||
1.成務天皇の時代
|
2.「纒向学」はどこへ行くのか
|
「纒向学」を研究している寺沢薫先生は私と立場が違う。そこで寺沢先生の説と私の考えと、どういうところが共通点であって、どういうところが違うか、何回かに分けて詳しく述べてみたいと思う。 (1)出土物にもとづく「邪馬台国=奈良県説」成立の確率(存在しうるかどうかではなく、確率を求める)
この鏡に加え鉄鏃、勾玉、絹のデータを加えて、ベイズ統計学で表すと下記となり、邪馬台国が福岡県である確率が圧倒的に多くなる。奈良県の確率は0となってします。
この結果について、松原教授の話。 私たちは、確率的な考え方で日常生活をしています。たとえば、雨が降る確率が『0.05%未満』なのに、長靴を履き、雨合羽を持って外出する人はいません」(『文芸春秋』2013年11月号) 『季刊邪馬台国』118号 また、天文学の分野で、大まかに言えば、 B.ケプラー(ドイツ)がその観測事実を丁寧に整理して、三法則(惑星は太陽を一つの焦点として楕円軌道上を動くなど)を見出した。 C.ニュートン(イギリス)がケプラーの法則は万有引力の法則で説明がつくとした。 これになぞらえて日本古代史にあてはめれば、 a.膨大な発掘記録がある b.邪馬台国の遺物・遺跡についての強い法則性 これについて、寺澤薫氏は沈黙しておられる。 c.邪馬台国の遺物・遺跡についての総合命題 これは、穴沢咊光(わこう)「梅原末治論」(角田文衡『考古学京都学派』[雄山閣出版1997年刊]所収、『季刊邪馬台国』120、121、122郷に転載)で述べていることにあてはまる。 「研究方法も「モノを一つ一つ丹念に観察し、実測し、写真や拓本をとり、その形態や装飾をアタマにたたきこむだけではダメなのであって、青銅器は成分の鉛同位体比を測り、鉄器はX線検査、土器は胎土分析、石器は使用痕の研究、木器は年輪年代の測定、動植物遺存体は専門家の鑑定、遺跡の土は土壌分析と花粉分析を行い、その結果を総合しなければ本当のことはわからない」といった時代になった。 穴沢咊光氏の述べているように、データの一部だけをつかまえて発言すると、群盲象をなでるようなことになる。 また。バイオ関係でも、榎木英介(えのきえいすけ)『嘘と絶望の生命科学』(文春新書、文藝春秋社 2014年刊)は下記のことを述べている。 このように、統計的にとらえることが重要なのである。 (2)箸墓古墳の築造年代 しかし、寺澤氏は「明らかに布留0式古相の土器群とPrimaryな状態で共存したと判断された桃核」と書いている。 寺沢薫『王権誕生』(講談社200年刊) (3)ホケノ山古墳の築造年代 『ホケノ山古墳の研究』(奈良県立橿原考古学研究所編、2008年刊)は「ホケノ山古墳」についての現在、最終の正式報告書である。このなかで、「小枝については古木効果の影響が低いと考えられるため有効であろう」と書かれている。 しかし4世紀である確率の方が高い。 ホケノ山古墳出土の小枝資料が300年以後のものである確率(2)[資料No.2] 「寺澤薫氏の見解」 (A)「わずか二点」とはデータをふやせという意味のようにみえる。 しかし、データが多くあれば何とかなる問題ではない。約1700年で±20の精度である。これはデータの数の問題ではない。 (1)もっとも新しい年代をとる寺澤説にとって、さらに不利になる。 (2)測定誤差を小さくすることをめざす(加重平均をとる) (B)「追従する」というが、現在、ホケノ山古墳については、これをこえる年代資料は提出されていない。かつ、寺沢氏自身の示す箸墓古墳出土の桃核資料データとも、整合的である。 桃核試料については、名古屋大学年代測定総合研究センターの中村俊夫教授が、「クルミの殼」について、「クルミの殼はかなり丈夫で汚染しにくいので、年代測定か実施しやすい試料である。」(日本文化財科学学会第26回大会特別講演資料)と述べておられることが、参考になるであろう。 (C)寺沢説の成立の確率は? 確率は大きい小さいによって判断すべきである。すこしでも可能性があればそれは認めるべきであるというような議論をすれば、寺沢しはとうぜん、安本説を否定できなくなる。 つまり、ホケノ山古墳の年代が270年以前である確率は10%以下であるということである。「十中八、九以上」の確率で支持されるのは寺沢説ではない。 データを集めるさいの精密さにくらべ、データから推論をする手つづきは愕然するほど粗い。「年代」という「数字」をとりあつかいながら、数的データはなにも示しておられない。
|
3.『魏志倭人伝』を徹底的に読む(狗邪韓国)
|
(1) 倭人について。 原文(「紹興本」による) (2) 狗邪韓国 原文(「紹興本」による)
■どこから出発したか (1)帯方郡の郡治(郡役所)の所在地とし、その位置を、現在の京城(ソウル)付近とする説
(3)『魏志倭人伝』の「郡より倭にいたる」の出発点の「郡」は、帯方郡ではなく、洛陽郡をさすとする説 ▼参考文献 ▽出発点の「郡」を、「洛陽郡」とする見解は、榧本杜人「魏志倭人伝の里程について」(『朝鮮学報』、第四十一輯彙報、1966年1月)に述べられている。
■狗邪韓国はどこか (1)倭の一国とみる説
これは、下記の記事から日本と朝鮮半島の金海付近との共通性からも考えられる。 とにかくこれら日本系銅器の伽耶古墳での少なからざる出現は、当該銅器に対する韓日両国考古学界の関心を大いに高めているが、後述の碧玉製品と共に副葬品として両国の間で同じような精神的・物質的意義、或いは価値が与えられているという事実が、当時の両国の文化関係を考えるのに重要である。今後の冷静な視角が望まれる。 (2)倭の一国とはみない説 さらにまた、通説では、邪馬台国に帰る倭の使は、狗邪韓国を通ったと考えるが、狗邪韓国を通らなかったとする説もある(張明澄など)。その根拠は、つぎのとおりである。 現に、昭和五十年に、角川書店の主催で、古代船野性号で朝鮮海峡を渡ろうとしたが、船は東に流されて、人のこぐ力だけでは対馬につくことができず、母船に曳航してもらった。船はもっと西のほうの地占から出発し、潮の流れにのって、対馬に到着したはずである。 ずっと後にできた『新元史』の「日本伝」は、つぎのように記す。 ・「韓伝」から弁辰、辰韓の記述 「弁辰(べんしん)は、辰韓(しんかん)と雑居し、亦(ま)た城郭有り。衣服居処は辰韓と同じ。言語・法俗相(あい)似たるも、鬼神(きしん)を司祭(しさい)するに異なる有り、竈(そう)を施(ほどこ)すに皆(みな)戸の西に在(あ)り。其の瀆盧(とくろ)国は倭と界(さかい)を接す。十二国亦(ま)た王有り、其(その)の人、形皆(みな)大なり。衣服は絜清(けっせい)にして長髪。亦(ま)た広幅の細布を作る。法俗特に厳崚(げんしゅん)なり。」 ■任那の存在について 任那については下記の記事がある。 ・『新撰姓氏録』「吉田連(きちたのむらじ)」(左京皇別下)(崇神天皇) このように、崇神天皇の時代(4世紀)に任那の記述があったようだ。 ・『日本書紀』に第29代欽明天皇23年の頃に同じような記事がある。 ・なお三国史記には新羅真興王二十三(欽明二十三)年九月条に「加耶(加羅)叛。王命異斯夫討之。斯多含副之。斯多含領五千騎先馳、入栴檀門立白旗。城中恐懼、不知所為。異斯夫引兵臨之、一時尽降」という記事がある。
・参考に加羅(から)について、末松保和『任那興亡史』、今西竜「加羅疆域考」(『朝鮮古史の研究』所収)によると、下記となる。 ・任那(みまな)についての記載に下記がある。 ・金官加羅について下記に記載がある 注:宋は倭王武(雄略天皇)に対し次のよう任じた。「詔(みことのり)して武(ぶ)を使持節(しじせつ)・都督倭新羅任那加羅秦韓慕韓六国諸軍事(ととくわしんらにんなからしんかんぼかんりっこくしょぐんじ)・安東大将軍(あんとうだいしょうぐん)・倭王(わおう)に除(じょ)す。」 |
| TOP>活動記録>講演会>第332回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |