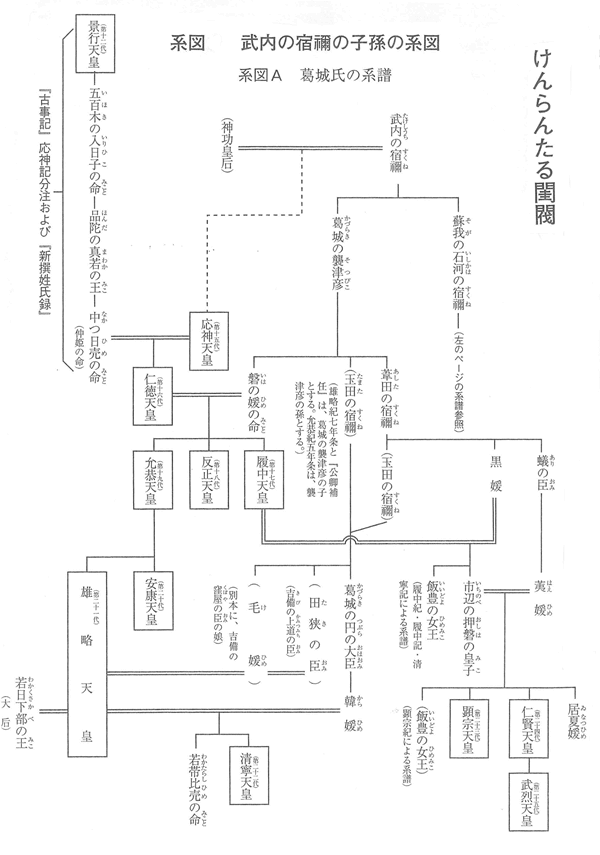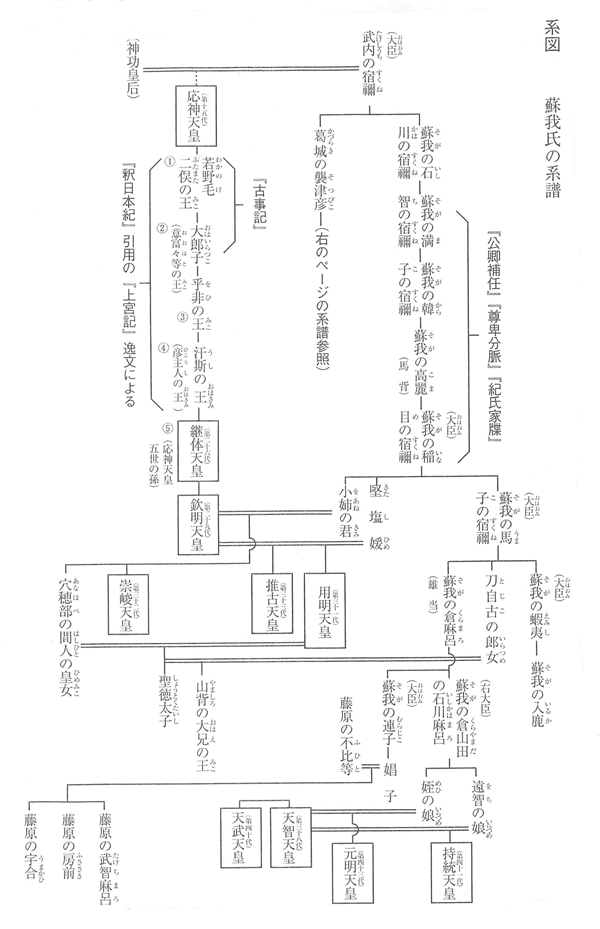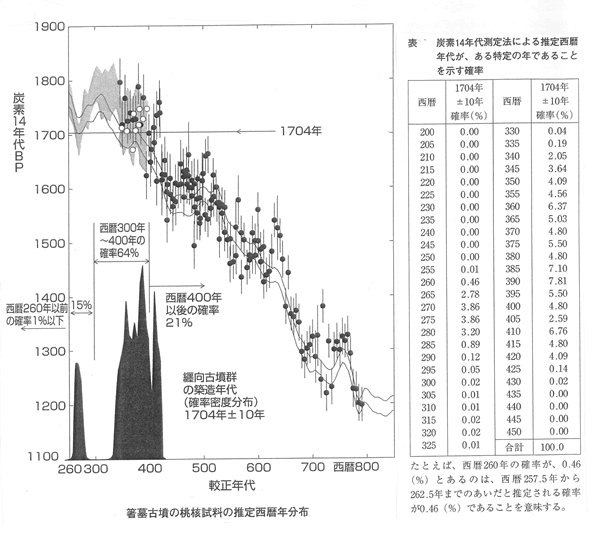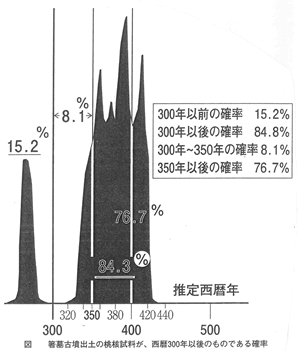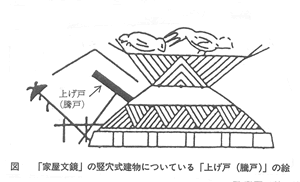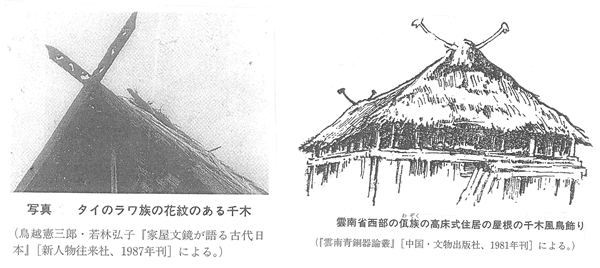■神功皇后の出生
成務天皇の後継ぎは成務天皇の子ではなかった。日本武の尊(やまとたけるのみこと)の子が仲哀天皇として即位した。
その仲哀天皇の皇后が息長帯比売(おきながたらしひめ)の命である神功皇后である。
戦前は日本の力を外国にも示したとして、お札に神功皇后が印刷されるまでになったが、戦後一転して、神功皇后の話は作り話だとされるようになった。
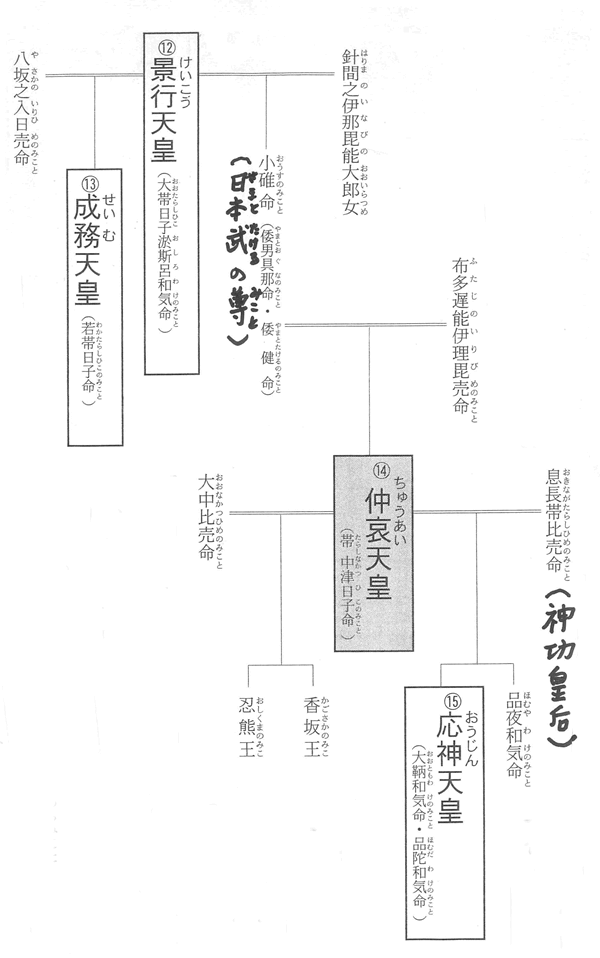
「息長(おきなが)」は近江国坂田郡(滋賀県坂田郡近江町)を本拠とする豪族である。
また、彦坐王(ひこいますのおう)の妃である息長水依比売(おきながのみずよりひめ)は野洲郡の出身である。そこから息長は坂田郡から野洲郡付近に広がっていた豪族あるいは地名であると思われる。
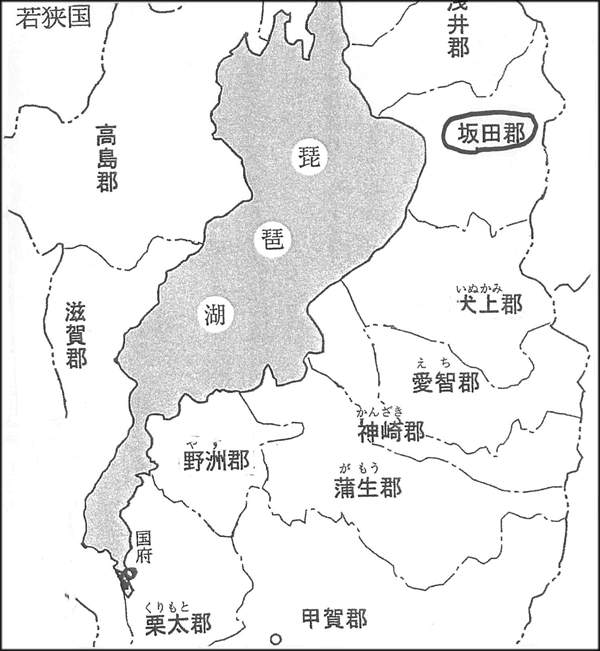
第十四代仲哀天皇の皇后の神功皇后は、『古事記』『日本書紀』ともに、天皇とはしていない。しかし、『常陸国(ひたちのくに)風土記』は「息長帯比売(おきながたらしひめ)の天皇(すめらみこと)」と記している。
これは、『日本書紀』によって、天皇の歴代が確定する以前の呼び方を記したものである。
『扶桑略記(ふそうりゃっき)』は、神功皇后を第十五代の天皇とし、「神功天皇」「女帝これより始る」と記している。
これらによると、『常陸国風土記』の神功皇后は天皇の扱いとなっており、『扶桑略記』でも女帝として、天皇としている。
神功皇后の系図では第10代開化天皇の5代の孫であるとしており、母は葛城高額比売(かずらぎのたかぬかひめ)としている。
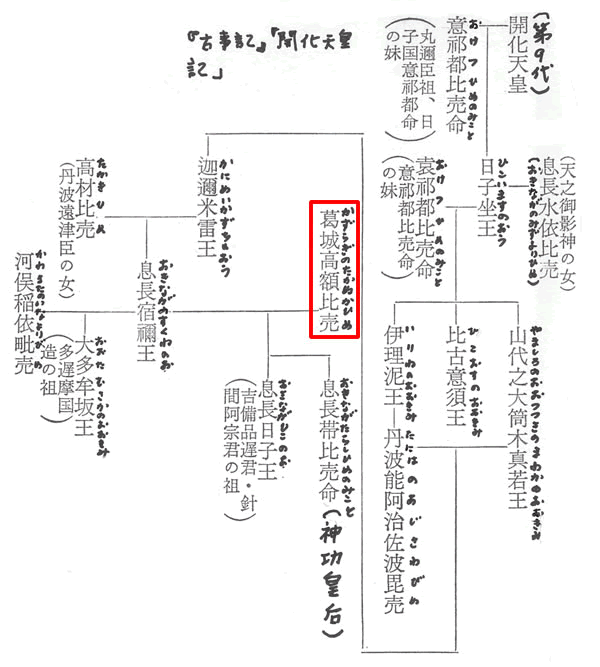
この葛城高額比売は天日槍(あめのひぼこ)の5代の孫となっている。つまり新羅の王子の子孫となっているのだ。
神功皇后はいわゆる三韓征伐で新羅を攻めたことになっているが、新羅と関係している。
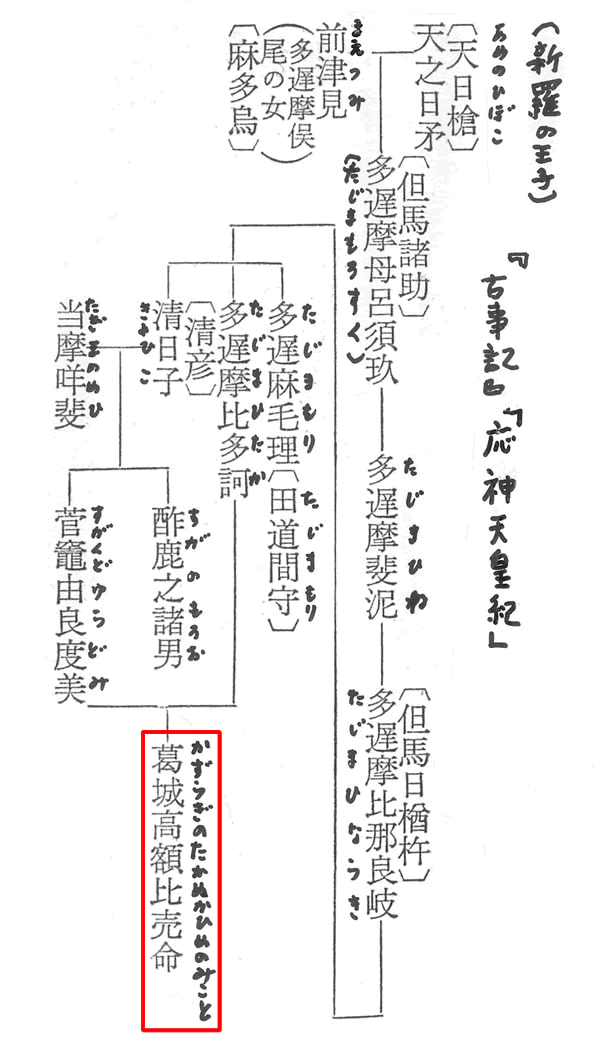
■神功皇后の年代
天皇1代10年説の天皇年代論から、仁徳天皇を基準点Ⅰとすれば、2代遡った仲哀天皇没年の推定は404年となる。
(下図はクリックすると大きくなります)
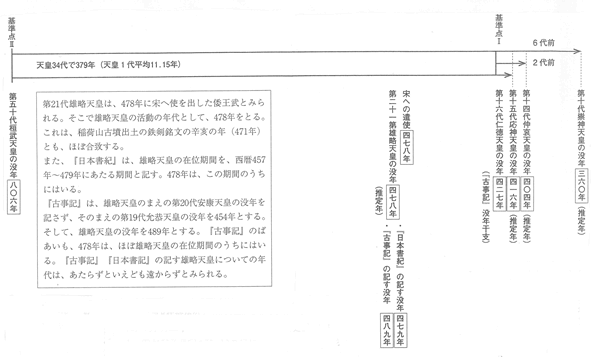
この404年頃というのは下記の時期と合うと考えられる。
・崇神天皇陵古墳の年代は四世紀の半ばすぎ(森浩一・大塚初重・齊藤忠・川西宏幸・関川尚功の諸氏)
・400年、倭は新羅城に満ちていた(『広開土王碑文』)
・402年、未斯斤(みしきん)人質(『三国史記』)
・404年、「倭は不軌にも、帯方界に侵入」(『広開土王碑文』)
・407年、広開土王は倭と合戦・「斬殺蕩尽」(『広開土王碑文』)
・413年、倭王讃あり(『晋書』の(安帝紀)、『南史』の「倭国伝」)
・471年、辛亥の年、獲加多支鹵大王(わかたけるだいおう)、斯鬼(しき)の宮に在る。(稲荷山古墳出土鉄剣銘文)
この年代については、『三国史記』「新羅本紀」で「元年(402)三月、倭国と好(よしみ)を通じ奈勿王(なぶつおう)の子、未斯欣(みしきん)を人質とした。」とある。
更に、『日本書紀』でそれと同じような記述がある。
『日本書紀』「神功皇后紀」仲哀天皇九年
①爰(ここ)に新羅の王 ②波沙寐錦(はさむきむ)、皍ち ③微叱己知波珍干岐(みしきんはとりかんき)を以て ④質(むかはり)として、仍(よ)りて金(こがね)・銀(しろがね)・彩色(うるはしきいろ)、及び綾(あやきぬ)・羅(うすはた)・縑絹(かとりのきぬ)を齎(もたら)して、八十艘(やそかはら)の船に載(のせい)れて、官軍(みいくさ)に從(したが)はしむ。
①以下、一行、微叱己知の入貢を述べ、五年三月条の伏線とする。仲哀記にはない。この一連の話は、これまでの征討の物語とは違い、史実を核としたもので、朝鮮側にも以下に述べるような異伝が記録されている。
②波沙は、三国史記、新羅本紀の第五代婆娑尼師今(尼師今は王号)なる伝説的王。寐錦は、広開土王碑・智証大師寂照塔碑に見え、尼師今(尼叱今)と同語か。
③微叱己知は、第十五代奈勿王の子の未斯欣(三国史記。三国遺事では美海、また未叱喜)。波珍干岐は、新羅十七等官位の第四波珍干(飡)=海干(海の朝鮮古訓patar.)。五年三月条では「微叱許智」伐旱に作る。
④入貢の年を三国史記は第十六代実聖王元年(402)、三国遺事は奈勿王三六年(390)とする。
注:【三国史記】(さんごくしき)朝鮮の現存最古の史書。五〇巻。高麗の仁宗の命で金富軾らが撰。1145年成る。新羅・高句麗・百済の三国の歴史を紀伝体に記す。
■倭と新羅、百済との関係
・「戦闘および不和」の文脈のなかであらわれる「倭」とは、たとえば、つぎのようなものである。これらは、すべて、「新羅本紀」のなかにあらわれる。
「倭兵が大挙して攻めてくる……。」
「倭人は、大いに敗れて逃走した。」
「倭人が来て、金城を包囲して、五日も解かなかった。」
「倭兵が、明活城(慶州付近)に攻めてきて、勝てずして帰るところを、王が騎兵をひきいて、独山(迎日郡)の南で迎撃して、ふたたび戦ってこれを破り、三百余名を斬殺した。」
「倭人が、東辺をおかした。」
「倭人と風島で戦ってこれに撃ち勝った。」
・「戦闘および不和」の文脈以外の文脈のなかであらわれる「倭」は、ほとんど、「百済本紀」のなかにあらわれる。
以下は、「百済本紀」のなかにみえる例である。
「王は、倭国と友好関係を結び、太子の腆支(てんき)[直支(とき)]を人質にした。」
「使者を倭国に遣わして、大きな珠を求めた。」
「倭国の使者が来たので、王は、彼を迎えて、慰労し、とくに厚く遇した。」
「[王が薨(こう)じ]腆支太子は、倭国において、訃報を聞いて、哭泣(こっきゅう)しながら、帰国を請うた。倭王
は、兵士百名をともなわせて、護送してくれた。」
このように、倭、新羅、百済、高句麗の国際関係を示す、この図から倭と新羅の関係は友好より、敵対関係であったことが分かる。それに対し百済とは友好的であったことが分かる。
(下図はクリックすると大きくなります)
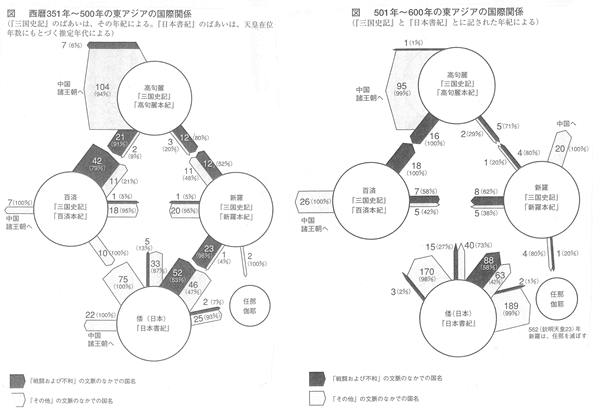
■任那割譲
大伴談(かたり)の子で武烈天皇・継体天皇の即位実現に功があり、宣化天皇にいたる4朝の大連(おおむらじ)であり、筑紫の磐井の乱の鎮圧で功績を上げた大伴金村(おおとものかなむら)は欽明天皇元年(540)に百済への任那4県割譲の責任をとわれ失脚した。
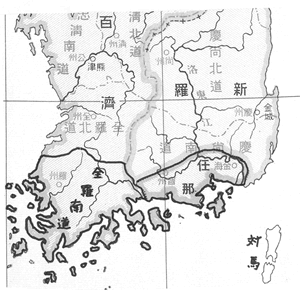 このように、欽明天皇という歴史的記録が確かな時代に、日本は任那の4県を百済に割譲している。この4県は全羅南道のほとんど全域に及ぶ。ということは、それ以前に日本は朝鮮半島を支配していたことを物語る。
このように、欽明天皇という歴史的記録が確かな時代に、日本は任那の4県を百済に割譲している。この4県は全羅南道のほとんど全域に及ぶ。ということは、それ以前に日本は朝鮮半島を支配していたことを物語る。
その後、歴史の流れは下記となる。
・562年、新羅が任那を滅ぼす(欽明朝)
・660年、百済が日本に救援を求める(斉明朝)
・663年、白村江の戦いで日本大敗、百済滅亡(天智朝)
白村江の大敗で、日本は朝鮮半島から撤退する。
■神功皇后の懐妊
・懐妊期間を十月十日としている
『日本書紀』によれば、仲哀天皇は、仲哀天皇の九年二月五日になくなり、応神天皇は、仲哀夫皇の九年十二月十四日に生まれたという。
人間が胎内にいる期間は、十月十日(とつきとおか)であるというよく知られている期間に、正確にあっている。
『日本国語大辞典』(小学館刊)は、記している。
「とつき 十日(とおか)10か月と10日。人が胎内にある期間をいう。」
人が胎内にある期間は、統計的に280日土17日といわれている。一朔望月(さくぼうげつ)(月の新月からつぎの新月まで、または、満月からつぎの満月にいたる期間)は、29.5日あまりであるから、正確には、陰暦で計算しても、平均して十月十日にはならない。
しかし、いつのころからか、人が胎内にある期間は、十月十日であるといいならわしてきた。
『日本書紀』の記述では、応神天皇は仲哀天皇の没した日から数えて、ちょうど十月十日目に生まれたことになっている。
この話は十月十日と同じ日とし、奇妙である。
・神功皇后は、無意識の世界で、夫仲哀天皇の死を願っていた
『古事記』は、つぎのように記している。
「皇后の息長帯日売(おきながたらしひめ)の命(神功皇后)は、神懸りをした。
仲哀天皇が、筑紫の香椎(かしい)の宮にいて、熊曾の国を撃とうとしたときに、天皇が琴を弾き、建内(たけうち)の宿禰(すくね)が祭りの庭にいて、神の言葉を乞い求めた。
皇后に神が懸って、神が教えたことは、つぎのとおりであった。
『西のほうに国がある。金銀をはじめ、目をかがやかせる種々の宝物がその国に多い。私が、いま、その国を与えよう。』
仲哀天皇が、答えて言った。
『高いところに登って、西のほうを見ても、国は見えない。ただ大海だけだ』
いつわりを言う神だと思って、琴を押し退けて、弾かずに黙っていた。
そこで、神は、大そう怒って、
『すべて、この国は、お前[汝(いまし)]の治めるべき国ではない。お前は、この世の人が行くべきただひとつの道、すなわち死の国へ行け。』
とのべた。
そこで、建内の宿禰が言った。
『おそれ多いことです。陛下、やはりその琴をお弾き遊ばせ。』
そこで、仲哀天皇は、その琴をすこし引きよせて、しぶしぶと弾いていた。まもなく、琴の音が聞こえなくなった。火をともしてみると、すでに天皇は、薨去(こうきょ)していた。」
現代の心理学や精神医学の教えるところによれば、神憑(かみがか)りなどの憑依(ひょうい)現象は、外部の神などが、人間にとりつくのではなく、人間の潜在意識が、神などの別人格の形をとって表面にあらわれるものであるという。
神懸りして天理教をはじめた中山みきも、大本教をはじめた出ロナオも女性であった。第二次世界大戦後、「おどる宗教」として注目を集めた北村サヨも、「神懸り」して、天照皇大神宮教をはじめたが、女性であった。
これから、考えられることは、応神天皇は仲哀天皇の子であったのであろうか。
『住吉大社神代記』
津守(つもり)氏の氏文。天平三年(731)津守宿禰客人・島麻呂による住吉大社司の解文の体裁で、延暦八年(789)の摂津職(せっつしき)判をもつ。
「是の夜、天皇(すめらみこと)忽(たちま)ちに病(みやまひ)発(おこ)りて崩(かむあが)りましぬ。是(ここ)に、皇后(おほきさき)と大神(おおかみ)と密事(みそかごと)有り。[俗(くにひと)、夫婦(めをひと)の密事(みそかごと)を通(かよ)はすと曰(い)ふ。]」といふ。
ここでは神功皇后と住吉大社との密事を記している。
しかし、一番疑わしいのは神功皇后の側にいた武内の宿禰ではないか。
武内の宿禰の子孫の系図を下記に示す。絢爛たる閨閥である。
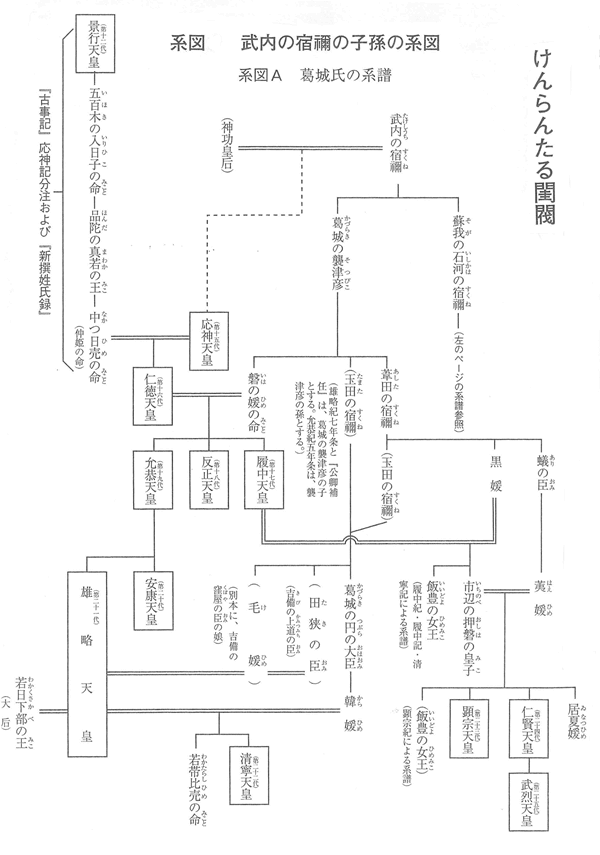
更に蘇我氏に繋がっている。蘇我氏の一族から天皇が大勢誕生している。
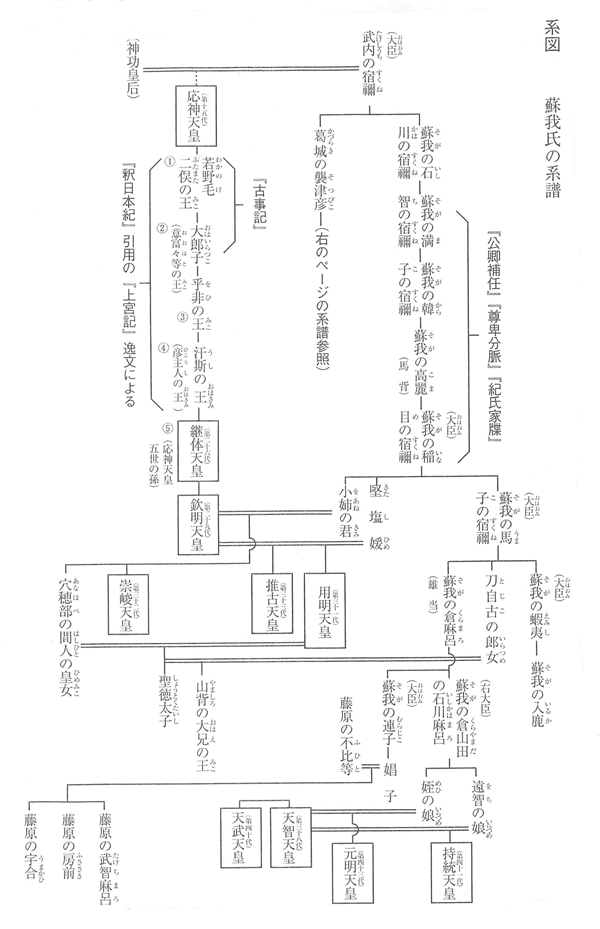




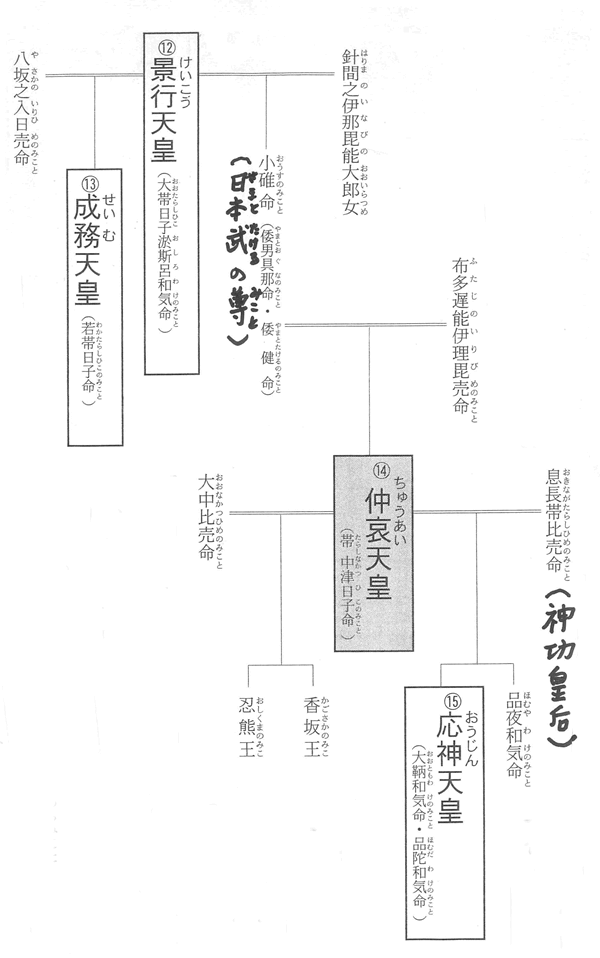
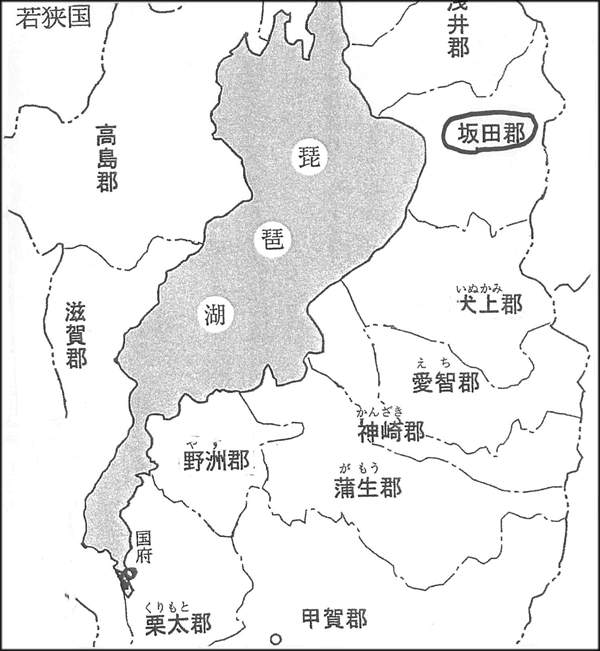
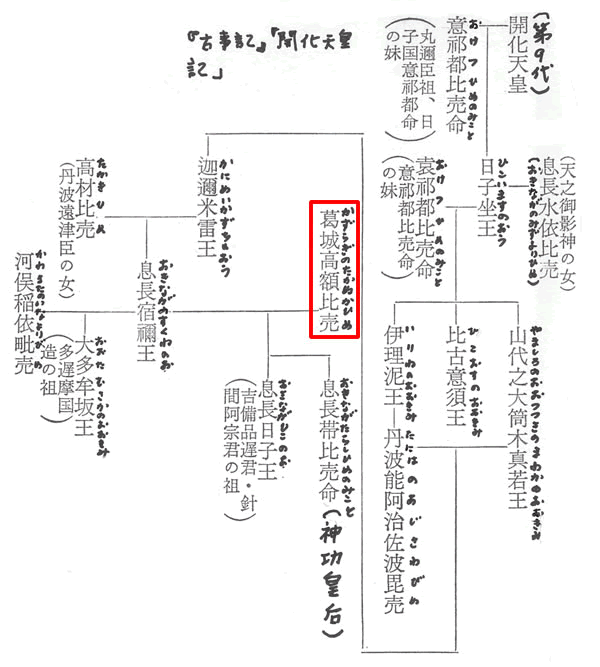
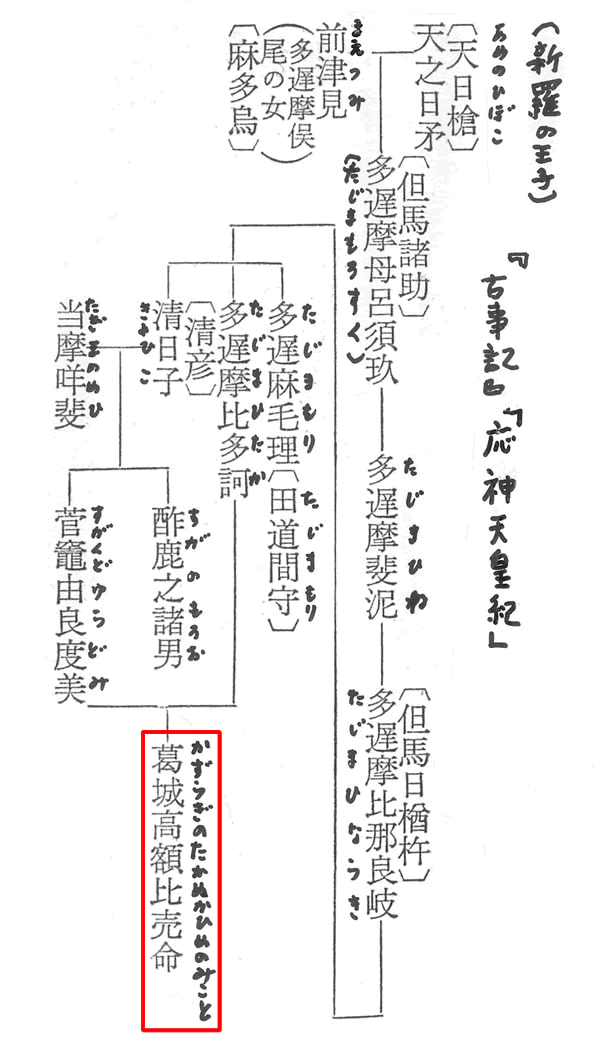
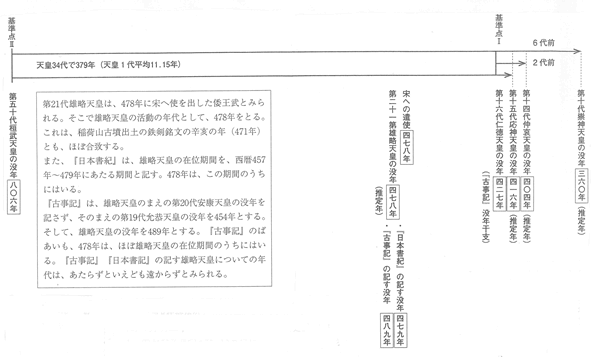
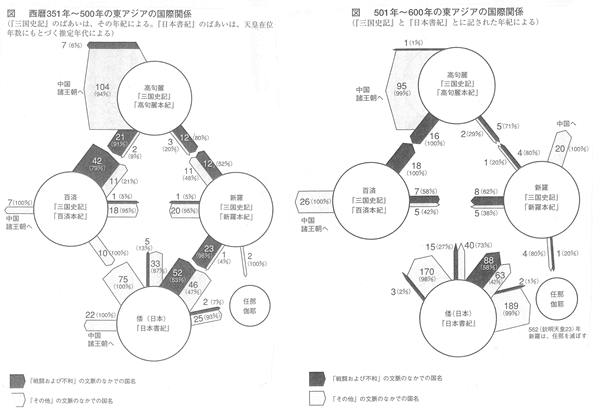
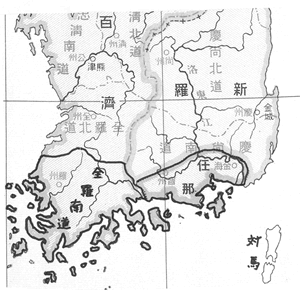 このように、欽明天皇という歴史的記録が確かな時代に、日本は任那の4県を百済に割譲している。この4県は全羅南道のほとんど全域に及ぶ。ということは、それ以前に日本は朝鮮半島を支配していたことを物語る。
このように、欽明天皇という歴史的記録が確かな時代に、日本は任那の4県を百済に割譲している。この4県は全羅南道のほとんど全域に及ぶ。ということは、それ以前に日本は朝鮮半島を支配していたことを物語る。