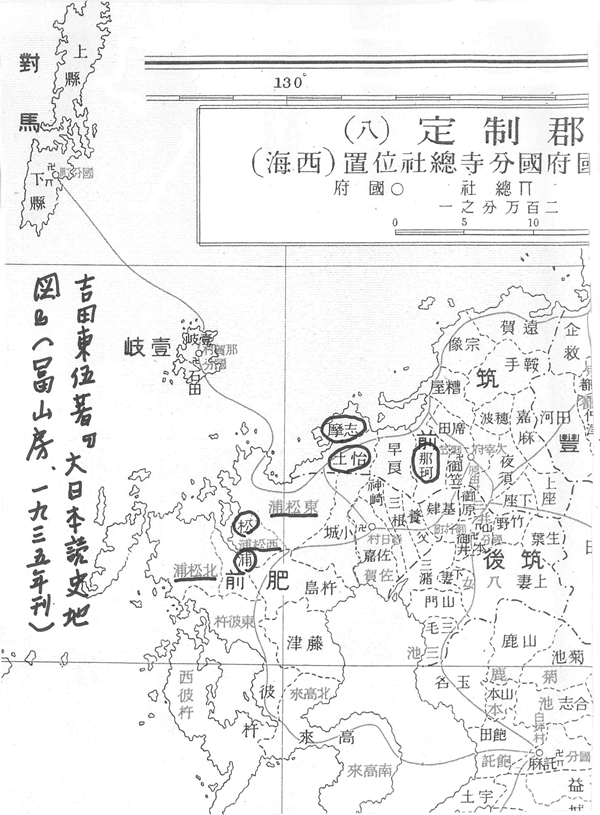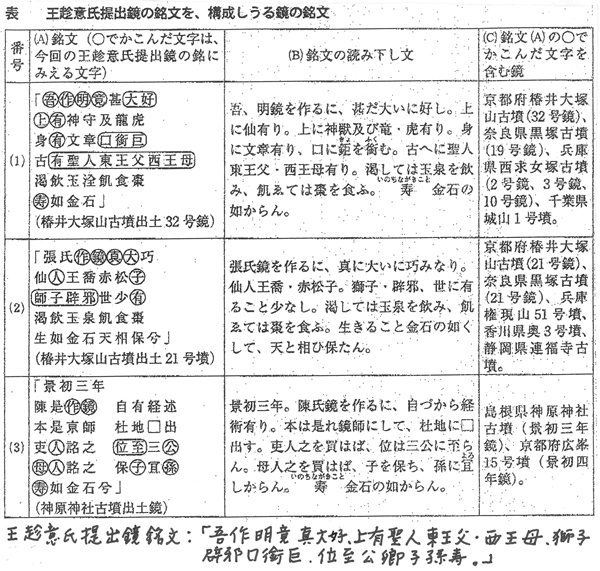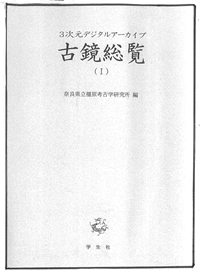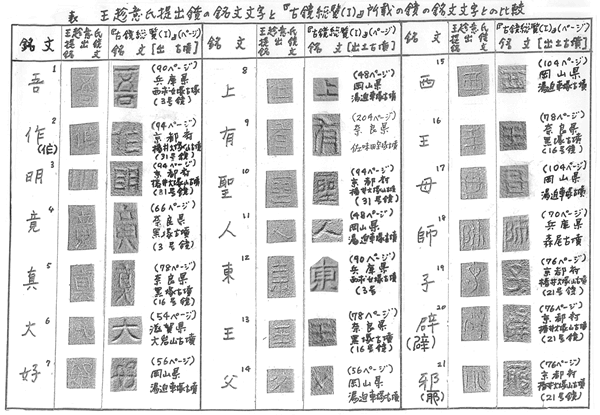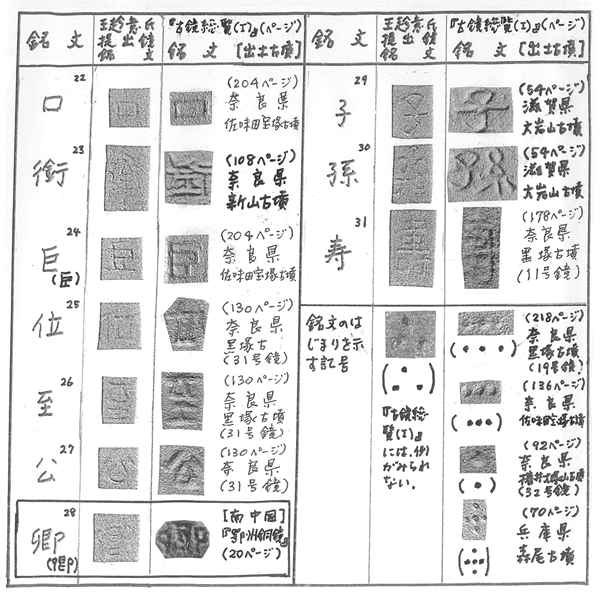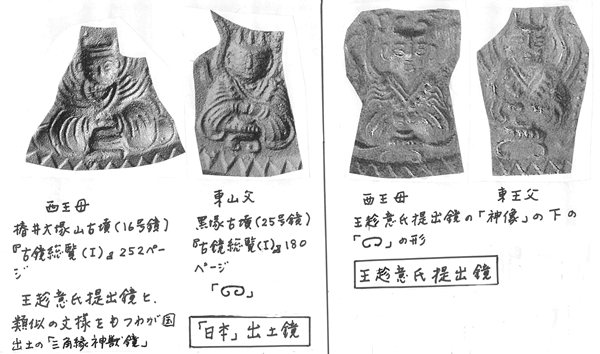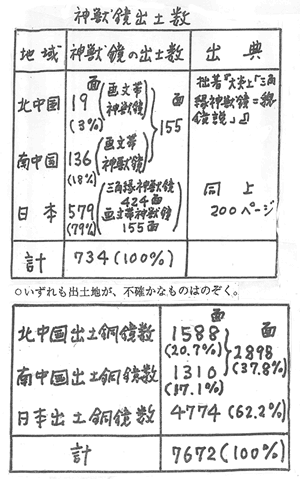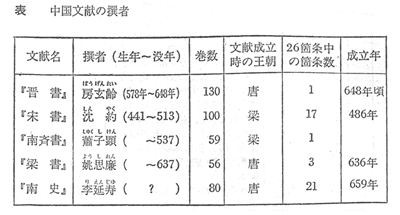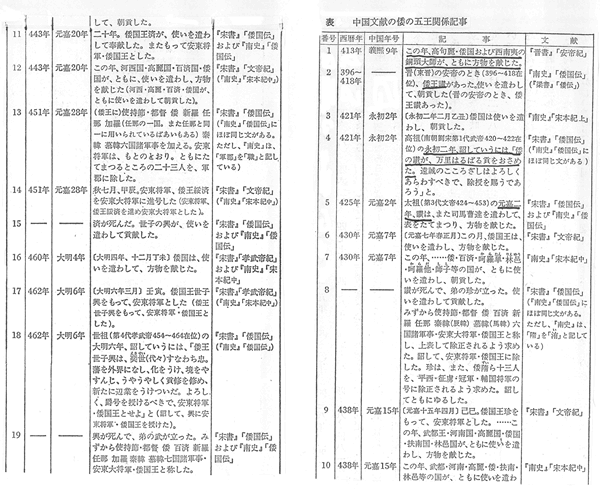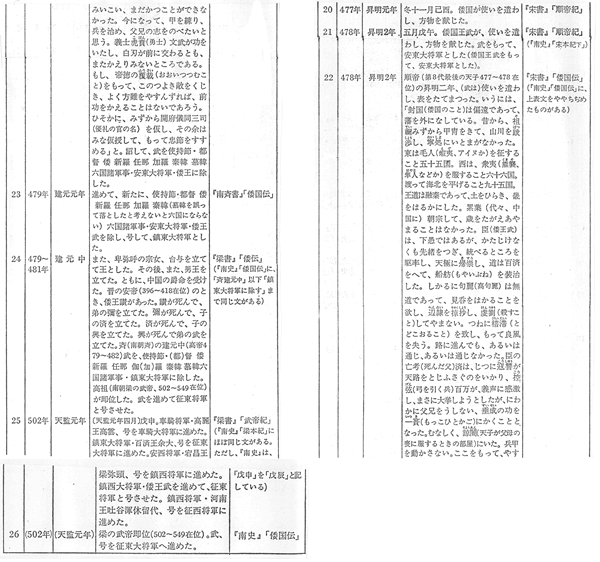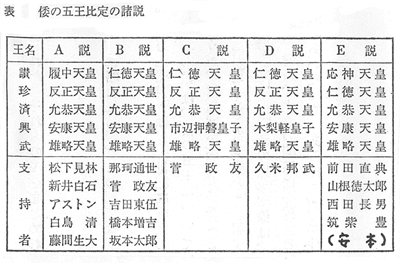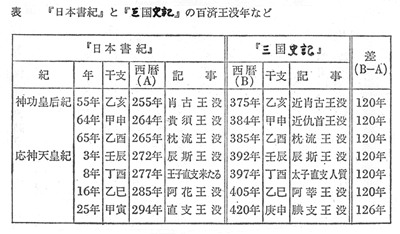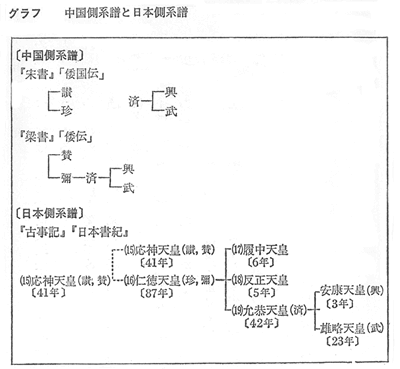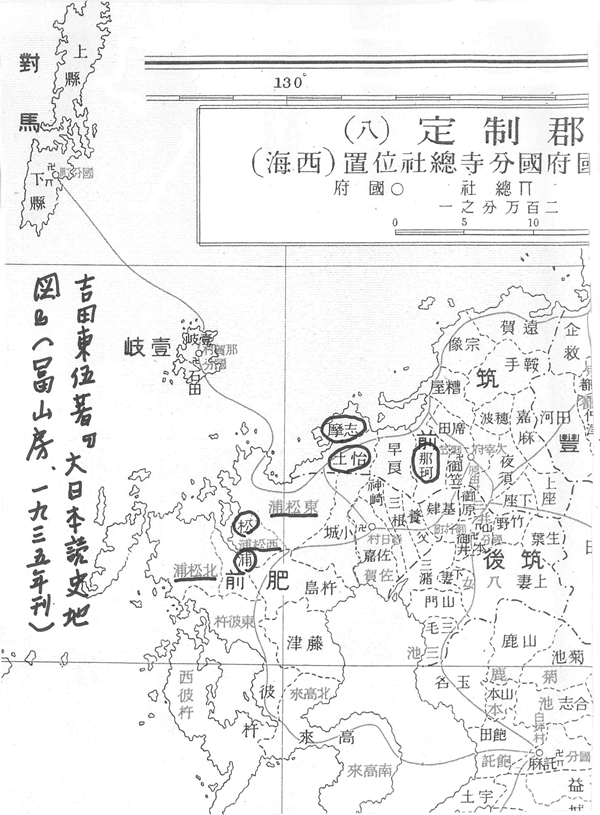■『魏志倭人伝』記載の「末盧」「伊都」「奴」の国々
・末盧国
また、一海をわたる。千余里で、末盧国(肥前の国、松浦郡)にいたる。四千余戸がある。山が海にせまり、沿岸にそって居(住)している。草木が茂りさかえ、行くに前の人をみない(前の人がみえないほどである)。(住民は)よく魚や鰒(あわび)を捕える。水の深浅をとわず、みな沈没してこれをとる。
又渡一海千餘里至末盧國有四千餘戸濱山海居草木茂盛行不見前人好捕魚鰒水無深淺皆沈没取之
・伊都国
東南に陸行すること五百里で、伊都国(いとこく)[筑前の国怡土(いと)郡]にいたる。官を爾支(にき)といい、副(官)を泄謨觚(しまこ)・柄渠觚(ひここ)という。千余戸がある。世々王がある。みな女王国に属している。(そこは帯方)郡使が往来するときつねにとどまるところである。
東南陸行五百里到伊都國官曰爾支副曰泄謨觚柄渠觚有千餘戸丗有王皆統屬女王國郡使往来常所駐
・奴 国
東南(行)して、奴国(なこく)[筑前の国、那の津、博多付近]にいたる。百里である。官を兕馬觚(しまこ)という。副(官)を卑奴母離(ひなもり)(夷守)という。二万余戸がある。
東南至奴國百里官曰兕馬觚副曰卑奴母離有二萬餘戸
■上古音と中古音
・末盧国の読み
「末盧」の地もまた、「壱岐」「対馬」のばあいと同じく、三世紀から八世紀まで、呼び名にほとんど変化がなかったと考えると、理解しやすい。
すなわち、「末盧」の地は、三世紀から八世紀まで、一貫して、「まつら」と呼ばれつづけてきたと考えると、理解しやすい。
「末盧」は、ふつう、壱岐からもっとも近い現在の松浦の地(肥前の国松浦郡)をさすと考えられている。
この地のことを、『万葉集』は、「麻都良(まつら)」「末都良(まつら)」「麻通良(まつら)」「麻通羅(まつら)」などと記している。『古事記』の「仲哀天皇記」には、「末盧県(まつらのあがた)」と記されている。『日本書紀』の「松浦県」も、「まつらのあがた」と読むのがふつうである。
『和名抄』の郡名では、「松浦(万豆良)」と記されている。「末盧」の上古音は、「まつら」に近く、中古音は、「まつろ」に近い。
「末」の字は、八世紀の万葉仮名でも「ま」または「まつ」と読まれている。『古事記』の「仲哀天皇記」の「末羅(まつら)県」では、「末」が「まつ」と読まれている。「末 muat」という漢字の二音目の子音の夕行の音を活用させて、「つ」と読んでいるのである。
「盧」の字の上古音「hlag」[藤堂明保による。蕙同龢(とうどうか)は、lagと考える]は、「ら」の音に近い。「盧」の上古音は、三世紀の「倭人語」の「ら」をあらわすのに用いられたとみられる。
ところが、中国では、のちに、「盧」の字の音は変化し、「ろ」の音に近いhloのようになった。そのため、八世紀の万葉仮名では、「盧」の字は、「ろ(乙類)」をあらわすのに用いられている。
八世紀においては、「ら」をあらわすさいに、「盧」の字を用いることができなくなったので、『古事記』にみられるように「羅」の字を用いるようになったのである。
『魏志』の「東夷伝」の弁辰の条に、新羅の前身の「斯盧」という国名がみえる。この国について、『南史』の「東夷伝」新羅の条に、
「魏の時には新盧といい、宋の時には新羅といい、あるいは斯羅という。」とある。
このばあいも、国名は、一貫して「しら」であったとみられる。「盧」の字の音の方が、「ら」から「ろ」に変化したので、「盧」を「羅」におきかえたのである。
『魏志』の「末盧」が、『古事記』で「末羅」と記されているのも、まったく同じ事情によるとみられる。
西暦414年に建立された広開土王碑の碑文には、「新羅」と記されている。広開土王碑の時代には、「盧」の音が、「ら」から「ろ」に変わっていた可能性が強い。
「末盧国」について、頼惟勤(らいつとむ)は、つぎのようにのべている。
「つぎは『末盧国』です。これは普通『マツラ』と読んでいて、あまり異説がないのですが、普通は『ロ』と読む『盧』の字を『ラ』と読む。これは日本に『マツラ』というところがあって、それは『日本書紀』以来、『松浦』と書いたところに違いないから『ラ』になるわけです。
それではそういう日本の現実の地名に合わせて文字を勝手に読んだのかといいますと、決してそうではないのです。この『盧』の字を『ロ』と読むのは、専門の言葉で中古音、つまり隋唐時代の音というものです。隋唐時代の音、これを晋の陳寿が書いた〈倭人条〉で使うはずはない。少なくとも晋以前の音を使っているわけです。ところが、隋唐時代から遡って行きますと、晋を含めて途中の音がずっとわからなくて、はるか以前の先秦時代の音がいきなりわかるわけです。その先秦時代の音を上古音といっています。
この上古音では、『盧』は『ラ』という部分を含む音であったらしい。通説ではlagであったとされています。ですから、Lagという上古音が、途中いろいろ変遷を経て、ついに中古音loに到達すると考えられます。これが日本の『ロ』です。『ラ』から『ロ』への変化を途中に、この『三国志』の記録があるわけです。」(「〈魏志・東夷伝・倭人条〉の文章」)
・上古音で読むべきなのか、中古音で読むべきなのか
『魏志倭人伝』の倭人語は、漢字で記されている。その漢字は、中国語の上古音(周・秦・漢代の音)に近い音で読むべきなのか、中古音(隋・唐代の音)に近い音で読むべきなのか。上古音と中古音とでは音が異なっている。神戸市外国語大学の長田夏樹(おさだなつき)教授は、上古音に近い音で読むべきことを主張されている(『邪馬台国の言語』学生社刊)。
大阪外国語大学の森博達助教授は、むしろ、中古音に近い音で読むべきことを主張されている(『倭人伝を読む』中公新書、『倭人の登場』[日本の古代1]中央公論社刊)。
中国語学者、藤堂明保は、およそつぎのようにのべている。
「言語の音韻体系からいうと、隋・唐がわかっている、周・秦・漢も概略わかっている。ただ、残念ながら、上古から中古へのあいだの魏の時代と六朝の時代がブランクになっている。魏の時代、六朝の時代の中国語は、果たしてどういう発音であったか。それは周・秦・漢から隋・唐へ移る『過渡期』であるということはわかる。しかし、『魏志倭人伝』のなかの倭国のいろんな地名の漢字音を正確に出せ、とわれわれに要求されましても、ちょっと困る。上古に近いようにもっていくか、中古に近い形にもっていくかによって、だいぶ発音が違ってくる。」(『日本古代語と朝鮮語』毎日新聞社刊)
『魏志倭人伝』の、「一支」「末盧」「伊都」「奴」は、ふつう、「いき」「まつら」「いと」「な」と読み、それぞれ後世の地名、「壱岐」「松浦(まつら)(『古事記』の記す『末羅(まつら)』の地)」「怡土(いと)」「儺(な)(『日本書紀』の記す『儺(な)の県(あがた)』の地)」にあたるとしている。
ところで、「一支」「末盧」「伊都」「奴」を、すべて、上古音に近いとして読めば、「いき」「まつら」「いた」「な」となって「伊都」の音が、後世の「怡土(いと)」の音とあわなくなる。逆に、すべてを、中古音に近いとして読めば、「いし」「まつろ」「いと」「の(ど)」となって、「一支」「末盧」「奴」の音が、後世の「壱岐」「松浦」「儺」の音とあわなくなる。
このことについては、かつて、明治大学の鈴木武樹(たけじゅ)教授が、およそつぎのようにのべている。
「上古音というのは二世紀まで使われた音で、おそらくそれは朝鮮半島には残っていたはずである。しかし、三世紀中葉の帯方郡の使者が上古音で話していたかどうかは疑問である。陳寿の時代になると中古音である可能性も出てくる。『東夷伝』の固有名詞を全部、上古音で読むのはまずい。中古音で読むのはもっとまずい。
たとえば、上古音で読むと、『奴』は『な』である。中古音で読むとこれは『の』としかならない。ところが、現在まだ残っている地名からすれば『奴』は『な』と読むほうがよい。しかし、『倭人伝』に出てくる地名を全部上古音で読んでしまうと、『伊都』の『都』は『た』と読まなければいけなくなる。
そこで、僕はつぎのような折衷案を提出したい。つまり、『三世紀になって中国に新しく知られた国々の名称は中古音で読まれている可能性がある。しかし三世紀初頭以前からすでに中国で知られていた国(<奴>は知られている。西暦57年に中国へ入貢しているから)、すなわち、中国で上古音が用いられていた時代からもう中国に名前が知られていた国々は、上古音で読まれている』。
三世紀というのは、中国がそろそろ中古音を用いはじめる時代であるから、その時代になってから中国に知られた国々は、中古音で書かれている可能性があるというわけである。そうすると、つじつまが合う。たとえば『一支(いき)』は上古音である。それから『末盧(まつら)』も上古音である。この『盧』は『ろ』でなく『ら』である。『新羅(しら)』のばあい、最初『斯盧』であるが、『盧』が中古音で『ろ』としか読めなくなる
と、『羅』でもってその『ら』という音にあてるようになる。『奴』も、中古音で『の』としか読めなくなってくると『那』に変わっていく。したがって、『一支』『末盧』『奴』―こういった国々は上古音で読んでいい。ところが、『伊都』とかいった新しい国々は、中古音で『いと』と読むべきではないかと思われる。
このように、固有名詞の読み方も、上古音または中古音で読む、と固定するのではなく、上古音ならこうなる。中古音ならこうなると、二段構えで出しておいて、なぜこの国の読み方は、上古音、あるいは中古音で読まなければならないのかということも、考えておく必要があると思う。」(以上、松本清張編『邪馬臺国の常識』 1974年、毎日新聞社刊による。)
鈴木武樹の、「中国で上古音が用いられていた時代からもう中国に名前が知られていた国々は、上古音で読まれている。三世紀になって中国に新しく知られた国々の名称は、中古音で読まれている可能性がある」という見解は、一つの、興味ある見解である。
鈴木の見解を支持するような事例をあげておこう。
『隋書』は、636年に成立した。あきらかに、中古音の行なわれていた時代に成立した。
そこには、「都斯麻(つしま)国(対馬)」「一支(いき)国(壱岐)」「竹斯(つくし)国(筑紫)」「阿蘇(あそ)山」などのわが国の地名がみえる。
これらは、いずれも、わが国の八世紀文献の万葉仮名の読み方で読んでも。それぞれ、「つしま」「いき」「つくし」「あそ」などと読めるもので、特に問題はないようにみえる(『時代別国語大辞典上代編』三省堂刊の、巻末の「主要万葉仮名一覧表」参照)。
しかし、『隋書』のなかのわが国の地名も、上古音で読むべきものと、中古音で読むべきものが、まじった形となっている。
「一支(いき)国」の「支(き)」は、上古音で読むとき「き」となり、中古音で読むとき、「し」となる。したがって、「一支国」のばあいは、上古音で読まれていることになる。「阿蘇(あそ)国」の「蘇(そ)」は、上古音で読むとき「さ」となり、中古音で読むとき、「そ」となる。したがって、「阿蘇国」のばあいは、中古音で読まれていることになる。
『隋書』のなかのわが国の地名を表記した文字は、全体的に、万葉仮名として、使用頻度の高いものが用いられている。
わが国の人が、万葉仮名で書いたものを、中国の人がうつした可能性も、多分にある。
しかし、「一支」の「支」の音は、中国の上古音では「き」に近い音であり、中古音では、「し」に近い音である(お茶の水女子大学の頼惟勤(らいつとむ)教授は、『邪馬臺国の常識』のなかの「〈魂書・東夷伝・倭人条〉の文章」という論文のなかで、『一支(いちし)』ですが、その『支(し)』が、昔はサ行の『シ』ではなく、力行の『キ』であった。これははっきりとした証拠があって疑うことができない点です。」とのべている)。
わが国の多くの八世紀文献が、「き(甲類)」をあらわす万葉仮名として、「支」を用いているのに、『日本書紀』が、「き(甲類)」の万葉仮名として、一回も、「支」を用いていないのは、『日本書紀』が、おもに、中古音系列の万葉仮名を用いることを原則としていたためとみられる。
そして、『日本書紀』は、「一支」をあらわすのに、中古音においても、「いき」と読むことができる「壹岐」「壹伎」などを用いている(『古事記』は、「伊伎」と記す)。
すなわち、『日本書紀』の編者は、『魏志』などにみえる「一支」という表記を尊重し、それと意味上、または、視覚上似た文字を選びながら、中古音で「いき」と読める文字に、書きあらためているのである。
「支」という文字を、上古音系列の「き(申類)」と読む伝統は、わが国では、八世紀の万葉仮名のなかに残っている。そのため、よく用いられている万葉仮名で表記すると、上古音と中古音とがまじることになる。
『魏志』にも、『隋書』にみられたようなことが起きている可能性がある。『魏志』に記されているすべての「倭人語」を、上古音、および、中古音で読んだリストなどは、拙著『倭人後の解説』(勉誠出版、2003年刊)に示されている。
・井上光貞 他著『鉄剣の謎と古代日本』(新潮社1979年刊)
岸俊男:それから、その次は「?居」と書いた字でありますが、これは今申しましたように、草冠のある「獲」であるということまでたどりついたわけです。ところが、この字を万葉仮名として用いた例は『万葉集』とか、あるいは『日本書紀』、『古事記』などにはない。最初に私の頭に思いつきましたのは、『魏志倭人伝』に邪馬台国の官名として出てまいります「弥馬獲支」です。
これは従来は、「ミマカキ」というふうに読んでおられたんじゃないかと思うんです。ところが辞書をひきますと、この「獲」という字には、「クワク」という音とともに、「ワク」という音があります。その「ワク」という音に注目したのは、そのあとに出てくる「居」という字との関係からです。すなわち「欽明紀」では、たとえばミヤケを「弥移居」と書いて「居」の字を「ケ」と読んでおりますし、あるいはそのほかに元興寺の塔の露盤銘とか、天寿国繍帳銘とかではトヨミケカシキヤヒメ(豊御食炊屋姫)を「等已弥居加斯支夜比売」というふうに、この「居」を使っております。それで「ワク」プラス「ケ」で「ワケ」というふうになれば、記紀などに人名に付してしばしば出てくるワケ(別)というのにちょうど合うんじゃないかと。
ところで「?」が「ワク」ないし「ワ」と読めるようだとすると、次の「?加多支?」という部分も「?」の次は力行の「加」ですから、「ワカタ・・・」、それからその次の文字なんですけれども、この「支」という字は万葉がなでは甲類の「キ」であります。ところが、それが「ケ」と読めるかどうかということなんですが、私は、同じ甲類の「キ」という音を表わす「祁」という字がございますね。これを『日本書紀』では「キ」と読んでいる例が二、三例あると思うんです。
ところが『万葉集』になると全部「ケ」と読んでいます。だから「キ」は「ケ」に変わり得るんじゃないかと、そういうふうに考えたわけであります。
大野晋: それはどういうことで言っているのか知りませんけれども、「タケル」という言葉は「夕キ」がもとなので、それは背が高いということです。「タキ」の「キ」は甲類だと考えられる。
その「タキ」に「アル」がつくと「タキアル」でtakiaru→takeruという変化で、「タケル」というのが出てくるんです。
■有声のh
いわゆる「有声のh」(英voiced h 《音声》)というのは無声音[h]に対する有声音で、国際音声字母[IPA(International Phonetic Alphabet)]では[ɦ]で表わされる.[ɦ]は、しかし、音声学的には通常の有声音とは異なる。
英語のahead、日本語の「御飯」などの母音間の/h/は無声にはならず、不完全ながらも声帯の振動を伴うことが多い。このような場合に現われるのが[ɦ]である。この場合、声帯は通常の有声音の場合ほど接近せず、声門に隙間を残したままで不完全な振動をし、息もれの多い発音になる。ラディフォギッド(P. Ladefoged)によれば、このような声門の状態はつぶやき「声(murmur)」を発音するときの声門の状態と同じであるという。それで彼は「有声のh」という言い方は不適当で、「つぶやきの声のh(murmured h)」とよぶべきだとしている(Ladefoged、 1975)。また、彼によればヒンディー語などに現われる有声帯気音では、つぶやき声の有声音の出わたりにおいて[ɦ]が現われるという(たとえば[bɦal]「額(ひたい)」.[..]はつぶやき声をあらわす)(『言語学大辞典』第6巻[三省堂刊])
・邪馬台国の官の「弥馬獲支」
『魏志倭人伝』によれば、邪馬台国の役人に、「弥馬獲支」がいた。
「弥馬獲支」は、なんと読んで、なにを意味するのだろう。
「弥馬獲支」の「弥」「馬」「支」は、いずれも、万葉仮名に使用例があり、ふつうに読めば、「み(甲)」「ま」「き(甲)」である。
問題は、「獲」の字であるが、稲荷山古墳出土の鉄剣銘文の「獲(獲の異体字)加多支鹵」が、「わかたける」と解読され、「獲」が、「わ」の字であることがわかった。
じじつ、「獲」の上古音は「ɦuak」であり、万葉仮名で、「わ」をあらわす「和」の字の上古音「ɦuar」、中古音「ɦua」と基本的に同じである。ここからも、「獲」は、「わ」をあらわすことが、たしかめられる。

「獲加多支鹵」のばあいの「獲加」は、「獲」の字の終わりの子音「k」と、「加」の字の語頭の子音「k」との、「子音重複の表記法」がみとめられる。そして、「弥馬獲支」の「獲支」のばあいも、同じような「子音重複の表記法」がみとめられるようにみえる。
以上から、「弥馬獲支」は、まず、ふつうに読めば、「み(甲)まわき申)」である。
「みまわき」とは、なんだろう。
まず、「み(甲)ま」は、『日本書紀』にみえる「天孫(あめみま)」「皇孫(すめみま)」「天神(あまつまみ)の孫(みま)」や、『続日本紀(しょくにほんぎ)』にみえる「美麻乃弥己止(みまのみこと)」、『令集解(りょうのしゅうげ)』の儀制令の古記の「須売弥麻之美己等(すめみまのみこと)[天皇をさす]」、『常陸(ひたち)国風土記』久慈郡の条の「珠売美万命(すめみまのみこと)(ニニギノミコトをさす)」などの「み(甲)ま」(貴人の子孫、あるいは、皇統に生まれた神たる人の意味)を連想させる。
しかし、安本は、「弥馬獲支」の役目などから考えて、「弥馬」を、「玉体」の意味の「体」であろうと考える。『延喜式』巻一、「神祇一 四時祭上」の「御体(おほみま)を卜(うら)ふ」の条に、とくに、「辞(ことば)に於保美麻(おほみま)と曰(い)ふ」と註記されているものである。
「わき(甲)」は、「腋(わき)」「傍(わき)」の意味で、「みまわき」は、「王の傍(わき)にはべるもの」の意味であろう。
「御体傍(みまわき)」ならば、「み(甲)まわき(甲)」で、「弥馬獲支」と、音が、正碓にあう。
「御体別(みまわけ)」とすると、「み(甲)まわけ(乙)」となって、音がややあわない。
「支」の字は、「獲加多支鹵(わかたける)」のばあいのように、「け」とも読まれうるが、そのばあいは、「甲類のケ」である。
以上から、「弥馬獲支」は、「御体傍(みまわき)」であると考えられる。
大野晋氏は、『日本語の世界1』(中央公論社刊)において、「弥馬獲支」を、「御馬傍」で王の馬の傍にいるものと解釈されているが、『魏志倭人伝』には、「その地に牛馬なし」と明記しているので、この解釈は、無理ではなかろうか。
内藤湖南氏は、「弥馬獲支」を、崇神天皇の名の「御真木入日子印恵(みまきいりひこいにゑ)の命」と結びつける。「御真木」は、「み(甲)まき(乙)」で、「弥馬獲支」の「み(甲)まわき(甲)」とやや音がはなれる。
■末盧国での上陸地点
まず。一支国から末盧国への道程は、里程記事だけがあって、方向記事がぬけている。
壱岐の対岸で、壱岐からもっとも近い松浦(まつうら)の地(肥前の国松浦郡)を、『万葉集』では、「麻都良(まつら)」「末都良(まつら)」「麻通良(まつら)」「麻通羅(まつら)」などと記している。『古事記』の「仲哀天皇記」では、「末羅県(まつらのあがた)」と記しており、『日本書紀』の「松浦県」も、「まつらのあがた」と訓(よ)むのがふつうである。『和名抄』の郡名では、「松浦(万豆良)」と記されている。
言語学の分野では、しばしば、地名は、「言語の化石」といわれる。ふつうのことばにくらべ、地名は、歳月による風化を、ずっとうけにくい。とすれば、『魏志倭人伝』に記されている末盧国は、壱岐からの近さ、音の類似などからみて、やはり、肥前の国松浦郡の地に求めるべきである。
魏の使、あるいは、倭の使が壱岐から来たさい、具体的に船をつけた場所となると、つぎにわかれる。
①呼子港説
呼子(よぶこ)[名護屋(なごや)港は、天然の良港である。標高50メートルないし80メートルの山にかこまれ、どの方向から風が吹いても、風の影にはいる。古代においては、船舶の安全が、最優先されたはずである。豊臣秀吉が、朝鮮出兵において、名護屋港を基地にしたのも、この港が、古代から近世まで、北部九州随一の良港であったためとみとめられる。壱岐の原ノ辻あたりから来るとすれば、呼子は、もっとも近く、まずここに寄ったとみるのは自然である。
魏からの使が、呼子港に寄ったとみられることを詳論した論文に、高橋実の「舟から見た邪馬台国」(『季刊邪馬台国』13号~16号)がある。
博多湾や唐津港は、都市が発展し、船が大型で頑丈になって、はじめて良港となった。文永の役のさい、元軍が全滅に近い損害をうけたのは、戦術を優先し、太宰府に近い博多湾に入港したためである。
また、魏の使は、末盧国に上陸したあと、伊都国へむけて、「東南に陸行」している。伊都国を、『延喜式』『和名抄』の記す筑前の国怡土(いと)郡の地とすれば、呼子港から怡土郡へは、まさに、「東南」となる。末盧国を唐津港とすれば、唐津から怡土郡へは「東南」というよりは「東」になってしまう。
②唐津港説『魏志倭人伝』は、「狗邪韓国→対馬」間を「千余里」、「対馬→壱岐」間を「千余里」としている。そして、「壱岐→末盧国」間も「千余里」としている。「末盧国」を呼子港としたのでは距離が近すぎる。
唐津の地名は、「韓津」から起きている。唐津は、古来、朝鮮半島へわたる港として知られている。また、唐津市を中心とする東松浦郡一帯は、弥生前期・中期の遺跡・遺物が、豊富である。
弥生後期の資料は、桜馬場遺跡を除いては断片的である。しかし、桜馬場遺跡の後期初頭の甕棺からは、後漢鏡2面、国産の有鉤銅釧(ゆうこうどくしろ)26個、巴形銅器3個が、出土している。この甕棺墓は、後期初頭における末盧国の「王墓」級のものとみられている(武末純一)。小田富士雄(北九州市立考古博物館館長)、武末純一 (北九州市立考古博物館)など、唐津市を中心とするあたりを、末盧国の所在地とみる考古学者は多い。
魏使の、末盧国への上陸地点は、呼子港付近、末盧国の王の居住地は、唐津市付近とは、みられないだろうか。