■「黄幢(こうどう)」について
・『魏志倭人伝』の記述
46 正始六年難升米に黄幢
其六年詔賜倭難升米黄憧付郡假授
その六年(正始六、245)、詔して倭の難升米に黄憧(黄色いはた、高官の象徴)をたまわり、(帯方)郡に付して(ことづけして)仮綬せしめた。
47 卑弥呼と卑弥弓呼との不和
其八年太守王頑到官倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和遣倭載斯鳥越等詣郡説相攻撃状遣塞曹掾史張政等因齎詔書黄幢拜假難升米爲檄告愉之
その八年(正始八、247)、(帯方郡の)太守王頑(おうき)が、(魏国の)官(庁)に到着した(そして、以下のことを報告した)。
倭の女王、卑弥呼と狗奴国の男王卑弥弓呼とは、まえまえから不和であった。倭(国)では、載斯(きし)・鳥越(あお)などを(帯方郡に)つかわした。(使者たちは)(帯方)郡にいたり、たがいに攻撃する状(況)を説明した。(郡は)塞(さい)の曹掾史(そうえんし)(国境守備の属官)の張政(ちょうせい)らをつかわした。(以前からのいきさつに)よって、(使者たちは)詔書・黄憧をもたらし、難升米に拝仮し、(また)檄(げき)(召集の文書、めしぶみ、転じて諭告する文書、ふれぶみ)をつくって、(攻めあうことのないよう)告諭した。
『魏志倭人伝』によれば、正始六年(245年)、魏の皇帝は、倭の難升米(なしめ)に、帯方郡の太守を通じて、「黄幢(こうどう)」を与えたという。
正始8年(247年)に、帯方郡の塞(さい)の曹橡史(そうえんし)[国境守備の属官]の張政は、皇帝の詔書と黄幢を倭の地にもたらし、難升米にうけとらせた。
・烏形幢(うけいのはた)、日像幢(にちぞうどう)、月像幢(げつぞうどう)
ここで、「幢」の字は、『古事記』、『日本書紀』には使用例がない。しかし、『続日本紀(しょくにほんぎ)』や、律令の施行細則である『延喜式』、さらに、『文安御即位調度図(ぶんあんごそくいちょうどず)』などに使用例がある。
『続日本紀』では、「烏形(うけい)の幢(はた)」[巻第二、文武天皇、大宝元年(701年)春正月]のように、「憧(はた)」と訓(よ)んでいる。
岩波書店刊の新日本古典文学大系本の『続日本紀一』にはこの「鳥形の憧」などについて、つぎのように説明している。
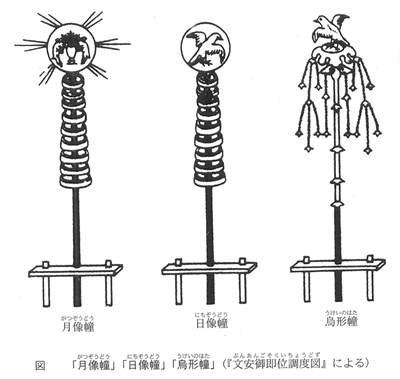 烏形幢
烏形幢
金盤の上に蓮花の台をとりつけ、その上に翼をひろげ頭をのばした金銅製の三本足の烏の像をすえる。その高さは三尺五寸。台の四か所から纓絡(ようらく)を飾りさげる。竿の長さは三丈。烏を北に向けてたてる。
日像幢
径三尺の銅の鋳物の円板に金薄を貼り、これに朱色で二本足の烏をえがき、長さ三丈の旗竿の先端にとりつける。竿には九輪を配する。
月像幢
径三尺の銅の鋳物の円板に金薄を貼り、これに月桂樹・蟾蜍(ひきがえる)・菟(うさぎ)等をえがき、長さ三丈の旗竿の先端にとりつける。竿には九輪を配する。月形の中にはひきがえるをえがくのが本来のもの。」
この説明のなかに、「三本足の烏」や、「ひきがえる」のことがでてくる。
『日本の神々 神社と聖地4 大和』(白水社刊)の、「鏡作坐天照御魂神社」の項(大和岩雄氏執筆)に、つぎのようなことがのべられている。
『磯城(しき)郡誌』には、つぎのように記されている。
「社伝に、本社は三座にして中座は天照大神(あまてらすおおみかみ)の御魂(みたま)なり。伝へ言ふ。崇神天皇六年九月三日、此地に於(おい)て日御象(ひのみかた)の鏡を改鋳し、天照大神の御魂(みたま)となす。今の内侍所(ないしどころ)の神鏡是(これ)なり。本社は其像鏡(そのみかたかがみ)を、祭れるものにして、此地を号して鏡作(かがみつくり)と言ふ。佐座は麻気神即(すなわち)ち天糠戸神(あまのぬかとのかみ)なり。此神日(ひ)の御像(みかた)を作る。今の伊勢の大神是(日の御像)なり。右座は伊多神即ち石凝姥(いしこりどめ)なり。此神日像の鏡を作る。今の紀伊国日前(ひのくま)神社是なり。」
『古語拾遺』に、石凝姥の神に、天の香山の銅(かね)をとらせて、「日の像(みかた)の鏡」を鋳らせた、という記事がある。また、『日本書紀』の一書(ひとふみ)の第一に、「(天照大神の)象(みかた)を図(あらわ)し造りて」とある。
このように日の像(みかた)の鏡が日像幢と関係しているのではないか、日像幢が鏡の模様に入っていると考えられる。
・「天王日月」銘
わが国で前方後円墳が作られ、三角縁神獣教が埋納された時代、すなわち、崇神天皇~景行天皇のころ、中国の華南に、東晋(317~420)が存在した。
このころ、華北は、ほぼ、五胡十六国の時代であった。
ここで注目すべきことは、五胡十六国では、「天王」号がさかんに用いられていた。
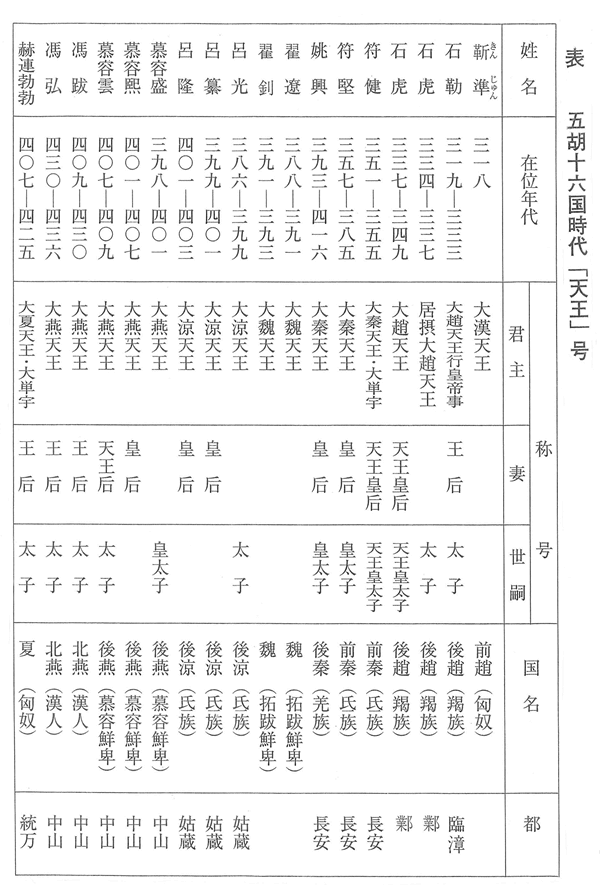
さて、「天皇」のことを、「天王」とも記したことは、古く『日本書紀』に見える。
すなわち、「雄略天皇紀」につぎのような文がある。
①「百済新撰(くだらしんせん)に云はく、辛丑年(かのとのうしのとし)に、蓋歯王(かふろわう)(在位455~475)、弟(いろど)昆支君(こにききし)を遣(まだ)して、天王(すめらみこと)に侍(つかへまつ)らしむ。」(五年七月条)
②「二十三年の夏四月(うづき)に、百済の文斤王(もんこんわう)(在位四七九)、薨(みう)せぬ。天王(すめらみこと)、昆支王(こんきわう)の五(いつとり)の子の中に、第二末多王(ふたりにあたるまたわう)の、幼年(わか)くして聡明(さと)きを以て、勅(みことのり)して内裏(おほうち)に喚(め)す。」
いずれも、対外関係記事のなかにあらわれる。『百済新撰』などは、現在は、ほろびて存在しない。
『日本書紀』にのみ引用されている。
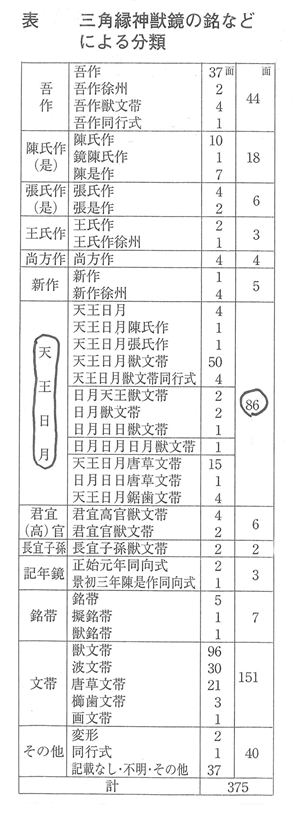
考古学者原田大六氏の考察
ここで思い出されるのは、考古学者原田大六氏(1917~1985)の、つぎのような発言である。
「『天王日月』の銘をもつ三角縁神獣鏡の背面にレリーフされている神像が、天帝である日月をあらわしているということは、東京国立博物館の原田淑人(よしと)(1885~1915)が早く説いているところである(「漢画象石に見ゆる怪物の意義に就いて」『考古学雑誌』五ノ一二 1915)。
福岡県沖ノ島祭祀遺跡や、山口県都濃(つの)郡宮州から出土している三角縁神獣鏡は、いうところの同笵鏡(どうはんきょう)である。この鏡にも『天王日月』の銘があるが、原田淑人の説をみごとに裏付けする構図からなっている。
その鏡の銘文『日月』の『日』は玄武(北)の方向に彫られた有翼の神獣に近く、『月』は朱雀(南)の方向に彫られた。これも有翼の神像側に近く書かれているだけでなく、 両神像と脇侍(きょうじ)との中間に描かれている笠松の下には、『日』の方向に烏、『月』の方向に『ひきがえる』を配している。
出土地は不明であるが、呉の天紀二年(278)の銘のある重列式神獣鏡の上方に三本脚の烏と『ひきがえる』がそれぞれ円環の中に描かれているのがある。また、これは高句麗の壁画古墳にも見られるものであって、三本脚の烏が『日』を、『ひきがえる』が『月』をあらわしているのは御存知であろう。また、『日月』という場合には、『日』は『月』の上位に立つものであるから、『日』は天子の御坐の方向である北に、『月』は南に坐しているのも争われない。
もちろん、烏側か日神、ひきがえる側か月神をあらわしている。天王といい日神月神といい、日本神話との関係を考えて、三角縁神獣鏡をすべて日本製でないかと考える人が出ただけに、どうも日本古代史とは切り離して考えられない問題を抱えている。」(『邪馬台国論争上』三一書房、1975年刊)
中国の神話では、太陽のなかにカラスがいるとされ、月のなかにヒキガエルがいるとされている。
小林行雄氏(京都大学・考古学者)
「(三角縁神獣鏡のなかには、)〈天王日月〉という四字句を、数力所くりかえしてあらわしたものがある。天王といい、日月といえば、日神月神を祖先とする天皇が統治者になるという、日本の神話に関係がありそうである。」(『古鏡』)
三角縁神獣鏡の「天王日月」が多いのはこのようなことが関係しているのかもしれない。
三角縁神獣鏡の銘などによる分類では「天王日月」86/375=23%で「文帯」の40%に続いて2番目に多い。
・笠松模様
「元日および即位には、宝幢をかまえ建てる。鳥像幢を建て、左に日像幢。右に月像幢。」
また、『文安御即位調度図』は、有職故実書(ゆそくこじつしょ)(礼式などの古来のきまりを述べた本)である。
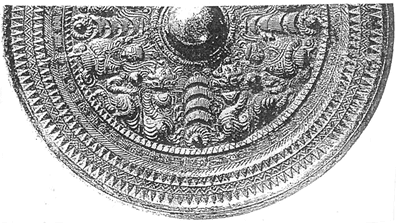 文安は、1444年~1449年の年号である。『文安御即位調度図』では、日像幢、月像幢などの大きさ、材質、色などについて、さらにくわしくのべている。
文安は、1444年~1449年の年号である。『文安御即位調度図』では、日像幢、月像幢などの大きさ、材質、色などについて、さらにくわしくのべている。
元宮崎公立大学教授の奥野正男氏はのべている。
「幢幡紋は、日本の考古学界では『傘松形図形』とよばれてきたものである。また、人によっては『松笠文様』などともよんでいる。この種の図形が三角縁神獣鏡のように内区主紋の神像や獣形の間に一個から五個にわたって配置されている例は、中国出土鏡のどの鏡式にも見ることができない。」
「日本にのみ出土する三角縁神獣鏡という鏡式にだけ狂い咲きのように盛行する事実の社会的契機もまた考えなければならない。」(『邪馬台国の鏡』新人物往来社刊)
三角縁神獣鏡の「笠松」は、日像幢や月像幢を描いたものであることを示しているのではないか。
奥野正男氏は、「笠松」文様は、卑弥呼に与えられた「黄幢(こうどう)」を描いたものであろうとする。
・黄幢について
「幢」は、中国で刊行されている『漢語大詞典』を引くと、つぎのようにある。
「一種の旌旗(せいき)[はた、のぼり]。垂れた筒形。飾として、羽毛がある。綿の繍(ぬいとり)がある。古代ではつねに、軍事の指揮、儀杖の行列、舞踏(ぶとう)の演じられるときに使用された。」(原文は、中国文)
なぜ、「黄色い」幢(はた)なのか
『魏志倭人伝』によれば、魏の皇帝は、倭国に、「黄幢」を与えた。
なぜ、「黄色い」幢を与えたのであろうか。
これも、いくつもの可能性が考えられる。
①三国時代、魏の国の帝位を、「黄祚(こうそ)」といった。魏は、五行思想で、土徳にあたるとされ、黄は、土の色とされた。すなわち、「黄」が、魏の国のシンボルカラーであった。
邪馬台国は、その南方の狗奴国と対立抗争していたので、魏は、「錦の御旗」的なものとして、「黄幢」を与えたと考える。『宋史』に、「幢は、方(くに)の色に随(したがう)う」とある。
なお、漢は火徳で、「赤」が漢の国のシンボルカラーであった。
②「黄」は、天子の服の色であった。「黄蓋(こうがい)」「黄屋(こうおく)」といえば、天子の車のきぬがさであった。「黄蓋」は、皇帝の車駕をもさした。
「黄旗(こうき)」は、天子の旗であった。
「黄麾(こうき)」は、天子ののる車の装飾品であった。『漢書』の顔師古(がんしこ)[唐の学者]の注に、「憧は、麾(き)なり」とある。「黄傘」も、皇帝の儀杖の一つであった。「黄鉞(こうえつ)」は、黄金で飾ったまさかりであるが、天子が征伐に出かけるときのしるしとして用いた。「黄門」は、「宮門」であった。
すなわち、「黄」は、皇帝そのもののシンボルカラーであった。
「黄幢」は、皇帝の権威を示す「錦の御旗」、「威信財」として与えられた。
③「黄幢」といえば、古代中国で、軍中において用いられた旗であった。諸橋轍次編の『大漢和辞典』の「幢」の説明に、「軍の指揮に用いるはた」とある。
『魏志倭人伝』によれば、「黄幢」は、直接的には、女王国の難升米に与えられている。難升米は、魏から、率善中郎将に任命されていた。中郎将は、宮殿警備の武官である。「黄幢」は、将軍旗として与えられたものと考える。諸橋轍次編の『大漢和辞典』に、「幢将(とうしょう)」の説明に、「禁衛の軍隊を統べるもの。幢は、百人の部隊をいう」とあり、「幢主(とうしゅ)」の説明に、「はたかしら」「一軍の司令官」とある。
「黄憧=将軍旗説」は、早稲田大学の教授であった水野祐(みずのゆう)氏が、『評釈魏志倭人伝』(雄山閣出版刊)のなかでのべている。




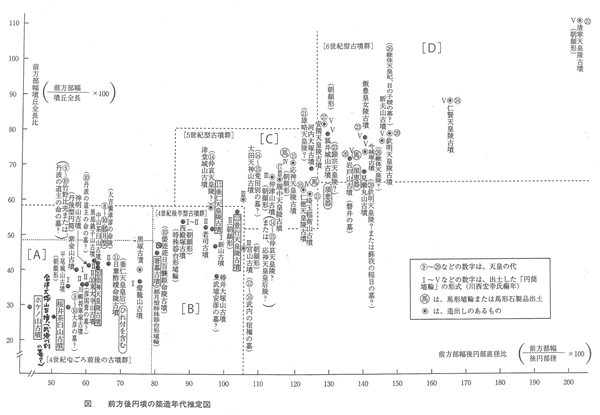
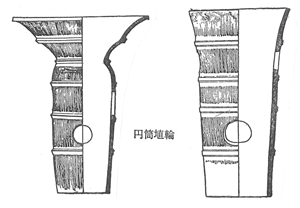
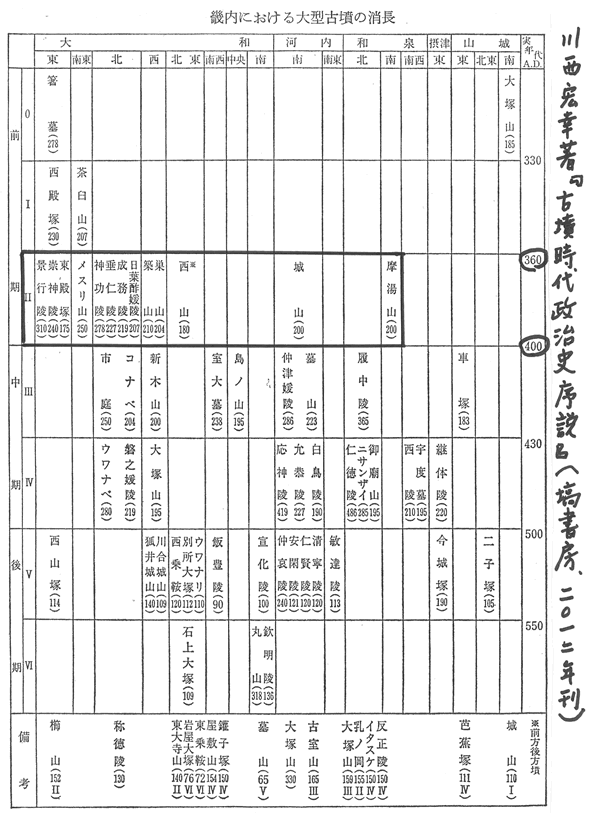
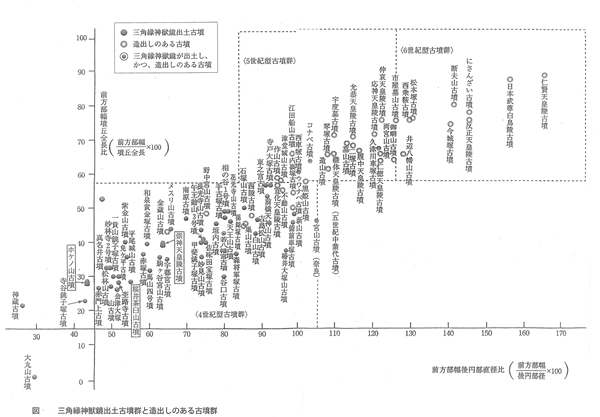
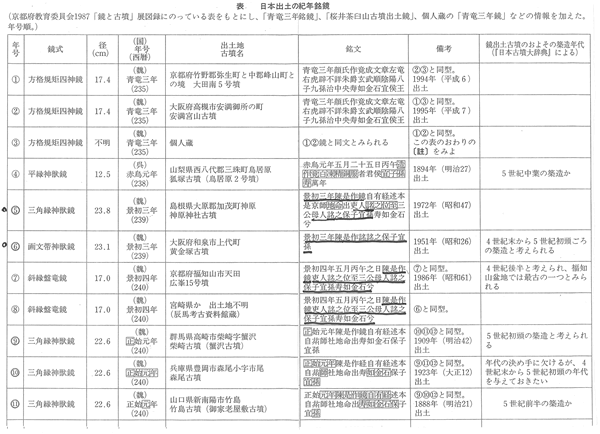
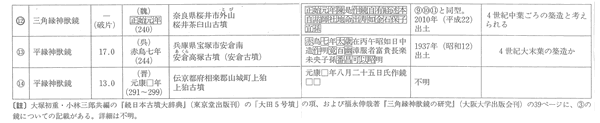
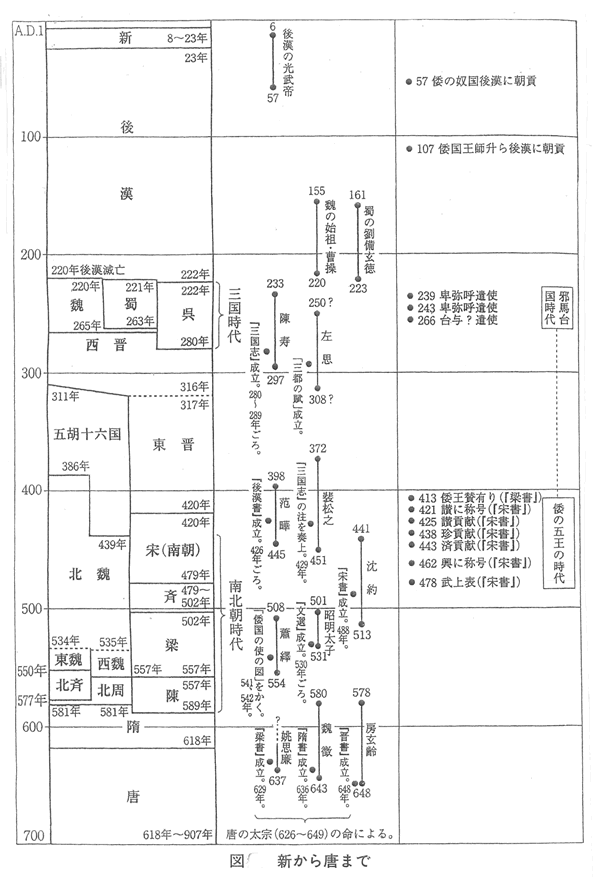
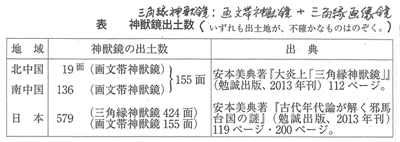
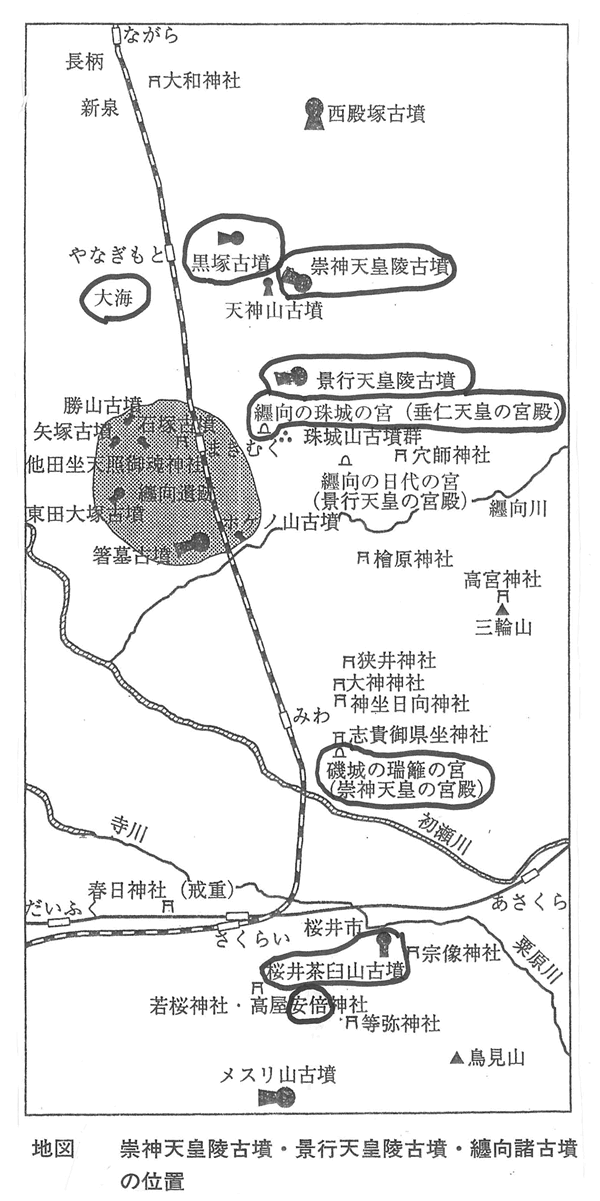
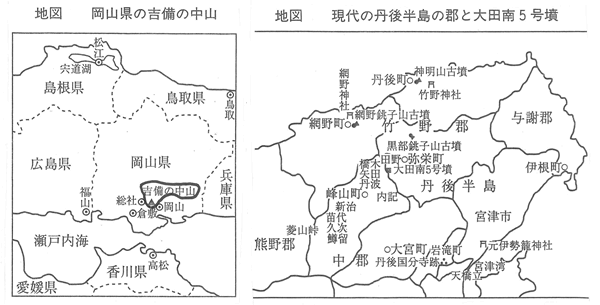
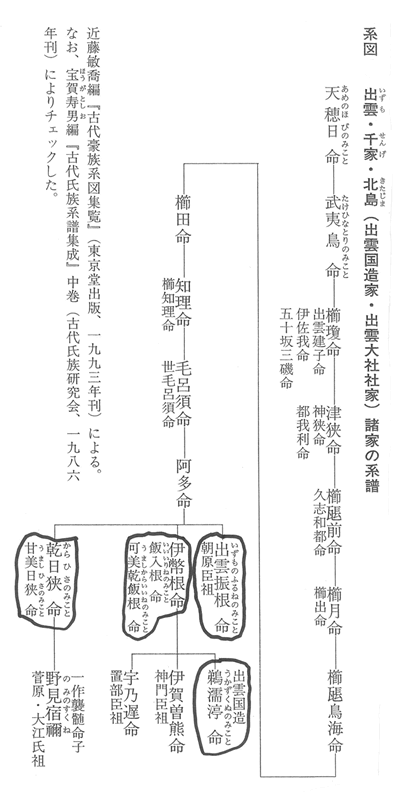
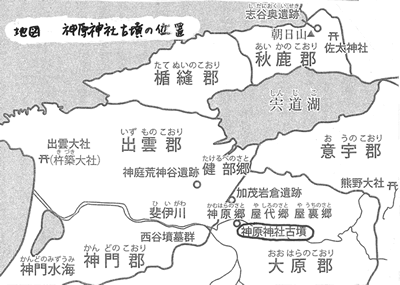 天の穂日の命の何代目の子孫かという点では、文献によって、多少の異同がある。しかし、飯入根の命が、崇神天皇の前後の人であることは、『日本書紀』以外の文献でも、うかがえる。
天の穂日の命の何代目の子孫かという点では、文献によって、多少の異同がある。しかし、飯入根の命が、崇神天皇の前後の人であることは、『日本書紀』以外の文献でも、うかがえる。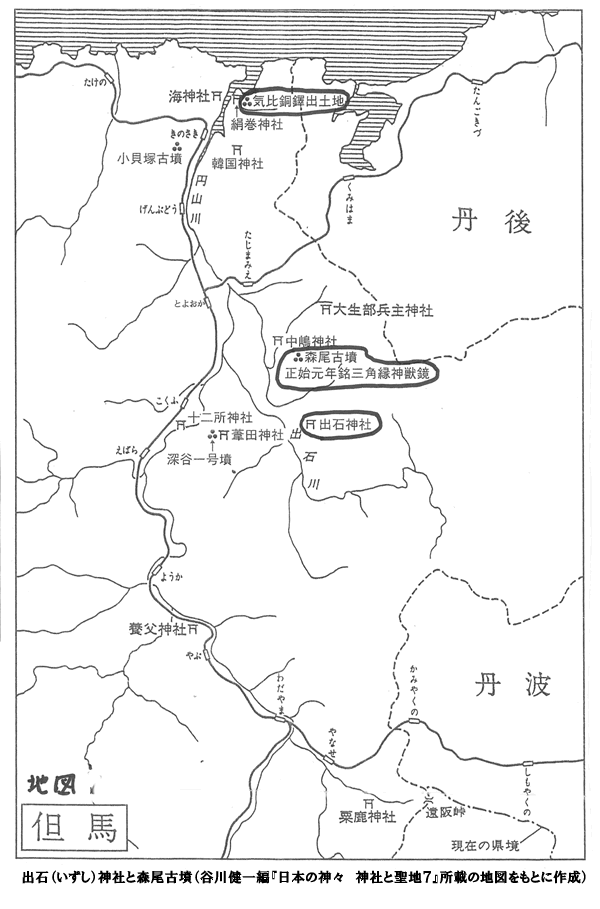
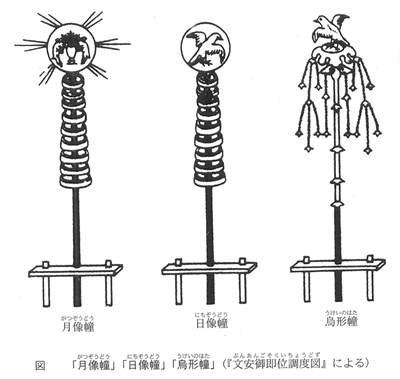 烏形幢
烏形幢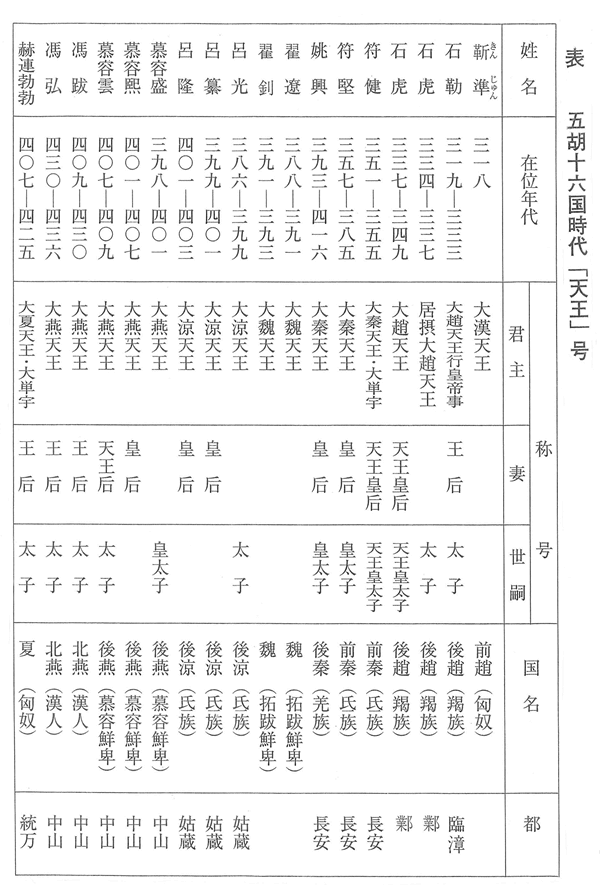
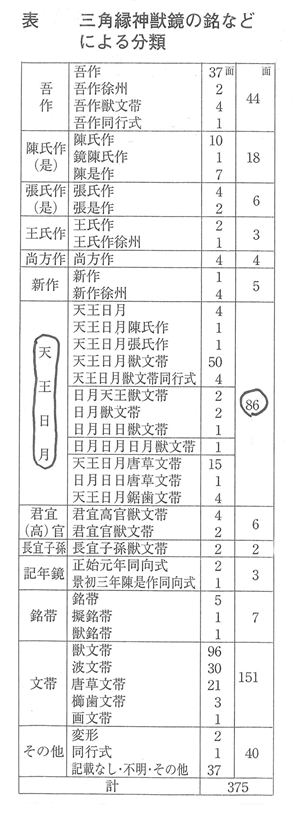
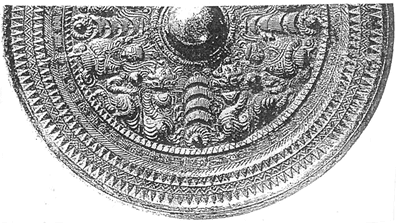 文安は、1444年~1449年の年号である。『文安御即位調度図』では、日像幢、月像幢などの大きさ、材質、色などについて、さらにくわしくのべている。
文安は、1444年~1449年の年号である。『文安御即位調度図』では、日像幢、月像幢などの大きさ、材質、色などについて、さらにくわしくのべている。