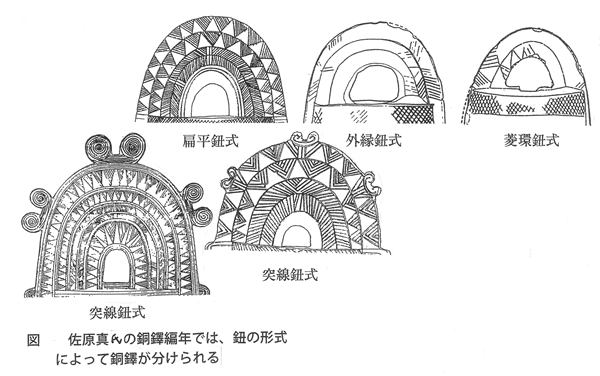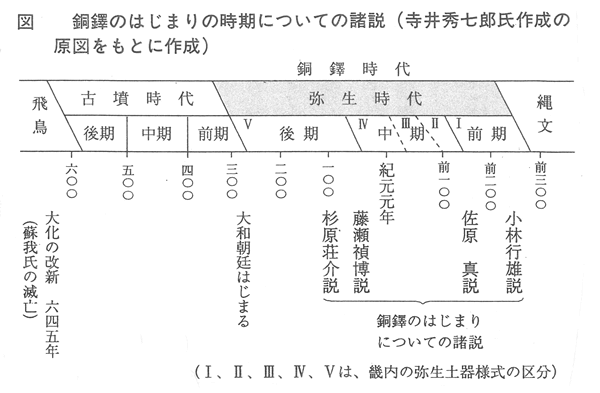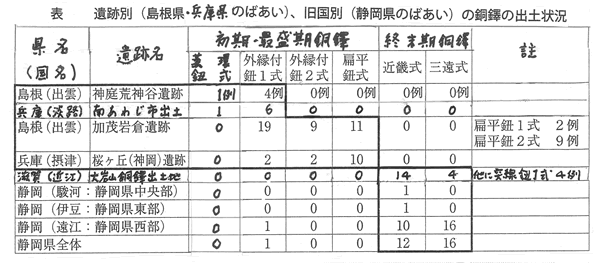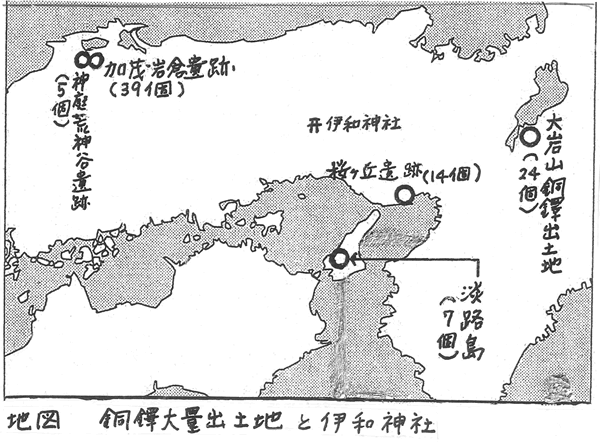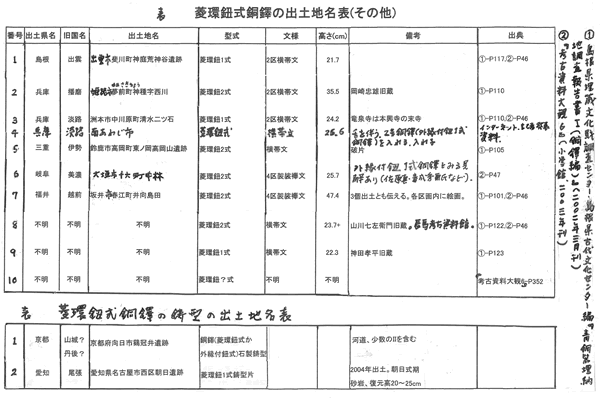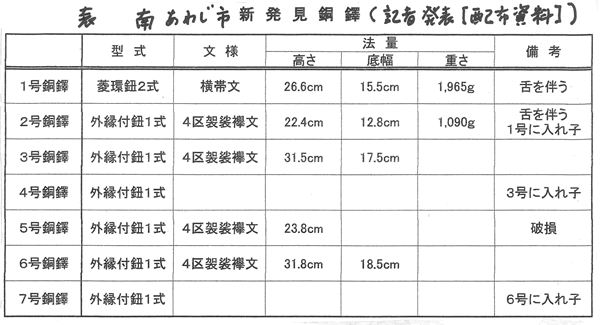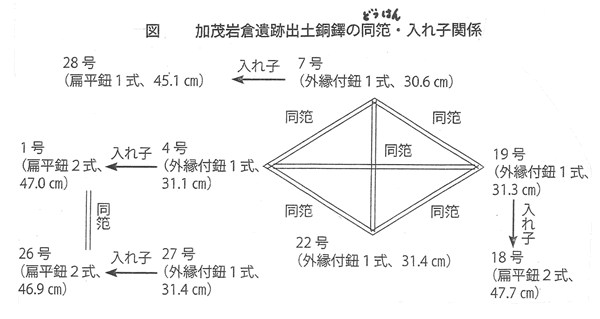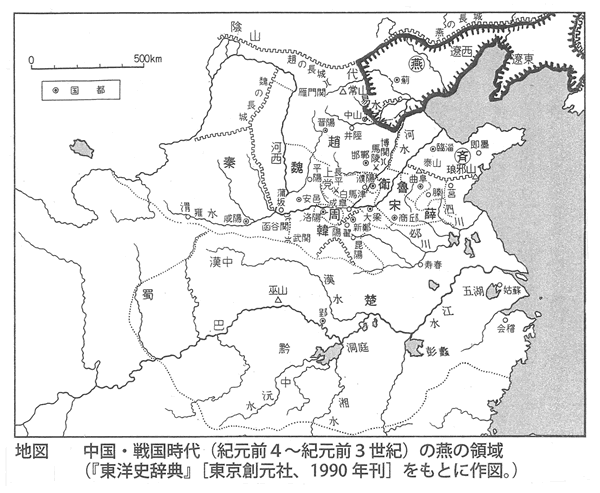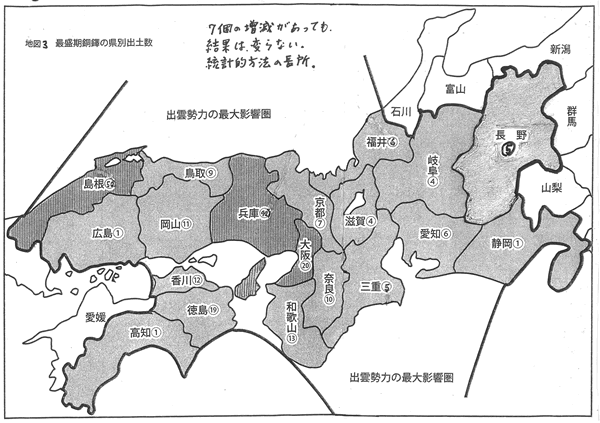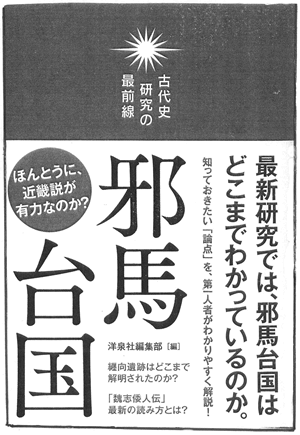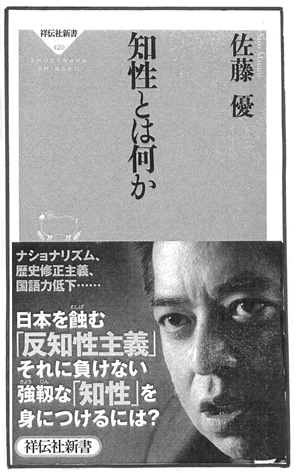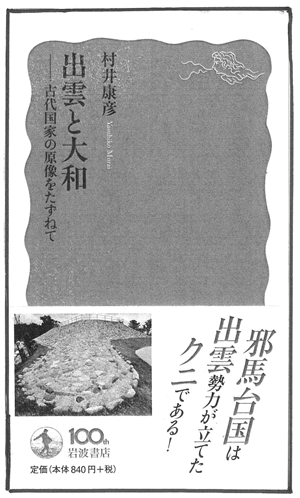| TOP>活動記録>講演会>第340回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第340回 邪馬台国の会(2015.6.28 開催)
| ||||
1.淡路島出土の銅鐸
|
2.中国で新発見の三角縁神獣鏡について再論
|
■今回の「中国で新発見の三角縁神獣鏡について」から感じられること しかし、この鏡の評価は、現在真っ二つに割れているといっていい。一つは出土地がはっきりしないことを認めながらも、今回の「発見」に一定の意味を見いだそうとするものだ。要するに王氏のいう通り、中国から出土したことを前提として考えるなら、三角縁神獣鏡は、やはり中国製の鏡とみていいのではないかとする意見である。 一方、今回の発見を否定的にとらえる見解もある。出土地のはっきりしない資料をもとに議論すること自体意味がないという意見や、日本から持ち込まれたものだとする意見、(まだ実物を見た日本の研究者はいないのだが)、精巧な贋作だとする意見などである。実際、安本美典さんは、この鏡について、明らかな贋作と断じており、講演会や雑誌(注:季刊邪馬台国125号)でその旨を主張している。 この項でも書いてきたように、これまでに三角縁神獣鏡は卑弥呼がもらった鏡だとする説はあっても、それが証明されたわけではない。これを踏まえるなら、今回の「発見」の意義は、せいぜい、三角縁神獣鏡の製作地の候補として中国の洛陽も有力視できるようになった……ということに留まることがわかる。 卑弥呼の鏡については、前に述べた富岡謙蔵の研究以来、考古学者の間では、いわゆる中国の「魏晋鏡(ぎしんきょう)」の中に見いだそうとする説が有力となっている。もちろん、三角縁神獣鏡もその候補の一つだ。 一方、絵画のような文様帯をもった後漢の鏡の中に見いだそうとする意見もある。 また、本書にも執筆している、西川寿勝さんは「卑弥呼がもらったのは宝飾鏡で、三角縁は朝鮮半島の楽浪郡製鏡」であるとの説を唱えでいる。 このように、同じ朝日新聞でも宮代栄一氏は塚本和人氏と違って、バランスをとった発言をしている。
このように、考古学的分野での議論が混乱する理由の一つに、用語や推論の方法の不正確さ、無頓着さがある。用語や推理が不正確であるから、なんでもいえてしまう。みずからの好む任意の結論を導出できる形になっている。その中で生活しているから、不正確さや、無頓着さに気がつかない。 「考古学的発掘による出土」も、「骨董(こっとう)市で出現」も、同じく「発現(発見)」で、同等の証明価値をもつかのように、用語をきちんと定義しないまま議論するのでは、話になりません。
更に、下記の話も参考になる。 第一は、言葉の定義がなされていない、あるいは定義が恣意(しい)的で、しかも論理の整合性が崩れている本だ。よく言えば、「独創的」な内容ということになるのだろうが、こういうテキストを読んでも、知力は向上しない。人生は短い。われわれの持ち時間は限られている。したがって、こういうでたらめなことを書いてある本を読書対象から排除することが必要だ。 第二は、積み重ね方式の知識が必要とされるものだ。例えば、金融工学の専門書を読み解きたいと思っても、偏微分に関する知識がなければ理解できない。高校数学の関数が理解できていない人が、偏微分の教科書を購入しても内容を理解できない。小中学校での四則演算に不安がある人は、高校教科書を理解することができない。 このような積み重ね方式で身につけなくてはならない知識が必要とされる本については、基礎知識が欠けていると理解できない。その場合は、自分に欠損している知識を埋め合わせる勉強をするか、あるいはそのために割く時間とエネルギーがない場合には、「この分野については、自分には理解できない。それだから、信頼できそうな専門家や有識者の意見に頼らざるを得ない」と見切りをつけることになる。」 この意見から、現在の考古学者は反知性主義者が多いように見える。 |
3.卑弥呼について
|
最近ベストセラーとして下記の本がある。 ほんとうに「邪馬台国や卑弥呼の名が『古事記』や『日本書紀』に一度として出てこない」のであろうか? カオス状態のようにもみえる古代史を言語化することによって、脈絡をつけ復元する。そのためには、言語を正確に用いることが必要である。 安本美典『倭人語の解読』(勉誠出版、2003年刊)で下記のように示した。 「呼」の字は、任那(みまな)の地名「下哆呼利県(あるしたこりのあがた)」(『日本書紀』)のような、読み方に、やや不確実性をともなう事例をのぞいては、「こ」をあらわすための万葉仮名として、使用された例がない。 では、「呼」は、「こ」を表記するためには用いられえないのであろうか。そんなことはない。 さて、『日本書紀』の「神代上」の巻に「興台産霊(こごとむすび)」という神名がでてくる。この神名には、「許語等武須 「h音」を「k音」に読めば、「呼」は、「か」か、「こ(甲)」に読める。このように考えれば、「呼」は、たしかに、「コ(甲)」とも読める。 ②姫児(ひめご)説 『播磨国風土記』では、「蚕(かいこ)」のことを、「蚕子(ひみこ)」といっている。「蚕(かいこ)」のことを古語で、たんに「蚕(こ)」ともいうが、養蚕や機織(はたおり)には、女性がたずさわることが多いので、「蚕子(姫子)」といったのであろう。 「姫子」「比咩古」の音は、いずれも、「ひ(甲)め(甲)こ(甲)」であって、「卑弥呼」の音に一致する。「姫子」は、古典にあらわれるひとつの熟語として、「卑弥呼」と完全に一致する。「卑弥呼」が、「姫子」であるとすれば、「姫」という語に、愛称または尊敬の「子」がついたものであろう。 「卑弥呼」を「ヒメコ」と読む説は、東京大学の教授であった日本史家、坂本太郎が、論文「『魏志』『倭人伝』雑考」 (古代史談話会編『邪馬台国』1954年9月刊のなかで説いている。 (ⅰ)等已弥居加斯夜比弥乃弥己等(とよみけかしやひめのみこと)(元興寺塔露盤銘、元興寺縁起) などのように、『古事記』以前の表記法を伝えるとみられるもののなかに、「甲類のメ」をあらわすために用いられている例がある(文例は、坂本太郎の列挙による)。このような事例をみると、「姫(ひめ)」は、むかしは、「ひ(甲)み(甲)」といっていたのではないかと疑われるが、そうではないことは、「上宮記」において、「布利比弥命(ふりひめのみこと)」を「布利比売命(ふりひめのみこと)」とも記していることからわかる。「弥」は、あきらかに、「甲類のメ」に読まれているのである。 『万葉集』の167番の歌で、「天照(あまて)らす日女(ひるめ)の尊(みこと)(天照日女之命)」という語のすぐあとに、「高照(たかて)らす日(ひ)の皇子(みこ)(高照日之皇子)」という語がでてくる。「日女」は、「ひめ」とも読める。「卑弥呼」は「日女皇子(ひめみこ)」のような語をうつしたものであろうか。 ③姫(ひめ)の命(みこと)説
「卑弥呼」の意味 『日本書紀』では、「女王」は、 「卑弥呼」は、「ひめこ」と読み、「姫子」あるいは「姫御子」の意味とみられる。 狗奴(くな)国の男王「卑弥弓呼(ひみここ)」は、「卑弓弥呼」の書き誤りと考えて、「彦御子(ひこみこ)」のこととする説がある。「卑弓弥呼」と記すべきところを、すぐ上に、「卑弥呼」の名があらわれるので、それにひかれて、「卑弥弓呼」と記したのであると考える。 もし、そうであるとすれば、『魏志倭人伝』の、 「倭(やまと)の女王(ひめみこ)、卑弥呼(ひめこ)、狗奴国(くなのくに)の男王(ひこみこ)、卑弓弥呼(ひこみこ)と素(もと)より和(あまな)はず。」 すなわち、「卑弥呼(ひめこ)」「卑弓弥呼(ひこみこ)は、そのまえの、「女王」「男王」という漢語の「大和(やまと)ことば」を、万葉仮名風に表記しただけのこととなる。 この可能性は、かなり大きいように思える。 のちの時代の話であるが、つぎのような例がある。 魏の人から、「女王」「男王」のことを、なんと言うかとたずねられて、倭人は、「ひめみこ」「ひこみこ」と答え、それを魏人が漢字の音で、表記したものであろうか。 「上表」という句は、『日本書紀』にしばしば用いられており、そこでは、「上表(かみたてまつる)」と読まれている。 なお、「卑弓弥呼(ひこみこ)」の「弓」の字の中国での中古音は、「kɪuŋ」である。 また、『日本書紀』の「神功皇后紀」の、四十七年の条に、「千熊長彦(ちくまながひこ)」という名があらわれ、『日本書紀』の編者は、これを、『百済記』にいう「職麻那那加比跪(ちくまなながひこ)」のことかと、疑っている。 以上から、「彦」は、「ひく」に近い音で発音されたこともあったようである。(乙類の「こ」の音のばあいは、「ひきょ」に近い。) いずれにせよ、「卑弓弥呼」は、「彦御子(ひこみこ)」「男王(ひこみこ)」を表記しているとみられる。
■「音韻」と「音声」 「山」を、男性が発音したばあい、女性が発音したばあい、子どもが発音したばあい、おとなが発音したばあい、それぞれ「音声」は異なる。しかし、同じ「音韻」を発音しているとみられるとき、同じ意味をうけとる。 英語では、「l音」と「r音」とのあいだに、「音韻的区別」がある。同じ「コレクション」でも、「collection(収集)」と「correction(訂正)」とでは、発音も音韻も異なり、意味も異なるとみなされる。 フランス語では、「h音」を、「音韻」としてみとめない。そのため、「hotel」を、「オテル」と発音する。 日本人が、「音声」としては、「l音」も「r音」もだしていても、それによって意味の区別をしない。それと同じように、フランス人は、「音声」としては、「ho音」も「o音」もだしていても、それによって意味の区別をしないのである。 |
| TOP>活動記録>講演会>第340回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |