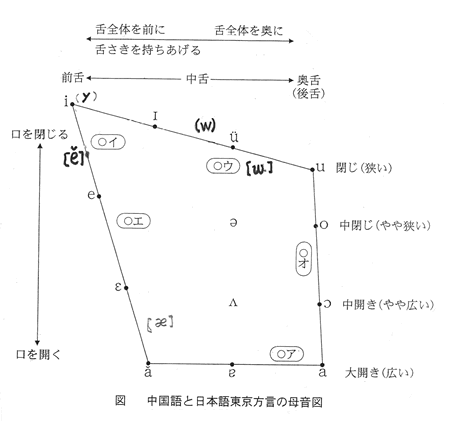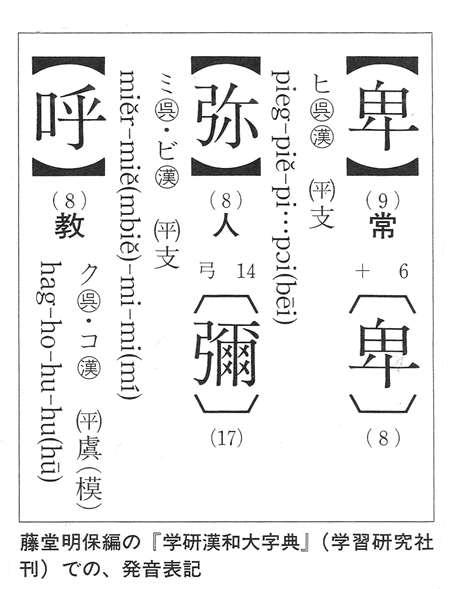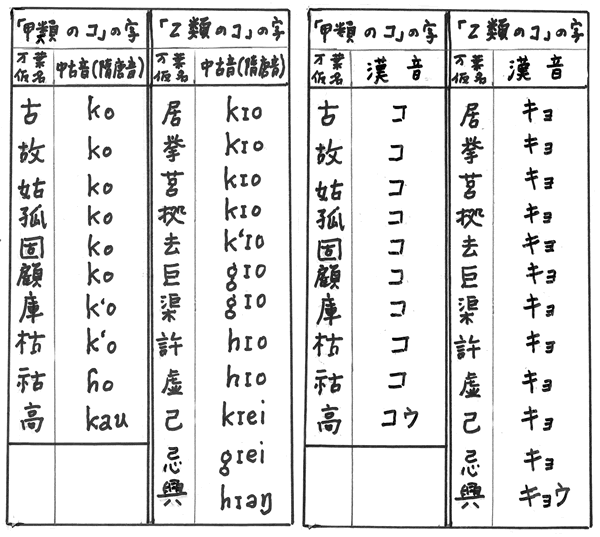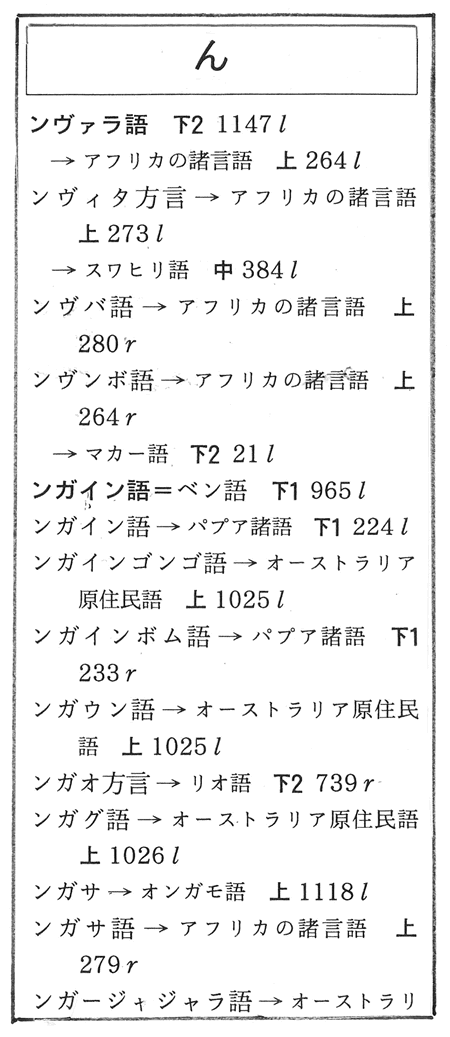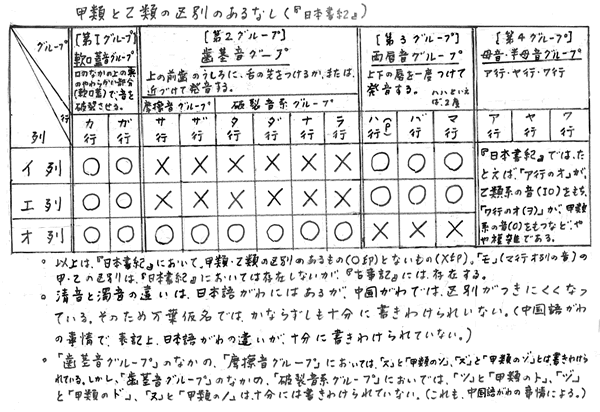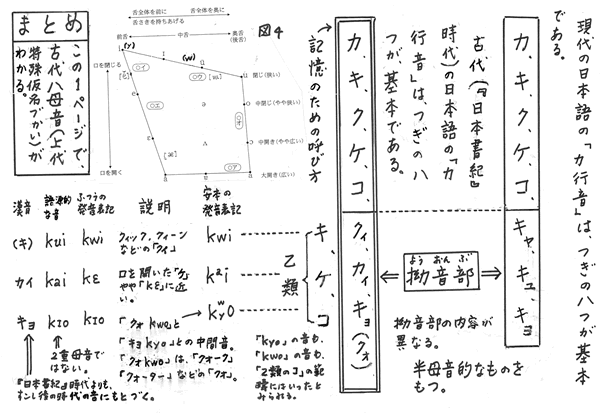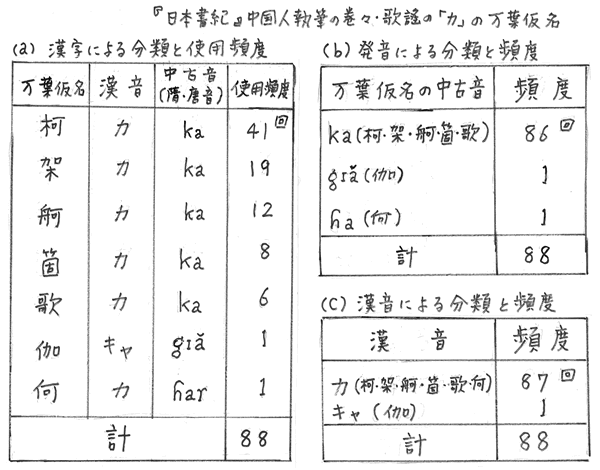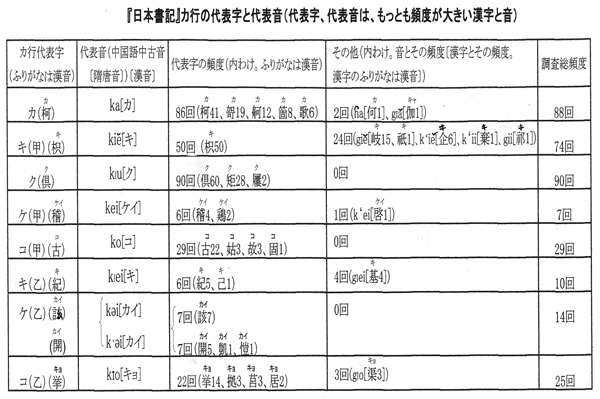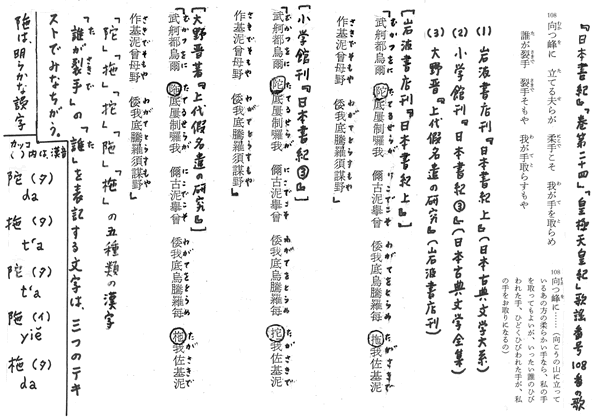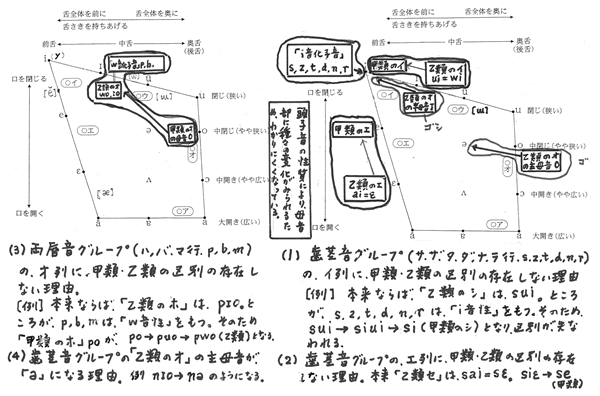■古代八母音
古くは八つも母音があったとされている。このことは国語学者の橋本進吉(はしもとしんきち)氏により指摘されているが、どのように発音されていたかは分からない。詳しく書いた本もない。
『言語学大辞典 第6巻 術語編』(三省堂1996年刊)で、「万葉仮名の使い分けの)具体的な音価の違いは、現在に至るまでなお明らかでない。」とある。
注:橋本進吉(はしもとしんきち)(1882~1945)大正~昭和時代前期の国語学者。明治15年12月24日生まれ。昭和4年東京帝大教授。上代特殊仮名遣いを解明。文法理論(橋本文法)は学校文法の中心となった。国語学会初代会長。昭和20年1月30日死去。64歳。福井県出身。東京帝大卒。著作に「国語音韻の研究」「新文典別記」など。
・上代特殊仮名遣(じょうだいとくしゅかなづかい)
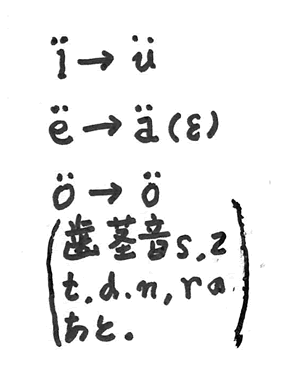 現代の日本語と、今から千二、三百年以上まえ(ほぼ奈良時代以前)の日本語との大きな違いとしては、母音の数の違っていたことがあげられる。この事実は、国語学者の橋本進吉によって指摘され、現在の国語学界では、ひろく認められている。
現代の日本語と、今から千二、三百年以上まえ(ほぼ奈良時代以前)の日本語との大きな違いとしては、母音の数の違っていたことがあげられる。この事実は、国語学者の橋本進吉によって指摘され、現在の国語学界では、ひろく認められている。
現在、私たちは、a、i、u、e、o の五つの母音しか用いない。しかし、むかしは、八つの母音があったと考えられている。すなわち、現在私たちが用いている五つの母音のほかに、i、e、o にウムラウトが付く ï、ë、ö の三つの母音があったと考えられる。
明治時代に日本語の言語学はドイツの影響を受け、ドイツ語的説明がされていたので、ウムラウトが使われた。
ï、ë、ö の発音について、ï の母音はドイツ語の üに近く、ë の母音はドイツ語の ä(є)に近い。また、ö の母音は、s、z、t、d、n、r の後は上の前歯に舌をくっ付けて発音するので、ドイツ語の ö に近い。
注:ウムラウト【Umlaut】はゲルマン語、特にドイツ語で、母音 a・o・u が後続の母音 i(またはe)の影響を受けて音質を ä、ö、ü に変える現象。
当時の人々は、これら八つの音を、それぞれ別の音として、いいわけていたし、聞きわけていたと考えられる。そのため、ひらがなやカタカナが用いられるようになる以前に、日本語を書きあらわすのに用いられていた万葉仮名(漢字)では、書きわけられている。たとえば、カ段の「こ」は、「ひこ(彦)」「こ(子)」などでは「古」の字が使われ、決して「許」の字は用いられない。そして、「こころ(心)」「ところ(所)」などでは「許」「挙」「拠」などの字が使われ、決して「古」の字は混用されていない。
ここに示した「こ」の音の例のような、用いられた漢字の別で示される音の違いは、今日、甲類、乙類と名づけて区別されている。
これを、「上代特殊仮名遣」における甲類、乙類の別という。
甲類、乙類の区別のあるのは、五十音図のすべてについてではない。「き」「け」「こ」「そ」「と」「の」「ひ」「へ」「み」「め」「も」「よ」「ろ」の十三についてである(「も」の区別のあるのは、『古事記』だけ)。
なお、上代においては、ア行の「え」と、ヤ行の「え」、ワ行の「ゑ」も、別の音として区別されていた。
甲類のアイウエオは東京方言のアイウエオとほぼ同じ発音をする。
乙類の母音について、橋本進吉氏の説が参考になる。(安本説と違うところもある)
・i、e、o の母音について、橋本進吉氏説は下記である。
イ列甲類 -i
乙類 -ïi(ï は中舌母音)
エ列甲類 -e
乙類 -Əiまたは-ᴂ(Əは英語にあるような中舌母音)[安本説は ä]
オ列甲類 -o
乙類 -ö[安本説はs、z、t、d、n、r の後のみ成立]
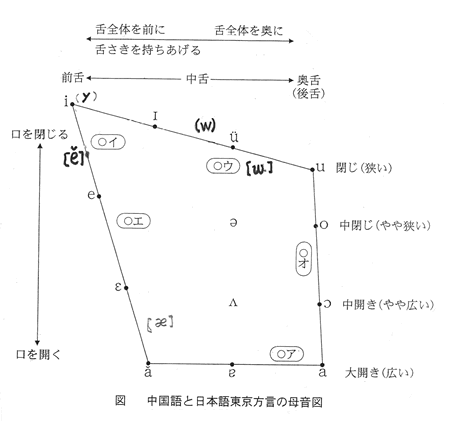
・口の閉じ方と、舌の位置から、母音の発音に種類があり、
中国語と日本語東京方言の母音図が参考になる。(右図参照)
楕円で囲ったものが東京方言の「アイウエオ」である。
東京方言では5つの母音しかないが、このように多くの母音を区別している言語があるということである。
例えば東京方言の「イエア」の発音も「є」「ᴂ」などのような発音があり、発音を区別している言語もあるのである。
・古代の発音が現代人に理解できるかの疑問に、下記の万葉集を読むと理解できる。
『万葉集』(巻二)の、133番目の歌に柿本人麻呂(かきのうえのひとまろ)の、つぎのような歌がある。
万葉仮名:
小竹之葉者(ささのはは) 三山毛清尓(みやまもさやに) 乱友(さやげども) 吾者妹思(あれはいもおもふ) 別来礼婆(わかれきぬれば)
現代語訳:
「笹(ささ)の葉は み山(やま)もさやに さやげども 我(あれ)は 妹思(いもおも)ふ 別(わか)れ来(き)ぬれば」(笹の葉は、全山さやさやと、風に吹かれて乱れているが、わたしは、[心を乱さずに]妻のことを思う。別れてきたので)
「ささのはは」は「さ」の音は「ツァ」に近く、「の」は乙類の「の」で、「ナ」に近く発音記号でなければ表せない。「は」は「パ」に近い。その結果、「ツァツァナパパ」と聞こえ、古代人の発音を現代人が聞いても分かりにくい。
・発音記号による発音
ある文字の発音を説明するのに、反切(はんせつ)というものがある。
反切(はんせつ)は中国で、漢字音を示すのに、他の漢字二字を借りてする法。すなわち上の字(父字または音字)の頭子音と、下の字(母字または韻字)の韻とを合せて一音を構成するものである。
例えば、「東」の字音を「都籠切」という形で示し、「都」の頭音[t]と「籠」の韻[oŋ]とによって[toŋ]を表す類。
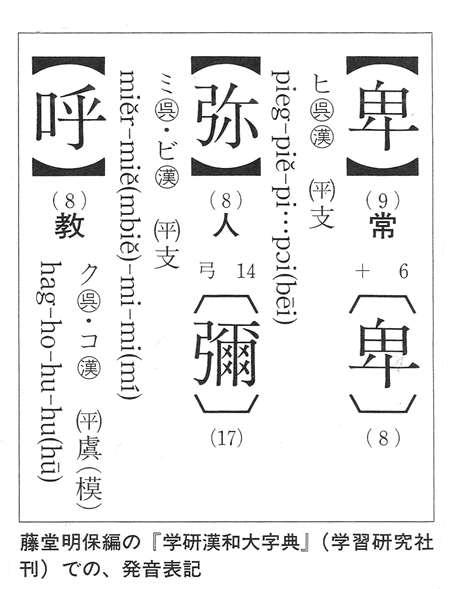
しかし、漢字の発音を説明するのに、漢字を使っているので、上の例でも、「東」の発音を説明する「都」の発音はどうするのか?これでは、すべての発音を説明することができない。
ところが、藤堂明保編の『学研漢和大字典』(学習研究社刊)での、発音表記がある。この『字典』では、そこにのせられているすべての漢字について、中国での上古音(周・秦音)、中古音(隋・唐音)、『中原音韻』(元音)、北京語(および、北京式ローマ字)が、発音記号で示されている。この『字典』は、倭人語解明の大きな手がかりを与えている。
例は右図の卑弥呼の発音が発音記号で表せている。
「呼」の発音について、「h」は日本になかったので、「k」の音に聞こえる。
・万葉仮名(まんようがな)による表記
万葉仮名は日本語を表記するために、漢字の音または訓を借り用いた文字である。
例えば、余能奈何波(世の中は)、羽計(はばかる)、二八十一(にくく)など。奈良時代以前から行われて記紀にも用いられたが、「万葉集」の中で多く用いられたためにこの名がある。真がな、まんにょうがな、ともいう。
・甲類と乙類の母音
例えば、「コ」の発音も甲類と、乙類では万葉仮名の漢字の使い方ではっきり区別している。
「甲類のコ」と「乙類のコ」との違いは、発音の違いである。表記形式、表記習慣の違いではない。
隋唐音である中古音の場合の発音記号に示したものと、唐代の長安音である漢音の場合カタカナで示したものは下記である。(カ行の場合は発音が一致する)
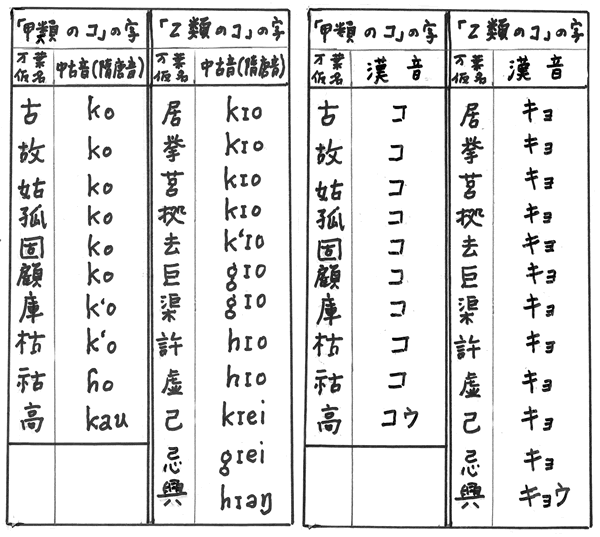
注:漢音(かんおん)[広辞苑による]
日本漢字音のひとつ。唐代、長安(今の西安)地方で用いた標準的な発音を写したもの。遣唐使・留学生・音博士などによって奈良時代・平安初期に輸入された。「行」をカウ、「日」をジツとする類。官府・学者は漢音を、仏家は呉音を用いることが多かった。漢の時代の発音ではない。
■乙類の母音についての通則
・乙類の「メ」「ヘ」「ベ」「ケ」「ゲ」の音価
通則1
「天」は、「あま」と読むこともあり、「あめ」と読むこともある。「目」は、「ま」と読むこともあり、「め」と読むこともある。
「爪」は「つま」と読むこともあり、「つめ」と読むこともある。
このように、同じ意味内容の単語に、「ま」も用いられ、「め」も用いられるようなことがあるばあい、その「め」は原則的に、「乙類のメ」である。
同じように、「酒(さけ)」は「さけ」と読むこともあり、「さか」と読むこともある。「酒杯(さかずき)」「酒家(さかや)」「酒盛(さかも)り」・・・など、熟語的な表現のなかである。その「け」は原則的に、「乙類のケ」である。また、「菅(すげ)」は「すが」ともいう。その「げ」は原則的に、「乙類のゲ」である。
通則2
「天(あま)」「目(ま)」「爪(つま)」などは、より古い時代の単語とみられ、原則的に、熟語的表現のなかで用いられる。単独で用いられるばあいは、「天(あめ)」「目(め)」「爪(つめ)」となる。「一寸の虫にも、五分の魂」「一寸さきは闇」などの熟語的表現のなかでは「一寸」「五分」などの古い尺貫法による表現が遺存する。熟語などでは、古い表現が残りやすい。
「まなこ(目の子、の意味)」「まなじり[目の後(しり)、の意味]」「まつげ[目(ま)つ毛、の意味]」「まぶた[目蓋(まぶた)の意味]などの熟語のなかでは、「目」は、「ま」である。
「守(まも)る」は、もともと、「目守(まも)る」で、じっと目を離さずにいる意味であった。「まのあたり」「まみ(目もと)」「まなかひ(目と目のあいだ)」「まかつ[目(ま)勝つ、気遅れせずにらみつける]」「まぐはし(見て美しくおもう)」「まなしかたま(無目籠。すきまのない竹籠)」など、熟語のなかで用いられている「目」は多い。広島県あたりで、「まゆげ」のことを、「まひげ」というが、あるいは、語源を伝えているのかもしれない。
「天」も、「あまくだる(天降る)」「たか(あ)まのはら(高天の原)」「あまぐも(天雲)」「あまつかみ(天つ神)」「あまざかる」「あまてらすおほみかみ(天照大御神)」など、熟語的表現のなかでは、「天(あま)」となる。
「爪(つめ)」の「メ」も乙類である。そして、「爪先(つまさき)」「つまだつ(佇つ、爪立つ)」「つまづく(爪突く)」「爪(つま)びく(爪引く)」「爪(つま)はじき」「爪櫛(つまぐし)」「爪木(つまぎ)(爪で折れる小枝)」など、熟語的な表現のなかでは「爪(つま)」となる。
通則3
『日本書紀』のなかの、中国からきた人たちが編集したとみられる巻々のなかの、「歌謡」を表記した万葉仮名においては、つぎのような規則性が認められる。
「『乙類のメ』を表記するための万葉仮名として用いられている漢字の『漢音』は『梅』『毎』など『バイ(マイ)』系統の音である。『甲類のメ』を表記するための万葉仮名といて用いられている漢字の『漢音』は『謎』のような『ベイ(メイ)』系統の音である。」
以上の三つの通則から、「乙類のメ」は古く「マ」の音にさかのぼることができ、「マイ」と親近性をもつ音であったとみられる。
なぜ、このような通則が成立するのであろうか。
それは、つぎのような理由によるとみられる。
たとえば、「目」にあたる日本語は、古くは「ま(ma)」であった。そこに、いつのころからか、「i」の音が付加され「mai」の音になった。
この「mai」の音が、乙類の「メ」の原形である。奈良時代の「乙類のメ」の音価は、本来は「mai」いう二重母音に近いとみられる。
国語学者・大野晋著『日本語の文法を考える』(岩波新書、岩波書店1978年刊)が次のように述べている。
「エ列乙類はどのようにして出現するかを考えてみる。たとえば『歎(なげ)き』という動詞がある。これは『長息(ながいき)』つまり長い息をすることで、これがつまると nagaiki→nagëki という変化を起す。そして『歎き』が成立した。ナゲキのゲはゲの乙類である。また、高市皇子(たけちのみこ)という人がいたが、これは高市(たかいち)→高市(たけち) takaiti→takëti という変化によって生じた。この二つに共通に ai→ë という変化が見える。すると。ai からエ列乙類の ë が出てくることが分る。」
・乙類の「ミ」「ヒ」「ビ」「キ」「ギ」の音価
通則 「神」は、単独で用いられるばあいは、「かみ」と読まれる。しかし、熟語的表現のなかでは、「かむ」と読まれる。たとえば、「神産巣日神(かむむすびのかみ)」「かむがかり」「かむつどひつどふ」「かむながら」「かむなび」「かむなづき」「かむぬし」「かむやらひやらふ」など。
また、「身」は、単独で用いられるばあいは、「み」と読まれる。しかし、熟語的表現のなかでは、「むくろ(身プラス幹(から)の意という]」「むざね(身実。本人、実体の意味)」「むかはり(身代り。人質)」「身狭(むさ)[地名]」などのように、「む」と読まれる。
このように、同じ意味内容の単語に、「む」も用いられ、「み」も用いられるようなことがあるばあい、その「み」は、原則的に、乙類の「ミ」である。「神(かむ)」「身」などは、より古い時代の単語とみられる。
このような通則が成立する理由は、つぎのようなものであろう。
たとえば、「身」にあたる日本語は、古くは、「む(mu)」であった。
そこに、いつのころからか、「i」の音が付加されて、「mui」の音になった。
この「mui」の音が、乙類の「ミ」の原形である。
なぜ、語尾に、「i」がついたか
語源的に、「あま(天、ama)」であった語の末尾に、「i」音がつき、「amai」となり、この「mai」という二重母音から乙類の「メ」が生じた。
語源的に、「かむ(神、kamu)」であった語の末尾に、「i」音がつき、「kamui」となり、この「mui」という二重母音から、乙類の「ミ」が生じた。
ここで、アイヌ語のカムイは日本語からの借用語だが、古い時代の「kamui」の発音時代借用されたものか?
では、なぜ、いくつかの語「ama」や「kamu」の末尾に、「i」音がつくようになったのか。
つぎに、その理由を考えてみよう。
(1)「くぶつつい」[頭椎(くぶつつ)の太刀(たち)のこと]の末尾の「い」は、ふつう、指示強調の助詞とみられている。「い」は体言または体言に準ずる語につき、とくにとりたてて強調する。例をすこしあげてみる。
(a)「母以(ははい)もれども(母が私を守っているけれども)」(『万葉集3393番の歌)
(b)「紀の関守伊(きのせきもりい)とどめてむかも(紀伊の国の関の関守が、私をとどめてしまうだろうか)」(『万葉集』545番)
(c)「君いし無くは(あなたがいなければ)」(「し」は強めの助詞。『万葉集』537番)
これらの用例をみると、名詞のうしろに用いられているが、英語の定冠詞theの用法に、きわめて近い。「ザ・母」「ザ・紀の関守」「ザ・君」といった感じである。
ヨーロッパの言語でも、ルーマニア語では、冠詞は、名詞のうしろにおかれる。「い」は、ルーマニア語の冠詞の用法に近い。このような冠詞は、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語など、北方ゲルマン諸語にもあり、「後置定冠詞」とよばれる。
ヨーロッパの諸言語の定冠詞のほとんどすべては、発生的には、指示代名詞から転化したものである。
いまかりに、日本語の「い」を、「準後置定冠詞イ」とよぶことにしよう。
日本語の「準後置定冠詞イ」も、発生的には、「指示代名詞イ」から来たとみられる。「指示代名詞イ」の用例には、つぎのようなものがある。
(a)「伊(い)が作り仕へまつる大殿(おおとの)[お前がお造り申しあげた大殿]」[「伊(い)」は、あいてをいやしめていう二人称代名詞。この「伊(い)」は、「それ」の意味に近いとみられる。『古事記』「神武天皇紀」]
(b)「噫(あ)、入鹿(いるか)……儞(い)が身命(いのち)、亦(また)殆(あやふ)からずや(ああ、入鹿・・・・お前の生命は、あぶないものだぞ。)」(この儞(い)は、「お前」をさすが、意味は、「儞(い)が身命(いのち)」で、「その命(いのち)」に近い。)(『日本書紀』「皇極天皇紀」二年)
「準後置定冠詞イ」のつぎのような用法も、英語の定冠詞の用法に近い。
(a)「これをたもつ伊(い)は称(ほまれ)をいたし、捨つる伊(い)はそしりを招きつ(これをたもつものは、名誉をえ、捨てるものは、そしりを招いた)」(「これをたもつ」「捨つる」は形容句。英語のばあいも「the poor貧しい人々」「the yong若い人たち」のように、形容詞のまえに定冠詞を付ける。これと同じよう使われるのである。
(b)「青柳の糸の細(くは)しさ春風に乱れぬい間(あいだ)に・・・(青柳の糸のこまやかな美しさよ。春風に乱れてしまわない その 間に・・・・)」(これは、英語で、関係代名詞によってみちびかれる形容文によって修飾される名詞のまえに、定冠詞子theをつける用法によく似ている。)
英語の定冠詞theのばあい、名ざすだけで相手にそれとわかるものに冠する用法がある。「the sun」「the earth」「the sea」など。
日本語の「準後置定冠詞イ」にも、それに近い用法があり、特定の名詞につき、それが乙類の母音をもたらしたのではないかとみられるふしがある。
「the heaven」=「天(あま)イ」→「天(あめ)」
「the god」=「神(かむ)イ」→「神(かみ)」
この立場にたつばあい、「うみ(海)」のように、はじめから「甲類のミ」が用いられているばあい、そこに「準後置定冠詞イ」がついても、「海イ」→「海」となって、形が変わらないものと仮定する。
「準後置定冠詞イ」がついたかとみられる名詞は、あるていどかぎられているようにみえる。ただし、これらの名詞は、古代人の生活に密接で、特別な重要性をもち、使用頻度の比較的多い単語が多い。
つぎに、「準後置定冠詞イ」がついて成立したかとみられるものを分類してみる。
(a)古代人が、なんらかの尊敬をもっていたかとみられる語。
「天(あめ)」「神(かみ)」「上(かみ)[この『み』は甲類]」「上(うえ)」「君(きみ)[この『み』は甲類]」「瓊(に)」「霊(ち)」
(b)木、火、土、金、水
「木(き)」「火(ひ)」「土(つち)」「金(かね)[金(かな)に、準後置定冠詞『イ』がついて、金(かね)になったかとみられる]」「水(み)(この『み』は甲類)」
木、火、土、金、水は、中国の原子論、五行説の五元素。中国的思想が、古代にはいっていたか。『古事記』神話には、木、火、土、金、水のすべてについて、関係する神の名があらわれる。
(c)大きなもの
「天(あめ)」「土(つち)」「海(うみ)」
(d)天然自然
「日(ひ)(この『ひ』は甲類)」「月(つき)」「星(ほし)」「陰(かげ)(光の意味がある)」「雨(あめ)[天(あめ)と同源か]」「風(かぜ)」
(e)身体語
「目(め)」「耳(みみ)(この『み』は甲類)」「口(くち)」「毛(け)」「髪(かみ)(この『み』は甲類)」「胸(むね)」「手(て)[手(た)に、『イ』がついて手(て)になったとみる]」「足(あし)」「爪(つめ)」「身(み)」「乳(ち)」「血(ち)」
(f)食物・植物
「稲(いね)「米(こめ)」「黍(きび)(この『び』は乙類とみられる)」「酒(さけ)」「種子(たね)」
(g)用具
「瓮(へ)」「笥(け)」「樋(ひ)」「船(ふね)」
(h)家
「家(やけ)」「戸(へ)」
(i)その他
「亀(かめ)(うらないに使ったか)」「占(け)」
(2)日本古典文学大系の『万葉集一』に、537番の歌の「君いし無くは」の「い」を説明し、つぎのようにある。
「朝鮮語の主格助詞にも i がある。同源の語と認められる。」
西暦660年に百済がほろびるなどして、多くの渡来人が日本に来て、畿内に多く住んだ。朝鮮語の影響をうけることは、ありうることである。
しかし、日本語の「イ」は、主格を示すとはかぎらない。
目的格の語についているばあいがある。
(3)中国語で、「これ」を意味する語の多くが、「イ」か「シ」の音をもつ。
「伊(これ)」「惟(これ)」・・・・イ
「之(これ)」「此(これ)」「斯(これ)」「是(これ)」「茲(これ)」・・・・シ
など。
そして、日本語でも、「イ」 や「シ」の形の指示代名詞があり、また、「イ」や「シ」の形の、語をとくに強調するための助詞がある。
さきに例をあげた「関守伊(せきもりい)とどめてむかも」は、「関守伊[これ](が)とどめてむかも」と、中国語の意味で理解しても、通じる形になっている。
中国語の影響も、あるのかもしれない。
(4)658年に、阿倍比羅夫(あべのひらぶ)は、蝦夷(えみし)をうった。大和朝廷による蝦夷の征討は、四、五世紀ごろから行なわれたようである。『日本書紀』の「景行天皇紀」に、日本武尊(やまとたけるのみこと)がとりこにした蝦夷を、伊勢や大和に住ませた話がみえる。アイヌ語にも、「それが」「それを」を意味する「i」がある。
また、アイヌ語の「i」には、さまざまな用法があるから、とりこにするなどして、あちこちに移住させたアイヌの人たちの言語の影響もあるかもしれない。
私は、日本語の「準後置定冠詞イ」が、生活においてとくに重要ないくつかの語につくようになったものと考えるのが、いちばん可能性が大きいように思う。
しかし、日本語のまわりの、朝鮮語、中国語、アイヌ語などのすべてが、日本語と意味的に近い「i」という語をもっているから、複合的な要因が働いている可能性もある(ただし、英語で、「それ」を意味する「it」でさえ、「i」音をもつから、どこまでが真に影響をもち、どこまでが偶然の類似なのか、みきわめがたい)。
動詞の接頭語「イ」強調形? 「い及(し)く」([それに]追いつく) 「います」([そこに]おられる) 「いのる」{[それに]宣(の)る} 「いでます」([そこに]おいでになる) 「い行く」([そこに]行く) 「い立つ」([そこに]立つ) 出(で)る→出(い)づ
■上代音探求は、なんの役に立つか?
(1)語源の探求ができる
・飴(あめ)の語源
「飴(あめ)」の「め」は、「乙類のメ」である。
「乙類のメ」は、「mai」の音にさかのぼりうる。
語の最後の「i」音は、後置定冠詞的なものとみられるから、「飴」は、「ama」にさかのぼりうる。
「ama」は、「甘(あま)」とみられる。
「飴」は、「the sweets」の意味で、「甘いもの」ということであろう。
・亀(かめ)の語源
「亀(かめ)」の「め」は、「乙類のメ」である。
「乙類のメ」は、「mai」の音にさかのぼりうる。
したがって、「亀(かめ)」の古代音は、「kamai」とみられる。
語の最後の「i」の音は、後置定冠詞的なものとみられるから、「亀(かめ)」は、「kama」にさかのぼりうる。
この、「かま」は、おそらくは、「竈(かま)・釜(かま)・窯(かま)」と関係するのであろう。むかしの、土器をやくカマや炭焼きガマなどには、「亀」の形に似たものがある。
・月(つき)の語源
「月(つき)」の「き」は、「乙類のキ」である。
「乙類のキ」は、「kui」の音にさかのぼりうる。
語の最後の「i」は、後置定冠詞的なものとみられるから、
「月(つき)」は「tuku」にさかのぼりうる。
「月夜(つくよ)」のような熟語においては、古形がのこり、「つく」と
読まれる。
「つく」は、「尽く」であろう。月の満ち欠けからきているとみられる。
(2)文献や金石文の成立年代を推定できる。
中国において、漢字の音は時代とともに変化している。
したがって、漢字の音を用いて、日本語を表記するのに用いた万葉仮名も、用いる漢字が、時代とともに変化する。そのことを利用すれば、文献や金石文の成立年代を推定できる。
『古事記』の成立年代を、『日本書紀』の成立年代よりもあととする『古事記』偽書説があるが、この説は、おそらく成立しない。
■「音韻」と「音声」との違い
言語学的には、「音韻」と「音声」とは、別ものである。
たとえば、「l(エル)音」と「r(アール)音」とは、音が異なる。しかし、日本語では、「理論」を、「lilon」と発音しようが、「riron」と発音しようが、意味は、異ならない。つまり、日本語では、「l音」と「r音」との、「音韻的区別」はない。「l音」と「r音」は、日本語では、「音声(発音)」は異なっていても、意味の違いをもたらさない。このようなばあい、「l音」と「r音」とは、日本語では、同じ「音韻」とみなされているという。
「山(やま)」を、男性が発音したばあい、女性が発音したばあい、子どもが発音したばあい、おとなが発音したばあい、それぞれ「音声」は異なる。しかし、同じ「音韻」を発音しているとみられるとき、同じ意味をうけとる。
「音韻」は、「音声」よりも、抽象的な概念である。
「音声」はどちらかといえば、物理学的概念である。これに対し、「音韻」は、人間社会で伝統的に成立した「約束ごと」で、言語学的な概念である。
「言語」は、人間の社会で、無意識の「約束ごと」の体系をなしている。どのような音のくみあわせによって、どのような意味をあらわすか、などはある特定の人間社会でとりきめられている「約束」である。
英語では、「l音」と「r音」とのあいだに、「音韻的区別」がある。同じ「コレクション」でも、「collection(収集)」と「correction(訂正)」とでは、発音も音韻も異なり、意味も異なるとみなされる。
英語では、「l音」と「r音」とでは、意味の違いをもたらし、異なる「音韻」である。
どのようなものを、その言語の「音韻」としてみとめるかは、言語ごとに、歴史的・伝統的にきまっている。集団での「約束」であるといえる。言語ごとに、その「約束」の体系、「音韻体系」が異なる。
フランス語では、「h音」を、「音韻」としてみとめない。そのため、「hotel」を、「オテル」と発音する。
つまり、「ho」と「o」とで、「音韻的区別」がないのである。
フランス語に、「h」という音がない、というと、では、フランス人は、笑うとき、「ハハハ(hahaha)」と笑わないのか、などというのは、音声」と「音韻」とを、ごっちゃにした議論である。
フランス人も、笑うときは、「h音」をだしている。しかし、それは、「音声」としてその音をだしているのであって、「音韻」としては、みとめない「約束」にしたがっているのである。
日本人が、「音声」としては、「l音」も「r音」もだしていても、それによって意味の区別をしない。それと同じように、フランス人は、「音声」としては、「ho音」も「o音」もだしていても、それによって意味の区別をしないのである。
「k」「t」「p」などの破裂音のあとに、激しい吐く息の音をともなうか、ともなわないかによって、意味の区別をする言語は多い。
唇のまえに下げた紙がゆれるような、激しい吐く息をともなった音、「kh」「th」「ph」は、「ki」「ti」「pi」などのようにも書かれる。「帯気音」とか、「有気音」とかなどとも呼ばれる。
朝鮮語、中国語、サンスクリット語、ギリシャ語などには、「帯気音」と、そうでない「無気音(強く吐く息の音をともなわない音)」とのあいだに、「音韻的区別」がある。つまり、「帯気音」か、「無気音」かによって、意味の区別をする。
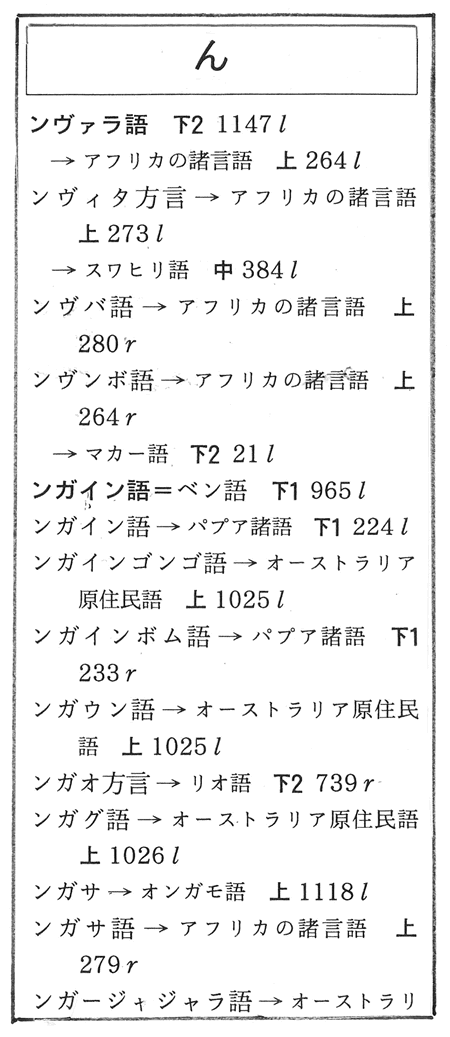
いっぽう、「清音」と「濁音」の「音韻的対立」のない言語もある。
そのような言語では、「カギ(鍵)」と「カキ(柿)」、「マド(窓)」と「マト(的)」などが、同じ音とみなされるのである。個人は、無意識に、自国語の集団的「約束」をうけいれている。そのため、外国語を学ぶときは、一定の意識的学習を必要とする。新しい「約束」の学習を必要とする。そうしないと、「ガラス」と「からす」とが、聞きわけられなかったりする。
外国人は、しばしば、日本語を、自国語の音韻体系のクセをもつ、なまりのある発音で話す。それは、以上のべできたような理由による。
要するに、「音韻」とは、ある言語社会において「意味の区別」をもたらす音の違いである。奈良時代語は、日本語の一種であるが、現代日本語と異なる音韻体系をもっている。奈良時代語を理解するためには、外国語を学ぶのと同じように、一定の、理論的、意識的学習を必要とする。
例えば、日本語にいろいろな特徴がある。
現代の日本語では、濁音が頭に立つが、古代の大和言葉では濁音は頭に立たない。
「どこ」は「いずこ」と言っていた。朝鮮語も同じで、濁音は頭に立たない。
また、「ん」は「先頭に立たない。しかし「ん」が頭に立つ語は沢山ある。(右図参照)
■中国の文字で、日本語を十分表記できない
森博達(もりひろみち)著『日本書紀の謎を解く』(中公新書、中央公論社1999年刊)で、『日本書紀』30巻の中国人執筆と日本人執筆とを分けている。
(下図はクリックすると大きくなります)
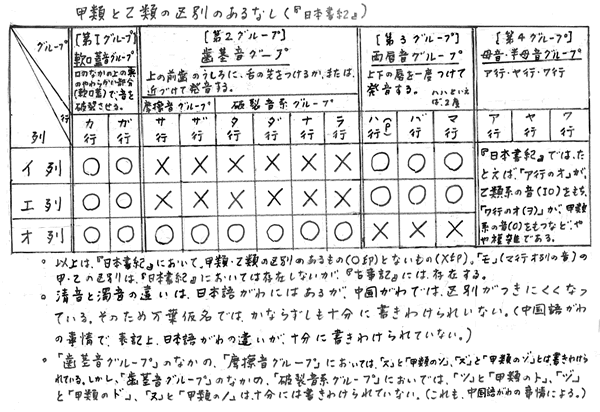
何故このようなことが起きるのか、中国人は日本語の発音が十分に書き分けられなかったのではないか。
以上、古代八母音について説明したことを「カ行」としてまとめて1枚にすると、下記となる。
(下図はクリックすると大きくなります)
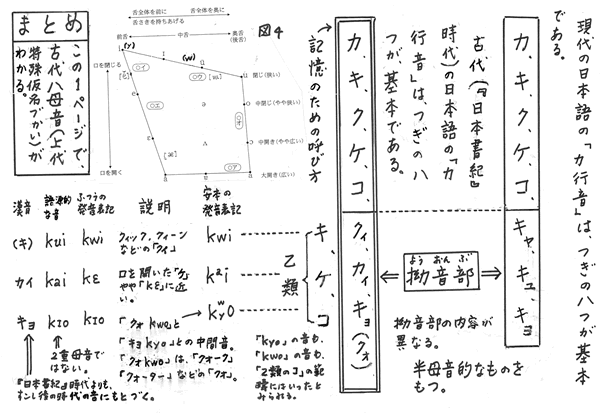
『日本書紀』の中国人執筆の巻々・歌謡の「カ」の万葉仮名について、表にすると下記となる。
万葉仮名の使用頻度があり、これを万葉仮名の中古音(隋唐音)の頻度でみると、「ka」の音の頻度は86回で、[giâ]{伽(きゃ)}が1回と[ɦar]{何(か)}が1回ある。漢音にすると、[ɦar]は「カ」と同じ発音となり、「カ」が87回、「キャ」が1回となる。
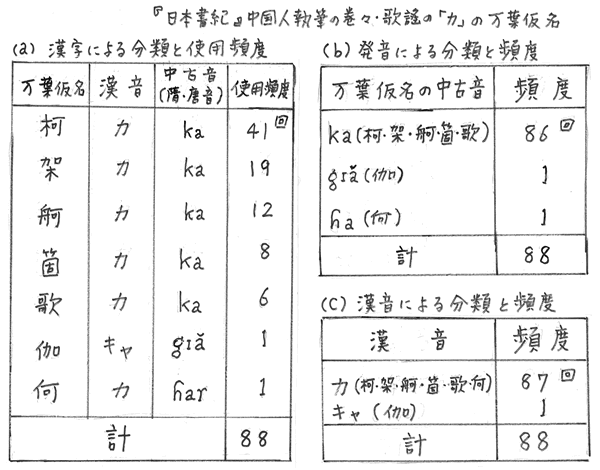
『日本書紀』カ行の代表字と代表音について、まとめると下記となる。
(下図はクリックすると大きくなります)
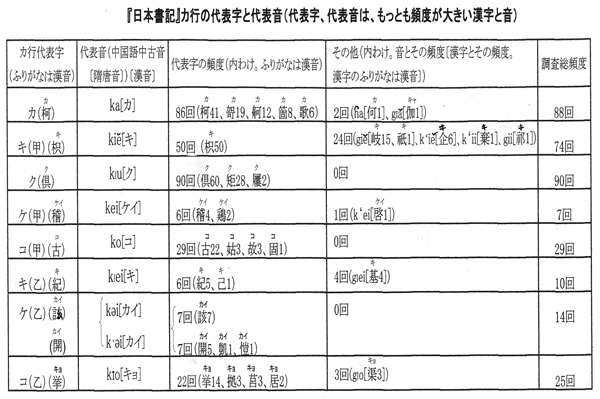
『日本書紀』の「巻第24」「皇極天皇紀」の歌謡番号108番の歌について、万葉仮名で表すにあたり、三つの文献で「た」の漢字を当てはめるのに、「陀」「拖」「拕」「陁」「柂」と異なる漢字を使っている。
『日本書紀』は古い時代に編集された文献であり、多くの写本がある。この写本段階で間違ってきたのではないか。
「陁」は「イ」の発音であり、漢字の発音から明らかに間違っている。
(下図はクリックすると大きくなります)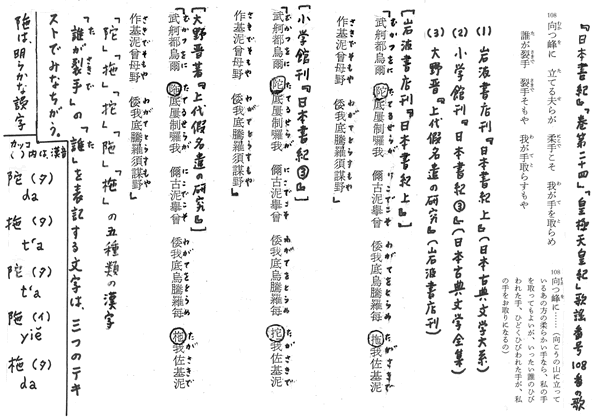
・甲類と乙類と区別がなくなる問題
子音のs、z、t、d、n、rは「i音」を持つため、s、z、t、d、n、r後の乙類の「エ」は
甲類と乙類と区別がなくなる。その他の例も下記に示す。
(下図はクリックすると大きくなります)
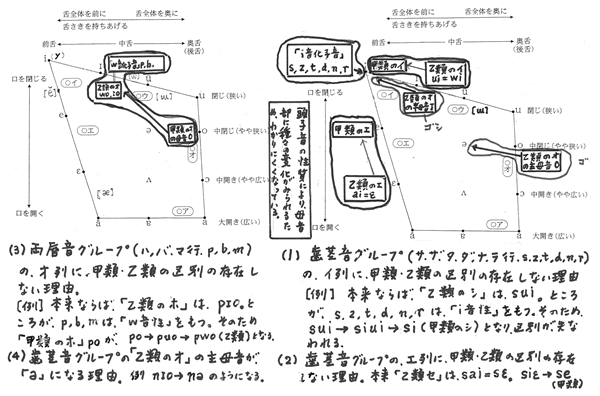




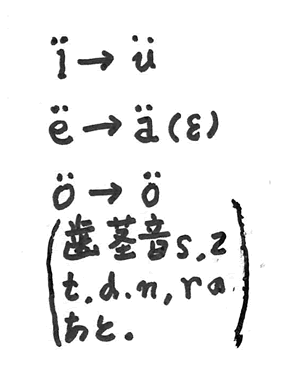 現代の日本語と、今から千二、三百年以上まえ(ほぼ奈良時代以前)の日本語との大きな違いとしては、母音の数の違っていたことがあげられる。この事実は、国語学者の橋本進吉によって指摘され、現在の国語学界では、ひろく認められている。
現代の日本語と、今から千二、三百年以上まえ(ほぼ奈良時代以前)の日本語との大きな違いとしては、母音の数の違っていたことがあげられる。この事実は、国語学者の橋本進吉によって指摘され、現在の国語学界では、ひろく認められている。