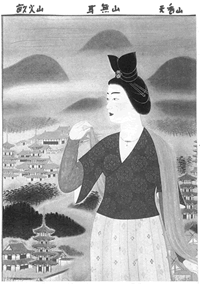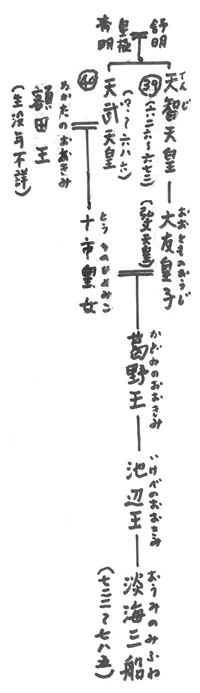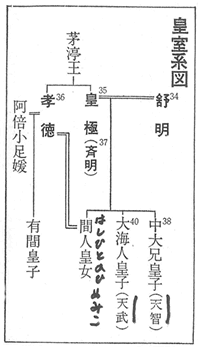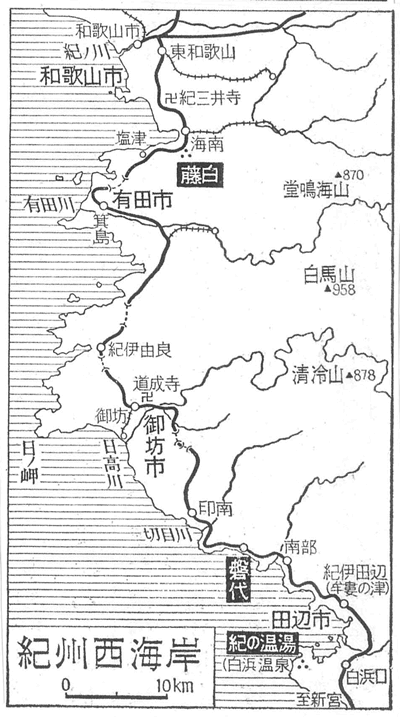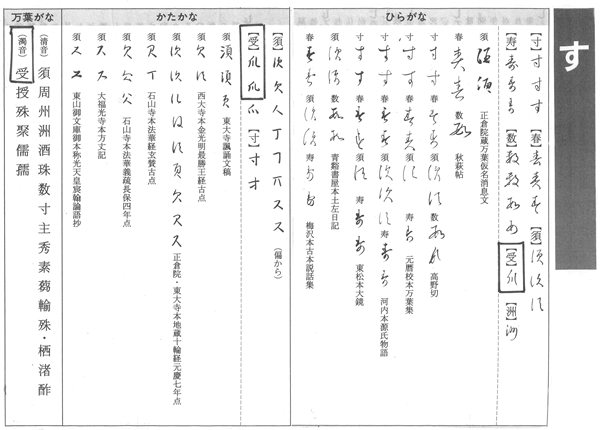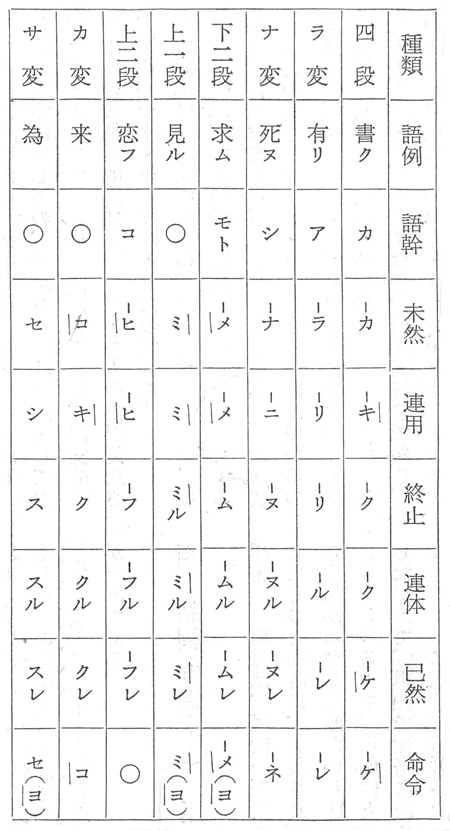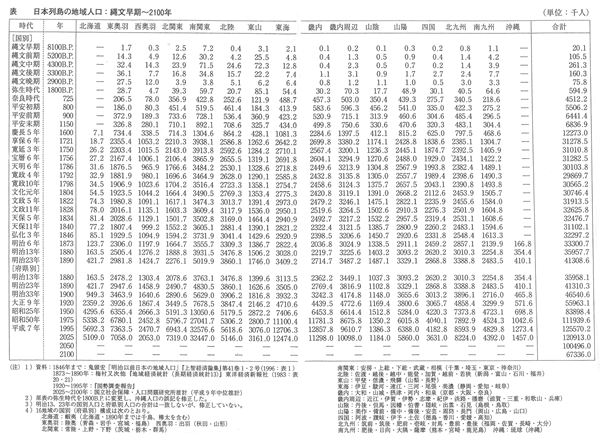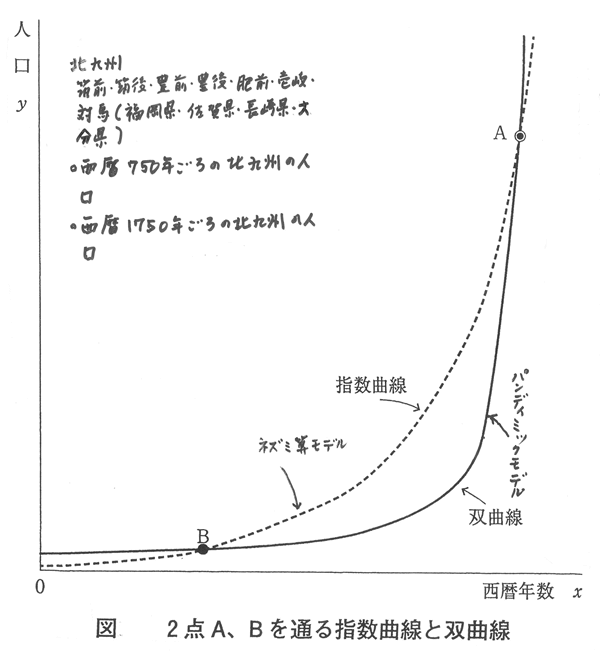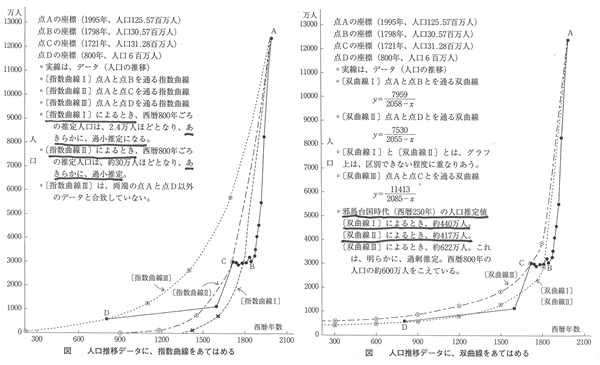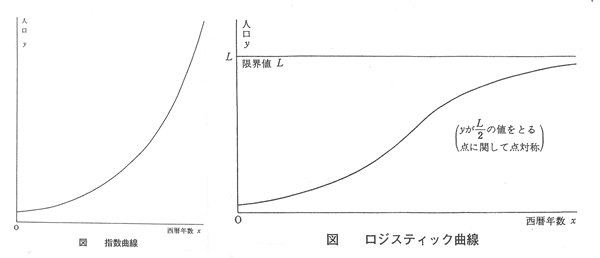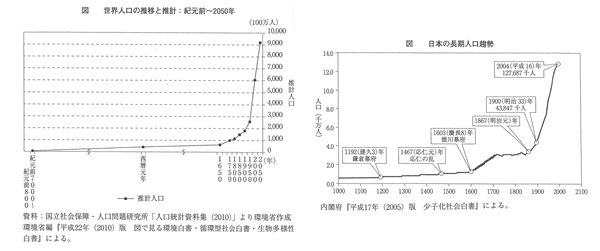■額田王(ぬかたのおおきみ)と難訓歌
額田王(ぬかたのおおきみ)は生没年不詳で飛鳥時代の歌人である。鏡王の娘で、舒明朝(629-641)のなかばごろに生まれる。 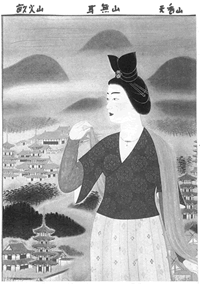
大海人皇子(おおしあまのおおじ)(天武天皇)との間に十市皇女(とおちひめみこ)を生むが、のち大海人皇子の兄の天智天皇の後宮にはいったという。作歌は斉明朝から持統朝までの長期におよび、作品は『万葉集』におさめられている。天皇、皇太子の代作歌もおおい。額田姫王(ひめみこ)ともいう。
額田王の子の十市皇女(とおちひめみこ)の子孫が淡海三船(おうみのみふね)である。 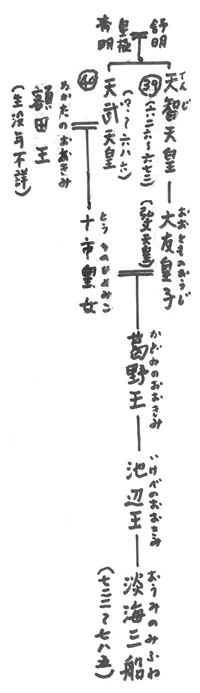
淡海三船は神武天皇~光仁天皇までの漢風諡号を撰定したといわれている。(左の系図参照)
万葉集に次の歌がある。
天智天皇が蒲生野(がもうの)で狩をなさった時に、額田王(ぬかたのおおきみ)が作った歌
万葉集第20番(万葉集の歌には番号が付けられている)
あかねさす 紫草野行(むらさきのゆ)き 標野(しめの)行き 野守(のもり)は見ずや 君が袖(そで)振る
【万葉仮名】
茜草指(あかねさす) 武良前野逝(むらさきのゆき) 標野行(しめのゆき) 野守者不見哉(のもりはみずや) 君之袖布流(きみがそでふる)
【現代語訳】
(あかねさす)紫草野(むらさきの)を行き 標野(しめの)[普通の人が入ることを禁じられている丘陵]を行って 野守[禁野の番人]が見ているではありませんか あなたが袖をお振りになるのを
皇太子の答えのお歌 この皇太子は明日香宮(あすかのみや)の天皇、諡(おくりな)を天武天皇という。
万葉集第21番
紫草(むらさきの) にほへる妹(いも)を 憎くあらば 人妻(ひとづま)故(ゆゑ)に 我恋(あれ)ひめやも
【万葉仮名】
紫草能(むらさきの) 尓保敝類妹乎(にほへるいもを) 尓苦久有者(にくくあらば) 人嬬故尓(ひとづまゆゑ) 吾恋目八方(あれこひめやも)
【現代語訳】
紫草(むらさき)のように におうあなたを憎いと思ったら 人妻と知りながら恋しく思いましょうか
日本書紀に「天智天皇の七年(668年)五月五日に、蒲生野で狩が催された。この時、皇太弟(大海人皇子)・諸皇族・内臣(藤原鎌足)および群臣がことごとくお供した」とある。
これは、額田王と大海人皇子(天武天皇)との微妙な歌である。
額田王は中大兄皇子(天智天皇)、大海人皇子(天武天皇)と関係があった女性であった。
また、中大兄皇子、大海人皇子、間人皇女は皇極天皇(後の斉明天皇)と舒明(じょめい)天皇の子であり、兄弟であった。(右の系図参照) 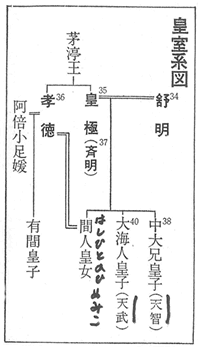
今回はこの額田王の難訓歌について、説明する。
難訓歌は万葉集「巻第一」第9番の歌である。
莫囂円隣之大相七兄爪謁気 我(わ)が背子(せこ)が い立たせりけむ 厳橿(いつかし)が本(もと)
【万葉仮名】
莫囂円隣之大相七兄爪謁気 吾瀬子之(わがせこが) 射立為兼(いたたせりけむ) 五可新何本(いつかしがもと)
この歌は斉明天皇が紀の温泉に行幸された時に、額田王が作った歌である。
紀の温泉は白浜温泉である。(下の地図参照) 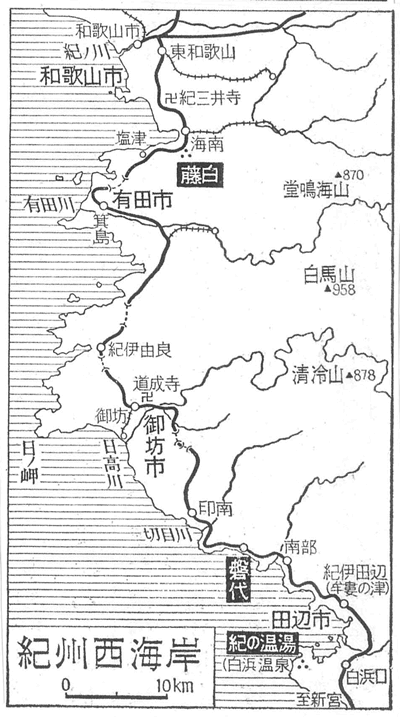
万葉集の10番、11番の歌を見てみる。
中皇命(なかつすめらみこと)、紀の温泉(ゆ)に往(ゆ)く時の御歌(みうた)
万葉集第10番
君が代も 我(わ)が代も知るや 岩代(いはしろ)の 岡(をか)の草根(くさね)を いざ結びてな
【万葉仮名】
君之歯母(きみがよも) 吾代毛所知哉(わがよもしるや) 磐代乃(いはしろの) 岡之草根乎(をかのくさねを) 去来結手名(いざむすびてな)
【現代語訳】
あなたのお命も わたしの命をもつかさどるこの岩代(いわしろ)の 岡の草を さあ結ぼうよ
万葉集第11番
我が背子は 仮廬(かりいほ)作らす 草(かや)なくは 小松が 下(もと)の 草(くさ)を刈らさね
【万葉仮名】
吾勢子波(わがせこは) 借廬作良須(かりいほつくらす) 草無者(かやなくは) 小松下乃(こまつがもとの) 草乎苅核(くさをからさね)
【現代語訳】
わが君よ 仮の庵(いおり)をお作りになる 萱(かや)がないなら あの小松の根元の 草でもお刈りなさい
10番、11番は中皇命(なかつすめらみこと)が作った歌である。
中皇命は誰であろうか?
中皇命は間人皇女(はしひとのひめみこ)であろうか。間人皇女は天智天皇の妹、天武天皇の姉に当る。三十六代孝徳天皇の皇后となり、難波宮に在ったが、孝徳天皇と反目した中大兄皇子に連れられ、母の皇極上皇らと飛鳥に帰った。孤立した孝徳天皇は恨んで、「かなきつけ我(あ)が飼ふ駒を引き出(だ)せず我が飼ふ駒を人見つらむか」と歌を詠んで崩じた。斉明天皇崩御後も天智は称制し、天智四年(665)二月皇女が薨(こう)じた後、同七年にようやく即位した。あるいはその間、間人皇女を名義上の天皇とし、そのために中皇命と呼んだものか。また斉明天皇と見る説もある。
■直木孝次郎著『日本の歴史2』古代国家の成立 中央公論社1965年刊に下記がある。
・太子、大和へ帰る
653年(白雉4)に入って、孝徳天皇と中大兄皇子との不和が表面化した。
それは、中大兄皇子(なかのおおえのおおじ)が都を大和へうつしたいと申しでたのを天皇が許さないという意見の対立となってあらわれた。
なにゆえに中大兄皇子が遷都を希望したのかよくわからない。大和の旧豪族を統制する必要からではないか、ともいわれるが、できたばかりの難波宮をすてて大和へ帰らねばならぬほどの不穏の形勢が、白雉(はくち)4年におこったとは思われない。天皇が許さなかったのは当然と考えられるが、中大兄はそれを無視して、母の皇極上皇や弟の大海人皇子をはじめ、公卿・大夫・百官をひきつれて飛鳥川のほとりの川辺(かわべ)の行宮(かりみや)にうつった。孝徳天皇の皇后である間人皇女までが天皇をすてて中大兄にしたがった。天皇と中大兄皇子との対立はきわめて深刻であったと思われる。
これについて思いあわされるのは、同じ年の五月、僧旻(みん)が病気になり、翌月、いよいよ死の近づいた旻を見舞った天皇が、旻の手をとって、「もしお前が死ぬようなことがあったら、わたくしはお前のあとを追って明日にも死のう」といったという伝えのあることである。天皇と中大兄との関係はこのころもう悪化しており、大化元年以来の重臣である国博士(くにつはかせ)旻の力によって、ようやく二人の仲がたもたれていたという事情があったのではなかろうか。
しかし、そもそも孝徳と中大兄の不和の原因はなんであろうか。思うに、政治の実権ははじめから太子である中大兄の手中にあったが、最初は中大兄もいちおう天皇をたて、群臣をひきいてゆくのに、まず自分が天皇に忠節をつくすというポーズをとり、天皇をも満足させていた。ところが改新の業が軌道にのり、新しい体制が安定してくると、中大兄はしだいに天皇を無視して独断で政治をとることが多くなり、天皇を怒らせたのではなかろうか。天皇と姻戚関係にある阿倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)と蘇我石川麻呂(そがのいしかわまろ)とがなくなったことも、天皇の地位を弱くし、中大兄の自由なふるまいを助けたであろう。天皇が政治をとるという原則がまだ生きているこの時代では、孝徳の目からみれば中大兄の態度はがまんがならなくなってくる。
だがそれだけでは、間人皇后まで孝徳をすてて中大兄にしたがい、大和へうつったことは理解しにくい。間人皇后は中大兄の同母妹であるが、それは夫をすてる理由にはならぬ。参徳が皇后を追いだしたのでもないことは、孝徳が大和へ行った皇后につぎのような歌を送っていることからもわかる。
金木(かなき)[鉗]つけわが飼ふ駒は引き出(で)せずわが飼ふ駒を人見つらむか
表面の意味は、「厩(うまや)のなかの棒に頸(くび)をつないでわたくしの飼っている駒は、引き出(だ)すこともせずにたいせつに飼っているのであるが、その駒を人が見たことだろうか」[相磯貞三(あいそていぞう)氏訳]であるが、むろん皇后を愛馬にたとえ、自分の意にそむいて宮をでた皇后と、皇后をつれさった中大兄皇子とに恨みをのべた歌だ。
・中大兄皇子と間人皇后
しかし、この歌はただそれだげの意味だろうか。いったい、「見る」ということばは現在でも複雑な内容をもっているが、古代、とくに男女間にもちいるばあいは特殊な意味がある。つまり夫婦の契りをむすぶという意味である。国文学者の吉永登(よしながのぼる)氏はこれに着眼して、歌の意味は、「だれよりも愛していたお前を他人が奪ってしまったのではないか。お前はわたくしを捨てて他の男のもとに走ったのではないか」と解釈した。
孝徳のいう「人」(他人、他の男)とはだれか。いうまでもなく中大兄である、と吉永氏は考える。中大兄皇子は叔父の孝徳天皇から皇后を奪ったのである。母を同じくする中大兄と間人皇后とのあいだでそのようなことはありえない、というのは現代人の常識にすぎない。はらちがいの兄妹(異母兄妹)間の結婚は、敏達天皇と推古天皇とがそうであったように、堂々とおこなわれているのだから、同母兄妹間の結婚も古代ではありうることであろう。そう考えれば間人皇后が孝徳をすてて大和へはしった疑問はとける。わたくしは吉永氏の洞察にしたがいたいと思う。
もちろん同母の兄妹の結婚が古代でもタブーであったことは事実だ。允恭天皇の皇太子軽(かる)皇子が、同母妹の軽大郎女(かるのおおいらつめ)と結婚したために皇太子の地位をうしない、皇位につくことができなかった話は、たんなる伝説かもしれないが記紀に伝えられている。中大兄も間人皇后との結婚を表むきにはできなかった。かれがこののちも長く皇太子のままでいるのはそのためではないか、というのが吉永氏の解釈である。天皇になれば皇后をきめなければならないが、それができないのである。
その証拠に、中大兄が正式に即位するのは間人皇后がなくなってからではないか、と吉永氏は論ずる。なるほど、間入皇后が死ぬのは665年(天智称制4)、天智天皇の正式即位は668年(天智称制7)である。いわれてみると、なぜ中大兄は23年もの長いあいだ皇太子のままでいたか、という古代史の疑問もとけるのである。
吉永氏のいうとおりであるとすれば、難波におきざりにされた孝徳天皇の怒りは察するにあまりがある。天皇はときに位を去ろうかと思うほどであったが果たさぬうちに、翌654年(白雉5)には病床にふす身となった。天皇の病いおもしときいて、中大兄皇子は皇極上皇や間人皇后以下の人々をつれて難波宮にかけつけたが、天皇の胸のうちが形だけの見舞いになごんだとは思われない。この年十月十日、天皇は恨みを抱いたまま死ぬが、天皇のただ一人の男子である有間皇子は、死の床に侍する中大兄皇子をどのような眼でみつめていただろうか。
■木梨軽(きなしかる)の皇子の恋について
・母を同じとする兄弟での結婚は古代での重大なタブーであった。記紀に書かれている。
かつて、天皇位も、さらには、みすがらの命さえも、恋の業火(ごうか)に投げ入れた皇子(おうじ)がいた。
第十九代允恭(いんぎょう)天皇の第一皇子・木梨軽(きなしかる)の皇子は、今日のキムタクのように、美目秀麗であった。
『日本書紀』は記す。
「(木梨軽の皇子の)容姿佳麗(かおきらぎら)し。見るひと、自(おの)ずからに感(め)でぬ(見る人は、自然にみとれ、感嘆した)。」
そして、木梨軽の皇子の同母の妹、衣通(そとおり)の郎女(いらつめ)も、輝く美女であった。衣通(そとおり)の郎女(いらつめ)の名の「衣通(そとおり)」は、身体(からだ)の光が、衣(そ)[ころも]を通して輝き出るところから、そう呼ばれたのであった。
当時、同母の兄妹が結ばれるのは、強い社会的なタブーであった(異母兄妹の場合は許されていた)。
木梨軽の皇子は、衣通の郎女に、死ぬほど恋こがれる。
『日本書紀』は記す。
「衣通の郎女にひかれる心は、はなはだ盛んであって、ほとんど、死にそうなほどであった。皇子は思う。空(むな)しく死ぬよりは、刑(つみ)を得ることがあっても、どうして、忍ぶことができようか、と。ついに、衣通の郎女と結ばれた」
木梨軽の皇子は、ふるえる思いを歌心して残している。
我(わ)が泣(な)く妻を(泣くほど恋しい私の妻に)
今夜(きそ)こそは(今夜こそは)
安く肌触(はだふ)れ(心おきなく肌を触れる)
〔明日は、どうなるか分からないけれども〕
抜きん出て輝く容姿を持つ皇子、皇女の二人にふさわしい相手は、この世では実の兄、実の妹しかいなかったのである。
この世は、二人が出会うためにあった。肌を触れた一瞬の感激のためにあった。
二人は、世の指弾をあび、とも心死ぬ。
ただただ、あわれというほかはない。
・『古今和歌集』仮名序に下記がある。
「をののこまちは、いにしへのそとほりひめの流なり。あはれなるやうにて、つよからず。いはば、よきをうなの、なやめるところあるににたり。つよからぬは、をうなのうたなればなるべし。
やまとうたは、ひとのこゝろをたねとして、よろづのことの葉とぞなれりける。世中にある人、ことわざしげきものなれば、心におもふことを、見るもの、きくものにつけて、いひいだせるなり。花になくうぐひす、みづにすむかはづのこゑをきけば、いきとしいけるもの、いづれかうたをよまざりける。ちからをもいれずして、あめつちをうごかし、めに見えぬ鬼神をも、あはれとおもはせ、お(を)とこ女のなかをもやはらげ、たけきものゝふのこゝろをも、なぐさむるは哥なり。」
このように、古代では衣通(そとおり)の郎女(いらつめ)が美人の代名詞であった。
この衣通の郎女と木梨軽の皇子の結びつきは悲劇となる。そして同母兄弟の結びつきが重大なタブーであったことが分かる。
■このような背景を理解して、額田王の難訓歌を読み解く。
「莫囂円隣之大相七兄爪謁気 吾瀬子之(わがせこが) 射立為兼(いたたせりけむ) 吾可新何本(いつかしがもと)」
小学館刊の日本古典文学全集の『万葉集1』は、この歌に、つぎのような「現代語訳」を与えている。
「紀伊(き)の温泉に(斉明天皇が)行幸された時に、額田王が作った歌
莫囂円隣之大相七兄爪謁気 わが君が そばに立たれたという 厳橿(いつかし)の木の下(もと)」
つまり、最初の十二文字については、読みかたも、意味もわからないので、現代語訳が、与えられていないのである。
そして、この『万葉集1』の頭註には、つぎのようにある。
「諸本によって、(文字に、)多少の異同があるが、いずれによっても訓義未詳。今日まで三十種以上の試訓が提出されているが現在のところ従うに足るものはない。」
鎌倉時代のお坊さんで、万葉学者の仙覚(せんがく)[1203~?)は、『万葉集註釈』(『仙覚抄』)で、この歌を、つぎのように読んだ。
「夕月(ゆふづき)の 仰(あふ)ぎて問(と)ひし 吾(わ)が背子(せこ)が い立たせるがね いつかあはなむ」
『万葉集註釈』には、そのように読む論拠も記されているが、今日では、仙覚が、額田王のこの難訓歌に、最初に読みを与えたという、研究史的な意味しかもたない。
岩波書店刊の新日本古典文学大系1の『万葉集一』は、この歌について、およそ、つぎのようにのべている。
万葉集には今日に至るまで解読不可能な歌がある。なかんずく、この歌の初・二句にあたる十二文字は、難訓の代表としてもっとも著名である。
仙覚の『夕月の仰(あふ)ぎて問(と)ひし』(『万葉集註釈一』)というあたらしい読みかた以来、多種多様な訓(よ)みかたが試みられ、武田祐吉の増訂『万秦集全註釈』(1956年)は三十三種、伊丹末雄(いたみまつお)『万葉集難訓考』(1970年)は六十種以上の諸説を列挙している。『万葉集私注』は、「なまじいに訓を試みるのは愚の至りであるが、大事を取って手をつける人がなくなったのでは、いつになっでも進歩はないと思う。・・・あえて私見を記しとどめる」として、初・二句を「勾(まがり)のたぶしに見つつ行け」とする案を掲げた。
沢瀉久孝(おもだかひさたか)の『万葉集注解』の試訓は「静まりし浦浪さわく」。『万葉集全註釈』は初・二句と結句には訓をほどこさない。『万葉集難訓考』は、初・二句を「夕月のかげ踏みて立つ」と試読。古典文学大系・新編古典文学全集は初・二句の訓釈を保留。
以上のように、この歌はよるべき訓釈がまったくえられていない。
本書にも遺憾ながら新しい提案を出しえない。
原文の文字そのものについては、諸本のあいだに大きな異同はない。
第四句は「い立たせりけむ」と訓む説にしたがう。結句の原文「五可新本」は「いつかし(厳橿)がもと(本)」と訓みうる。」みもろのいつ橿(かし)がもと[伊都加斯賀母登(いつかしがもと)、橿(かし)がもと[加斯賀母登(かしがもと)」(古事記・下(雄略)・歌謡)、
「磯城(しき)の厳橿之本(いつかしがもと)に鎮(しづ)め坐(いま)せて」(日本書紀・垂仁天皇二十五年)。
題詞の「紀温泉(きのゆ)」行幸は、『日本書紀』(斉明紀)に、「四年(658)冬十月(かんなづき)庚戌(かのえいぬ)の朔甲子(ついたちきのえねのひ)(十五日)に、紀温湯(きのゆ)に幸(いでま)す」、「五年(659)春正月己卯(むづきつちのとう)の朔辛巳(ついたちかのとのみのひ)(三日)に、天皇(すめらみこと)、紀温湯(きのゆ)より至(かへ)りたまふ」と載る。」
また、岩波書店刊の日本古典文学大系4の『万葉集一』は、この歌について、およそ、つぎのようにのべる。
「この歌難解で古来有名。とくに上二句が難読。いま、諸訓の一部をあげておく。
夕月の仰ぎて問ひし(『仙覚抄』)。
夕月し覆ひなせそ雲[契沖(けいちゅう)『万葉代匠記』精撰本]。
紀の国の山越えて行け(賀茂真淵『万葉考』)。
三諸(みもろ)の山見つつ行け[鹿持雅澄(かもちまさずみ)『万葉集古義』]。
真土山(まつちやま)見つつこそ行け[井上通泰(みちやす)『万葉集新考』]。
さか鳥のおほふな朝雪[粂川定一(くめかわさだいち)「莫囂円隣」『万葉』1968年7月)。
ふけひの浦西つめに立つ(宮島弘氏)。
第四句「射て立たしけむ」(森本治吉博士)。
静まりし雷(かみ)な鳴りそね(土橋利彦氏)。
まがりのたぶし見つつ行け(土屋文明氏)。
み吉野の山見つめ行け吾背子(わがせこ)がい立たせすがね何時(いつ)か逢はなも・み吉野の山見つめ行け吾背子(わがせこ)がい立たすがねを何時(いつ)か逢はなも(尾山篤二郎氏)。
夕月の光(かげ)踏みて立つ(伊丹末雄氏)。
静まりし浦波見放(うらなみみさ)け・静まりし浦波さわく[沢瀉(おもだか)博士]。
■
解読のヒント
短歌は、「五・七・五・七・七」の五句からなる。
そして、初句・二句にあたる「莫囂円隣之大相七兄爪謁気」
は、十二文字からなる。
このことは、「莫囂円隣之・大相七兄爪謁気」の・「五・七」の形に区切れることを思わせる。
また、「五・七」の句が、ちょうど十二文字からなることは、この部分が、「一字一音」の万葉仮名に近い形で書かれていることを思わせる。
あとの、「わがせこが」の部分の五音は、「吾瀬子之」の四文字で書かれ、「いたたせりけむ」の部分の七音は、「射立為兼」の四文字で書かれ、「いつかしかもと」の七音は、「五可新何本」の五文字で書かれている。一文字で、二音以上を記しているのである。
「莫囂円隣之大相七兄爪謁気」の部分は、文字が多い。「五・七」の十二音を、十二文字で記している。
最初の十二文字について、まずとりあえずは、「一字一音」を原則として読むべきであろう。
最初の十二文字を、
「莫囂円隣之」
「大相七兄爪謁気」
の形に区切ってみる。
すると、各句のおわりの「之」の字も、「気」の字も、万葉仮名として、比較的よく用いられている文字であることに気がつく。
・「之」と「気」の用例
まず、『万葉集』での、「之」の用例は、たとえば、つぎのようなものである。
a.初句の終りにでてくる「之(し)」と読む例
「阿佐比左之(あさひさし)(朝日さし)」(4003)
「安乎尓与之(あおによし)(青丹よし)」(4107)
「打霧之(うちきらし)[うち霧(き)らし]」(1441)
「波之伎余之(はしきよし)[愛(は)しきよし。愛すべきである、の意味]」(498)
b.初句の終りにでてくる「之(の)」と読む例
「秋風之(あきかぜの)(秋風の)」(1626)
「秋芽子之(あきはぎの)(秋萩の)」(1608)
「朝露之(あさつゆの)(朝露の)」(2689)
「雁鳴之(かりがねの)(雁そのもののこと)」(2097)
「大夫之(ますらをの)(76)
c.初句の終りではないが、「之(が)」と読む例
「妹之髪(いもがかみ)」(123)
「妹之袖(いもがそで)」(2187)
「雁之鳴(かりがねの)」(2195)
「君之服(きみがきる)(君が着る)」(2675)
「鶏之鳴(とりがなく)[東(あずま)の枕詞(まくらことば)]」(382)
用例数からいえば、「之」は、「し」と読まれていることが、もっとも多く、「の」がそれにつぎ、「が」と読まれる例が、もっともすくない。
つぎに、「気」の用例は、たとえば、つぎのようなものである。
d.句の終りにでてくる「気(け)」の例
「宇都久之気(うつくしけ)[愛(うつく)しけ]」(4414)
「多麻久之気(たまくしけ)[玉櫛笥(たまくしげ)]」(3726)
「多麻古須気(たまこすけ)(玉小菅)」(3445)
「八船多気(やふねたけ)(船をあやつり)」(1266)
「夜麻可都良加気(やまかづらかげ)(山かづらかげ)」(3573)
以上のほかに、「気」は、
「気衝明之(いきづきあかし)(息づき明し)」(210)
のように、「気(いき)」と読む例が、少数みられる。ただ、この歌のばあい、なるべく一字一音で読むとすれば、「気」を、「いき」と二音で読んでいるとはみられないので、「気」は、まず、「け(または、げ)」と読むべきである。
なお、奈良時代には、母音部の音の違いにより、「け」には、甲類と乙類の二種類がある。「気」の字は、乙類の「け」の表記に用いられる。
かくて、「気」を「け(乙類)」と読むということで、この一文字だけは、ぽぼ、読みが定まった。
■「莫囂円隣之」の解読
・「円隣之」の読み
「莫囂円隣之」の部分を読むことにしよう。
「隣」の字も、『万葉集』に使用例があり、
「八十一隣之宮(くくりのみや)[八十一は、かけ算の九九(くく)で、九九(くく)=八十一なので、くく、と読む)」(3242)
のように、「隣(り)」と読まれている。
「隣之」は、「・・・・りし」「・・・・りの」のいずれかに読めるが、
「・・・・りし」の可能性のほうが大きいといえよう。
つぎに、「円」の字も、『万葉集』に使用例がある。
「高円山(たかまどやま)」(1028)
「円方之(まどかたの)(円方は、的形で、現在の三重県内の地名)」(1162)
のように、「円」を、「まど」と読んでいる。これは、「円」は、「まるい」から、「まろ(まる)」と読み、それを、「まど」に通わしているのである(ひら仮名をおぼえはじめたばかりの子どもが、「電車(でんしゃ)」のことを、「れんしや」と書いたりするのに注意。「で」と「れ」の音は近い。
ここから、「円隣」は、万葉仮名で読めば、「まり」となる。
「まる」の「る」の音は、つぎの「隣」の語頭音のなかに吸収されているとみるべきである。
「獲居(わけ)(ɦuεk-kɪo)(kの重複。稲荷山古墳出土鉄剣銘文)「[軻遇(かぐ)突智(つち)(duƏ t-tɪĕ)(つち)]」(tの重複・『日本書紀』) など、万葉仮名の表記では、前の漢字の最後の音が、つぎの漢字の語頭の音に吸収される例は多い。
以上から、「円隣之」は、万葉仮名として、一字一音に用いられているとすれば、「・・・・まりし」と読まれる可能性が大きい。
・「莫囂」の読み
「莫囂円隣之」の、「莫」の字も、『万葉集』に、万葉仮としての使用例がある。すなわち、つぎのようなものである。
「落日莫死(おつるひなしに)(欠ける日もなく)」(2676)
「知跡言莫君二(しるといはなくに)(知るといはなくに)」(97)
「莫」という漢字には、「ない」「なかれ」の意味があるので、「な」と読んでいる。
そして、『万葉集』で、万葉仮名として、「莫」の字を用いるときは、多く、「ない」「なかれ」の否定の意味を、あるていど残している。
「莫囂円隣之」の五文字のうち、「囂」の字だけは、万葉仮名としての使用例がみられない。
「囂」は、漢音(唐代の音にもとづく)は、「ゴウ」または「キョウ」で、意味は、「かまびすしい」という意味である(「喧々囂々(けんけんごうごう)」という四字熟語がある)。(「囂(ごう)すること(うるさく)莫(な)く)『源氏物語』などの平安文字にでてくることばに、「あなかま」という表現がある。
「あなかま」の「あな」は感動詞、「かま」は、「囂(かま)し」の語幹で、「あなかま」は、「ああ、やかましい」「静かにしなさい」という意味である。
「莫」という漢字には、「なかれ」「・・・・してはいけない」の意味があるから、「莫囂」と「あなかま」とは、ほぼ同じ意味になる。
そこで、「莫囂」の意味をとって。
「莫囂円隣之」
の「莫囂」の部分を、「しづむ(静む)」と読み、それが、つぎの「円隣之(まりし)」と続く関係で。
「莫囂円隣之(しづまりし)」
になると考え、「静(しづ)まりし」と読むことにする。
『万葉集』学者の沢瀉久孝(おもだかひさたか)氏や、土橋利彦氏が、「莫囂円隣之」の部分を、「静まりし」と読んだのは、理由のあることである。
■「大相七兄爪謁気」の解読
・解読の準備作業
つぎに、「大相七兄爪謁気」の解読にとりかかる。
この部分を解読するためには、すこし、準備作業が必要である。
額田王の超難訓歌は、斉明天皇の四年(658)十月に、紀(き)の湯(ゆ)[和歌山県の牟婁(むろ)の湯(ゆ)、白浜町の湯崎温泉]へ斉明天皇が行幸したさいにつくられている。
その斉明天皇の行幸には、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)も、いっしょなのである。
そして、『日本書紀』の斉明天皇六年の条に、この超難訓歌を解読する手がかりになるようなことが書かれている。
『日本書紀』の斉明天皇六年(660)の条には、「童歌(わざうた)」がのっている。
童歌は、上代の歌謡の一種で、作者不明の民間のはやり歌である。政治上の諷刺や、社会的事件の予言が歌にこめられた。
「わざ」は、なんらかの意図をもつことを意味する。もとは、かくされた神意が、人、とくに子どもの口をかりて、人々に示されると考えられた。
「斉明天皇紀」六年の童歌(わざうた)は、古来難訓歌として多くの学者によって新解釈を提出されながら、いまだ定説をえない。
その童謡は、つぎのようなものである。
「まひらくつのくれつれおの〔さ〕へたをらふくのりかりがみわたとのりかみをへたをらふくのりかりが甲子とわよとみをのへたをらふくのりかりが(摩比邏矩都能倶例豆例於能〔社〕幣陀乎邏賦倶能理歌理鵝美和陀騰能理歌美烏能陛陀鳥邏賦倶能理歌理鵝甲子騰和与騰美烏能陛陀烏邏賦倶能理歌理鵝)」(〔〕内は、異本にみられる「能」の字の異字)
この歌を読み解くヒントになるらしいものが、卜部懐賢(うらべかねかた)(1278~1306年ごろの人)著の『釈日本紀(しゃくにほんぎ)』(鎌倉時末期成立)に記されている。
卜部懐賢は、『承平私記』(931~938年)の文を引用して、つぎのように記す(「私記」は、『日本書紀』についての講義の筆記ノート)。
[一部掲載、他は略]
麻比羅矩都能(マヒラクツノ)[私記曰。翻云都摩比羅矩能(ツマヒラクノ)。妻開也]
理鵝(リカ)[私記曰。翻云鵝里歌理(カリカリ)能倶邏賦(ノクラフ)。雁ゝ之喰也]
これから、下記のように示せる。
「まひらくつの」は、「つまひらくの(妻開くの)」であり、
「くれつれ」は、「つくれれ(作れれ)」で、「おのへたを」は、「をのだへを(小野田へを)」であるというのである。
つまり、この童歌は、「アナグラム(anagramu)」によって記されているというのである。
「アナグラム」というのは、単語の音(文字)をばらばらに崩して、あらたに組みあわせることにより、まったく別の単語を作る遊び、または、暗号である。ことばの、つづりかえ遊びである。
たとえば、「おとめ(乙女)」のアナグラムが「めおと(夫婦)」で「たばこ」のアナグラムが「こばた(小旗)」であるというものである。英語のばあいであれば、「live」から「evil」を作る、など。
そして、『釈日本紀』は記している。
「およそ、童歌(わざうた)の意味は、つぎのようなものである。
『斉明天皇は、女帝である。よって、天下を、女の作る田にたとえている。雁が稲の実を食うというのは、不祥(不吉なきざし)である。百済に援軍をつかわせば、つぎつぎに敗れる、といっているのである。』」
かりに、アナグラムであるとしても、問題は、アナグラムには、何とおりもの解がありうることである。
「やまたいこく(邪馬台国)」は、こまたいくや(子また行くや)」にも、「こまくいたや(鼓膜痛や)」にも、「やいたこくま(焼いた小熊)」にもなりうる。解釈の多義性をさけられない。
この童歌(わざうた)は上からストレートに読んでも明確な意味をなさない。また、歌謡中に使われた「甲子」という用字は特異である。「甲子」は、一字一音の万葉仮名なのか、そうでないのか。この歌については、一人一説というほどの解釈の幅が生じている。
「斉明天皇紀」の童歌(わざうた)に、やや近い話が、『続日本紀』の孝謙天皇の758年(天平宝字二年)の二月二十七日の条にのっている。
つぎのような話である。
「大和(やまと)の国守の大伴宿禰稲公(おおとものすくねいなきみ)たちが奏上をした。
『管轄内の城下郡(しきのしもぐん)の大和神山(やまとかむやま)に、ふしぎな藤の木が生えました。その藤の木の根もとに、虫が、文字を彫りつけました。それは、つぎの十六文字です。
王大則并天下人此内任大平臣守昊命(わうたいそくへいてんかにんしないにむたいへいしんしゅこうめい)』
そこで、天皇が、博士たちに、その十六文字を下して議論させたところ、みな、つぎのように読むべきだと答えた。
『臣(しん)、天下(てんか)を守(まも)り、王(おおきみ)の大(おお)いなる則并(のりあわ)す。内をこの人に任(まか)せば、昊命太平(こうめいたいへい)ならむ。』
これでわかった。群臣が忠をつくして、ともに天下を守る。王(おおきみ)は、大(おお)いに覆(おお)い載(の)せて、兼(か)ね并(あわ)せずということなし。聖上(せいじょう)が賢人をあげて、内をこの人に任(まか)せば、昊天(こうてん)(大空)は、その徳にむくいて、命(めい)が太平であろう、ということを。」
つまり
「王大則并天下人此内任大平臣守昊命」
の十六文字は、アナグラムとして読むべきで、つぎのように、文字をならべかえて読むべきだというのである。
「臣、守天下、王并大則。
内、任此人、昊命大平。」
当時は、暗号、あるいは、言葉あそびとして、文字の順番をいれかえることが、わりに行なわれていたことがわかる。
・「大相七兄爪」の読み方
以上のようなことを、予備知識としてもったうえで、額田王の難訓歌の「大相七兄爪」の部分を、じっとながめてみよう。
まず、「大兄」ということばが目にはいる。
『万葉集』では、額田王のこの難訓歌のすぐつぎに、中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)のことを歌った歌がでてくる。
額田王の難訓歌のなかの「大兄」という文字は、「中大兄皇子」のことをさすのであろう。
つぎに、「相」の字は、『万葉集』で、
「人言(ひとごと)を、繁(しげ)み、言痛(こちた)み、我(わ)が背子(せこ)を、目には見れども、逢(あ)ふよしもなし。」[人のうわさが、たえずうるさいので、私の彼氏を、目では見るけれども、逢(あ)うすべもない。]
の歌の、「逢(あ)ふよしもなし」のところが、原文では、「相因毛無(あふよしもなし)」となっている。このことからも、うかがわれるように、「相(あふ)」は、男女関係をもつことを意味する。
「逢(相)ふ」にういて百人一首の下記例もある。
逢ひ見ての のちの心にくらぶれば
昔はものを 思はざりけり
権中納言敦忠(43番)『拾遺集』恋二・710
【現代語訳】
恋しい人とついに逢瀬を遂げてみた後の恋しい気持ちに比べたら、昔の想いなど、無いに等しいほどのものだったのだなあ。
「大相七兄爪」をアナグラムとして「相七大兄爪」とする。そして、もし漢文で読むと、「七大兄」で区切り、相七大兄爪[七大兄(なせ)に相(あ)はず)と読める可能性がある。
「なせ」を辞書で引くと下記となり、「七大兄」は親愛なる人と読める。
なせ【汝兄】〔名〕上代語。親愛の情を込めて男を呼ぶ語。あなた。「あがなせ「那勢」の命入り来ませる事かしこし」〈記・上・伊邪那岐伊邪那美〉。
「なせ[奈勢]の子や等里(とり)の岡道(をかぢ)し中だをれ吾(あ)を哭(ね)し泣くよ息衝(いくづ)くまでに〈万葉・14・3458〉。「いとこ(=親愛ナル人)なせ[名兄]の君居り居りて」〈万葉・16・3855〉→なにも(汝妹)
「七」は「な」と読める。
十一月、大伴坂上郎女(おおとものさかのいらつめ)が、大宰帥の旅人卿の家を出発して帰途についた時、筑前国(ちくぜんのくに)宗像郡(むなかたぐん)の名児山(なごやま)という名の山を越える際に作った歌一首
『万葉集』第963番
大汝(おほなむぢ) 少彦名(すくなびこな)の 神こそば 名付(なづ)けそめけめ 名のみを 名児山と負(お)ひて 我(あ)が恋(こひ)の 千重(ちへ)の一重(ひとへ)も 慰(なぐさ)めなくに
【万葉仮名】
大汝(おほなむぢ) 小彦名能(すくなびこなの) 神社者(かみこそば) 名著始鷄目(なづけそめけめ) 名耳乎(なのみを) 名児山跡負而(なごやまとおひて) 吾恋之(あがこひの) 千重之一重裳(ちへのひとへも) 奈具佐米七国(なぐさめなくに)
【現代語訳】
大国主(おおくにぬし)と 少彦名(すくなびこな)の 神々が 名付け始めたということだが 名前だけ 名児山といってわたしの恋のつらさの 千分の一も なぐさめてくれないことだ
『万葉集』第1781番 高橋連虫麻呂の歌
海(うみ)つ路(ぢ)の 和(な)ぎなむ時も 渡らなむ かく立つ波に 船出(ふなで)すべしや
【万葉仮名】
海津路乃(うみつぢの) 名木名六時毛(なぎなむときも) 渡七六(わたらなむ) 加九多都波二(かくたつなみに) 船出可為八(ふなですべしや)
【現代語訳】
海路の 静かな時にでも 渡ればよろしいのに こんなに波の荒い時に 船出(ふなで)してよいものでしょうか
『万葉集』第5番
霞立(かすみ)立つ 長き春日(はるひ)の 暮れにける わづきも知らず むら肝(きも)の 心を痛み
【万葉仮名】
霞立(かすみたつ) 長春日乃(ながきはるひの) 晩家流(くれにける) 和豆肝之良受(わづきもしらず) 村肝乃(むらきもの) 心乎痛見(こころをいたみ)
『日本国語大辞典』で「す」は「受」の漢字を使う。そしてくずすと「爪」と書く。万葉仮名で「受」は濁音で「ず」となる。
(下図はクリックすると大きくなります)
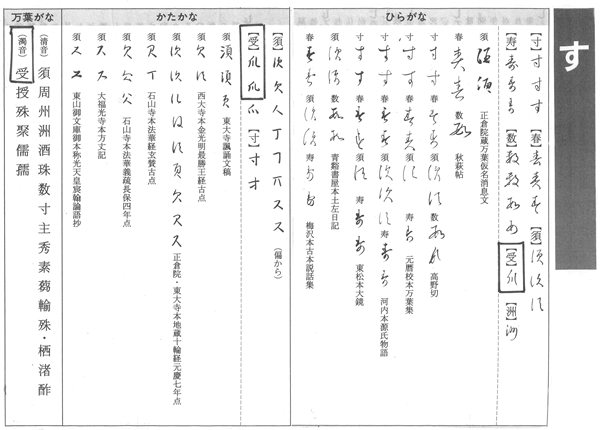
万葉仮名の「受」を「ず」として、使った例は下記である。
『万葉集』第22番
河上(かはのへ)の ゆつ岩群(いはむら)に 草生(む)さず 常(つね)にもがもな 常娘子(とこをとめ)にて
【万葉仮名】
河上乃(かはのへの) 湯都盤村二(ゆついはむらに) 草武左受(くさむさず) 常丹毛冀名(つねにもがもな) 常処女煑手(とこをとめにて)
或本の歌
『万葉集』第56番
河上(かはのへ)の つらつら椿 つらつらに 見れども 飽(あ)かず 巨勢の春野は
【万葉仮名】
河上乃(かはのへの) 列ゝ椿(つらつらつばき) 都ゝゝ尓(つらつらに) 雖見安可受(みれどもあかず) 巨勢能春野者(こせのはるのは)
このようにして、「爪」は「ず」と読めるので、「大相七兄爪」は七大兄(なせ)に相(あ)はずと読める。
・「謁気」の読み方
下記『時代別国語大辞典』(三省堂刊)の動詞の活用表で、左に線を引いたのは、乙類の母音で、右に線を引いたものは甲類の母音である。「行け」は動詞の四段活用なので、命令形の「行け」は甲類の母音となる。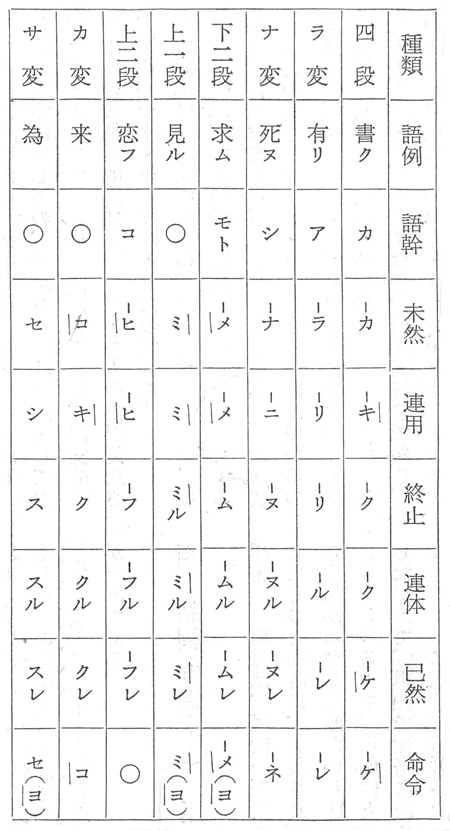
「謁」の字を「湯」の誤記とみて、「湯気」を「行け」の意味にとると、「行け」の「ケ」は「甲類のケ」でなければならない。
「気」は「乙類のケ」の代表的な文字で音があわない。
「気」の字は、「乙類のケ」と読むべきであることは、すでにのべた。
それでは、「気」の字のまえの「謁」の字は、なんと読むべきであろうか。
「謁」は、万葉仮名としての使用例がない。
ただ、藤堂明保氏の『学研漢和大字典』を引いてみると、「謁」の字の隋・唐音は、「・ɪⴷt」となっている。そして、この字と同じ母音部をもつ「英(隋・唐音は、・ɪⴷŋ)」は、『万葉集』に、万葉仮名としての使用例がある。それは、
「英遠浦(あをのうら)(富山県の海岸名)」(4093)のように、「英(あ)」と読んでいる。
したがって、「謁気」は、「あけ」と読める。
「謁気(あけ)」は、「明ける」の意味で、「期間が終る」の意味であろう。
「明(あ)く」は、下二段活用の動詞で、連用形の「明け」の「け」は、「乙類のケ」であるから、「気[ケ(乙)]」と音があう。
以上から、
「大相七兄爪謁気」
の部分は、
「なせ(大兄に)あはず(夜が)あけ」と読める。
■「五可新何本」の解読
・「五可新何本(いつかしがもと)」の解釈
『古事記』の「雄略天皇紀」に、つぎのような話がのっている。
「あるとき、雄略天皇が遊びに行き三輪川(みわがわ)に着いたとき、川で衣服を洗っている乙女(おとめ)にであった。その姿がたいへん美しかったので、天皇はその乙女に、『おまえはだれの子か』とたずねた。乙女は、『私の名は引田部赤猪子(ひけたべのあかいこ)といいます』と答えた。そこで天皇は、『おまえは他の男と結婚するな。まもなく召そう』と伝えて、宮殿に帰った。
赤猪子は天皇の言葉を期待して待つうちに、はや八十年がたった。そこで赤猪子は、『お召しを待っているあいだに、こんなに多くの年がたってしまった。体も痩せしぼんで、まったく頼むところもない。けれども、待ち続けた私の心を表わさずにいたのでは、気持が晴れない』と思い、多くの贈りものを持って、参内して献上した。しかし、天皇は、以前に自分のいったことをすっかり忘れていた。赤猪子に尋ねていった。『おまえはどこのお婆さんか。どういうわけで来たのか。』
赤猪子(あかいこ)は答えた。『さる年のさる月、天皇のお言葉をうけたまわって、仰せを心待ちにしていました。今日までに八十年が過ぎました。今はすっかり年老いて、もはや頼むところもありません。けれども、私の心だけは表わし申しあげようとして参内したのです。』
雄略天皇はひどく驚いて、『私はすっかり前のことを忘れていた。しかし、おまえが操を守り、召しを待って、むなしく娘ざかりの年を過してしまったことは、まことに申しわけない。』
内心では、赤猪子を抱きたいと思ったが、赤猪子がたいへん年老いて、交わるわけに行かない。そこで、歌を賜った。その歌にいう。
『みもろの厳白檮(いつかし)が本(もと)白檮(かし)が本(もと)、ゆゆしきかも、白檮原童女(かしはらおとめ)』」
ここに、額田王の難訓歌と同じく、「厳白檮が本」ということばがでてくる。
『万葉集』では「五可新何本」としたものが、『古事記』の雄略天皇紀では「伊都加斯賀母登(厳白檮が本)」として出てくるのである。
雄略天皇の歌の意味は、つぎのようなものである。
「御諸(みもろやま)の神聖な樫(かし)の木。
その樫の木は、神聖で近よりがたいよ。
その樫の木と同じように、三輪の社の樫原乙女は、神聖で、タブーなので、近よりがたいよ(どうも、あなたを抱くわけには行かないな)。」
この歌などは、額田王のころの宮廷大にとっては、ポピュラーなものであったであろう。
以上から、額田王の難訓歌の理解は、一応は、つぎのようになる。
莫囂円隣之(しづまりし)[静まりし]
大相七兄爪謁気(なせあはずあは)[なせ(大兄に)あはず(夜が)あけ」]
吾瀬子之(わがせこが)[わが君が]
射立為兼(いたたせりけむ)[その木のそばに立っておられるのであろう]
五可新何本(いつかしがもと)[神聖な樫の木]
「い立つ」の「い」は強調の接頭語であるが、「それ」という代名詞からきているとみられる。
・「五可新何本」の真の意味
さて、ここで、さらに踏みこんで考えてみよう。
額田王(生没年不詳。630~636年ごろ生まれと考えられる)は、はじめ、大海人皇子(おおしあまのおうじ)(のちの天武天皇)とのあいだに、十市皇女(とおちのひめみこ)を生む。しかし、のちに、天智天皇(かつての中大兄皇子)の後宮にはいった。額田王が、いつ、天智天皇(中大兄皇子)と結ばれたのかは、わからない。
額田王の難訓歌は、斉明天皇の四年(658)には、額田王と中大兄皇子とが結ばれていたことを思わせる。このころ、額田王は、二十二歳~二十八歳ごろであったとみられる。おそらく、二十八歳に近かったであろう。
「五可新何本(いつかしがもと)」は、「神聖な樫の木」の意味であるとしても、この「神聖な樫の木」は、特別な意味に解釈できる余地がある。
間人皇女(はしひとのひめみこ)のことである。中大兄皇子の同母妹で、孝徳天皇の皇后となった人のことである。
653年、孝徳天皇と中大兄皇子との意見が対立し、中大兄皇子は、同母妹で、孝徳天皇の皇后である間人皇女をつれて、大和に帰る。孝徳天皇は、難波の宮におきざりにされる。中大兄皇子と間人皇女とのあいだには、男女関係があったとする説がある。とくに、国文学者、吉永登(よしながみのる)氏らが説き、有力な見解となっている。この説を、一応うけいれてみよう。
古代において、同母の兄妹間の男女関係は、強いタブーであった。
中大兄皇子は、このタブーをおかしていたため、斉明天皇の没後も、天皇に即位せず、「称制」という特異な形で、政治を行なった。皇太子のままで、政治を行なったのである。
中大兄皇子は、二十三年ものあいだ、称制の形で政治を行ない、665年に間人皇女がなくなってから、天皇の位につく(668年即位)。
この間の年代をみてみよう。
653年、中大兄皇子は、間人皇女とともに、大和に帰る。
658年、中大兄皇子は、間人皇女や額田王とともに、紀伊の温泉に行く(斉明天皇の行幸にともなう)。
661年、斉明天皇没。
658年の、斉明天皇の紀伊の温泉行幸には、間人皇女も、額田王も、ともに行っているのである。
とすると、「我が背子(せこ)が、い立たせりけむ、厳橿(いつかし)が本(もと)」は、「私の彼である中大兄皇子は、タブーであって触れてはならない女性(間人皇女)のそばに立っている」という意味になる。
このようにみてくると、額田王の難訓歌の解釈は、つぎのようになる。
「静かである。
中大兄皇子にあわず(夜が)あけ、
わが君は、
触れてはならない樫の木(女性)のところに、立っておられるのであろう。」
雄略天皇の歌の「厳白檮が本」も、本来、触れるのがタブーの樫原乙女を指していた。
『万葉集』で、額田王の難訓歌のすぐつぎに、間人皇女が、中大兄皇子のことを歌った歌が並べられているのは、大伴家持(おおとものやかもち)などの、『万葉集』の撰者が、難訓歌の意味を、理解していたからであろう。
さらに、そのあとに、中大兄皇子の有名な歌がある。
「香具山(かぐやま)は 畝傍雄雄(うねびおお)しと 耳梨(みみなし)と相争ひき 神代より かくにあるらし古(いにしへ)も 然(しか)にあれこそ うつせみも 嬬(つま)を 争ふらしき」
この歌については、どの山を女性とみ、どの山を男性とみるかで、さまざまな説がある。
額田王の難訓歌と関係づければ、香具山(女性)、畝傍山(男性)、耳梨山(女性)で、二人の女性が、一人の男性を取りあった、という意味になるであろう。なお、「嬬(つま)」という文字(語)は、『万葉集』の153番の歌では、「夫(つま)[男性]」の意味で用いられている。また、「畝傍雄雄(うねびをを)しと」の部分の原文は、「雲根火雄男志等(うねびををしと)」と書かれている。あまり原文の文字にひきずられるべきではないが、「雄男(をお)」などの文字の使われているところをみれば、畝傍山を男性とみているのであろう[この部分、上の「雄(を)」を助詞とみて、「を愛(を)し」「を惜(を)し」とする説がある]。
あるいは、畝傍山を女性とみ、間人皇女をさし、二人の男性である孝徳天皇と中大兄皇子とが取りあうと解釈できるかもしれない。
結論:額田王の難訓歌の解釈は、つぎのようになる。
「静かである。
中大兄皇子にあわず(夜が)あけ、
わが君(中大兄皇子)は、
触れてはならない樫の木(タブーである間人皇女)のところに、立っておられるのであろう。」
と歌ったものである。
このような内容なので、暗号めいた表現にする必要があったのだと思われる。