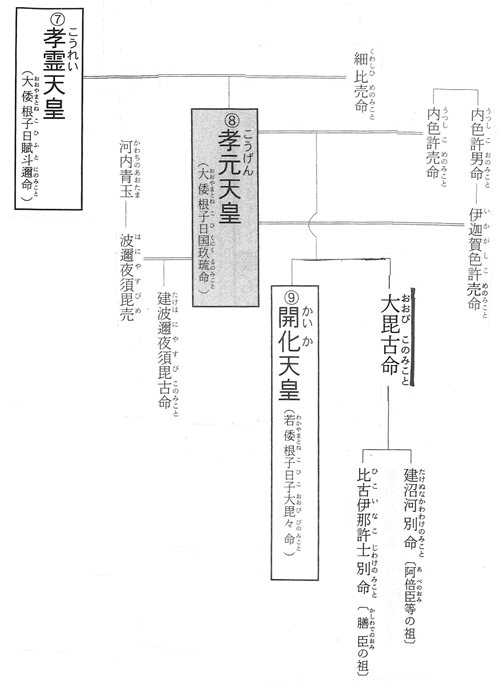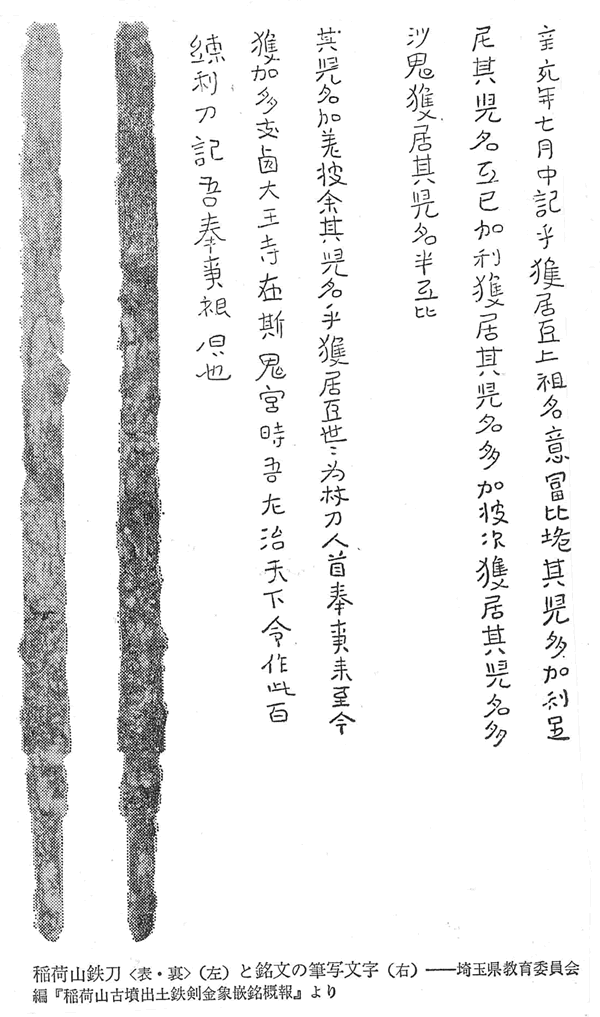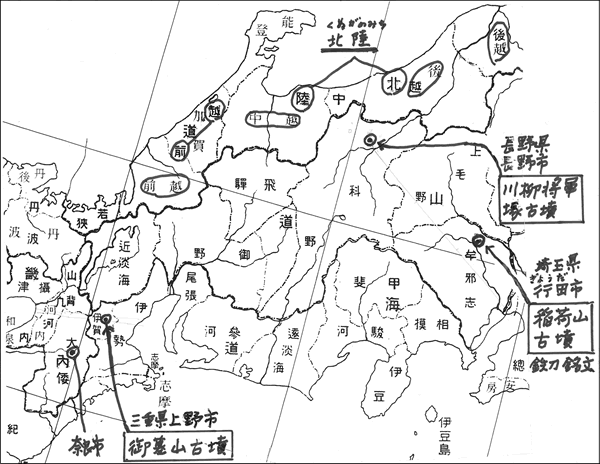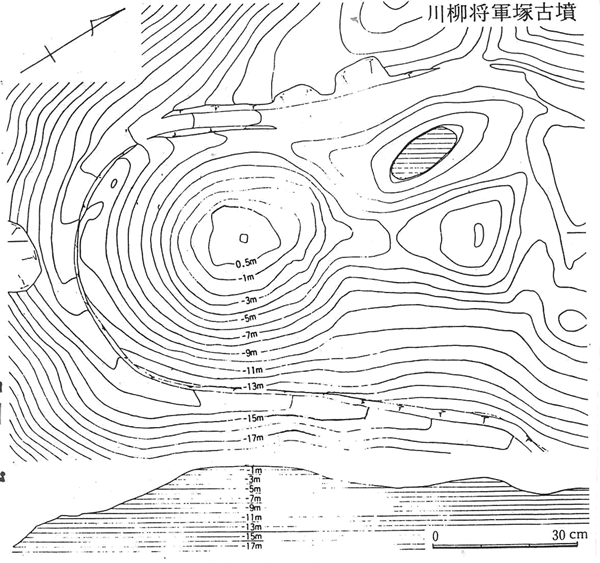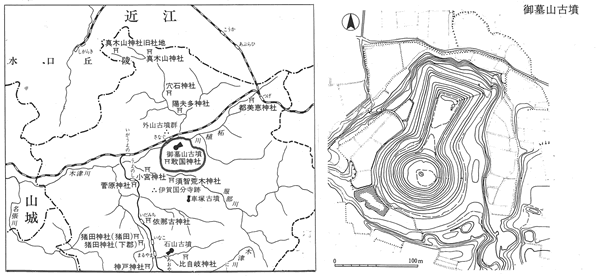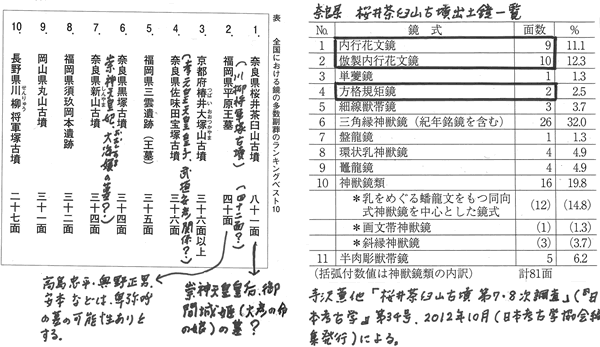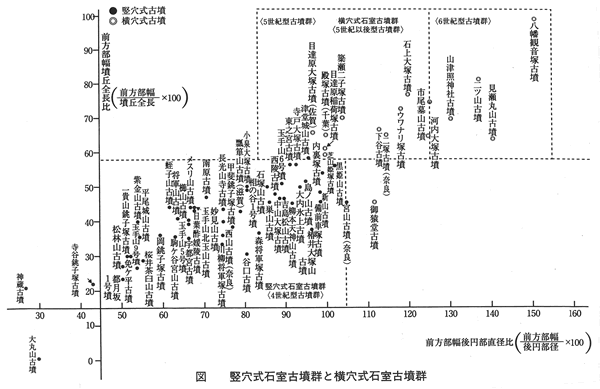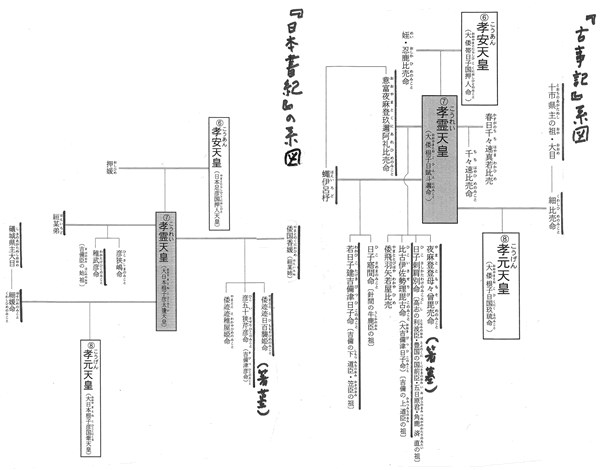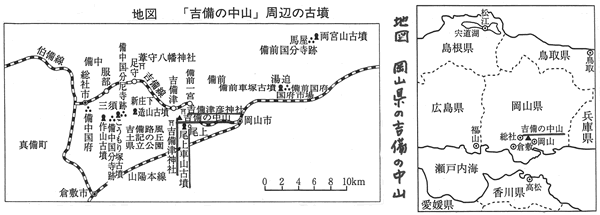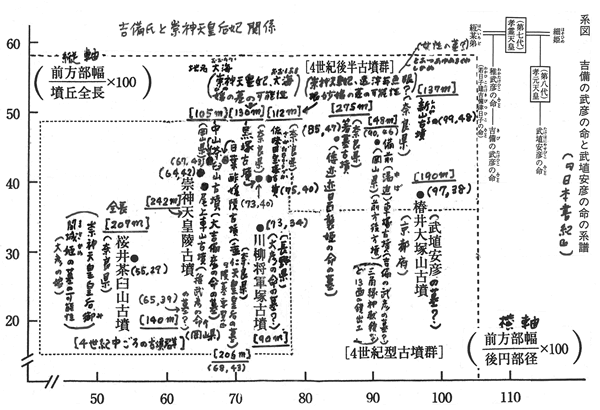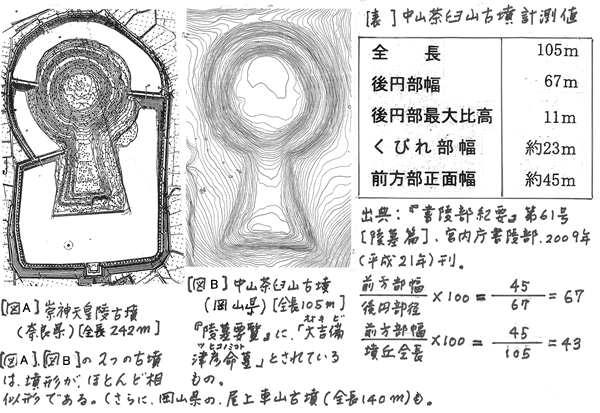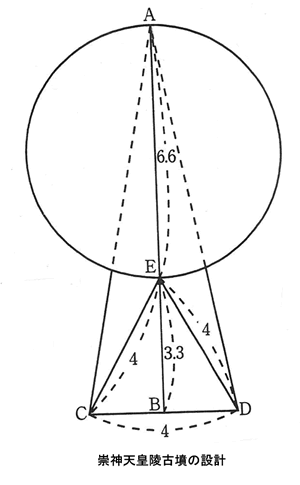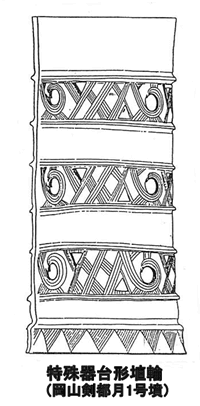■大吉備津彦(おおきびつひこ)の命(みこと)の墓
『古事記』と『日本書紀』による孝霊天皇ころの系図は下記となる。
(下図はクリックすると大きくなります)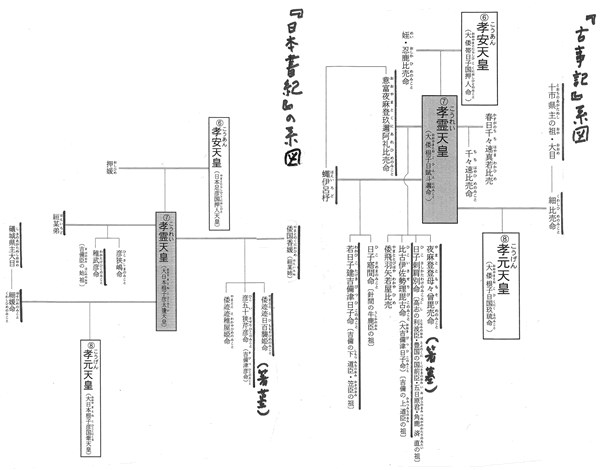
『陵墓要覧(りょうぼようらん)』(宮内省「宮内庁」の職員の執務用の便覧書(べんらんしょ)。大正4年(1915)初版発行。以後、平成24年(2012)版まで5回の改訂版がでている。
孝霊(こうれい)天皇 片丘馬坂陵(かたをかのうまさかのみささぎ)
傍丘 奈良県北葛城郡王寺村大字王寺
陵 山形、周囲土手、石柵
系 六・皇太后押媛命
崩 七六(四四六、三、二三)
皇子 大吉備津彦命(おおきびつひこのみこと)墓
岡山県御津郡一宮村大字尾上(おのうえ)、吉備津郡真金村(元宮内)界字茶臼山(吉備の中山、中山茶臼山古墳)
皇女 倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)墓
山辺 奈良県磯城郡織田(おだ)村大字箸中(はしなか)字茶屋ノ前(ちゃやのまへ)
墓 前方後円、周囲 カシ生垣
薨 崇神天皇一一、九(五七四)
岡山県の吉備中山とその周辺の古墳
(下図はクリックすると大きくなります)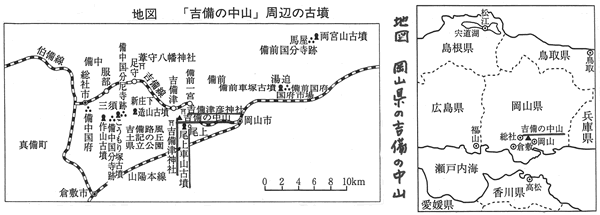
・大吉備津彦(おおきびつひこ)の命(みこと)の墓と伝承されている岡山県「吉備の中山」の中山茶臼山古墳
『日本書紀』の第十代崇神天皇の巻に、四道(しどう)将軍派遣の話がのっている(「崇神天皇紀」十年九月の条)。
すなわち、遠国には、まだ大和朝廷に従わないものが多くいたので、皇族のなかから四人の将軍がえらばれて、各地に派遣された。大彦(おおびこ)の命を北陸に、武渟川別(たけぬなかわわけ)の命を東海に、吉備津彦(きびつひこ)の命を西の道(山陽)へ、丹波の道主(たにはのみちぬし)の命を丹波(山陰)へ遣わしたという。
『日本書紀』の話にほぼ対応する記事は、『古事記』にもみえる。
『古事記』によれば、第七代孝霊天皇の皇子であった大吉備津日子の命[吉備津彦の命、またの名を比古伊佐勢理毘古(ひこいさせりびこ)の命]と、その異母弟の若日子建吉備津日子(わかひこたけきびつひこ)の命の二人が力をあわせて、吉備の国を平定したという。
『古事記』の記事と『日本書紀』の記事とでは、若干のちがいがある。すなわち、
(1)『古事記』では、大吉備津日子の命の吉備の国平定の話は、「孝霊天皇記」にみえるが、『日本書紀』では、「崇神天皇紀」にみえる。ただし、『古事記』の記事は、孝霊天皇皇子の事跡を記したものであって、吉備の国平定の行なわれた時期が、孝霊天皇の時代であると明記されているわけではない。
(2)『古事記』には、「四道将軍」としてはでてこない。
(3)『古事記』では、大吉備津日子の命と、異母弟の若日子建吉備津日子の命とが協力して平定にあたったことになっているが、『日本書紀』の、「四道将軍」派遣のところでは、吉備津彦の命[彦五十狭芹彦(ひこいさせりひこ)の命]の名だけがみえる。
(4)『古事記』では、大吉備津日子の命(比古伊佐勢理毘古の命)は、「吉備の上(かみ)つ道(みち)の臣(おみ)の祖」で、異母弟の若日子建吉備津日子の命は「吉備の下(しも)つ道(みち)の臣(おみ)の祖」となっているのに、『日本書紀』では、「上つ道の祖」も、「下つ道の祖」も、ともに、稚武彦(わかたけひこ)の命(『古事記』の若日子建吉備津日子の命)の子孫となっている。
本居宣長は、『古事記伝』において、このことを論じ、大吉備津日子の命と異母弟の若日子建吉備津日子の命とは、ともに、吉備の国を平定したが、兄の大吉備津日子の命の子孫はいなくて、ただ弟の若日子建吉備津日子の命の子孫だけが、吉備の地で、栄えたのであろうか、としている。
(5)『古事記』では、若日子建吉備津日子の命の子どものことを、ややくわしく記しているのに、 『日本書紀』では、孫のことを、ややくわしく記している。いずれにしても『古事記』『日本書紀』ともに、弟の若日子建吉備津日子の命の子孫のことを記し、兄の大吉備津日子の命の子や孫の名を、直接的には記していない。
・茶臼山古墳築造の時期
さて、以下は前に示した「岡山県の吉備中山とその周辺の古墳」の地図を参照しながら読み進めていただきたい。岡山市の中心部から、直線距離で6キロほど西に、『吉備(きび)の中山(なかやま)』といわれる山がある。岡山平野のほぼ中央に位置し、岡山県岡山市尾上(おうえ)ならびに吉備津に所在する。
「吉備の中山」は、備前(びぜん)の国と備中(びっちゅう)の国との国境にある。そこから、「中山」の名はおきたとみられる。東西の幅約2キロ、南北2.5キロ、周囲はおよそ8キロほどの独立した小山である。
中山茶臼山古墳は、明治七年(1874)に、宮内省(現宮内庁)の管轄するところとなり、公式には、「大吉備津彦命墓(おおきびつひこのはか)」と呼ばれることになった。現在、大吉備津彦命陵墓参考地に指定されている。
中山茶臼山古墳は、前期古墳の特徴をそなえているようにみえる。
茶臼山古墳からは、退化した特殊器台形埴輪片が出土しており、築造の時期は、前期のI期の後よりと推定されている(大塚初重他編『日本古墳大辞典』東京堂出版刊。近藤義郎「中山茶臼山古墳」『岡山県史18』1986年参照)。
つまり、四世紀代の墓と推定されている。
『日本書紀』によれば、大吉備津彦の命は、崇神天皇の時代に活躍した人である。
■中山茶臼山古墳は、崇神天皇陵古墳と相似形
特筆すべきことは、中山茶臼山古墳は、奈良県の崇神天皇陵古墳と、平面図がほとんど相似形であることである。
前方後円墳の形態によって、築造の時期が推定されるとすれば、中山茶臼山古墳は、崇神天皇陵古墳とほぼ同じ時期、つまり、340~360年前後に築造されたことになる。下図参照
(下図はクリックすると大きくなります)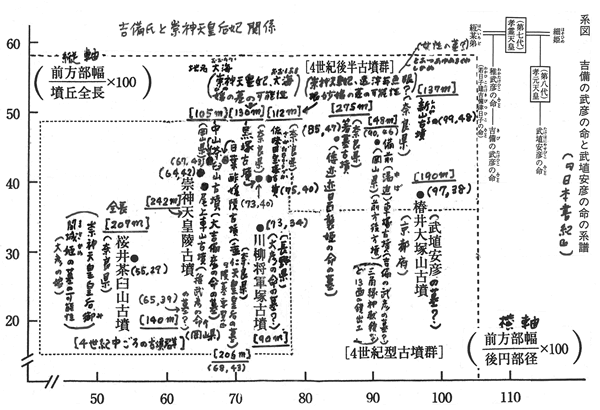
『日本古墳大辞典』に記されている岡山県の中山茶臼山古墳の記述と、崇神天皇陵古墳の記述とのあいだには、いくつかの共通性がある。すなわち、
(1)ともに、前方後円墳である。
(2)ともに、自然の丘陵地形を利用したもので、丘尾切断法で築造されている。
(3)ともに、五世紀古墳にみられるような造出(つくりだ)し(前方部と後円部とをつなぐくびれ部の両側または片側に付設された方壇状の部分)がない。
私は、茶臼山古墳を、伝承どおり大吉備津彦の命の墓とみてよいと考えるものである。
なお、崇神天皇陵古墳の墳丘全長は、晋尺(しんじゃく)ではかって、ほぼ正確に一千尺である。
文献上において同時代で関連があるとされている人たちの墓が、形態上も関連し、同時代性を示している。
(下図はクリックすると大きくなります)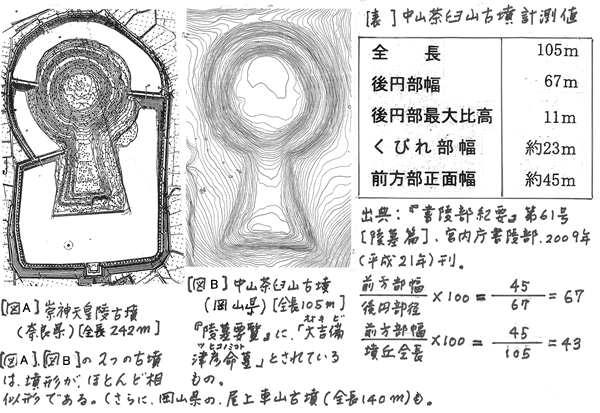
このような事実は、四道将軍派遣の記事がたんなる伝説ではなく、四世紀代の史実にもとづくことを示しているようにみえる。
■崇神天皇陵などの設計
崇神天皇陵や中山茶臼山古墳では、墳丘全長の直線ABをまず定め、(下図参照) 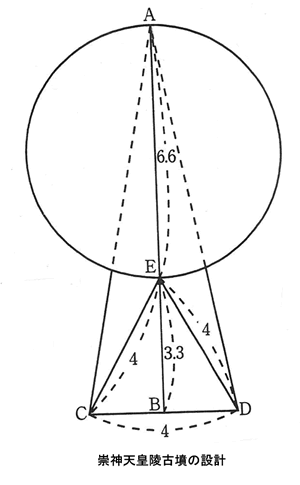
つぎに墳丘全長の三分の二の長さで、後円部の直径を定め、さらに墳丘全長の四割ほどの長さで、前方部の幅を定めて、直線CDを引き、AとC、AとDを結ぶというような設計によっているようである。このようにすると、上図のECDは、大略正三角形になる。
あるいは、逆に、CDをまず定め、CDを一辺とする正三角形をえがき、つぎに、その正三角形の高さを半径とする円を描いたのかもしれない。
いずれにしても、比較的簡単な設計によっているようである。
■大吉備津彦の命をまつる吉備津神社
「吉備の中山」の西のふもとに、備中の吉備津神社がある(前に示した「吉備の中山」周辺古墳の 地図参照)。所在地は、岡山市吉備津である。
吉備津神牡は、吉備津彦神社または吉備津の宮ともいう。
JR吉備津線吉備津駅から、500メートルほどである。
明治時代に官幣中社とされた。
『古今集』の1082番の歌に、「まがねふくきびの中山おびにせるほそたに川のをとのさやけさ」がある。
「まがねふく」は、「吉備」の枕詞である。
「まがねふく」は、鉄を吹きわけるの意味であるが、吉備の国は、古く鉄を産したので、この枕詞がある。
吉備津神社は、かつて、備中の国吉備郡真金村(まがねむら)に属していた。
さきの歌の意味は、「吉備の中山が帯にしている細谷川の音のさやけさよ」という意味である。
この歌には、「承和の御べのきびのくにのうた」と、説明がついている。
承和は、仁明天皇時代の年号で、834年~848年である。「御べ」は、「おほんにへ」の略で、大嘗(おおにえ)の祭(まつり)、すなわち、即位後はじめての新嘗祭(にいなめさい)のことである。 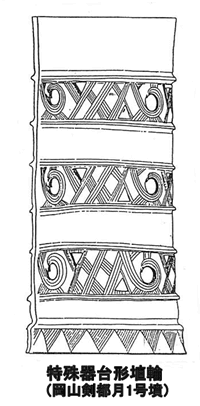
[メモ1]前に示した「吉備氏と崇神天皇后妃関係」の図からうかがえるように、日葉酢媛(ひばすひめ)陵古墳(垂仁天皇皇后の墓)と佐味田(さみた)宝塚古墳とは、かなり近い墳形をしている。そればかりではなく、この二つの古墳からは、きぬがさ埴輪、家形埴輪、鰭(ひれ)付円筒埴輪、盾の埴輪や、碧玉製の鍬形石・石釧・盒子(ごうし)など、共通の形式の遺物が出土している。ともに、女性の墓であろうか。
[メモ2]中山茶臼古墳と箸墓古墳とからは、ともに、特殊器台形埴輪が出土している。とくに、箸墓古墳からは、都月型の特殊器台形埴輪が出土している。都月型埴輪は、岡山県の都月坂1号墳出土の特殊器台形埴輪を標式とする。岡山県との関係をうかがわせる。
吉備津神社は、「吉備津造り」と呼ぼれる建築様式をもつ。
本殿を外からみるとき、檜皮葺(ひはだぶき)の大屋根が、入母屋造(いりもやづく)りを二つ前後に連結した形であるところに特色がある。「吉備津造り」とも「比翼(ひよく)の入母屋造り」ともいわれる。(下の写真参照)
山陰を代表する神社が出雲大社であるとすれば、山陽地方を代表するのがこの吉備津神社と、安芸の厳島(いくつしま)神社である。
吉備津神社の本殿の建坪は、255平方メートルある。大建築である。高さにおいては出雲大社におよばないが、広さは出雲大社の本殿の二倍以上ある。
社伝によれば、吉備津神社は、大吉備津彦の命(吉備津彦の命)を主神とし、異母弟若日子建吉備津彦(わかひこたけきびつひこ)の命と、その子の吉備の武彦(きびのたけひこ)とをあわせまつるという(以下、よく似たこの三人の名前が頻出するので区別すること。要注意)。
なお、『新撰姓氏録』では、吉備の武彦は、若日子建吉備津日子の命の子または孫とされている。
この文では、以下、子としてあつかう。
吉備津神社の名は、『延喜式』にみえる。いわゆる式内社である。
『延喜式』の神名帳では、備中の国賀夜(かや)郡の項に、「吉備津彦神社(名神大)」とある(「名神大」は、「名神大社」のことで、名神祭にあずかる社格をもった神社のこと)。

吉備津神社の社伝によれば、大吉備津彦の命は、吉備の中山のふもとに、「茅葺(かやぶき)の宮」をつくって住み、この御殿で、吉備の統治にあたったという。そして、281歳の長寿で、この宮に没し、吉備の中山のいただきに墓がいとなまれたという。
また、近世になってできた社伝によれば、仁徳天皇の時代に、大吉備津彦の命の五代の孫の、加夜の臣奈留美(かやのおみなるみ)の命、大吉備津彦の命の御殿であった茅葺の宮のあとに社殿をたてて、祖神をまつったのが、鎮座の起源であるという。その後も、加夜の臣の子孫が、吉備津の宮に奉仕した。神社の重職は、後代にいたるまで賀陽(かや)氏であった。
古来、朝野の崇敬は、すこぶる厚く、全盛の時代には、神職の数は、300人におよんだという。
吉備津神社は、はじめ備前、備中、備後の「三備の一の宮」とよばれた。つまり、吉備の国の一の宮であった。
一の宮は、各国で由緒があり信仰のあつい神社で、その国の第一位のものをいう。
吉備津神社は、吉備津彦神社または吉備津の宮ともいう。
■尾上車山古墳の被葬者は、若日子建吉備津彦の命か
相似形前方後円墳の性質からみて、注目すべき重要な古墳がある。
それは、「吉備の中山」の近く、岡山県岡山市尾上にある尾上車山古墳である。(前の「吉備中山」とその周辺の古墳の地図参照)
この古墳は前に示した「吉備氏と崇神天皇后妃関係の図」からうかがえるように、崇神天皇陵、中山茶臼山古墳などと、ほとんど相似形の古墳である。
尾上車山古墳は、岡山平野の中央に位置する「吉備の中山」の丘陵の南東先端に立地する大型前方後円墳である。
尾上車山古墳は、主軸全長が140メートルで、大吉備津彦の命の陵とされる中山茶臼山古墳の120メートルより、一まわり大きい。
これまでに円筒埴輪や形象埴輪の破片が採集されているが、内部主体(内部構造)や、他の出土物(副葬品)は不明である。
大塚初重他編の『日本古墳大辞典』では、中山茶臼山古墳を古墳時代前期のI期のあと寄りに、尾上車山古墳を古墳時代前期のⅡ期の前寄りに推定されている。つまり、ともに四世紀の古墳で、尾上車山古墳を中山茶臼山古墳にすぐつづく時期のものとされている。
尾上車山古墳は、中山茶臼山古墳のすぐ近くにあることや、中山茶臼山古墳と大略相似形古墳であることからみて、この古墳の被葬者は、中山茶臼山古墳の被葬者と密接な関係をもつことが推定される。
『古事記』『日本書紀』の記述から、そのような人物を求めれば、若日子建吉備津彦の命が浮かびあがってくる。
若日子建吉備津彦の命は、大吉備津彦の命の異母弟であり、『古事記』によれば、大吉備津彦の命と協力して吉備の平定にあたったとされている人物である。大吉備津彦の命よりごくわずか時代が下るとみられ、これは古墳の築造の前後関係ともあう。また、若日子建吉備津彦の命は、吉備津神社の祭神でもある。
さらに、若日子建吉備津彦の命は、吉備の武彦の父親である。
吉備の武彦の墳墓かとみられる備前車塚古墳が、尾上車山古墳よりも後の形式をもつことは、前に示した「吉備氏と崇神天皇后妃関係の図」などをみればわかる(備前車塚古墳が吉備の武彦の墳墓かとみられることについては、あとでのべる)。
ここでも、系譜の前後関係が、古墳の前後関係と合致している。
四世紀代の古墳で、中山茶臼山古墳に距離的に近く、中山茶臼山古墳とほぼ相似形で、しかも中山茶臼山古墳よりも規模が大きく、時代的にややあとかとみられる古墳の被葬者を求めるとすればやはり、まず第一に、若日子建吉備津彦の命の名に指を折るべきであろう。
なお、この例にみられるように、相似形古墳は、小さい古墳が、大きい古墳の模倣をしたとはかぎらず、大きい古墳が後出で、小さい古墳を模倣して、規模を大きくしていることがあることも、留意すべきである。
★『古事記』『日本書紀』の記述と考古学的事実との並行性
筑波大学教授の考古学者、岩崎卓也氏は、その著『古墳の時代』(教育社、1990年刊)のなかでのべる。
「弥生時代の墳丘墓が、地域によってさまざまな様態を示すのに対し、いわゆる古墳は全列島的規模で等質的である。この点にこそわが国の古墳にこめられた政治的意義があると考える近藤義郎教授は、墳丘墓から古墳を識別する特色として、つぎの三点を強調する(『前方後円墳の時代』1983年)。
(1)鏡の大量副葬指向。
(2)長大な割竹形木棺とそれを被覆する施設。
(3)前方後円という墳丘の定式化とその巨大性。
前方後円墳に象徴される古墳の広範な出現は、畿内の首長を頂点とする同族的関係で結ばれた首長連合の形成という、政治社会の成立を意味するのである。
『古事記』『日本書紀』などによれば、皇族将軍たちが、各地に派遣されている。大和朝廷に関係のある人たちが、各地に封じられている。
畿内を中心として全国へ普及していく前方後円墳という形式の共通性。そして、前方後円墳のなかには三角縁神獣鏡がしばしば埋められていることなどの埋納品の共通性。これらの共通性は、『古事記』『日本書紀』などの記述にもとづいて理解しうるものと、私は考える。
第14代仲哀天皇以前の第10代崇神天皇の時代の話などは、たんなる作り話とする山片蟠桃や津田左右吉などの話には、とても賛同できない。