------------------------------------------------------------------------
コラム 「三角縁神獣鏡(さんかくえんしんじゅうきよう)」とは?。 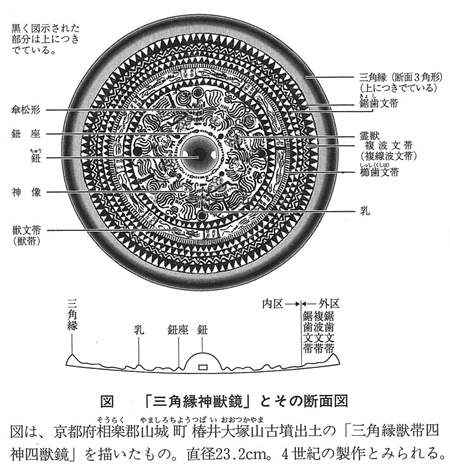
「三角縁神獣鏡」は「さんかくえんしんじゅうきょう」と読む人と、「さんかくぶちしんじゅうきょう」と読む人とがいる。
「三角縁神獣鏡」は、縁の部分の断面が、突出して三角形をなしており、かつ、神獣の模様の刻まれた鏡である。
右図は、京都府相楽(そうらく)郡山城町(やましろちよう)椿井大塚山(つばいおおつかやま)古墳出土の「三角縁獣帯四神四獣鏡|を描いたもの。直径23.2cm。4世紀の製作とみられる。
『魏志倭人伝』は、魏の皇帝が、倭の女王に、「銅鏡百枚」を与えたことを記している。京都大学の考古学者・小林行雄や、樋口隆康氏らは、卑弥呼が魏からもらった鏡は、この「三角縁神獣」鏡を主とする鏡であろうとする。
しかし、「三角縁神獣鏡」は、中国から出土した例がなく、また、確実な三世紀の遺跡からの出土例がない。四世紀以後の古墳時代の遺跡から出土する。鏡の直径も平均22センチほどで、中国でみいだされる後漢・三国時代の鏡よりも、ずっと大きい。そのため、森浩一氏、奥野正男氏などは、「三角縁神獣鏡」は、中国から輸入された鏡ではなく、わが国で作られた鏡であろう、と主張している。
----------------------------------------------------------------------------
■位至三公鏡(いしさんこうきょう)
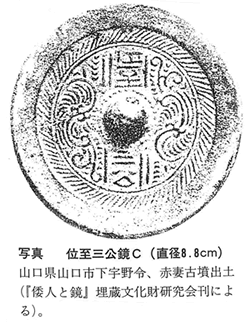
位至三公鏡は、「位は三公(最高の位の三つの官職)に至る」という銘のある鏡である。鈕をはさんで、上下に「位至」と「三公」の銘文をいれ、内区を二分する。
左と右とに、双頭の獣の文様を配する。獣の文様は、ほとんど獣にみえないことがある。小形の鏡である。
右図は 位至三公鏡(直径8.8cm)で、山口県山口市下宇野令、赤妻古墳出土(『倭人と鏡』埋蔵文化財研究会刊による)
下図は 「画文帯神獣鏡」の例
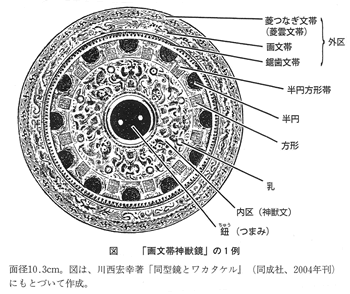
左図の画文帯神獣鏡は、
面径10.3cm。
川西宏幸著『同型鏡とワカタケル』(同成社、2004年刊)にもとづいて作成。
・位至三公鏡と画文帯神獣鏡の中国と日本の出土状況
(下図はクリックすると大きくなります)
・三角縁神獣鏡の中国と日本の出土状況
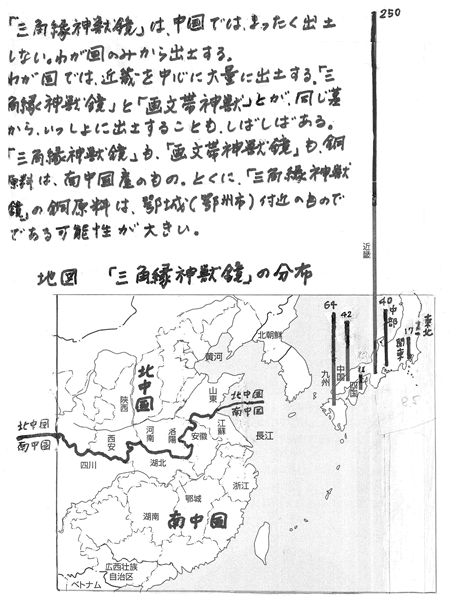
東晋の時代の都は、建康(南京)であった。長江流域の地である。
西晋時代の「位至三公鏡」などの、わが国での埋納年代が、320年~350年ごろとみられるから、「三角縁神獣鏡」のわが国での埋納年代は、そのあとの350年~400年ごろ、すなわち4世紀が中心とみられ、これは、東晋の時代である。
東晋時代の中国では戦乱などのために、鏡製造業は、不振であったとみられる。この時代の中国での鏡の出土数は、前後の時代にくらべてすくない。技術と原料とをもった東晋の工人たちは、生活のために、埋葬用の鏡の需要の大きかった日本へ来た可能性がある。
日本と東晋とは、国交があった。
日本へ来た東晋の工人は、『魏志倭人伝』を読んでいた可能性がある。
朝鮮の歴史書『三国史記』の「新羅本紀」の真徳王二年(648年)3月の記事に、新しく撰修された『晋書』を、唐の太宗が、新羅からの使者に与えた話がのっている(『晋書』については、644年ごろ成立説、646年成立説、648年成立説などがある)。太宗が『晋書』を与えた話は、『旧唐書(くとうじょ)』や『新唐書(しんとうじょ)』にものっている。
『魏志倭人伝』のおさめられている『三国志』の成立の時期は、西暦284年前後とみられている。東晋の工人がわが国へ来だのが、350年前後とすれば、『三国志』の成立から、およそ70年後である。東晋の工人が、『魏志倭人伝』を目にしていた可能性は、かなりあるようにみえる。
1965年に西域(せいいき)の吐魯番(トルファン)で、『三国志』の一部80行が発見された。西晋(265年~316年)時代のもので、紙に墨で書かれたものである。内容は、『呉志』の「孫権伝」の一部であった(中国の研究誌『文物』1972年第8期による)。
『三国志』の成立は、284年ごろであるから、成立後30年ほどのちまでには、西域にまでもたらされていたことがわかる。
吐魯番からすこし東の現代の鄯善(ぜんぜん)[ピチャン]からも『三国志』の一部が出土している。西晋の陳寿の編纂した『三国志』の原文に近いとみられている。
東晋の工人たちが、わが国へ来て、わが国での需要にあわせて「三角縁神獣鏡」を製作したものとしよう。すると、
(1)東晋の都の建康(南京)から西域の吐魯番までの距離に比べれば、建康からわが国の奈良県までの距離は、ずっと近い。直線距離では半分を少し超える程度である。
(2)西晋の時代(265年~316年)のうちに、『三国志』の一部が吐魯番までとどいているとすれば、東晋の時代(317年~420年)までに『三国志』がわが国にとどいていることは、十分ありうることのようにみえる。
(3)東晋の工人たちが日本に来たとすれば、当時の晋の国においての、日本に関する公的な基本情報の代表的なものといえる『三国志』の『魏志倭人伝』に目を通していた可能性は十分に考えられる。
「三角縁神獣鏡」は、わが国で古墳築造時に、その古墳の比較的近くで鋳造されたとみられる根拠が、それぞれ別の人によって、別の根拠によって主張されている。
■「三角縁神獣鏡」の、「古墳築造時鋳造説」
「三角縁神獣鏡」は、わが国で古墳築造時に、その古墳の比較的近くで鋳造されたとする見解は、私の知るところ、次の三つである。
(1)鈴木勉氏の見解
(2)新井宏氏の見解
(3)私(安本美典)の見解
まず、(1)の鈴木勉氏の見解は、鏡の鋳造技術面から見た発言である。
奈良県立橿原考古学研究所共同研究員で、工芸文化研究所所長の鈴木勉氏は、その著『三角縁神獣鏡・同位(型)鏡論の向こうに』(雄山閣、2016年)の中で、次のように述べている。
「三角縁神獣鏡の仕上げ加工痕が、出土古墳によって異なる、つまり、仕上げ加工技術が出土古墳ごとにまとまりを見せる。このことは鏡作りの工人らが出土古墳近くの各地に定住していたか、あるいは移動型の工人集団が各地の政権からの依頼を受けて各地へ赴いて製作にあたったか、を考えることになる。
「椿井大塚山古墳の『研削』鏡16面は、どれも同じ目の砥石を使って仕上げ加工されたことが分かる。湯迫車塚(ゆばくるまづか)古墳の3面の『研削』鏡には同じ細かい目の砥石が使われたことがわかり、佐昧田宝塚古墳の3面の『研削』鏡にも同レベルの細かい目の砥石が使われたことが分かる。」
「仕上げ加工の方法は、同範(型)鏡群よりも、出土古墳によって規定されている。」 三角縁神獣鏡製作の仕上げのさいの加工の技術が、出土古墳ごとにまとまりを見せる、というのである。
つまり、仕上げ加工の方法は、同位(型)鏡(工場でつくられた製品のように、同じ文様、同じ型式の鏡)でも、出土古墳が異なっていれば違いがあり、同じ古墳から出土した鏡は、異種の鏡でも、同じであるというのである。
また、数理考古学者の新井宏氏は、鏡の原料の銅にふくまれる鉛の同位体比について調べ、鈴木勉氏とまったく違う方法・根拠により、鈴木勉氏とほぼ近い結論を述べておられる(新井宏氏の見解は、『古代の鏡と東アジア』(学生社、2011年)に収められた論文「鉛同位体比から見た三角縁神獣鏡」に述べられている)。
・コピー鏡を作るさいの面径の変化に着目
私も鈴木勉氏や新井宏氏と、ほぼ同じ結論に到っている。ただ、そのような結論を導き出す方法、根拠は両氏とは、また異なる。
私の方法は、鏡のコピー鏡(同笵鏡、同型鏡、踏み返し鏡などといわれるもの)を鋳造するさいに、収縮や、拡大現象がおき、もとの鏡(原鏡、原型など)にくらべ、条件により、コピー鏡の面径が、大きくなったり、小さくなったりすることがあることに着目するものである。
「三角縁神獣鏡」には、コピー鏡が多いが、そして、同一古墳から、コピー鏡が数面出土することがあるが、ある鏡の、同一古墳から出土したコピー鏡では、面径が一致する傾向がみられ、異なる古墳から出土したコピー鏡のあいだでは、古墳ごとに面径が異なる傾向がみられる。このことに着目した議論である。
このような議論については、拙著『「邪馬台国畿内説」を撃破する!』宝島社新書、宝島社、2001年)や、『大炎上「三角縁神獣鏡=魏鏡説」』(勉誠出版、2013年)において、データを示し、ややくわしく論じた。
■森浩一氏、王仲殊氏の見解
日本と外交交渉のあった年の年号のはいった鏡が、日本からでている。
『魏志倭人伝』にでてくる景初三年や正始の記事は、『日本書紀』の神功皇后紀にも引用されている。古くから、日本人によく知られた年号であったようにみえる。
このことに関し、考古学者の森浩一氏は、つぎのようにのべている。
「今から十五年ほどまえに岐阜県の『荻の島の窯跡(かまあと)』の発掘がありました。この窯は明治十年代に日本最初の電気の碍子(がいし)を美濃焼で焼いていたのです。この窯では茶碗なども同時に大量に焼いていたらしく、その破片もたくさん出てきました。そのなかに中国の有名な年号が出てくるんです。日本の年号を書いたものは一つもありません。明治十年代に操業をしていた窯ですよ。宣徳年製とかいう二~三百年まえの有名な年号を書いた破片が、ぞろぞろ出てくるんです。
「有名な年号しか、とっていない。私たちが、年表ひいてやっとわかるようなものは、使わない。このように明治十年代の岐阜県の焼物屋さんでも、中国の有名な年号を堂々と使っている。」
「年号を、そういう風に見なおしてくると、たとえば『日本書紀』の割り注の中に、景初も正始もどちらも出てくる。もちろんあの割り注をいつ入れたかには問題はありますが、日本人が古くからよく知っていた国際関係での重要な年号だということ、少なくとも奈良時代の人はこのことを知っていた。奈良時代からいつまでさかのぼるかということは将来のこととしても、年号というのは、そういうような危険性のあるものだという資料にはなるわけです。だから年号にそのままとびつくのはあぶない。」
「またこんな経験もありました。京都では工事で、いろんなところの地下をよく掘ります。すると、どこを掘ってもよく出てくるのが『大明(だいめい)年製』と底に書いてある陶磁器の破片です。このあいだ僕の大学で、『大明年製』の類を集めさせたら百余りすぐ集まりました。ほとんどが日本のもので、中国製は二点か三点でした。この場合も中国製は、一割を切っていますよね。五%ぐらいと見ましょうか。あとは全部日本の各地の伊万里とか、清水とかの窯で作られたものでした。清水焼の窯元に丁稚奉公いたしますとまず『大明年製』と書くのを毎日稽古させられたと聞いたことがあるほどです。」
「そんな話を『朝日グラフ』に書きましたら、岐阜県の方がお手紙で『今でも、乾隆(けんりゅ)製と書いたラーメン鉢を焼いている。特別売出しの景品などに使うものです。」と言ってきてくださった。
乾隆は清の年号ですよ。荒物屋で一個四百円ぐらいで売るんだそうですが、現在も、焼いているんですよ。このラーメン鉢の年号の部分の破片を道路にでも落としておいたらどうなりますかね。ガンコな学者は『乾隆と書いてありますよ。乾隆は清の年号ですから中国製ですよ。これは』とおっしゃるでしょうね。」
「年号鏡の意味を解く場合は、突飛なようですが、現在の窯でなお乾隆年製のラーメン鉢が焼かれている、という事実も考え合わせなければいけません。鏡は鏡、ラーメン鉢はラーメン鉢と別けて考えてはいけない。どちらも同じ人間のすることです。」(『季刊邪馬台国』11号、36号)
そして、森浩一氏は、和泉黄金塚出土の景初三年銘の画文帯神獣鏡の年号について、「大和朝廷の支配者が自分たちの先祖を由緒あらしめるために、五世紀ごろになって作った鏡ではないか」という藪田嘉一郎氏の見解を、つよく支持している(「語りかける出土遺物」『邪馬台国のすべて』朝日新聞社、1976年刊)。(私は、前方部があまり発達していない古墳の形態などからみて、和泉黄金塚古墳を、四世紀の古墳であろうと考えるが、森浩一氏も、和泉黄金塚古墳の築造年代そのものは、四世紀末と考えておられる。)
王仲殊氏も、倭と魏とのあいだにあった重要な事件を知っている呉の職人によって、景初三年や正始元年の年号を記したものが製作されたのだという(『謎の鏡』同朋舎刊)。
■「景初四年鏡」について
『三国志』などの史書は、案外早くから遠くまでもたらされているようである。
そして、東晋の工人は、『魏志倭人伝』にみえる「其(そ)の四年」(これは、正始四年=西暦243年をさす)を、「景初四年」の意味に読みまちがえた可能性がある。
というのは、次のような例があるのである。
ずっと後の話であるが、清の時代に、康煕帝(こうきてい)の勅撰で1711年に成立した『類書(百科全書)』に、『佩文韻府(はいぶんいんぷ)』がある。その中に、本来存在しない年号の「景初四年」が、2度でてくる。一つは、さきの『魏志倭人伝』の「其の四年」を、読みまちがえたものである。いま一つは、『晋書』の「天文志」の文を読みまちがえたものである。『晋書』の「天文志」がまた、いかにも、「景初四年」のことと読みまちがえても、仕方がないような書き方をしているのである。
このようなことについては、奈良県立橿原考古学研究所の人倉徳裕(いりくらのりひろ)氏のくわしい考察「『晋書』に「景初四年」は存在しない」(『季刊邪馬台国』108号、2011年)、および、「『佩文韻府』の景初四年について」(『季刊邪馬台国』111号、同年)がある。『佩文韻府』は、勅撰の類書である。そうとうていねいに、校正が行なわれたはずである。それでも、誤りがおき、「景初四年」が、2度でてくるのである。
例がある、ということは、わが国出土の年号鏡にみえる「景初四年」もまたそうであろうという「証拠」にはもちろんならない。しかし、「畿内説」の「専門家」の論考においては、類似の事例もあげない断言が、かなりみうけられる。
たとえば、中国で確実な出土例が1面もない種類の鏡の「三角縁神獣鏡」が、わが国で400面以上出土するのは、中国で、わが国のために、特別に鋳造したからである、と主張する(「特鋳説」)。そのように主張するならば、せめて、他にも、中国で特別に作られて、他の国にとくに輸出されたもので、他の国からは、何百例も出土がみられるが、中国からは、まったく出土例がみられないような「事例」を、(できれば鏡の類で)あげてみていただきたい。
ある鏡のコピー鏡、孫コピー鏡、ひ孫コピー鏡などが、多数製作されているとすれば、鏡に、たとえば、「景初三年」という銘があったとしても、その鏡は、「景初三年」に鋳造されたとは、かぎらないことになる。「もとの鏡」と、「ひ孫コピー鏡」とは、鋳造時期が異なると考えられるからである。
げんに、わが国出土の島根県雲南市・神原神社(かんばらじんじゃ)古墳出土の「景初三年」銘鏡と、大阪府和泉市・和泉黄金塚古墳出土の「景初三年」銘鏡との銘文を比較すると、和泉黄金塚古墳出土の「景初三年」銘鏡の銘文は、神原神社古墳出土の「景初三年」銘鏡の銘文の文字を、文章の意味を理解せずに、ひろい取って並べた形をしている。文章としては、意味の通じないものとなっている。
あるいは、「文字」を、「文様」のようなものとみたのであろうか。
この二つの「景初三年」銘鏡は、鋳造の時期が異なるとみられる。そして、神原神社古墳出土の鏡が、一番もとの鏡であるという保証も、またない。別の鏡のコピー鏡である可能性もある。
このようにみてくると、鏡の「鋳造年代」は、その鏡の「埋納年代」にくらべ、情報がすくないとみられる。したがって、「鏡の年代」は、基本的に、「埋納年代」によって考察したほうがよいとみられる。
ちなみに、『日本古墳大辞典』(東京堂出版)を引くと、神原神社古墳の築造推定年代は記されていないが、和泉黄金塚古墳のほうは、「4世紀末から5世紀初頭ごろの築造と考えられる。」とある。景初三年(239年)からは、100年以上のへだたりがある。わが国出土の「年号鏡」(年号のはいった鏡)のうち、出土古墳の築造推定年代が、『日本古墳大辞典』に記されているものが、8例みられるが、それらは、すべて、「4世紀中葉ごろ」から、「5世紀中葉」のものである。これまでに述べてきた「三角縁神獣鏡」全体の推定埋納年代と一致する。
中国を代表する考古学者であった王仲殊は、「三角縁神獣鏡」は、中国の呉(222年~280年)の工人が、日本へ来て製作したものと考えた。
いっぽう、わが国の考古学者、森浩一は、呉の工人とは限らず、「江南系の鏡作り工人の渡来」によって製作されたと推定される鏡であるとする。
森浩一は述べている。
「弥生時代が終わって、前方後円墳が西日本のみならず東日本でも突如として造営される古墳時代になると、"謎の鏡"といわれる三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)が大流行した。謎といわれる理由は、日本の古墳に大量に出土するにもかかわらず、一部の学者が中国製、それも魏の鏡だという仮説を立て、中国に出土しないという事実を、考古学資料によってではなく言葉の操作でカバーしようとしているという点にある。だが、考古学の方法に徹すれば謎はどこにもなく、江南系の鏡作り工人の渡来によって、さらに弥生時代の発達していた青銅器生産の技術をも取り入れ、おそらく近畿地方が生産の中心になって大量に製作されたと推定される鏡である。この鏡は直径が22センチ前後で、同時代の中国の尺寸に直せば、ほぼ九寸の大型鏡である。」(『日本神話の考古学』朝日新聞社、1993年)
私も、「三角縁神獣鏡」は、中国の東晋(317年~420年、江南の建康「南京」に都をおいた)の工人が日本に来て製作した可能性や、東晋の工人の指導をうけた日本の鏡作り師が製作した可能性も、考慮にいれたほうがよいと考える。そのように考える理由は、以下のとおりである。
(1)「三角縁神獣鏡」のほとんどは、中国の東晋時代にあたるころの、わが国の古墳時代(布留式土器の時代)の、前方後円墳などから出土している。
(2)「三角縁神獣鏡」の銅原料としては、長江流域の銅が用いられている(鉛同位体比の測定分析による)。
「三角縁神獣鏡」を魏から与えられた鏡であると主張する人たちは、なぜ魏の鏡に、敵国だった呉の領域の銅原料が用いられているのかを、説明しなければならない。
これは、いわゆる「魏鏡説」がもつ大きな矛盾点の一つである。
■三角縁神獣鏡の生産構造
このような点などからみても、三角縁神獣鏡は、古墳がつくられたさいに、その近くで、鏡作り氏によって鋳造され、埋納されたとみるべきである。
そもそも、時代のさかのぼる平原遺跡のばあいでさえ、ほとんどの鏡を、日本で製作している。時代の下った墓で、その墓にうずめるためのほとんどの鏡を、そのたびに輸入品にたよるということが、あるであろうか。
あらかじめ輸入しておいて、死者がでるたびに遺族にくばったのであろうか。とすれば、大量の鏡を、どこかで保管していたことになるが、……?
やはり、死者がでるたびに、土師氏(はじし)のつくる埴輪などと同じように、鏡作り氏のつくる鏡も、葬具として、その地の近くで手工業的につくられたとみるべきである。
すなわち、生産構造として、つぎのようになっていた、と考えるべきである。
『魏志倭人伝』に、「(倭人は)租賦(租税とかみつぎもの)を収む」と記されている。倭人は、邪馬台国時代から、租税制度をもっていたのである。
そして、下図のような構造で、鏡作り氏が、鏡を製作していたと考えられる。
下図のいちばん下の、鏡作りの部民(べみん)は、ふだんは、農民として自営するが、特産物として、鏡作りの造(みやつこ)の指導のもとに、鏡をつくる。そして、それを現物租税としておさめる。
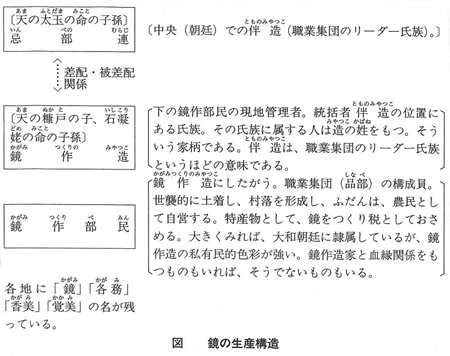
リーダー氏族の鏡作り氏は、中央(朝廷)の伴造(とものみやつこ)[職業集団のリーダー氏族]である忌部氏(いんべし)の指図(さしず)をうける形で、中央とつながっていた。
鏡作り氏は、各地に住んでいた。現在も、各地に、各務郡(かがみぐん)[岐阜県]、香美郡(かがみぐん)[高知県]、鏡作郷(かがみつくりごう)[奈良県田原本町(たわらもとちょう)などの地名があり、「鏡」「各牟(かがみ)」「各務(かがみ)」などというファミリーネーム(姓)があるのは、そのゆえである。
鏡作り氏は、もちろん、租税におさめる以外の鏡もつくった。
その土地の豪族がなくなれば、鏡作り氏は、租税としての鏡も収めたし、なくなった豪族の親族や、土地の他の豪族の注文をうけて現在の花輪にあたるものとしての鏡をつくったとみられる。
三角縁神獣鏡は、大きくて立派である。そのわりには、文様が形式化しており、銘文なども、意味が通らなかったり、不自然なものがあったりするのも、花輪的なものであったためとみられる。
また、鈕が鋳放しなのも、一つの墓にたくさん埋納されたりするのも、そのためとみられる。
さらに、つぎのような点も、このような考えを支持する。
(1)同一の古墳から、三角縁神獣鏡の同型鏡が出土することがよくある。ある形式の鏡の同型鏡においては、同一の古墳から出土したものは、面径の一致するものが多い。異なる古墳から出土したものは、面径の異なるものが多い。
これは、ある特定の古墳のばあいは、同じ毋鏡または原型(げんけい)[鏡のもとになる型]をもとにして、同型鏡が製作されているからである。異なる古墳から出土したものは踏み返し鏡[製作された鏡を毋鏡としてつくった孫コピー鏡、曾孫(ひまご)コピー鏡など]をつくるため、つまり、製作の時期が異なるため、鏡の大きさがちぢんだりして、(同型鏡でも)大きさが異なってくるのである。
これについて、よりくわしくは、拙著『「邪馬台国畿内説」を撃破する!』(宝島社新書、2001年刊)、『三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡か』(廣済堂出版、1998年刊)などを参照されたい。
なお、この私の見解には、批判もみられる。しかし、その批判は、統計的有意差検定による有意差と、たんなる統計的平均値の差とを混同したもので、問題にならない。
(2)これは、数理考古学者の、新井宏氏がのべているところであるが、つぎのような事実がある。
原料の銅にふくまれている鉛の同位体比をしらべ、新井宏氏はのべている。
「(わが国出土の年号鏡は、)同型鏡でも鉛同位体比が異なり同時期製作とは考え難い場合が多いのに対して、年号の異なる紀年鏡間でまったく同じ鉛同位体比を示す場合が二系列ある。」ここで、「二系列ある」という意味は、年号の異なる紀年鏡が、AとBとの二つにの系列分かれて製作されたということである。つまり、わが国出土の紀年鏡が、二回にわたり別々に製作された可能性が高い、ということである。鉛同位体比の異なる同型年号鏡は、踏み返し鏡であるため、同位体比が異なるものとなったとみられる。新井宏氏は、さらにのべる。
「中国においては、異なる年度の紀年鏡を同時に作ることはないと考えるので、この事実は、中国以外の地でこれらの鏡がコピーされた状況を強く示唆している。」
車崎正彦氏は、三角縁神獣鏡は、従来舶載鏡(中国からの輸入鏡)とされたものも、倣製鏡(日本でつくった国産鏡)とされたものも、すべて中国でつくられ、輸入された鏡であると説く。これについて、新井宏氏はのべる。
「とくに注目する必要があるのは、兵庫県城山(じょうのやま)古墳の例である。表(安本注。表は省略)に示した二例は共に車崎正彦氏が魏晋の倣古鏡として挙げているものであるが、両者の鉛同位体比が誤差もなく完全に一致しているのである。このことは、日本において同時に複製されたか、あるいは同時に製作されたことを強く印象付ける。魏晋鏡であるとすれば、不自然さを免れないからである。」
「さらに、このような状況は兵庫県鶴山丸山古墳の例を見ると、より明快にわかる。すなわち、鶴山丸山古墳から同時に出土した倣製鏡のうち、10面がまったく同一の鉛同位体比を示していて、同時に発注し、同時に入荷したとしか考えられない状況にあるからである。それらがすべて倣製鏡であることに留意すれば、城の山古墳の例も同様と考えられるのである。」
「なお、鶴山丸山古墳の10例の内には、倣製三角縁神獣鏡が2面含まれている。これらの2面も他の倣製鏡の鉛同位体比と同じ組成を示しているのであるから、同時に製作された可能性がきわめて高い。
そうであれば、車崎正彦氏の唱える『仿製三角縁神獣鏡も中国鏡』と言う説は成り立たない。
また、序論で長野県兼清塚(かねきよづか)古墳出土の斜縁二神二獣鏡が複製鏡である可能性が高いと述べたが、それは 同時に出土した内行花文鏡や画文帯神獣鏡と同じ鉛同位体比を持っていることから、いっしょに製作された可能性が高いと判断したことによっている。」(以上、『古代の鏡と東アジア』[学生社、2011年刊]による。)
新井宏氏が指摘している事実は、(1)の同一古墳出土の三角縁神獣鏡の同型鏡の面径の一致率が高いこととあいまって、三角縁神獣鏡にコピー鏡があり、古墳築造のさいに製作されていることを、強く示唆している。
車崎正彦氏のような議論をすればわが国出土の「画文帯神獣鏡」のほとんども、中国からの輸入鏡としなければならなくなるであろう。
「敵は何万ありとても」式の議論は、いさましくて、マスコミうけする。しかし、いさましいだけの解釈論は、空想と紙一重である。リアルの現実をみなければ、一億一心になっても戦争に勝てないことは、第二次世界大戦などで経験ずみのはずである。
なお、鏡作りで説明したような生産構造は、玉作りなどでも、同じであったと考えられる(下図参照)。
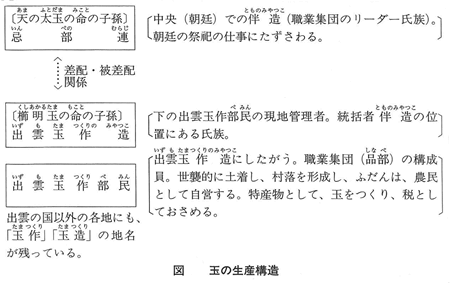 以前、海部俊樹(かいふとしき)氏という方が、総理大臣であったことがある。この海部という姓は、古代の海部氏と関係しているのであろう。
以前、海部俊樹(かいふとしき)氏という方が、総理大臣であったことがある。この海部という姓は、古代の海部氏と関係しているのであろう。
海部氏の部民は、ふだんは、農民として自営し、海産物をとり、製塩などを行ない、海部氏は、海産物や塩を、税として貢納していたとみられる。
各地に、海部(あま)郡(愛知県、和歌山県、島根県)、海部(あまべ)郡(大分県)、海部(かいふ)郡(徳島県)などがあるのは、海部氏の活動と関係があるとみられる。
「土師(はじ)」という地名が、仁徳天皇陵古墳や、応神天皇陵古墳の近くにのこっている。土師氏が大量の埴輪をつくったためとみられる。
大阪府は、もちろんのこと、徳島県、鳥取県、岡山県、栃木県、福岡県などの各地に、「土師郷」があるのも、鏡作りのばあいと、同じような事情によるとみられる。
鏡も、埴輪などと同じく、死者にささげるべくつくられた。葬儀のためにつくられた。死者の生前の使用物ではない。
このような生産構造は、わが国の古代においては、一般的なものであった。
奈良県の纏向遺跡やオオヤマト古墳集団の近くには、田原本町(たわらもとちょう)に、鏡作郷(かがみつくりごう)があり、神社がある。職業部である鏡作部に由来する地名である。
また、滋賀県野州郡の大岩山古墳からは、三角縁神獣鏡三面のほか、二面の鏡が出土している。大岩山古墳の近くの天王山古墳からも、三角縁神獣鏡一面と画像鏡類の鏡が一面出土している。そして、この近くに、「鏡村」があったことは、『日本書紀』の垂仁天皇の条にみえる。この地には、現在も、「鏡」「鏡山」「鏡口」などの地名があり、「鏡神社」がある。
つぎに、鏡の鋳造についての、古典の記述をみておこう。
■古典の記述
考古学者の小林行雄は、三角縁神獣鏡は中国で作られたもので、倭王権の中枢に保持され、服属のあかしとして、地方の首長に分配されたものであろう、と考えた。しかし、私は、三角縁神獣鏡を、日本の国内で作られたものと考える。そのばあい、三角縁神獣鏡は、だれによって、どのような形で作られたのだろうか。
いますこし、くわしくみておこう。
『古語拾遺』に、つぎのような記事がある。
「また、天の富の命(あまのとみのみこと)[太玉の命(ふとだまのみこと)の孫。太玉の命は、高皇産霊の命(たかみむすび)の子で、忌部(いんべ)氏[斎部(いんべ)氏]の祖神]をして、もろもろの斎部(いんべ)氏をひきいて、種々の神宝(かむだから)、鏡・玉・矛・盾・木綿(ゆう)・麻(お)などを作らせた。」(神武天皇の段)
「崇神天皇の時代にいたって、宮中にまつられていた天璽(あまつしるし)の鏡と剣とから天皇は威圧を感ずるようになられ、同じ宮殿に住むことに不安をおぼえられた。そこで、斎部氏をして、石凝姥(いしこりどめ)の神の子孫と、天の目一箇(あまのまひとつ)の神の子孫との二氏をひきいて、さらに鏡を鋳造し、剣を作らせて(レプリカを作らせて)、天皇の護身用のものとした。これが、いま、践祚する日にたてまつる神璽の鏡と剣である。」(崇神天皇の段)
これでみると、宮廷の祭祀をつかさどる氏族である忌部(斎部)氏が、石凝蛯の神の子孫(鏡作り氏)などをひきいて鏡を鋳造したという。鏡作氏は、職業集団をひきいる伝統のあるリーダー氏族[伴造(とものみやつこ)氏族]である。
『古語拾遺』は、斎部広成(いんべひろなり)の撰である。ここに引用した文は、中央での鏡作りの状況をつたえるものであろう。
東晋建国(317年)前後の動乱のさいに、食いつめた中国南部の優秀な工人たちが、鏡を尊重する伝統をもった倭国をめざして、大挙して渡ってきた可能性がある。
中国から来た工人などは、鏡には名を記していても(あるいは、鏡のなかに鋳こまれている名は、中国鏡に存在してた名を写しただけかもしれないが)、鏡作り氏などのリーダー氏族の配下に属し、身分的には、あまり高くなかったとみられる。
中国の官営の手工業の仕事場ではたらく一般の工人の身分は高くはなかった。実質的には工業奴隷(工奴)であった(これについては、『三角縁神獣鏡の謎』(角川書店刊)におさめられている中国社会科学院考古研究所の楊泓氏の見解を参照)。
今日の、エンジニアのステータスとはかなり異なる。
のちの時代のわが国の『律令』の「職員令」の「典鋳司(いもののつかさ)」などの条を読むと、この役所は「金銀銅鉄を造(つく)り鋳(い)ること」をつかさどるとしている。そこに配されている雑工戸(ぞうくべ)[雑戸(ざっこ)の一つ。雑戸は、律令制の諸官庁に隷属し、手工業その他の技術を必要とする労働に従事した人々]は、「古記・令釈(りょうしゃく)」によれば、「高(句)麗・百済・新羅の雑工人」などを配したという。のちの時代でも渡来人を配している。雑工戸は、世襲的な伴部(ともべ)[下級役人]の指揮・管理のもとに動いており、身分的には、高くない。唐では、雜戸は賎民であったが、わが国では良民の最下層の身分であった。
わが国の「雑戸」は、その職種に応じた特殊な姓(かばね)を付され[朝妻(あさずま)の金作(かなつく)り、など]、特別な戸籍(雑戸籍)に編入されていた。一般の公民籍と区別された。
『続日本紀(しょくにほんぎ)』の天平十六年(774)年二月の聖武天皇の勅に、雑戸の人に対して「なんじらの今負(お)う姓(かばね)[銅工(あかがねのたくみ)、鉄工(くろがねのたくみ)、金作(くがねつくり)、甲作(よろいつくり)、鞍作(くらつくり)など]は、人の恥ずるところなり。」とある。
当時のわが国は、氏姓制度の時代であった。
たとえば、海部氏(あまべうじ)というリーダー氏族がある。各地に、連(むらじ)・直(あたい)・臣(おみ)・首(おびと)・公(きみ)などの姓(かばね)の海部氏がいた。
■ここまでの議論をまとめ
ここまでの議論をまとめると、次のようになる。
a.卑弥呼の時代に、洛陽付近で、多量の「三角縁神獣鏡」が作られたのならば、次の西晋の時代に、西晋鏡の「位至三公鏡」などにまじって、「三角縁神獣鏡」がすこしは出土してもよさそうなものである。しかし、そのような事実は、みとめられない。
b.わが国での「三角縁神獣鏡」の出土状況をみると、「三角縁神獣鏡」は、総じて、「位至三公鏡」よりも、あとの時代の遺跡から出土する。
すなわち、「位至三公鏡」「双頭竜鳳文鏡」など、「いわゆる西晋鏡」は、とくに、北部九州の庄内式土器の時代の遺跡から出土するが、「三角縁神獣鏡」は、そのあとの、布留式土器(古墳時代)の遺跡から、近畿を中心に、大量に出土する。
「三角縁神獣鏡」が卑弥呼の時代に、わが国に与えられたものならば、その時代にあたる弥生時代や、庄内式土器の時代の遺跡から、「三角縁神獣鏡」が出土してもよさそうなものなのに、そのような事実はみとめられない。
c.銅にふくまれる鉛の同位体比の分析の結果からは、わが国出土の「三角縁神獣鏡」には、すべて、長江(揚子江)流域産の銅が、原料として用いられている。この点は、「位至三公鏡」など、「いわゆる西晋鏡」と同じである。北中国の洛陽などに、長江流域産の銅が流れこむのは、西暦280年に、呉の国が西晋の国に滅ぼされてから以後と考えられる。
「三角縁神獣鏡」がもし、卑弥呼の時代に、魏の時代に作られたものならば、中国北方の銅原料が用いられそうなものである。ところが、西晋時代の「位至三公鏡」などと同じく、長江流域系の銅原料が用いられている。
ここからは、「三角縁神獣鏡」が作られたのは、280年以後のこととなる。そして、「位至三公鏡」などの「いわゆる西晋鏡」よりも、さらにあとの時代に作られたもので あることになる。
銅原料ばかりでなく、「三角縁神獣鏡」の文様も、長江流域系の「画文帯神獣鏡」や「三角縁画像鏡」などに近いものがある。「三角縁神獣鏡」は、「画文帯神獣鏡」と「三角縁画像鏡」の特徴をあわせもつ。中国の考古学者、王仲殊は述べている。
「日本の三角縁神獣鏡は、基本的には、中国の平縁(ひらぶち)神獣鏡を参照してつくられ、同時に中国の三角縁画像鏡をも参照してつくられたものと言えるのです。
しかも、中国の平縁神獣鏡と三角縁画像鏡が、ともども呉の鏡であったことからしますと、日本の三角縁神獣鏡と中国の呉鏡との間には、つながりがあった、とりわけ長江下流の会稽郡の呉鏡と密接なつながりがあった、とはっきりと言えると思います。」(王仲殊「日本の三角縁神獣鏡について」(王仲殊ほか著『三角縁神獣鏡の謎』角川書店、1985年所収)
d.わが国で出土する鏡に、「三角縁神獣鏡」の仲間の、「三角縁仏獣鏡」がある。「仏像鏡」の一種である。
ところで、「仏像鏡」は、中国の華北からは、まったく出土例がない。長江中流域の鄂城市(湖北省にある。1983年から鄂城県と合わさり鄂州市)付近から何面も出土している。また、わが国出土の「三角縁仏獣鏡」のうち、2面については、鉛同位体比が測定されている。それらを見れば、「三角縁神獣鏡」と同じく、鄂城市付近の銅原料が用いられているとみられる。これは、なぜなのか。d.は、c.と関連する問題のようにみえる。
e.中国と日本とでは、鏡の使用目的が違う。中国では、死者生前の使用品が、墓にうずめられた(あの世でも使ってもらうためかとみられる)。そのため、中国で出土した鏡は、一般に、あまり大きくない(大きいと重くて、もち運びに不便である)。
また、一つの墓に埋納される鏡は、1、2面がふつうである。
日本では、鏡は、「葬具」として、いわば、花輪的に用いられた。そのために、立派にみえるように、面径のより大きな鏡が埋納されるようになった。また、何人かの人がささげるために、一つの墓に何面もの鏡が埋納されるようになった。そのさい、築造される古墳の近くで、同じ鏡作り師(集団)に、製作を依頼するため、同じ鏡(同笵鏡、同型鏡)が何面も、一つの墓に埋納されることが起きるようになった。
なお、「土師(はじ)」という地名が、仁徳天皇陵古墳や、応神天皇陵古墳の近くにのこっている。土師氏が大量の埴輪を作ったためとみられる。
大阪府は、もちろんのこと、徳島県、鳥取県、岡山県、栃木県、福岡県などの各地に、「土師郷」がある。
鏡も、埴輪などと同じく、死者にささげるべくつくられた。葬儀のためにつくられた。
死者の生前の使用物ではない。
奈良県の纒向遺跡やオオヤマト古墳集団の近くには、田原本町(たわらもとちょう)に、鏡作郷(かがみつくりごう)があり、鏡作神社(かがみつくじんじゃ)がある。職業部である鏡作部に由来する地名である。
また、滋賀県野洲郡の大岩山古墳からは、三角縁神獣鏡3面のほか、2面の鏡が出土している。大岩山古墳の近くの天王山古墳からも、三角縁神獣鏡1面と画像鏡類の鏡が1面出土している。そして、この近くに、「鏡村」があったことは、『日本書紀』の垂仁天皇の条にみえる。この地には、現在も、「鏡」「鏡山」「鏡口」などの地名があり、「鏡神社」がある。
■「三角縁神獣鏡」をめぐる諸氏の見解
早稲田大学文化財整理室調査員の考古学者、車崎正彦氏は、日本で出土しているすべての三角縁神獣鏡は、中国からもってきた「舶載鏡」であるとする。
2015年になくなった中国を代表する考古学者、王仲殊氏(中国の社会科学院の考古研究所は、「三角縁神獣鏡」などは、中国で作られたものではなく、中国の工人が、日本に渡ってきて、日本で作ったものである、とする説をかねて述べてこられた方であった。
王仲殊氏は、さきの車崎正彦氏の説には、いささかあきれたようで、「破天荒な新説」「仿製三角縁神獣鏡まで中国伝来の『舶載鏡』であるという驚くべき説」とし、つぎのようにのべる。
「三角縁神獣鏡は全て中国鏡であるという車崎氏の新説によれば、230・240年代から三世紀末ないし四世紀前・中期までの期間において、中国王朝は倭王のために特鋳品として三角縁神獣鏡を作り続けたことになる。これはまことに長い期間であり、しかも、この間には『八王の乱』や『永嘉の乱』などの大動乱があった。それにもかかわらず、魏王朝の後を継いだ西晋王朝が倭のためだけに三角縁神獣鏡を特鋳し続けたなどということを信じることができるだろうか。」(王仲殊「仿製三角縁神獣鏡の性格といわゆる舶載三角縁神獣鏡との関係を論ず(上)(下)」『東アジアの古代文化』102号、103号、2000年・冬号、2000年・春号)
車崎正彦氏は、可能性として、どんなにありそうにないことでも、ありうるとして、説をたてているのである。
考古学者の森浩一氏は、車崎正彦氏の説について、1999年4月1日付『朝日新聞』夕刊の記事のなかでのべる。
「三角縁神獣鏡が中国で発見されていないことをどう説明するのか。これまでの研究の歴史や方法を無視しており、認め難い。」
正論である
森浩一氏はまた、『週刊 日録20世紀』(講談社刊)の1999年8月3日号の「20世紀の発見・発掘物語」で、つぎのようにのべている。
「いまだに三角縁神獣鏡は全部魏(中国)で製作された、などと主張する人がいますが、研究史の上での汚点やね。」
王仲殊氏はまた、京大教授であった考古学者の樋口隆康氏との議論のなかでのべる(『三角縁神獣鏡と邪馬台国』梓書院、1997年刊)
「樋口先生は事実が大事だということでありますが、何が事実かということです。たとえば銅鏡の上に、黄初という二文字があるから、これは魏の鏡だ。これだけが事実でしょうか。そうではないと思います。事実ということであれば、中国では一個も三角縁神獣鏡が出てないわけです。この事実を樋口先生はどう思っておられるかということです。もちろん、樋口先生は1957年に中国に行って、いろんなところに行かれましてご苦労されましてそれでも見つからなかったわけです。
樋口先生は1953年から銅鏡の研究を始められ、私は51年から日本の富岡謙蔵先生や梅原末治先生の銅鏡の本などを読むようになりまして、その後、後藤守一先生の漢式鏡などの本を見て研究しました。で、樋口先生が中国で探しても見つからなかったわけです。私も一生懸命三角縁神獣鏡を探しました。私も最初は、見つからないことを望んでいたわけではなく、見つかることを望んでいました。そして、二十年余りの長い期間中に、あちこちに行って探しました。80年代に、私は考古学研究所の所長として、全国の考古学研究者に三角縁神獣鏡を探して欲しいと呼び掛けました。樋口先生が57年に探されたのと同じように、私もずっと探し続けましたが、一面も見つかりません。
でも、三角縁神獣鏡というものは、写真でも見ましたし、アメリカでも見ました。日本から伝わったものがアメリカにあるのですが、それも見ました。その後京都に行って、樋口先生から多くの三角縁神獣鏡を見せていただきました。見ましたら、中国の銅鏡とは、あまりにも違うということに気づきました。つまり、作風が全然違っています。中国に三角縁神獣鏡がないということは、もちろん問題ないと思います。そして日本の先生方も、もう中国で探す必要はないと思います。
私が三角縁神獣鏡についての最初の論文を出してから十六年になりますが、中国の全ての博物館などは、王仲殊というのが、中国には三角縁神獣鏡がないという論説を出していることを、みんなもう知っています。日本の先生方が中国で見つかることを望んでいることも、みんな知っているわけです。ですから博物館の人たちは、何とか自分のところで三角縁神獣鏡を見つけようと、努力しているわけです。一個でも見つかれば、まず樋口先生に、宝だと言って捧げるんではないかと思います。
ですから皆さん、もう心配しなくていいです。中国には考古学者がたくさんいますが、何が三角縁神獣鏡か知らない人がいっぱいいるんです。おかしいと思われるかもしれませんが、これはおかしいことではないんです。なぜかというと、中国にないからです。知るわけがないのです。
2015年の2月24日(火)の、『読売新聞』に、明治大学教授であった大塚初重氏の著書『日本列島発掘史』(2014年KADOKAWA刊)の書評がのっている。
つぎのようなものである。 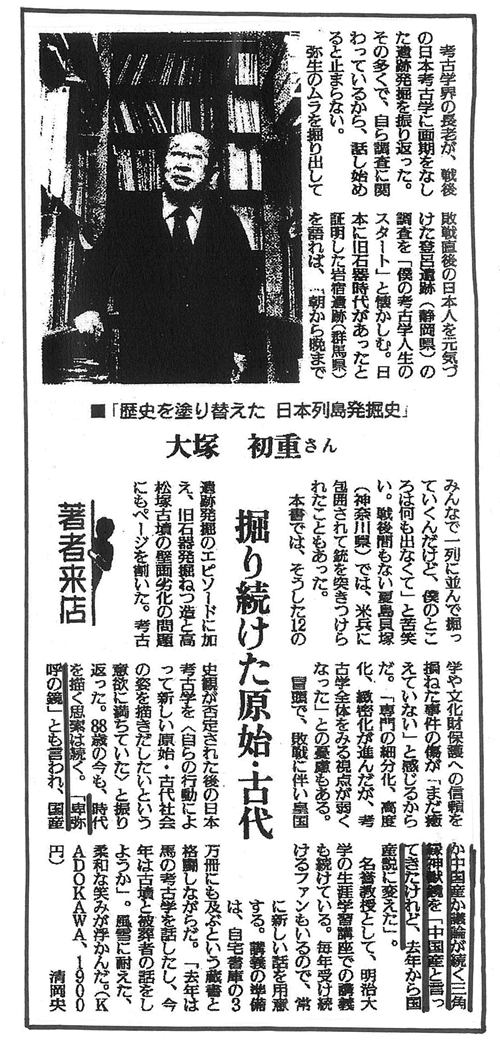
この記事のなかに、次のような文章のあることが、注目される。
「『卑弥呼の鏡』とも言われ、国産か中国産か議論が続く三角縁神獣鏡を『中国産と言ってきたけれど去年から国産鏡に変えた』。」
■河上邦彦氏、石野博信氏、原口正三氏の見解
33枚の三角縁神獣鏡が出土した奈良県の黒塚古墳の発掘の計画者であり、直接の指揮者である奈良県立橿原考古学研究所調査研究部長の河上邦彦氏は「三角縁神獣鏡が『卑弥呼の鏡』などということはありえない」「ヤマト政権が作り出した鏡に違いない」と、『産経新聞』1998年1月16日付朝刊の記事のなかで、明言している。
三角縁神獣鏡は、「葬式に使った葬具」で、「ヤマト政権が、配下の豪族の死にあたって葬具として分け与えたのだろう」と、河上氏はいう。
河上邦彦氏は、『東アジアの古代文化』の1998年春・95号の、「黒塚古墳発掘の意味」という鼎談(ていだん)の中で述べている。
「ここでしっかりと書いておいて欲しい。新聞に書かれた各説がウソばかりだと(笑)。」
そして河上邦彦氏は、冗談のような感じで、三角縁神獣鏡問題を考えるうえで、きわめて重要な意味をもつとみられる発言をしている。
「京大には椿井大塚山古墳の鏡が保管され、その関係者はその鏡を十分見ることができた。三角縁神獣鏡は、重く、大きく、文様がすばらしい。これは舶載鏡だと信じ切ったら、もうそのままで来ている。京大の関係の人たちでどうも舶載鏡説が高いのはそのへんに原因するのではないか。」
京都大学は、近畿にある。かつての王城の地である。近畿を発掘すれば、当然、多くのものが出土する。地の利か与えられている。発言の機会も与えられやすい。
「何年も研究したエライ肩書の専門家が、あれだけ断定的にのべるのだからそうとうな根拠があるのだろう」と、マスコミも、ふつうの人も思ってしまうだろう。しかし、マスコミを通してのPRばかりがあがって、その実体がない。
「邪馬台国=畿内説」の考古学者、石野博信氏も、98年の『歴史と旅』4月号所載の「”卑弥呼の鏡”ではない」の中で、次のように述べている。
「(三角縁神獣鏡は)ヤマト政権が弥生以来の祭式を廃止し、中国鏡をモデルとして、四世紀にヤマトで創作した鏡なのである。」
「平成十年と年が改まって早々の1月9、10日は、橿原考古学研究所と天理市教育委員会によって調査された黒塚古墳出土の三十二面の鏡の報道でもりあがった。その後、1月23日に”鏡の取り上げは終了した”と報道されるまでの十三日間は、17、18日の現地説明会をはさんでマスコミ各社とも黒塚報道が続いた。ある調査員の。”これは(文化現象ではなく)社会現象だ”というつぶやきは、まさにその通りだと思う。
なぜそうなったのか。三角縁神獣鏡は、倭国の女王卑弥呼が西暦239年に魏の皇帝から貰った鏡だ、という学説をマスコミがそのまま信じたからだ。確かに『魏志倭人条』には、他の品々と共に『銅鏡百枚』を賜う、と書いてあるけれども、いま考古学界で三角縁神獣鏡とよんでいる鏡が、これに相当するかどうかはまだ結論が出ていない。
それなのに”邪馬台国の鏡””卑弥呼の鏡”として、連日大見出しで報道した全マスコミの罪は大きい。たとえ本文で、非中国鏡説があると書いていても、読者は見出しの大きさに圧倒されてしまうし、圧倒しようという意図がまる見えである。
私は、現地で三角縁神獣鏡が二十面をこえたと聞いたときに、これは中国からの輸入鏡ではないと、感じた。なぜか。」
「大和(おおやまと)古墳集団には、二十七基の前期前方後円(方)墳がある。そのうち黒塚古墳と同等以上の全長120メートルをこえる古墳が十八基ある。十八基の古墳がすべて三十面の三角縁神獣鏡をもっているとすれば、この地域だけで540面が埋もれていることになる。(「魏志倭人伝」で卑弥呼が賜ったとする)「銅鏡百枚」をはるかにこえてしまう。全長200メートルをこえる四基の大王墓が、一基で百面をこえる三角縁神獣鏡をもっていたとすればどうなるのか。
このような単純計算に対して、中国鏡論者は、黒塚古墳や三角縁神獣鏡三十二面が出土した京都府山城町の椿井大塚山古墳の被葬者は、鏡配布にかかわる職務を担当していたから多量に保持していたが、他の職務の人はそうとは限らないという。
たまたま調査した二つの古墳被葬者が鏡の配布担当者というのも都合がよすぎる考えだし、両者で六十面以上の『中国鏡』を保持するのは、どう考えても持ちすぎ、隠匿のしすぎである。三角縁神獣鏡は、大王から配布を命ぜられた公器だというのだから。
以上のように、今回の黒塚古墳調査の大きな成果の一つは、三角縁神獣鏡が邪馬台国とはなんら関係ないことが判明した点である。」
石野博信氏は、共著『邪馬台国研究新たな視点』(朝日新聞社、1996年)の中で、次にまとめられるような見解も述べておられる。
(1)京都の椿井大塚山古墳は、土器からすると、どうみても4世紀の中ごろから4世紀後半ぐらいのものではないかと思われる。
(2)椿井大塚山古墳から、三角縁神獣鏡が三十数面出土している。
(3)3世紀の三角縁神獣鏡が、だれでも認める形ででてこない。3世紀だと考えた三角縁神獣鏡をもつ古墳は、かなり努力して古くしている方のものである。
(4)椿井古墳の三角縁神獣鏡と同じ型で作った鏡を、いくつかの古墳で分有するようになるのは、4世紀中葉以降であると考えられる。それは、前方後円墳が、東北から九州まで全国的に広まった段階と一致するのではないか。
このように、「三角縁神獣鏡」は、「位至三公鏡」など、「いわゆる西晋(265年~316年)の鏡」のあとで、中国の東晋(317年~420年)の国の時代にあたるころに、わが国でのみ出土する鏡なのである。
前掲書『邪馬台国研究新たな視点』の中で、石野博信氏は述べる。
「あれ(三角縁神獣鏡)を勉強しなくても卑弥呼のことがわかる。後のことなのだからあれは無視していいと考えればいいのではないかと思っている。
京都大学を卒業した人でも、京大考古学のエスタブリッシュメント(既成勢力)の見解に、したがわない人たちがいる。
そのような考古学者の一人、原口正三(はらぐちしょうぞう)氏は、高槻市教育委員会編『邪馬台国とか安満宮山(あまみややま)古墳』(吉川弘文館、1999年)におさめられた「基調報告 三角縁神獣鏡から邪馬台国を解く」の中で述べている。
「要は、三角縁神獣鏡は中国にも朝鮮にも一枚もない。これは皆さん、ひとつ肝に銘じておいていただきたい。」
「卑弥呼がもらった鏡は二〇センチを超えるようなものではなくて、直径十数センチまでの小さいものだった。三角縁神獣鏡は、その後、それをモデルにして大量生産をした。そうでなければ、同じ地域で十回も順番をつけて同じ鋳型からつくるという追いかけ鋳型は、製作地でないと出てきません。」
「梅原末治先生は、富岡謙蔵(とみおかけんぞう)さんの後を受けて鏡の研究をされた方ですが、先生の書かれた本を読むと、大正時代から昭和十五年ぐらいまで、全国の鏡の集成をやったり枚数をそろえたりされています。そのころから、ほかの鏡に比べて三角縁神獣鏡はとびきり枚数が多いわけです。現在、朝から晩まで全国で各自治体にいる職員が血眼になって調査をしていますから、ますます鏡の枚数は増えるだろうと思います。それを、あくまであれは魏でつくったのだと言い張っているのは、もう信仰にも近い考え方だろうと思います。」
以上を要するに、「邪馬台国畿内説」は「宣伝」があって、「証明」がない。あるいは、そこで取られている方法が、「証明」になるということじたいの「証明」がない。「証明」ということばについてのメタ説明が必要である。
なにが「証明」になるのか、不明なままでは、「証明」は、できないではないか。
京都大学の考古学では、どうも、梅原末治、小林行雄、樋口隆康諸氏の流れをくむ人しか、京都大学の先生になれないようである。多様性が失われているようにみえる。
今後、「邪馬台国問題」を解決するためには、「京大考古学の体質問題」を検討する必要がでてくるであろう。
先生や先輩たちの語っていることが正しいのではない。本来、「過去」じしんの語っていることが正しいのだ。
原理主義者、ルターは述べた。「聖書にかえれ」と。それにならっていえば、「過去じしんにかえれ」ということになる。
牧師は、キリストの教えにかえる方法を教えてくれなければならない。先生や先輩は、「過去」が語ることにかえる方法を教えてくれなければならない。
私たちは、ともすれば、誰かの語ることにしたがう「属人主義」になりやすい。
以上によって、「邪馬台国問題」が、なぜ解けないのか、その理由がおわかりいただけたであろうか。
私も、京大卒業生の一人として、この章の最後に、一言記そう。
「ねえ、君たち、巨大な迷路を掘っているよ!」







