古代の日朝関係の研究には、きわめて大きなダブーがある。しかし、そのタブーに触れなければ、真実の古代の姿は見えてこない。そのタブーの存在には、はなはだもっともな理由がある。
そのことについて考える。
朝鮮半島で発見された「前方後円墳」の存在する場所は、いずれも、『日本書紀』『宋書』『広開土王碑文』などの史書・史料になんらかの形で、倭人の足跡のあったことが記されでいる場所である。
そのことの意味をたずねる。
津田左右吉によって代表されるような十九世紀的文献批判学の方法に固執し、『古事記』『日本書紀』などを、歴史史料として用いることを、頭から拒否しているような研究は、現代の世界基準の「歴史学」に達しているとは、認められない。
ただし、そのような、「前前世紀的」な立場に立つ人々の業績であっても、正確な発掘にもとづく、出土資料についての正確な記述は、「記述考古学」としての高い価値を有しうることに留意すべきである。
「文献学」と「考古学」とは、「歴史学」という車にとって、欠くことができない両輪である、「記述考古学」だけでは、現代の「歴史学」といえるものに達しているとは、認めがたい。
■402年前後の史実
神功皇后や広開土王の活躍年代の中心年代と推定される402年前後の史実をみてみよう。次のようになる。下の地図(「地図 倭の最大侵攻領域と、領域が時代とともに失われて行く状況」)参照。
(下図はクリックすると大きくなります)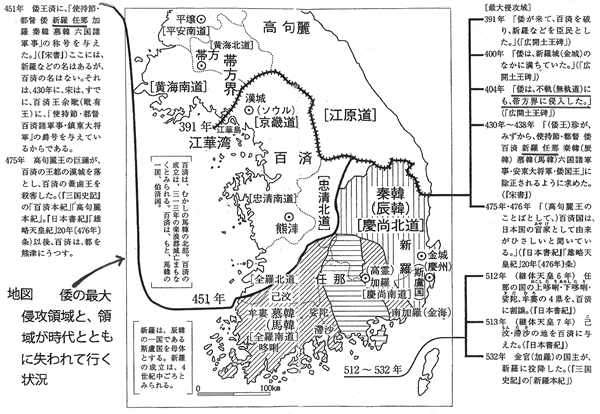
(1)400年、「倭は新羅城(新羅の王都・金城〔慶州〕)に満ちていた。」(『広開土王碑碑文』)
(2)402年、「新羅の王子、未斯欣(みしきん)が、倭の人質となった。」(朝鮮の歴史書『三国史記』の「新羅本紀」)。そして、新羅の王子、微叱己知波珍干岐(みしこちはとりかんき)が、日本の人質になった話は、『日本書紀』の「神功皇后紀」にも記されている。この未斯欣の話と微叱己知波珍干岐の話とは、ふつう、同一の話の異伝とみられている。
(3)404年、「倭は不軌にも(無軌道にも)、帯方界(むかし、帯方郡のあった地域)に侵入した。」(『広開土王碑碑文』)
(4)407年、広開土王は、倭と合戦し、「斬殺蕩尽」した。(『広開土王碑碑文』)
(5)413年、倭王「讃(第15代の応神天皇のことか)」あり。(『晋書』の「安帝紀」、『南史』の「倭王伝」など)
(6)451年、倭王済(第19代の允恭天皇か)を、「使持節・都督 倭(わ) 新羅(しらぎ) 任那(みまな) 加羅(から)[任那(みまな)の一国、または任那と同じ意味に用いられている場合もある]・秦韓(しんかん) 慕韓(ぼかん) 六国諸軍事・安東将軍」にしている。つまり、倭の軍事支配権が、新羅などにまで及んでいることを、客観的存在である中国の宋がみとめている。(『宋書』「倭国伝」、『南史』「倭国伝」など)
この間の状況について、京都府立大学名誉教授の坂元義種氏は、その著「倭の五王」(教育社、1981年刊)のなかで、つぎのようにのべている。
「好太王(広開土王)碑文によると、倭軍は高句麗によってさんざん敗られたことになっているが、実際はかならずしも『倭寇、潰敗(かいはい)し、斬殺すること無数』というわけにはいかなかったようである。倭軍が何度となく出兵して高句麗軍と戦っていることは、高句麗側が決定的な勝利をおさめることができなかった証拠といってよかろう。また、『三国史記』によると、実聖尼師今(にしきん)元年(402)三月、新羅は倭国と好(よし)みを通じ、奈勿王(なぶつおう)の王子未斯欣(みしきん)を人質として倭国に送ったという。これは高句麗の庇護(ひご)だけでは迫りくる倭軍の脅威を払いのけることができなかったことを示しており、これもまた朝鮮半島における倭の勢力を物語るものであろう。
百済や新羅の王族が人質として倭国に送られている事実や、たび重なる倭軍と高句麗軍との戦闘を考慮するならば、好太王碑文の『倭、辛卯の年を以て来りて海を渡り、百残(ひゃくざん)[百済のこと]口口(二字欠落か)新羅を破り、以て臣民と為す』という記事がまったくの妄言(ぼうげん)ではないことが理解されるであろう。
倭国王が『使持節、都督倭(わ)・百済(くだら)・新羅(しらぎ)・任那(みまな)・秦韓(しんかん)・慕韓(ぼかん)六国諸軍事、安東大将軍、倭国王』とか、『使持節、都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓七国諸軍事、安東大将軍、開府儀同三司(かいふぎどうさんし)、倭国王』などと自称して、倭国だけでなく朝鮮半島南部の軍事的支配を主張した歴史的背景の一端はここにあるのである。
新羅が王族を人質として倭国に送ったのは、倭との軍事的対決を回避するのが目的であったかもしれないが、他面、見方によっては、新羅が倭と結び、高句麗の軍事的支配から脱却しようとした試みであったとみることもできる。後者の見方を重視するならば、倭国王の自称称号は、倭国王がみずからを強敵高句麗と対決する最高軍司令官---倭と朝鮮半島南部(以下、韓と略称)諸勢力の最高軍司令官---に位置づけたものとみることができよう。」
広開土王(374~412。在位は391~412)は、古代の朝鮮半島から中国東北地方にかけて栄えた高句麗第19代の王である。好太王(こうたいおう)ともいう。一代の英傑といってよい。
広開土王が18歳のとき、父の故国壌王(ここくじょうおう)が没したので、王位を継いだ。まもなく、百済を攻めて、漢江以北の地を奪った。396年、ふたたび百済を攻め、日本・百済の連合軍を破って、百済の王都に迫った。かくて、朝鮮半島の大部を支配下におさめた。 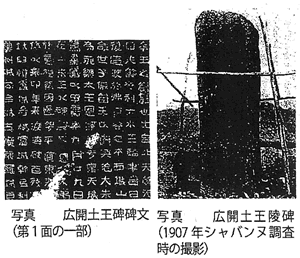
あとを継いだ長寿王により、広開土王の死後二年(414年)に、広開土王の功績を記した石碑が、鴨緑江岸の、通溝(中華人民共和国の吉林省集安県の地)東北方六キロメートルのところに建てられた。広開土王の陵を守護するためのもので、高さ6.3メートルの巨碑である。この碑文は、1884(明治十七)年に、わが国の学界に紹介された。四世紀末から五世紀はじめにかけての同時代史科である。
その碑文は、碑の四面にきざまれ、41字詰44行、約1800字からなる。
■「獲(う)るところの鎧甲(がいこう)一万余領」
「広開土王碑の碑文」によれば「倭人は、新羅の国境に満ち」ていた。
西暦400年に、好太王は軍令を下し、歩騎五万を派遣して、新羅を救った。
高句麗軍が男居城から新羅の国城にいたると、倭がその中に満ちあふれていた。
高句麗軍がいたると、倭賊は退去した。
しかし、その四年ののちの404年に、「倭は不軌(ふき)[無軌道]にも、帯方界(もとの帯方郡のあった地域)に侵入」した。
帯方界といえば、現在の京城から、その北のあたりをさす。倭は、朝鮮半島の、そうとう奥地にまで侵入しているのである。
「広開土王碑の碑文」は記す。
「好太王の軍は、倭の主力をたち切り、一挙に攻撃すると、倭寇は潰滅し、(高句麗軍が)斬り殺した(倭賊は)無数であった。」
さらに、407年、好太王は、「軍令を下し、歩騎五万を派遣して」、「合戦して、残らず斬り殺し、獲るところの鎧狎(よろいかぶと) 一万余領であった。持ち帰った軍資や器械は、数えることができないほどであった。」
朝鮮に侵入した倭は、正規の高句麗軍五万と、くりかえし戦う力をもつ、万を超える大軍であった。
■神功皇后の実在説
東大の日本史家、坂本太郎は、つぎのようにのべている。
「この伝説(神功皇后の新羅征伐についての伝説)には神秘的な童話的な要素の多くの混在が見られるとはいえ、畢竟その時代、我が武力が南朝鮮に及び、之をして服従せしめた事実を核心としていることは疑いない。」(『大化改新の研究』至文堂刊)
神功皇后の物語を机上でつくられた物語であると説く説は、文献学的、考古学的にみて、つぎのような数多くの不自然な点をもつ。
(1)神功皇后が、新羅を征討したとする伝承は、『古事記』『日本書紀』『風土記』『万葉集』などの主要な奈良時代文献が、こぞって記し、また『続日本紀』『古語拾遺』『新撰姓氏録』など、平安時代以後の諸文献も、昔あった事実であると受けとった書き方をしている。また、とくに九州を中心とする諸社の縁起、各地の地誌、あるいは伝説において、神功皇后と結びつけられたものは、きわめて多い(神功皇后に関する各地の伝承などについては、河村哲夫著『神功皇后の謎を解く』[原書房、2013年刊]にくわしい)。
宇佐神宮や香椎廟の伝えなどが示すように、古くから数多くの民間伝承があった(たとえば、『八幡宇佐宮御託宣集』や『八幡愚童訓』などに見える「住吉縁記云、大帯姫(おおたらしひめ)[神功皇后]新羅軍(いくさ)之時」「大帯姫為降伏異国」「我国ノ我国タルハ、皇后ノ皇恩也」など)。
神功皇后の物語が、「創作された」のが、史的事実であるというのであれば、その「創作された」という史的事実じたいを記している文献などを示すべきである。
文献的根拠はなにもなしで、多数の古代文献に記されていることを否定し、「創作された」という新たな史実をつくりだすのは、論理的に正しい方法といえるであろうか。「創作」説はひっきょう想像説を出ない。「創作説」こそ、文献的な根拠のない「創作」である。日本史家、横田健一 (関西大学教授など)も、論文「神功皇后の系譜について」(『神功皇后』所収)のなかで、つぎのようにのべている。
「広汎な伝承、とくにそれが『風土記』のように、かなり広い地域にわたって民間伝承として浸透するには、現代のようにマスコミの発達していない時代では、相当の年月を要するものとみなければならない。」
「もし、応神なり神功なりが架空の人物であり、そうした人物に付会した諸氏族の伝承がつくられるとすれば、諸氏族ごとに、その伝承の付会、形成過程が、証明されねば、ほんとうに証明したとはいえない。」
(2)中国の『宋書』などをみれば、倭王武などは、「使持節・都督 倭 新羅 任那 加羅 秦韓 慕韓 六国諸軍事・安東大将軍・倭国王」の爵号を受けている。つまり、日本の軍事的支配権が、朝鮮におよんでいることを、客観的存在である中国がみとめている。これは、倭王武を雄略天皇であるとし、その数代まえの神功、応神のころ、日本の朝鮮半島への征討があったとすれば、きわめて自然に理解できる。五世紀ごろ、朝鮮半島への軍事的進出のあったことは、広開土王碑の碑文や、朝鮮の歴史書『三国史記』なども、記しているところである。すなわち、五世紀ごろ「倭(日本)」の朝鮮半島への軍事的進出のあったことは、中国、朝鮮、日本の文献が、そろって記している。
(3)神功皇后の物語などは、天皇や大和朝廷の権威を高めるには、すこしも役立たない。新羅征伐の物語をつくりたければ、天皇の権威を高める方向でつくりそうなものであるのに、すこしもそうなっていない。以下、そのことを、具体的にみてみる。
(4)天皇や大和朝廷の権威を高めたいのであれば、男性の天皇が直接新羅を征伐して、武威を高めるか、あるいは、英明な天皇が指導して、優秀な将軍を派遺して征討したことにすればよいはずである。しかるに、『古事記』『日本書紀』に記されているのは、やや、ぐずな仲哀天皇を、神功皇后が、叱咤激励するという図式なのである。 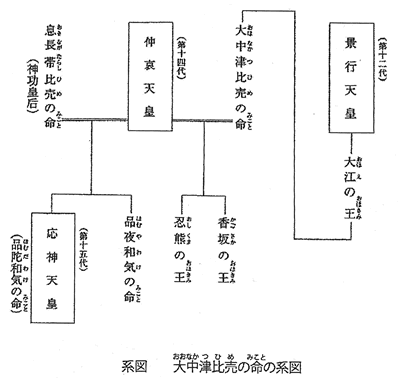
(5)神功皇后に神懸りした神は、仲哀天皇に、「西の方の、金銀をはじめ、多くの宝物のある国を与えよう。」という。しかし、仲哀天皇は、「高いところに登って、西の方を見ても、国が見えない。」などという。すると、神功皇后に神懸りした神は大いに怒り、「この国はお前[汝(いまし)]の治めるべき国ではないのだ。お前は一本道(死への道)に進みなさい。」という。そして、天皇は、まもなく、息がたえてしまう。
このように、天皇は、神功皇后に寄りついた神によって、命をおとす。むしろ、天皇の権威を、失墜させるような話になっている。
(6)大中津比売(おおなかつひめ)の命(みこと)は、仲哀天皇と結婚して、香坂(かごさか)の王(みこ)と忍熊(おしくま)の王(みこ)とを生む。この大中津比売の命は、神功皇后よりも、出自が、ずっとよい。すなわち、『古事記』によれば、大中津比売は、景行天皇の孫とされている(右の系図参照)。
これに対し、神功皇后は、『古事記』の「開化天皇記」によれば、開化天皇の五世の孫とされており、天皇家との血縁関係は、大中津比売にくらべてはるかにうすい。ふつうの人であれば、『古事記』『日本書紀』に系譜がのせられないはずのていどの出自である(下の神功皇后の系図参照)。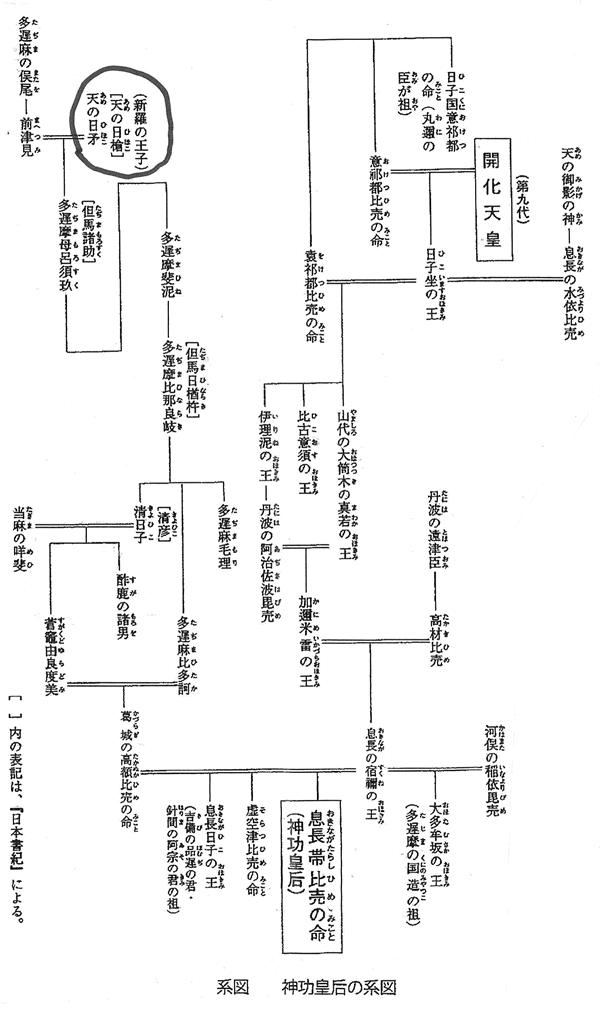
『古事記』『日本書紀』ともに、神功皇后は、大和にいた香坂(かごさか)の王(みこ)と忍熊(おしくま)の王(みこ)を滅ぼして大和にはいったことを記している。そして、神功皇后は、のちに、自分の子の品陀和気(ほむだわけ)の命(みこと)を、天皇の位につける(応神天皇)。
応神天皇の出自を神聖化するために、神功皇后の物語をつくったなどと説かれるが、そうであれば、神功皇后の出自なども、もっと立派につくるはずである。神功皇后を架空の人物とすれば、系図もつくられたことになる。しかし、その系図は、神功皇后に天皇的な権威を与えうるほどすばらしいものではない。神功皇后は、天皇のようにふるまうが、正式の天皇ではない。
この事実は、神功皇后に独特な色彩を与えている。ある天皇の五世の孫が天皇になるのは、のちに継体天皇にいたってはじめておきることである。
(7)『古事記』の「応神天皇記」によれば、神功皇后の母の葛城の高額比売(たかぬかひめ)は「新羅国の皇子」の天(あめ)の日矛(ひほこ)の五世の孫とされている(上の系図参照)。すなわち、神功の体には、敵国として戦っている新羅の王室の血がはいっていると記されている。『令集解」(りょうのしゅうげ)』の引用する「古記」は、新羅を「蕃国(ばんこく)[教化されていない未開人の国、または、日本のまわりの属国]」としてあつかっており、『古事記』『日本書紀』なども、けっして新羅を尊敬すべき国としては、描いていない。新羅を蕃国視していた七、八世紀の貴族が、神功皇后の出自を新羅国王の子に結びつけるのは、そのころ物語がつくられ、系譜もつくられたとすると、まったく不自然である。神功皇后の家系をもっと立派につくる方法は、いくらでもあったはずである。神功皇后が、父祖の国、新羅を攻撃しているのは、なぜなのだろう。あるいは、天の日矛は、新羅では、政争に敗れるなどして日本に来たのだろうか。新羅でのおもしろくなかった思い出が、神功皇后に伝えられたのであろうか。
(8)『古事記』『日本書紀』『延喜式』などは、神功皇后の陵墓の所在地を、つぎのように記す。
・『古事記』……狭城(さき)の楯列(たてなみ)の陵(みささぎ)
・『日本書紀』……狭城の楯列の陵
・「延喜式」……狭城の楯列池上陵
奈良県奈良市佐紀町から歌姫町・法華寺町にかけての、奈良盆地北部、佐紀丘陵南斜面にかけて、佐紀盾列古墳群(さきたてなみこふんぐん)が存在する。四、五世紀ごろの古墳とみられる。
神功皇后陵、成務天皇陵とよばれる古墳が、ここに存在する。
「佐紀盾列古墳群」は、大きく、東群と西群にわけられる。東群より、西群が古式であるといわれている。「西群は、四世紀後半から五世紀前半ごろの、東群は五世紀中葉から後半ごろの築造と考えられる」(大塚初重・小林三郎編『古墳辞典』東京堂出版刊)。神功皇后陵古墳は西群に属する。
『日本書紀』の「神功皇后紀」四十六年の条に、百済の王が、日本の使臣に、「鉄鋋(ねりかね)四十枚」をあたえたとの記事がみえる。
鉄鋋(てってい)は、鉄材であるが(貨幣ではないかとみる説もある)、その実物とみられるものが、佐紀盾列古墳群から出土している。
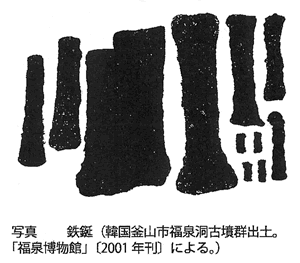
すなわち、佐紀盾列古墳群の東群に属する宇和奈辺(うわなべ)古墳の陪塚の一つの、大和六号墳から、多量の鉄鋋(てってい)が出土した。大型の鉄鋋(重さ200~700グラム)が282枚、小型の鉄鋋(重さ20グラム)が590枚、計872枚が、鉄製斧頭102、鉄製鍬(くわ)先または鋤(すき)先179、鉄鎌139、鉄刀子状工具284などとともに出ている。
鉄鋋はまた、新羅の故郷、慶州の金冠塚などからも、多量に出土している。森浩一・石部正志両氏は、この鉄鋋について、つぎのようにのべている。(「古墳文化の地域的特色5 畿内およびその周辺」『日本の考古学Ⅳ---古墳時代』〈上〉所収、河出書房新社刊)。(文中に、傍線を引いたのは、安本。)
「五世紀初頭を中心にした約一世紀間に構築された畿内の大古墳のうちで、多数の鉄製武器を副葬する例は、河内の古市誉田(ふるいちこんだ)古墳群、和泉(いずみ)の百舌鳥(もず)古墳群がとくに顕著である。大和では、河内・和泉ほどではないが、おなじ傾向がこの佐紀古墳群と馬見(うまみ)古墳群にあらわれている。南朝鮮に鉄の産地があったことは『魏志』の東夷伝弁辰の条(「国鉄を出す。韓・濊・倭みな従ってこれを取る……」)にうかがうことができるので、大和勢力の南鮮出兵の盛衰が古墳に副葬された鉄素材や鉄製品の増加や減少の傾向に関係があるとすれば、奈良盆地の古墳群のうちでも、この佐紀盾列古墳群は南鮮出兵に関与したか、出兵の影響を直説につよくうける集団の古墳群と想定したい。」
この文にあらわれる古市誉田古墳群は、応神天皇陵古墳(誉田山古墳)、仲哀天皇陵(岡ミサンザイ古墳)、允恭天皇陵(市の山古墳)などを含む古墳群で、築造年代は、ほぼ五世紀に集中し、倭の五王の時代にあたるとみられる。
また、百舌鳥古墳群は、仁徳天皇陵古墳、反正天皇陵古墳、履中天皇陵古墳などを含む古墳群で、築造年代はやはり五世紀に中心をおき、ほぽ、倭の五王の時代にあたるとみられる。
さらに、馬見古墳群は、奈良県北葛城郡河合町から広陵町、さらに、香芝市(かしばし)周辺を含む地域に存在し、葛城氏とその系譜にある有力首長層の墓とみられている。
葛城氏は、四、五世紀に、天皇家の外戚として栄え、『日本書紀』に新羅を撃つために朝鮮半島に遣わされたと記されている。
森浩一氏は、また、づぎのようにものべている(「古墳文化に現われた地域社会・畿内」『日本考古学講座』5<古墳文化>、河出書房刊)。(文中に、傍線を引いたのは、安本。)
「大和六号墳は、単に倍塚の内容究明に役立ったばかりではない。われわれの興味をひくのは、鉄板の形状と鉄の埋蔵量が小古墳としては予想を飛びこえて多いことである。この鉄素材[鉄鋋(てってい)。上の写真参照]の形と大きさは、古代の著名な鉄産地であった南鮮新羅の主要な古墳から出土する鉄素材と類似し、五世紀代には大量の鉄が、素材のままで南鮮から輸入されたことがあるという推測が生じる。文献の研究成果からいっても四世紀後半から五世紀にかけては大和朝廷が南鮮侵略に成功していた時期であるから、大量の鉄素材の輸入も充分可能であったわけであり、この現象によって説明困難な大和朝廷の南鮮侵略の目的そのもののうちに鉄素材の獲得があったとも考えられる。鉄素材に限らず鉄製武器、工具が畿内中心部では四世紀から五世紀中頃にかけて、巨大な古墳には突然変化的に埋蔵量が増大している。実例は省略するが、このことは大和朝廷を中心とする有力な豪族が南鮮侵略によって多量の鉄を独占する方法を確保したことを示しており、彼らはおびただしい武器や農工具をこしらえ、武力においても生産力においても他地方の豪族達を圧倒し、やがては、この鉄の確保が彼らを支配する原動力となっていったのであろう。」
このように、四世紀後半から五世紀にかけての大和朝廷の南朝鮮侵略を裏づける考古学的資料が、多数存在している。
神功皇后伝承の核心的部分には、四、五世紀における大和朝廷の南朝鮮侵略の史的事実が、存在しているとみられる。
■任那四県の割譲事件
さらに、つぎのような事実もある。(以下、下の「6世紀の朝鮮半島南部」の地図参照)。 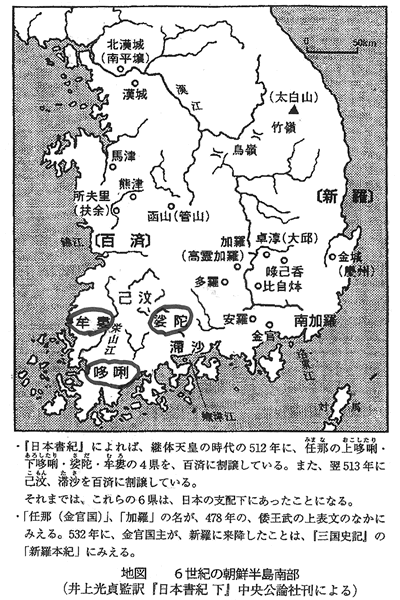
西暦400年前後の、朝鮮半島への出兵から百年ほど時代がくだり、継体天皇の六年、すなわち、西暦512年のことである。天皇は、穂積(ほずみ)の臣(おみ)押山(おしやま)を百済(くだら)につかわして、筑紫(つくし)の馬40匹を、百済に与えた。
穂積の臣押山は任那のなかの、哆唎(たり)の国守であった。このように、任那へは、日本から国守をつかわしていた。
512年の冬の十二月に、日本で生まれたと伝えられる百済の武寧王(ぶねいおう)は、使いを大和朝廷につかわして、貢(みつぎ)をたてまつった。別に表(ふみ)によって「任那国の上哆唎(おこしたり)・下哆唎(あろしたり)・娑陀(さだ)・牟婁(むろ)の四県(上の地図参照)を百済に与えてほしい。」とのべた。
これについて、穂積の臣押山が奏上した。
「この四県は、百済に近接し、日本からは遠くへだだっております。四県と百済とは朝夕に通いやすく、鶏や犬も、どちらの国のものか区別がつかないほどです。いまこれらの四県を、百済に与え、同じ国にすれば、これらの地をたもつ策としては、これにまさるものはないでしょう。
たとえ百済に与えてその国にあわせても、後世には危いことがあるかもしれません。
しかし、このまま切りはなしておいたのでは、とても何年とは、守りきれないでしょう。」
大伴(おおとも)の大連(おおむらじ)の金村(かなむら)は、穂積の臣押山の意見に同意して、天皇に奏上した。
そこで、継体天皇は、物部(もののべ)の大連(おおむらじ)麁鹿火(あらかひ)を、使いとして、難波(なにわ)の館(外国使臣のための客舎)につかわし、望みのままに、四県の地を与えるむねの勅を、百済の使いに伝えようとした。
ところが、物部の麁鹿火の妻が、夫にかたくいましめて言った。
「住吉(すみのえ)の大神(おおかみ)は、海のかなたの金銀の国、高麗(こま)[高句麗]・百済・新羅・任那などの国を、応神天皇にお授けになりました。そこで、神功皇后は、大臣の武内の宿禰とはかって、国ごとに官家(みやけ)をおいて、海表(わたのほか)の蕃屏(まがき)(海外の属国)とされました。その後、ながい年月を経て今日に至っています。もし、四県を百済に割譲するならば、もと定めた区域と違うことになります。そうすれば、後世の非難をまぬがれないでしょう。」
物部の麁鹿火がいう。
「お前の言うことは、まことにもっともだ。しかし、勅命に背(そむ)くわけに行かない。」
妻は、さらにきびしく、いさめて言う。
「病気だと申しあげて、勅命を伝えることをおやめなさい。」
麁鹿火は、ついにそのことばに従った。
そこで、朝廷では、使いを別の人にあらためて、百済の使いに勅を宣し、望みのままに、任那の四県を、百済に与えた。
このとき、勾(まがり)の大兄(おおえ)の皇子(みこ)[のちの安閑天皇]は、事情があって、四県割譲の評議に関与していなかった。あとで、事情を知り、おどろき、あらためようとした。
「応神天皇が、官家(みやけ)を置いた国を、軽々しく、与えてはならない。」
別の使いを難波につかわして、百済の使いに、命令を改め伝えた。
しかし、百済の使いは答えた。
「父君の継体天皇が事情をお考えになり、勅命によって、四県をお与えになったのです。その子である皇子が、勅命にたがい、命令を改めて発するということがありえましょうか。これは、かならず、虚(いつわりごと)でしょう。たとえ、ほんとうのことであるとしても、天皇の勅は重く、皇子の命令は軽いはずです。」
こう答えて、百済に帰ってしまった。
世間では、つぎのような流言があった。
「大伴の大連金村と、哆唎(たり)の国守の穂積の臣押山とは、百済から、賄賂(わいろ)を受けとったのだ。」
以上は、いわゆる「任那四県割譲事件」の緊迫したやりとりである。
六世紀はじめの継体天皇の時代に、物部の麁鹿の妻のことばにあるように、朝鮮半島の官家(みやけ)は、神功皇后と武内の宿禰とがおいたものであると、一般に認識されていたのである。麁鹿火の強い妻。その個性とことばには、臨場感がある。おそらくは、事実そのようにのべたのであろう。
そして、それが世間に伝えられたのであろう。
もし、これが麁鹿火の妻のことばでなかったとしても、六世紀はじめの継体天皇の時代に、朝鮮半島の官家は、神功皇后と武内の宿禰とがおいたものという認識があったことを思わせる。
神功皇后は実在しなかったとか、朝鮮半島への出兵は存在せず、推古朝の新羅征討の事実など、後世の七、八世紀の史実をモデルに創作された架空の物語である、などとしたばあいには、歴史のすじみちが、まったく見えてこない。
任那四県の割譲の話までも、後世の創作とするのであろうか。つじつまの合わない話だらけになってしまう。
■倭軍の侵攻と軍事支配権の範囲
領有権の範囲は、いつの時代でも、当事国と相手国などとで、主張が異なるものである。現代でも、中国との尖閣(せんかく)諸島問題、韓国との竹島問題、ロシアとの北方四島問題など、いくつかの領有権問題がある。
古代においても、同様な問題があった。
『宋書』によれば、西暦430年代(430年から、438年のあいだのころ)、倭王珍が、「みずから、使持節・都督 倭 百済 新羅 任那 秦韓(辰韓)慕韓(馬韓)六国諸軍事・安東大将軍・倭国王」に除正されるように求めている。
ここで、百済は、むかしの馬韓から起きているが、倭王珍のころ、百済に属していないむかしの馬韓の地を、慕韓と呼んだものとみられる。
倭王珍の主張では、百済、新羅などに、倭国の軍事支配権が及んでいるとの認識であったようにみえる。
中国の宋王朝としては、すでに、430年に百済の毗有王には、「使持節・都督 百済諸軍事・鎮東大将軍」の爵号を与えている。そのため、倭国がわの主張を、全面的に認めるわけにはいかなかったようである。珍のつぎの倭王の済(せい)には、451年に、「使持節・都督 倭 新羅 任那 加羅 秦韓 慕韓 六国諸軍事」と、「百済」だけをのぞいた形で称号を与えている。
新羅や任那などに、倭国の軍事支配権が及んでいたことを、一応、客観的存在である中国が、みとめる形になっている。
倭王珍の、百済にも倭国の軍事支配権が及んでいた、とする主張にも、あるていどの根拠がある。高句麗の広開土王の碑文に、「倭が、辛卯の年(391)に、来りて海を渡り、百残(百済)を破り、口口新羅を臣民とした」と読める文がある。
と、中国の宋王朝とで異なるところがあるが、倭のがわの最大侵攻領域と、それが時代がくだるとともに失われて行く状況とを、史料的根拠とともに地図に示せば、前に示した地図(「地図 倭の最大侵攻領域と、領域が時代とともに失われて行く状況」)のようになる。
■韓国で発見された前方後円墳
韓国でも発見された前方後円墳については、森浩一編著「韓国の前方後円墳---「松鶴洞一号墳問題」について---」(社会思想社、1984年刊)が出ている。
この本には、韓国領南大学の姜仁求(カンイング)氏による「韓国で発見された前方後円墳」の位置が示されている。それを、地図上にプロットすれば、下の地図のようになる。姜仁求氏は、韓国の前方後円墳問題について、極的発言をしておられる方である。下の地図と前に示した地図(「地図 倭の最大侵攻領域と、領域が時代とともに失われて行く状況」)とを、じっと見くらべると、つぎのようなことに気がつく。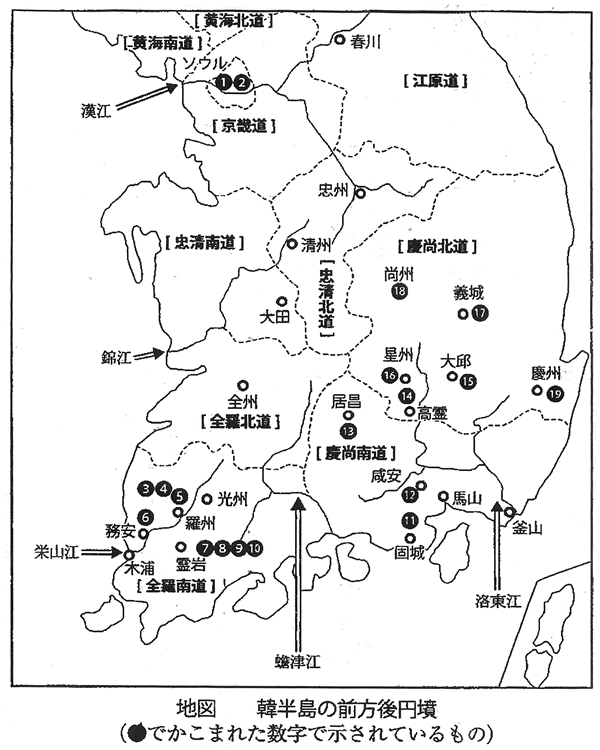
(1)韓国の「前方後円墳」が、もっとも多く発見されているのは、「全羅南道」の地である。
この地は、まさに、『日本書紀』「継体天皇紀」が、512年年に、百済に割譲したと記す「上哆唎・下哆唎・娑陀・牟婁」の四県の地にあたる。つまり、それまでは、日本の支配権に属し、穂積の臣押山が、哆唎の国守であった。
朝鮮半島の前方後円墳は、五、六世紀のものが多い。「継体天皇紀」の記す年代と、大略あっている。このころになれば、『日本書紀』の記す年紀も、ほぼ信頼できるものといえよう。
日本の役人などの墓が、日本の風習にしたがい、前方後円墳にほうむられたとしてもふしぎではない。
(2)「全羅南道」についで、「前方後円墳」が多いのは、「慶尚北道」と「慶尚南道」である。この地は、新羅の国の地にあたる。
新羅の都(新羅城)は、慶尚北道の慶州市の地にあった(金城)。
西暦400年にあたる年に、「倭は新羅城に満ちていた」ことは、『広開土王碑文』に記されている。それに呼応するかのように、『日本書紀』の「神功皇后紀」は、神功皇后の軍が、新羅の王城にいたり、神功皇后の矛を新羅の王の門にたてたことなどが記されている。
西暦400年の倭の新羅城入城の結果であろう。西暦402年に。新羅の王子が、倭への人質となったことは、朝鮮の歴史書、『三国史記』が記す。そして、新羅の王子が、日本への人質となったことは、『日本書紀』の「神功皇后紀」に記されている。
新羅城は、金城とよばれた。現在の慶州市の地である。そして、その慶州市の地に、前方後円墳が存在している。
(3)中国の「宋書」によれば、第21代雄略天皇にあたるかとみられる倭王武に、「使持節・都督 倭 新羅 任那 加羅 秦韓 慕韓 六国諸軍事・安東大将軍・倭国王」の爵号が与えられている(478年)。
また、倭王武のまえには、451年に、第19代允恭天皇にあたるかとみられる倭王済に、すでに、倭王武と同じ爵号が与えられている。
つまり、日本の軍事支配権が、新羅の地におよんでいたことを、中国がみとめている。
新羅の地に、日本の役人などの墓が、日本の風習にしたがって築造されたとしても、かならずしも不自然とはいえない状況が存在していたようにみえる。
(4)さらに、北方のソウルでも、二基の「前方後円墳」が発見されている。
東洋史学者の那珂通世(なかみちよ)、白鳥庫吉、池内宏、榎一雄、朝鮮史学者の今西竜(いまにしりょう)などの諸氏は、『魏志倭人伝』にみえる帯方郡の郡治(郡役所)は、ソウル付近にあったとする。
そして、『広開土王碑文』は「404年に、倭は不軌(ふき)にも(無道にも)、帯方界(むかしの帯方郡のあった地域)に侵入」と記す。
以上みてきたように、「韓国の前方後円墳」の存在する場所は、いずれも、史書に、なんらかの形で、倭人の足跡が記されている場所である。
『日本書紀』をふくめ、史書にもとづいて、「韓国の前方後円墳」の意味をたずれるのは、かなりな妥当性をもつようにみえる。
■いくつかの補足説明
以上述べてきたことについて、いくつかの補足説明をしておく。
(1)いま、次のような状況を考える。
私の机の右がわには、『古事記』の本文にみられるような、もとは口承伝承によったのかも知れない神話・伝説的な国内資料が、まとめておかれている。
これは、天皇の名とか、父子関係による系譜などで、あるていど時代順に整理することができるのであるが、そこにみられる天皇がいつごろの人であるか、とか、ある出来ごとがいつごろ起きたことであるか、などの年代は、正確には、わからない。
いっぼう、私の机の左がわには、『魏志倭人伝』とか、朝鮮関係の資料とか、外国で成立した倭人関係の国外の資料が、まとめておかれている。
そこに記されている年代は、かなり正確なのであるが、遠くてよく知らない外国の倭国のことを記しているので、内容は断片的で、そこに記されている「邪馬台国」でさえ、どこにあったか正確にはわからない。
このような、机の左右の国内資料と国外資料とをくみあわせて、日本の古代史のすじを構成しようとする。
この作業には、現代の私たちが、頭を悩ますところであるが、情況は、たとえば、『日本書紀』の編纂者などにとっても、同じであったと考える。
編纂者たちが、勝手に、あるいは意図的に材料を作り出したものではなく、材料は、一応存在していたと考える。
以上述べたような情況は、たとえば、昭和時代の古代史学者、三品彰英(みしなあきひで)[1902~1971、同志社大学教授など]が、すでに想定しているところである。
三品彰英は、その編著。『上世年紀考』(養徳社、1948年刊)の中で、つぎのように述べる。
「異質的にしてかつ別系統の史料を比較考証せんとすることの困難さは、今日我々の当面せる問題の例としては、『魏志』倭人伝の記事と、わが記紀の伝える古史伝との比較研究において充分に経験しているところである。」
「神功皇后の外征を年次的にいつごろに持って行くべきか、また、それを知りうる範囲の外国史料のいずれに推当すべきであるかが、今日の吾々にとっても、また、書紀撰者にとっても、ひとしく日朝関係史研究上の根本問題であることは明らかである。」
(2)『日本書紀』の編纂者たちは、国内伝承の中の、神功皇后伝承に、着目する。
国外にまで威をふるった女性としては、神功皇后がいる。
『魏志倭人伝』に記されている卑弥呼は、おそらく神功皇后であろうと、『日本書紀』の編纂者たちは考えた。
かくて、『日本書紀』では、卑弥呼に神功皇后をあてはめ、『魏志倭人伝』の年紀にあうように、年代が記されている。
しかし、『日本書紀』にみられる年代は、大幅に、古いほうに延長されている。
(3)年代だけは古いほうにもっていったが、そこに登場する人物や、舞台装置は、卑弥呼よりも150年ほどあとの、四・五世紀のままである。
おそらく、もととなった伝承じたいが、そうなっていたのであろう。
現代風の背広を着た人物が、現代風の舞台装置の中で、江戸時の侍(さむらい)の立ちまわりをしているような形になっている。
たとえば、「神功皇后紀」に、新羅の王子、微叱己知波珍干岐(みしこちはとりかんき)が、日本の人質になった話がでてくる。これは、朝鮮の歴史書『三国史記』の「新羅本紀」に記されている「新羅の王子、未斯欣(みしきん)が、倭の人質になった。」という話の異伝とみられる。
ところが、『三国史記』の「新羅本紀」によれば、未斯欣が、倭の人質になったのは、402年のことである。
卑弥呼の時代よりも、150年以上新しい。
また、「神功皇后紀」には、新羅、百済の名がみえるが、新羅、百済が成立したのは、4世紀の中ごろであった。
3世紀の卑弥呼の時代は、馬韓、辰韓、弁韓の三韓の時代であった。
(4)たしかな年代資料がないばあい、私たちは、とかく、年代を、実際よりも、古く古くみつもりがちである。旧石器捏造事件のばあいなどは、数十万年も年代を古いほうにもっていっていたが、ほとんどの専門家は、その誤りに気がつかなかった。
なお、すでに、1889(明治二十一)年に、阿部弘歳[阿部杖策(じょうさく)、文部省の官吏。かなり多くの啓蒙書を発表)が、『文』に発表した「征韓考」のなかで、つぎのようにのべている。
「(神功皇后の)征韓といっていることは、広開土王碑の墓碑の辛卯(西暦391年)のことであるのを、(『日本書紀』編纂の)史家が(年代を)誤って伝えたものである。」(以上、原文は、文語文)。
(5)津田左右吉は、神功皇后の「新羅征討の物語」について、つぎのように述べる。
「古事記の物語に事実と認むべきことがなくして、全体の調子が説話的であること、進軍路の記載が極めて空漠であること、新羅問題の根原ともいうべき加羅(任那)のことが全く物語に見えていないこと、事実としては最初の戦役の後、絶えず交戦があったらしいのに、それが応神朝以後の物語に少しも現はれていないこと、などを考えると、これは事実の記録または伝説口碑から出たものではなく、よほど後になって、恐らくは新羅征討の真の事情が忘れられたころに、物語として構想せられたものらしい。進軍路のあいまいなこともこのゆえであって、海からすぐに都城に進まれたように見えるのは、たゞ海外の国の征伐という抽象的概念から作られた話だからであろう。」
「この物語の大筋をなしている皇后の親征ということも問題になる。上に試みた研究の結果によれば、皇后の行動として語られているこの物語の種々の説話は、いずれも事実として認めがたいものであって、最初の神の託宣に関すること、征討の経過、有名な石の物語、また前には述べなかったがタマシマの里の年魚(あゆ)の物語などか、皆それである。」
「それから、歴史的事実の明白に知られる時代になって、一度も韓地に対する天皇の親征ということが無かった、という事実も参考しなければならぬ。」
「さて皇后の新羅親征が事実でないとすると、仲哀天皇のツクシヘゆかれたことが事実でないことは、この点からもまた知られ、応神天皇の生誕に関するいろいろの物語も、また事実ではないことになる。両方とも、皇后の新羅親征の説話から離しては考えられないものだからである。」(以上、『津田左右吉全集』第一巻[岩波書店、1963年刊]所収の「日本古典の研究 上」による。)
では、なんのために、「天皇の親征」ではなく、「皇后の親征」というような不自然な話を作らなければならなかったのか。
『宋書』などが、倭王の済や武に、新羅に対する軍事支配権を認めるような爵号を与えているのはなぜなのか。
高句麗の広開土王が、朝鮮半島において、くりかえし戦った「倭」の正体は、なんであったのか。
私には、すこしでも神話的、説話的な記述は、史的事実なく、よほど後になって「作られたもの」とする津田左右吉の説は、抽象的観念(思いこみ)によって構想された空漠たる学説としかみえない。
いまだに、このような、前前世紀的な論法がわが国では幅をきかせている。世も末である。
なお、津田左右吉の学説の上に(天皇の権威を否定的にみる「左翼性」を重ねたり、あるいは、逆に、津田左右吉説批判に、天皇の権威を肯定的にみる「右翼性」を重ねたりするのも、議論を混乱させる原因となる。
客観性をたもつためには、津田学説が、現代の科学の立場からみて、合理的といえるかどうかだけを検討すべきであろう。そして、私は、津田左右吉説は、現代社会で求められる水準の科学的合理性を、そなえていないと判断する。
■高田寛太氏の著書『「異形」の古墳---朝鮮半島の前方後円墳---』について
さきの姜仁求氏が、1984年に発表されたもの以外で、朝鮮半島南部の、全羅南道、全羅北道地域の、1984年以後に発掘された前方後円墳については、国立歴史民俗博物館准教授の高田寛太氏の著書「「異形」の古墳---朝鮮半島の前方後円墳---」(角川選書、2019年、KADOKAWA刊)に、一覧表がのっている。
下の表(「朝鮮半島南部(全羅道・全羅北道)の前方後円墳」)のようなものである。
(下図はクリックすると大きくなります) 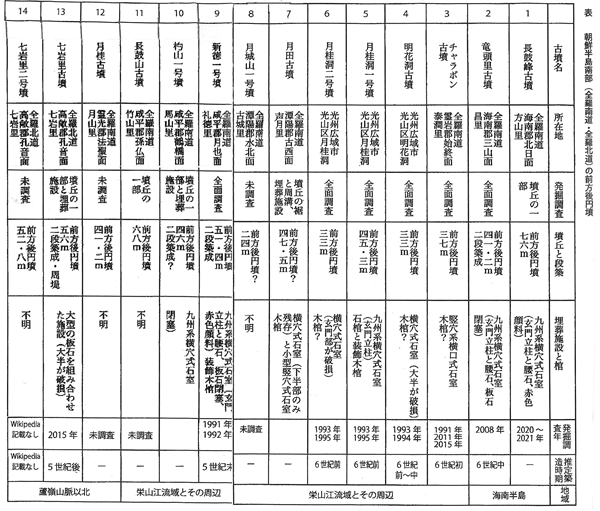
Wikipedia(ウイキペディア)で、「朝鮮半島南部の前方後円墳」を引けば、一覧表がのっているが、これは、高田寛太氏の示された表に示したものの、部分集合をなすものである。ただし、Wikipediaでは、「発掘調査年」「推定築造時期」など、高田寛太氏の示された表にふくまれていない情報も示されている。
そこでこの表では、Wikipediaにより、「発掘調査年」と、「推定発掘時期」とを、おぎなった。
高田寛太氏の示された表により、全羅南道、全羅北道地域の前方後円墳の分布状況を示せば、下の地図(「朝鮮半島南部の前方後円墳」)のようになる。
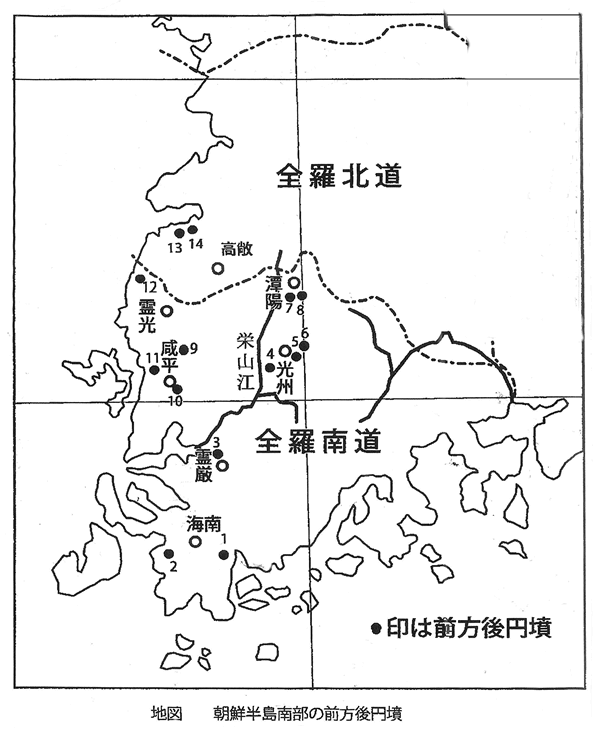
全羅南道に、前方後円墳の多いこと、また、光州市付近など、栄山江の流域に、そのクラスターが見られることは、前に示した「6世紀の朝鮮半島南部」の地図と同じである。
ところで、光州市の付近は、昔の「哆唎(たり)」の地であったとみられる。
小学館刊の「日本古典文学全集」の『日本書紀2』」の297ページに、「継体天皇紀」六年(516)十二月条にみえる「上哆唎(おこしたり)・下哆唎(あろしたり)」についての頭注が記されている。
そこに、次のようにある。
「現全羅南道栄山東岸一帯の地。光州の無等mu-tar山や月奈tar-na(霊巌)、道武tor-mu(康津)などに「哆唎」の名が残る。」
前示した「朝鮮半島南部(全羅道・全羅北道)の前方後円墳」の表をみると、古墳5、6の「月桂洞」、古墳7の「月田」「声月里」、古墳8の「月城山」、古墳9の「月也面」、古墳12の「月桂」「月山里」など、「月」の字のはいっているものが多い。
「月」の朝鮮語(韓国語)は、「tar(tal)」であるいは、「哆唎」の名ごりか。
岩波書店刊の「日本古典文学大系」の『日本書紀 下』の26ページの、「継体天皇紀」六月の条にみえる「上哆唎(おこしたり)・下哆唎(あろしたり)」についての頭注には、「哆唎(たり)は全羅南道の栄山江東岸の地方か」とある。そして、『日本書紀』によれば、この穂積(ほずみ)の臣(おみ)の押山(おしやま)が、「哆唎(たり)の国(くに)の国守(みこともち)」として、日本からつかわされていたのである。
『日本古代氏族人名辞典』(吉川弘文館刊)は、「穂積臣押山(ほずみのおみおしやま)の頂で、『日本書紀』の記事にもとづき、つぎのように記す。
「朝鮮の哆唎に駐在した大和朝廷の執政官」穂積の臣押山の名のみえる継体天皇の六年は、西暦516年にあたる。六世紀の前半である。前の表(「朝鮮半島南部(全羅道・全羅北道)の前方後円墳」)に記されている朝鮮半島の前方後円墳の築造時期に大略あう。
以上から、この地にみえる前方後円墳は、穂積の臣押山など、日本からこの地につかわされていた役人や、その家族などの墓とみるのが、順当であろう。
このような情況がもたらされたのは、神功皇后の時代に、
倭が朝鮮半島に進出し、一時期、朝鮮半島の南部に、為政権をもったために生じた現象であろう。
ただ、さきの高田寛太氏の著書『「異形」の古墳』では、『日本書紀』に記されている哆唎の国守、穂積の臣押山の話や、四県割譲についての話などにはふれられていない。
「「異形」の古墳』は、一つ一つの古墳の状況については、大変丁寧な説明がなされており、参考になるところが大きい。
高田寛太氏は、現代の日韓関係などを考慮し『日本書紀』の記述にふれることを、慎重にさけられたのであろうか。
結論:おそらくは、朝鮮半島の前方後円墳は朝鮮半島に日本軍が進出した時期があって、その日本人のお墓を造った。それが、朝鮮半島の前方後円墳である。特に百済に割譲した任那4県は日本から穂積臣押山という人が執政官として行っていた。そうすれば大体つじつまが合うのではないか。
ここで、下記の記事がある。
すでに、『週刊朝日』の1983年9月2日号に、韓国出身の考古学者の李進煕(りじんひ)氏(和光大学教授など)が、韓国の前方後円墳問題について、「日本のほうがルーツで、それが韓国に伝わったようだ。むしろ任那日本府の根拠になる」という声が出てくることを心配している、との談話がのっている。
つまり、神功皇后が朝鮮半島に進出した話は、戦前などにおいて、日本の軍国主義の宣伝を鼓吹するための宣伝道具として使われていた。そのため韓国の人々は重要な抵抗感を持っている。だから神功皇后の話は御伽話で、この朝鮮半島の前方後円墳はもともと朝鮮半島の人の墓であって、日本の前方後円墳の原点であると主張している韓国の学者がいる。
しかし日本の前方後円墳よりは韓国の前方後円墳の方が新しいことが分かってきた。だからといって、韓国の前方後円墳のことを日本から進出した人の墓だと単純に主張すると、問題となる。今後、韓国の考古学者と協力して考古学を進めることが難しくなる。
このようにデリケートな問題を抱えていることを顧慮しなければならない。







