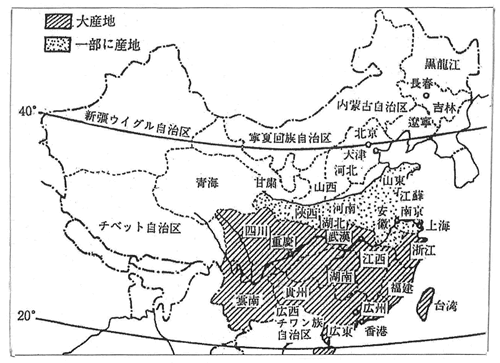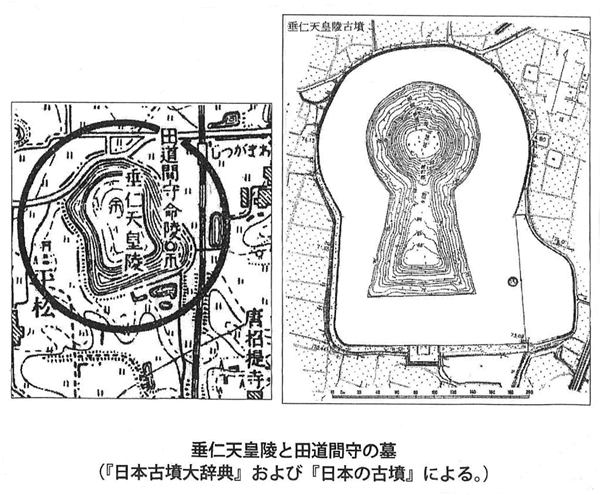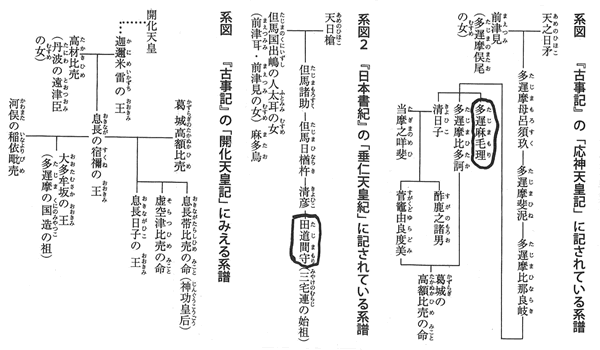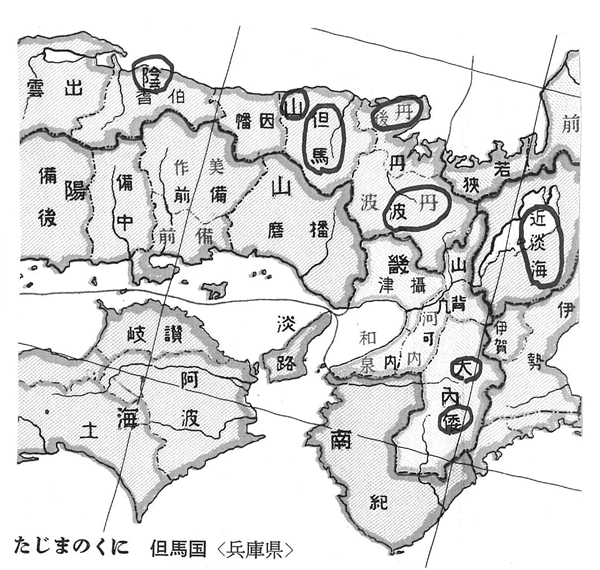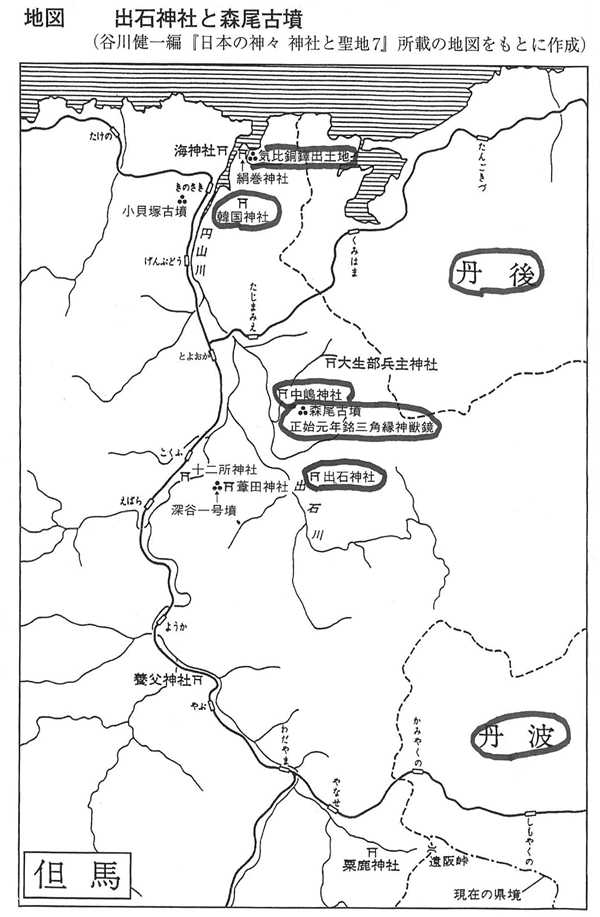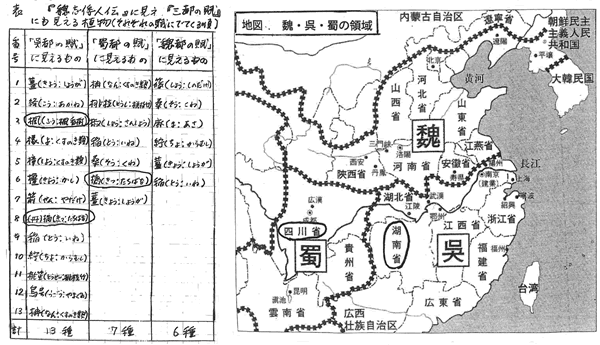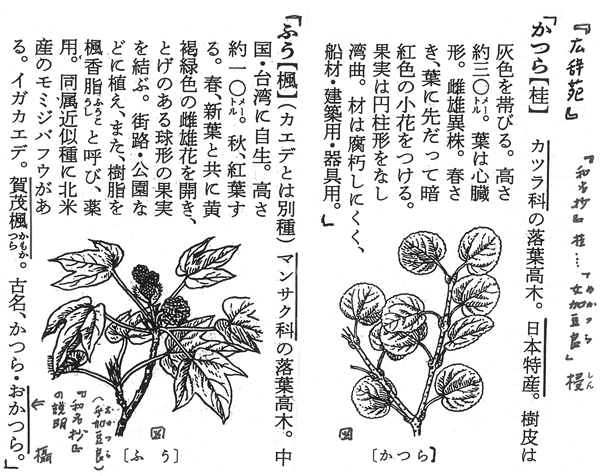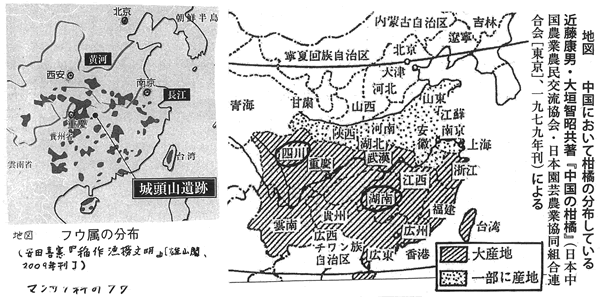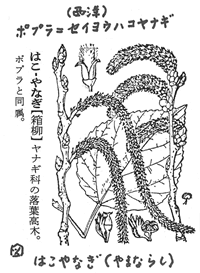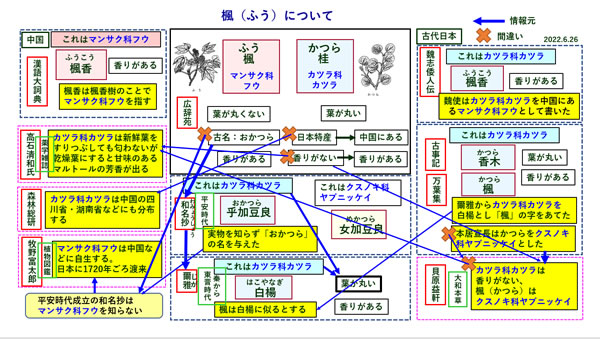みかん物語・田道間守(たじまもり)の話
■「タチバナ」と「ミカン」
・朝日新聞の記事
2016年12月9日(金)夕刊に下記の記事がある。
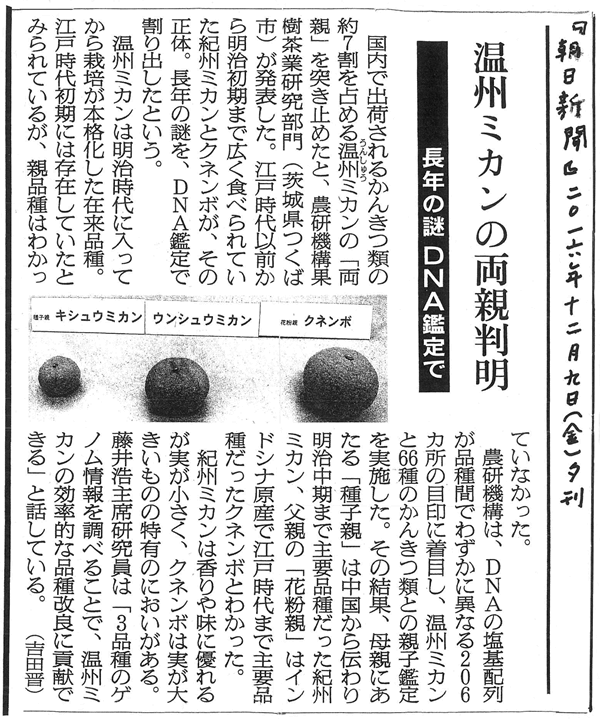
この記事は、現在国内で「ミカン」として食べられている温州(うんしゅう)ミカンは紀州ミカンとクネンボからなると書かれている。
そして、『魏志倭人伝』に下記がある。
「倭の地は温暖、冬夏生菜(生野菜)を食す。……薑(きょう)[しようが]・橘(きつ)[たちばな]・椒(しょう)[さんしょう]・蘘荷(じょうが)[みょうが]あるも、もって滋味とするを知らず。(不知以為滋味)」
このように、『魏志倭人伝』には「橘があるが、賞味することを知らない。」とある。
わが国の柑橘類(かんきつるい)の歴史において、主流をなすものは、次の三つとみるのが、妥当なようである。
(1)『魏志倭人伝』にみえる「橘」の類
これは、野生種(日本固有種)の「ヤマト(ニホン、ニッポン)タチバナ」(植物分類学者・牧野富太郎の命名)とみるべきである。
「ニッポンタチバナ=ミカン科」は下記のように書かれている。
和歌山県、山口県、四国、九州などの海岸線に近い山地にまれに自生している日本固有の常緑小高木。樹高は二~四メートルで初夏に白い五弁花が咲く。花は非常に香りがよく、観賞目的で植栽されたが、実は酸っぱくて食用には向かない。京都御所の紫宸(ししん)殿前に植えられている橘は本種の栽培品といわれる。
(2)『続日本紀(しょくにほんぎ)』にみえ、「菓子(くだもの)の長上(もっともすぐれたもの)」とされた「橘」の類。
これは、『古事記』 『日本書紀』の垂仁天皇の条にみえる「ときじくのかくの実」とつながると考えられ、「紀州みかん[小(こ)みかん]」の類とみられる。
このように、「橘」は3世紀の『魏志倭人伝』の時代には食べないとされたが、8世紀の『続日本紀』の時代(奈良時代)には「菓子(くだもの)の長上」とされた。
また、『万葉集』4266 大伴家持のものに下記がある。
あしひきの・・・赤(あか)る橘(たちばな) うずに刺(さ)し
注:
・赤る橘--この赤ルは熟して赤く色づくこと。
・うずに刺(さ)し--ウズは冠に添える飾り。「推古紀」十一年の条に「髻花(けいか)、此云干孺」とあり、古くは「熊白檮(くまかし)が葉をうずに刺せ」(記・中)のように植物の花葉の類を髪に挿していたようであるが、後、金銀製品や鳥獣の尾などを冠に付けた。ここは橘の実を用いている。
この「赤」について、コラム1がある。
----------------------------------------------------------------------------
コラム1「鞠(まり)と殿さま」と赤いみかん
西条八十(さいじょうやそ)作詞、中山晋平作曲の童謡、「鞠と殿さま」は、よく知られている。
この歌のなかにでてくる「みかん」は、「紀州みかん」と考えられる。そして、この歌の五番に、「赤いみかん」とあることに注意。
1番
てんてんてんまり てん手まり
てんてん手まりの 手がそれて
どこからどこまで とんでった
垣根をこえて 屋根こえて
表の通りへとんでった
とんでった
2番から4番は省略
5番
てんてん手まりは 殿様に
だかれてはるばる たびをして
きしゅうはよいくに 日の光
山のみかんになったげな
赤いみかんに なったげな
なったげな
---------------------------------------------------------------------------
この歌は「赤いみかん」とした。つまり紀州ミカンは赤かった。
また、3世紀の『文選(もんぜん)』に「赤い橘」についての下記がある。
左太沖(左思)による『文選』の「呉都の賦」(注:呉都は建業で後の南京、229年の呉の都となる)にも「赤」が書かれている。
其(そ)の果は則(すなわ)ち丹橘(たんきつ)・余甘(よかん)・茘枝(れいし)の林あり。[果物の類では、赤い橘・余甘(よかん)・茘枝(れいし)の林がある。]
そして、前に示したように奈良時代に菓子(くだもの)の長上(ちょうじょう)となった。(詳細は下記)
・797年に撰進された『続日本紀(しょくにほんぎ)』の、天平八年(736)十一月十一日の条に、和銅元年(708)十一月二十五日の宴で、元明(げんめい)天皇がのべた言葉として、つぎのような文が記されている。
「橘(たちばな)は、菓子(くだもの)の長上(ちょうじょう)[最上のもの]にして、人(ひと)の好(この)むところなり。」
三世紀の『魏志倭人伝』の段階では、「滋味とすることを知らず」。すなわち、食べていなかったようにみえるものが、八世紀のはじめに、「菓子(くだもの)の長上」、つまり、おいしく食べられるものになっている。
このおよそ500年のあいだに、なにがあったのか。
その間の事情をうかがわせるような記事が、『古事記』『日本書紀』の垂仁天皇の条に記されている。
すなわち、やや伝説化しているが、つぎのような記事である。
「垂仁天皇は、多遅摩毛理(たじまもり)[『日本書紀』の表記は田道間守(たじまもり)。新羅(しらぎ)の王子で日本に来た天の日矛(あめのひぼこ)の子孫]を常世(とこよ)の国につかわして、ときじくのかくの木の実(このみ)(四季変らない香りをもつ実)を求めさせた。多遅摩毛理は、その木の実をとり、縵八縵(かげやかげ)・矛八矛(ほこやほこ)(乾し柿のように縄にとりつけた形のもの八つ。団子のように串にさした形のもの八つ)を、持って帰った。このときじくのかくの木の実は、今の(『古事記』『日本書紀』が編纂されたころの)橘である。」
この記事によれば、多遅摩毛理がもって帰った「ときじくのかくの木の実」は、『古事記』の編纂されたころ、つまり奈良時代の橘であると認識されていたことがわかる。
そして、『古事記』が成立した712年に近い和銅元年(708)には、「橘は、菓子の長上」とされていたのである。
天皇の在位一代平均約十年説によれば、第十一代垂仁天皇が没したのは、西暦370年前後となる。ちょうど、三角縁神獣鏡がうずめられている古墳の多くが、きずかれていたころである。中国の王朝は東晋の時代である。
『魏志倭人伝』に記されている「橘」と、奈良時代の橘(多遅摩毛理がもってきたとみられるもの)とは、種類がちがうようにみえる。
(3)現代の「みかん」
現代のわれわれが、もっともふつうに食べている「みかん」。これは、明治中期よりものちに普及したもので、「温州(うんしゅう)みかん」とよばれるものである。
このミカンは「温州(うんしゅう)[雲州]みかん」といわれるものである。
「温州みかん」については、小学館刊の『日本国語大辞典』にのっている説明が、要領がよい。
「うんしゅう・みかん「温州蜜柑・雲州蜜柑」」[名]ミカン科の常緑低木。日本の中部および南部で広く栽培される。日本で創製した品種。高さ約3メートル。葉は長さ7~10センチメートルの楕円形で先はとがる。初夏白い五弁の花が咲く。実は直径5~8センチメートルで、やや扁球形。外皮が薄く、熟すると橙黄色となり、ふつう9~13個の胞(ほう)をもち、種子はなく汁が多くて食用に適する。原種とみられる在来(筑後)温州をはじめ、早生(わせ)温州、尾張温州、池田温州などの品質がある。『うんしゅう』は『温州(うんしゅう)』または『雲州』と書くが、中国の地名『温州(おんしゅう)[日本のミカン名はウンシュウ、中国の地名はオンシュウであることに注意)』(浙江省)や日本の『出雲国』(島根県)とは無関係。」
ここでわが国の「温州(うんしゅう)みかん」と、中国の浙江省の「温州(おんしゅう)[市」」とが、「無関係」とわざわざ記されているのは、わが国の柑橘(かんきつ)学の権威であった田中長三郎氏(1885~1976)の実地踏査によれば、浙江省温州市付近には、日本の「温州みかん」と同類のものは、発見できなかったということによるとみられる。ただし、浙江省温州市は、柑橘類の産地ではある。また、わが国の「温州(うんしゅう)みかん」の「温州(うんしゅう)」と、中国浙江省の「温州(おんしゅう)市」の「温州(おんしゅう)」とでは「うんしゅう」と「おんしゅう」で読みが違うことにも注意。
この「温州(雲州)みかん」は、明治の中期よりもあとになって普及したみかんである。それまでは、「紀州みかん(小みかん)」が、日本の代表的品種であった。そのことは、『日本国語大辞典』に、つぎのように記されているとおりである。
「きしゅう・みかん【紀州蜜柑】 【名】ミカン科の常緑小低木。中国原産で、古く渡来し、ウンシュウミカンの普及する明治中期までの日本の代表的品種。幹は五メートルぐらいになり、枝は細く、よく分岐する。枝にはとげはなく、葉は長卵形で互生する。果実は、径四センチメートルほどの平らな球形で、冬に熟し黄赤色となり、甘味に富むが種子が多い。こみかん。」
江戸時代に、紀伊国屋文左衛門が、みかんを嵐のなかを、紀伊の国(和歌山県)から江戸へはこんだといわれる。この「みかん」も、「紀州みかん(小みかん)」とみられる。
「紀州みかん」は、種子は多いが、味はよい。味は、現代の「温州みかん」と、それほど変わらないように、私には思える。
以上からみると、つぎのように考えるのが、穏当なようである。
『魏志倭人伝』の橘……やまと(にほん)たちぱな
『続日本紀』の橘(ときじくのかくの木の実)……紀州みかん(小みかん)
現代の「みかん」……温州(うんしゅう)[雲州]みかん
ここで、「やまとたちばな」は、牧野富太郎氏の命名による野生種で、酸味が強く食べられない。食べられる「たちばな」とは区別される。
平凡社刊の『世界大百科事典』に、つぎのように記されている。
「たちばな〔橘〕 Citrus tachibana
直径2.5~3センチほどの小さな果実ができるミカン科の常緑小高木。日本列島におけるミカンの仲間のただ一つの野生種で、近畿地方から西の海に近い山に生じ、枝にとげがある。高さ4メートルに達し、葉は互生する楕円形の披針形で、長さ4~6センチ、柄が短く翼がなく葉身との間に関節がある。六月ころ、ふつう短枝の頂に白い小さな五弁花が咲く。果実は平たい球形で黄色、ユズに似たかおりがある。果嚢は六~八個、一~二個の大きな種子が入っていて、酸味が強く食べられない。牧野富太郎は古代名のタチバナはキシュウミカンに似た食用ミカンであるとの理由から、野生のものにヤマトタチバナの名を与えた。また、有名な京都の紫宸殿(ししんでん)の〈右近の橘〉は、野生のタチバナの改良種であるといわれている。(奥山春季)」。
「やまと(にほん)たちばな」は「酸味が強く食べられない」ものであること、「日本列島におけるミカンの仲間のただ一つの野生種」であることなどにおいて、『魏志倭人伝』の記述にあてはまるとみられる。
他の柑橘類は、あてはまらない。
たとえば、「からたち」は、「唐(から)たちばな」の略で、中国の原産である。
「だいたい」も、中国からはいった。そのことは、「だいだい」の「だい」は、「橙」の中国音の転訛(『広辞苑』)であることからもうかがわれる。
また、奈良時代の人は、『古事記』『日本書紀』の記す「ときじくのかく実」を、奈良時代に「菓子(くだもの)の長上」とみた「橘」と、同じものと考えている。
国文学者の西宮一民(にしみやかずたみ)氏は、奈良時代の「橘」を、「橙(だいだい)の類」としている(新潮社刊『古事記』新潮日本古典集成)。しかし、「橙の類」では、「菓子の長上」とはいえないであろう。
かつ、『三国志』を編纂した陳寿と同時代に生きた左太沖は、あとで紹介する『文選(もんぜん)』におさめられた「蜀都の賦(ふ)」のなかで、つぎのように記し、「橘」と「橙」とを書きわけ、区別しているのである。
「戸に橘(きつ)・柚(いう)[ゆず]の園あり。その園には、すなわち、林檎(りんご)・枇杷(びわ)・橙(だいだい)・柿(かき)・・・・」
そして、小尾郊一著『文選(文章編一)』(集英社刊)は「橘(きつ)・柚(いう)」に注をして、「みかん。大を柚といい、小を橘(きつ)という」と記す。
「橘」は、小形の「柑橘類」をさすようである。
奈良時代の「橙」は、牧野富太郎の説くように、小形の「紀州みかん」の類とみるべきであろう。
「くだもの」の語源は、「木(く)の物(もの)」で(「けだもの」の語源が、「毛(け)の物(もの)」であるのと同じ語構成)、果実の食用となるものをさしている。
■多遅摩毛理(たじまもり)は、「ときじくのかくの実」を、どこにとりに行ったのか
『古事記』『日本書紀』は、多遅間守は「常世(とこよ)の国」に行って、「ときじくのかくの木の実」をもって帰ったという。
『広辞苑』で、「常世の国」を引くと、「古代日本民族が、遥(はる)か海の彼方(かなた)にあると想定した国」「不老不死の国」「仙郷」「死者の国」などの意味がのっている。多遅摩毛理は、遠い海外の国に行ったことを思わせる。その国は、どこの国であろう。国文学者の次田潤(つぎたうるう)氏は、その著『古事記新講』(明治書院刊)のなかで、つぎのようにのべる。
「田道間守(たじまもり)が江南の橘を得て帰ったことがよしや伝説であっても、その伝説を生ずるに至った背後には、外来の珍宝が続々渡来した事実があったことであろう。」次田潤は、田道間守が、「江南の橘」を得て帰ったように記している。
岩波書店刊の『古事記』(日本思想大系)にも、「垂仁天皇記」の橘について、「中国(の江南の)浙江省原産の温州蜜柑の原種かとする説がある。」
とのべられている。
日本の食べられる「橘」の源を江南の地に求めるのは、あるていどの根拠をあげることができるように思える。まず、江南の地は、むかしから食べられる柑橘類の産出地としてしられる。
『日本国語辞典』で、浙江省の「温州(おんしゅう)」の項を引くと、つぎのようにある。
「温州(おんしゅう)、中国、浙江省南部の都市。甌江(おうこう)の下流に位置し、茶、柑橘類の集散地として知られる。」
同様の記事は、他の辞書類にも記されている。
「今は甌江(おうこう)流域に産する茶、竹林、木材、ミカン類や、本市で製造する陶磁器、紙、織布などが主要な移出品である。」(『世界大百科事典』平凡社刊、「温州(おんしゅう)の項)「農業は茶・煙草・柑橘・木材等」(「東洋歴史大辞典」臨川書店刊、「温州」の項)
「浙江省」という項目で引いても、つぎのようにある。
「浙江(せっこう) 中国の省の一つ。中国南東部の東シナ海岸に位置する。温暖多雨で米、綿、茶、柑橘(かんきつ)類などを産出。寧波(にんぽー)・温州(おんしゅう)・紹興(しょうこう)などの都市がある。古代の越の地。」(『日本国語大辞典』)
「温州、西湖、紹興は製茶の中心地である。温州ミカンの原産地であるのみでなく、奉化の水蜜桃(すいみつとう)その他全国的に知られたくだものの産地が多い。」(「世界大百科事典」)
■多遅摩毛理は、中国の江南・東晋の地へ行つたとみられる
垂仁天皇の時代は、四世紀の後半ごろにあたるとみられる。
そのころ、中国の江南には、東晋の王朝が存在した。(下記の地図参照)
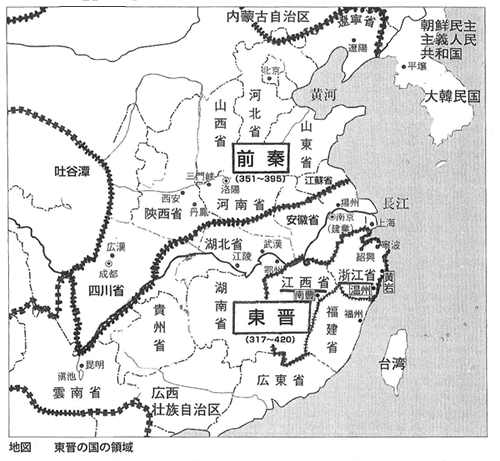
中国浙江省の温州の地なども、東晋の領域にはいっていた。三国時代の呉の国と東晋の国とは、都はともに、現在の南京の地で、領域はかなり重なる。そして、わが国は、この東晋と交渉をもっていたとみられる。
卑弥呼は、三世紀前半に、北中国の魏と外交関係を結んだ。
魏はそのうち、司馬懿(しばい)仲達の子孫の司馬炎(武帝)に国をゆずる。晋(西晋、265~316)が成立する。
倭人が、西晋とも交渉をもっていたことは、『日本書紀』の神功皇后紀の616年の条に引用されているつぎの文によってうかがわれる。
「晋の起居の注(天子の言行録)に云う。武帝の泰初(秦始)の二年(西暦266)の十月に、倭の女王、訳(おさ)を重ねて(日本語を朝鮮語に訳し、その朝鮮語を中国語に訳すというように通訳を重ねて)貢献(こうけん)せしむという。」
この「倭の女王」は、卑弥呼のあとに立った台与のことであろうといわれている。
『晋書』の「武帝紀」にも、
「泰始二年(266)、十一月己卯(つちのとう)[五日]、倭人来(きた)りて、方物を献ず。」とある。
『晋書』の「四夷伝」の倭人の条にも、つぎのように記されてる。
「その女王(卑弥呼)は、使をつかわして、帯方にいたり朝見す。その後貢聘(こうへい)[みつぎたずねる]絶えず。文帝[司馬懿(しばい)仲達の子司馬昭]の相となるにおよび、またしばしばいたる。泰始のはじめ、使をつかわして、訳を重ねて入貢す。」
ここには、「しばしばいたる」とある。
また、わが国では、一面だけであるが、西晋の「元康」(291~299)の年号のはいった紀年銘鏡が出土している。
この鏡が、輸入されたものであるならば、元康(291~299)のころまで、中国と直接または間接の交流があったことになる。
この鏡が、国産のものであるならば、西晋の「元康」の年号についての知識をもつものによって、「元康」以後につくられたことになる。やはり、「元康」または「元康」を下るころまで、中国と直接または間接の交流があったことになる。
西晋の国政はやがて乱れ、南匈奴の軍が、晋の都洛陽をおとしいれ、西暦316年に、晋は、いったんほろぶ。
晋の王室の一族の司馬睿(しばえい)[元帝]は、江南で、晋を再興する。東晋(317~420)である。
やがて、華北全般は、前秦の苻堅(ふけん)が統一し、揚子江流域以南は、東晋が確保し、南北対立の時代をむかえる。
四世紀の前後、わが国と東晋が、直接関係があったのではないかと思わせる資料も、いくつか存在する。
(1)西晋の266年に、西晋に、倭の女王が、使をつかわし貢献したことは、すでにみた。東晋は、西晋をつぐものであるから、倭が、東晋とも交渉をもったことは、十分考えられる。
(2)『晋書』の帝紀には、「倭」とは記されていないが、「東夷」と関係をもっていたことは、しばしば記されている。たとえば、つぎのように。
「(武帝紀の)太康十年(289)東夷絶遠三十余国来献。」
「(武帝紀の)太熙元年(290)東夷七国朝貢。」
「(恵帝紀の)永平元年(291)東夷十七国内付。」
「(孝武帝紀の)太元七年(382)九月、東夷五国が使を遣わして来たり、方物を貢じた。」
(3)『晋書』の安帝紀に、つぎのようにある。
「義熙九年(413)十一月、この歳(とし)、高句麗、倭夷、および、西南夷、銅頭大師が、ともに方物を献じた。」
413年には、倭は、あきらかに、江南の東晋と直接交渉をもっているのである。
(4)江南には、東晋のあと、東晋から禅譲をうけて、劉裕(武帝)が、宋王朝(420~479)をひらく。
いわゆる倭の五王時代、わが国は、しばしば、宋と交渉をもつ。これは、西晋、東晋以来の交流の流れを、うけつぐものであろう。
(5)永寧二年(302)の骨尺にもとづけば、晋の一尺は、二十四センチである。このものさしではかれぱ、崇神天皇隆古墳の全長240メートルは、ちょうど1000尺である。垂仁天皇陵古墳の全長は、950尺、景行天皇陵古墳の全長は1300尺である。晋のものさしを用いて、古墳の設計が行なわれているようにみえる。
『日本書紀』は、「垂仁天皇紀」の田道間守伝承のなかで、つぎのようにのべている。
「田道間守は、万里(とおく)浪を踏(ふ)み、弱水(よわみず)を渡り、絶域(はるかなるくに)に行った。その常世の国では、神仙(ひじり)の秘区(かくれたくに)で、ふつうの人の行けるところではない。峻(たか)い瀾(なみ)をしのいで、非常(ときじく)の香(かく)の実をもって帰った。」
垂仁天皇の時代よりものちの時代に、朝鮮半島から渡来してきた人たちの系譜の人を、中国につかわしてる例は多い。
田道間守は、祖先の出身地の、朝鮮半島のことはよく知っていたはずである。香(かく)の実を求めた常世の国は、朝鮮半島方面でないことはいえそうである。朝鮮半島方面ならば、はっきりとそのように書きそうである。
また、「常世の国は、神仙の秘区」などの表現は、「常世の国」が、神仙思想の行なわれていた地域であることを思わせる。
とすれば、「常世の国」は沖縄や、南洋方面をさすのではないであろう。
中国の南部では、神仙思想をえがいた鏡がつくらていた。
三角縁神獣鏡には、神仙と獣形がえがかれている。神仙として、東王父、西王母、伯牙、黄帝などがえがかれていると判断される。
三角縁神獣鏡は、中国では、出土しないが、中国で出土する三角縁画像鏡と平縁の神獣鏡(画文帯神獣鏡など)とを、ミックスしたようなデザインになっている。そして、中国の三角縁画像鏡と平縁の神獣鏡とは、おもに、中国の長江(揚子江流域)で出土するものである。
神話化し、伝説化しているけれども、田道間守のおもむいた先は、中国の南部の地、東晋の地だったようにみえる。
■田道間守(たじまもり)がおとずれた地
-----------------------------------------------------------------------------
コラム4 クネンボと紀州ミカン
岩波書店刊の『広辞苑』に、「クネンボ」と「紀州ミカン」について、つぎのような説明がある。
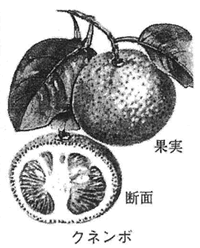 ・「くねんぼ【九年母】ミカン科ミカン類の常緑低木。タイ・インドシナ原産。高さ約三メートル。葉はミカンに似て大形。初夏、香気の高い白色五弁花をつける。果実は秋熟し、大きさはユズに似る。皮が厚く、佳香と甘味とを有する。香橘(こうきつ)。香橙。くねぶ。〈季・冬〉」
・「くねんぼ【九年母】ミカン科ミカン類の常緑低木。タイ・インドシナ原産。高さ約三メートル。葉はミカンに似て大形。初夏、香気の高い白色五弁花をつける。果実は秋熟し、大きさはユズに似る。皮が厚く、佳香と甘味とを有する。香橘(こうきつ)。香橙。くねぶ。〈季・冬〉」
・「きしゅうみかん【紀州蜜柑】ミカンの一品種。
中国原産。枝の多い低木で、葉は小形。果実も小さく、種子が多い。わが国で最も古くから暖地に栽培され、寛永(1624~1644)年間に紀州から江戸に出荷され、長く賞味されたが、温州(うんしゅう)蜜柑の普及によって圧倒された。」
「紀州ミカン」は、タネが多い。そのため、「子宝運」をよくするということで、明治時代のはじめごろまでは、よく食べられ、よく栽培されていた。しかし、現在では、生産量がすくない。ただ、インターネットで検索して注文すれば、一定の時期(十二月ごろ)入手可能。
[図は『新世紀ビジュアル大辞典』(学習研究社刊)による]
-----------------------------------------------------------------------------
さて、今回、『朝日新聞』などに紹介された農研機構果樹茶業研究部門の発表は、「温州ミカン」両親にあたるものを明らかにしたものであった。
すなわち、母親にあたる「種子親」は、「紀州ミカン(小みかん)」、父親の「花粉親」は、「クネンボ」であることを明らかにしたものであった(前に示した「タチバナ」と「ミカン」の朝日新聞の記事参照)。
これは、「紀州ミカン(小みかん)」の原産地はどこであるか、とか、「紀州ミカン」がどのようなルートでわが国にわたってきたか、とかを、直接教えてくれるものではない。ただ、多遅摩毛理が、「どこへ」、「ときじくのかくの実」をとりに行ったのかを推定するさいに、推定の範囲を、ある程度せばめてくれる情報を、もたらしてくれているようにもみえる。
この新聞発表の内容について、記事のなかに名のみえる藤井浩主席研究員に御連絡させていただいたところ、早速、原発表論文(英文)や多量の参考文献コピーを、恵送いただいた。まことに感謝にたえない。
その原著論文は『Breeding Science(育種科学)』のVol.6、No.5(2016)に発表されたもので、以下の題名のものである。
「Parental diagnosis of satsuma mandarin revealed by nuclear and cytoplasmic markers(核および細胞質マーカーによるウンシュウミカン[Citrus unshiu Marc.]の親子鑑定)」(藤井浩、太田智、野中圭介、片寄裕一、松本敏美、遠藤朋子、吉岡照高、大村三男、島田武彦、共同執筆)
なお、ご論文をお送りいただいたあとで気がついたが、このご論文の全文は、インターネットで見ることができる。
このご論文のなかに、つぎのような文章がある。
「結論として、薩摩マンダリン(温州ミカン)は、紀州ミカンタイプのマンダリン(「南豊蜜橘」の子孫あるいは同類)の種子親と、クネンボタイプのマンダリン(「本地広橘」の子孫あるいは同類)の花粉親とのたまたまの交雑に由来しているようにみえる。」
ここで、「南豊蜜橘」は、同論文のなかで、「中国の広西省において栽培されているおもな品種である。」とある。
江西省には、南豊県が存在する。「南豊蜜橘」の名は、南豊県に由来するとみられる。
インターネットでしらべると、京都大学の北島宣(きたじまあきら)氏らの研究論文「無核性カンキツの探索とその起源に関する研究」がのっており、そこでは、南豊蜜橘の原産地を「江西省南豊県」としている。
また、「本地広橘」については、インターネットの「コトバンク」に『世界大百科事典』の第2版を引用して、つぎのように記す。「(中国の)浙江省黄岩県からもたらされた。」
浙江省で、栽培されている品種のようである。
なお、浙江省の黄岩県については、田中長三郎氏が、「温州蜜柑(みかん)の起源併(ならび)に学名に就(つい)て」(『柑橘研究』[田中柑橘試験場編集]第一巻、第一号、1927年刊)という論文のなかで、「小みかん」について、その支那沿岸に於(お)ける産地は、」「(浙江省の)黄岩県のみ」と記している。
以上に名のみえる「江西省」「浙江省」の二つの省を中国の地図上でみると、前に示した「東晋の国の領域」の地図のようになる。いずれも、長江の南に存在する。その地図には、「南豊県」「黄岩県」「温州市」の場所も示した。
田道間守がおとずれたのは、このような江南の地であろうと、思わせる。
漢の時代に、淮南王(わいなんおう)の劉安(りゅうあん)が編纂した本に、『淮南子(えなんじ)』がある。
その『淮南子』のなかに、つぎのような句がある。
「江南の橘(きつ)[たちばな]、江北の枳(き)[からたち]となる。」(長江の南岸に生えているタチバナを、北岸に移し植えるとカラタチに変化する。人も境遇によって、性質が変わる。)
これは、南の橘を北に持って行くと、枳(き)[からたち]になるとしている。これは南にあるものは「橘」としている。このことから、『魏志倭人伝』のた「橘」として「カラタチ」とはしていない。つまり南の柑橘類とした。
田道間守がもって帰ったのが、「橘」であるとすれば、それは、やはり、江南の地からもって帰ったものであろう。なお、『文選(もんぜん)』の「三都の賦(さんとのふ)」では、すでに紹介したように、「呉都の賦」にみえる「丹橘(たんきつ)」、「蜀都の賦」にみえる「橘(きつ)・柚(ゆう)」のように、柑橘類についての紹介がみえる。
ただ、魏の都の鄴(ぎょう)のことを写した「魏都の賦」では、桃(もも)・李(すもも)・梨(なし)・栗(くり)・棗(なつめ)などの果物を紹介しながら、柑橘類については、ふれるところがない。
これも、北の方の魏の都には、柑橘類がすくなかったためであろう。
下記の地図に、「中国において柑橘の分布している省を示す。 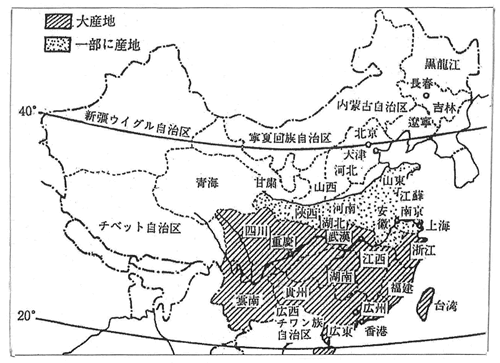
中国浙江省の温州の地なども、東晋の領域にはいっていた。三国時代の呉の国と東晋の国とは、都はともに、現在の南京の地で、領域はかなり重なる。そして、わが国は、この東晋と交渉をもっていたとみられる。
この地図を前の地図とみくらべれば、中国での柑橘類の「大産地」は、おもに、かつての、呉の国と、蜀の国との領域内になることがわかる。
なお、クネンボについては、室町時代以前に、中国の福建省の福州から沖縄に持ちこまれたとする説や、直接東南アジアから沖縄にもちこまれたとする説などがある。沖縄は、柑橘類の生育に適しており、柑橘類伝来の主要なルートの一つと考えられている[稲福(寺本)さゆり氏の学位論文(鹿児島大学)『琉球列島在来カンキツ遺伝資源』(2011年)による]。
■「弱水(よわのみず)」とはなにか
さきの『日本書紀』の「垂仁天皇紀」の文のなかには、「弱水(よわのみず)」ということばがでてくる。
「弱水(よわのみず)」とは、なんだろう。
中国文献にみえる「弱水(じゃくすい)」について、くわしい考察を行なっているのは、明治から昭和期前期にわたって活動した東洋史学者、白鳥庫吉である。
白鳥庫吉は、論文「弱水考」(1896年11月・12月『史学雑誌』第7編第11号・12号、岩波書店、1970年刊『白鳥庫吉全集第五巻』所収)をあらわしている。
中国文献にみえる「弱水」には、さまざまなものがある。
たとえば、『後漢書』『三国志』『晋書』の「夫余国伝」や『晋書』の「粛慎伝(しゅくしんでん)」にみえる「弱水」は黒竜江をさす。
『後漢書』『三国志』『晋書』には、「夫余国の北に弱水がある」と記されている。
「晋書」には、「粛慎氏の北、弱水に極まる(弱水まで達している)」とある。
田道間守が、「橘」を、黒竜江方面に求めたとは考えられない。『広辞苑』で、「柑橘類」を引くと、「原産は東南アジア」とある。食べられる「橘」を求めるとすれば、あたたかいところであろう。
『日本書紀』の「垂仁天皇紀」にみえる「弱水」は、黒竜江をさしているとはみられない。
また、『後漢書』の 大秦国(ローマ帝国)伝」に、つぎのようにある。
「その国(大秦国)の西に、弱水流沙がある。西王母の居するところに近く、日の入るところに近い。」
田道間守が、ローマ帝国方面まで行って、「橘」を求めたとも思えない。
中国文献にみえる「弱水」は、いずれも、『日本書紀』「垂仁天皇紀」の「弱水」にはあてはまらない。
白鳥庫吉は、『日本書紀』「垂仁天皇紀」の「弱水」については、およそ、つぎのようにのべる。
「田道間守伝承中の弱水は、特別な川を指しているのではない。ただ編者が文章を修飾するために、西王母の仙譚のなかにみえる河の名をかりて来たか、そうでなければ、伝聞の誤りである。」
「弱水の名の意味について、はじめて解釈をこころみた中国人は、東晋の郭璞(かくはく)である。この学者の説によれば、弱水の水は弱くて、鴻毛(こうもう)[鴻(おおとり)の羽毛。きわめて軽いもののたとえ)にもたええない。ゆえに、溺水と名づけたのであるという。『日本書紀』の「弱水」の訓みに『よわのみず』とあるのも、この釈意を汲(く)んだのであろうか。」
「弱水」と西王母との結びつきなどから、神仙思想の影響で、『日本書紀』の編者は、「弱水」ということばを用いたのであろう。あるいは、たんに、西の方の意味で用いたのかもしれない。
「弱水」が、西の方と結びつくイメージのあったことは、すでに漢代の文人の揚子雲(紀元前53~18)が、「甘泉の賦」(「文選」所収)のなかで、およそつぎのようにのべていることからもうかがえる。
「弱水」の小さな流れを一飛びにわたり、西海の外にある不周の山のうねうねと続く峰を越えて西の果てにいたり、西王母のことを思い起こして……。」
なお、『古事記』『日本書紀』のストーリィの流れからいえば、垂仁天皇の条よりもまえの、神話の巻にあらわれる「竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(おど)の阿波岐原(あはぎはら)」(『古事記』)、「日向(ひむか)の小戸(おど)の橘(たちばな)の檍原(あわぎはら)」(『日本書紀』)の「橘」は、野生の「やまとたちばな」とみるべきであることになる。
■田道間守(たじまもり)の墓
田道間守の墓についてお話しよう。
まず、『日本書紀』の「垂仁天皇紀」に、つぎのような記事がある。
「(垂仁天皇がなくなられた年の)翌年春三月の辛未(しんび)朔(ついたち)の壬午(じんご)[十二日]に、田道間守は常世国から帰って来た。
その時、持ち帰って来た物は、非時香菓(ときじくのかくのみ)、八竿(やほこ)八縵(やかげ)であった。田道間守は、天皇が崩御されたことを聞いて、泣き悲しんで、『ご命令を天皇より承って、遠隔の地に参り、万里の波浪を越えて、遥かに弱水(よわのみず)を渡りました。この常世国は、神仙が隠れ住む世界であって、俗人が行ける所ではありません。そういうわけで、往復する間に自然に十年が経過いたしました。思いもよらないことでありました。ただひとり高い波頭を越えて再び本土に戻ることができようとは。しかしながら、聖帝の神霊によって、かろうじて帰って来ることができました。今、天皇はすでに崩御され、帰着の復命をすることもかないません。わたしが生きていても、また何の甲斐(かい)がありましょうか」と申した。そうして、天皇の御陵におもむき号泣して、自ら死んだ。群臣はこれを聞いてみな涙を流した。田道間守は、三宅連(みやけのむらじ)の始祖である。」(現代語訳は、『新編日本古典文学全集2』の『日本書紀』[小学館刊]による。)
そして、「日本古墳大辞典」(東京堂出版刊)の「垂仁天皇陵古墳」の項に、つぎのような記事がある。
「垂仁天皇陵古墳 奈良県奈良市尼ヶ辻に存在する墳丘全長227m、後円径123m、埴輪と葺石をもつ整美な南面の前方後円墳。平野部に立地し、周堀の東側に接して近鉄橿原線が走る。陵名は菅原伏見東陵(すがわらのふしみのひがしのみささぎ)といい、宝来山古墳の別名がある。墳丘は2段築成の可能性があり、後円部径123m、高さ17.3m、前方部幅118m、高さ15.6m、周堀を含めた総長は330mに達する。周堀内の東南口に1小円墳があり、垂仁紀の田道間守の説話によって陪塚とする伝えがある。明治時代修築の際に陪塚として指定された。また周堀の東南部外堤が外方へ張り出しているのも、後世の変形によるものであろう。【文献】末永雅雄『日本の古墳』1961、朝日新聞社」
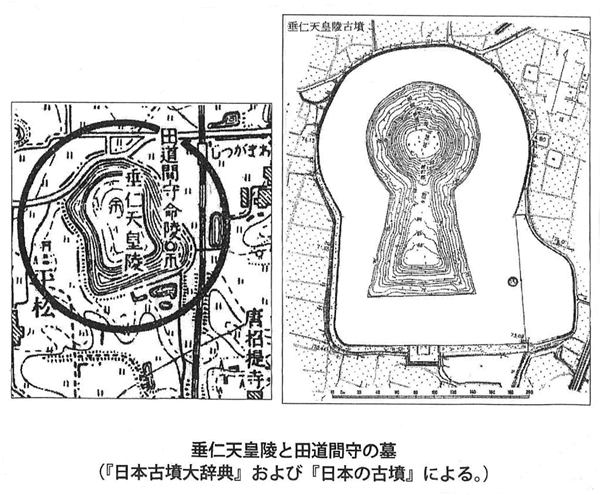
ここに、垂仁天皇陵の「陪塚」として「田道間守」の墓のことが記されている。
また、末永雅雄著『日本の古墳』(朝日新聞社、1956年刊)に、田道間守の墓の位置を示す図や写真がのっている。また、インターネットにも、「田道間守」の墓の写真がかなり多くのっている。
■多遅摩毛理(たじまもり)の系譜
多遅摩毛理の系譜は、『古事記』『日本書紀』に記されている。
それらによれば、多遅摩毛理は、新羅(しらぎ)から来た王子、天之日矛(あめのひほこ)[天日槍]の子孫である。
『古事記』に記されている系譜と『日本書紀』に記されている系譜とでは、多少異なっている。(下の系図右の2つ)
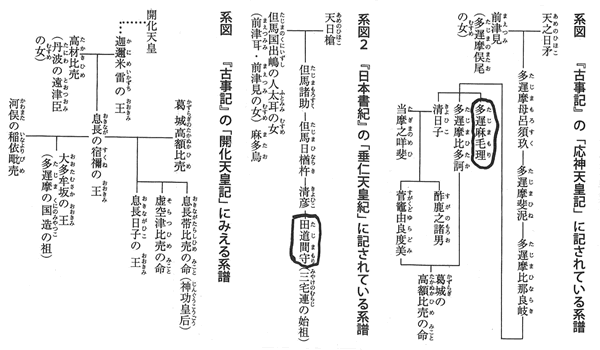
また、上の系図の一番右の『古事記』の「応神天皇記」の最後にみえる「葛城(かずらぎ)の高額比売(たかぬかひめ)」は上の系図の一番左の『古事記』の「開化天皇記」にみられるように、第十四代仲哀天皇の皇后、神功皇后の母である。
また「多遅摩毛理」の名は、兵庫県北部にあった国名、「但馬(たじま)の国」(下図参照)と関係があるとみられる。
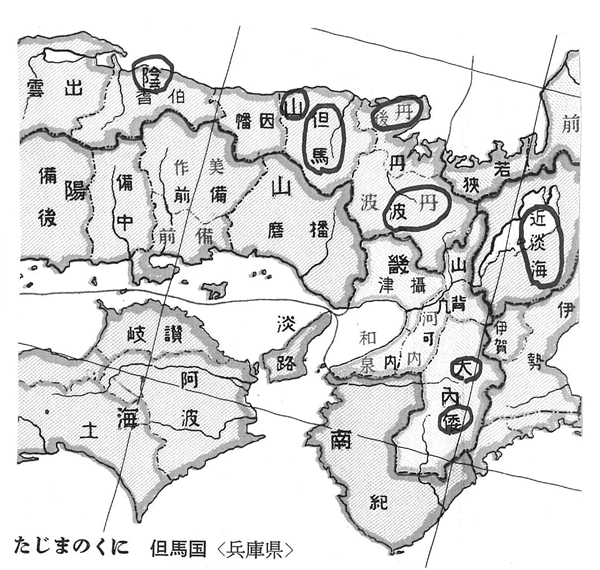
■万葉集にも書かれた多遅摩毛理
橘(たちばな)の歌一首と短歌
▼申すのも はなはだ恐れ多い 古(いにしえ)の 聖天子の御代(みよ)に 田道間守(たじまもり)が 常世の国に渡り。八矛を持って 帰朝した時 非時(ときじく)の 香菓(かくのこのみ)として恐れ多くも お残しになったところ 国じゅうに 生(お)い満ち茂り 春になると 新しい枝が出 ほととぎすの 鳴く五月には 初花を 枝どと折って 乙女(おとめ)らに 贈ってやったり (白たへの) 袖(そで)にもしごき入れ 良い匂いなので しぼむまで置いたりし 落ちた実は 玉として緒(お)に通し 手首に巻いて 見ても飽きない、秋になると しぐれが降って (あしひきの) 山の梢は 紅(くれない)に 染まって散るが 橘の なったその実は 一面に照り輝き 一段と見事で 雪の降る 冬ともなれば 霜が置いても その葉も枯れず 変ることなく いよいよ輝きを増して それだからこそ 神代の昔から いみじくも この橘を 非時(ときじく)の 香菓(かくのこのみ)と 名付けたのだろう
反歌一首
▼橘は 花でも実でも 見ているが ますます年じゅう なおも見たいものだ
これは、天平感宝(てんぴょうかんぽう)元年(749年)閏(うるう)五月二十三日に、大伴宿禰家持(おおとのすくねやかもち)が作ったものである。
このように、多遅摩毛理は有名で万葉集にも歌われている。
■但馬(たじま)の国について
『日本書紀』の「垂仁天皇紀」の三年三月の条に、新羅の王子の天の日槍(あめのひほこ)が、近江の国の吾名(あな)の邑(むら)に住んだのち、近江から若狭(わかさ)の国(福井県の西部)をへて、西の但馬の国(兵庫県の北部)にいたって住むところを定めたことが記されている。
天の日槍は、そこで、但馬の国の出嶋(いずし)[出石]の人である太耳(ふとみみ)[前津耳(まえつみみ)または前津見(まえつみ)ともいう]のむすめの麻多烏(またお)と結婚し、但馬諸助(もろすく)を生む。諸助は、但馬日楢杵(ひならき)を生み、日楢杵は、清彦(きよひこ)を生む。清彦は、田道間守(たじまもり)を生んだという。天の日槍の子孫は、代々但馬にいたようである。
また、『日本書紀』の「垂仁天皇紀」八十八年七月の条に、天の日槍がもってきた神宝は、但馬の国にあると記されている。
『古事記』では、天の日矛(あめのひぼこ)が持ってきたのは、八種の宝で、その八種の宝は、「伊豆志(いづし)の八前(やまえ)の大神(おおかみ)[伊豆志は、但馬の国出石(いずし)郡]」(つまり、八種の宝が、神社の神体)と記している。
『日本の神々 神社と聖地7 山陰』(谷川健一編、白水社刊)の「出石神社(兵庫県出石郡出石町宮内字芝地)」の項には、つぎのように記されている。
「豊岡市・出石町を中心とする北但馬(たじま)の地域には、新羅の王子天日槍(あめのひぼこ)とその一族および従神を祀る古社が分布する。当社はその中核に位置し、式内名神大社、但馬一の宮として古代から崇敬を集めてきた。『延喜式』神名帳の但馬国出石郡二十三座(大社九座・小社十四座)の筆頭に『伊豆志坐(いづしにます)神社八座並名神大』とあり、天日槍が将来したという八種(やくさ)の神宝(かんだから)[『古事記』のいう珠二貫(たまふたつら)・振浪比礼(なみふるひれ)・切浪(なみきる)比礼・振風(かぜふる)比礼・切風(かぜきる)比礼・奥津(おきつ)鏡・辺津(へつ)鏡。ただし『日本書紀』本文は羽太玉(はふとのたま)一個・足高(あしたか)玉一個・鵜鹿鹿赤石(うかかのあかし)玉一個・出石小刀(いづしのかたな)一口・出石桙(いづしのほこ)一枝・日鏡(ひのかがみ)一面・熊野籬(くまのひもろき)の七種とし、一(ある)に云(いは)くとして葉細珠(はほそのたま)・足高(あしたか)玉・鵜鹿鹿赤石珠・出石刀子・出石槍(ほこ)・日鏡・熊野籬・胆狭(いさ)とし、一(ある)に云(いは)くとして葉細珠(はほそのたま)・足高(あしたか)玉・鵜鹿鹿赤石珠・出石刀子・出石槍(ほこ)・日鏡・熊野籬・胆狭浅大刀(いささのたち)の八種とする]を祭神『出石八前(やまえ)大神』とし、天日槍の御霊(みたま)を併せ祀っている。」
このように、この神社の祭神は、天の日槍と八種の神宝である。
出石神社は、中世から、但馬の国の一の宮(各国の、由緒があり信仰のあつい神社で、その国第一位のもの)とされている。
室町時代の古図には、本殿を六角か八画かと思われる特殊な形式に描き、両側に七社ずつの末社を、かたわらに天日槍廟所と伝称する塚を描く。社殿は、永正元年(1504)に兵乱で焼けてからは、旧観を失ったという。
奈良時代に、すでに、但馬の国最大の神社であった。
さて、地図をみればわかるように、出石神社の近くに、森尾古墳(兵庫県豊岡市森尾市尾)がある。
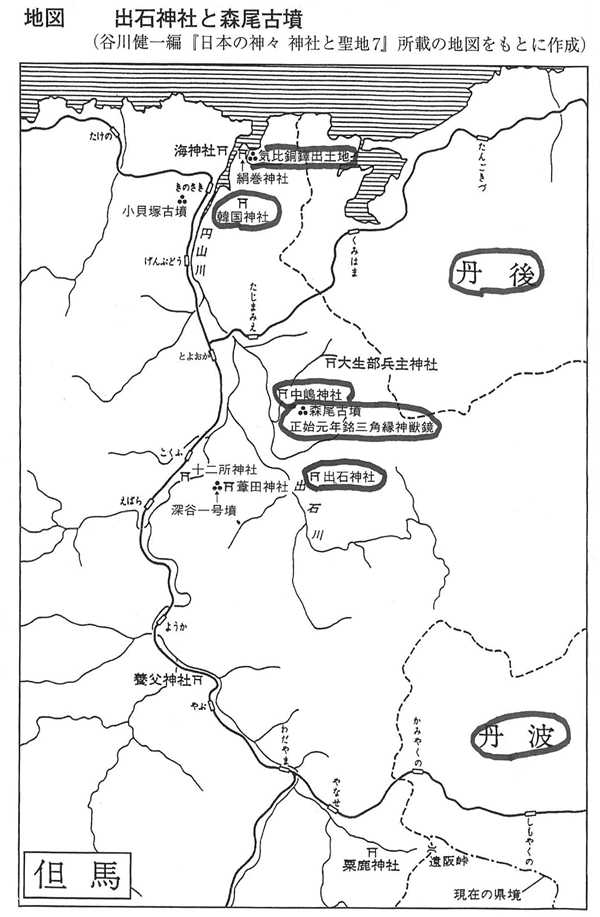
森尾古墳は、円墳である。径約九メートル、高さニメートルほど。
森尾古墳からは、「正始元年」銘の三角縁神獣鏡のほか、もう一面の三角縁神獣鏡と、方格規矩鏡とが出土している(計三面)。
森尾古墳からは、竪穴式石室が見いだされている。大塚初重氏らの『日本古墳大辞典』は森尾古墳の築造年代について、「年代の決め手に欠けるが、四世紀末から五世紀初頭の年代を与えておきたい。」とする。
森尾古墳のすぐ近くに、中嶋神社がある(上の地図参照)。『延喜式』の神名帳にのっている神社である。
この神社の祭神は、田道間守(たじまもり)である。天の日槍の子孫である。
森尾古墳は、おそらく、天の日槍の系列の人の墓であろう。
出石神社や森尾古墳の北方、日本海の近くに、気比銅鐸出土地(兵庫県豊岡市気比字鷲崎)がある。ここからは、四個の銅鐸が出土している。
森尾古墳のばあい、つぎのような点において、大岩山古墳群のばあいと共通している。
(1)天の日槍に関連した伝承地が近くにある。
(2)重要な三角縁神獣鏡が出土している。
大岩山古墳群のばあいは、わが国でもっとも古いかとみられる三角縁神獣鏡が出土している。森尾古墳のばあいは、「正始元年」銘の年号鏡が出土している。
(3)近くから銅鐸が出土している。
「播磨風土記」に天の日槍伝説があり、これは、天の日槍は但馬開発にあたった渡来人集団を象徴したものと考えられるとする説がある。
出石神社は八種の神宝があり、近くの森尾古墳から「正始元年」銘の年号鏡が出土している。また、その近くに中島神社がありその祭神が田道間守である。
紀年銘鏡として、但馬(たじま)の森尾古墳から「正始元年」、丹波の大田南五号墳から「青龍三年」、出雲の神原神社古墳から「景初三年」が出土している。
このようなことから見ると、鏡の問題と関係しているように思える。今回は鏡関係の話は省略する。




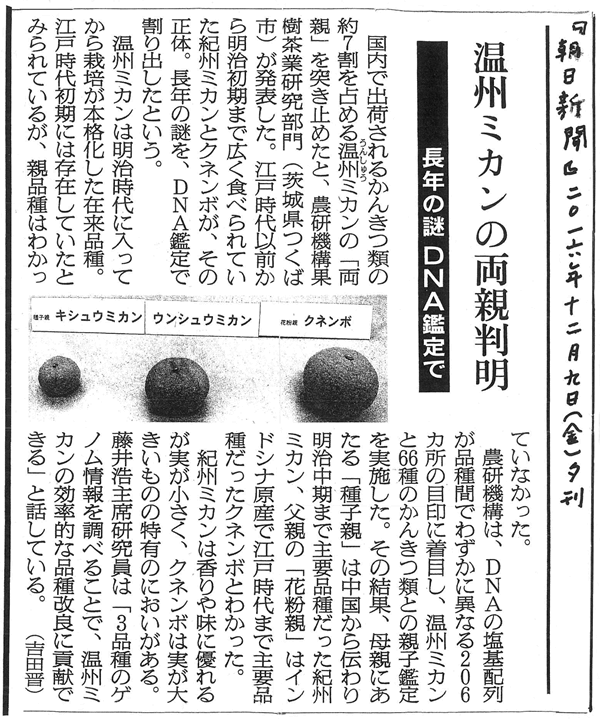
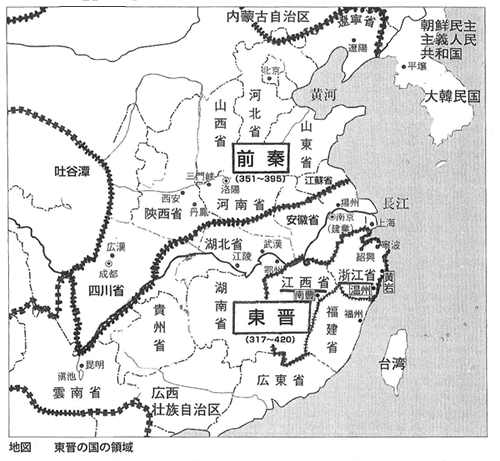
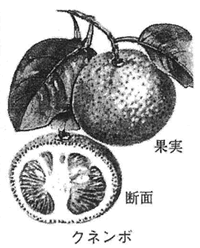 ・「くねんぼ【九年母】ミカン科ミカン類の常緑低木。タイ・インドシナ原産。高さ約三メートル。葉はミカンに似て大形。初夏、香気の高い白色五弁花をつける。果実は秋熟し、大きさはユズに似る。皮が厚く、佳香と甘味とを有する。香橘(こうきつ)。香橙。くねぶ。〈季・冬〉」
・「くねんぼ【九年母】ミカン科ミカン類の常緑低木。タイ・インドシナ原産。高さ約三メートル。葉はミカンに似て大形。初夏、香気の高い白色五弁花をつける。果実は秋熟し、大きさはユズに似る。皮が厚く、佳香と甘味とを有する。香橘(こうきつ)。香橙。くねぶ。〈季・冬〉」