■「応神天皇陵古墳」の築造年代
私は、「讃=応神天皇」の陵墓は、「応神天皇陵古墳=誉田御廟山古墳」でよいものと考える。
その理由は、つぎのとおりである。
(1)応神天皇の年代を古くみつもり、「倭王讃=仁徳天皇」説をとると、天皇の在位の時期と、応神天皇陵古墳の推定築造時期とが、あわなくなる。
しかし、応神天皇を、すでにのべたように、西暦430年ごろまで在位した人であるとすれば、応神天皇の年代と、応神天皇陵古墳の推定築造時期とはあう。たとえば、筑波大学名誉教授の川西宏幸(かわにしひろゆき)氏は、円筒埴輪についての精緻な編年にもとづき、古墳の年代推定を行なっておられる。
川西宏幸氏の著書『古墳時代政治史序説』(塙書房、2012年刊)によれば、大型古墳の時期の実年代推定値は下の表のようになっている。
(下図はクリックすると大きくなります)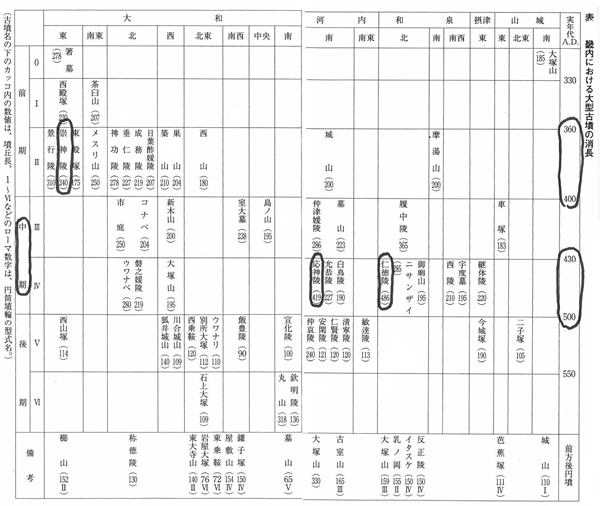
この表によれば「応神天皇陵古墳(表に応神陵とあるもの)」「仁徳天皇陵古墳(表に仁徳陵とあるもの)」の実年代推定値は、「430年~500年」とある。
応神天皇の在位を430年ごろまでとすれば、ほぼ、年代はあっている。
(2)応神天皇陵については、『古事記』は、「川内(かわち)の恵賀(えが)の裳伏(もふし)の崗(おか)にあり」と記す。「恵賀」の地は、「餌香(えが)の市(いち)」のあったところである。現在の「古市古墳群(ふるいちこふんぐん)」のある場所である。
927年に撰進された『延喜式(えんぎしき)』の「諸陵寮」に、応神天皇陵は、「河内の国志紀郡にあり。」と記しているのも、『古事記』の記述とあう。また、『延喜式』は、応神天皇の陵の兆域について「東西五町、南北五町」と記す。
ここに記される「町」は、どれぐらいの大きさを示すのであろうか。
ふっうは、1町は109メートルほどと考えられている。
ただ、平城京や平安京においては、1町を、121メートルとする長さの単位が用いられていた(『日本国語大辞典』[小学館刊])。たとえば、藤田元春著『尺度綜攷(しゃくどそうこう)(考)』(刀江書院、1929年刊)に、ただ、平城京や平安京においては、1町を、121メートルとする長さの単位が用いられていた(『日本国語大辞典』「小学館刊」)。たとえば、藤田元春著『尺度綜攷(考)』に、『九院仏閣抄』という文献が紹介されている。そこに、平安時代前期の僧の伝教大師(最澄)の言として、「四十丈が一町をなす」と記されているという。「四十丈が一町」なら、一町は121メートルほどである。
応神天皇陵の五町四方は、
・1町を109メートルとみれば、545メートル四方。
・1町を121メートルとみれば、605メートル四方である。この兆域はかなり大きい。
一方、応神天皇陵古墳の墳丘全長は、『日本古墳大辞典』(東京堂出版刊)に、425メートルとある。
応神天皇陵古墳は、『延喜式』に記されている兆域内に、おさまることになる。
いっぽう、古市古墳群には、多くの天皇陵古墳がある。『延喜式』に記されているそれらの天皇陵古墳の兆域は、つぎのようになっている。
・第十四代、仲哀天皇陵古墳 東西二町南北二町
・第二十二代、清寧天皇陵古墳 東西二町南北二町
・第二十四代、仁賢天皇陵古墳 東西二町南北二町
・第二十七代、安閑天皇陵古墳 東西一町南北一町
このように、たとえば「東西二町南北二町」の範囲では、応神天皇陵古墳は、兆域内には、はいりきれない。
(下図はクリックすると大きくなります)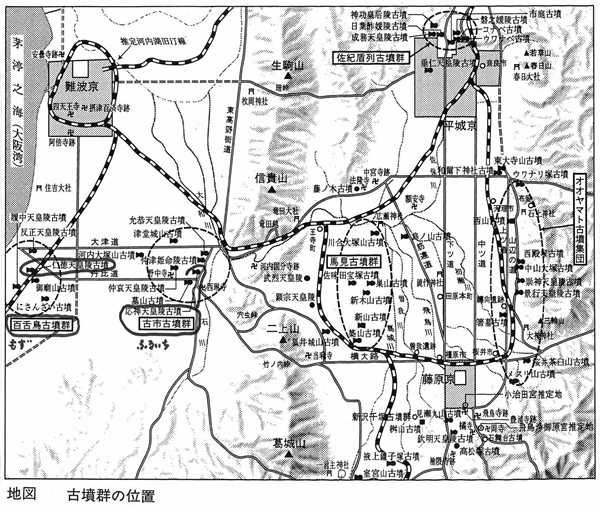
応神天皇陵古墳は、古市古填群のなかでは、最大の古墳である。『延喜式』の記す「東西五町南北五町」の兆域にふさわしいのは、応神天皇陵古墳である。
1915年に宮内省諸陵寮の職員の執務の便のために編纂された『陵墓要覧』も、応神天皇陵古墳を応神天皇の陵とする。
現在の『宮内庁治定陵墓の一覧』でも、応神天皇陵古墳を、応神天皇の陵としている。
かつ、応神天皇の皇后の仲姫命(なかつひめのみこと)の仲津姫命陵古墳(なかつひめのみことりょうこふん)も、応神天皇陵古墳のすぐ近くにある。
応神天皇陵古墳は、応神天皇の陵の本命(ほんめい)とみてよい古墳である。
(3)『日本書紀』の「雄略天皇紀」の九年七月の条に、つぎのような話がのっている。
「飛鳥戸郡(あすかべのこおり)[現羽曳野(はびきの)市の飛鳥から柏原(かしはら)市国分にかけての地]の人である田辺史伯孫(たなべのふびとはくそん)の娘は、古市郡[現羽曳野(はびきの)市古市(ふるいち)付近]の人である書首加竜(ふみのおびとかりょう)の妻である。伯孫は、その娘が、男の子を生んだと聞いて、聟の家にお祝いに行き、月夜に帰途についた。蓬蔂丘(いちびこのおか)の誉田(ほんだ)陵[応神天皇陵]の下で、赤馬に乗った人に出あった。その馬は、そのときうねるように行き、竜のごとくに首をもたげた。急に高く跳びあがって、鴻(おおとり)のように驚いた。その異(あや)しい体が、峰のようになり、あやしい形相がきわだっていた。伯孫は近づいてみて、心の中で、手に入れたいと思った。乗っていた葦毛の馬に鞭(むち)うって、轡(くつわ)を並べた。赤馬がおどりあがるさまは、塵埃のようで、さっとあがっては消え、走りまわる速さは、滅没するよりももっと速かった。
葦毛の馬は、遅くて追いつくことができなかった。その速く走る馬に乗っていた人は、伯孫の願いを知って、とまって馬を交換し、別れにあいさつをのべて去っていった。伯孫は、速く走る馬を得て、たいへんよろこび、走らせて厩に入れた。鞍をおろし、馬に秣(まぐさ)を与えて寝た。翌朝、赤馬は、埴輪の馬に変わっていた。伯孫はあやしんで、誉田陵にとってかえして探してみたら、葦毛の馬が、土馬(はにま)の中にいたのを見つけた。取りかえて、かわりに土馬を置いた。」
この記事で、田辺史伯孫は、南の古市から北の柏原市のほうへ向かっているのである。下の地図をみていただきたい。この記事の「誉田陵」は、明らかに、古市古墳群のなかに存在していた陵を示す。 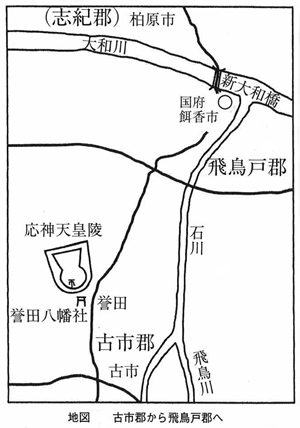
また、『日本書紀』は、応神天皇のことを、「誉田天皇(ほんだのすめらみこと)」と記しており、「誉田陵」は応神天皇の陵のこととみてよい。
じじつ、815年に成立した『新撰姓氏録』の、「左京皇別」の下の上毛野(かみつけの)
の朝臣(あそみ)の条に、さきの「雄略天皇紀」と同じ話をのせ、つぎのように記している。
「雄略天皇の御代、努賀(ぬか)の君の子の百尊(はくそん)は、娘が子を生んだので、聟の家に行き、夜をおかして帰った。応神天皇の陵の付近[応神天皇御陵辺(おうじんてんわうのみさざきべ)]で、馬に乗った人にあい、ともに語りあった。馬をとりかえて別れた。翌日、とりかえた馬をみると、土の馬であった。よって陵辺(みさざきべ)の君という姓を負う。」
ここでは、はっきりと、「応神天皇御陵辺」と記されている。
『日本書紀』や『新撰姓氏録』が編纂されたころ、応神天皇陵古墳が、応神天皇陵であると考えられていたとみられる。
現在も、応神天皇陵古墳は、大阪府羽曳野市誉田(こんだ)にある。この地名の「誉田(こんだ)」は、応神天皇の名の、「品陀和気(ほんだわけ)の命(みこと)」(『古事記』)、「誉田別皇子(ほむたわけのみこ)」「誉田天皇(ほむたのすめらみこと)」(『日本書紀』)の「ほむた」を伝えているとみられる。その地の地名にもとづいて、天皇の名がつけられたか、逆に、天皇の名にもとづいて、地名がつけられたものか。
これは、その地の地名にもとづいて、天皇の名がつけられた可能性のほうが、やや大きいようにみえる。応神天皇は、『古事記』によれば品陀(ほむだ)の真若(まわか)の王(おおきみ)の女(むすめ)を皇后としている。応神天皇以前の人の名に、「ほむた」があらわれる。河内方面の開発にあたり、皇后の父が地盤をもつ地に、応神天皇陵をきづいたものか。
「誉田(ほむた)」「誉田(こんだ)」にみられるような、「h音」と「k音」との交替は、日本語においてすくなくない。『日本書紀』の「神代紀」に、「岐(ふなと)[布那斗]」の神のもとの名は、「来名戸(くなと)」の祖(さえ)の神といったとある。
『日本書紀』の「景行天皇紀」にみえる「日高見(ひたかみ)国」は、そこを流れる「北上(きたかみ)川」と、語源を同じくするとみられる。
「乞食(こじき)」や「物貰(ものもら)い」を意味する「ホイト」は、「コフヒト(乞ふ人)」から来たとする説がある。
なお、誉田の地には「誉田(こんだ)八幡宮」がある。誉田八幡宮は、現在は、応神天皇陵古墳の南がわにあるが、かつては古墳の後円部の頂上部にあったという。
「八幡神(やはたのかみ、はちまんしん)」は、応神天皇のこととされる。「八幡宮」は、多く応神天皇、神功皇后などをまつるが、誉田八幡宮も、「品陀別命(ほんだわけのみこと)[応神天皇]」を主神とし、神功皇后、仲哀天皇のほか、住吉三神をまつる。
(4)1985年に発行された『季刊大林』20号の『王陵』によれば、仁徳天皇陵古墳の総動員数は、延ベ680万7千人(ただし、一日あたりピーク時で2000人)、工期は、15年8ヵ月と見つもられている。
応神天皇陵古墳の築造にも、これに近い動員数が必要とされたとみられる。これほど多数の人々を動員すれば、これが、仁徳天皇陵、あるいは、応神天皇陵であるという伝承は、クチコミで広がり、伝わりやすかったとみられる。被葬者を、あとで変更するのは、むずかしかったであろう。
(5)東京大学の教授で、考古学者であった斎藤忠は、『国史大辞典と(吉川弘文館、1990年刊)の「仁徳天皇」の項で記す。
「近年[仁徳天皇陵古墳=百舌鳥耳原中陵(もずのみみはらなかのみささぎ)を]仁徳天皇陵とすることに学問的な疑問をいだき『大仙古墳』という名称も提出されているが、墳丘の形態と重厚な歴史の伝承の上から、仁徳天皇陵とすることが適切と考えてよい。」
応神天皇陵古墳は、仁徳天皇陵古墳に近い時期とみられる古墳であるが、古墳の形式からいって、仁徳天皇陵よりやや古いとみられるから、仁徳天皇陵古墳を、仁徳天皇の陵とみるならば、応神天皇陵古墳も、応神天皇の真陵とみてよいように思う。
たとえば、大阪府教育委員会文化財保護課の考古学者であった野上丈助なども、応神天皇陵古墳を、応神天皇陵とする見解を、強く主張している(「応神天皇の陵墓は「応神陵」か」[『歴史読本』1986年臨時増刊号])。
■「前方後円墳築造時期推定図」の読み方
前方後円墳は、時代が下るにつれ、後円部に比し、前方部が相対的に発達する。 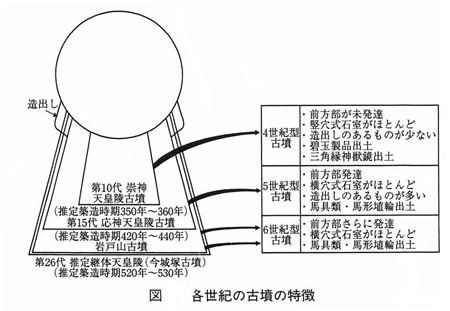
前方後円墳においては、右の図にみられるように、墳丘全長および後円部の径に比して、前方部の幅が、古い時代の前方後円墳ほど小さく、後代の前方後円墳ほど、大きくなる傾向がみとめられる。
いま、横軸(x軸)に、前方部の幅を後円部の直径で割った値、
[前方部幅/後円部径×100]をとる。
また、縦軸(y軸)に、前方部の幅を墳丘全長で割った値、
[前方部幅/墳丘全長×100]をとる。
そして、天皇陵古墳や皇后陵古墳、さらに代表的な前方後円墳などをプロットすれば、下の二つの図のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)
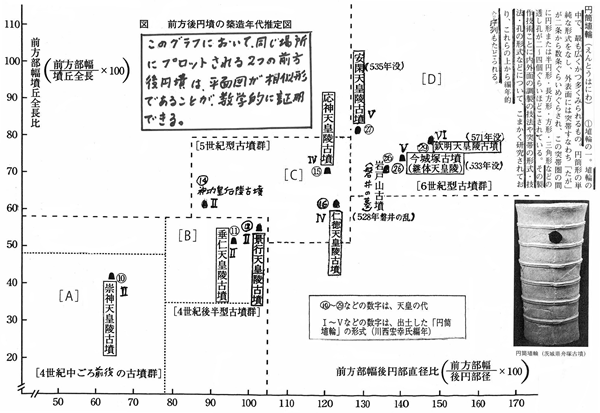
(下図はクリックすると大きくなります)
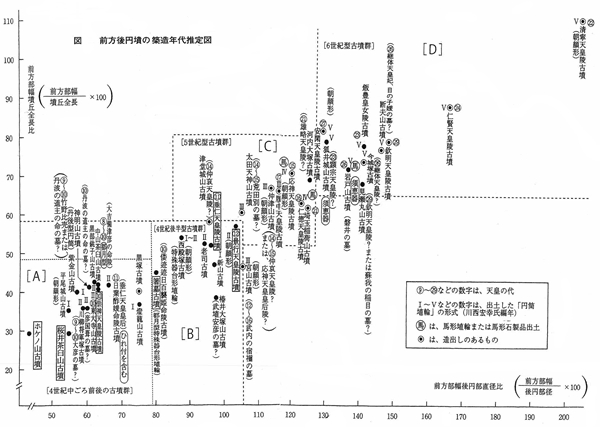
このようにグラフを描くと、古い時代の古墳は全体的に左下に、新しい時代の古墳は全体的に右上にプロットされる、それは、時代がくだるにつれ、後円部に比し、前方部が、しだいに発達する傾向があるからである。
すなわち、墳丘全長および後円部の径に比して、前方部の幅が、古い時代の前方後円墳ほど小さく、後代の前方後円墳ほど大きくなる傾向がみとめられる。
上の二つの図によって、前方後円墳の大略の築造時期を推定できる。
たとえば、第10代崇神天皇陵古墳、第11代垂仁天皇陵古墳、第12代景行天皇陵古墳などは、左下の「四世紀型古墳群」のなかに位置する。崇神天皇陵古墳を、西暦360年前後の築造とみてよいことはすでにのべた。
第15代応神天皇陵古墳、第16代仁徳天皇陵古墳、第17履中天皇陵古墳などは、「五世紀型古墳群」のなかに位置する。第21代雄略天皇のころの古墳とみられる埼玉県の稲荷山古墳は、「五世紀型古墳群」のなかでも、ほとんど「六世紀型古墳群」に近いところに位置する。
第24代仁賢天皇陵古墳、第26代継体天皇陵であることが通説になりつつある今城塚(いましろづか)古墳、第29代欽明天皇陵古墳などは、「六世紀型古墳群」に属する。第26代継体天皇のころの、西暦527年に反乱をおこした筑紫の国造(くにのみやつこ)磐井の墓とされる岩戸山古墳も、「六世紀型古墳」に属する。
そして、たとえば、第18代反正天皇陵古墳のように、五世紀の人物であるのに、天皇陵古墳が、「六世紀型古墳群」に属するというようなケースは、その古墳が、ほんとうに反正天皇の陵であるのかというように、古墳に当該天皇がほうむられているのか、従来からいろいろな根拠により強く疑われているものばかりといってよい。
全体的にみれば上に示した二つの図の「前方後円墳築造時期推定図」は、各古墳の築造時期を、かなりよく弁別しているといってよい。
この二つの図において、⑧などのような丸の中の数字は、その古墳の被葬者と一応されている人物が、ほぼ第何代目の天皇と同時代になるかを示したものである。たとえば、岡山県の吉備の中山茶臼山(ちゃうすやま)古墳は1915年に宮内庁からでている『陵墓要覧』では、吉備津彦の命の墓とされている。吉備津彦の命は、第7代孝霊天皇の皇子で、第10代崇神天皇の時代に活躍した人物である。したがって、中山茶臼山古墳のところには、⑧~⑩と記されている上の二つの図をみれば、およそつぎのようなことがわかる。
(1)古い代の天皇に関連した古墳は、おおむね左下にくる傾向があり、新しい代の天皇に関連した古墳はおおむね右上にくる傾向がある。そしてこの傾向は、考古学の分野で一般にいわれている古い時代に築造されたと推定されている古墳と、より新しい時代に築造されたと推定されている古墳との関係に対応している。このことは、すくなくとも統計的にみたばあい、いわゆる天皇陵古墳が、古墳の築造年代推定のあるていどの基準になりうることを示している。また、当該古墳に、ある天皇などが葬られているという伝承には、あたらずといえども遠からずていどの信憑性のあることを示している。
(2)筑波大学の川西宏幸氏による円筒埴輪の形式による編年は、信頼度が高いとされている。「円筒埴輪」が出土している古墳については、古墳名のそばに、「I期」~「V期」のどの期の「円筒埴輪」が出土しているのかが、ローマ数字で記されている。「V期」の「円筒埴輪」の出土した古墳は、右上のほうにくる。「I期」「Ⅱ期」の円筒埴輪の出土した古墳は、左下にくる傾向がある。すなわち、「古墳の形態」と「円筒埴輪の形式」という二つの別規準にもとづく古墳の築造年代推定編年が、ほとんど正確に合致している。その古墳がいつ築造されたかについての、円筒埴輪などにもとづく考古学的な推定年代と、天皇の一代平均在位年数約十年説による天皇の活躍時期についての統計的推定年代とが、大略合致している。このことは、その古墳に、伝承によって伝えられる被葬者が葬られている可能性を高めるものであろう。また、考古学的な年代推定の結果と、文献にもとづく統計的年代推定の結果との信憑性を、相互に高めるものであろう。
全体的に大きくみれば、上に示した二つの図の示す古墳の傾向は、前方後円墳の新旧の示す傾向と、かなりよく一致している。前方後円墳の築造時期を推定するのに役立つ。
しかし、このような方法によるばあい、こまかくみれば、箸墓古墳のように、前方部が、三味線の撥(ばち)形にひろがっている古墳は、真の年代よりも、やや新しめに推定される傾向があり、逆に、あとでとりあげる桜井茶臼山古墳のように柄鏡(えかがみ)型で、前方部があまり広かっていない古墳は、真の年代よりも、やや古めに推定される傾向があるようにもみえる。
上に示した二つの図の下の図では、同じ四世紀型古墳でも、箸墓古墳のほうが、崇神天皇陵古墳よりも、前方部が発達しているため、年代がやや新しい古墳のようになっている。
これについては、考古学者の斎藤忠がつぎのように主張していることも、主張の根拠が示されているので留意する必要がある。
「『箸墓』古墳は前方後円墳で、その主軸の長さ272メートルという壮大なものである。しかし、その立地は、丘陵突端ではなく、平地にある。古墳自体の上からいっても、ニサンザイ古墳(崇神天皇陵古墳)、向山(むかいやま)古墳(景行天皇陵古墳)よりも時期的に下降する。」
「この古墳(箸墓古墳)は、編年的にみると、崇神天皇陵とみとめてよいニサンザイ古墳よりもややおくれて築造されたものとしか考えられない。おそらく、崇神天皇陵の築造のあとに営まれ、しかも、平地に壮大な墳丘を築きあげたことにおいて、大工事として人々の目をそばだてたものであろう。」(以上、「崇神天皇に関する考古学上の一試論」「古代学」13巻1号)
そして、斎藤忠は、崇神天皇陵古墳の築造の時期を、「ほぼ四世紀の中ごろ、あるいはこれよりやや下降する」と推定している。したがって、箸墓古墳の築造の時期は、ほぼ四世紀の後半にはいることになる。ここで、斎藤忠が、「丘陵の突端でなく、平地にある」「平地に壮大な墳丘を築きあげたことにおいて」と、箸墓が「平地」に築かれたものであることに触れていることは、留意する必要がある。
大塚初重・小林三郎共編の『古墳辞典』(東京堂出版刊)の「用語解説編」において、つぎのようにのべられている。 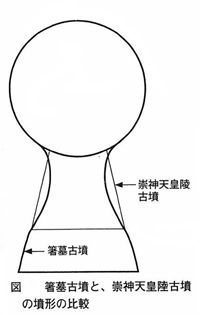
「(前期古墳は、)丘陵尾根上・台地縁辺など低地を見おろすような地形に立地し、前方後円墳・前方後方墳・双方中円墳・円墳・方墳などの種類がみとめられる。墳形をととのえるのに自然地形をよく利用しているのも前期古墳の特色である。」
箸墓古墳は、丘陵尾根上や台地縁辺などに築かれたものではない。平地に築かれたものである。あるいは、崇神天皇陵古墳よりも時代の下るものか。
箸墓古墳の前方部は、崇神天皇陵古墳よりも、あきらかに発達している。右の図のとおりである。
箸墓古墳の後円部の径は、約157メートル。崇神天皇陵古墳の後円部径は、158メートル。1メートルほどの差で、ほとんど変わらない。(測定値は、『前方後円墳集成近畿編』「山川出版社刊」による。)
かりに、崇神天皇陵古墳の築造時期が、箸墓古墳の築造時期よりも古いとすれば、崇神天皇陵古墳は寿陵(じゅりょう)[生前に建てられた陵]で、早めに造られたことなどが考えられよう。
■「三角縁神獣鏡」「画文帯神獣鏡」の埋納された古墳
下の図は、「三角縁神獣鏡」を出土した諸古墳を、プロットしたものである。対比のために、「造出(つくりだ)し」のある前方後円墳をプロットした。
「造出し」は前方後円墳の前方部と後円部の接続部分であるくびれ部に付設された小丘である。祭りをする場であろうと考えられている。
(下図はクリックすると大きくなります)
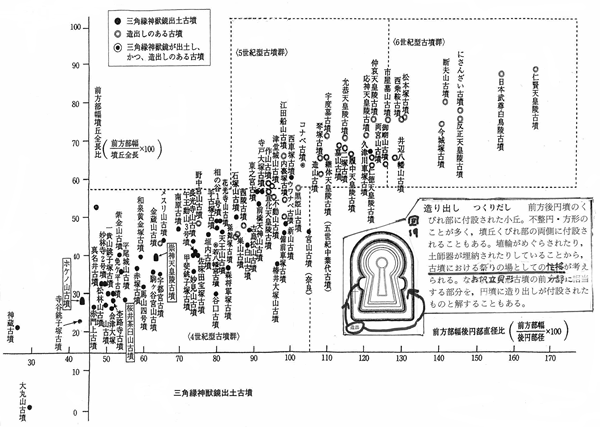
この図をみれば、つぎのようなことがわかる。
(1)「三角縁神獣鏡」は、崇神天皇陵古墳に近い形の前方後円墳から出土していることが多い。崇神天皇陵古墳の築造年代から考えて、「三角縁神獣鏡」は、おもに、四世紀を中心とする諸古墳から出土しているとみられる。
(2)「造出し」のある諸古墳は、「三角縁神獣鏡」の出土する諸古墳よりも、時代的にあとに発生しているようにみえる。「造出し」のある諸古墳は、おもに、五世紀、六世紀ごろに築造されたもののようにみえる。
つぎに下の図をご覧いただきたい。
この図は、「画文帯神獣鏡」を出土した諸古墳をプロットしたものである。
この図をみれば、つぎのようなことがわかる。
(1)「画文帯神獣鏡」も、おもに、崇神天皇陵古墳前後の諸古墳から出土しているようである。「三角縁神獣鏡」と、それほど変わらない時代の諸古墳から出土している。じじつ、この図にみられように、「画文帯神獣鏡」と「三角縁神獣鏡」とがともに出土している古墳も多い。
(下図はクリックすると大きくなります)
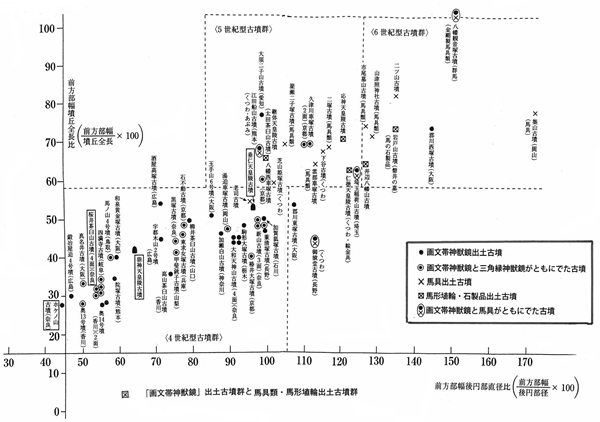
ホケノ山古墳からも「画文帯神獣鏡」が出土している。ここからも、ホケノ山古墳の築造年代が、四世紀であることが疑われる。
そのように考えられる理由として、つぎのようなこともあげられる。
下の図に示す県別分布では、「画文帯神獣鏡」も「三角縁神獣鏡」も、奈良県を中心に分布する。これは、庄内様式期の出土鏡が、全体的にみて福岡県を中心に分布するのとは、パターンが異なる。「画文帯神獣鏡」の県別出土パターンは、四世紀の布留式土器時代のパターンとみられる。このような県別分布パターンによって、鏡の行なわれた主要な年代を、あるていど判断することができるようにみえる。
(下図はクリックすると大きくなります)
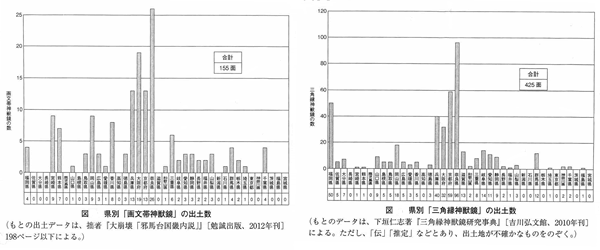
崇神天皇陵古墳時代前後の前方後円墳の主要な特徴として、つぎのようなものがあげられる。
①竪穴式石室の盛行
②碧玉製品の盛行
その状況は、下の図のとおりである。
この時代は、四世紀を中心とする時代で、おもに布留式土器の行なわれた時代とみられる。
(下図はクリックすると大きくなります)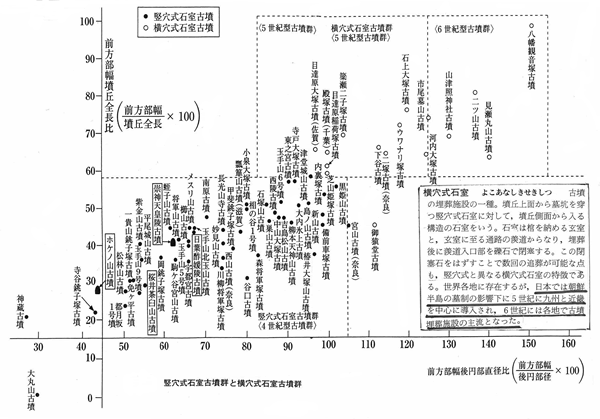
(下図はクリックすると大きくなります)
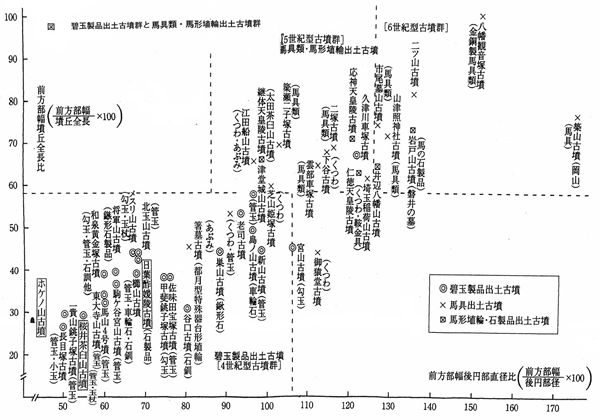
このことからも崇神天皇の時代は倭の五王より前の時代であり、崇神天皇の時代に築造されたと考えられる箸墓古墳が卑弥呼の墓であるとは考えられない。
■統計的に諷査すると、古代の天皇の一代平均在位年数は、約十年となる。これをもとに、「天皇の系譜」により、古代の天皇・豪族らの活躍時期の大略を推定できる。
また、巨大前方後円墳の築造時期は、その古墳の形態・副葬品、出土した埴輪や土器の形式などから推定できる。
このことからも倭の五王推定の有力な根拠が導き出せる。







