■前方後円墳は非常に大きなものがあり、小さいものもある。この大きい小さいはいったい何を意味するのか、ここにかなり重要な意味があるように思える。そのことについて述べる。
『季刊邪馬台国』の77号(2002年刊)に「前方後円墳」のデータベース(情報をあつめたもの)がのっている。
いま、そのデータベースなどを参考に、墳丘全長が200メートル以上の前方後円墳を示せば、下の表1のようになる。

表1をみて気がつくことは、巨大前方後円墳には、天皇陵、または、皇后陵とされているものが多いことである。
とくに、墳丘長の大きいものから上位20番目までをとれば、およそ半分が、天皇陵または皇后陵とされている古墳である。
いま、表1をもとに、ある天皇と、その天皇の皇后とが、ペアになるような形で、墳丘全長を示せば、下の表2のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)

陵墓の比定は、基本的に『陵墓要覧』にもとづいた。
『陵墓要覧』は、宮内省(宮内庁)の職員の勤務用の便覧書(べんらんしょ)で、陵墓台帳のようなものである。大正4年(1915)初版発行依頼、平成24年(2012)版まで、五回の改訂版がでている。『季刊邪馬台国』の47号(1991年刊)に、大正4年版の『陵墓要覧』が転載されている。
表2をみれば、天皇陵は皇后陵もひとまわり程度大きい。しかし唯一、「仲哀天皇と神功皇后」のペアだけが、夫である仲哀天皇の古墳よりも妻である神功皇后のほうが、墳丘全長が大きい。
■神功皇后陵古墳の異状
さきに述べたことは、また、以下のようなこととも関係がありそうである。
まず、『日本書紀』では、原則的に、ほぼ一人の天皇には、一つの巻をあてている。(一つの巻に、二人または三人の天皇を当てているばあいもある。)
ところが、神功皇后のばあいだけは、例外的に、神功皇后一人のために、天皇なみに一つの巻を当てている。「神代」の巻をのぞく「天皇紀」において、天皇以外の人に一つの巻をあてている唯一の例である。天皇なみのあつかいである。
しかも、「神功皇后」の巻に、夫である仲哀天皇よりも、多くの紙数をあてている。
たとえば、岩波書店刊の「日本古典文学大系」本の『日本書紀』でみたばあい、つぎのようになっている。
○『日本書紀』巻第八の「仲哀天皇」の巻にあてられているページ数------10ページ
○『日本書紀』巻第九の「神功皇后」の巻にあてられているページ数------32ページ
じつに、妻である神功皇后のほうに、夫である仲哀天皇の三倍以上のページ数が割(さ)かれているのである。
さらに、古文献は、しばしば、神功皇后を「天皇」と記している。
『常陸国風土記(ひたちのくにふどき)』は、神功皇后のことを「息長帯比売(おきながたらしひめ)の天皇(すめらみこと)」と記す。『摂津国風土記(つのくにふどき)』の二つの別の土地のことを記した逸聞も、「息長足比売(おきながたらしひめ)の天皇(すめらみこと)」「息長帯比売(おきながたらしひめ)の天皇(すめらみこと)」と記す。
平安時代末期成立の歴史書『扶桑略記(ふそうりゃくき)』は神功皇后を、第15代天皇とし、「神功皇后」「女帝これより始まる」と記す。
また、1345年成立の中国の歴史書『宋史』の「日本国伝」に、「神功天皇(じんぐうてんのう)」「息長足姫天皇(おきながたらしひめてんのう)」とある。
そして、神功皇后陵古墳築造のあとのころから、前方後円墳は、それまでの竪穴式石室の時代から横穴式室の時代に変わる。
横穴式石室は、朝鮮半島からもたらされたものとされている。
そして、そのころの古墳から、馬具や、馬形埴輪、馬形石製品が、多数出土するようになる。騎馬文化が本格的に渡来してきたようにみえる。
このことは、神功皇后の朝鮮半島進出伝承と呼応しているようにもみえる。
しかし、神功皇后は開化天皇の五世の孫とされている。
仲哀天皇の妃(みめ)の大中津比売(おおなかつひめ)は、景行天皇の孫とされる。
当時は、天皇家の血の濃さが、尊重される時代であった。神功皇后は妃(みめ)の大中津比売よりも、天皇家の血はうすい。夫の仲哀天皇は、日本武(やまとたける)の尊(みこと)の子である。なにもかも、異例である。
神功皇后の話などは、おとぎ話のようなつくり話とする津田左右吉氏らの説がある。
しかし、皇室の威厳が海外にまでもとどろくという話を作るのであれば、天皇親征、または、皇族将軍派遣のような話を作りそうなものである。
なんのために、女性である皇后が、朝鮮半島へ渡るという異常というか、特異な話を作る必要があったのであろうか
■墳丘全長の大きさは何を意味するか
墳丘全長の大きさが、何を意味しているのであろうか。それを以下に考えてみよう。
第10代崇神天皇の時代に、四道(四つの地域)に、皇族将軍を派遣している。また第12代景行天皇の時代に、皇子の日本武(やまとたける)の尊(みこと)を九州や東国に派遣している。これも皇族将軍といえる。
これらの皇族将軍の墓ではないかとされているものについて、墳丘全長をまとめると、下の表3のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)

比定にたしかな反証のあげられるものを除くと、墳丘全長の平均値は105メートルほどとなる。
この値は、表2の皇后陵古墳の平均値の半分以下である。
また、「国造(くにのみやつこ)」といわれるものがいる。ほぼ現在の郡ぐらいの大きさの地域の領主(地方官)である。朝廷(天皇)によって任命されるが、世襲制である。一度任命されると、代々その一族(氏族)から、次の国造を出した。
「県主(あがたぬし)」といわれるものもいる。「国造」と「県主」とは、ほぼ同じような役目をはたす。「国造」と「県主」との違いについては、いろいろな議論があるが、「県主」の方がやや早く(古く)発生したようである。
「国造」と「県主」の墳墓とみられるものについて、墳丘全長を調べると、下の表4のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)

世襲制なので、代々の国造の墳墓とみられるものが、一つの地域に、いくつも存在することがある。そのばあいは、墳丘全長の大きいものから三つまでをとった。
皇族将軍たちの墳墓の大きさと、国造・県主たちの墳墓の大きさとは、それほど変わらない。
これにくらべれば、皇后陵古墳はいずれも200メートル以上、平均250メートルほどで、ずっと大きい。
ところで、皇族将軍たちの墳墓や、国造・県主らの墳墓よりも、ずっと大きな墳墓をもつようなグループが、別に存在する。
それは天皇の后妃などの出身地の、巨大前方後円墳が存在するという傾向である。
下の表5をご覧いただきたい。
(下図はクリックすると大きくなります)

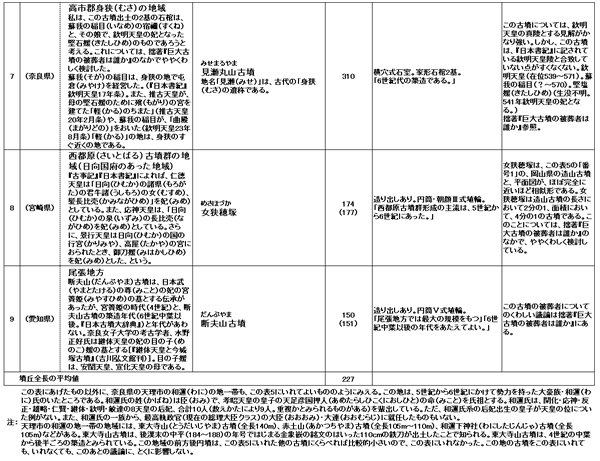
表5のたとえば、番号1、2、3の吉備地方(岡山県)は、四道将軍の大吉備津日子(おおきびつひこ)の命(みこと)や若建吉備津彦(わかたけきびつひこ)の命(みこと)の墳墓は表3にみられるように、100メートルをややこえるていどなのに、この地域から応神天皇や仁徳天皇の妃(みめ)が輩出するような時代(おもに五世紀ごろ)になると、この地に300メートルをこえる大前方後円墳が築かれるようになっているようにみえる。
『古事記』や『日本書紀』によれば、仁徳天皇や応神天皇が、国に帰った妃(みめ)の黒日売(くろひめ)や兄媛(えひめ)にあうために、吉備の国まで出かけている。
天皇の后妃を出した地域に、大きな古墳が作られた理由として、つぎのようなケースが考えられる。
(1)天皇の后妃を出すことは、その土地の人にとって、名誉なことであった。
后妃がなくなったばあい、あるいは、その女性が老いるなどして国に帰ったばあい、名誉をたたえ、それを目に見える形として残すため、その女性のために墳墓を作ったばあい。
(2)天皇と后妃とのあいだに生まれた皇子が、その女性の出身地の長となり、為政者となり、その皇子のために墳墓が作られたばあい。これは古代においてよくみられる「両家相続」と、基本的な構造は同じである。ただ、ふつうの「両家相続」では、貴種である皇子などが、地方に出むき、その地方の女性と結婚しているのに対し、ここでは、地方の女性を、天皇のいる中央である都に召しているところが、すこし異なる。いずれにせよ、貴種である人物と地方の女性とが結ばれ、その間に生まれた子が、その地方の長となるのである。
---------------------------------------------------------------------------------
・ノート
両系相続パターン---女性中継(なかつ)ぎによる支配権の継承、貴種への帰属パターン
身分の高い、ある貴種の人(皇子など)が、出身地以外の土地にはいる。そして、その土地の豪族・主権者の娘と結婚する。そのあいだに生まれた男子が、やがて、その土地と人民の主権者になる。
このパターンを通じて、その土地の勢力は、貴種がわの勢力に、くみいれられていく。
貴種の一族は、支配権のおよぶ範囲をひろげていく。
古代においては、神話時代以来、このパターンが、じつにしばしばみえる。
たとえば、次のようなものである。
(1)『古事記』によるとき、九州出身らしい伊邪那岐(いざなぎ)の命(みこと)が、出雲出身らしい伊邪那美(いざなみ)の命(みこと)と結婚する。[古代の女性は、しばしば出身地に墓がつくられる。伊邪那美の命は、出雲(いずも)の国と伯岐(ほうき)の国とのさかいの比婆の山にほうむられている。]
そして、伊邪那岐の命と伊邪那美の命とのあいだに生まれた須佐の男(すさのお)の命(みこと)は、出雲方面の主権者となっている。
(2)大国主の神は、須佐の男の命の娘の須勢理毘売(すせりびめ)と結ばれる。そして、須佐の男の命の政治的支配権のシンボルである大刀(たち)と弓矢と琴とをうばって、二人でかけおちをする。このようにして、大国主の神は、出雲の国の主権者となる。
大国主の神は、多くの地の女性と結ばれることによって、支配権をひろげていったとみられる節(ふし)がある。
(3)天皇家も、しばしばこの方法をとって支配権をひろげていった。
第9代開化天皇の皇子の日子坐(ひこいます)の王(おおきみ)は、天(あま)の御影(みかげ)の神の娘の息長(おきなが)の水依比売(みずよりひめ)と結婚する。そのあいだに生まれた水穂(みずほ)の真若(まわか)の王(おおきみ)が、近(ちか)つ淡海(おうみ)の安の国造の祖となっている。
なお、大正~昭和時代の女性史研究家の高群逸枝(たかむれいつえ)は、『母系制の研究』(全集第1巻、理論社、1966年刊など)をあらわした。高群逸枝は、一対の夫婦のあいだに生まれた子どもは、父方親族の一員であるとともに、母方親族の一員である資格をもっていたとのべる。この考え方によれば、ある人物や氏族の「祖先」は、ある特定の男性に収斂(しゅうれん)するのではなく、父系と母系の複数の祖先に拡散していくことになる。高群逸枝は、多くの事例をあげて論じている。
たとえば、『新撰姓氏録(しんせんしょうじろく)』の「山城国神別(やましろのくにしんべつ)」に、次のような記事がある。
「秦忌寸(はたのいみき)は、神饒速日(かむにぎはやひ)の命(みこと)の後裔である。」
秦忌寸は、秦の始皇帝の子孫で、本来、渡来系の氏族とされている。その渡来系の氏族が、饒速日の命の子孫で、「神別」氏族(神々の子孫と称した氏族)とされているのは、一見矛盾である。
これは、父系相続のみを考えるから、奇異な印象を与えるのである。
たとえば、神饒速日の命の子孫の男性が、秦忌寸出身の女性と結ばれ、(当時は、一般に男性の通い婚であった)その子が、その女性のもとで育てられ、秦忌寸氏の土地、人民の支配権をうけついだような種類の、両系相続があったとすれば、説明がつく。饒速日の命の子孫でありながら、渡来系の氏族の長であるということがおきるのである。
『新撰姓氏録』をみれば、このような事例は、かなりあげることができる。
ふつう私たちは、ある祖先からはじまって、子孫の数がふえて行く図式を考える。
しかし、父系、母系の両方を考える両系相続では、むしろ、さかのぼるにつれて、先祖の数がふえて行く図式が考えられる。
小説家の陳舜臣の『中国の歴史』(平凡社刊)に、次のような文章がある。
「春秋時代もけっこう戦争は多かったのですが、完全亡国はあんがいすくなかったようです。完全に国をほろぼすと、祭祀をうけない祖神が祟るとおそれられました。だから、周は殷(いん)をほろぼしても、殷の後裔(こうえい)を宋(そう)に封じて、祭祀をつづけさせたのです。春秋時代、虢(かく)という国が晋にほろぼされましたが、これも完全亡国ではなく、小虢と呼ばれる小国が存在を許されています。」
『古事記』『日本書紀』によれば、崇神天皇の一時代に、流行病がはやり、大国主の神の子孫の意富多多泥古(おおたたねこ)をさがしだして祖神を祭らせたという話がみえる。
これは、周が殷をほろぼしても、殷王朝の子孫に、祖神を祭らせたのと同じような考え方によるのであろう。
かつての大和の国の地もふくめた土地の支配者、大国主の神のたたりをおそれたものであろう。
「両系相続」(「双系相続」ともいう)を通じて、その貴種の系統が、勢力をひろげていくのである。
奈良時代に成立した文献には、「言向(ことむ)け和(やは)す」という語が、しばしばでてくる。
「言向け和す」は、「征服する」「服従帰属させる」「平定する」という意味であるが、もともとは、「言葉で説得して従わせる」「言葉で静め和(やわ)らげる」という意味である。
この「言向け和す」ための手段として、古代では、「両系相続」による婚姻政略が、よく用いられる。「征服する」ばあいに、相手を絶滅させる方法をとらないことが多いのである。
---------------------------------------------------------------------------------
また、「著名な皇子・皇女の墓」「臣(おみ)・君(きみ)以上の姓(かばね)をもつ人の墓」というような分類項目をつくり、墳墓の大きさを示せば、下の表6、表7のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)
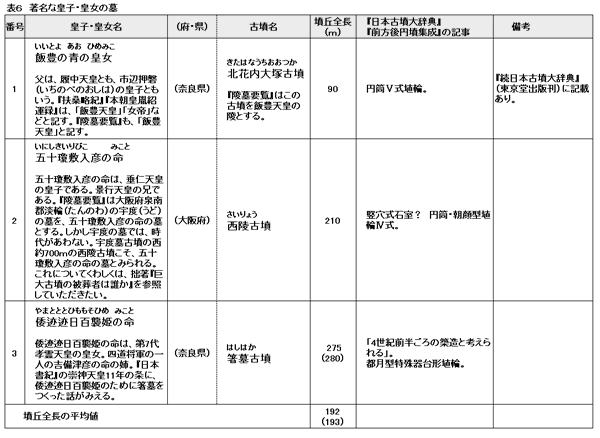
(下図はクリックすると大きくなります)
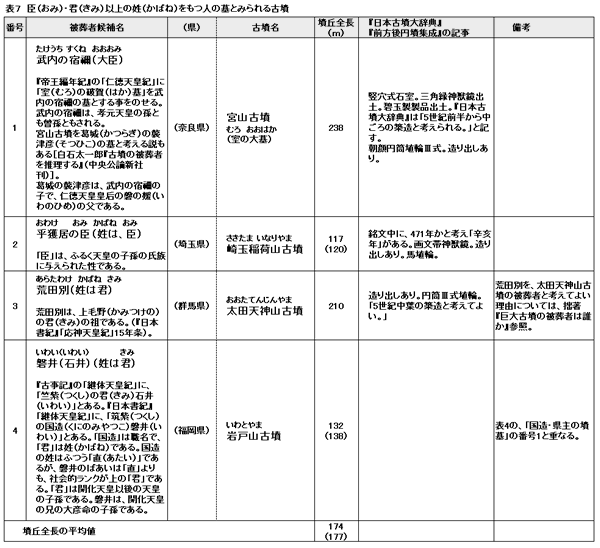
■墳丘全長からみた前方後円墳
以上の表2~表7の、墳丘全長の平均値などを一つの表にまとめれば、下の表8のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)
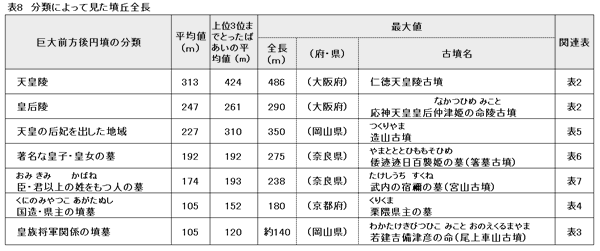
表8をみれば、さまざまなことに気がつく。
つぎのようなことである。
(1)「天皇陵」は、圧倒的に大きい。
平均値でみたばあい、「天皇陵」は、「国造(くにのみやつこ)」などの墓のおよそ三倍である。長さで三倍ということは、面積で九倍、体積で27倍ほどということである。
(2)「皇后陵」や「后妃」関係の墳墓が大きい。
「国造」などの墓の二倍以上である。長さで二倍ということは、面積で四倍、体積で16倍は十分あるということである。
(3)皇族将軍関係の墳墓は意外に小さい。前方後円墳時代のはじめのころ(四世紀代とみられる)の墓なので小さいとも考えられるが、それにしても、ほぼ同時代のはずの崇神天皇陵古墳(242メートル)、垂仁天皇陵古墳(227メートル)、景行天皇陵古墳(300メートル)の半分以下である。垂仁天皇皇后の日葉酢媛(ひばすひめ)の命(みこと)の陵墓古墳(206メートル)のおよそ半分である。
皇族将軍たちは、その奮闘努力のわりには、墳墓の大きさでは、めぐまれていないようにみえる。ただ、皇族将軍の次世代以後になると、吉備や丹波からは、后妃を出し、皇族将軍のおさめた地域に、巨大な古墳が作られるようになる。
日本武(やまとたける)の尊(みこと)のばあいも、その能褒野(のぼの)の墓の墳丘全長は、90メートルであるが、その子は、仲哀天皇で、仲哀天皇陵古墳の墳丘全長は242メートルである。能褒野の墓の二倍以上である。
以上から、つぎのようなことがいえそうである。
---------------------------------------------------------------------------------
古墳の大きさが、その被葬者の社会的地位を示すとすれば、圧倒的に社会的地位の高いのは、天皇である。ついで高いのは、后妃など、その天皇をめぐる女性である(「皇后」と「妃」に、明確な差があったのか?)。ついで、著名な皇子・皇女などが位置し、その下に、臣(おみ)・君(きみ)などの姓(かばね)をもつ氏族が位置し、さらに、多くは値(あたえ)の姓をもつ国造(くにのみやつこ)などが位置する。皇族将軍は、業績をあげた段階では、なお国造とならぶていどの位置である。
要するに、天皇を太い大きな柱とし、他は、そのまわりに位置している。
もう一度、表8をよく見ていただきたい。
---------------------------------------------------------------------------------
■血統と正義
ここで、「正義」という概念について考えてみよう。
「正義」の概念は、時代によって異なる。
古代を知るためには、古代人の考え方を知った上で古代を見る必要もある。
今日、私たちは、理性や道義にしたがうことを、正義と考える。あるいは、「最大多数の最大幸福」をめざすことを、正義と考える。社会主義であろうと、資本主義であろうと、社会の成員の、法的な、さらには、実質的な平等をめざすことこそ、正義であるとする考え方が根底にある。
しかし、古代においては、けっしてそうではなかった。
古代においては、伝統のある家系のものが上に立つのが正しく、人々は、その家系の人にしたがうのが「正義」であるとする考え方があった。
劉備玄徳(りゅうびげんとく)は「義兵」をあげた。それは、劉備玄徳は、漢の劉邦(りゅうほう)の血をひいており、帝王になるのが、「正しい」と考えたからであった。
後漢の光武帝が帝王となったのも、劉邦の血をひく人物が帝王になるのが「正しい」と、みずからも考え、人々もそう考えたからであった。
秦の始皇帝の没後、兵をあげた項羽(こうう)や劉邦が、はじめ、楚の懐王を擁立したのは、伝統のある家系の人を上にたてなくては、「正義」の名目がえられず、人心を収攬(しゅうらん)できないからであった。
「平等」こそが、古今東西を通じての「正義」であると考え、その立場から歴史をみれば、天皇制も国王制も、否定すべきものとなってしまう。天皇制こそは、わが国において、平等の実現を阻害してきた最大の要因である、ということになる。そして、歴史というものは、古代史であれ、現代史であれ、いかに人々が平等をめざして戦ってきたかという「人民の歴史」の立場から考察すべきだ、ということになる。
「人民の歴史」を強調する立場は、第二次大戦後、大きく燃えあがり、マルクス主義などによってささえられ、とくに学界を席巻した。
しかし、「人民の歴史」をとくに強調する立場にたてば、天皇制の源である大和朝廷も、本来、価値的に否定すべきものとして見ることとなる。そして、古代において大和朝廷が果たした一定の積極的役割を、評価しにくくなる。
私は、九州にあった邪馬台国が発展し、東遷して大和朝廷をたてたと考える。
邪馬台国は、中国の王朝によって権威づけられていた。
その王家の血をひくことは、古代において、もっとも権威あるものであった。
「人民の歴史」を強調することによって、はじめて見えてくるものはあるであろう。しかし、その立場のみが、唯一の正しい立場であると考えてはならない。その立場のみにたてば、見えなくなるものもある。
ここで、「ヒト」の生物学的な側面から、「血統」というものについて考えておこう日本ザルの集団には、ボスがいて、群を統括するという。
人間も、生物学的には、サルの仲間であって、その群においては、エラサの順をきめて、群としての秩序をたもとうとする傾向がある。
会社などでも、エラサの順をきめ、判断を下し、命令をする人と、命令をうけて実行する人とをきめておいて、会社の秩序をたもつ。
群として、まとまった仕事をするときに、このようなやり方で組織をつくるのは、おそらく、種としての人間の、生物学的な本性にもとづくところがあるのであろう。
では、人間は、どのような原理で、エラサの順をきめるのだろう。
「年功序列」は、経験と能力とにもとづいて、エラサの順をきめる方法といえるであろう。
「選挙」は、人気といった人格的な要素と、能力とによって、エラサをきめる方法といえよう。この方法は、現代になってさかんにとりいれられるようになってきた。
現代では、一般に、能力、経験、学歴などによって、エラサの順をきめる傾向が、かなり強くなっている。
しかし、かつては、どこの国でも、エラサをきめるのに、「出自」が大きくものをいった。
現代でも、社長の息子が、あっという間に出世して、社長のあとをつぐということは、よくあることである。
江尸時代の「士・農・工・商」という階級概念は、「出自」によって、エラサをきめたものである。インドの、カースト制度の「バラモン(僧侶)、クシャトリヤ(王族・武士)、ヴァイシャ(平民)、シュドラ(奴隷)」も、「出目」にもとづくものであった。
江戸時代において、将軍は、徳川家に生まれたがゆえに、もっとも大きな権力の座についた。能力、経験、人気などは、将軍となるための、第一要件ではなかった。
「徳川家に生まれたがゆえにエライ」という、エラサのきめ方には、モデルがあった。
それは、「天皇家に生まれたがゆえにエライ」、エラサを通りこして、「尊い」とする古代から存在した判断基準にもとづくきめ方である。
古代においては、天皇は、もっともエラかったのである。尊かったのである。そして、天皇と、血が近いほどエラかったのである。
今日、古代においては、天皇家も、他の氏族と同じていどの権力しかもっていなかったとする議論が、さかんである。しかし、私は、そのような議論は、古代における天皇の権威を、実質以上に低くみようとする一定の意図にもとづくものであると思う。
天皇家の権威は、大和朝廷の成立の当初から、他の氏族にくらべ、卓越していたとみられる根拠は、多々ある(私は「大和王権」という、最近はやりのことばを、あえて使わない。「大和王権」ということばは、「大和朝廷」の王権をさすばあいと、大和朝廷発生以前の大和に存在したとみられる「王権」をさすばあいと、明確に定義わけしないままで使われている場合が、しばしばであるからである。また、当時の王権が、本来「血の原理」にもとづくものであることを、強くは意識させない表現であるように思える)。
『古事記』『日本書紀』を読めば、天皇の「妻(みめ)」などでも、天皇家の血が濃い女性は、「出自」がよいとみなされて「皇后」になりやすく、天皇家から血のはなれた女性は「身分が卑しい」とみなされる傾向があったことは、あきらかである。
そのような事情は、平安時代においても、同じことであった。
『源氏物語』巻頭の「いとやむごとなき際(きは)にはあらぬが、……」は、光源氏の母親であった妃は、「高い身分のものではなかったが、……」ということをいっているのであり、「出自」のことをのべているのである。帝の寵愛だけで、「身分」を高くすることはできなかったのである。
『古事記』の序文において、天武天皇が、「帝紀(皇統譜のような記録)や本辞(神話・伝説など)」を、「邦家の経緯(国家行政の根本組織)・王化の鴻基(こうき)(天皇徳化の基本)」とのべている。
天皇を頂点とするヒエラルキーによって、エラサの順をきめ、社会の秩序をたもっているわけであるから、その「帝紀や本辞」が「正実に違(たが)ひ、多く虚偽を加ふ」ようになってしまっては、社会の秩序がたもてず、国家行政の根本組織が、おかしくなってしまうのである。
「血統」の原理が理解できないと、なぜ、「帝紀」が、国家行政の根本原理になるのか、わからなくなってしまう。
『日本書紀』の、第十九代允恭(いんぎょう)天皇の四年の条に、天皇が、つぎのように詔(みことのり)をくだす話がある。
「あるいは天皇の子孫、あるいは天降ったものの後裔である、と主張するものがいる。姓名(かばねな)が誤っていては、国を治めることはできない。私は、誤りを正そうと思う。もろもろの氏姓(うじかばね)の人たちは、斉戒沐浴(さいかいもくよく)して(心身をきよめて)盟神探湯(くかたち)せよ。」
「盟神探湯」は、神に祈り誓ったうえで、手を熱湯にいれるとき、正しい主張をしているものは手がただれず、いつわっているものは手がただれる、という当時信じられていた原理にもとづく正邪弁別法である。姓名(かばねな)をいつわっているものは、おじけしりぞいて、あらかじめ進むごとがなかったという。
「血統」をあきらかにし、社会の秩序をたもつために、そこまで行なう必要があったのである。
今日、会社では、辞令をだして、エラサの順をあきらかにするが、古代では、血統を明確にして、エラサの順をきめたのである。
私は、つぎのように考える。
大和朝廷、つまり、天皇家は、当初から、他の豪族に対して、ほとんど圧倒的に近い政治的権力をもっていた。
その力の源泉は、おもに、二つあった。
ひとつは、「血統」にもとづく伝統からくる力である。
中国の魏によって承認され、権威づけられた邪馬台国の後継勢力であり、宗教的、政治的な伝統をもつものが、古代から血の原理でつながっているということからくる力である。貴種がもつ権威からくる力である。
大和朝廷のもつ力の、いまひとつの源泉は、その政治システムである。
『魏志倭人伝』に、倭人は「租賦を収む」と記されている。「租税をとる」というアイデアは、中国からきたものであろう。「租税をとる」ことによって、「国家」は、はじめて、部族国家の域を脱する。強力な「国家」といえるものとなる。「租税」によって、戦争にとくに適した屈強の若者たちを、「兵士」としてやというる。それらの「兵士」は、戦争だけに専念することができる。組織的な訓練をうけることとなる。「租税」によって、最新鋭の武器を購入することができる。最新鋭の武器をもち、組織的な訓練をうけた兵士によって、王朝を守らせることができる。支配地域を拡大させうる。
武力によって、支配地域の人民から、「租税」を収奪することができる。
また、一方、治水や灌漑などの土木工事をより大規模に行なうことができる。外国の新技術も導入し、農業生産力をあげることができる。
国立歴史民俗博物館の春成秀爾(はるなりひでじ)氏は、弥生時代の村という村には、ほとんど環濠が掘られ、土塁がめぐらされていたであろう、と推定している。
私も、邪馬台国時代ごろから、環濠や土塁がなくなりはじめるが、それまでは、おのおのの村に、環濠や土塁がめぐらされていたであろうと考える。
京都府峰山(みねやま)町扇谷(おうぎだに)遺跡は、紀元前二世紀~三世紀ごろのものである。この遺跡では、環濠が二重にめぐらされていた。そこの土は、かこう岩の風化した岩のようなものであった。発掘調査で掘り起こすときも、2~3人がかりで、1日に1メートルしか掘れなかったという。
削岩機も、ツルハシももたずに、弥生人たちは、深さ4メートル、最大幅6メートル、のベ1キロメートルの環濠を掘っていた。
敵に襲われるのをふせぐためであったとみられる。
「租税」により、国家の武力が大きくなれば、環濠や土塁は、不要となる。
「租税」制度をもつ国家は、人々の生活を安定させ、より豊かにする。人口の自然増も大きくなる。支配地域そのものもひろげうる。
「租税」収入をより大きくし、武力を、すなわち、国家権力を、さらに大きくすることができる。
このようにして、国家権力の拡大再生産が可能となる。
アイヌは、最後まで、部族国家の域を脱しなかった。組織的な徴税システムをもたなかった。このような部族国家では、鮭(さけ)が川にのぼってくれば、戦争を放棄して、魚をとらなければならない。兵士は、日ごろは、生産に従事しており、戦争のプロではない。戦争のための組織的な訓練を、十分にうけているわけではない。
徴税システムをもつ「国家」と「部族国家」とが戦ったばあい、長い目でみると、「部族国家」に勝ち目はない。
大和朝廷は、徴税を行なうという、新機軸の国家システムによって、比較的短い期間で、日本列島を席巻していったとみられる。
『魏志倭人伝』は記している。
「其の(倭人)の俗、国の大人(たいじん)[身分の高い人]は、皆四、五(人)の婦(よめ)あり。下戸(げこ)(しもじもの家)は、あるいは、二、三(人)の婦あり。」三世紀倭人の伝統を引くのであろう。『古事記』『日本書紀』によれば、天皇は、多くの妻(みめ)をもっている。そして、『古事記』『日本書紀』によれば、天皇家の子弟は、各地に派遣されている。
皇子たちは、中央からの武力をともなって各地におもむき、その地に権威者としてのぞみ、その地で徴税システムをつくり、大和朝廷のさらなる発展に寄与することとなるのである。
中国の漢および後漢では、王子が、しばしば、各地の王に封じられている。大和朝廷がとった方法も、それに近い。
そして、各地におもむいた皇子たちは、各地で組織された兵をひきいて、中央の政府にも参画し、新たな征服戦にものぞむのである。
徴税システムという新文化をうけいれたのは、九州のほうが、畿内よりも早かったはずである。朝鮮半島や中国に近く、また、南方原産の稲がはいったのも、九州のほうが早かったとみられるからである。
そして、徴税システムをさきにうけいれたがわのほうが、国を統一して行く権力になりやすかったはずである。
邪馬台国の後継勢力による国土統一戦争は、古代において長期間つづいた一大革命戦争であった。
「血統」の正しい支配者を上にいただいているという、「正義はわれにあり」とする理念と、新しい組織的国家をつくろうとする意欲と、徴税システムという新文化と、さらに武力とによって、国土を席巻して行く運動であった。
すべての戦争には、大義名分が必要である。第二次大戦では、日本も、ドイツも、イタリアも、「正義」をかかげて戦った。湾岸戦争のさい、イラクのフセインも、みずからの「正義」を主張した。
大義名分は、世論を味方にし、協力者を得やすくさせ、部下たちの士気を鼓舞する。
大義名分のない戦いは、孤立をまねき、部下たちを戦いにくくする。戦争では、他を殺し、自分も死ぬ可能性がある。「正義」という酒に酔っていなければ、なかなかできないところがある。
いかなる組織(集団)であれ、自分の属している組織の存在意義がはっきりしており、また、その組織のなかでの自分の存在意義がはっきりしているとき、成員は、強力な戦力を発揮する。
古代においては、「血統」は、「正義」でありえたのである。
■威信を示す効果
『万葉集』の4260番、4261番の歌に、つぎのような歌がある。
「大君(おおきみ)は神にしませば赤駒(あかごま)の腹這(たらば)う田居(たい)を都(みやこ)となしつ」(大君は、神でいらっしゃるので、赤駒の、腹ばっていた田んぼでも都となさった。)
「大君は 神にしませば 水鳥(みずとり)のすだく水沼(みぬま)を 都となしつ」(大君は、神でいらっしゃるので、水鳥の、集まる沼でも、都となさった。)
立派な都をつくることは、天皇の神のような力を、人々に示すことであった。
中国でも『漢書』の「高帝紀下」に、つぎのような話がのっている。
漢の劉邦(りゅうほう)の時代に、丞相の蕭何(しょうか)が、長安に未央宮(びおうきゅう)を造営した。
劉邦が、長安にはいったとき、未央宮が、あまりに壮麗であるので、蕭何に怒っていった。
「天下がおののき、戦争に苦労すること数年、その帰趨(きすう)もわからないのに、こんな度はずれた宮殿をつくるとは、どうしたことか。」
蕭何が答えていった。
「できるだけ壮麗に造り、威光を示さなければ、天下はしたがわず、平定することはできないのです。」
テレビもマスコミもない時代、権力は視覚化される必要があった。人々の話の種となる材料が、必要であったのである。
天皇陵、皇后陵を中心とする巨大古墳は大和朝廷の圧倒的な力を、天下に誇示するものであった。天皇と一般庶民との力の「格差」は、現在では想像もつかない途方もなく大きいものであった。
その結果、5世紀には、仁徳天皇陵や、応神天皇陵などとてつもない大きな古墳が造られたのである。。







