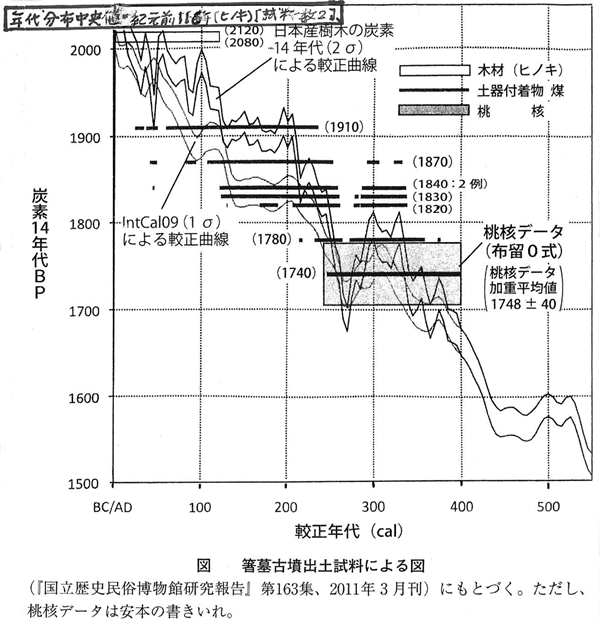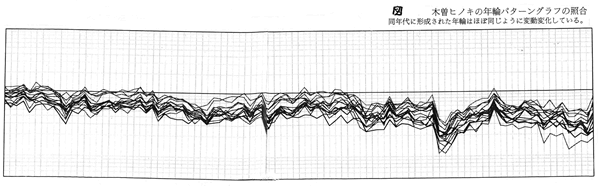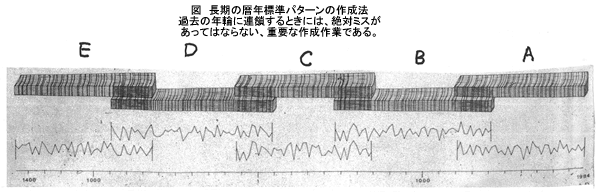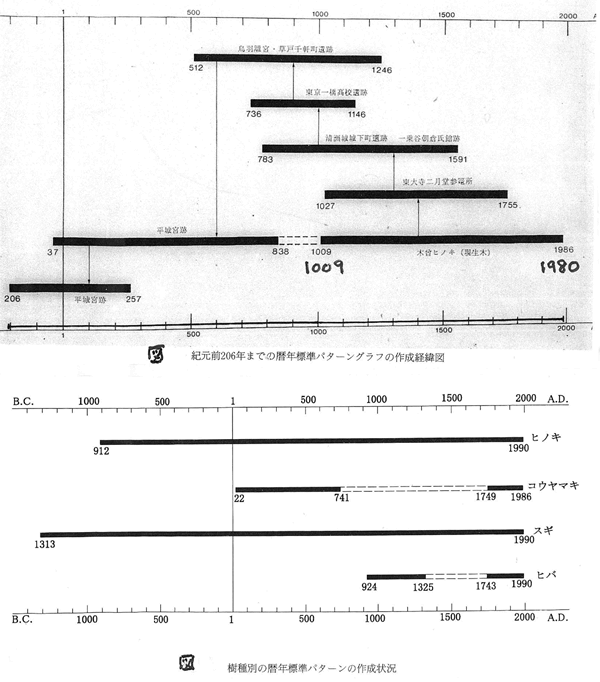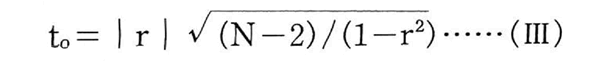■木材の伐採の年は、一般に、建築物などの築造年代ではない
木は、寒い年はすこししか成長せず、あたたかい年は、大きく成長する。年輪年代法は、寒暖から生ずる樹木の年輪のパターンにもとづき、木材の伐採年代を求める方法である。
年輪年代法は、科学的な方法である。木材の伐採された客観年代(絶対年代)を確定できる。その方法じたいは、十分に信頼できる。
しかし、木材を伐採した年代は、建築物などを作った年代と、一般には合致しない。それは、おもに、つぎの二つの理由にもとづく。
(1)建築物をつくるさい、木材は、伐採してすぐ使うものではない。水と油を除くために、長期間寝かせる。
つまり伐採された時期と、建物などが建てられる時期とのあいだには、年代差がある。これについては、宮大工(だいく)で、法隆寺大工の棟梁などをした西岡常一(つねかず)が、『日本経済新聞』連載の、「私の履歴書」のなかでつぎのようにのべているとおりである。
「(法隆寺の五重の塔の修理のさい)鉄材を補強に使った。垂木を鉄のバンドで引っ張るようにはめたのだが、二、三年したら、木を支えるはずのバンドの方がガタガタにゆるんでいた。木は切ったあとに長期間寝かせて、水と油を除くべきなのだが、当時は時間がなく、高周波乾燥という手短(てみじか)な手法をとった。あとで柱にヒビが入った。木の命を縮めて何の科学かと、これに対してはことに強く異議をとなえた。」[1989年11月20日(水)朝刊]
(2)建築物の木材は、数百年、ときに一千年をこえて、利用、再利用されることがある。つまり、木材の伐採された時期と利用された時期とが、数百年以上異なることがある。これについても、西岡常一が、『日本経済新聞』の「私の履歴書」のなかで、つぎのようにのべている。
「(法隆寺の)昭和大修理の当初、金堂や五重塔は、そのかなりの木、いやほとんどを新しくせねばもつまい、というのが大方の予想だった。
結果はまったくちがった。
五重塔のばあい、三割ちょっとのとりかえですんでしまった。それも、軒など直接雨風にさらされた部分がほとんどで、柱などはそのままで十分だった。計測では全体の六五%が減った。予算上はずいぶん助かったのではないか、という話はさておき、金堂にしても焼けていなければ同じことになっていたろう。塔の心柱の上部などは雷の被害の跡もあり、・・・よくぞ今日まで。
の感があった。」[1989年11月21日(火)朝刊]
「(法隆寺の千三百年前のヒノキの柱は、)ひからびて、くたびれている。修理の必要からカンナで削ると、ヒノキ特有の香りが漂ってきた。大工なら分かるが、生の木のにおいだった。」[1989年11月19日(日)朝刊]
「解体修理などではっきりしたことだが、スギなら七百年、八百年、マツなら四、五百年はもつ。しかし千年以上ビクともしないヒノキに勝るものはない。」[1989年11月20日(月)朝刊]
この文中で、「柱などはそのままで十分だった」とあるのに注意。
福田さよ子氏は、『ホケノ山古墳 調査概報』(学生社、2001年刊)のなかで、つぎのようにのべる。
「(ヒノキは、)保存性が高く、強靭で耐朽性・耐湿性に富む。特に心材は腐朽・水湿によく耐える。」
岩手県・平泉の中尊寺の金色堂の例もある。中尊寺の金色堂は、ほとんどヒバ(ヒノキ科の常緑樹高木。別名アスナロ)材で建てられていた。1981年に大修理されたとき、建立されてから八百五十年以上たっていたにもかかわらず、多くの部材は再使用可能であったという。
また、古代には、鉄斧などをはじめ、木材を伐採、加工する道具などは、なお十分に普及発達していなかった。大きな木材は貴重品であった。そのため、一度伐採された木材が、さまざまな形で再利用される。
年輪年代法には、つぎのような問題もある。
それは、九州からは、年輪年代測定を行ないうる樹種(ヒノキ、スギ、コウヤマキ、ヒバなど)の木材の資料が、まず出土しないことである。
九州は、弥生時代以来の遺跡が豊富である。
年輪年代法の結果にのみ強く焦点をあてると、九州には検討すべき遺跡・遺物は存在せず、近畿からは、つぎつぎと邪馬台国時代に伐採した木材が出土しているかのように見えてしまう。
結果的に、偏った判断をしてしまうことになる。
年輪により年代を正確に定める技術は、統計学的に洗練されており、高い水準に達している。得られた結果は、貴重で、信頼できる。しかし、再利用か否かを定める技術は、信頼性をもって発言できる段階になお達していない。
年輪年代法による年代は、その木材の伐採された年を教えてくれる。そして、遺構や建築物の築造時期は、使用された木材が伐採された年よりあとであることを教えてくれる。これはこれで十分貴重な情報である。ただ、あくまで、遺構や建築物の築造時期そのものを教えてくれるものではない。築造時期の上限を教えてくれるものである。そのため、使用木材の伐採年代と築造時期、あるいは再利用の時期とのあいだに、ときに、数百年、ばあいによっては千年をこえる差の生ずることがある。
邪馬台国問題は、あくまで、全体的な情報のなかで考えるべきである。年輪年代法も、全体のなかに適切に位置づけるべきである。
どのような方法であれ、一つの方法にのみ重点をおきすぎると判断を誤る。
揚子江でも、ある一つの地点でのみ観測すれば、東から西に流れているとみえることがある。部屋のなかでのみ考えれば、床は水平にのびており、地球は丸い、などとは思いいたらない。
邪馬台国問題は、全データを総合的に考えなければならない問題である。
■年輪年代法の測定発表例は、畿内に偏(かたよ)っている
『日本の美術6』(No.421)(東京国立博物館・京都国立博物館・奈良国立博物館監修、至文堂、2001年刊)で、光谷拓実(みつたにたくみ)氏の「年輪年代学と文化財」という特集が組まれている。
ここでは、年輪年代法による成果が、総合的にまとめられている。
大変読みごたえのあるよい特集である。
執筆者の光谷拓実氏は、慎重にのべている。
「年輪年代法で暦年が判明したばあい、たとえそれが樹皮型の遺跡出土材であっても、その暦年は原木の伐採年を示すだけであって、出土品の年代や遺跡の年代にならないことがある。それは、原木の伐採後、加工するまでの原木を保管したり、あるいは製品となってから長い間の使用後に廃棄したり、よくある例として古材を再利用したりしていることがあり得るからである。
これらのことを勘案すると、年輪年代まで得られた結果だけで遺跡の年代を決めることは慎重を要する。」
 当然の、そして銘記すべき注意事項である。
当然の、そして銘記すべき注意事項である。
ただ、それでも最初に指摘したいのは、『日本の美術6』にあげられているデータ例には、いちじるしい地域的偏(かたよ)りがあることである。
『日本の美術6』であげられている遺跡などの、地方別、県別例数は、右の表のようになっている。
近畿地方は、十六例とりあげられているのに、九州地方は、一例もとりあげられていない。奈良県の例は八例とりあげられているのに、福岡県の例は、もちろん皆無である。
九州の遺跡からは、木材が出土していないのであろうか。そんなことはない。
九州は、弥生時代以来の遺跡が豊富である。
光谷拓実氏に、お電話でうかがった話では、九州からは、年輪年代法で年代を測定するのにふさわしい樹種の遺物が、出土していないとのことであった。「ぜひ、そのような樹種の遺物を手に入れたいのであるが」、とのことであった。
年輪年代法の結果にのみ強く焦点をあてると、九州には検討すべき遺跡・遺物は存在せず、近畿からは、続々と邪馬台国時代を含む遺跡・遺物が出土しているかのような錯覚を与える。
結果的に、偏った判断をしてしまうことになる。
「年輪年代法」は、たんに、「邪馬台国畿内説」宣伝の具であってはならない。
■年輪年代学は、建築年代の上限を与える
 つぎに、『日本の美術6』にのせられているもので、文献によって、建物などの建築年代がほぼ確定できるものをとりあげ、年輪年代学による伐採年代とを比較してみよう。
つぎに、『日本の美術6』にのせられているもので、文献によって、建物などの建築年代がほぼ確定できるものをとりあげ、年輪年代学による伐採年代とを比較してみよう。
すると、右の表のようになる。
この表をみれば、つぎのようなことがわかる。
(1)塔や禅堂、神楽殿など、総じて、建築物のばあいは、(B)と(A)の年代差が大きい。力士像、円空仏、不動明王など、木像のばあいは、(B)と(A)とがほぼ合致する。これは、かりそめの建物ではなく、本格的な建築物のばあい、ヒビが入ったり、ゆがみをさけるために、使用のまえに、長期間寝かせ、水と油を除くためであろう。
(2)総じて、古代にさかのぼるにつれ、年代差[(B)引くと(A)の値]の大きくなっていることがわかる。これは、古代には、木材を伐採、加工する道具などが十分に普及発達していないため、伐採された木材を、再利用することが多かったことを思わせる。
年輪年代法による成果は貴重である。
この表(「年輪年代法による伐採年代」と「文献による建物などの建築年代」との比較)をみれば、はっきりと法則的に主張できることがある。
それは、つねに、「年輪年代法による伐採年代(A)」は、「文献による建物などの建築年代(B)」よりも小さいことである。
すなわち、
(A)=<(B)
である。
言葉でいえば、つぎのようになる。
「年輪年代法による伐採年代(A)」は、建物などの建築年代の上限を与える。つまり、その建物などの建築年代は、(A)をさかのぼらないことがいえる。」
これは、しばしば重要な情報をもたらす。
しかし、問題は、
(A)=<(B)
であって、
(A)=(B)
ではないことである。
上の表(「年輪年代法による伐採年代」と「文献による建物などの建築年代」との比較)をみれば、
(A)=(B) [(A)は、(B)にほとんど等しい。]
こともあるが、百年以上、時には数百年違っていることもある。
「奈良県国宝法隆寺所蔵百万塔」のばあいは、製作年代が確定できるものであるが、年輪年代法による伐採年代は、721年で、40年以上、50年近い差がある。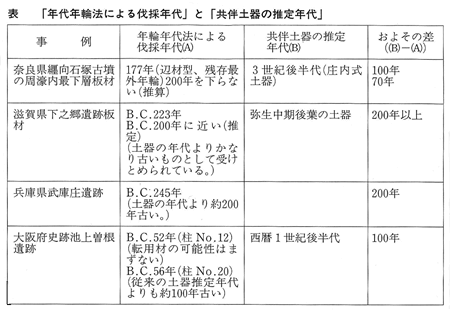
これくらいの差は、むしろ、ふつうのことなのではないか。
上の表(「年輪年代法による伐採年代」と「文献による建物などの建築年代」との比較)と同様のことは、共伴土器の年代を年輪年代法による伐採年代との関係(右の表参照)についてもいえる。
「年輪年代法による伐採年代(A)」は、つねに、推定される「共伴土器の推定年代(B)」よりも古くなっている。
ここでも、
(A)=<(B)
がなりたっている。
少し上の表(「年輪年代法による伐採年代」と「文献による建物などの建築年代」との比較)、すぐ上の表(「年代年輪法による伐採年代」と「共伴土器の推定年代」)ともに、同じような傾向がみとめられるのであるから、私たちは、「年輪年代法による伐採年代(A)」によって、従来の「共伴土器の推定年代(B)」が大きく組みかえるのには、慎重であるべきである。
新聞では、橿原考古学研究所の発表として、
「年輪の状態などから他の建物からの転用ではなく、また紫外線による劣化がなかったことから、伐採後すぐ使われたこともわかり、伐採年代が古墳の築造時期とほぼ同じころと判断された。」
と報じられている。
ほんとうにそんなことがいえるであろうか。
たとえば、少し上の表(「年輪年代法による伐採年代」と「文献による建物などの建築年代」との比較)の国宝元興寺(奈良市)の禅堂の木材は、飛鳥寺(奈良県明日香村)からの転用とみられる。
ここで、飛鳥寺で使われつづけたばあいと、奈良市に持って行ったばあいとで、紫外線による劣化が異なるなどということが起きえようか。年輪の状態によって区別できるであろうか。ほとんど、ばかばかしいというべき議論である。
「邪馬台国=畿内説」の立場の方方のためにする議論としか思えない。この種の議論の、確実な根拠を示していただきたい。
『日本の美術6』には、つぎのような記述もみられる。
「(兵庫県武庫庄遺跡の例について、)辺材部はほぼ完在しているものとみなした。しかも転用材の可能性は低い。つまり、柱根No.3の年輪年代245B.C.は原木の伐採年にかぎりなく近いものと思われる。
この結果は、土器の年代より約200年も古い。この年代差をどう埋めていくのか。実に頭のいたい問題を投げかけた例の一つである。」
つまり、転用材の可能性が低いばあいでも、どうも古くなりすぎということもあるようである。おそらく、使用前に、かなり長期間寢かせているばあいがあるのであろう。
田舎に行けば、百年まえ、二百年まえの大黒柱が立っていることがよくある。そのようなものを持って来て、再加工し、転用したばあい、ほんとうに転用かそうでないかの区別はつくのだろうか。
『読売新聞』は、さらに、「邪馬台国連合とは、次の時代であると考えられていた初期ヤマト政権そのものであった可能性が強かった。」とも記す。
邪馬台国時代から、初期ヤマト政権が存在していたとしよう。
それほど古い時代から、大きな古墳などを築造する権力をもっていたとすれば、そのことは、大和朝廷がわの伝承に、なんらかの根跡を残しそうなものである。たとえば、『古事記』『日本書紀』などの初期ヤマトの伝承のなかに、卑弥呼にあたる人物は、多少なりとも影を落としそうなものである。卑弥呼にあたる人物を『古事記』日本書紀』のなかに探ろうとすると、「邪馬台国畿内説」では、適格者を探しあぐねるということになるのではないか。
また、『古事記』『日本書紀』は、なんのために、大和朝廷の始祖である神武天皇が、九州から来たと記す必要があったのであろう。
■ヒノキ(檜・桧)は年代が古くでる
年輪年代測定法(樹木の年輪による年代決定法)や炭素14年代測定法などによって木材の年代を測定すると、その木材が出土した遺跡の構築年代よりも、明らかに著しく古い年代の得られることがしばしばある。主に木材の伐採年代と遺跡の構築年代とが異なるためである。これを、「古木効果」という。
「古木効果」が起きる理由として、つぎのようなものが考えられる。
(1)古代においては、大木を切り倒し運搬することは、労力的に大変であったとみられる。
そのため、一度使用した樹木の再利用をしばしば行った。
奈良県奈良市中院(ちゅういん)町の元興寺(がんごうじ)は、718年から建立がはじまったとみられる。その禅堂には、奈良県明日香村(あすかむら)の飛鳥寺(あすかでら)[本元興寺(ほんがんごうじ)、法興寺(ほうこうじ)]から移築されたとみられる586年ごろ伐採のヒノキが使用されていた[2010年8月14日(土)朝日新聞の朝刊の記事参照]。『続日本紀(しょくにほんき)』の霊亀二年(718)の九月条に、「法興寺を新京(平城京)に遷(うつ)す」という記事がある。
『続日本紀(しょくにほんき)』の桓武(かんむ)天皇の延暦(えんりゃく)10年(791)9月17日の条に、「平城宮(ならのみや)の諸門を壊し運ばせて、長岡宮(ながおかのみや)に移し、(門を)作らせた」との記事がある。これも木材の再利用を示す記事である。
(2)風倒樹や流木を用いた。『日本書紀』の「仁徳(にんとく)天皇紀」に流木で船を造った話がみえる。
(3)木材を貯蔵することがある。水分と油分を除くために長期間寝かせる。そうすることで、柱などにした際にヒビや歪みの入るのを防ぐ。
(4)大木の場合、年輪のどの部分を測定したかによってかなり異なる。
法隆寺の五重の塔の心柱(中心の柱)は、ヒノキである。年輪年代法による伐採年代は、594年ごろである。法隆寺は、711年ごろ再建されたとみられているので、およそ百年まえに伐採された木材が用いられていることになる。
法隆寺の場合、さきの(1)~(4)のいずれかが起きているとみられる。
たとえば、(1)の再利用や(3)の貯蔵木の問題を取り上げてみよう。
まず再利用についてである。建築物の木材は、数百年、ときに一千年を超えて利用、再利用されることがある。つまり、木材の伐採された時期と利用された時期とが、数百年以上異なることがある。
■池上曽根遺跡の事例
大塚初重氏は、ムック『邪馬台国の正体』のなかでのべる。
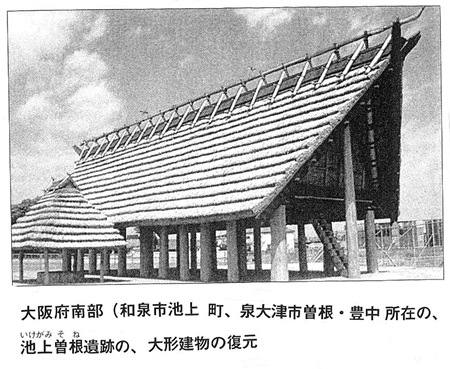 「大阪の池上曽根遺跡から発見された祭殿に使われた柱の年輪を分析したところ、紀元前52年に伐採されたことがわかりました。」
「大阪の池上曽根遺跡から発見された祭殿に使われた柱の年輪を分析したところ、紀元前52年に伐採されたことがわかりました。」
「一方、考古学ではどうなのか。1970年代まで、弥生時代中期と言えば、紀元前100年頃から紀元100年頃のことを指していました。しかし昨今、AMSを使った年代測定法の結果、その年代は見直され、従来よりも約50~100年は遡るのではないかと考えられるようになりました。」
しかし、このような発言はあぶない。
池上曽根遺跡から発見された柱は、ヒノキである。
そして、ヒノキは、年輪年代法によったばあいでも、炭素14年代測定法によったばあいでも、遺跡そのものの構築された年代よりも、はるかに古い年代を、しばしば示すことがしられている。
ヒノキは、年月の経過に対する耐久力がきわめて強い。そのため、再利用がよく行なわれたためである。
ヒノキを試料としたばあい、百年ていど年代が古く出るのであれば、「約50~100年」溯らせる必要はなくなってしまう。
箸墓古墳のばあい、二つのヒノキ材が、炭素14年代測定法によって測定されている。
二つの測定値同士は、きわめて近い。最終の西暦年数を推定するための途中段階の数字、炭素14年代BPの値で、わずか40年しか違わない(下の表参照)。

右の表には、同じ箸墓古墳から出土した遺物のヒノキと桃核(桃のタネの固い部分)の炭素14年代BPを示した。加重平均値で、ヒノキは、桃核にくらべ、352年、年代が古くでている。さらに、最終推定値である西暦年数換算値でみれば、上の表に示したように、じつに、この差は420年にひろがる。420年年代が古くでているのである。
その様子を示すのが、下の図である。
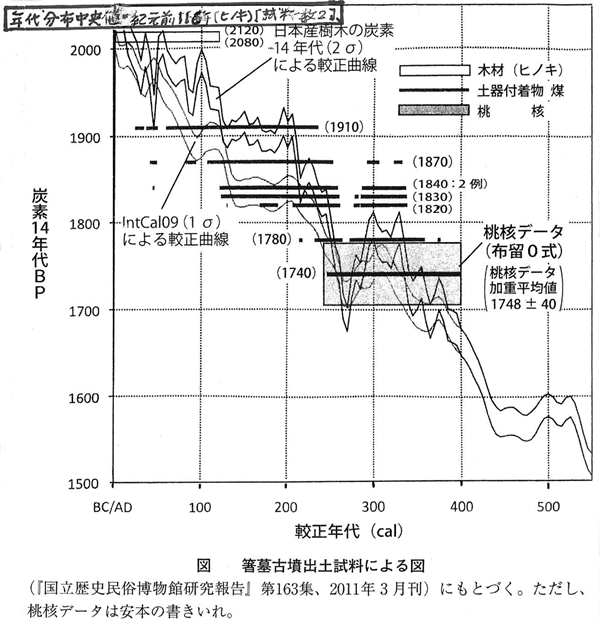
炭素14年代測定値では、まず上の図の縦軸の炭素14年代BP「BPは、Before Presentまたは、Before Physics[物理年]といわれる値を、途中段階の値としてまず求める。それを上の図の左下から右下の不規則な波形に下がる較正曲線といわれるものによって補正し、横軸上の推定西暦年数に換算する。縦軸の値を横にたどり、較正曲線にぶつかったところで、下にたどる。
西暦年推定値分布の中央値の算出などは、株式会社パレオ・ラボに依頼した。

一つ上の図(箸墓古墳出土資料による図)の左上の二つのヒノキのデータをみれば、ヒノキの年代がいかに古くでているかがうかがわれよう。
箸墓古墳の築造年代については、おもに、つぎの三つの説がある。
①四世紀の中ごろ(西暦350年前後)…関川尚功(せきがわひさよし)氏(元・奈良県立橿原考古学研究所)
②三世紀のおわりごろ(西暦270~300年ごろ)…寺沢薫氏(元・奈良県立橿原考古学研究所所員、現・桜井市纒向学研究センター所長)
③三世紀の中ごろ(西暦250年前後)…白石太一郎氏(大阪府立近っ飛鳥博物館長)
箸墓古墳の築造年代を、西暦紀元前の二世紀などにすることはできない。それは、どのような考古学者もみとめることのできない古い年代である。
ヒノキ材が、炭素14年代測定法によって、比較的安定した数値がえられている、というようなことでその年代をみとめられるのか。
それがみとめられないのであれば、池上曽根遺跡の紀元前52年への遡上説も簡単には、みとめるわけにはいかない。
箸墓古墳築造年代を西暦紀元前二世紀にもって行くのが、メチャクチャだというのなら、池上曽根遺跡の年代を、紀元前52年へもって行くのもメチャクチャである可能性が生ずる。
池上曽根遺跡の大形建物の柱材については、邪馬台国畿内説の考古学者、寺沢薫氏もくわしく検討して、「転用説(再利用説)」を、つぎのようにのべている。
「私は柱材の転用については否定するだけの証拠はないと思う」[寺沢薫「紀元前52年の土器はなにか-古年輪年代の解釈をめぐる功罪-」森浩一・松藤和人編『考古学に学ぶ遺跡と遺物』(同志社大学考古学シリーズⅦ)1999年刊、所収、参照]。
寺沢薫氏は、1998年に刊行された『最新邪馬台国事情』(白馬社刊)で記す。
「現時点で、年輪年代測定の成果に一方的に転向、依拠することは考古学者としての責務放棄でしかあるまい。」
■年輪年代法の原理
「年輪年代法」については、奈良文化財研究所の、光谷拓実(みつたにたくみ)氏が『日本の美術』6、No421「年輪年代法と文化財」(至文堂、2001年刊)において、かなり要領よく、かつくわしく紹介しておられる。
光谷氏は、その中でのべる。
普通、温帯や寒帯に生育する樹木の年輪は、年ごとの気象条件(おもに気温と降水量)の善し悪しに影響をうけながら、前年の年輪の外側に一層ずつ形成される。つまり、気象条件の良い年には広い年輪を、逆に悪い年には狭い年輪を形成する。この年輪幅を計測し、その変化を経年的に連続して調べてみると、生育環境が似かよった一定の地域範囲のなかでは、樹種ごとに固有の共通した変動パターンを描くことが判明している。こうした年輪特性を備えた樹種であれば、同年代に形成された年輪かどうか、それを判定することが可能となる。これを年輪変動パターン(略して年輪パターン)の照合という(下の図)。
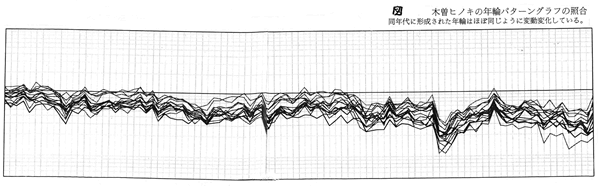
年輪年代法が適用できる樹種かどうかは、まさしくこの年輪パターンの照合が成立するか、しないかにかかっているのである。この検討作業をクリアした樹種だけが、年輪年代法の基本なる暦年の確定した標準年輪変動パターン(略して暦年標準パターン)の作成作業に取りかかれるのである。
年輪年代法では、まず第一に、年代を割り出す基準の暦年標準パターンを前もって作成しておかなければならない。その作成には、伐採年代の明らかな現生木の年輪からはじまって、古い建築部材や遺跡出土木材などから、多量の年輪幅の計測値データ(略して年輪データ)を収集、照合して同じ年輪パターンをもつ年代部分で順次連鎖していくと、長期の暦年標準パターンが作成できる(下の図)。
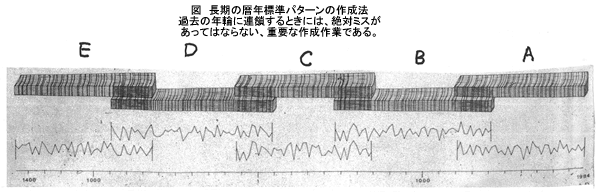
こうしてできあがった暦年標準パターンのなかのそれぞれの年輪データには、暦年代が確定していることになる。つぎに、年代不明の木材の年輪幅を計測し、試料パターンを作成する。これと暦年標準パターンとを照合し、双方の合致する年代部分をもとめれば、暦年標準パターンの暦年を試料パターン、すなわち試料木材の年輪にあてることができる。こうして、試料とした木材に含まれる年輪の年代が確定できると、その木材に関連した事象の年代を推定することができる。あるいは、いずれの地域の年輪パターンと合致するかを知ることによって適用範囲をあらかじめ確認できたり、場合によっては、試料材の産地の推定が可能なこともありうる。
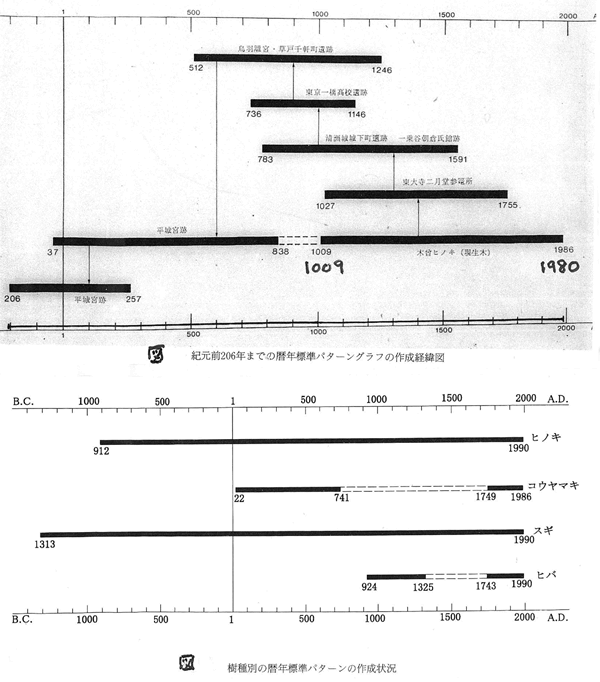
暦年標準パターンは、適用可能な樹種、すべてについて、また、地域ごとについて作成することが望ましい。しかし、樹齢が長くて、植生分布が広く、しかも古代から現代までよく利用されている樹種となると、ヒノキとスギの二種類に限られてくる。現在、ヒノキについては、現在から紀元前912年まで、スギは現在から紀元前1313年まで作成されている。
これ以外に、近畿地方のコウヤマキ材で741年から22年まで、東北地方のヒバで1325年から924年までのものができている。したがって、これら四樹種の年代確定範囲内においては、樹種別、地域別に使い分け、適宜応用して年代測定をおこなうことになる。ちなみに、ドイツでは約一万年前までのものができている。
・年輪パターングラフの作成
年輪年代法では、複数試料の年輪データを比較照合する方法として、年輪幅の変動状況を肉眼で観察する場合と、年輪データを統計的に処理する場合とがある。目視でもって観察するには、片対数グラフ用紙の均等目盛りの横軸に通常5mm間隔で年代をとり、対数目盛りになった縦軸に年輪幅の測定値をとってつないでいく。これが、年輪パターングラフである。この方法では、年輪幅をあらわすのに対数目盛りを使用するから、狭い年輪幅で推移する場合にも広狭が相対的に大きく表現できるところから、1mm以下の微細な変化が比較しやすくなる。
なお、年輪パターングラフ用紙には、透視台の上で重ねあわせて目視で比較するのが普通であるから、その便を考えて、トレーシングペーパーを使用すると便利である。
・コンピューターによる年輪パターンの照合
樹木の年輪幅は、同一年度に形成されたものでも樹齢や生育環境条件などの違いに応じて個体間で差が生じる。この個体の特徴が特に強い試料であれば他の試料との対比が困難になることがある。したがって、それを避けるために年輪データを補正し、個体的特徴を除去しなければならない。ここではこの規準化処理に五年移動平均法を用いることとした。
具体的には、つぎのようにおこなう。もとの年輪データを
x(i)(i=1,2,・・・,N)(但し、i=1は中心部から樹皮部に向けての一番目の年輪データであり、i=Nは最外年輪データである)として、次式によってN(i)を算定する。
N(i)=5x(i+2)/{x(i)+x(i+1)+x(i+2)+x(i+3)+x(i+4)}×100・・・(I)
すなわち、N(i)はx(i+2)つまり三番日の年輪データとその前後2年間を含む5年間の平均値との百分比である。この移動平均値は、自然対数に変換しておく。
つぎに、二つの試料の間の年輪パターンの類似の程度は、この対数変換値を用いて次式で定義される相関係数rによって測定した。

ここで、xiyiはさきの規準化処理によって求めた値の対数変換値であり、x(バー)y(バー)はxiyiのそれぞれの平均値、Nはデータ点数である。ついで(Ⅱ)式で求めた相関係数rの有意性の判定は、つぎのt分布検定でおこなった。(Ⅱ)式の相関係数rと組の数Nから
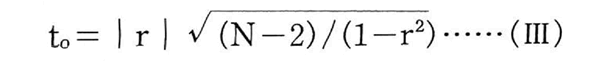
(Ⅲ)式で求めたt0は自由度(Nー2)のt分布に従うことから、帰無仮説を検定するのにt分布表より適当な有意水準αにおけるtの限界値tαを求め、これを基準にしてt0>tαであればその有意水準で帰無仮説は棄却され、相関があるという対立仮説の選択がおこなわれる。
ここで(Ⅲ)式で得られたt0(以下t値とする)は、この数値が大きければ大きいほど双方の年輪パターンの類似の程度が高いことを示す。
以下、ここではこの検討にあたり自由度はすべて60以上であるので、t値と危険率0.1%の、tα値(t≓3.5)とを比較して相関の有無を検討することとした。しかし、この方法だと一組の年輪パターンの照合を比較する場合、t値が3.5以上になる箇所が複数になる事例はごく普通である。そこで、コンピュー夕ーによるt値の検出にあたっては、tが3.5以上になったところをすべて取りだし、そのなかで最大値を示す箇所に着目することとしている。しかし、検出した最大t値の位置が必ずしも正しい照合位置を示すとはかぎらないことがある。その多くが重複部分の年輪データ数が少ない場合に限られる。そこで、こうした照合ミスを回避するために、t値が5.0前後あって、しかも照合分の年輪データ数が少なくとも百層分以上重複しているかどうかも、注意項目の一つとしている。
以上、年輪パターンの照合作業は、コンピューターで検出した最大t値の位置で、双方の年輪パターングラフを重ねあわせ、目視によって比較してから最終結論をだすことにしている。
■「科学的な証明」とはなにか
「邪馬台国九州説」も、一つの仮説であり、「邪馬台国畿内説」も、一つの仮説である。したがって、それらの仮説が正しいことを主張するためには、「根拠」を示し、「証明」が行なわれなければならない。
では、どのような議論が、「根拠」をもつものであり、「証明」のできた議論といえるのか。
このことを考えるのに、大変参考になる本が、最近刊行されている。
京都大学大学院文学研究科准教授の大塚淳(おおつかじゅん)氏の手になる『統計学を哲学する』(名古屋大学出版会、2020年)である。
3000円をこえる本であるが、私の買い求めたものでは、刊行後1ヵ月と少しで3刷となっている。この種の本を求める人の多いことがわかる。
この本の序章で、大塚氏は述べる。
「この本は何を目指しているのか。その目論見(もくろみ)を一言で表すとしたら、『データサイエンテイストのための哲学入門、かつ哲学者のためのデータサイエンス入門』である。ここで『データサイエンス』とは、機械学習研究のような特定の学問分野を指すのではなく、データに基づいて推論や判断を行う科学的/実践的活動全般を意図している。」
そして、さらに述べる。
「現代において統計学は、与えられたデータから科学的な結論を導き出す装置として、特権的な役割を担っている。良かれ悪しかれ、『科学的に証明された』ということは、『適切な統計的処理によって結論にお墨付きが与えられた』ということとほとんど同義なこととして扱われている。しかしなぜ、統計学はこのような特権的な機能を果たしうる(あるいは少なくとも、果たすと期待されている)のだろうか。
そこにはもちろん精密な数学的議論が関わっているのであるが、しかしなぜそもそもそうした数学的枠組みが科学的知識を正当化するのか、ということはすぐれて哲学的な問題であるし、また種々の統計的手法は、陰に陽にこうした哲学的直観をその土台に持っているのである。」
「例えば、ベイズ統計や検定理論などといった、各統計的手法の背後にある哲学的直観を押さえておくことは、それぞれの特性を把握し、それらを『腑に落とす』ための一助になるだろう。
ここで、統計学の重要な基本概念である帰無仮説(きむかせつ)がある。
帰無仮説(きむかせつ)とは『日本国語大辞典』(小学館刊)にあるように「仮説検定でその当否を検定しようとする仮説。否定されることを期待する形で提出されるところからいう。」である。
帰無仮説の例を示す。
【例】1の目が出ると勝ちとなる遊戯で、一つのさいころを3回投げたところ、3回とも1の目が出た。このさいは正常でないといえるか。
[解]このさいが正常であるという仮説を立てると、1の目が出る確率p=1/6である。したがって、このさいを3回投げて3回とも1の目が出る確率= (1/6)↑3 = 1/216 になる。この確率はきわめて小さい。したがって、このさいころは正常でないと判定する。このように、われわれが仮説を立てる場合には、これが棄却されることを予想して設定することが多い、このような仮説を帰無仮説(null hypothesis)という。
上例の確率が1/216であるというのは、仮説が正しければこのようなことは216回につき1回くらいしか起こらない珍しいことで、正常なさいならめったに起こらないとして仮説を棄却した。しかし、珍しいことは珍しくても絶対に起こらぬことではない。さいが正常であっても、 216回に1回くらいは起こりうるのである。
このように、仮説が正しいにもかかわらず、これを棄却する誤りを第1種の誤りといい、第1種の誤りを冒かす確率を危険率または有意水準(level of significance)という。例1の答としては、「1/216の危険率で、このさいは正常でないと判定する」というのが正確である。危険率をどのくらいにとるかということは、それぞれの場合の目的に応じて異なるが、 0.05以下、0.01以下という数値がよく使われる。
岡田泰栄(やすよし)著『統計』(共立出版刊)
つまり、帰無仮説により、判断の客観的基準を定めるのである。
また別の例として、下記がある。
旧石器捏造事件がおきたとき、人類学者で、国立科学博物館人類研究部長(東京大学大学院理学系生物科学専攻教授併任)の馬場悠男(ばばひさお)氏が、私が「洛陽発見の三角縁神獣鏡」について述べたのと同じようなことを語っている。
「私たち理系のサイエンスをやっている者は、確率統計学などに基づいて『蓋然性が高い』というふうな判断をするわけです。偉い先生がこう言ったから『ああ、そうでございますか』ということではないのです。ある事実が、いろいろな証拠に基づいて100%ありそうか、50%か、60%かという判断を必ずします。どうも考古学の方はそういう判断に慣れていらっしやらないので、たとえば一人の人が同じことを何回かやっても、それでいいのだろうと思ってしまいます。今回も、最初は変だと思ったけれども何度も同じような石器が出てくるので信用してしまったというようなことがありました。これは私たち理系のサイエンスをやっている者からすると、まったく言語道断だということになります。」
「経験から見ると、国内外を問わず、何ヵ所もの自然堆積層から、同じ調査隊が、連続して前期中期旧石器を発掘することは、確率的にほとんどあり得ない(何兆分の1か?)ことは常識である。
だからこそ、私は、東北旧石器文化研究所の発掘に関しては、石器自体に対する疑問や出土状況に対する疑問を別にして、この点だけでも捏造と判断できると確信していたので、以前から、関係者の一部には忠告し、拙著『ホモ・サピエンスはどこから来たか』にも『物証』に重大な疑義があると指摘し、前・中期旧石器発見に関するコメントを求められるたびに、マスコミの多くにもその旨の意見を言ってきた。
しかし、残念ながら、誰もまともに採り上げようとしなかった。とくに、マスコミ関係者の、商売の邪魔をしてもらっては困るという態度には重大な責任がある。」(以上、春成秀爾編『検証・日本の前期旧石器』学生社、2001年)
確率論的にみれば、「洛陽発見の三角縁神獣鏡事件」も、「旧石器捏造事件」も、問題の構造は、同じである。
ふつうの科学の基準では、ある仮説にしたがうとき、計算をすると、一定の確率(ふつうは、100分の5か100分の1以下)でしか起きないことが起きたことになるときは、もとの仮説は捨てる(棄却する)「約束」になっている。機械的(メカニカル)に棄却することによって、議論の客観性をたもつという「基準」をもうけている。




 当然の、そして銘記すべき注意事項である。
当然の、そして銘記すべき注意事項である。 つぎに、『日本の美術6』にのせられているもので、文献によって、建物などの建築年代がほぼ確定できるものをとりあげ、年輪年代学による伐採年代とを比較してみよう。
つぎに、『日本の美術6』にのせられているもので、文献によって、建物などの建築年代がほぼ確定できるものをとりあげ、年輪年代学による伐採年代とを比較してみよう。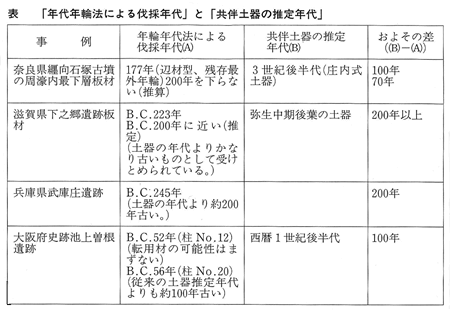
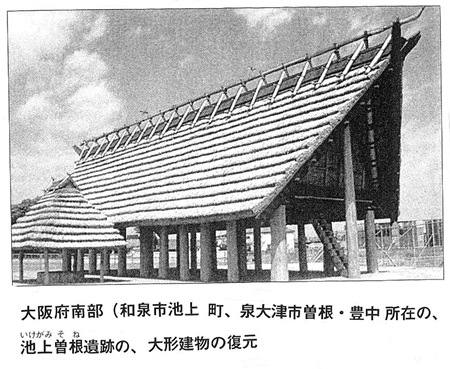 「大阪の池上曽根遺跡から発見された祭殿に使われた柱の年輪を分析したところ、紀元前52年に伐採されたことがわかりました。」
「大阪の池上曽根遺跡から発見された祭殿に使われた柱の年輪を分析したところ、紀元前52年に伐採されたことがわかりました。」