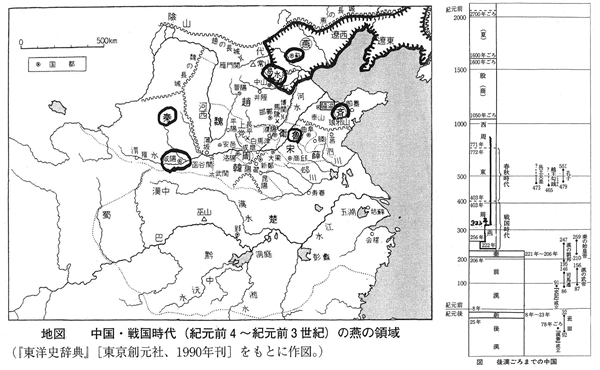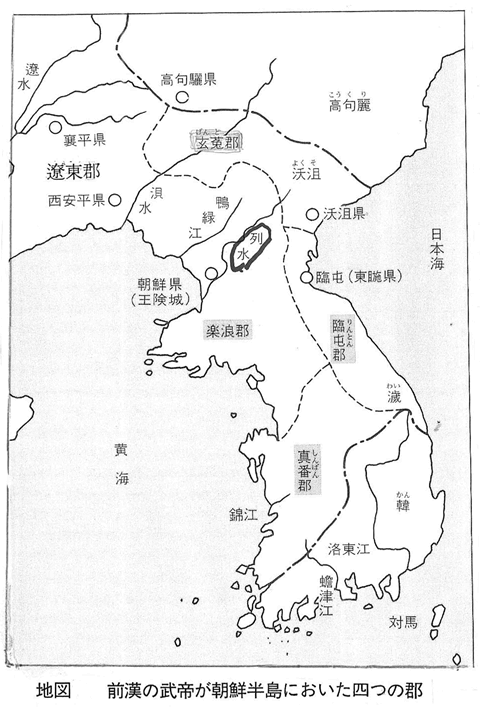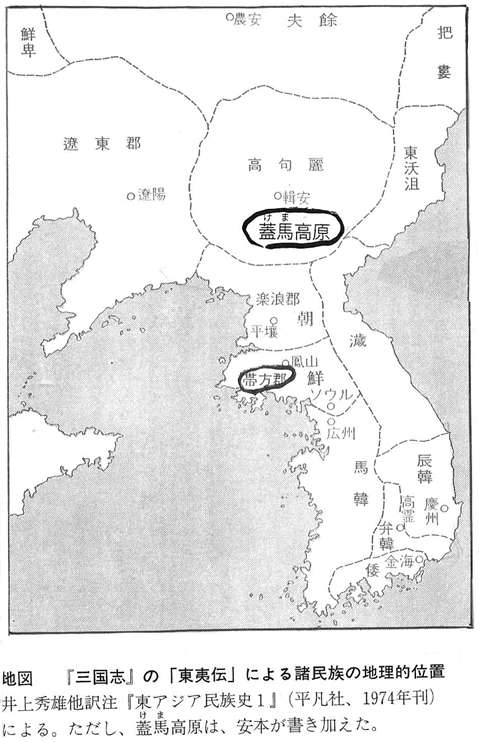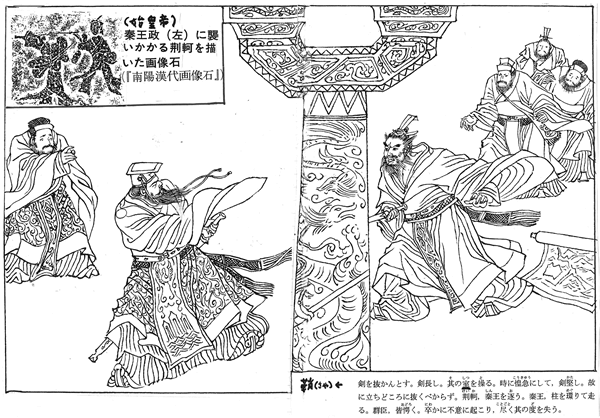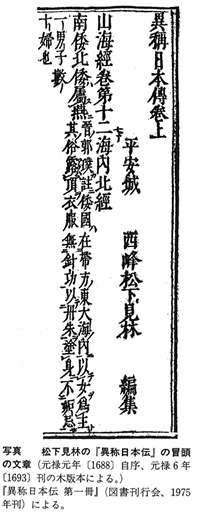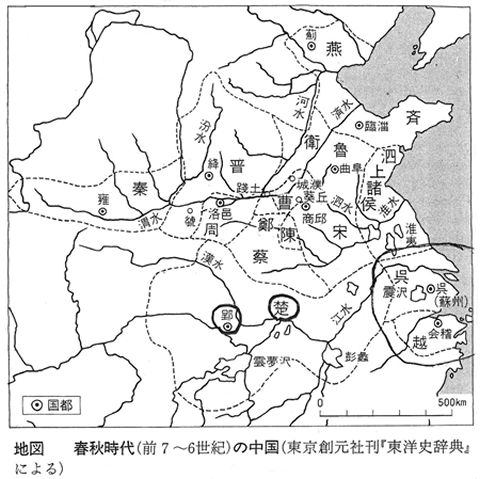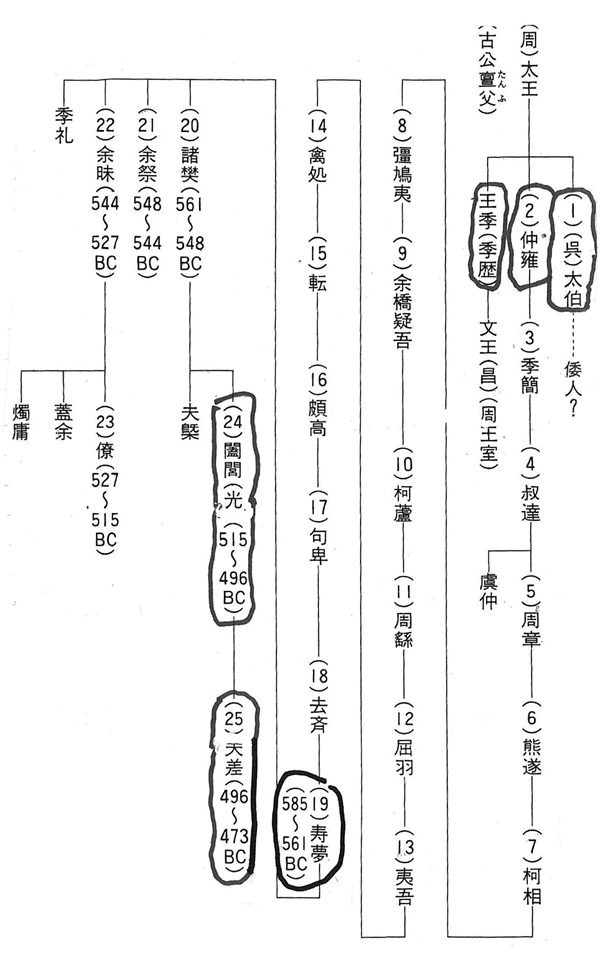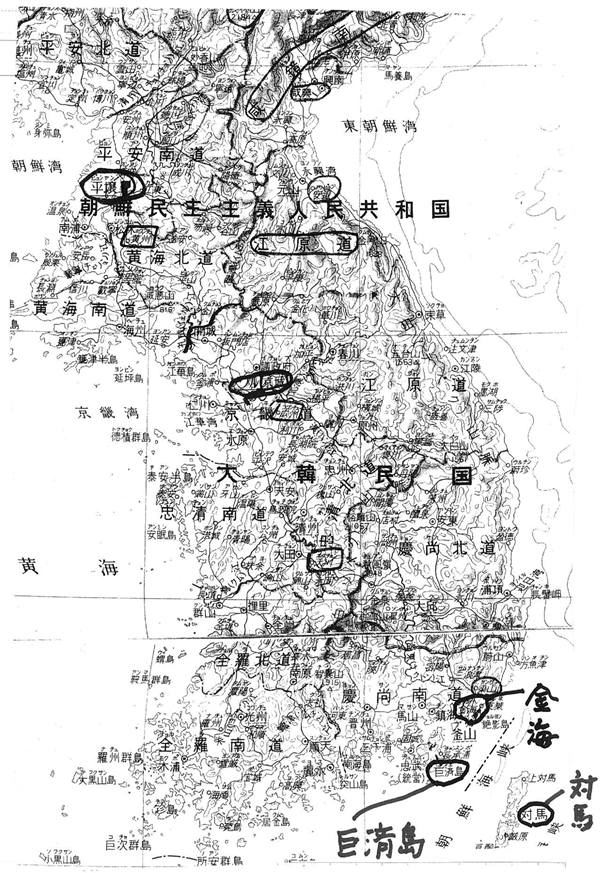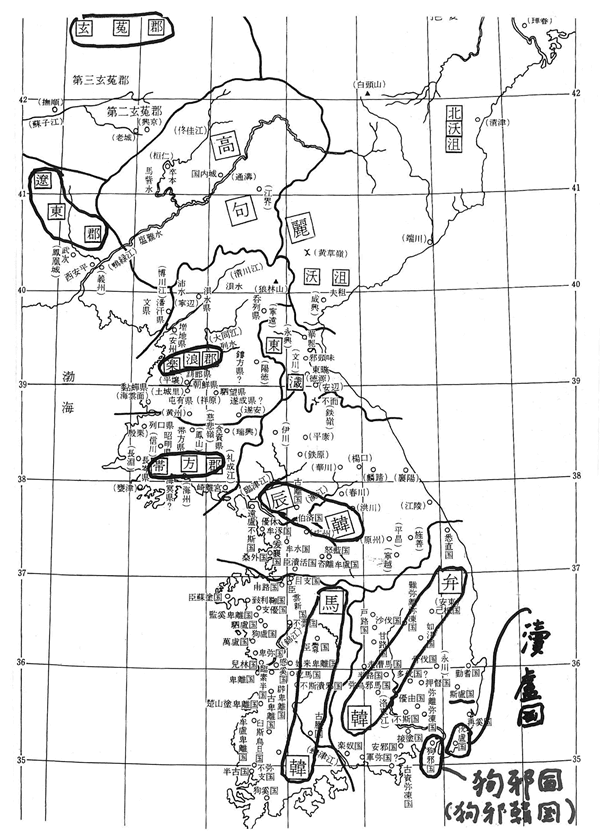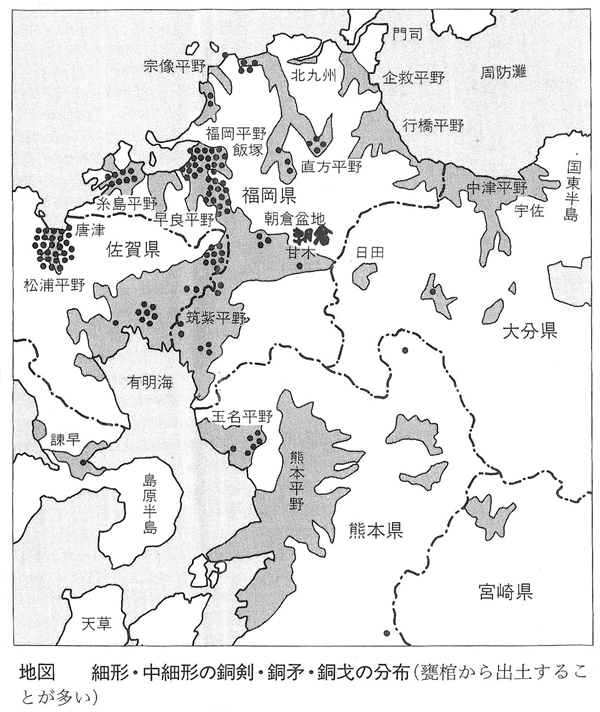遠いむかし、倭人と呼ばれる人々のすむ国があった。海原にうかぶ島国で、その存在をはじめて東洋史上にあらわしてくるのは、西暦紀元前後のことである。
■『漢書』「地理志」のなかの「倭」
『漢書』は、前漢の歴史を記した本である。後漢の班固の撰。西暦82年ごろに成立した。『漢書』の「地理志」の下の巻の燕地の条に、つぎのような文章がある。
「楽浪の海のかなたに、倭人がおり、百余国に分かれ、歳時(季節)ごとに来て、物を献上し見(まみ)えた[見(まみ)える]、という。(楽浪海中有倭人分為百余国、以歳時来献見云)」
この文章の問題点は、二つある。一つ目は「燕地」の条に記されていること、二つ目は、おしまいが「云(い)う」と伝聞になっていることである。
したがって、「献上し見(まみ)えた」対象が、「燕」であるとも「漢」であるとも読める。
すなわち、つぎの二とおりの読み方が成立しうる。
(1)かつて、倭は燕の国に属していた。そのころ倭人は、百余国に分かれていた。季節ごとにやって来て、物を献上し、燕の国に見(まみ)えたという話だ。
(2)かつて燕のあった地の楽浪の海のかなたに倭人がいる。百余国に分かれ、季節ごとに、(漢の武帝が、紀元前108年に今の平壌ふきんにおいた楽浪郡の官庁に、)やって来て、漢に対して物を献上し、見(まみ)えたと聞いている。
(下図はクリックすると大きくなります)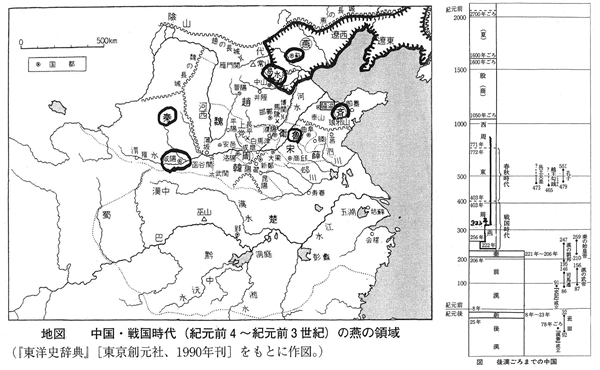
注:【燕(えん)】についての資料
①中国、春秋戦国時代の国。戦国七雄の一つ。周の武王が弟の召公奭(しょうこうせき)を薊(けい)に封じたのに始まり、河北省北部から東北地方南部一帯の中国北辺を領し約800年続いた。紀元前四世紀末に即位した昭王のとき、賢者、名将を登用して繁栄したが、紀元前222年秦に滅ぼされた。
②周と同姓の国。戦国七雄の一。始祖 召公奭(せき)は、兄の武王が殷を滅ぼしたのち、燕に封じられたと伝えられるが、卜辞金文の研究の結果は、必ずしもこれを立証しない。領土は大体今の河北省の北部にあたり、薊(けい)[北京の西北]に都した。戦国時代に入って当時の七大強国の一に数えられたが、辺境に位し、西に趙、南に斉の両強国があり、北は遊牧民に接していたので国力は振わず、7国中一番おくれて易王の10年(前323)に王を称した。昭王(前312~前279)のころもっとも栄え、王は郭隗(かくかい)の説を用い、幣を厚くして賢者を招き、前284年には楽毅を将とし、ほかの5国と結んで斉を攻めて大勝を博し、また名将秦開を用いて遼東に領土を拓(ひら)いた。昭王の死後、国勢衰え、王喜にいたって秦の圧迫を受けた。太子丹は危機を打開するため、荊軻(けいか)を送って秦王政(始皇帝)を刺殺しようとしたが、失敗し、前222年、秦のために滅ぼされた。
前漢の武帝は。紀元前108年に。朝鮮半島を領土とし、四つの郡をおき、郡県的統治を行なった。古朝鮮の首都王険城(平壌)を中心とする楽浪郡、その北の玄兔(げんと)郡、東の臨屯(りんとん)郡、南の真番郡がそれである。(下の地図参照) 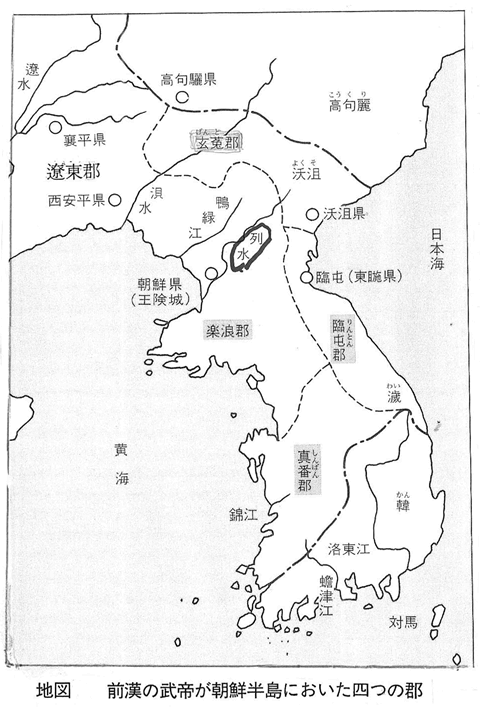
ただ、『後漢書』の「倭伝」の最初のところに、つぎのように記されている。
「倭は、韓の東南大海の中にある。(倭人は、)山島によりて居(すまい)を為(つく)る。およそ、百余国である(あるいは、百余国であった)。(前)漢の武帝が[衛氏(えいし)]朝鮮を滅ぼしたのち、漢に通訳と使者を派遣してきたのは、三十ヵ国ほどである。」
また、『魏志倭人伝』の冒頭には、つぎのように記されている。
「倭人は、(魏の)帯方郡の東南、大海のなかにある。山島(しま)のなかに国ができている。旧(もと)百余国(むかしは、百以上の国があった)。漢のとき、来朝するものがいた。今、使者と通訳とが往来しているのは、三十ヵ国である。」
これらの記事をまとめると、「漢以後には、使者と通訳とを派遣しているのは三十ヵ国ほどで、それよりもむかしには百余国あった。」ということであるようにみえる。
つまり、さきの『漢書』「地理志」の倭についての記事は、燕の時代のことの伝聞のようにみえる。
もともと、『漢書』の「地理志」の燕地の条の記載は、各地の伝統的風俗を述べている部分の一つとして、かつての燕の地で行なわれていたことを述べている部分に記されているものである。
■『山海経』のなかの「倭」
中国に『山海経(せんがいきょう)』という文献がある。
『山海経』は、古代中国の神話と地理のことを書いた本である。山や海の動植物のことや、金石のこと、また、怪談などを記す。十八巻からなる。
著者は不明である。古代中国の伝説上の聖王であった禹(う)が書いたともいい、また、禹の治水を助けた伯益(はくえき)が書いたともいう。もともと、ひとりの人が、ある特定の時代に書いたものではないとみられる。
『史記』を書いた司馬遷が読んでいる。前漢時代の学者の劉歆(りゅうきん)[紀元前53~紀元後21)が校定し、叙録(じょろく)[おおまかな内容を記したもの。解説文]を書いている。
したがって、漢代にはすでに存在していた。戦国時代~秦・漢代の著述とみられる。
その『山海経』の第十二の「海内北経」のなかに、「倭」についての、つぎの文がある。
「蓋国在鉅燕南倭北倭属燕」
この文は、現在、ふつう、つぎのように読み下されている。
「蓋国(がいこく)は鉅燕(きょえん)の南、倭の北にあり。倭は燕に属す。」
燕は、中国の戦国時代の国の名である。
本田済(ほんだわたる)・沢田瑞穂(さわだみずほ)・高馬三良(こうまみよし)訳の『抱朴子 列仙伝・神仙伝 山海経』(平凡社、1973年刊)では、この部分は、つぎのように日本語に訳されている。
「蓋国(がいこく)は強大なる燕(えん)の南、倭(わ)の北にあり、倭は燕に属す。」
史礼心・李軍注の『山海経』(中国・華夏出版社、2005年刊)では、「蓋国」などについて注をつけている。日本語に訳すと、つぎのようになる。
「蓋国(がいこく) 郝懿行(かくいこう)[清代の学者、1757~1825]の注に、つぎのようにある。
『三国志』の『魏志』の『東夷伝』にいう。
『東沃沮(とうよくそ)は、高句麗の蓋馬大山(がいまたいざん)の東にある。』
『後漢書』の『東夷伝』にも、同じ文がある。」
「李賢(唐の高宗の子。『後漢書』の注を行なった)の註にいう。
『蓋馬(がいま)は、県名である。玄菟郡(げんとぐん)に属する。』
いま考えるに、『蓋馬』は、もと蓋国であった疑いがある。
『鉅燕』は、大燕国のことである。」
中国語学者の藤堂明保訳の『倭国伝』(学習研究社、1985年刊)では、「蓋馬大山(がいまたいざん)」に注をつけ、「蓋馬(けま)高原全体を指すか。」と記している(蓋馬高原については、下の図参照)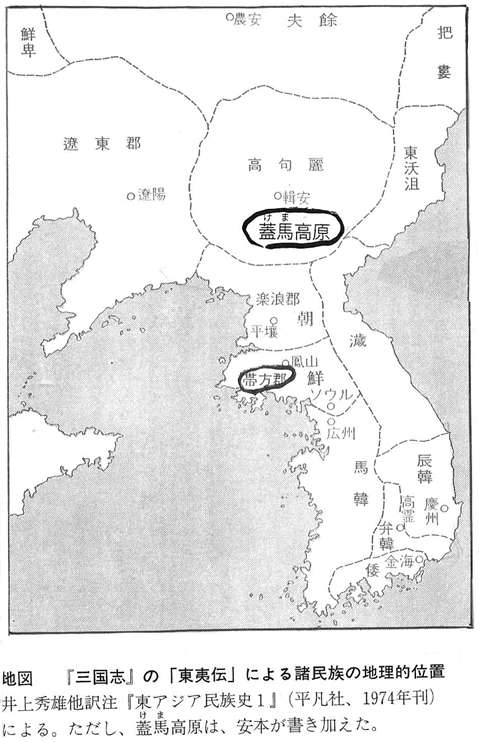
なお『山海経』の「海内北経」には、朝鮮について、つぎのように記している。
「朝鮮は、列陽河の東にある。海の北、山の南である。列陽河は、燕に属す(朝鮮在列陽東、海北山南。列陽属燕)。」
さきに紹介した史礼心・李軍注の『山海経』には、つぎのようなことが記されている。
「郭璞(かくぼく)[276~324。晋の時代の詩人、卜筮家(ぼくぜいか)。『晋書』に伝がある]の注にいう。
『朝鮮は、今、楽浪郡にある。箕子(きし)の封ぜられたところである。列は水(川)の名である。今、帯方にある。帯方は列水の河口の県である。』」
『山海経』は、また第十三の「海内東経」において、つぎのように記す。
「(中国の海内[国内]のうち、)強大なる燕は、東北の隅(すみ)にある。(鉅燕在東北阪)」
前の地図[中国・戦国時代(紀元前4~紀元前3世)の燕の領域]をみれば、燕の国が、中国の戦国時代において、中国の東北のすみにあったことがわかる。
燕は、戦国七雄(戦国時代[紀元前403~紀元前221]の七大国)に数えられる国の一つであった。その領域は、現代中国の東北(満州)の南部・朝鮮北部にわたっていた。都は、現在の北京の北西の薊(けい)であった。
燕は、紀元前222年に、秦の始皇帝によって滅ぼされる。
したがって、『山海経』のさきの記述は、燕が滅ぼされるまえ、紀元前222年以前の状況を記しているようにみえる。
■刺客(しかく)、刑軻(けいか)
燕が、滅びる数年まえに、燕の太子が、刺客の刑軻(けいか)をおくり、秦王政(始皇帝)を殺そうとした話は、司馬遷の『史記』に記されている。よく知られた話である。
学習院大学教授の、鶴間和幸(つるまかずゆき)氏の著者『中国の歴史3 ファーストエンペラー(始皇帝)の遺産』(講談社、2004年刊)は、そのときのことを、つぎのように記している。
「『史記』刺客列伝(しかくれつでん)には、暗殺を決行しようとした刺客刑軻の行動がじつにドラマティックに描かれている。燕の太子丹の命を受けた刑軻は、秦王への土産として秦の樊於期(はんおき)将軍の首と、督亢(とくこう)という豊かな土地の地図をもち、秦舞陽(しんぶよう)を連れて出発した。燕の易水(えきすい){前の地図[中国・戦国時代(紀元前4~紀元前3世)の燕の領域]参照}という川のほとりで見送られるときに、筑(ちく)という楽器に合わせて別離の悲しみを歌った詩はよく知られている。皆白い装束を着て見送った。易水のほとりまで来ると、道祖神(どうそじん)を祀(まつ)り、高漸離(こうぜんり)は筑を撃ち、荊軻はこれに合わせて歌った。見送りの者はすすり泣いた。荊軻はさらに歌った。
風蕭蕭兮易水寒、壮士一去兮不復還。
漢文書き下しでは、
風蕭々(かぜしょうしょう)として易水(えきすい)寒(さむ)し、壮士(そうし)一たび去(さ)って復(ま)た還(かえ)らず。」
「一行は咸陽(かんよう)に到着し、秦王を襲うクライマックスに入っていく。後漢(ごかん)時代の画像石(がぞうせき)は、死者を祀(まつ)る廟(びょう)の壁画の石に刻まれたものである。荊軻が秦王を暗殺しようとする場面が時間を凝縮して一場面に描かれている。いま『史記』刺客列伝(しかくれつでん)の記述に従って画面を見てみよう。
秦王から咸陽宮に迎え入れられた荊軻は、樊於期(はんおき)の頭を入れた函を持ち、秦舞陽(しんぶよう)は地図の箱を捧げて進んだ。いざ秦王の前に出ると秦舞陽は恐(おそ)れ震え出したので、群臣は怪しんだ。
画像石(右の図)画面右下に伏せる秦舞陽の姿はその瞬間だ。荊軻は振り返って笑い、『北方の蛮夷(ばんい)のいなかものゆえ、天子にお目にかかったことがないのです』とわびた。秦王が『地図を取らせよ』といったので、荊軻は王に渡した。最後まで開くと、隠してあったヒ首(あいくち)が現れた。荊軻は左手で秦王の袖をつかみ、右手でヒ首を持って剌そうとした。しかし身に届かないうちに、秦王は驚いて立ち上がったので、袖がちぎれた。画像石の中央右、ちぎれた袖が宙に浮いている。秦王は剣を抜こうとしても、とっさのことで剣が堅くて抜けない。荊軻は秦王を追い回し、秦王は柱を回って逃げた。柱の左右に、靴を残して逃げる秦王と髪を逆立てる荊軻が対照的に刻まれている。
群臣は急な事態に平静さを失った。
秦の法律では、側近は殿上に上がる時には武器を携帯できなかった。このとき侍医の夏無且(かむしょ)が持っていた薬嚢(やくのう)を荊軻に投げつけ、ひるんだすきに、秦王は剣を背負ってようやく抜き、荊軻を撃った。荊軻はヒ首を投げたが、柱にあたった。画像石中央にその瞬間が描かれている。荊軻は結局左右のものに殺された。」
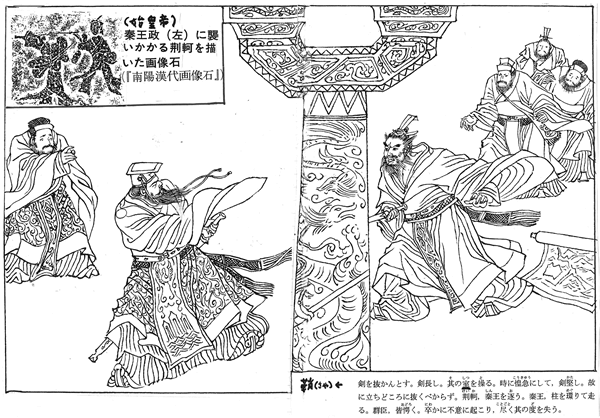
『東洋歴史大辞典』(臨川書店)から
樊於期(
ハンオキ)
戰國末秦の將軍。罪を得、燕に亡命す。時に燕の太子丹四方の賢士を集め宿怨ある秦に報ぜんとして居たので、快く彼を匿(かくま)うた。丹の傅鞠武(ふきくぶ)は秦の怒りを恐れ、彼を匈奴に入らしめ除かん亊を勸めたが、食客の保護者を以て自任した丹は肯(き)かず、其後荊軻を得て之を厚遇し、秦軍易水に迫るに及び荊軻をして秦王政に謁せしめ曹沫の故智に倣ひ侵地を還附せしむるか、然らずば之を刺殺せしめんとした時、荊軻は秦王を信ぜしめる爲に秦が金千斤、邑萬家の懸賞をつけてゐる樊於期の首を齎(もた)らさんと請(こ)ひ、逡巡する丹に代りて自ら於期に會ひ、自分が於期の首を以て秦王に獻じ、左手其袖を把り右手其胸を刺さば然ちば則ち將軍の仇は報いられ、燕の愧(はじ)は除かれんと説いた。
秦の爲に父母宗族を戮沒(りくぼつ)された漂零(ひょうれい)の樊將軍は之を聞き奮勵(ふんれい)切歯、荊軻の計を是とし自剄した。之を聞き丹は屍に伏し慟哭したが今は止むを得ず於期の首を函に盛り封じ、之と共に徐夫人のヒ首と督亢(とくこう)の地圖とを齎(もた)らしめて荊軻を秦に遣した。凄絶を極めたこの苦肉の計も秦の宮廷に於ける荊軻一行の失敗で水泡に歸し、樊於期を枉殺(おうさつ)せしむるに終った。参考:史記八六荊軻列博・戦国策三一燕丹子(百子全集)。
注:【曹沫(そうかい)】
春秋、魯(ろ)の人。勇力を以て莊公に事ふ。魯、齊(せい)[斉]と戰ひ、三たび敗北す。莊公懼れ、遂邑の地を献じて和し、齊と柯に會して盟ふ。沫、ヒ首もて、齊の桓公を劫(こう)し、三戰に亡へる地を復す。
司馬遷『史記』(筑摩世界文学大系7、『史記Ⅱ』筑摩書房刊)「刺客列伝」「荊軻伝」
荊軻(けいか)は太子がとうてい樊将軍を殺さないことを知り、ひそかに樊於期(はんおき)に会って言った。「秦のあなたに対する仕打ちは、まことに深刻といわなければなりません。父母をはじめ宗族をすべて殺戮(さつりく)し、いまや将軍の首に金千斤と万戸の食邑を懸けていますとか。将軍はいったいどうなさるおつもりですか。
樊於期が天を仰いで嘆息し、涙を流して、「わたしはそれを思うごとに苦痛が骨髄に徹します。しかし、どうすればよいのか、私にもわからないのです」と言うと、「いま一言で燕国のうれえを解き、将軍の仇を報いる策があります。将軍はそれをなんと思われますか。」
於期が進み出て、「それはどうするのか」と問うと、荊軻が言った。「あなたの御首をいただいて、秦王に献ずるのです。
秦王はかならず喜んでわたしを引見しましょう。そのとき、わたしは左手に秦王の袖をとり、右手でその胸を刺すのです。しからば将軍の仇は報いられ、辱しめられた燕の恥もすすがれましよう。あなたに御異存がございましょうか。」
すると樊於期は片肌をぬぎ、腕を握って進み出で、「これこそ私が日夜歯をくいしばり、胸を打って悶えたところ、いまこそ教えを承わることができた」と言い、ついにみずから首はねて死んだ。太子はこれを聞くと、馳せつけて屍に打ち伏し、哭泣(こくきゅう)して消えいるように哀しんだ。しかし、すでに死んだものは、いかんともする術がなく、樊於期の首を函に入れて封じた。これよりさき、太子は天下に鋭利なヒ首を求め、趙の人徐(じょ)夫人のヒ首を百金で手に入れた。そこで工人に命じ、毒薬をヒ首の刃に染めて人に試したが、血一筋うるおうだけで、たちどころに死なない者はなかった。こうして支度を整え、荊軻を秦に出立させることとなった。
燕国に勇士秦舞陽(しんぶよう)というものがいた。十三歳で人を殺したことがあり、恐れて誰ひとり逆ろう者がなかった。太子は、この秦舞陽を荊軻の副とした。
注:【徐夫人のヒ首】
「徐夫人」はヒ首を所蔵していた人の名。『索隠』は「徐は姓、夫人は名で、男子である」という。
藤堂明保監修『史記二』(学習研究社刊)「刺客列伝」の解説
これは春秋時代から戦国時代末期にかけて現れた五人の有名な刺客の伝である。
その五人とは、柯(か)で行われた盟会の席上、斉(せい)の桓(かん)公を脅かして、奪われた領地をすべて返還させた魯(ろ)の将軍の曹沫(そうかい)、呉(ご)王の僚(りょう)を刺殺し、ついに王子の光(こう)を呉王[闔閭(こうりょ)]とならしめた専諸(せんしょ)、その主君智伯(ちはく)のために仇の趙襄子(ちょうじょうし)をつけねらい、最後まで二心なきことを示してその厚い知遇に応えた予譲(よじょう)、厳仲子(げんちゅうし)の知己の情に感激し、仲子に代わってその仇の俠累(きゅうるい)を刺し殺した聶政(じょうせい)、燕(えん)の太子の丹(たん)のために、まさに天下を統一しようとしていた秦(しん)王の政(せい)[後の始皇帝]を刺そうとし、ついに果たし得なかった荊軻(けいか)である。
論賛において司馬遷は記している、「かれらは、その義心から発した行為が、成功した者もあれば、成功しなかった者もある。しかしその意図は明自であり、その素志を曲げることはなかった」と。義心とは何か。それは「士は己れを知る者のために死す」ということに他ならない。そこには一かけらの私利私欲もなかった。だからこそ、かれらは本来たたえられるべくもない行為をしながらも、なお多大の感動を後世に与えたのであった。
本篇では荊軻の伝が半ばを占める。筆者の時代に最も近く、伝える資料も多かったからであろう。最後に筑(ちく)をもって始皇帝に打ちかかった荊軻の友高漸離(こうぜんり)の伝を付す。
秦(しん)の皇帝、其(そ)の善く筑(ちく)を撃つを惜しみ、重んじてこれを赦(ゆる)し、乃(すなわ)ち其(そ)の目を臛(かく)す。筑(ちく)を撃たしむるに、未(いま)だ嘗(かつ)て善しと称せずんばあらず。稍(ようや)く益(ます)ますこれに近づく。高漸離(こうぜんり)、乃(すなわ)ち鉛を以(も)って筑(ちく)の中に置き、復(ま)た進みて近づくを得しとき、筑(ちく)を挙げて秦(しん)の皇帝を朴(う)つ。中(あた)らず。是(ここ)において、遂(つ)に高漸離(こうぜんり)を誅(ちゅう)す。終身、復(ま)た諸侯の人を近づけず。
[口語訳]だが皇帝はその筑の腕を惜しんで殺すに忍びず、死罪を許して目をつぶした。そうして筑を弾かせるたびに、いつもその芸に感嘆し、次第にかれを近づけて行った。そこで高漸離(こうぜんり)は鉛の塊を筑(ちく)の中に入れて置き、また近づく折を得しとき、筑を振り上げ皇帝に打ってかかった。当たらなかった。
皇帝はついに高漸離を死刑に処した。
それ以後、二度と他国(よそ)者を身辺に近づけなかった。
■『山海経』の文章の別の読み方
さきに、『山海経』のなかにある「蓋国在鉅燕南倭北倭属燕」の読み方として、つぎのようなものを示した、
「蓋国(がいこく)は鉅燕(きょえん)の南、倭の北にあり、倭は燕に属す。」
現代中国の学者たちも、このように読んでいる。これは、スタンダードな読み方である。ただし、中国の学者のこの部分の読み方は、現代日本人の学者の標準的な読み方の影響をうけているかもしれない。
『山海経』のさきの文章については、別の読み方も成立しうる。
別の読み方が、江戸時代中期の国学者、松下見林(まつしたけんりん)[1637~1704]の著書『異称日本伝』のなかにみえる。
『異称日本伝』は、おもに、中国の諸書のなかの日本に関する記事をあつめて編集した本である。
その『異称日本伝』の冒頭で、松下見林は『山海経』の文章を紹介している。
松下見林はつぎのように読んでいる。
「南倭北倭属燕」(右下の図参照)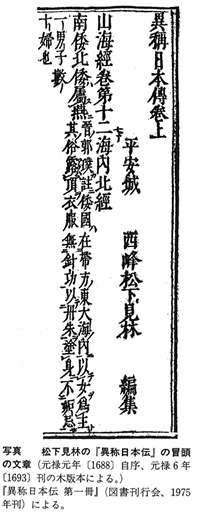
すなわち、さきの文章は、つぎのように読むべきだとしている。
「蓋国は鉅燕にあり。南倭北倭は燕に属す。」
この読み方でも、倭が燕に属していることには、変わりがない。
ただ、「南倭北倭」とは、なんだろう。
ひとつの解釈として、つぎのような考え方がなりたつ。
前に示した地図(「三国志」の「東夷伝」による諸民族の地理的位置)をご覧いただきたい。この地図は、朝鮮古代史の専門家、井上秀雄(東北大学名誉教授)が示しているものである。
この地図をみればわかように、『三国志』の時代、朝鮮半島の南部にも、「倭」はいた。これが古代的状況であるとしよう。すると、
「南倭北倭」
は、海の北の「倭」も、海の南の「倭」も、の意味に理解することができる。
『三国志』の「東沃沮(とうよくそ)伝」には、
「東沃沮(とうよくそ)は高句麗の蓋馬大山(がいまたいざん)の東に在(あ)り。」
なお、「蓋国在鉅燕」の「蓋」は「けだし」「おもうに」「全体を大まかに考えると」の意味もある。したがって、「蓋国在鉅燕」は「大まかに考えると、国(くにぐに)で、鉅燕にあるのは、……(以下、倭のこと、朝鮮のことなどを記す。)」の意味にとれないこともないように思う。「国」には、むかしは、「諸侯などの領地」の意味があった。
■倭は、「江南の呉から来た」という伝承をもっていた
中国の春秋・戦国時代(紀元前770~紀元前221)に、揚子江の河口地方を領有した呉と、呉の南の越とが争う(下の地図参照)。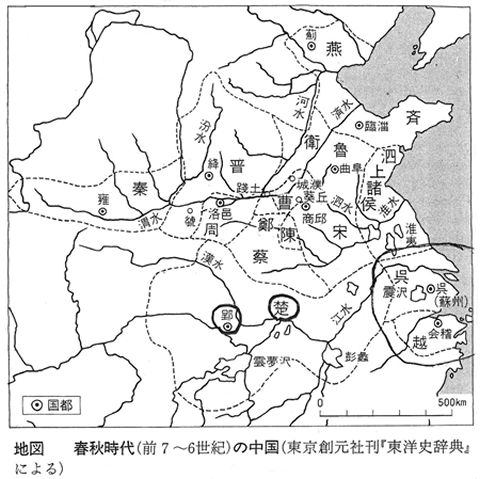
呉と越とは、江南地方にあった最初の国である。
越王句践(こうせん)(?~紀元前465)と、呉王夫差(ふさ)(在位紀元前496~紀元前473)との戦いは、有名である。
紀元前473年に、呉が越に滅ばされ、紀元前334年に、越が楚に滅ぼされた。
『魏志倭人伝』に、
「夏后(王)少康の子、会稽に封じられ、断髪文身(頭をそり、いれずみをする)してもって蛟竜の害を避く。今、倭の水人、好んで沈没し、魚蛤(ぎょこう)を捕う。文身し、またもって大魚水禽を厭(はら)う。のちややもって飾りとなす。諸国の文身おのおの異なり、あるいは左にし、あるいは右にし、あるいは大きく、あるいは小さく、尊卑により差あり。その道里を計るに、会稽(郡)東冶(とうや)(県)の東にあたる。」
と記されている。
この文にみえる会稽の地は、越の本拠地であった。
つまり、この文は、越の習俗と、倭の習俗とが似ていることをのべている。
また、越と戦った呉は、周の文王の伯父、太王の子の太伯(泰伯)と仲雍(ちゅうよう)とが建てた国であるという。周の太王の長子太伯と次子仲雍は、末子の季歴(王季)に継承権をゆずり、南に行って呉を建てた。
『論語』の「泰伯(たいはく)篇」には、呉の泰伯は、最高の人格者である、周の王朝の世継ぎの天子となるのを嫌って、その地位を弟季歴にゆずった、と記されている。
司馬遷の『史記』の、「呉太伯世家(せいか)」には、つぎのように記されている。
「ここにおいて、太伯とその弟の仲雍の二人は、荊蛮(けいばん)にはしり、文身断髪して、用うべからざるを示し(後継者として適切でないことを証明し)、もって末弟の季歴を避けた。」
太伯と仲雍が呉を建てたというのは、後世に付会された伝説であるともいわれるが、最近は、金石文などの研究により、一概に伝説とばかりいえないとの説も説かれている(平凡社刊『アジア歴史事典』)。
呉は、春秋時代、第十九代の王(太伯を第一代、仲雍を第二代とする)の寿夢(在位紀元前585~紀元前561)に至って強大となり、呉王と称して、楚に対抗し、寿夢の孫の闔閭(こうりょ)(廬)のときに、多年の敵である楚を打破して、その都の郢(えい)を陥れたが、のち越王勾践のために闔閭は敗死した(紀元前496年)。
呉の住民も、入墨・断髪の風習をもっていた。
儒教の古典『春秋穀梁(こくりょう)伝』の哀公(あいこう)十三年の条に、つぎのようにある。
「呉は夷狄(いてき)の国なり。髪を祝(た)ちて身に文(あや)す。」
現在、福岡県太宰府市の、大宰府天満宮に伝来する張楚金(ちょうそきん)撰、雍公叡(ようこうえい)注の『翰苑』がある。
平安初期の九世紀に書写され、そのまま今日に伝来したものである。
現存する『三国志』の版本の最古のものは、十二世紀のものである。『翰苑』の書写された時期は、それよりも古い。
その『翰苑』には、
「(倭人は、)文身黥面して、なお太伯の苗(びょう)と称す。」
とある。
また、『魏略』を引用して、
「その俗、男子は皆黥面文身す。その旧語を聞くに、みずから太伯の後という」
と記す。すなわち、倭人と、呉の王朝とは、祖先を、同じくするというのである(下の「呉系図」参照)。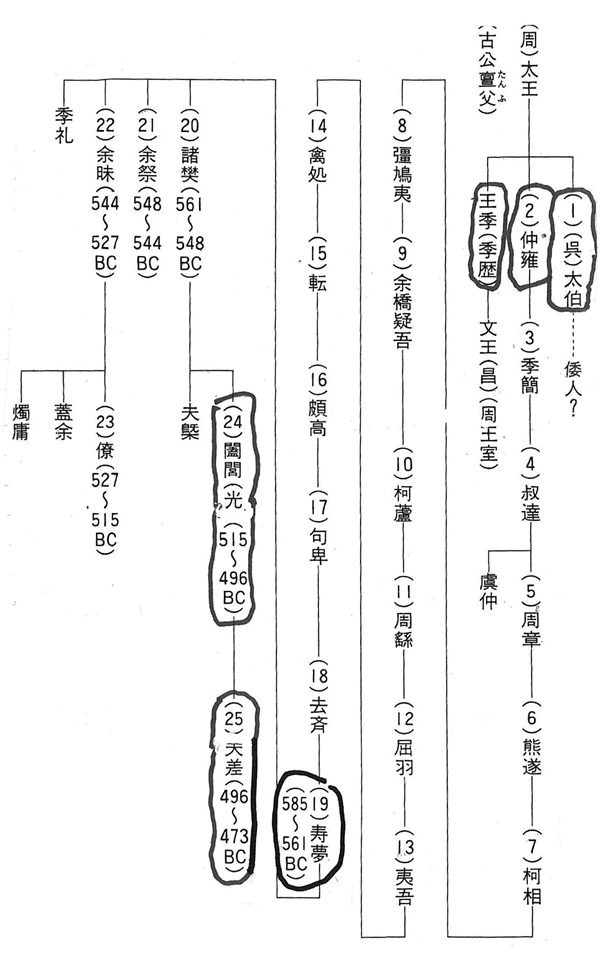
『魏略』は、『魏志倭人伝』の先行文献、または、同時代に成立した文献といわれている。
倭が、呉の太伯の子孫であるという記事は、他にいくつもの、中国の歴史書が記載している。つぎのとおりである。
「男子は大小となく、ことごとく黥面文身する。みずから太伯の後という。またいうには、『上古の使で、中国にいたるものは、みなみずから大夫と称した。むかし、夏の少康の子が、会稽に封じられ、断髪文身して蛟竜の害を避けた』と。いまの倭人は、好んで沈没して魚を取るが、また文身してもって水禽を厭(いと)わしめる。」(『晋書』「倭人伝」)
「倭はみずから太伯の後という。俗はみな文身する。」(『梁書』「倭伝」)
「俗はみな文身。みずから太伯の後という。」(『北史』「倭伝」)
宋の末、元の初めごろの歴史家、金仁山(1232~1303)は、『通鑑前編(つがんぜんぺん)』のなかで、つぎのように記している。
「日本いう。呉の太伯の後なりと。けだし呉亡んで、その支庶(ししょ)[傍流]、海に入って倭となる。」
なお、周は、姫姓であった。そのため、周からでた呉も姫姓であった。
『日本書紀』の平安時代の講義の筆記ノートである『日本書紀私記』に、「日本の国が、姫氏国と呼ばれるのはなぜなのか。」という質問がのってぃる。そのころ、日本が、中国から、太伯伝説にもとづいて、姫氏国と呼ばれていたことがわかる。
このようにみてくると、日本と呉越との関係は、考古学的にみても、あるいは、中国の歴史書をみても、深いものがあったといわなければならない。
呉の太伯は、西暦紀元前十二世紀ごろの人といわれている。呉の第十九代の王寿夢は、紀元前六世紀の人である。
いっぽう、わが国の稲作の起源は、紀元前十世紀のころまでさかのぼるという説がある。『魏志倭人伝』によれば、倭人は、「租賦(租税)」をおさめていたという。すなわち、税をとるシステムをもっていた。「税をとる」というアイデアじたいは、中国からきたものとみられる。
「税をとる」ことによって、王は、プロの軍隊を養うことができ、兵器を調達することができる。国家は、急速に強力となる。部族国家とは、異質のものとなりうる。
そのような「国家概念」をもった倭の為政者は、あるいは、伝承どおり、呉から来たという史的事実があったのかもしれない。
呉が越にほろぼされた西暦紀元前の473年のころは、村落共同体的な稲作集落が、ようやく国としてまとまる胎動をはじめたとしても、おかしくはない時期である。
■『後漢書』「倭伝」の記事
・朝鮮を滅ぼして・・・・・・前108年、漢の武帝は衛氏朝鮮を滅ぼし、その地に楽浪郡などの四郡を設置した。
倭(わ)は、韓(かん)の東南大海の中に在り、[倭人(わじん)は]山島に依(よ)りて居(すまい)を為(つく)る。
凡(およ)そ百余国なり。武帝の朝鮮(ちょうせん)を滅ぼしてより、使駅の漢(かん)に通ずる者、三十許(ばかり)の国ありて、国ごとに皆(みな)王と称(しょう)し、世世(よよ)統を伝う。其(そ)の大倭王(だいわおう)は邪馬台国(やまとこく)に居(すまい)す。
楽浪郡(らくろうぐん)の徼(きょう)は、其(そ)の国を去ること万二千里にして、其(そ)の西北界の、拘邪韓国(くやかんこく)を去ること七千余里なり。
『三国志』の『魏志』の「東夷伝」の「韓条」に、つぎのような文がある。
「韓(かん)は、帯方(郡)の南にあり。東西は海をもって限りとなし、南は、倭と接す。」
「その(弁辰の)と瀆盧(とくろ)国は倭と界を接す。」
この文は、韓が、南は、海をへだててではなく、陸つづきで、倭と接していたと、読みとれる文である。つまり、朝鮮半島南部に倭人が住んでいたことを示しているとみられる。前の方で示した朝鮮史学者の井上秀雄氏の手になる地図(「三国志」の「東夷伝」による諸民族の地理的位置)でも、金海あたりに倭がいたことになっている。
・『魏志倭人伝』の「狗邪韓国」記事
(帯方)郡から倭にいたるには、海岸にしたがって水行し、韓国(かんこく)(南鮮の三韓)をへて、あるときは南(行)し、あるときは東(行)し、倭からみて北岸の狗邪(くや)韓国(弁辰、十二か国の一つで、加羅すなわち金海付近)にいたる。
從郡至倭循海岸水行歴
韓國乍南乍東到其北岸
狗邪韓国
・『魏志韓伝』の記事
(弁辰の)国は鉄を出(いだ)し、韓(かん)・濊(わい)・倭(わ)皆(みな)従いて之(これ)を取る。諸々(もろもろ)の市買(しばい)には皆(みな)鉄を用い、中国の銭を用いるが如(ごと)くして、又(ま)た以(も)って二郡(にぐん)[帯方・楽浪郡]に供給す。
今、辰韓(しんかん)の男女は倭(わ)に近く、亦(ま)た文身(ぶんしん)す。
弁辰(べんしん)、辰韓(しんかん)と雑居し、亦(ま)た城郭有り。衣服居処は辰韓(しんかん)と同じ。言語・法俗相(あい)似たるも、鬼神(きしん)を司祭(しさい)するに異なる有り、竈(そう)を施(ほどこ)すに皆(みな)戸の西に在(あ)り。其の瀆廬国(とくろこく)は倭(わ)と界(さかい)を接す。
[口語訳]弁辰の国々は鉄を産出し、韓(かん)・濊(わい)・倭(わ)の人々はみなこの鉄を取っている。いろいろな商取引にはみな鉄を用い、中国で銅銭を用いるのと同じである。またこの鉄は帯方・楽浪の二郡にも供給されている。
辰韓の男女の風習は倭人のそれに近く、男女ともに入れ墨をしている。
弁辰は、辰韓の人と入りまじって生活している。また城郭がある。衣服や住居などは辰韓と同じである。言葉や生活の規律はお互いに似ているが、神の祭り方は違っている。竈(かまど)はみな家の西側につくっている。弁辰の瀆廬国(とくろこく)は倭(わ)と隣り合っている。
■狗邪韓国はどこか
狗邪韓国は、弁辰など十二ヵ国の一つである。『三国志』の「弁辰伝」に、弁辰の「狗邪国」とあるのは、狗邪韓国のことである。現在の慶尚南道の金海付近にあった。
朝鮮の歴史書『三国史記』では、「金官国」と記されている。また、『三国史記』にみえる「加耶(かや)国」の「加耶」も、「狗邪」に通じる。同じく朝鮮の歴史書である『三国遺事』では、「駕洛(からく)国」、『日本書紀』では、「南加羅」と記されている。
(下図はクリックすると大きくなります)
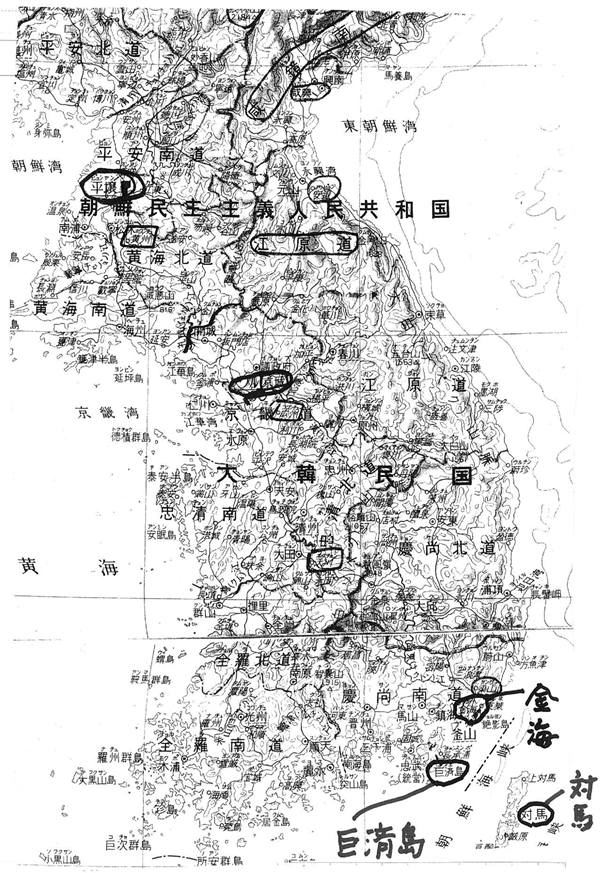
この狗邪韓国については、これを、倭の一国とみる説と、そうとは見ない説とがある。
(1)倭の一国とみる説
『後漢書』は、「其西北界狗邪韓国」と記し、狗邪韓国を倭の領域に属する国とみなしている。当時、朝鮮半島の南には、倭が住んでいた。狗邪韓国は、この倭の領域内にはいっていたとみる。『魏志倭人伝』には、「(中国または帯方郡と、)使者と通訳との通ずるところは、三十ヵ国」と記されている。そして、『魏志倭人伝』には、女王国に属する国として、二十九ヵ国の名があげられている。狗邪韓国を加えると、ちょうど三十国となり、「使者と通訳との通ずるところは、三十ヵ国」というのと、数があう。三十ヵ国は、通じていたからこそ、名が記されたのであると考える。『魏志倭人伝』には「(帯方)郡から倭にいたるには……」と記されており、帯方郡のあとに記されている狗邪韓国は、当然、倭のなかにはいると考える。(下の地図参照。このばあい、邪馬台国は三十ヵ国の代表として、他の二十九ヵ国の貢表もまとめたずさえて入貢したとみる)。
(下図はクリックすると大きくなります)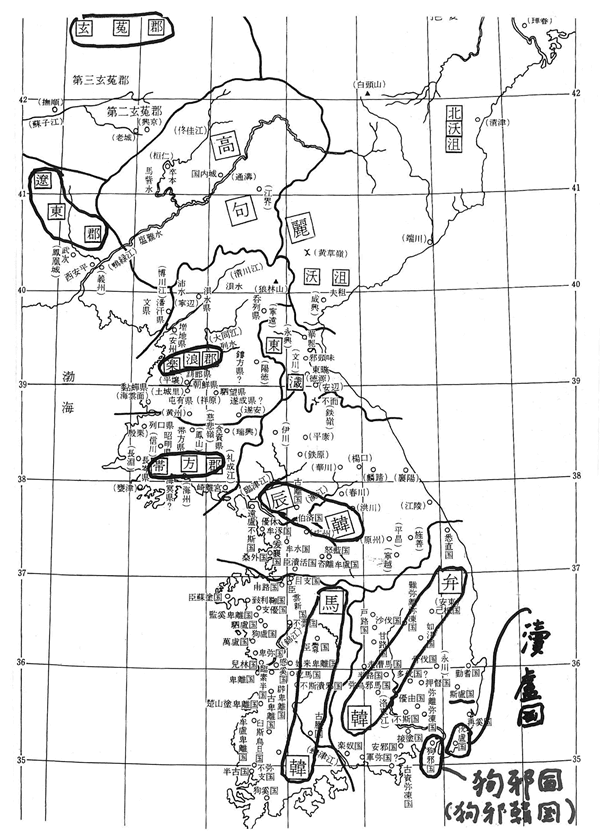
(2)倭の一国とはみない説
「狗邪韓国」と、国名に「韓国」という文字がはいっている以上、これは明らかに倭の国ではなく、韓の国である。『三国志』の「弁辰伝」に、「弁辰狗邪国」とあるのであるから、弁辰韓の一国と考えられる。当時、朝鮮半島の南に、倭が住んでいたとみる考え方には疑問がある。「使者と通訳との通ずるところは三十ヵ国」の「三十ヵ国」は、だいたいの数を記したともみられるし、あるいはまた、狗邪韓国を入れず、女王国に属さない狗奴国を入れて、「三十ヵ国」という意昧にもとれる。
さらにまた、通説では、邪馬台国に帰る倭の使は、狗邪韓国を通ったと考えるが、狗邪韓国を通らなかったとする説もある(張明澄など)。その根拠は、つぎのとおりである。
「朝鮮半島と対馬海峡との間の、朝鮮海峡は、かなり速い速度で、西から東へ流れている。金海付近まで行ってしまって、海を渡ろうとすると、船は大きく東に流されて、対馬につくことができない。現に、昭和五十年に、角川書店の主催で、古代船野性号で朝鮮海峡を渡ろうとしたが、船は東に流されて、人のこぐ力だけでは対馬につくことができず、母船に曳航してもらった。船はもっと西のほうの地点から出発し、潮の流れにのって、対馬に到着したはずである。
もともと、ここの原文は、藤堂明保などが、読み下しているように、つぎのように読むのが、中国文として自然である。
『[帯方(たいほう)郡(ぐん)従(よ)り倭(わ)に至るには、海岸に循(したが)いて水行し、(諸)韓国(かんこく)を歴(へ)て乍(たちま)ち南し、乍(たちま)ち東し、其(そ)の北岸狗邪韓国(くやかんこく)に到る。(郡より)七千余里にして、始めて一つの海を度(わた)り、千余にして対馬国に至る。』
すなわち、『七千余里』は、上の文の狗邪韓国にかかるのではなく、下の文にかかるのである。
帯方郡から七千余里いったところで、陸地をはなれて、海をわたったという意味である。『七千余里』は、帯方郡から、狗邪韓国までの距離を記しているのではない。狗邪韓国の名をここに記したのは、それが倭の一国なので、記したのであろう。狗邪韓国よりも西の、帯方郡から七千余里の地点から、海をわたったと考えるべきである。」
この、張明澄などの読み方は、現在、多数意見にはなっていないようであるが、一つの合理性のある見解といえるであろう。
ずっと後にできた『新元史』の「日本伝」は、つぎのように記す。
「巨済(きょさい)島に至り、はるかに対馬島を望んだが、大洋は万里、風と濤(なみ)とは、天を蹴っていた。」
魏の使も、巨済島から対馬に渡ったことが、十分考えられる。『魏志倭人伝』の、朝鮮半島から対馬へ至る記事には、方向が記されていない。朝鮮半島のかなり西のほうから、海流にのって対馬にわたったとみるほうが、自然であるようにも思える。
狗邪韓国が倭の一国であるかどうかは別として、狗邪韓国の付近に、倭人が住んでいたことは、『魏志』の「韓伝」および『後漢書』の「倭伝」の記事から、ほぼ確かといえるであろう。
■「倭国の極南界」とは、・・・・・
『後漢書』の「倭伝」につぎのような文がある。
建武中元(けんむちゅうげん)二年、倭(わ)の奴国(なこく)[の使者]、貢(みつぎ)を奉(ささ)げて朝賀す。使人は自(みずか)ら大夫(たいふ)と称(とな)う。[倭(わ)の奴国(なこく)は]倭国(わこく)の極南界なり。光武(こうぶ)は賜うに印綬(いんじゅ)を以(も)ってす。
[口語訳]
建武中元(けんむちゅうげん)二年(57年)、倭(わ)の奴国(なこく)の使者が、貢ぎ物を奉げて後漢(ごかん)の光武帝(こうぶてい)のもとに挨拶にきた。使者は大夫(たいふ)と自称した。倭の奴国は倭国の一番南の地である。光武帝は倭の奴国の王に、印章と下げひもを賜わった。
この「(倭の奴国は、)倭国の極南界なり。」という文の意味を考えてみよう。
後漢の時代は、わが国で、甕棺が行われていた時代にあたる。
『日本史総覧I 考古・古代(新人物往来社刊)に示されている出土地点の表にもとづいて、「細形・中細形の銅剣・銅矛・銅戈」の北九州での分布状況を示すと、下の地図のようになる。
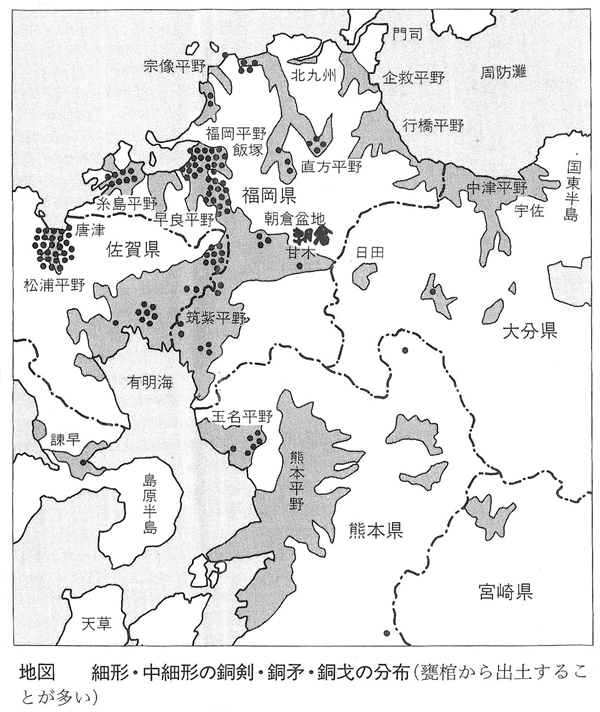
ただし、吉野ヶ里遺跡の甕棺から、三本の細形銅剣がでているので上の地図には、それも書き加えられている。
細形と中細形とをわけてグラフに書いても、銅剣と銅矛と銅戈とをわけてグラフに書いても、だいたいの傾向は、上の地図とそれほどかわらない。したがって、これらは、まとめてもよいものとみられる。
上の地図をみると、分布の中心は、唐津市を中心とする松浦平野と、福岡市を中心とする福岡平野である。
要するに、北九州の玄界灘がわの沿海地域である。
「細形・中細形の銅剣・銅矛・銅戈」は、しばしば、甕棺から出土している。
『後漢書』の記事、金印の出土、上の地図にみられる細形・中細形の銅剣・銅矛・銅戈の出土地点の分布、この三つは、たがいにおぎないあって、一世紀中葉ごろ、博多湾岸の倭人の国、奴国は、倭の国々の中心的地位をしめていたことをうかがわせる。
しかし、そのころ、倭人の国の中心的地域は、ここだけにあったのではない。
上の地図は、北九州における細形・中細形の銅剣・銅矛・銅戈の出土地点の分布を示している。
上の地図には、描かれていないが、出雲の荒神谷遺跡から、中細形銅剣が、358本出土している。この本数は、北九州から出土している銅剣の総数を上まわっている。
出雲にも、それなりの勢力があったことをうかがわせる。
そして、上の地図を、よくご覧いただきたい。もし、朝鮮半島方面から人がきたとすれば、その人は、唐津あたりの松浦平野をとおり、糸島平野をとおり、そして、奴国のあった福岡平野にいたったはずである。
この福岡平野こそが、当時、後漢などに知られていた倭の、地理的に最後の銅剣・銅矛・銅戈をつかう人々の密集地であった。
また、『魏志倭人伝』などを読めば、古代の中国人は、現代の地図でみられる実際よりも日本の地理を、やや、時計の針の逆回転方向にかたむけた形で、認識していたようである。
つまり、後漢の光武帝の時代、博多湾岸部に中心のあった「奴国」は、中国からは、順次人家の密集地をたどったさいの、「倭国の極南界」であると認識されていたとみられる。