この放送内容は、公共放送としては、あまりにも、基礎的な知識に欠け、非科学的、非学問的である。
■あまりにもひどすぎる内容
今年(2024年)の3月17日(日)NHKスペシャルで、「古代史ミステリー・邪馬台国の謎にせまる」が放映された。
それを見て、そのあまりのひどさにあきれた。あまりにも、基礎的な知識に欠け、非科学的、非学問的、独断的、矛盾だらけで、偏向している。到底公共放送の番組としては、ありえないような内容であった。かつて、旧石器捏造事件が起きたさい、読売新聞の記者であったジャーナリストの矢澤高太郎氏は、つぎのように述べている。
「新聞やテレビで大きく報道されることによって社会的な関心が高まり、遺跡の生命が守られたケースは多い。しかし、同時に弊害もまたさまざまな形で発生した。学者にとっては、地味な論文を発表する以前にマスコミで大々的に取り上げられるほうが知名度も高まり、学界内部での地位も保証される傾向が強まった。一部の学者や行政の発掘担当者はそれに気づき、狡知にたけたマスコミ誘導を行ってくるケースが多々見られるようになってきた。その傾向は、[旧石器捏造(ねつぞう)事件の]藤村(新一)氏以外には、考古学の。”本場”である奈良県を中心とする関西地方に極端に多い。そして、発表という形をとられると、新聞各社の内部にも何をおいても書かざるを得ないような自縄自縛(じじょうじばく)の状況が、いつの間にか出来上がってしまった。そんなマスコミの泣き所を突く誇大、過大な発表は、関西一帯では日常化してしまっている。藤村(新一)氏は『事実の捏造』だったが、私はそれを『解釈の捏造』と呼びたい。」(「旧石器発掘捏造”共犯者”の責任を問う」[『中央公論』2002年12月号])
「解釈の捏造」とは、言い得て妙である。要するに、「解釈(本人の主観的判断)にもとづくものであって、「事実」にもとづくものではない。フェイクニュースの類である。
「かすったら畿内説、風が吹いたら邪馬台国」ということばがある。
今回の放映は、おもにそのような「解釈の捏造」にのったもので、「解釈の捏造」の総特集のような感がある。
東海大学教授(当時、徳島大学助教授)の考古学者、北條芳隆(ほうじょうよしたか)氏も述べている。
「いわゆる邪馬台国がらみでも、(旧石器捏造事件と)同じようなことが起こっている。」
「証明を抜きにして、仮説だけがどんどん上積みされており、マスコミもそれをそのまま報じている。」
今回の放映は、北條芳隆氏が、述べるような「証明を抜きに」した「仮説」の「宣伝」であって、「マスコミもそれをそのまま報じている」典型的な例である。失敗から何も学ばなければ、失敗は繰り返されることとなる。
北條芳隆氏はさらに述べている。
「近畿地方では、古い時期の古墳の発掘も多いが、邪馬台国畿内説が調査の大前提になっているために、遺物の解釈が非常に短絡的になってきている。考古学の学問性は今や、がけっ縁(ぷち)まで追いつめられている。」(『朝日新聞』2001年11月1日付夕刊)
朝日新聞記者、宮代栄一(みやしろえいいち)氏も、旧石器捏造事件に関連して述べている。
「わたしは、今回の事件(旧石器捏造事件)は、慣習と前例に頼り、職人芸的な調査や推論に次ぐ推論に頼ってきた、日本考古学界が陥った大きな落とし穴であると考える。
考古学は歴史を語る学問だと言いながら、わたしたちは『解釈』の方法を、理論としてシステムとして確立する作業を怠ってきた。そのつけが回ってきたのである。」
「このようなケースは旧石器時代に限らない。邪馬台国畿内説や、狗奴国の所在地論争をめぐって、恣意的な解釈や強引な主張、仮説に仮説を継ぐ議論がいかに平然と行なわれていることか。考古学の学問性は、じつは今や風前のともし火なのである。」(以上、「脆弱さを露呈した考古学---捏造発覚から1年に思う」『前期旧石器問題とその背景』[段木一行(だんぎかずゆき)監修、株式会社ミュゼ、2002年])
この文章の中で、宮代栄一氏は「狗奴国の所在地論争をめぐっても、恣意的な解釈や強引な主張、仮説に仮説を継ぐ議論」が「平然と行われている」と述べておられる。
そのような、恣意的、強引な主張、議論の代表的なものが「狗奴国東海説」である。
ところが今回の放映では、狗奴国についての議論で、その「狗奴国東海説」がメインに紹介されている。
新井白石以来の、正統な学説が、まったく紹介されない。
狗奴国問題についても、邪馬台国問題にしても大論争が行われているまっ最中なのに、一方のがわの見解を中心にして、番組制作を行ない、他方の側の見解をまったく、あるいはほとんどとりあげない。ということはどういうことなのかこれは公共放送とはいえない。受信料不払い運動が起きるのも、無理がない、と思えてくる。番組制作のレベルが低すぎる。
「狗奴国東海説」については、たとえば『季刊邪馬台国』139号(2020年刊)の総力特集「その南に狗奴国あり」においても、奈良県橿原考古学研究所の所員であった関川尚功(せきかわひさよし)氏による詳細な批判がのっている。
関川氏の議論の要点は次のようなものである。
(1)「狗奴国東海説」は、邪馬台国大和説が前提となっている(仮説の上に仮説の形になっている)。しかし、その大和説じたいが成り立たない。
(2)考古学的にみて、大和と東海地域とは、親和的であって、『魏志倭人伝』が記すような抗争関係が生じているということは考えがたい。
『季刊邪馬台国』の139号では、正統派の狗奴国説も紹介されているが、それは「狗奴国東海説」のような、「仮説」や「解釈」にもとづくものではなく、以下のような「事実」にもとづいている。
■正統派の「狗奴国説」
『魏志倭人伝』は記す。
「其(そ)の南に狗奴国(くなこく)有り。男子を王と為(な)す。其の官には狗古智卑狗(くこちひこ)有り、女王に属せず。」(その[女王国の]南には狗奴国(くなこく)がある。男を王としてくいる。その官には、狗古智卑狗(くこちひこ)がおり、女王には従属していない。)
「狗古智卑狗」は、新井白石をはじめ、すでに多くの人の説いているように、肥後の国に「菊池郡」があるので、「菊池彦」とみるのが、もっとも妥当である。
「菊池郡」は『和名抄』に、「久久知」と注がある。『延喜式』も、「くくち」と読んでいる。後世になまって、「きくち」となった(吉田東伍著『大日本地名辞書』)。
『日本書紀』の「神代上」にみえる「菊理媛」も「くくりひめ」と読むのがふつうである。
「狗古智卑狗」は、「万葉仮名の読み方」で、「くくちひ(甲)こ(甲)」と読むことができ、「菊池彦[くくちひ(甲)こ(甲)]」と、正確に合致する。
『古代地名大辞典』(角川書店刊)にのっている「くくち」(「きくち」を含む)の地名は、熊本県の「菊池(くくち)郡」と「菊池城(くくちのき)」の二つだけである。古代において、ありふれた地名とは、いえない。
ただし、吉田東吾著の、『大日本地名辞書』(冨山房刊)には、熊本県の「菊池郡」「菊池城」以外に、摂津の国河辺郡(かわのべぐん)[兵庫県]の地名として、「久久知(くくち)」をのせている。
熊本県の地名の方が、大地名である。
東京大学の教授であった古代史家、井上光貞は、その著『日本の歴史I神話から歴史へ』(中央公論社、1965年刊)の中で、次のように述べる。
「この狗奴(くな)国について白鳥(庫吉)氏は、『熊本、球磨(くま)川にその名を残す球磨地方であろう』とした。なぜならウミハラ(海原)がウナバラとなるように、マ行とナ行之は転訛(てんか)しやすいからである。球磨地方はさらに南方と合して『熊襲(くまそ)』の名で知られているが、この地方は筑後山門(やまと)郡のちょうど南にあたる。だから倭人伝をそのままにうけとって、博多方面から南に邪馬台国があり、その南に狗奴国があると読んでもよく筋が通るのである。」
マ行とナ行との転訛例としては、次のようなものがある。
食物の「ニラ」は古代は、「ミラ」といった。巻貝の「ニナ」も古代には、「ミナ」といった。「かいつぶり」のことは、「ミホドリ」とも、「ニホドリ」ともいう。
「任那」は、「ニンナ」と書いて、「ミマナ」と読む。「壬生」は、「ニンブ」と書いて、「ミブ」と読む。「壬生(みぶ)」の人たちは、皇子・皇女の扶養にあたる。
古代の郡名以上の大地名で、『魏志倭人伝』の記述に関連するとみられる「くま」と「くくち」との両方が、そろって存在している地域は、「肥後の国(熊本県)」以外に存在していない。(これは、「解釈」ではなく、「事実」である。)
「狗奴国=肥後熊本説」は、他の諸説にくらべ、文献学的、考古学的根拠を、もっとも多くあげることができ、可能性がもっとも大きい説であるといえる。
『魏志倭人伝』には、「女王国よりも北は、その戸数と道里を、略載することができる」と記されている。
戸数と道里を記されている国のなかに、「伊都国」がある。つまり、「伊都国」は、「女王国」の北にあったのである。
「伊都国」の地は、のちの「怡土(いと)郡」の地で、これは確実といってよい。
また、『魏志倭人伝』によれば、「女王国」の南に「狗奴国」があった。
「女王国」は「伊都国」の南。「狗奴国」の北にあったのである。
以上の、「伊都国」「女王国」「狗奴国」の三つの位置関係を地図上に示せば、下図のようになる。
(下図はクリックすると大きくなります)
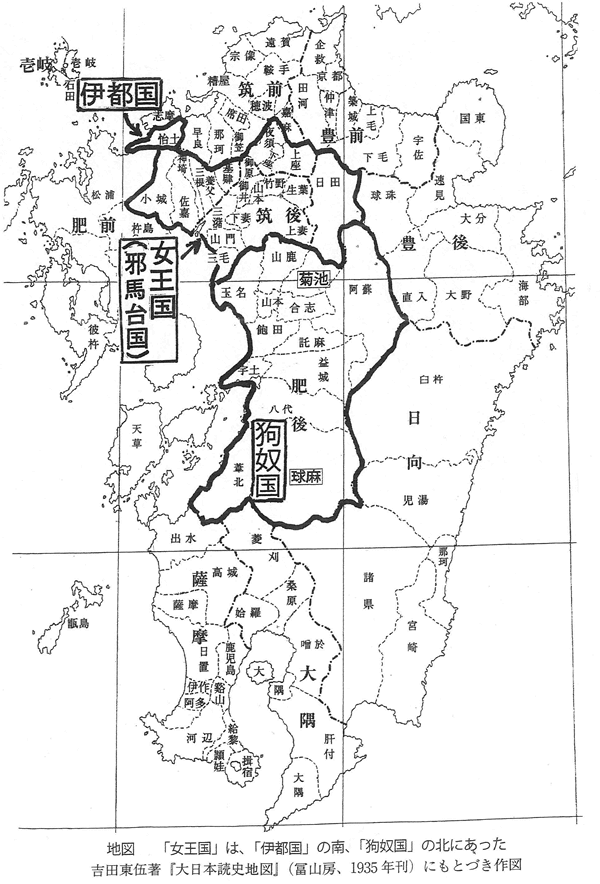
狗奴国は熊本県など九州南部にあったとする説は、江戸時代の新井白石以来、明治以後の白鳥庫吉(邪馬台国九州説)、内藤湖南(畿内説)、井上光貞(九州説)、小林行雄(畿内説)など歴代の碩学(せきがく)によって支持されてきた。正統派の説といってよいであろう。
正統派の説は、古典に通じた人なら誰もが思いつく自然な学説である。これに対して「狗奴国東海説」は奈良大学の教授などであった考古学者(文献学者ではない)の田辺昭三氏(1933~2006)によって1968年に『謎の女王卑弥呼』(徳間書店刊)の中で初めて提出された。
「邪馬台国大和説」を成立させるために案出された説と言える。
ある「仮説」が「定説」となりうるためには、いくつもの関所を越えなければならない。それが「証明」というものである。
『魏志倭人伝』に記されている「狗奴国」についての情報は限られているから。「狗古智卑狗」をどう考えるかは、一つの大きな関所であるはずである。
しかし、すでに見てきたように「狗奴国東海説」はこの関所を超えることができない。
しかし、「生活」の問題も関係している一群の考古学関係の方々は、別の方法で、この関所をパスしようとする。
すなわち、田辺氏の見解に賛成意見を表明し、それをマスコミに取り上げさせる方法である。そしてマスコミが取り上げたら、それが「証明」になると考える。
「狗奴国東海説」は「結論」が先にあって、その「結論」を成立させるために考え出された、いわゆる「論点先取」論法にもとづいている。「論点先取」は「証明法」としては、誤りとみなされているものの典型の一つのパターンである。
この説は、現代人の観念が生み出した説である。「空想説」といってよい。
このような論法を用いれば、狗奴国でも邪馬台国でも全国のほとんどどの地域にでももって行ける。しかし、田辺昭三氏のような議論に、利害関係をともなうすくなからざる考古学者達がのる。そして、あとはいかに宣伝合戦に持ち込むか、という話になる。そしてNHKものる。
はなはだ、非科学的、非学問的な話である。
「狗奴国東海説」と異なり正統派の説は、一つ一つ根拠(エビデンス)にもとづいてとなえられている説である。NHKの放映は、正統派の説を全く紹介せず、解釈捏造説といえるものに重点を置いて制作されている。
このようなことが起きるのは年間何百億円、年によっては一千億円を、ちょっと普通では考えられない膨大な資金が、緊急発掘費、調査費、研究費などとして、考古学の分野に流れ込んでいることが背景にある。それによって生活を立てる人の数も多くなり、資金を差配する考古学者たちが、大きな権限と、発言力とをもつようになった。
しかし、一方では国の経済が細くなり、重労働のゆえに、小学校や中学校の先生が不足するという事態も起きている。過去にこだわりすぎるあまり、わが国の未来が失われることがあってよいのだろうか。
マスコミは、数億円単位の自民党の政治資金パーティのことは、熱心に取り上げても、今後、大きな発掘があった場合に、情報がもらえなくなる可能性などの問題もあり、考古学者を批判しにくい雰囲気がある。
また、第二次大戦後、考古学関係の報道がニュースバリューを持つことが明らかになり、大学で考古学を学んだ人たちを記者として採用しているという事情もある。それらの記者は、身内の考古学関係の人たちの批判記事は書きにくい。
かくて本来は、学問的、科学的に議論をしなければならない問題が、選挙運動にも似たプロパガンダの対象となっている。また、地域おこしや研究者の生活など経済の問題もからむ問題となっている。
同志社大学の教授であった森浩一(1928~2013)は、述べている。
「ぼくはこれからも本当の学問は町人学者が生みだすだろうとみている。官僚学者からは本当の学問は生まれそうもない。」
「今日の政府がかかえる借金は、国立の研究所などに所属するすごい数の官僚学者の経費も原因となっているだろう。」(以上、『季刊邪馬台国』102号、梓書院、2009年)
「僕の理想では、学問研究は民間(町)人にまかせておけばよい。国家が各種の研究所などを作って、税金で雇った大勢の人を集めておくことは無駄である。そういう所に勤めていると、つい権威におぼれ、研究がおろそかになる。」(『森浩一の考古交友録』[朝日新聞出版、2013年])
これは率直にして、かつ、きわめて深刻な意見である。森浩一は、見聞きした経験にもとづく本音を述べている。
問題は、その官僚学者の生活の事も考えなければならない、ということがある。いっぽう官僚学者の自己保身にもとづくためにする発言にも、充分に気を付けなければならない。「狗奴国問題」は、簡明な事例なので、議論の状況を端的に示すものとなっている。
■残された遺物からは、・・・・・
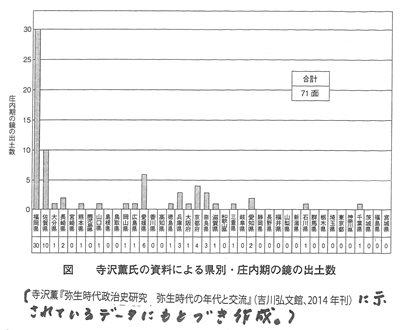 『魏志倭人伝』には、魏の皇帝が卑弥呼に銅鏡百枚や、五尺刀、絹製物を与えたとか、倭人は鉄の鏃(やじり)を用いるとか、卜骨を用いてうらないをするとか、絹製品を産出するとか、倭王は、白絹や勾玉(まがたま)の貢ぎ物をおくってきたとか、考古学的遺物を残しそうなものについての記述がいくつもある。
『魏志倭人伝』には、魏の皇帝が卑弥呼に銅鏡百枚や、五尺刀、絹製物を与えたとか、倭人は鉄の鏃(やじり)を用いるとか、卜骨を用いてうらないをするとか、絹製品を産出するとか、倭王は、白絹や勾玉(まがたま)の貢ぎ物をおくってきたとか、考古学的遺物を残しそうなものについての記述がいくつもある。
これらの遺物の出土状況から、邪馬台国の位置をさぐることができる。
いま、たとえば、近畿説の考古学者の寺沢薫氏の示すデータにより、邪馬台国の時代にあたるころの青銅鏡の都道府県別の出土数データを示せば、上図のようになる。(上図はクリックすると大きくなります)
福岡県からの出土数が、奈良県からの出土数に比べ、圧倒的に多いことがわかる。
また、弥生時代の鉄の鏃の、都道府県別の出土数データを示せば、下図のようになる。(下図はクリックすると大きくなります)
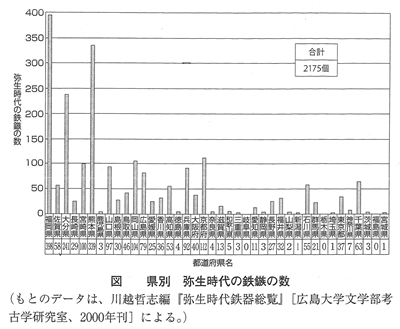
鉄の鏃の出土数は、福岡県が奈良県のおよそ百倍である。この図をよくご覧になられよ。
邪馬台国と狗奴国との戦いを反映するかのように、九州北部の福岡県と九州南部の熊本県とに、鉄の鏃の出土数がきわめて多い。
NHKの番組制作者は鉄の鏃のことや、女王国と狗奴国との戦いのことなどを取り上げながら、奈良県や東海地方からは、福岡県や熊本県の百分の一、あるいはそれ以下の鉄の鏃しか出土しないことを、番組制作者は知らないのであろうか。その矛盾に気が付かないのであろうか。
「邪馬台国畿内説」をとる考古学者の寺沢薫氏でさえ、比較的最近の著書『卑弥呼とヤマト王権』(中央公論新社、2023年刊)の中でつぎのようにのべている。
「(畿内説の鉄器出土量は)古墳時代の初めまで一貫して北部九州や中部九州の圧倒的な量におよばないことは一目瞭然だ。」
絹や勾玉などの出土状況も、鏡や鉄の鏃などと同様の傾向を示す。
絹について、考古学者の森浩一氏はその著『古代史の窓』(新潮文庫、1998年刊)のなかでつぎのようにのべている。
「ヤマタイ国奈良説をとなえる人が知らぬ顔をしている問題がある。(中略)
布目氏(布目順郎、京都工芸繊維大学名誉教授)の名著に『絹の東伝』(小学館)がある。目次をみると、『絹を出した遺跡の分布から邪馬台国の所在等を探る』の項目がある。簡単に言えば、弥生時代にかぎると、絹の出土しているのは福岡、佐賀、長崎の三県に集中し、前方後円墳の時代、つまり四世紀と、それ以降になると奈良や京都にも出土しはじめる事実を東伝と表現された。布目氏の結論はいうまでもなかろう。倭人伝の絹の記事に対応できるのは、北部九州であり、ヤマタイ国もそのなかに求めるべきだということである。この事実は論破しにくいので、つい知らぬ顔になるのだろう。」
以上のようなデータは、『魏志倭人伝』に記されている事物についての出土状況をみたものであって、研究者があらかじめもっている自説につごうのよいデータを集めたものではない。
また、これらは客観的なデータを示したものであって、研究者の主観的な判断を混えた解釈にもとづく「解釈捏造」の産物でもない。
このことの重要性が、プロパガンダに重点をおくある種の考古学関係の方々や、今回のNHKの番組制作者には理解できていないようである。
科学的探求のためには、客観的な根拠(エビデンス)を示す必要がある。
外部世界の客観的な事実に関する問題が、研究者の主観を混えた「解釈」のしかたしだいで解けると考えているところに、根本的な誤りがある。
何が「客観」で何が「主観」なのか、区別のつかない人たちが、声を大にして合唱しているのである。
旧石器捏造事件のときも、皆で間違えた。
■科学的な「証明」とは
京都大学大学院文学研究科准教授の大塚淳(おおつかじゅん)氏の手になる『統計学を哲学する』「名古屋大学出版会、2020年刊)というこの本の序章で、大塚氏は述べる。
「この本は何を目指しているのか。その目論見(もくろみ)を一言で表すとしたら、『データサイエンティストのための哲学入門、かつ哲学者のためのデータサイエンス入門』である。ここで『データサイエンス』とは、機械学習研究のような特定の学問分野を指すのではなく、データに棊づいて推論や判断を行う科学的/実践的活動全般を意図している。」
そして、さらに述べる。
「現代において統計学は、与えられたデータから科学的な結論を導き出す装置として、特権的な役割を担っている。良かれ悪しかれ、『科学的に証明された』ということは、『適切な統計的処理によって結論にお墨付きが与えられた』ということとほとんど同義なこととして扱われている。しかしなぜ、統計学はこのような特権的な機能を果たしうる(あるいは少なくとも、果たすと期待されている)のだろうか。
そこにはもちろん精密な数学的議論が関わっているのであるが、しかしなぜそもそもそうした数学的枠組みが科学的知識を正当化するのか、ということはすぐれて哲学的な問題であるし、また種々の統計的手法は、陰に陽にこうした哲学的直観をその土台に持っているのである。」
「例えば、ベイズ統計や検定理論などといった、各統計的手法の背後にある哲学的直観を押さえておくことは、それぞれの特性を把握し、それらを『腑に落とす』ための一助になるだろう。」
ここに、「ベイズ統計」の名がでてくる。
「ベイズの統計学」は、「原因の確率を求める統計」などとも言われる。
ふつうの確率論では、たとえば箱の中に赤、青、白などのいくつかの玉が入っていて、そこからとり出された玉についての確率を求める。2回続けて赤玉が出る確率はいくらかなど。
ところが「ベイズの統計学」では、話が逆で、いくつかの箱の中にそれぞれの何種類かの玉が、ある一定の割合ではいっていて、そこからとり出された玉の状況から見て、玉がどの箱から取り出された確率が大きいか、などを考える。不良品が出たばあいに、いくつかの工場のどの工場から出た可能性が大きいかなどの推定に用いることができる。
松原望氏(東京大学名誉教授)はわが国において、ベイズ統計学の第一人者といってよい方である。私は松原教授の指導を受けながら、松原教授とともに邪馬台国問題をベイズ統計学によって解くことを考えた。
松原教授は『文藝春秋』に乗せられた文章の中でのべておられる。
「統計学者が『鉄の鏃』の各県別の出土データを見ると、もう邪馬台国についての結論は出ています。畿内説を信じる人にとっては、『奈良県からも鉄の鏃が数個出ているじゃないか』と言いたい気持ちはわかります。しかし、そういう考え方は、科学的かつ客観的にデータを分析する方法ではありません。私たちは、確率的な考え方で日常生活をしています。
たとえば、雨が降る確率が『0.05%未満』なのに、長靴を履き、雨合羽を持って外出する人はいません」
「各県ごとに、弥生時代後期の遺跡から出土する『鏡』『鉄の鏃』『勾玉』『絹』の数を調べて、その出土する割合をかけあわせれば、県ごとに、邪馬台国が存在した可能性の確率を求めることが可能になります。その意味では、邪馬台国問題は、ベイズ統計学向きの問題なのです」(「邪馬台国を統計学で突き止めた」『文芸春秋』2013年11月号)
私も松原望教授との共同研究の成果をまとめ『データサイエンスが解く邪馬台国-北部九州説はゆるがない-』(朝日新書、朝日新聞出版、2021年刊)などの形で本にした。
結果をまとめれば、下表のようになる。
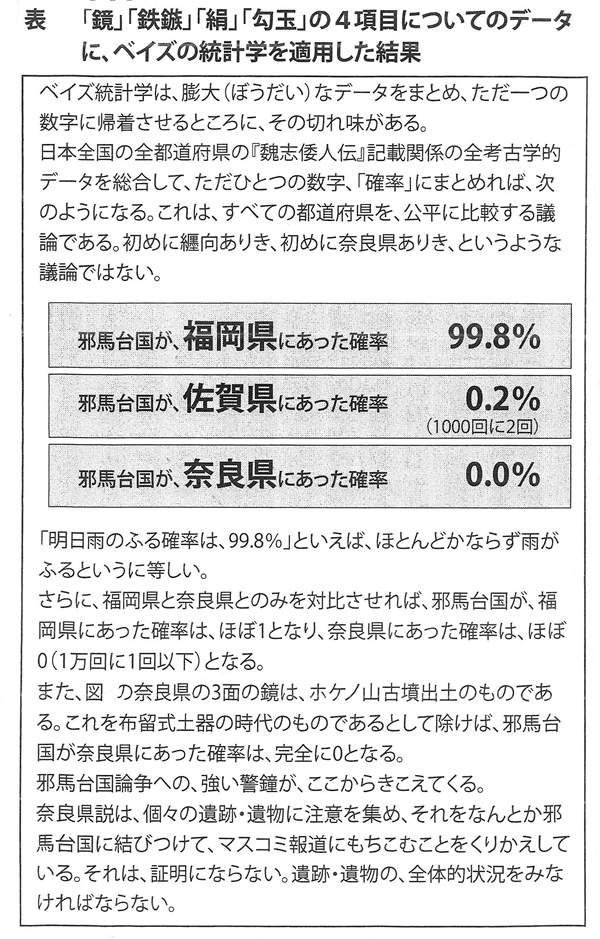
邪馬台国が北部九州にあった確率は百パーセント、奈良県にあった確率は、ほぼ完全に0(ゼロ)といってよい。
旧石器捏造事件を告発された竹岡俊樹氏も、最近刊行された本『考古学研究法』(雄山閣、2023年刊)において、邪馬台国九州説を述べておられる。
竹岡俊樹氏は旧石器捏造事件においても、邪馬台国問題においても、正しい判断を下されているようにみえる。
邪馬台国畿内説の方々は、不都合なデータを無視して自説のプロパガンダにふけるべきではない。
必要なのは、「宣伝」よりも、まず「証明」である。
何ごとによらず、ものごとに成功したり、上達したりすることの近道は、その道で成功したり上達したりしている人の方法のまねをすることである。
吉田兼好も、『徒然草』の中でのべている。
「先達(せんだつ)はあらまほしきことなり。」
邪馬台国が、九州にあったか機内にあったか、などのいわゆる「邪馬台国問題」は、古代史上最大の問題である。そしてそれは「証明」を必要とする問題である。
現在、諸科学、諸学問において、「証明」にもっともっとも成功しているのは「数学」である。
とすれば、「邪馬台国問題」も「数学」の方法によって解けばよいことになる。
「証明」は、数学によってもたらせる。そして、現代の数学は、データサイエンスの進展により、邪馬台国問題なども数学の応用問題としてとける段階に充分達している。
学者や研究者は、アメリカの大統領であったトランプ氏のように証明よりもプロパガンダを優先してはならない。政治は科学的成果にもとづいて行われるべきである。トランプ氏は疫学的根拠をもたないマスク無用説をのべ、多くの賛同者を得た。
だからといってそれでコロナに有効に対処できたことにはならない。マスク無用説によって、死者の数はふえたはずである。
旧石器捏造事件がおきたとき、人類学者で、国立科学博物館人類研究部長(東京大学大学院理学系生物科学専攻教授併任)の馬場悠男(ばばひさお)氏は、のべている。
「私たち理系のサイエンスをやっている者は、確率統計学などに基づいて『蓋然性が高い』というふうな判断をするわけです。偉い先生がこう言ったから『ああ、そうでございますか』ということではないのです。ある事実が、いろいろな証拠に基づいて100%ありそうか、50%か、60%かという判断を必ずします。どうも考古学の方はそういう判断に慣れていらっしゃらないので、たとえば一人の人が同じことを何回かやっても、それでいいのだろうと思ってしまいます。今回も、最初は変だと思ったけれども何度も同じような石器が出てくるので信用してしまったというようなことがありました。
これは私たち理系のサイエンスをやっている者からすると、まったく言語道断だということになります。」
「経験から見ると、国内外を問わず、何ヵ所もの自然堆積層から、同じ調査隊が、連続して前期中期旧石器を発掘することは、確率的にほとんどあり得ない(何兆分の1か?)ことは常識である。
だからこそ、私は、東北旧石器文化研究所の発掘に関しては、石器自体に対する疑問や出土状況に対する疑問を別にして、この点だけでも捏造と判断できると確信していたので、以前から、関係者の一部には忠告し、拙著『ホモ・サピエンスはとこから来たか』にも『物証』に重大な疑義があると指摘し、前・中期旧石器発見に関するコメントを求められるたびに、マスコミの多くにもその旨の意見を言ってきた。
しかし、残念ながら、誰もまともに採り上げようとしなかった。とくに、マスコミ関係者の、商売の邪魔をしてもらっては困るという態度には重大な責任がある。」(以上、春成秀爾編『検証・日本の前期旧石器』学生社、2001年)
東京大学名誉教授の医学者、黒木登志夫氏は、その著『研究不正』(中公新書、中央公論新社、2016年)で、12年に発覚した、ある麻酔科医のおこした一連の論文捏造事件こついて、次のように記す。
「学会とジャーナルは積極的に自浄能力を発揮した。特に、日本麻酔科学会の報告書は、今後のお手本になるだろう。」
そして、旧石器捏造事件については、次のように記す。
「日本考古学協会は、検証委員会を立ち上げたが、ねつ造を指摘した竹岡(俊樹)と角張(かくばり)[淳一(じゅんいち)]は検証委員会に呼ばれなかった。ねつ造発見の10日前に発行された岡村道雄の『縄文の生活誌』は、激しい批判にさらされ回収された。しかし、岡村は、責任をとることなく、奈良文化財研究所を経て2008年退官した。」
「SF(藤村新一)のねつ造を許したのは、学界の長老と官僚の権威であった。その権威のもとに、相互批判もなく、閉鎖的で透明性に欠けたコミュニティが形成された。」
この黒木登志夫氏の文中にでてくる竹岡俊樹氏は、かねてから、旧石器が捏造物であることを、告発していた。『毎日新聞』のスクープ記事が出るまえからである。しかし、考古学界の大勢は、それを無視しつづけていた。
竹岡氏は、事件発覚後、述べている。
「私がさらに情けないと思うのは、発覚の後の対応である。自らの行ってきた学問に対する反省はまったく行われなかった。藤村というアマチュアや、文化庁(岡村)に責任を押し付け、その上、批判する者を排除しつづけた。検証は名誉職が好きな『権威者』たちによるパフォーマンスにすぎず、生産的なことは何もおこなわれなかった。」
「この十年間待っていたが何も変わらなかった。」(『考古学崩壊』勉誠出版、2014年)
会社の不正を告発した社員を、会社が圧迫しつづけているのと同じような印象をうける。
旧石器捏造事件は、現在も、日本考古学の世界のある種の体質がどのようなものであるかについての「情報(シグナル)」を、世間に発信しつづけることになった。
それは、すなわち、次のような「情報(シグナル)」である。
「この考古学の世界では、エスタブリッシュメント(既成の権威、制度、組織)の、『組織の論理』のほうが、『科学や学問の論理』よりも強いのですよ。
まず守られなければならないのは、組織や伝統です。科学や学問的に真実と思われることを優先するのは、この世界の中で、組織人として生きて行く上で、政治的にも経済的にも、不利になることがありますよ。」
考古学の分野では、エスタブリッシュメントが存在し、そこでは、「組織人としての論理」のほうが、「科学者、学者としての論理」よりも強い。
考古学の世界の組織や文化が、大きな問題をもっていることを示している。
学問や科学の世界では、疑問のある見解に対しては、論理や証拠によって反論すべきである。組織の中で不利益をもたらしますよ、というシグナルを送って、口を封じようとすべきではない。
方法も空気も、前々世紀的なものがあるようである。
これでは、組織は守られても、学問は守られない。科学は守られない。
このような文化になれてしまうと、非合理を非合理と思えなくなってしまう。
徳川家康が言ったという「不自由を、常と思えば不足なし」ということばがあるが、「非合理も、常に習えば、慣れてくる」状況になる。正しいように思えてくる。慣れてしまえば、不合理な行動をとっていることも、わからなくなる。
失敗から学ばなければ、同じような事件が、くりかえされることとなる。
そして、それを、国立の大学の先生や、教育委員会などの研究者が行なえば、税金の無駄づかいとなる。
大きな失敗がおき、そのために無駄な大金が消費されても、だれも責任をとらないという体制ができているようにみえる。
考古学研究者も世間一般の人も、旧石器捏造事件は藤村新一氏の、個人的な性向から生じた事件のように考える傾向がある。
しかし、そうとばかりはいえない。藤村新一氏は、一部の考古学者やマスコミがどこかで望んでいたものを、そのご要望に合わせて出しつづけた、といえる面がある。
研究者やマスコミが、「もっと古いものを」「さらに古いものを」とおねだりするから、藤村新一氏は、そのご要望に応(こた)えつづけたのである。
ここまで古いものを出しても大丈夫なら、さらに古いものをという形になったのである。
古墳の築造年代をどんどん古くくり上げ、箸墓古墳を、三世紀の卑弥呼の墓にあてるなどというNHKの今回の放映なども、それと同じパターンとなっている。
同志社大学教授であった考古学者の森浩一氏は述べている。
「最近は年代が特に近畿の学者たちの年代が古いほうへ向かって一人歩きをしている傾向がある。」(『季刊邪馬台国』53号、1994年春号)
旧石器捏造事件のさい、『ネイチャー』誌は、「捏造された出土物は、批判の欠如をさし示す(Fake finds reveal critical deficiency)」という文章をのせ、「井の中の蛙、大海を知らず」という『荘子』にもとづく日本のことわざの英訳 "a frog in a well that is unaware of the ocean" を引用して、この事件を痛烈に批判している(Cyranoski,D.,Nature,Vol.408 2000年11月号)。
そこには、次のような文章がみえる。
「この(旧石器捏造事件の)話は、藤村新一が捏造作業をつづけるのを許した科学文化についての疑問をひきおこした。」
「日本では、人々を直接批判することは、むずかしい。なぜなら、批判は、個人攻撃とうけとられるからである。」
「直観が、ときおり、事実をこえて評価される。」
旧石器捏造事件は、日本の考古学界のある種の風土の問題の中から生じた事件といえる。
今回のNHK番組は、旧石器捏造事件から何も学ばず、日本考古学が、ふたたび、みたび、世界の笑いものとなる日を、はぐくんでいるようにみえる。
小畑峰太郎著『STAP細胞に群がった悪いヤッら』(新潮社、2014年)という本がある。
この本のなかに、北海道大学名誉教授の武田靖氏の、鋭くも的確な見解が、紹介されている。
武田靖氏は、STAP細胞騒動を、「科学系と技術系という本質的に相容れない二つの集団」「基本的に知識体系の異なる集団」の対抗の観点からみる。
武田靖氏と、小畑峰太郎氏は述べる。
「【武田】そこ(化学工学)では、科学に最も重要な『なぜ?』という内なる問いかけに、答えを見出すことが、ほとんど困難なのだ。その結果、『なぜ?』という問いかけすらしなくなり、ただひたすら実験を繰り返すことになる。(安本注 これと、ひたすら掘って、出てきたものを、正確に記録することを繰り返すことを基本とする考古学とを重ねてみよう。)
おそらく小保方は、そのように学んできたのだろう。つまり、『なぜ?』という問いかけをすることの重要性を学んでいない。
彼女の言い分を聞いていると、そうとしか思えない。実験を繰り返して、二〇〇回も実現できるようになっていれば、どういうパラメーター(媒介変数)の範囲でそれが実現されるかを考えるものだ。科学的な姿勢と発想を持っていれば、『なぜ』そうなのかを、当然考えてしかるべきなのである。
なぜそうなるかを考えていれば、もっと自信を持って説明できるはずなのだ。何も全てを分かる必要はなく、分かることと分からないことが、はっきりしていれば良いのである。
「【武田】小保方を擁護するとすれば、『技術者』ならば、それでも良いということだ。『なぜ』かが分からないとしても、確実に物が作れれば良いのであるから。安本注 考古学では、とにかく掘って結果を出せばよい。)」
「【小畑】今、日本の科学の世界では、そうした風潮が蔓延しているように思える。産業に結びつくための技術に偏した科学、あたかも結果を即座に出せるかのような。そこに利権と予算と拙速主義が集中して同居すると、必然的に今回のような捏造事件が起きてしまうのではないか。」
「【武田】科学と技術は、別の文化で、だから科学者と技術者は異なる人種なのだ。」
「【小畑】科学という学問、そして研究は、従事する者に対して、情け容赦ない苛烈な献身を要求する。『それでも地球は回る』と言ったガリレオの時代から、己が身を焼き尽くすような科学への憧憬と献身、自己犠牲が、科学者の栄光を保証し、彼らの名をその歴史に刻んできたのである。時代の変遷の中。科学を忘れた科学者がメイン・ストリームに立つようなことも、たとえ一時はあるにせよ、まかり間違っても、技術者が科学者に成り代わるような世は決して来ないのではないか。それを科学は許さないだろう。
技術者が自らの法(のり)を超えて、『科学者』として、科学の世界に一歩でも足を踏みこんだが最後、僭称者には手酷い復讐が待ち受けている。」
考古学は、基本的に、「技術」であり、邪馬台国の探究は、「科学」の問題なのであろうか。
わが国の考古学は、遺跡を発掘し、遺跡・遺物を記録するということでは、きわめて高い水準に達していることは確かである。しかし、その「技術力」を修練によって高めれば、古代はほんとうに見えてくるのか。
「技術」に力をそそぐあまり、「科学」のほうはおろそかになっているのではないか。
従来の方法を発展させて行くという進み方は、限界にきているのではないか。古代史像をつかもうとするばあいに、不正確で恣意的な「解釈」と、大幅な「空想」をともなうようになってきているようにみえる。
真実は「証明」によってもたらせる。「宣伝」や「プロパガンダ」やそれらによってもたらされる付和雷同によってはもたらされない。
今回のNHKの放映には、天下のNHKが放送すれば、泣く子も黙るであろうとの思い上がりがうかがわれる。番組制作者には、学者や研究者たちよりも、一段上にたって判断してもよいとの思い上がりである。
科学を志すものは、ガリレオ以来の伝統にならって立つべきである。発言すべきである。
敵はいかに大敵であろうと、現代において、ガリレオのようなひどい目にあうことはありえない。
■「卑弥呼の墓=箸墓古墳説」について
今回のNHK放映において、「卑弥呼の墓=箸墓古墳説」が大々的にとりあげられていた。
しかし、奈良県の箸墓古墳が卑弥呼の墓であるとする説には、相当以上の無理がある。
すでに東京大学の考古学者斎藤忠氏や、奈良県立橿原考古学研究所の所員であった関川尚功氏は、「箸墓古墳は4世紀中ごろ以後に築造されたものであること」を根拠を挙げてのべている。
卑弥呼の死後、百年程度はたってから築造されたとみられる古墳である。
邪馬台国畿内説の立場に立つ考古学者寺沢薫氏によれば、奈良県の「ホケノ山古墳」は庄内様式期の築造とされている。布留0式期に築造箸墓古墳はホケノ山古墳よりもあとの時期に築造されたことになる。
ところで、奈良県立橿原考古学研究所編集および発行の『ホケノ山古墳の研究』(2008年刊)という報告書がある。
『ホケノ山古墳の研究』には、12年輪の小枝試料についての炭素14年代測定値の結果がのっている。
この試料は、相当に注意深く選ばれ、「(試料として、)有効であろうと考えられる」と記されている。
その小枝試料の西暦年数推定値の代表値、中央値(メディアン)は、西暦364年であった。ここからは、箸墓古墳の築造年代は西暦364年ごろ以後となる。
『日本書紀』は、箸墓古墳を第10代崇神天皇の時代に、倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)の墓として築造されたものとし、その築造の状況を記している。
西暦800年以前の存在と在位年数とが確実な諸天皇の平均在位年数は、およそ300年間の期間にわたって約十年である。
同時期の中国の皇帝・王たちの在位年数も約十年である。
このようなデータにもづき、何人かの統計学の専門家たちが、古代の諸天皇などの、活躍年代などを推定している。
このような文献に記されたデータにもとづく数理統計学的年代論によれば、崇神天皇の活躍年代の推定値の平均値は、西暦368年である。この値は先のホケノ山古墳の築造年代の、炭素14年代法による推定値の西暦年の代表値364年と、わずか4年しか異ならない。
このように、斉藤忠氏、関川尚功氏などの考古学者の見解、文献史料にもとづく数理統計学的年代論にもとづく推定値、炭素14年代法による推定値などが、ほぼよく一致しているのである。
旧石器捏造事件の告発者、竹岡俊樹氏は先に紹介した著書『考古学研究法』の中で、まず関川尚功氏の見解を紹介する。
「ホケノ山古墳をどうしてもみんな古く古くしたがるのですが、いくら古くしようと思っても、ホケノ山古墳には布留1式というくびきが掛かっているわけです。(安本注。ホケノ山古墳からは、布留式土器の指標とされる小型丸底土器が出土している)これ以上はもう古くはできません。・・・・それを動かそうとしたら、それは考古学ではなくなりますから。
そういう考古学の編年の基本原則というのは、やはり、きっちりしておかなければいけないと思います。」
その上で竹岡俊樹氏は述べる。
「高島(忠平)も布留1式に出現する小型丸底壺が出土していることから、ホケノ山古墳は4世紀後半のものであるとしている。小枝の年代と合致する。」
竹岡俊樹氏は、今回も事態を正確にとらえておられるように見える。
ホケノ山古墳の築造年代が4世紀の後半なら、箸墓古墳の築造年代も4世紀後半ということになる。
以上のような議論の根拠は『季刊邪馬台国』(144号2024年1月刊)所載の拙稿に、データを示して述べられている。
なお、炭素14年代法、年輪年代法。酸素同位体比年輪年代法などの自然科学的方法を用いたものであるばあい、たとえば、木材試料のばあい、再利用問題などを、クリアする必要などがある。
木材はしばしば再利用されることがある。そのため、年代が古く出がちである。
箸墓古墳の出土物のばあいでも、炭素14年代測定法で、ヒノキ材で測れば、年代推定値(中央値、メディアン)で、西暦紀元前116年という年代が得られる。桃の種(核)で計れば4世紀の年代が得られる。ヒノキは堅牢なので、再利用され、年代がいちじるしく古く出ることが多い。
ホケノ山古墳のばあい、試料として、小枝を選でいるのは、再利用の可能性などをさけるためである。
年代を古くした方が、ニュースバリューを生ずるので、考古学者もマスコミも「年代を古くしたがる病」にかかりやすい。
旧石器捏造事件のときもそうであった。今回もまたそうである。
新しい説が正しいとはかぎらない。新説がたんに空想や捏造の発展型であることもあるのだ。
これまでの「解釈捏造説」でも、マスコミも支持してくれて通ると思えば、やがて要望にこたえてもっと誇大な「解釈捏造説」が登場してくる。
そのくりかえしのはてには、旧石器捏造事件のような大破綻が待ちうけている。
ここらへんで少し歯止めをかけるべきではないか。しらずしらずのうちに、捏造者の共犯者になることは、発表する無責任な考古学者とマスコミとは利益を得ても、国費の浪費となり、社会に迷惑をかけることになるのだ。大きな失敗から少しは、学んではどうか。







