■前回までの説明の主要ポイントの整理
●「年代」は、歴史を構成する脊柱(せきちゅう)である●
歴史上のことを考えるさいに、「年代」が必要であることは、地図に、緯度や経度が必要であるのにも似ている。
たとえば、第十代の崇神天皇は、実在の人であるとして、いつごろの人なのか。ある事件がおきたのは、いつなのか。ある遺跡や遺物は、いつつくられたものなのか。
「年代」は、歴史を構成する脊柱(せきちゅう)である。
「歴史を構成する」とは、天皇や事件、遺跡、遺物を、「年代」という太い一次元の座標軸上に、統一的に位置づける作業であるともいえる。
しかし、人間は、なかなかリアルに、「年代」を把握することができない。
古い時代の年代は、客観的な真実の年代よりも、より古く考えがちであるという無意識の傾向をもつ。
このような傾向があるということじたいを、強く意識化し、たえず用心する必要がある。このような無意識の傾向あるいは欲求を「年代延長欲求」と名づけよう。「年代延長欲求」じたいが、しばしば、日本古代史混迷の元凶(げんきょう)となっている。共同体がもつ幻想の源(みなもと)となっている。
旧石器捏造事件のさいは、五十万年、七十万年と、年代がくりあがっていっても、専門家も、ふしぎと思わなかった。専門家も、マスコミも、夢のような「年代」にひきずられていった。そのような年代が、教科書にものった。
『日本書紀』の記す古代の年代は、大はばに延長されている。しかし、第二次世界大戦がおわるまで、千年以上のあいだ、『日本書紀』の記す年代が、基本的には信じられていた。
第二次世界大戦以前には、『日本書紀』の記す年月日にもとづいて、「紀元節」が祝日として定められていた。
現代の古代史や、考古学の年代も、ともすれば古いほうへ、古いほうへとなびきがちになっていないか。
科学的年代論の示す結果との「くいちがい」が、大きくなっていないか。そのような「くいちがい」を「年代延長欲求」によって、無意識のうちに無視したり、見おとしたりしていないか。
年代のばあい、多数意見のように見えるものに、不用意にしたがうのは、しばしばまちがいのもとである。
「年代」をリアルに把握するには、「年代延長欲求」じたいを意識化し、「客観化」を教える現代諸科学や方法も援用して考える必要がある。
「年代」という太い座標軸そのものをしっかりと定める必要がある。
「年代」は、私たちの外部世界の客観的実在として存在したと考えられる。それは、「客観的存在」を探究するのにふさわしい言語である「数字」「数学」によって探究されることが望ましい。
天皇の平均治世年数などにもとづく古代年代論を、はじめて、系統的に論じたのは、明治時代の那珂通世(なかみちよ)[1851~1908]であった。

注:【那珂通世(なかみちよ)】(1851~1908)明治時代の東洋史学者。嘉永(かえい)4年1月6日生まれ。藤村操の叔父。陸奥(むつ)盛岡藩士の子。那珂通高(みちたか)[梧楼(ごろう)]の養子となる。千葉師範校長などをつとめ、明治27年高等師範教授。日本で最初に「東洋史」の名称をつかい、日本の紀元問題の研究でも知られる。明治41年3月2日死去。58歳。慶応義塾卒。本姓は藤村。著作に「支那通史」「那珂東洋小史」
那珂通世は、東洋史学者である。
日本で、最初に「東洋史」の名称を用いた。
那珂通世の『上世年紀考』は、科学的年代論の幕あけをつげるものであった。三品彰英(みしなあきひで)[1902~1971]によれば、「(那珂)博士のこの優れた論説(『上世年紀考』など)は当時年なお若き明治の学界に一大反響を呼び、一時この道の学徒にして年代論を口にせざるものなき活況を呈した」という。
明治という時代を考えるとき、那珂通世はおそるべき知性のもち主であった。その論考は、その後長く、強い影響を残した。
那珂通世は、『日本書紀』の記す神武天皇の時代などは、660年ほどの、年代の延長がある、とのべた。
■「代数」と「世数」
コラム1 世数と代数
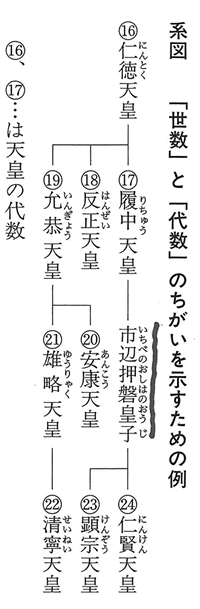 古代の天皇の活躍年代(あるいは、即位年代、在位年代など)を推定しようとするばあい、天皇の「代数」を基本的な変数(独立変数)と考える立場と、天皇の「世数」を基本的な変数と考える立場とがある。
古代の天皇の活躍年代(あるいは、即位年代、在位年代など)を推定しようとするばあい、天皇の「代数」を基本的な変数(独立変数)と考える立場と、天皇の「世数」を基本的な変数と考える立場とがある。
たとえば、右の系図のようなばあい、第24代仁賢天皇は、第16代仁徳天皇から数えて「8代目」の天皇である。しかし、世数からいえば、「3世目」の天皇である。「世数」では、親子関係によって、何世目かを数えるわけである。
そもそも、那珂通世の年代論は、基本的に「世数」情報によるものである。
「代数」と「世数」とは、どうちがうか。コラム1にその違いを記した。
現代でも、たとえば、宝賀寿男(ほうがとしお)氏は、『神武東征の原像』(青垣出版、2006年刊)や中川八洋氏の『神武天皇実在論』(ヒカルランド、2023年刊)などで、世数情報にもとづく年代論を展開しておられる。
しかし、私は「世数」情報によって、古代の天皇の活躍年代を推定することには、賛同できないでいる。
それは、以下にのべるような理由にもとづく。
(1)代数情報よりも、世数情報のほうが信用できるとは思えない。たとえば、古代の百済の王系のばあいでも、王の代数情報については、『日本書紀』と、朝鮮の史書『三国史記』とで、伝えるところが一致している。しかし、王の系譜の父子関係、兄弟関係などは、『三国史記』と『日本書紀』とで、かなり異なっている(下の系図参照)。時代の古いところで、その異なりは大きい。
たとえば、第21代蓋鹵王(こうろおう)と第22代文周王(もんすおう)との関係は、『日本書紀』では、兄弟関係になっている。しかし、『三国史記』では、親子関係になっている。そして、どちらのほうが、より信頼できるかについてのキメテがない。
『日本書紀』によるとき、第二十代毗有王(ひゆうおう)の四世目(父子関係で、四世代目)の孫が、第二十七代威徳王(いとくおう)である。いっぽう、『三国史記』によるとき、第二十代毗有王の六世目の孫が、第二十七代威徳王である。
王の代数は『日本書紀』も『三国史記』も、威徳王は毗有王から数えて、同じく七代目で一致している。
しかし、世数は四世目と六世目とで異なっている。
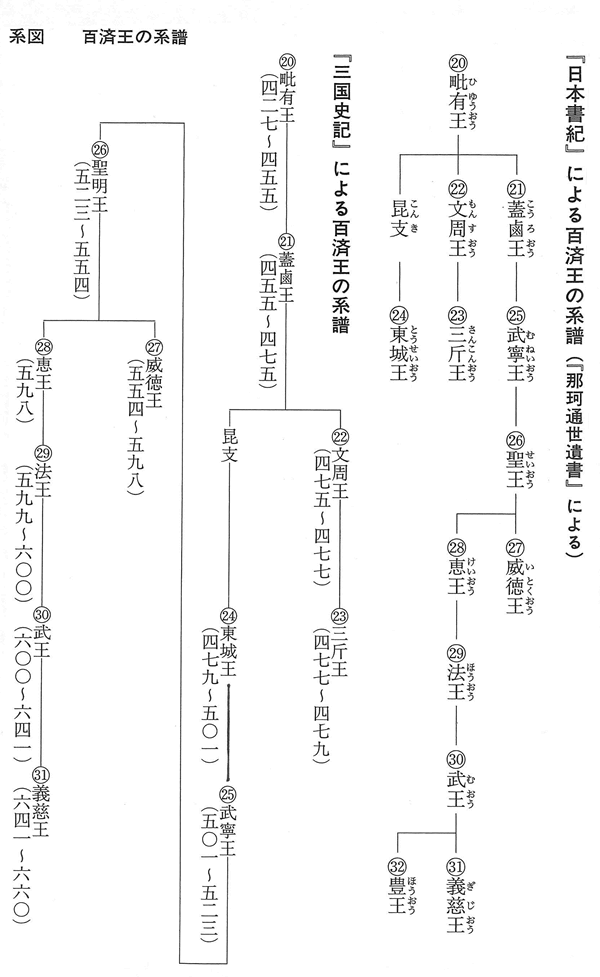
しかも、『日本書紀』と『三国史記』とは、それぞれ文献としての長所をもっている。すなわち、つぎのとおりである。
(a)『日本書紀』の成立は、720年である。『三国史記』の成立は、1145年である。『日本書紀』のほうが、『三国史記』よりも、400年以上はやく成立している。すなわち、古い情報をとどめている可能性が大きい。
(b)『三国史記』は、地元の朝鮮で成立した文献である。外国の史書『日本書紀』の記事よりも、伝聞的要素が少ないはずである。伝えられた資料も、多かったはずである。
このように、世数情報(父子関係情報)は、あやふやであるが、王の代数情報は、よりよく伝えられているようにみえる。
すでに、慶応大学の教授であった橋本増吉は、大著『東洋史上よりみたる日本上古史研究』(東洋文庫、1956年刊)のなかで、つぎのようにのべている。
「父子直系のばあいの一世平均年数が、ほぼ二十五、六年ないし三十年前後であることは、那珂博士の論じられたとおりであろうけれども、わが上代のおよその紀年を知るために必要なのは、父子直系の一世平均年数ではなく、歴代天皇のご在位年数なのであるから、那珂博士算出の平均一世年数をもって、ただちに上代の諸天皇の御在位平均年数として利用すべきでないことは、明白なところである。」
また、あとで紹介する笠井新也は、つぎのようにのべている。これは、世代数に対する疑問をのべたもので、那珂通世の議論の、基本的前提じたいを否定しているものである。
「わが国の古代における皇位継承の状態を観察すると、神武天皇から仁徳天皇にいたるまでの十六代の間は、ほとんど全部父から子へ、子から孫へと垂直的に継承されたことになっている。しかし、このようなことは、私の大いに疑問とするところである。なぜならば、わが国において史実が正確に記載し始められた仁徳以後の歴史、とくに奈良朝以前の時代においては、皇位は、多くのばあい、兄から弟へ、弟からつぎの弟へと、水平的に伝えられているからである、かの仁徳天皇の三皇子が、履中(りちゅう)・反正(はんぜい)・允恭(いんぎょう)と順次水平に皇位を伝え、継体天皇の三皇子が、安閑(あんかん)・宣化(せんか)・欽明(きんめい)と同じく水平に伝え、欽明天皇の三皇子・一皇女の四兄弟妹が、敏達(びたつ)・用明・崇悛(すしゅん)・推古と同じく水平に伝えたがごときは、その著しい例である。したがって、この事実を基礎として考えるときは、仁徳天皇以前における継承が、単純に、ほとんど一直線に垂下したものとは、容易に信じがたいのである。」
山路愛山(やまじあいざん)は、その力作『日本国史草稿』において、このことに論及し、『直系の親子が縦の線のごとく相次いで世をうけるのは、中国式であって、古(いにしえ)の日本式ではない』。それは、『信ずべき歴史が日本に始った履中天皇以後の皇位継承の例を見ればすぐわかる』『仁徳天皇から天武天皇まで通計二十三例のあいだに、父から子、子から孫と三代のあいだ、直系で縦線に皇位の伝った中国式のものは一つもなく、たいてい同母の兄弟、時としては異母の兄弟のあいだに横線に伝って行く』『もし父子あいつづいて縱に世系の伝って行く中国式が古(いにしえ)の皇位継承の例ならば、信ずべき歴史が始ってからの二十三帝が、ことごとくその様式に従わないのは、誠に異常なことと言わなければならない。ゆえに私達は、信ずべき歴史の始まらないまえの諸帝も、やはり歴史後と同じく、多くは同母兄弟をもって皇位を継承してであろうと信ずる』と喝破(かっぱ)しているのは傾聴すべきである。」(「卑弥呼即ち倭迹迹日百襲姫命」『考古学雑誌』第十四巻、第七号、1924年[大正十三年]四月、所収)
たとえば、為政者である江戸幕府の将軍のばあいでも、五代将軍徳川綱吉が、家康を一代目として五代目であることは、(「五代将軍綱吉」といういい方をよくするので)すぐに答えられる人は多いであろう。しかし、家康から数えて、「何世目」であるかをたずねられれば、答えられない人が多くなるであろう(綱吉は、三代将軍家光の四男で、家康から数えて「三世目」)。
つまり「世数」は、「代数」にくらべ、情報が正確には、伝わりにくいとみられる。
(2)コラム1のなかに示した系図の例にみられるように、「世数」情報を考えるばあいには、その「世数」のなかに、市辺押磐皇子(いちのべのおしはのおうじ)のように、ふつう、天皇位につかなかったとみられている人も、一世として数えられることになる。古代においては、天皇は政治「権力」を直接にぎっていた。そのため、天皇の座は、他からねらわれる対象であった。
そのため、「天皇の座にいる期間」と、市辺押磐皇子のばあいのような、天皇の位につかず、たんに「父でありえた期間」とは、同質ではないものとなる。
現在でも、政治「権力」の座である首相の位置にいる期間は平均してみじかい。現在では天皇は、直接の政治権力から離れている。父帝からつぎの天皇に位がゆずられ、一世が一代という形になっている。
天皇の位にある期間が、「一世」の長さとなっている。このため現代では、総理大臣一代の平均の長さは、天皇一代の平均の長さにくらべ、いちじるしく短くなっている。
古代では、天皇は現代の総理大臣のような、直接の権力の座にいたのである。
中国文献の記す外国の王の系譜記事は、一般に、かなり粗雑である。たとえば、『宋書』(485年成立)、『梁書』(629年成立)よりも、ずっとのちに成立した『新唐書』(1060年成立)をとりあげてみよう。
中国の文献の記す天皇の系図と、わが国の史書の記す系図とを、かなりなていど対照できるのは、『新唐書』である。
『新唐書』も、『宋書』『梁書』と同じく奏勅撰書であるが、『新唐書』の記す天皇の系譜は、誤りだらけといってよい。
『新唐書』は、「天智死して、子の天武立つ。」と記す。誤りである。天武天皇は、天智天皇の弟である。
『新唐書』は、推古天皇を、「欽明の孫女(まごむすめ)」と記す。誤りである。推古天皇は、欽明天皇の子である。
『新唐書』は、神功皇后を、開化天皇の「曾孫女(ひまごむすめ)」とする。誤りである。神功皇后は、開化天皇の五世の孫である。
『新唐書』は、文武天皇が死ぬと、「子の阿用立つ。」と記す。まったくの誤りである。文武天皇のつぎに立ったのは、天智天皇の子の元明天皇[名は、阿閉(あべ)]である。
『新唐書』は、元明天皇が死ぬと、「子の聖武立つ。」とある。誤りである。元明天皇のつぎは、「子の元正天皇」である。聖武天皇は、元明天皇の孫である。
朝鮮の歴史書、『三国史記』の「新羅本紀」も、中国文献の誤りをわざわざ記している。「第二十九代武烈王は、第二十五代真智王の孫である。『唐書』に、第二十八代真徳王の弟としてあるのは誤りである。」武烈王は、かなり時代がくだり、654年に即位した人である。
続柄は、伝わる過程で、誤りを生じやすい。
■卑弥呼は、だれか
『魏志倭人伝』の伝える「卑弥呼」を、『古事記』『日本書紀』の伝える天皇の系譜の上に位置づけると、どうなるであろうか。卑弥呼はどの天皇の時代の人なのであろうか。
卑弥呼を「わが古代史上のスフィンクス」と呼んだ笠井新也は述べている。
「邪馬台国と卑弥呼とは、『魏志倭人伝』中のもっとも重要な二つの名で、しかも、もっとも密接な関係をもつものである。そのいずれか一方さえ解決を得れば、他はおのずから帰着点を見出すべきものである。すなわち、邪馬台国はどこであるかという問題さえ解決すれば、卑弥呼が九州の女酋であるか、あるいは、大和朝廷に関係のある女性であるかの問題は、おのずから解決する。また、卑弥呼が何者であるかという問題さえ解決すれば、邪馬台国が畿内にあるか九州にあるかは、おのずから決するのである。したがって、私は、この二つのうち、解決の容易なものから手をつけて、これを究明し、その他へ考えおよぶのが、怜悧な研究法であろうと思う。」(『考古学雑誌』第十二巻第七号所載「邪馬台国は大和である」、1922年)
卑弥呼はだれか、卑弥呼はどの天皇の時代の人なのか、についてのおもな説としては、つぎの五つがある。
(1)卑弥呼=神功皇后説
神功皇后は、第14代仲哀天皇の皇后。第9代開化天皇の五世の孫(『古事記』)
『日本書紀』において示されている説である。『神皇正統記』をあらわした南北朝時代の北畠親房(きたばたけちかふさ)や、『異称日本伝』をあらわした江戸元禄時代の国学者、松下見林(まつしたけんりん)も、『日本書紀』の記述をうけて、神功皇后を卑弥呼にあてている。明治以後の学者でも、小中村義象(こなかむらよしかた)、森清人など、「卑弥呼=神功皇后説」をとった学者は、かならずしもすくなくない。
(2)卑弥呼=倭姫説
倭姫は、第12代景行天皇のころの人である(第8代垂仁天皇の皇女、第12代景行天皇の妹)。
「卑弥呼=倭姫説」は、明治のすえに、京都大学の内藤湖南(こなん)[虎次郎]がとなえた。現代でも、坂田隆などは、「卑弥呼=倭姫説」をとっている。
(3)卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説
倭迹迹日百襲姫は、第10代崇神天皇のころに活躍したとされている人である(第7代孝霊天皇皇女)。
「卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説」は、大正時代に、笠井新也がはじめてとなえた。現代でも、歴史学者の肥後和男、和歌森太郎、考古学者の原田大六、その他、『日本誕生の謎』を書いた井上赳夫(いのうえたけお)、『倭日の国』を書いた熊本大学の藤芳義男など、「卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説」をとる研究者はすくなくない。
(4)卑弥呼=天照大御神説
卑弥呼を、第1代神武天皇より5代まえと伝えられる天照大御神(天皇家の祖先神、皇祖神)にあたるとする説である。
この説は、いずれも東京大学の教授であった白鳥庫吉、和辻哲郎が示唆し、その後、栗山周一が明確な形で主張し、林屋友次郎、飯島忠夫、和田清、市村其三郎、安本美典、鯨清、平山朝治などによってうけつがれている。
この説に立つとき、邪馬台国は、九州にあったことになり、のち西暦300年前後の人と推定される神武天皇の時代に、東遷したことになる。いわゆる「邪馬台国東遷説」を主張することになる。
(5)卑弥呼=九州の女酋説
魏へ使をつかわしたのは、大和朝廷とは関係のない九州の女酋であるとする説である。この説は、江戸時代に、本居宣長が説き、その後、鶴峰戊申(つるみねしげのぶ)、星野恒(ほしのひさし)、吉田東伍などによってうけつがれた。
(6)卑弥呼は不明とする説
『古事記』『日本書紀』は、八世紀に成立したものである。卑弥呼は、三世紀に存在した人である。その間に、五百年ちかいへだたりがある。『古事記』『日本書紀』の伝える初期の諸天皇には、実在の疑われる人もあり、『古事記』『日本書紀』によっては、卑弥呼や邪馬台国は、さぐれないとする立場である。津田左右吉が、このような考え方を、体系的にまとめ、現在、この立場に立つ人は多い。
以上のうち、(1)の「卑弥呼=神功皇后説」、(2)の「卑弥呼=倭姫説」、(3)の「卑弥呼=倭迹迹日百襲姫説」は、だいたい、「邪馬台国=大和説」となる。(4)の「卑弥呼=天照大御神説」、(5)の「卑弥呼=九州の女酋説」は、「邪馬台国=九州説」となる。
また、(1)、(2)、(3)、(4)は、卑弥呼を、皇室の系譜のうちから求められるとする説であり、(5)、(6)は、皇室の系譜のうちに求められないとする説である。
■グラフによるまとめ(卑弥呼はだれかの棒グラフ化)
①神武天皇を西暦紀元前後とする那珂通世の説
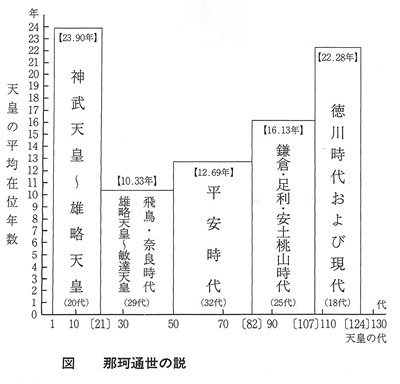 第1代神武天皇の活躍時期………西暦元年
第1代神武天皇の活躍時期………西暦元年
第21代雄略天皇の活躍時期 …西暦478年
この間20代で478年(1代平均23.90年)
20代で478年であるから、1代平均23.90年となる。グラフにかくと、右図のようになる(グラフでは雄略天皇~敏達天皇の時代と、飛鳥・奈良時代とでは、平均在位年数が、ほとんど変わらないので、まとめてある)。
23.90年という値は、そのまえの時代全体の平均在位年数の、二倍以上の値である。
②卑弥呼は神功皇后とする説
つぎに、卑弥呼を三韓征伐で知られる神功皇后であるとする説をとりあげる。
神功皇后は、第14代仲哀天皇の妃である。
いっぽう、卑弥呼は、西暦239年に、魏に朝貢している。すなわち、そのころが卑弥呼の活躍していた時期と考えられる。したがって、つぎのようになる。
卑弥呼(神珎皇后)の活躍時期……239年
第21代雄略天皇の活躍時期 ……478年
この間7代で239年(一代平均34.14年)
この間の平均在位年数は34.14年で、グラフにかくと下図のようになる。
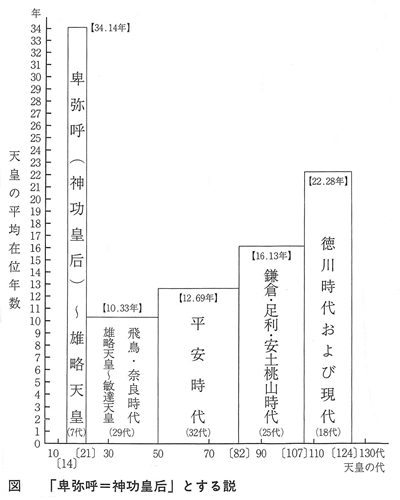
34.14年という値は、飛鳥・奈良時代の平均在位年数よりも三倍以上長い。卑弥呼を神功皇后とみることは、無理なようである。
すでに、明治の末に、那珂通世は「上世年紀考」をあらわし、「卑弥呼=神功皇后」の成りたちえない根拠を、くわしくのべている。
③卑弥呼は倭姫とする説
明治の東洋史家、内藤湖南(虎次郎)は、卑弥呼を倭姫(やまとひめ)であると説いた。倭姫は、第12代景行天皇のころの人である。この説では、つぎのようになる。
卑弥呼(倭姫)の活躍時期…………239年
第21代雄略天皇の活躍時期 ……478年
この間9代で239年(一代平均26.56年)
グラフにかくと、下図のようになる。
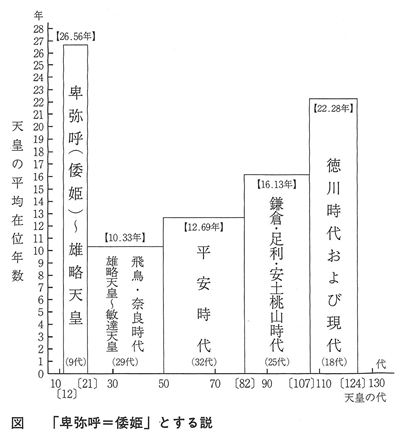
26.56年という値は、飛鳥・奈良時代の平均在位年数よりも二倍以上長い。卑弥呼を倭姫とみることは、やはり、無理なようである。
④卑弥呼は倭迹迹日百襲姫とする説
さらに、大正、昭和にいたり、笠井新也、肥後和男、和歌森太郎などにより、卑弥呼を倭迹迹日百襲姫であるとする説がとかれた。
倭迹迹日百襲姫は、第8代孝元天皇のころの人である。この説によれば、つぎのようになる。
卑弥呼(倭迹迹日百襲姫)の活躍時期………239年
第21代雄略天皇の活躍時期 ……………478年
この間13代で239年(一代平均18.38年)
グラフにかくと、下図のようになる。
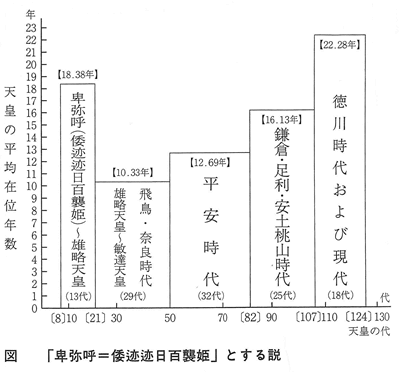
このばあいの平均在位年数も、飛鳥・奈良時代の平均在位年数よりかなり長くなる。年代の延長傾向がみとめられる。
以上の説を通観するとき、『日本書紀』の記載になんらかの形でしばられ、卑弥呼~雄略天皇の平均在位年数を、大きくみつもりすぎる傾向があるようである。
言葉をかえていえば、大和朝廷の歴史を古く考えすぎる傾向があるようである。
⑤「卑弥呼=天照大御神説」は、……
最後に、東京大学の東洋史家、和田清、東洋大学の日本史家、市村其三郎などをはじめ、栗山周一、林家友次郎、飯島忠夫など、これまでに少ながらざる人々がとなえてきた「卑弥呼=天照大御神説」をとりあげておこう。卑弥呼を、神武天皇の五代まえと伝えられる天照大御神とするときには、どのようになるであろうか。
このばあいには、つぎのようになる。
卑弥呼(天照大御神)の活躍時期………239年
(第21代雄略天皇の活躍時期 ………478年
この間25代で239年(一代平均9.56年)
グラフにかくと、下図のようになる。
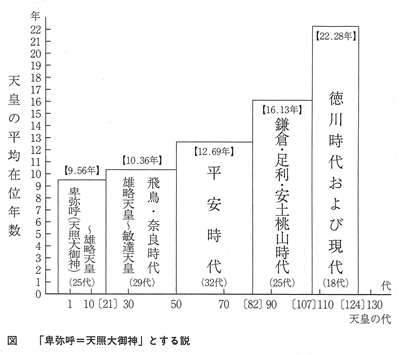
この結果は、つぎの二つの点からみて、不自然さがないように思われる。
(1)この平均在位年数9.56年は、そのつぎの時代(雄略天皇~敏達天皇の時代および飛鳥・奈良時代)の平均在位年数にくらべ、一年たらず(0.8年)短いにすぎない。すなわち、つぎの時代の平均在位年数とのつづきかたがスムーズである。
(2)しかも、傾向としては、次の時代の平均在位年数よりも、短くなっている。これは、現代に近づくにつれ、平均在位年数が、長い眼でみたばあい、はじめはゆっくりと、しかし、だんだん急速にのびている傾向と合致している。
『古事記』『日本書紀』に、「帝紀」のみ記されている第2代綏靖天皇~第9代開化天皇の、在位期間は短かったとみられる。
この説をまとめれば、邪馬台国の卑弥呼女王のころは、まだ、大和王朝は成立していなかったことになる。
■パラレル年代推定法
400年ごとにまとめて、実在と在位期間のあきらかな諸天皇の平均在位年数を算出してみる。もとのデータは、東京創元社刊の『日本史辞典』による。
すると、下図の図①の「日本の天皇の平均在位年数」ようになる。
図①の意味は、たとえば(E)の時期の、「17世紀~20世紀」の400年のあいだに即位した天皇は、17天皇いて、その、のべの在位期間は、379年間ということである。
(下図はクリックすると大きくなります)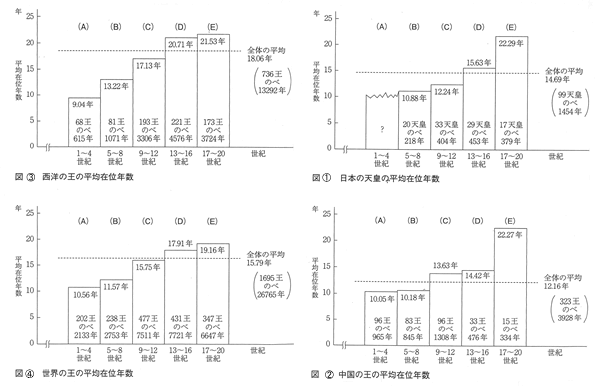
もちろん、一人一人の天皇をとれば、在位年数の長かった天皇も存在するし、短かった天皇も存在する。
しかし、400年間のように、長い期間の平均値をとれば、一定の傾向がみてとれる。
それは、古代にさかのぼるにつれ、平均在位年数が、短くなる傾向である。
十七世紀~二十世紀の天皇の平均在位年数は、昭和天皇のように長く在位した人もふくめて、22.29年であった。これに対し、五世紀~八世紀ごろの平均在位年数は、その半分以下の10.88年となっている。
同様のグラフを、東京創元社刊の『東洋史辞典』『西洋史辞典』にもとづき、「中国の王」「西洋の王」「世界の王」という形でまとめれば、上図の図②~図④のようになる。
すると、「中国の王」のばあいも、「西洋の王」のばあいも、「世界の王」のばあいも、「日本の天皇」のばあいと、同じような傾向がみとめられる。
すなわち、古代にさかのぼるにつれ、平均在位年数が、短くなる傾向がみられる。
とくに、「日本の天皇」のばあいの上図の図①と、「中国の王(皇帝)」のばあいの図②とは、かなり近い形になっている。400年ごとにまとめた(B)(C)(D)(E)各時代のそれぞれにおいて、平均在位年数は、一年前後てぃどしか違わない。下表のとおりである。
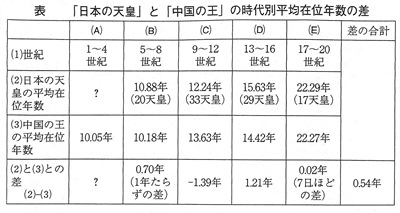
機械的に、「(2)と(3)との差」の合計をとれば、0.54年、約半年ていどしか異ならない。
いま、「日本の天皇の平均在位年数」と「中国の王の平均在位年数」との、(B)(C)(D)(E)のそれぞれ対応する時期におけるパラレルな増加傾向の様子をみるために、ためしに、つぎのようなことを行なってみよう。
かりに、(B)(C)(D)(E)の各時期において、「日本の天皇の平均在位年数」が、対応する時期の「中国の王の平均在位年数」と同じであったとしたばあい、同じとみなさなかったばあいと、全期間で、どれだけの年数の違いを生ずるものであろうか。
それを計算したのが、つぎの下の表のパラレル状況である。
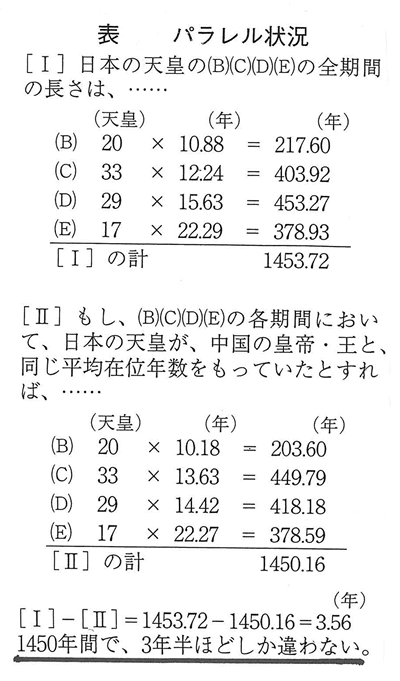
日本の天皇と中国の皇帝・王とは、個々でみると、長い在位年数の人、短い在位年数の人がいる。しかし、双方が、同じような傾向をもって、いわば並行的(パラレル)に、後代になるほど在位年数が、平均して大きくなって行く、そのため、長い期間でみると、プラス、マイナスなどの誤差がうちけしあい、1450年間ほどで、わずか三年半ほどしか違わない、というようなことがおきるのである。
このことを利用すると、つぎのような「パラレル年代推定法」が考えられる。
倭の国(日本)は、卑弥呼の時代に、中国の魏の国と国交をもった。そのあと、西晋の国、東晋の国、南朝(江南、南中国)の宋の国など、連続する中国王朝と国交をもった。
南朝宋についての歴史書『宋書』に、西暦478年にあたる年に、倭王の武が、来王朝に使いをつかわし、文書をたてまつったこと、宋の第8代皇帝の順帝の準(じゅん)が倭王武に、「安東大将軍、倭王」などの称号を与えたことなどが記されている。
この倭王武は、つぎの理由により、わが国の第21代の天皇の、雄略天皇のことであるとみられている。
(1)『古事記』によっても、『日本書紀』によっても、478年は雄略天皇の治世の時代とみられること。すなわち、雄略天皇の没年を、『古事記』は、489年にあたる年と記し、『日本書紀』は、479年にあたる年と記している。
(2)倭王武の「武」の名は、雄略天皇の名である「大長谷若建の命(おおはつせわかたけのみこと)」(『古事記』)、「大泊瀬幼武の天皇(おおはつせのわかたけのすめらみこと)」(『日本書紀』)などの「建(たけ)」「武(たけ)」と関係があるとみられること。
(3)埼玉県稲荷山古墳出土の鉄剣銘文により、471年[辛亥(しんがい)の年]が、雄略天皇[獲加多支鹵(わかたける)大王]の時代とみられること。
以上から、わが国の第21代天皇の雄略天皇を、中国の南朝宋の第8代皇帝順帝準とほぼ同時代の人であるとみとめる(下表参照)。
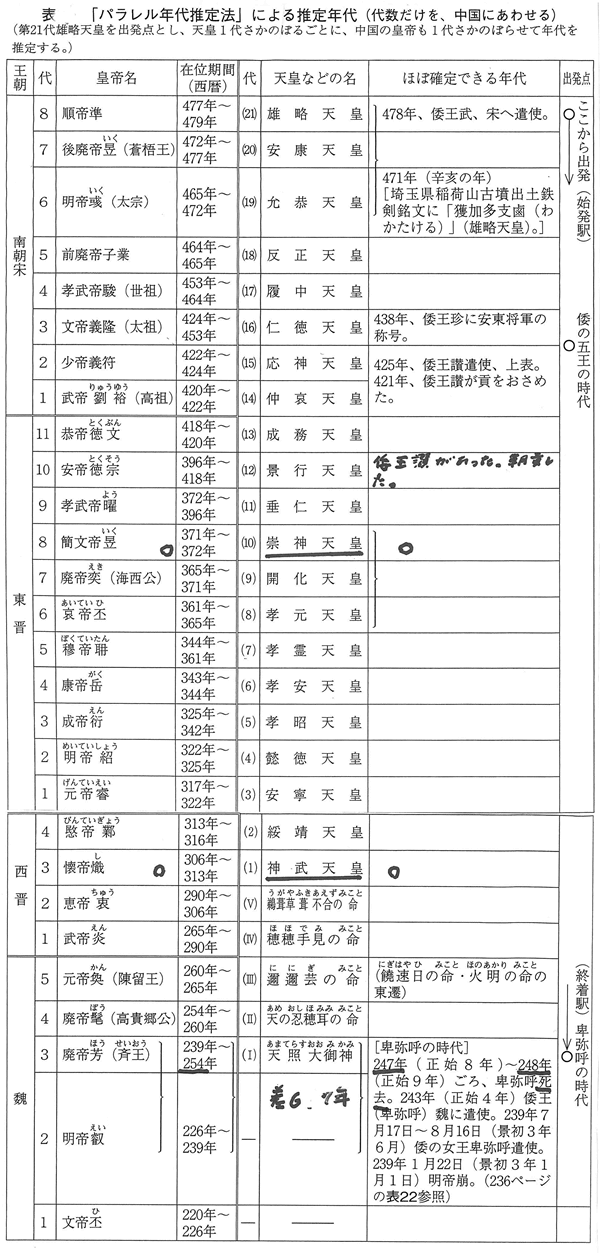
この表の中国側の皇帝の年齢を示すと、下表となる。
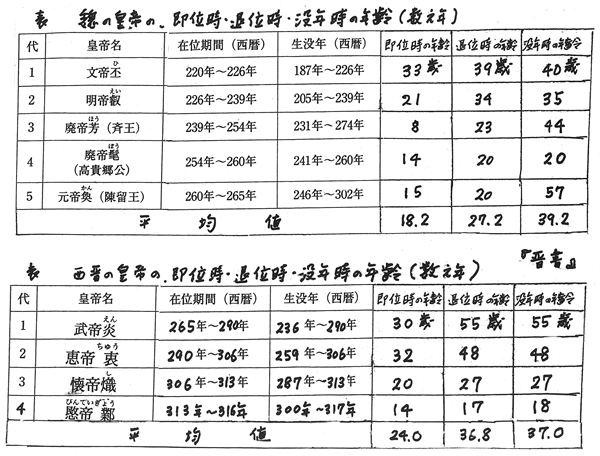
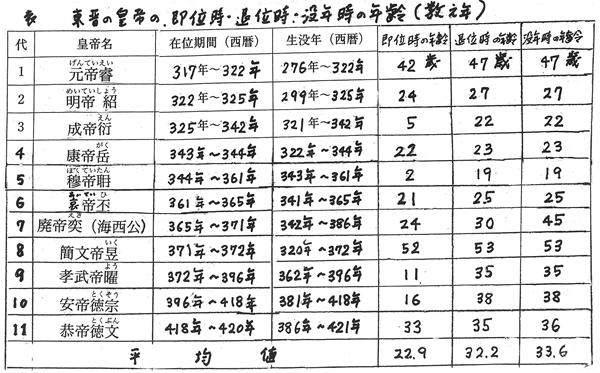
更に、上記の表をまとめて統計計算すると、下の表のようになる。
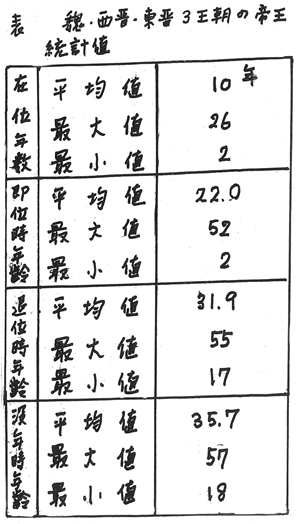
魏、西晋、東晋の3王朝の帝王の統計結果から、没年の平均値は35.7歳となり、50歳に遠く及ばない。そして最大で57歳である。若いと18歳で亡くなる。現在の年齢に対する考えと大分違う。
また、即位時の年齢の平均は22歳、在位年数の平均10年である。
この中国の皇帝の結果を見ると、
「卑弥呼の宗女壱(台)与[とよ]、年十三なるものを立てて王となす。」(『魏志倭人伝』の記述)は当時、ありうる年齢と言える。
そして、雄略天皇からn(エヌ)代さかのぼった天皇は、順帝列からn(エヌ)代さかのぼった中国の皇帝と、大略同時代の人と推定することにする。
古代の中国の皇帝については、史書の「帝紀」などに、くわしい記載がある。上の表の中国がわの、皇帝の在位期間データは、しっかりとしたほぼ確実なデータである。上の表は、一応それを手すりとして、古代への階段をのぼり、はっきりとはしない日本の古代の天皇などの、大まかな活躍年代を推定しようとする方法である。
このような方法によると、第21代雄略天皇から、機械的に25代さかのぼった天照大御神の時代は、中国の魏の廃帝芳(ほう)[斉王(さいおう)、在位239~254年]の時代にほぼあたることとなる。そして、『魏志倭人伝』は、239年、243年に、卑弥呼が、魏の国に遣使したこと、斉王芳の在位期間中の247年か248年のころに、卑弥呼が死去したことなどを記している(下表参照)。
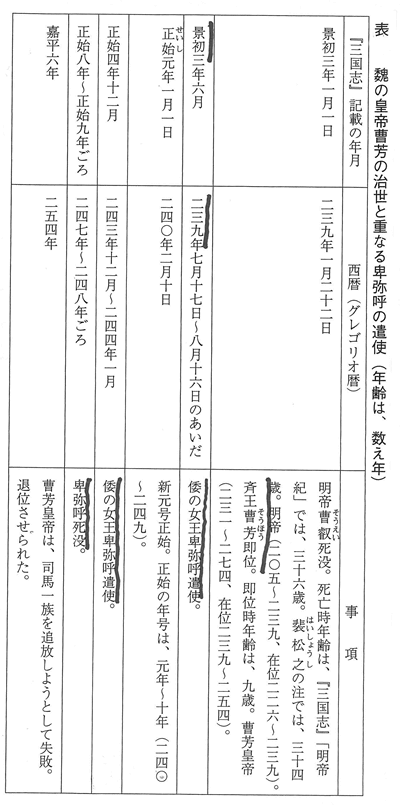
すなわち、廃帝芳(斉王)の治世時期を手がかりに、卑弥呼と天照大御神の同時代性が浮かびあがってくる。
つまり、第21代雄略天皇の時代から、同じ代数だけ古代への階段をさかのぼった日本の天皇や祖先神と、中国の皇帝らのペアが、それぞれまったく同じ在位年数をもっていたならば、天照大御神の時は、卑弥呼の時代に、ほぼちょうど重なりあうことになる。
ペアになる中国の皇帝の治世年代によって、日本の古代の諸天皇の大まかな年代を推定しよう、というわけである。
この方法を、「パラレル年代推定法」と名(な)づける。
「パラレル年代推定法」では、ペアとなる皇帝と天皇との在位年数が、完全に同じでなくても、推定期間における「在位年数の平均値」が、中国と日本とでほぼ同じならば、同様の推定結果がえられることになる。
そして、古代の皇帝や天皇の在位年数の平均値が、中国と日本とで、それほど変わらないと判断されることは、すでにのべた。
■天皇の和風謚号(しごう)の兄弟の類似性
『古事記』『日本書紀』で、系譜上、兄弟とされている天皇の和風謚号には、しばしば、類似性のあることに気づく。たとえば、つぎのとおりである。
第23代顕宗天皇 ヲケ
第24代仁賢天皇 オケ
第27代安閑天皇 ヒロクニオシタケカナヒ
第28代宣化天皇 タケオヒロクニオシタテ
第29代欽明天皇 アメクニオシハルキヒロニワ
第35代皇極天皇 アメトヨタカライカシヒタラシヒメ
第36代孝徳天皇 アメヨロズトヨヒ
第38代天智天皇 アメミコトヒラカスワケ
第40代天武天皇 アマノヌナハラオキノマヒト
第41代持統天皇 オオヤマトネコアメノヒロノヒメ
第43代元明天皇 ヤマトネコアマツミシロトヨクニナリヒメ
第42代文武天皇 ヤマトネコトヨオオジ
第44代元正天皇 ヤマトネコタカミズキョタラシヒメ
兄弟関係にある天皇は名前(和風謚号)がよく似ている。
下の『古事記』の系図から、
天邇岐志国邇岐志天津日高日子番能邇邇芸命(あめにきしくににきしあまつひこひこほのににぎのみこと)と天の日明の命(あめのほあかりのみこ)が兄弟となっている。
天の日明の命は邇芸速日の命(にぎはやひのみこと)[饒速日の命(にぎはやひのみこと)」のことではないかとされてている。
邇邇芸命 ニニギノミコト、
邇芸速日命 ニギハヤヒノミコト
は、「ニギ」が似ている。
(下図はクリックすると大きくなります)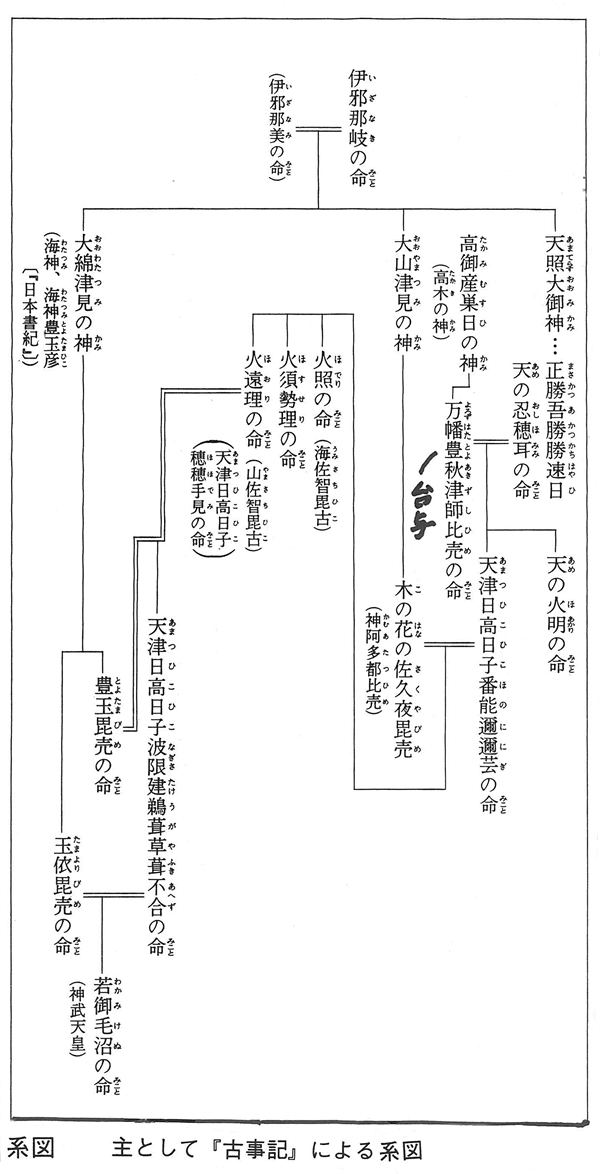
■『古事記』の記紀神代と『魏志倭人伝』の人名などとがよく一致している
皇學館大学の学長などであった日本史家の田中卓氏は、『日本国家の成立と諸氏族』(田中卓著作集2で国書刊行会刊)のなかで、『先代旧事本紀』が、饒速日の命を、瓊瓊杵尊の兄と特筆するのは、「否定しがたい古伝」であったであろうとする。
1956年に『魏志倭人伝』の現代語訳を出した島谷良吉(しまやりょうきち)[1899~1980。高千穂商科大学教授などであった)は、その『国訳魏志倭人伝』の「前がき」の中で述べている。
「陳寿編纂『魏志巻三十』所載の東夷の一たる『倭人』の記述を見ると、まったく記紀神代の巻の謎を解くかのように思える。」
『魏志倭人伝』は、卑弥呼のあとをつぐ宗女(一族の娘)の名を、「台与(とよ)」と記す。
下の系図をみると、「トヨ」という音のはいる女性の神名に、「万幡豊秋津師比売(よろづはたとよあきづしひめ)」「豊吾田津姫(とよあたつひめ)」「豊玉姫(とよたまひめ)」などがある。
(下図はクリックすると大きくなります)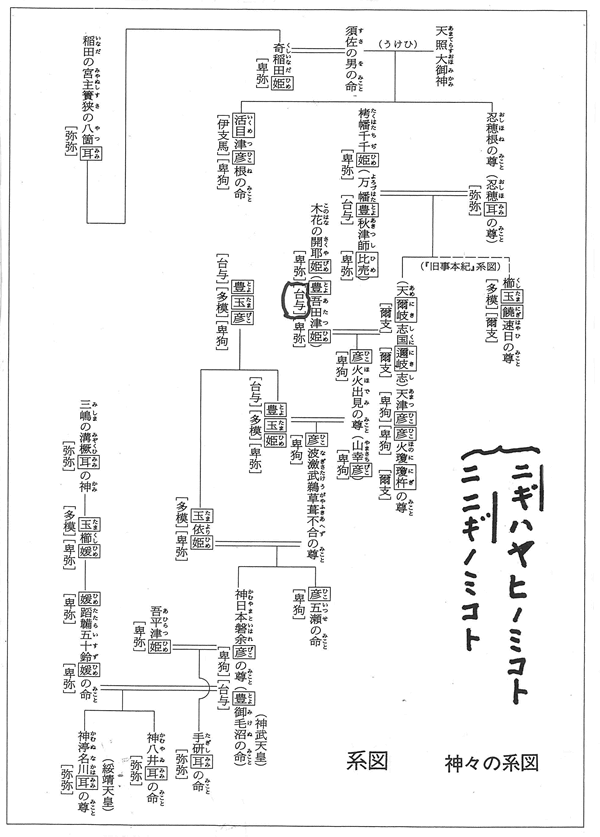
とくに、「万幡豊秋津師比売(よろづはたとよあきづしひめ)」は、高御産巣日の神(たかみむすびのかみ)の娘で、天孫降臨をする瓊瓊杵の尊(ににぎのみこと)[邇邇芸の命(ににぎのみこと)]の母である。天照大御神を「卑弥呼」にあて、万幡豊秋津師比売を「台与」にあてれば、世代的には、あう。
・『古事記』の神話時代の神名・人名が、『魏志倭人伝』の人名・官名と、とくに、よく一致している
『魏志倭人伝』の官名に、「弥弥(みみ)」「爾支(にき)」「多模(たま)」などがある。
『古事記』にみえる「とよ」「みみ」「にき」「たま」を含む神名、人名について全数調査をすると、下の表のようになる。
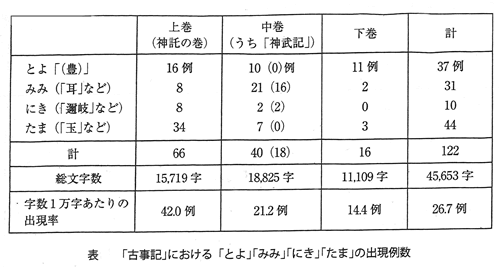
すなわち、「とよ」「みみ」「にき」「たま」を含む神名、人名は、『古事記』全体で、のべ122回あらわれる。
そのうち、過半の66回は、『古事記』上巻(神話の巻)にあらわれる。
また、中巻にあらわれる「とよ」「みみ」「にき」「たま」はのべ40回のうち、18回は、最初の、「神武記」にあらわれる。
したがって、「神武記」以前(上巻と「神武記」とを加えたもの)に、「とよ」「みみ」「にき」「たま」は、のべ、84回あらわれることになる。
じつに、「とよ」「みみ」「にき」「たま」の、三分の二以上、69パーセントは、「神武記」以前にあらわれる。
『古事記』の、上巻と中巻と下巻とでは、分量が異なる。
このことを考慮しても、結論はかわらない。いな、「とよ」「みみ」「にき」『たま』は、他の巻よりも、上巻に頻出するという傾向は、さらにはっきりとうかびあがってくる。
■太田亮(あきら)氏の「高天の原=肥後山門説」
東大系の学者ではないが、系譜学者として、わが国の氏族についての厖大なデータを整理した太田亮氏(1884~1956)は、1928(昭和三)年に、『日本古代史新研究』(磯部甲陽堂刊)をあらわしている。太田亮氏は、この本のなかで、高天の原論争史上はじめて、「邪馬台国=高天の原説」を、はっきりとうちだした。太田亮氏は、種々の氏族の地域的分布などから、高天の原を邪馬台国であるとし、それを、肥後の菊池郡の山門を中心とする地にあてた。
この太田亮氏の説を、のちに、「卑弥呼=天照大御神説」を説いた東大系で東洋大学の教授であった市村其三郎氏は、その著『秘められた古代日本』(1952年、創元社刊)のなかで、「太田亮氏の高天の原肥後説は大分合理的であるように思われる。」と評している。
太田氏は、その『日本古代史新研究』の第四編、「天神民族の故国」のなかで、およそ、つぎのようにのべる。
「中臣(なかとみ)氏も、大伴(おおとも)氏も、九州発祥の氏であるらしいが、たとえ、そうでないとしても、大和中心の氏族と離れて、九州に一族がある。中央貴族中、天孫とか皇別と称する皇室より分れたという氏族をのぞけば、大多数は、大和と九州とを中心として氏族が分布されている。そのいずれの中心が古いかといえば、私は、九州と答えたい。それは、大伴や中臣や物部(もののべ)の発祥地が、九州らしいというばかりではない。また、宇佐とか、壱岐とか、対馬、松浦とかの古い氏が、天神の子孫であると称しているばかりでもない。また、高天の原神話が、九州を中心としているばかりでもない。
もし、これらの氏が、はじめから大和を中心として栄えたものならば、皇別諸氏のごとく、大和をのみ中心として発展しなければならない。また、近畿の国造(くにのみやつこ)、県主(あがたぬし)というような土地の領主中に一族がなければならない。しかし、事実は、これに反している。よって、ある時代に、これら貴族の中心地が、大和に大移動をしたものであって、それ以前は、九州であったと思うのである。
したがって、天祖の都城は、これを九州にもとめなければならない。すなわち、神武天皇の東征を、史実と考えるのである。九州中において、天祖の都城として、もっとも適当なのは、畿内ヤマトと同じ名をもつ肥の国のヤマトの外にないと思う。高天の原神話は、この地を中心としているらしく考えられ、また、畿内のヤマトは、このヤマトの名を移したと思われる。」
貴族の中心地が、九州から、大和に大移動をしたものであろうということについては、戦後の、地名学者、鏡味完二(かがみかんじ)氏の研究が、おもいおこされる。鏡味氏も、その著『日本の地名』のなかで、九州と近畿とのあいだで、地名の名づけかたが、じつによく一致しているという、太田亮氏とは異なる見地から、やはり、九州から、近畿への大きな集団の移動のあったことを想定している。ただし、地名の一致からは、大和への移動の時期が不明である。これにたいし、太田氏の氏族の分布による推定では、大和朝廷に記憶がのこりうるころという時間の指定が可能である。
太田亮氏は、また、つぎのようにものべる。
「天神族の祖国は、これを九州に求めるのが、一番おだやかだと思う。そして、それは、沃野の打ちつづく、人の住みやすい地でなければならないと考える。その地は、その後も、自然の破壊がなければ、戸数人口の密な場所に違いないのである(下の地図参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)
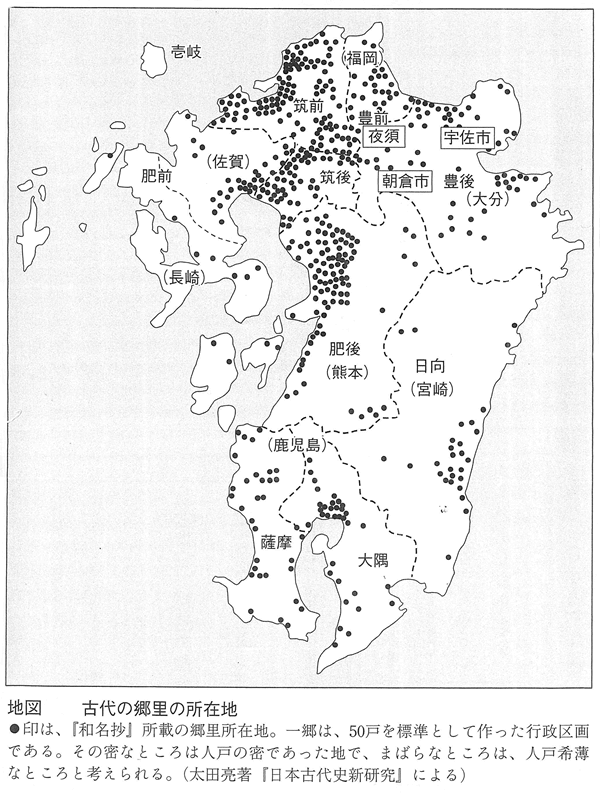
注:上の地図は郷里の所在地であり、下の地図は箱式石棺の分布で、平野部も示している。郷と平野部とが一致しているように見える。
(下図はクリックすると大きくなります)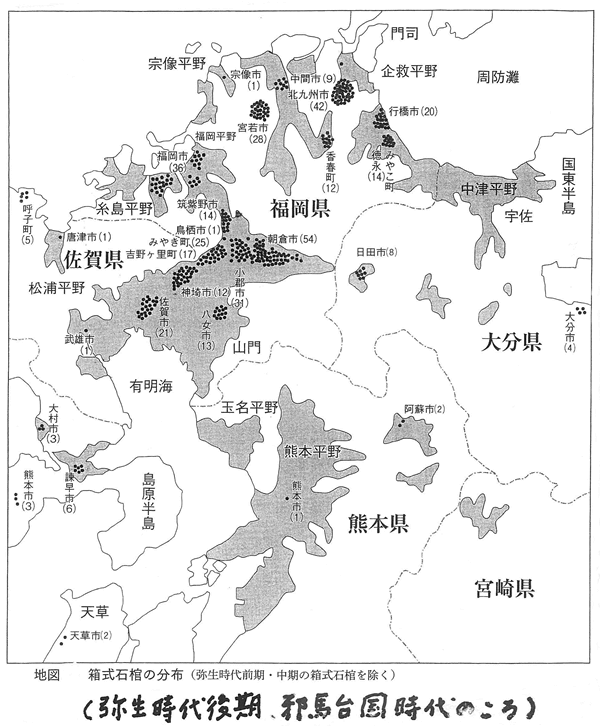
こう考えてくると、直感的に、天祖の都は、邪馬台国のような地であったのではないかと思われる私は、この広くもない、日本列島中の九州と畿内に、ヤマトという二つの大きな国のあったことをあやしむ。わが国は、西から東へと開けていったのである。東の大和なる名称は、肥後のヤマトの名が種族の移住とともに、移ったのであろうと考える。つまり、朝廷が、畿内の今の大和の地にうつったのち、天祖の故国なるヤマトなる名称が、帝都所在地の国名として選ばれたと考えざるをえない。
このような考えから、天神の故国を、邪馬台国と思う。それは、氏族分布からみた想像からいっても、高天の原神話中にふくまれた地理的観念からかえりみても、そうであったという感じを、禁じえない。」







