■パスカルの方法
自然科学の発展とともに、科学方法論自体もしだいに深くたずねられてきた。そして、どのような論理が学問にとって望ましい論理であるかということも、明らかになってきている。そのような論理の基本的な基準は、すでに十七世紀に、フランスのパスカルが、その著『幾何学的精神』のなかでのべている。
パスカルの論理の基準については、埼玉大学の吉田洋一、立教大学の赤摂也(せきせつや)氏共著の『数学序説』(培風館刊)にきわめて要領よくまとめられている。以下、両氏の著書により、まずパスカルの規準を紹介しよう。
パスカルは、まず定義についての三つの規則をあげている。
(1)それよりもはっきりした用語がないくらい明らかなものは、それを定義しようとしないこと。
(2)いくぶんでも、不明もしくはあいまいなところのある用語は、定義しないままにしておかないこと。
(3)用語を定義するに際しては、完全に知られているか、または、既に説明されている言葉のみを用いること。
また、公理(議論の出発点、前提)について、二つの規則をあげている。
(1)必要な原理は、それがいかに明晰で証明的(論証や検証によらなくても、それじたいが、直接的に明らかで疑いえないもの)であっても、けっして承認されるか否かを、吟味しないままに残さないこと。
(2)それ自身で、完全に明証的なことがらのみを公理として要請すること。
さらに、論証について、三つの規則をあげている。
(1)それを証明するために、より明晰なものをさがしても無駄(むだ)なほど、それだけで明証的なことがらは、これを論証しようとしないこと。
(2)すこしでも不明なところのある命題は、これを、ことごとく証明すること。そして、その証明にあっては、きわめて明証的な公理、または、すでに承認せられたか、あるいは証明された命題のみを用いること。
(3)定義によって限定された用語のあいまいさによって誤らないために、つねに心の中に定義された名辞の代わりに、定義をおきかえてみること。
パスカルの方法をまとめれば、自明のものをのぞくすべての「言葉」を「定義」し、また、自明でないすべての「命題」を「証明」しつくすということになるであろう。
■現代の公理主義
パスカルの規準は、ギリシャ人が幾何学を建設するのに用いた方法にほかならない。だからこそ、パスカルは、自分の書物を『幾何学的精神』と名づけたのである。
ところで、このような方法論は、自然科学のめざましい進展とともに、さらに洗練されてきている。
幾何学的精神の現代的な形式としては、「公理主義」がある。ある理論において、他の命題の前提となる基本命題の体系(公理系)を明らかにし、その公理系と、特定の推論規則とから、演繹的に理論をくみたてることを、公理的方法、または公理論という。ユークリッドの幾何学は、不完全であるにしても、その適例であると考えられる。またパスカルの方法は、公理主義の原初的な形といえよう。
現代の公理主義が、パスカルの説いた方法と異なる点は、主として「公理」についての考え方にある。パスカルにおいては、「公理」は「それ自身で完全に明証的なことがら」で、「万人に承認される明晰なことがら」でなければならないと考えられていた。ところが十九世紀のはじめに、「万人に承認される」とはいえない公理をもとにして、完全に無矛盾な非ユークリッド幾何学が建設されるにおよんで、この「公理」についての考え方は大きくゆらいだ。そしてドイツのヒルベルト(1862~1943)により、公理の考え方についての大転換が行なわれた。一言でいえば、ヒルベルトは、「公理」はなんら自明の真理である必要はなく、たんに明確に定められた「仮定」で十分であるとしたのである。すなわち、いくつかの「仮定(公理・仮説)」をおき、そこから、形式的に結論をみちびいて、そこに矛盾を生じなければよいとしたのである。
ヒルベルトは、数学の基礎として、自分の考えをのべた。しかしその考え方は、やがて自然科学全体に、きわめて広汎な影響をおよぼすこととなった。
オーストリア生まれ、のちアメリカにわたったカールナプ(1891~1970)らは、この方法だけが科学的方法であり、すべての科学は公理論的に構成されるべきであるとして、「公理主義」をとなえた。さらにカールナプらは、それまで主として数学を基礎づける道具として発達してきた記号論理学を、広く諸科学を分析し基礎づける道具として用いることを説いた。
以上のべてきたことについて、いますこし補足をしておこう。
ポーランドに生まれ、アメリカに帰化し、意味論を提唱し、一般意味論研究所の所長となった論理学者、コージプスキー(1879~1950)は、ことばを二種類にわけた。すなわち、専門用語と非専門用語とである。
コージプスキーは、専門用語においては、たとえば、90°とかH₂Oとか書けば、誤解なくコミュニケートできるが、そうでない非専門用語は、誤解をまねくことばであるとのべている。
90°とかH₂Oとかにおいて、ことばの意味が一義的である。学問を進めるにあたっては、そこで用いられることばは、明確な定義によって限定され、可能なかぎり一義的であることが望ましい。このことは、パスカルの規則のなかにも含まれていることであるが、とくに重要なことであると私は考える。
科学のことばとして、しばしば数学や数理が用いられる。数学や数理は、意味や論理の展開が、一義的であるからである。
京都大学人文科学研究所の教授であり、西洋史学者であった会田雄次(あいだゆうじ)は、その著『合理主義』(講談社現代新書)のなかで、つぎのようにのべている。
「合理主義的なものの考え方をつきつめると、いっさいを量の変化において考え抜こうという精神です。」
■公理的方法についての私の立場
ここで、公理主義についての私の考えをのべておこう。
私は、「公理」は、たしかに「それ自身で完全に明証的なことがら」で、「万人に承認される明晰なことがら」でなければならないとは考えない。その意味では、パスカルよりも、ゆるやかな立場をとりたいと思う。
しかし、明確に定められた「仮定」であれば、どのようなものであってもよいとは思わない。
あるていど、経験的事実や直感に合致したものが望ましいと考える。この点ヒルベルトほどゆるやかな立場はとらない。
ヒルベルトは、「テーブルと椅子(いす)とコップとを、点と直線と平面との代わりに使っても、やはり幾何学はできるはずだ」とのべたと伝えられる。
私が、「公理」は、あるていど、経験的事実や直感に合致したものが望ましい、と考えるのは、そのような立場の方が説得力があると考えるからであって、そのような立場をとらなければならないという論理上の根拠は存在しない。
十七世紀の末に、アイザック・ニュートンは『プリンキピア』(原題『自然哲学の数学的原理』)をあらわし、万有引力の法則をはじめて世に知らせた。これにより、天体の力学と地上の力学とは統一的に把握されることとなった。
『プリンキピア』は、ユークリッドの『ストイケイア』(幾何学原論)にならって書かれたものであった。たとえば、ニュートンはその第1部で、「質量」や「運動量」などを定義したのち、公理をのべている。
【公理Ⅰ】
「すべての物体は、力が働かないかぎりは、静止しているものは、いつまでも静止し、一様な直線運動をしているものは、その運動をつづける。」
【公理Ⅱ】
「運動の変化は、作用する力に比例し、かつ力が働く方向に起こる。」
【公理Ⅲ】
「作用は、常に反作用に等しい。いいかえると、二つの物体の相互間の作用は、つねに等しいが、方向は反対である。」
ニュートン力学の三法則も、ここで提唱されている。また、力の合成に関する「平行四辺形の公理」も、補足的に示されている。これらの公理から、力学の基本原理、たとえば「万有引力の法則」が演繹されている。
ユークリッドの幾何学とニュートンの力学とは、数学的なものと物理学的なものとして、現代では別々に把握されている。しかし、もともとは同質のものといえる。ともに、はじめに公理を定め、さまざまな定理・命題を導き出すという形をとっている。そして、導き出された定理・命題が、経験的事実と一致する。すなわち、これらは、一つの論理的な整合性をもった理論体系であるとともに、日常の経験世界の忠実な記述でもある。
ユークリッド幾何学もニュートン力学も、ともに観察によって認識されうるようないくつかの「事実」的なものを公理とし、それらを出発点としたうえで、多くのことがらを説明したところに、その強みがあったといえる。ユークリッド幾何学が、非ユークリッド幾何学があらわれるまでの、およそ二千年の歳月に耐えることができ、ニュートン力学が、今世紀のはじめに量子論があらわれるまでの、二百年の歳月に耐えることができたのは、観察可能な「事実」的なものを基礎としていたことがあげられうるであろう。
私は、ユークリッドの『ストイケイア』やニュートンの『プリンキピア』は、経験科学のあるべき叙述の姿の、ある意味での典型をなしていると思うものである。
以上をまとめるならば、私は、わが国の古代の探究のために、基本的には、公理的方法にしたがう立場をとる。ただしこの公理は、「万人に承認される明晰なことがら」でなければならないとは考えないが、どのようなものであってもよいとはしない。ある程度、経験的な「事実」や直感に合致したものが望ましいとする。
また、用語は、可能なかぎり明確な定義により限定された一義的なものであることが望ましいとする。
なお、「公理」(前提、仮定、仮説、出発点)の数は、できるだけ少なく、相互に独立のものが望ましいとする。
■私の邪馬台国論の論理構造
わが国の古代史全体を統一的、構造的に把握しようとするばあいには、私は、公理(仮説、仮定、前提、出発点)としてつぎの二つを設定したいと思う。
【公理Ⅰ】
「『古事記』『日本書紀』に記されている天照大御神以下の五代、および諸天皇の代の数は、信じられるものとする。」(これは、代の数のことをのべているのであって、ある天皇と、つぎの天皇との関係は、親子関係であるとはかぎらない。)
【公理Ⅱ】
「西暦何年ごろに活躍していたか、実年代が不明の天照大御神以下の五代、および古い時代の諸天皇の活躍の時期は、活躍の時期がはっきりしている諸天皇の一代平均の在位年数をもとに、推定しうるものとする。」
この二つの公理を設定するとき、つぎのようなことがらが、定理的に導出される。
(1)天照大御神は、卑弥呼とほぼ同時代の人となる。(そしてこの二人が、ともに女王的な存在で、宗教的な権威をもち、夫をもたなかったこと、天照大御神が、のちにわが国最大の政治勢力となった大和朝廷の系譜上の人物であること、などは、この二人が同一の人物であることを指向する。)
(2)神武天皇は、西暦280~290年ごろの人となる。(このころからあとに、大和に古墳がおこり・刀剣、矛、鏃、鉄、鏡、玉などの分布の中心が、九州から大和に移っている。
すなわち、記紀に記されている神武天皇の東征によって説明しうると思われる事実が存在する。)
(3)崇神天皇は、西暦350~360年前後の人となる。(奈良県天理市大字柳本に存在する崇神天皇の陵を、東大の考古学者、歴史学者である斉藤忠博士は、四世紀の中ごろ、またはそれをやや降るころのものとしている。筑波大学の川西宏幸(ひろゆき)教授は、崇神天皇陵古墳を、360年~400年ごろのものとする。)
そしてさらに、(1)の「系」として、記紀によれば、天照大御神(卑弥呼)の活躍していた場所が、北九州であると考えられ、また大和朝廷が九州に興ったと考えられる少なからぬ根拠が存在するところから、
(1)邪馬台国は、北九州である。
ということがみちびかれる。
以上の議論は、【公理Ⅰ】【公理Ⅱ】をもうけ、そこから、統計学、確率論などの数学の論理をかりて、「定理」、あるいは「系」をみちびきだすという形をしている。
ヒルベルト的な公理設定の自由性をみとめる立場にたてば、【公理Ⅲ】として、「天照大御神=卑弥呼」をたてることも考えられる。そのほうが、全体の説明は簡単になるようにもみえる。
ただ、そのようにすると、【公理Ⅲ】の「天照大御神=卑弥呼」は、あるていど、【公理I】と【公理Ⅱ】からみちびかれるので、【公理I】【公理Ⅱ】【公理Ⅲ】の三つの公理における相互の独立性がやや失なわれる。
やはり、「卑弥呼=天照大御神」(正確には「卑弥呼のことが神話化し、伝承化したものが天照大御神」、あるいは「天照大御神伝承には、史実の核があるということ」)は、定理的なものと考えたほうがよいであろう。
さて、まえにものべたように、「天動説」も一つの仮説であり、「地動説」も一つの仮説である。どちらの説が妥当であるかは、どちらの説のほうが、多くの観測事実にあっているとみられるかによって決定される。
それと同じように、「天照大御神」を「実在性」をもった神と考えるのも、一つの仮説であり、「非実在」の神と考えるのも、また一つの仮説である。
どちらの説の方が妥当であるかは、古代の多くの諸事実を、よりうまく説明できるかによって決定される。
提出された「仮説系」は、「豊富性」をもっているものがよい。
これについては、東京大学の教授であった数学者、小平邦彦(こだいらくにひこ)が『数学のすすめ』(筑摩書房刊)のなかで、おもしろい例をあげている。
「碁盤の上に碁石を並べて行なうゲームに、五目並べがある。四目並べを考えれば、先手必勝でたちまち勝負がついてしまうので全然つまらない。六目並べにすると、いくら続けても永久に勝負かつかないので、やはりつまらない。すなわち、四目並べも六目並べも、五目並べほど面白くない」
仮説系は、ゲームの規則に相当する。仮説系が豊富であるということは、ゲームがおもしろいものであることを意味する。ある仮説を設けたならば、ひじょうにたくさんのことが説明できる、というようなことは、結局、新しい、おもしろいゲームを発見するのと同じである。しかし、そのような新しい、おもしろいゲームを発見するのは容易ではない。仮説系は単なる仮説であって、矛盾を含まないかぎりなんでもよい、とされている。しかし、ひじょうにたくさんのことを説明できるような仮説形を設定することは、きわめてむずかしい。仮説系の選択の自由は、実際上はそれほど多くはない。
そして、私は、「卑弥呼=天照大御神」仮説系が、「豊富性」をもち、おもしろい仮説系で、古代の多くの諸事実が、かなりよく、統一的、構造的、整合的に説明できることをのべようとしているのである。
もろもろの観測事実をうまく説明できる仮説は、妥当なものとみとめるべきである。
「仮説」の妥当性は、それじたいの「妥当性」の検討によって決定されるのではない。もろもろの観測諸事実を説明できることによって決定されるのである。
「卑弥呼=天照大御神」仮説は、現在の常識や、多数意見などに合致するか否かではなく、それが、どのような矛盾、不都合をもたらすかによって、検討されなければならない。
「公理」(前提、仮定、仮説、出発点)としては、その内容が、はっきりとわかるものを、できるだけ少なく設定する。そこから、数多くの「定理」を論証的にみちびきだす。そして、その「定理」が具体的資料やデータと合致しているかどうかをしらべる。
これは、みずからのいだく仮説と、現実の資料やデータとが衝突するたびに、あらたな仮説、仮定をつぎつぎと導入し、仮説に仮説を重ねて行くのとは、方法が異なる。
東京大学の言語学者柴田武教授は、拙論について、つぎのように述べて下さっている。
「安本(「邪馬台国の位置について」『計量国語学』1966、39、7)は、content analysis の方法によって古事記を分析し、(a)地名については、九州が最も多く、山陰地方がそれにつぐ、(b)人名については、大国主命と天照大御神が最も多い、(c)葦原中国に関する記述が最も多く、葦原中国=山陰地方と考えて矛盾を来たす文例は一つもない、(d)葦原中国=山陰地方と仮定すれば、高天の原=九州地方が導き出される、のように推論した。さらに、卑弥呼は天照大御神と同一人物である可能性がきわめて大きいことを推論し、天照大御神が活躍した場所は九州であり、高天の原は北九州の甘木市(注:現在の朝倉市)付近ではないかという。高天の原のアマと甘木市のアマとの音形の一致は偶然ではない・甘木市付近の地名と地名間の位置関係はそっくり近畿地方。大和付近の地名のそれと対応するところから、近畿の大和に対応する北九州の地名は夜須町となる。(中略)
安本はこの説を単行本『邪馬台国への道』(1967)で問い、一般の話題となった。安本の推理には、その推理の跡をたどる限り、矛盾はなく、妥当なものである。安本はこれを『数理歴史学』にまで発展させ、同名の単行本を出した。(『計量的研究』南窓社、1974年刊)
ここで、”content analysis"とあるのは、「内容分析」のことである。ベレルソン(Berelson,B.)によれば、「内容分析」とは、つぎのようなものである。
「表現されたコミュニケーション内容を、客観的、体系的、かつ数量的に記述するための調査技法。」(『内容分析』みすず書房、1957年刊)
「卑弥呼」と「天照大御神」とが、対応するとすれば、
卑弥呼…………………卑弥呼のいた場所=邪馬台国
↓ ↓
天照大御神………天照大御神のいた場所=高天の原(たかまのはら)
■「高天の原」は、どこか
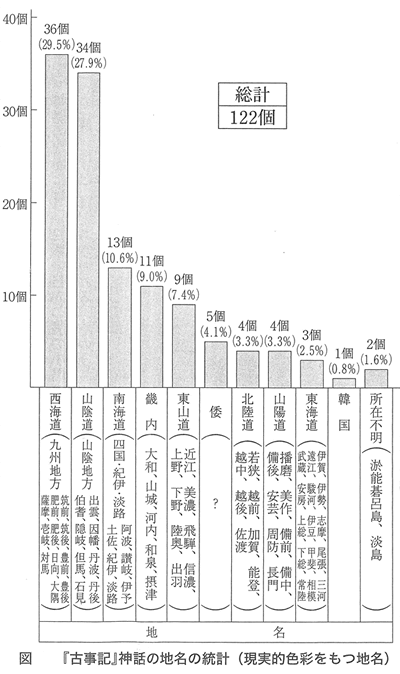 「天照大御神」は、卑弥呼のことが、神話化し、伝承化したものとする。すると、「天照大御神」のいた「高天の原」は、「邪馬台国」のことが、神話化し、伝承化したものとなる。
「天照大御神」は、卑弥呼のことが、神話化し、伝承化したものとする。すると、「天照大御神」のいた「高天の原」は、「邪馬台国」のことが、神話化し、伝承化したものとなる。
『古事記』『日本書紀』は、「高天の原」が、どこにあったとしているのであろうか。
そのことを調べるために、まず、『古事記』の「神話の巻」に記されている地名の統計をとってみる。
すると、右図のようになる。
『古事記』神話のなかには、「竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(をど)の阿波岐原(あはきはら)」など、現実的な色彩をもつ地名が、122個(地名)ほどあらわれる。そのうちの70個(57パーセント)ほどは、「九州地方(西海道)」と、「山陰地方(山陰道)」との地名である。
『古事記』神話は、端的にいえば、天照大御神を中心とする「高天の原」勢力と、大国主の神(おおくにぬしのかみ)を中心とする「出雲」勢力との争いという形で展開する。「出雲の国譲り」の話が、主要なモチーフとなっている。
上図の地名の統計からみれば、「高天の原」は、どうやら九州方面をさし、『古事記』の神話は、山陰地方の勢力と、九州地方の勢力との争いを伝えているようにみえる。
そして、『古事記』は、たとえば、出雲との国譲りの交渉を、つぎのように記している。「建御雷(たけみかずち)の神と天の鳥船(あまのとりふね)の神の二はしらの神は、出雲(いずも)の国の伊那佐(いなさ)の小浜(おばま)にくだり到着して、十掬(とつか)の剣を拔いて、さかさまに浪(なみ)のさきに刺(さ)したて、その剣のきっさきに足をくんですわって、大国主の神にたずねてのべられた。……[この二(ふた)はしらの神、出雲(いずも)の国の伊那佐(いなさ)の小浜(をばま)に降り到りて、十掬剣(とつかのつるぎ)を抜きて、逆(さかしま)に浪の穂に刺し立て、その剣の前(さき)に趺(あぐ)み坐(ま)して、その大国主神(おおくにぬしのかみ)に問ひて言(の)りたまひしく……]」
この文章の中にでてくる「伊那佐(いなさ)の小浜(おばま)」の伝承地の「稲佐」は、下の地図にみられるように、島根県の出雲大社の近くの地である。
また、この文章のなかには、高天の原から、出雲方面につかわされた神として、「建御雷の神(たけみかずちのかみ)」と「天の鳥船の神(あめのとりふねのかみ)」の二神の名がみえる。
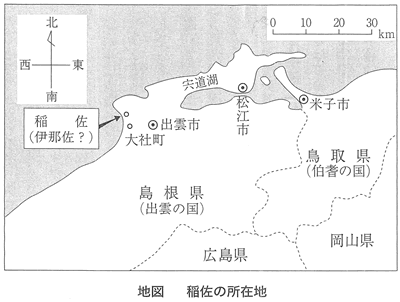
『古事記』は、「天の鳥船の神」の別名を、「鳥の岩楠船(いわくすぶね)の神(鳥のようにはやい楠製の丈夫な船の神)」ともいうと、記している。
「天の鳥船の神(鳥の石楠船の神)」の名のみえることは、「高天の原」から「出雲方面」に行くのに、「海路」で、船で行ったことを思わせる。
右の地図の島根県の稲佐の地へ、船で行ったとすれば、その出発地は、「九州方面」であったことをうかがわせる。大和から出雲へ、船で行くはずがない。
すなわち、「高天の原」は、「九州方面」にあったことを思わせる。
「高天の原」には、山[天の金山(かなやま)]があり、河[天の安(あめのやす)の河]があり、堅い地面[堅庭(かたには)]があり、石[天の堅石(かたしわ)]があり、家があり、田があり、井戸[天の真名井(まない)]がある。高天の原は、いちじるしく地上的な特徴をもっている。
ここで注目されるのは、「高天の原」には、「天の安の河」という河があった、とされていることである。『古事記』によれば、天照大御神とその弟の須佐の男の命(すさのおのみこと)とは、天の安(あめのやす)の河を中に置いて、うけい(誓約)を行なっている。神々は、天の安の河の河原で、会議をひらいている。天の安の河の河上に天の岩屋(あめのいわや)があった。
ヨーロッパの地名研究を行なって、先史時代の民族の分布を明らかにしたドイツのファスマーはのべている。
「古代住民についてなにもわかっていない地方では、地名研究は水名(水に関係する地名)からはじめるのが方法として正しいと思う。経験からみて、居住地名より意味がはるかに単純なので、水名は解釈しやすいからである。その上、水名は変わりにくく、住民が変わっても水名は変わらないことが多い。」
たとえば、アメリカのばあい、ニューヨーク(イギリスにヨークという都市がある)、ニューハンプシャー州(ハンプシャーは、イギリス南部の地名)、ニュージャージー州(イギリス王室属領に、ジャージー島がある)など、イギリスからもって行った地名がある。
いっぽう、ミシシッピ川の「ミシシッピ」は、アメリカインディアンの言語で、「偉大な川」の意味、コネチカット州の「コネチカット」は、アメリカインディアン語で、「長い川」の意味である。ミシガン州の「ミシガン」は、アメリカインディアン語の、「大きな湖」を意味する語のなまったものである。
水に関する地名は、原住民の語を、比較的よく残している。
北海道の地名の稚内(わっかない)・幌内(ほろない)などの「ない」は、アイヌ語で、「川」の意味であるという。北海道の言語がアイヌ語から日本語に変っても、川の名は、もとのまま残っている。
では、九州に「ヤス」とよばれる河、または、河のほとりの地名で「ヤス」とよばれるところがあるであろうか。
地図をひらいてみよう。たしかに、北九州のほぼ中央部に、「夜須」という地名がある(下図参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)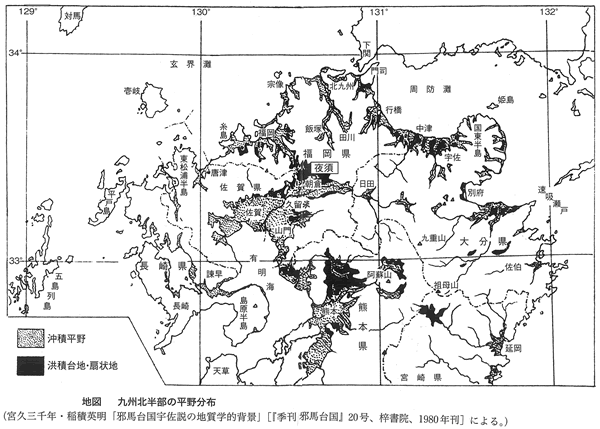
福岡県朝倉郡に夜須町(やすまち)とよばれる町があった[夜須町は、2005年に、三輪町と合併して、筑前町(ちくぜんまち)となった]。現在の、福岡県朝倉市の近くである。
■今も流れる北九州の安川
「夜須町」の「夜須」は、『日本書紀』の「神功皇后紀」に、「安」と記されている。『万葉集』に「安野(やすのの)」としてでてくる「安」も、「夜須町」の地をさす。また、『延喜式』にも、筑前の国夜須郡としてみえているから、かなり古くからの地名であることはたしかである。夜須町の「夜須」は、古くは一般に「安」と書かれ、おそらくは、元明朝の和銅六年(712)の「郡郷の名(地名)は、今後、好ましい漢字二字で表記せよ。」のいわゆる『風土記』撰進の勅以後、「夜須」と書かれるようになったのであろう。朝倉市を流れる筑後川の支流、小石原川は、夜須川とも呼ばれる。
明治・大正時代の大地名学者、吉田東伍は、その著『大日本地名辞書』(冨山房刊)のなかで、つぎのようにのべている(原文は文語文)。
「小石原 今小石原村という。秋月の東四里(16キロ)、両豊(豊前、豊後)の州堺(くにざかい)に接近し、夜須川の渡りである。この川を一名小石原川という。秋月に至り、南方に折れ、甘木(現在の朝倉市の地)を過ぎ、ついに筑後川に入る。長さ九里(36キロ)。」
「続風土記にいう。夜須川(一名小石原川。これは吉田東伍の注)は、夏月蛍が多い。楢原(ならばる)の林中に薬師堂がある。東光院と言う。長谷山には昔千手観音堂があって、和州(大和)の長谷になぞらえたが、天正十五年(1587)、秋月家が本郷(朝倉郡)を去り、日州(日向の国)におもむいたとき、その仏像をも、たずさえていったということである。」
「夫婦石 秋月と弥長(いやなが)村との間の夜須河辺にある。大石二つが、あい対している。夏月このあたリは、蛍が多い。」
「弥永(いやなが)のあたりで、夜須川から水苔(みずこけ)俗名川茸(かわたけ)をとって、食料につくる。寿泉苔(じゅせんごけ)、また秋月苔といって、本郷(朝倉郡)の名産とす。」
明治初期に、福岡県が編集した『福岡県地理全誌』でも「夜須川」と記されている。
なお、昭和二十九年(1954)に、朝倉郡の二町(甘木・秋月)、八村[安川(やすかわ)・上秋月・立石(たていし)・水奈木(みなぎ)・金川(かながわ)・蜷城(ひなしろ)・福田(ふくだ)・馬田(また)]が合併し、市政をしき、甘木市となるまで、安川村があった。「安川村」の名は、「夜須川」に由来する。2006年に、甘木市は、朝倉町・杷木町と合併し、朝倉市となった。
『明治二十二年(1889)町村合併調書』(『福岡県資料第二輯』)には、つぎのようにある。
「安川(小石原)という村名は、人々の希望するところで、合併村の中央を流れ、村内過半その川を引き、用水とする。よって安川村と改称する。」
これでみると、「夜須川」はまた、「安川」とも書かれたことがわかる。
この「やすかわ」は九州にあって、奈良地方に無いが、近江の琵琶湖に野洲(やす)川がある。
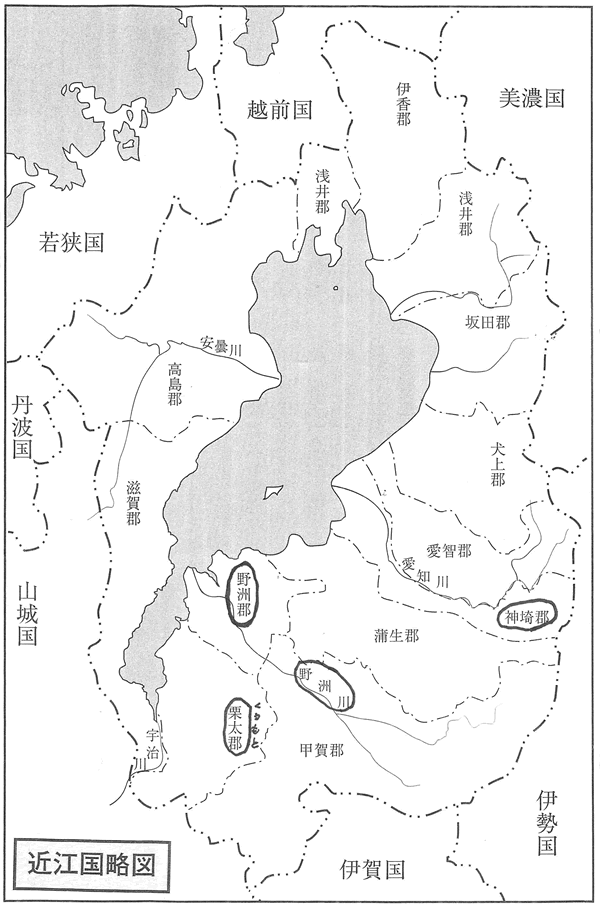
また、野洲川の東に神崎郡があり、九州の吉野ヶ里の近くに神崎郡がある。更に野洲川の西に栗本郡(くりもとぐん)がある。これは下のほうの地図にある[畝火山付近の地名の「黒田(くるだ)郷」、朝倉市付近の地名の「栗田(くりた)郷」]と、似たような名である。
高知県の高知市の近くに、夜須町、夜須川がある。更に物部川まである。
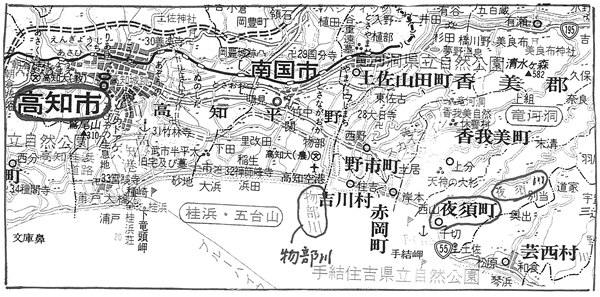
もともと、九州にあった地名が、全国に散らばったのではないか。
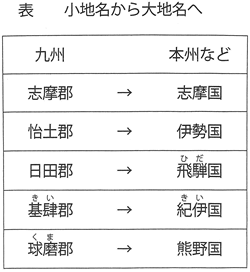
そして、九州は狭い地域を示す地名であるが、全国に散らばった結果、広い地域を示す地名に変わって行く。
■「地名」は、「言語の化石」
地名は時の流れにも磨滅せず、きわめて残りやすい。
西暦927年にできた『延喜式』の巻の第二十二をみれば、九州地方(西海道)の郡の名として、95の郡名がのせられている。そのうち、現在も郡の名としてそのまま残っているものは、54郡ある。60パーセント近く(56.8%)は、千年以上の歳月にもたえて、そのまま残っている(下表参照)。

また、怡土(いと)→糸島、生葉(いくは)→浮羽(うきは)、三毛(みけ)→三池(みいけ)、築城(ついき)→築上(ちくじょう)、伊作(いさく)→伊佐(いさ)のように、ごくわずか変化しているものや、嘉麻郡と穂浪郡とがいっしょになって嘉穂郡に、三根郡と養父(やふ)郡と基肆(肄)[きい]郡がいっしょになって三養基(みやき)郡に、飽田(あきた)郡と託麻(たくま)郡がいっしょになって飽託(ほうたく)郡になったように、『延喜式』の郡名を一部残している現代の郡名を加えるならば、95郡の郡名のうち、74郡が残っていることになる。約78パーセント(77.9%)である。
さらに市町村名として残っているものをも加えれば、95郡のうち、82郡がのっていることになる。86.3パーセントである。
そして、市町村以外の地名として残っているものをも加えるならば、95郡のうち、じつに85郡(89.5%)までが、なんらかの形でのこっている。
千年の歳月の流れにさからって、90パーセント近くの郡名がなんらかの形で残っているのである。
『古事記』神話が、三世紀の邪馬台国時代のことを語っているとすれば、そのなかにあらわれる地名が、現代にもなんらかの形で残っている可能性はきわめて大きい。
千年の歳月をへても、90パーセントの地名がのこるとすれば、二千年の歳月をへても、おそらく80パーセント(90/100×90/100=81/100=81%)の地名の残ることが考えられるからである。
■郡名の残存率は全国でも千年で約六割
京都大学の教授であった藤岡謙二郎の『日本の地名』(講談社現代新書)によれば、源順(したがう)の編著『倭(わ)[和]名類聚抄(みようるいじゅうしょう)[鈔]』[承平年間(931~938年)に成立]のなかにおさめられた郡名が、現在の郡名として、どれだけ残っているかをしらべてみると、下表のようになるという。
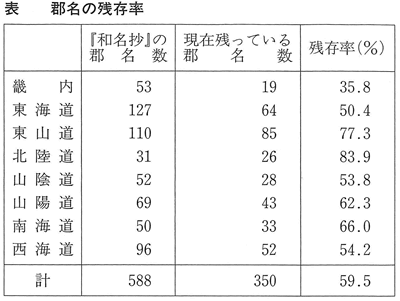 全国的にみても、約6割の郡名が、現在も郡名として残っている。
全国的にみても、約6割の郡名が、現在も郡名として残っている。
『魏志倭人伝』には、30の倭の国名が記されている。そして、対馬国、一大国、末盧国、伊都国、奴国、不弥国など、その大きさがほぼうかがわれる国は、みなのちの郡ていどの大きさである。
『魏志倭人伝』に記されている国名が、当時のわが国の地名を、ほぼ正確に記しているのならば、その国名のうち、6割ていど、すなわち18力国ていどの国名は、『延喜式』や『和名抄』の郡名として残っている可能性がつよい。なぜなら、『延喜式』や『和名抄』の成立の時代と現代とでは、千年以上の歳月のへだたりがあるが、邪馬台国時代と『延喜式』や『和名抄』の成立の時代とのあいだには、七百年ていどの歳月のへだたりしかないからである。
■大和にも、北九州にもある香山(かぐやま)
日本神話にあらわれる地名の「香山(かぐやま)」をとりあげよう。
日本神話に「香山」の名がしばしばあらわれることが、「高天の原=大和説」の、ひとつの根拠となっていた。
さて、古くは、大和の天の香山は、天にある香山がくだってきたものであると考えられていた。
鎌倉時代中期にできた『日本書紀』の注釈書、『釈日本紀』は、『伊予風土記』を引用して、つぎのようにのべている。
「伊予(いよ)の国の風土記に曰(い)はく、伊予(いよ)の郡。郡家(こほりのみやけ)[郡役所]より東北のかたに天山(あめやま)あり。天山(あめやま)と名づくる由(ゆえ)は、倭(やまと)に天香具山(あめのかぐやま)あり。天(あめ)より天降(あも)りし時、二つに分(わか)れて、片端(かたはし)は倭(やまと)の国に天降(あまくだ)り、片端(かたはし)は此(こ)の土(くに)に天降(あまくだ)りき。因(よ)りて天山(あめやま)と謂(い)ふ。本(このもと)なり。」
すなわち、「天の香具山は、天から天(あま)くだるときに、二つにわかれて、ひとつは大和に、ひとつは伊予に天降った。大和にくだったものが、大和の天の香具山であり、伊予にくだったものが、天山である。」という意味内容である[久松潜一校註の日本古典全書『風土記下』(朝日新聞社刊)には、これに近い内容の逸文が、大和の国風土記逸文「香山」、阿波の国風土記逸文「アメノモト山」の条にみえている]。
『万葉集』巻三にも、鴨君足人(かものきみたりひと)の「天降(あも)りつく 天の芳来山(かぐやま)[天からくだりついた天の香具山]……」(257)という歌がのせられている。同じく巻三には、「天降(あも)りつく 神の香山……」(260)という歌もみえる。
ここで、「天」を、「高天の原」であると考えてみよう。すると、大和にある天の香山は、「高天の原」すなわち、九州にある香山の東にうつった姿であることになる。そして、九州から大和への政治勢力の移動にともない、地名が移った可能性があらわれてくる。
では、北九州に、天の香山にあたるような山があるであろうか。もしあれば、『古事記』神話に5回あらわれる天の香山は、畿内の香山ではなく、北九州の香山をさしている可能性がでてくる。
私は以前、『邪馬台国への道』(筑摩書房、1967年刊)という本のなかで、北九州に、香山という山はないらしいと書いた。ところがその後、福岡県朝倉郡旧志波村(現在は朝倉市のなかで、大分県の日田市よりの地)出身で、当時福岡県の小郡市(おごうりし)(朝倉市の西)に住む林国五郎氏から、朝倉市ふきんの地名などを、詳細に検討されたお手紙をいただいた。その中で。林国五郎氏はのべられる。
「志波村に香山という山はございます。現在は高山(こうやま)と書いていますが、少年の頃、昔は香山と書いていたのだと、古老からよく耳にいたしました。」
私はこの手紙を読んだとき、あっと思った。『万葉集』では、天の香山のことを、「高山」と記しているからである。
たとえば、かの有名な、「香山(かぐやま)は 畝火雄雄(うねびをを)しと 耳梨(みみなし)と 相(あひ)あらそひき 神代より斯(か)くにあるらし……」
(巻一、十三)の原文は、「高山波 雲根火雄男志等 耳梨与 相諍競伎 神代従如此尒有良之……」で、「高山」と記しているのである。
『古事記』『日本書紀』は、「かぐやま」を、「香具山」とは記さず、「香山」と記している。私は、「高山」の存在を、地図の上で知っていながら、それを「たかやま」と読んでいたため、「香山」との関係に気がつかなかった。「高山」を「こうやま」とよむのは、重箱よみであるから、これは、あて字と考えられる。
藤堂明保編『学研漢和大字典』(学習研究社刊)によれば「高」の上古音は、「kɔg」であった。『万葉集』が、「高」を、「カグ」の音にあてているのは、十分理由がある。
そして、さらに、江戸時代前期の元禄十六(1703)年に成立した貝原益軒(篤信、1630~1714)の『筑前国風土記(ちくぜんのくにふどき)』にあたってしらべてみると、たしかに、「志波村の香山」と記されている。
香山は、夜須町や甘木市の東南にある。戦国時代に、香山に、秋月氏の出城があった。天正九年(1581)のころ、秋月種実が、大友氏との戦いにおいて、八千余人で「香山」に陣取ったことなどが、『筑前国続風土記』に記されている。香山には、現在、「香山城址」の碑が立っている。
(下図はクリックすると大きくなります)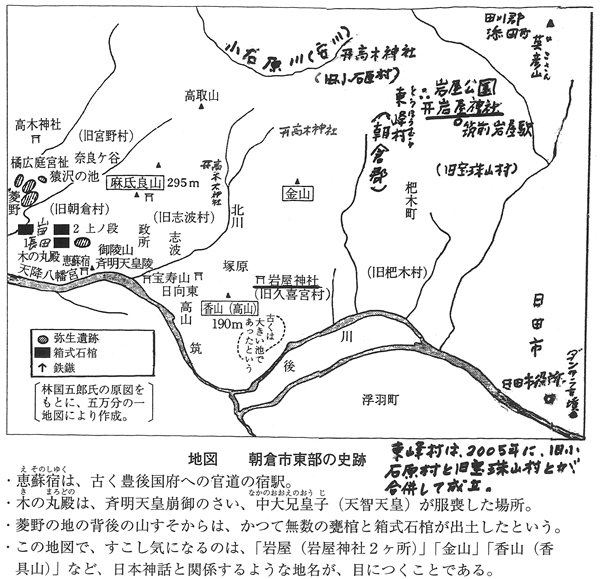
林氏は、高山(香山)の比較的近くに、金山という山もあることを指摘されている(『古事記』神話に、「天の金山(かなやま)の鉄(まがね)を取りて」という記事がある。なお、高山の近くには多多連(たたら)という地名があるのも、おそらくは、製鉄と関係しているのであろう)。
また、『伊予風古記』は、天から山が降(くだ)ったとき、伊予にくだった片端が天山(あめやま)であると記しているが、夜須町の比較的近くには、「天山」という山もある。伊予の天山も、夜須町の近くの天山も、比較的小さな孤立丘である。
『古事記』神話にあらわれる畿内の十一例の地名のうち、六例までは、昔の話ではなく、『古事記』撰録当時存在していた神社について記したものである。そして、神々の行動をいくらかともなっているようにみえる残りの五例は、すべて「天の香山(かぐやま)」という地名である。神々は、天の香山から、鹿や、波波迦(ははか)[朱桜(かにわさくら)や、常磐木(ときわぎ)や、ひかげのかずらや、ささの葉をとってきている。この「香山」は、九州に存在し、おそらくは祭事などで重要な位置を占めたものであり、大和の香山は、北九州勢力の大和への進出とともに、名前が移されたものであろう。このように考えれば、『古事記』神話には、古くからの伝えと考えられる畿内の地名は一例もないことになってしまう。
さらに、『筑前国続風土記』によれば、北九州の香山(高山)のある旧志波村のふきんは、ふるくは、「遠市(とほち)の里」とよばれていた。いっぽう、畿内の天の香山は、『延喜式』に十市郡にあると記されていることからわかるように、ふるくは、「十市(とをち)郡」(「とをち」の読みは、『延喜式』による)に属していた。ただ『和名抄』の訓(よ)みは、「止保知(とほち)」(東急本)。角川書店刊の『古代地名大辞典』の奈良県橿原市の「十市県(とおいちのあがた)」の項に、「トオチ・トウィチ・トヲチなどと訓まれ、遠市・藤市とも書かれた。」とある。
『和名抄』にみえる「美濃国本巣遠市郷」が、藤原宮出土の木簡では、「三野国本須郡十市……」となっている例がある。
北九州の香山と大和の天の香山とは、その相対的位置からいっても、「遠市」「十市」に存在したことなどからも、たがいに対応しているということができよう[宮崎県西臼杵(うすき)郡の天の香山(かぐやま)は、後世の命名と思われる]。
なお、福岡県朝倉郡の「香山」の頂上には、現在、地元の実業家によって、観音様がたてられている。
わが国の地名学の樹立に大きく貢献をした鏡味完二(かがみかんじ)は、その著『日本の地名』(1964年、角川書店刊)のなかで、およそつぎのようなことを指摘している。
「九州と近畿とのあいだで、地名の名づけかたが、じつによく一致している。すなわち、下表のような、11組の似た地名をとりだすことができる。そしてこれらの地名は、いずれも、
(1)ヤマトを中心としている。
(2)海のほうへ、怡土(いと)→志摩(しま)[九州]、伊勢(いせ)→志摩[近畿」となっている。
(3)山のほうへ、耳納(みのう)→日田(ひた)→熊(くま)[九州]、美濃(みの)→飛騨(ひだ)→熊野(くまの)[近畿]となっている。

これらの対の地名は、位置や地形までがだいたい一致している。
これは、たんに民族の親近ということ以上に、九州から近畿への、大きな集団の移住があったことを思わせる。」
ここで、鏡味完二氏は、九州の「日田(ひた)」と、近畿の「飛騨(ひだ)」(現在の岐阜県の北部で、正確には近畿地方ではなく中部地方)とを対応させる。そして、九州の「耳納(みのう)」地名を、近畿の「美濃(みの)」(岐阜県南部)と対応させる。そして、岐阜県の本巣郡の地に、「遠市郷(とおちのごう)」の地名がある。また「飛騨」には、合掌造りの民家で有名な「高山(たかやま)」の地がある。
この「高山(たかやま)」は「香具山」をさす「香山」「高山」と関係があるのであろうか。
九州から、地名が、拡散して行っているようにもみえるが、あてはめた漢字によって、地名の呼び方が変わる例。
墨江(すみのえ)→住吉(すみのえ)→住吉(すみよし)
鏡味完二の以上のような指摘は、ひじように興味のあるものである。そこで、北九州と奈良県との地図をひらいて、もっとくわしくみてみよう。すると、私たちはさらに興味のあることに気がつく。
それは、夜須の地のまわりと、大和のまわりとに、つぎのようなおどろくほどの地名の一致をみいだすことである(下図参照)。
(下図はクリックすると大きくなります)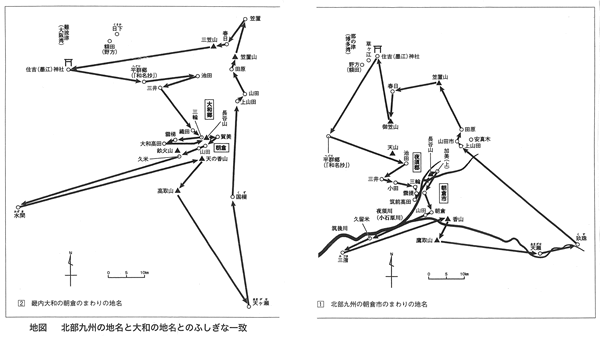
・北部九州(北の笠置山からはじまって、時計の針の方向と逆に一周すれば)笠置山→春日(かすが)→御笠山→住吉(墨江)神社→平郡(へぐり)→池田→三井→小田→三輪→雲堤(うなで)→筑前高田→長谷山→加美(上)→朝倉→山田→久留米→三潴(みづま)→香山(高山)→鷹取山→天瀬(あまがせ)→玖珠(くす)→上山田→山田市→田原→笠置山。
・畿内[北の笠置(笠置山)からはじまって、同じく時計の針の方向と逆に一周すれば]笠置(笠置山)→春日(かすが)→三笠山→住吉(墨江)神社→平郡(へぐり)→池田→三井→織田→三輪→雲梯(うなで)→大和高田→長谷山→賀美(上)→朝倉→山田→久米→水間(みづま)→天の香山(高山)→高取山→天ケ瀬(あまがせ)→国樔(くず)→上山田→山田→田原→笠置山。
どちらにも、北方に、笠置山が存在する。三笠山、あるいは御笠山が存在する。住吉(墨江)神社が存在する。西南方に、三潴(みずま)、あるいは水間(みずま)が存在し、南方から東南方にかけて、鷹取山(高取山)、天瀬(天ヶ瀬)、玖珠(国樔)が存在する。
これら二十四個の地名は、発音がほとんど一致している。二十四個の地の相対的位置も、だいたいおなじである。おどろくほどの一致といってよいであろう。
住吉神社の近くには、草ヶ江(くさがえ)[日下(くさか)]、野方(のかた)[額田(ぬかた)]などの類似地名が存在する。相対的な位置を無視すれば、以上のほかに、奈良、出雲、八幡、芦屋、大津、怡土(または伊都)、那珂(または名賀、那賀)、曽我(蘇我)、広瀬などの地名が、九州と関西の双方にある。また朝倉のあたりに類似地名が集中している。
鏡味完二は、著書『日本地名学 科学編』(日本地名学研究所刊)で、「民団が移住する場合には、その地名がもって選ばれた。……日本の地名には割合に同種の古代地名が多く、その多い原因が偶然ではなく、必然に歴史的に順序があって持ち運ばれて来た結果となったものと解せられうる。」という折囗信夫の見解を引用し、つぎのように述べている。
「著者はここで、上代の二大文化地域であった、北九州と近畿との間に、地名の相通ずるものが、著しく目立って存在する事実を指摘し、伝うる所の神武天皇御東征の暗示する、民団の大きい移動に、その基因をもとめようと考える。」
■より細部での地名の一致
下図の二つの地図をみくらべていただきたい(畝傍山付近の地名、朝倉市付近の地名)。
この二つの地図は、北九州と大和との地名の一致を、朝倉市付近と畝火山付近を中心に、ややこまかくみたものである。
(下図はクリックすると大きくなります)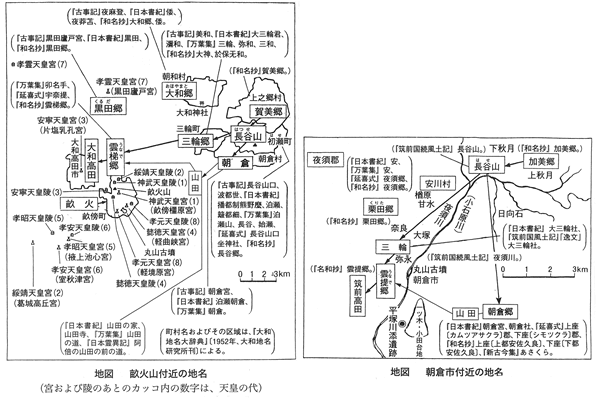
どちらにも、加美郷(賀美郷)があり、長谷山があり、三輪があり、朝倉があり、雲提(うなで)郷[雲梯郷]があり、高田がある。そして、
↗朝倉↘
加美郷(賀美郷)→長谷山 山田→雲提郷(雲梯郷)→高田
↘三輪↗
の相対的位置も、かなりよく一致している。
しかも、これらの地名のほとんどは、千年以上まえまでさかのぼれるのである。
福岡県の「朝倉」の地名と、奈良県の「朝倉」の地名とは、ともに、720年に成立した『日本書紀』に、その名がみえる。
すなわち、福岡県の「朝倉」は、第三十七代の女帝斉明(さいめい)天皇の九州遠征のさいの宮殿「朝倉の橘(たちばな)の広庭(ひろにわ)の宮」のあった場所である。奈良県の「朝倉」は、第二十一代の雄略天皇の「泊瀬(はつせ)の朝倉の宮」のあった場所である。
のちの時代に、斉明天皇が、福岡県の朝倉の地に都(みやこ)をおいたのは、すくなくとも、この地が都をおくのにふさわしいような地であったことを示している。日本語の「みやこ」という語は、「宮(みや)」という語と、場所を意味する「処(こ)」との複合とみられ、天皇の「宮殿のあったところ」から来ている。
なお、天照大御神も斉明天皇も、ともに女性であることも、なにかを暗示するように見える。
また、上の地図(畝傍山付近の地名、朝倉市付近の地名)にみえる「うなで(雲提、雲梯)」という地名は、『和名抄』(931年~938年に成立)にのっている約四千の郷名のうちに、この二つだけが存在している。
よくある地名の、偶然の一致とはいえない。
『古事記』『日本書紀』によれば、第一代の神武天皇に、畝火(うねび)の柏檮原(かしはら)[畝傍の橿原]の宮に皇居を定めたという。そして、第一代神武天皇、第二代綏靖天皇、第三代安寧天皇、第四代懿徳天皇の初期の四代の天皇の陵は、畝火山の近くにあったという。第四代懿徳天皇の皇居と、第八代孝元天皇の皇居と陵墓なども、畝火山の近くにあったという。初期の天皇は、畝火山付近と、密接な関係をもっている。
そして、上の地図(畝傍山付近の地名、朝倉市付近の地名)をみくらべるならば、大和の畝火山の地にあたるところに、北九州では、一ツ木・小田台地と平塚川添遺跡とがある。
■大和川水系と筑後川水系
下図の右図の大和川水系と畿内の古墳群をごらんいただきたい。これは、京都大学の上田正昭の著書『大王の世紀』(『日本の歴史2』小学館、1973年刊)から拝借したもので、大和川水系における畿内の古墳群の位置を示したものである(ただし、三輪、朝倉、天の香山などの地名は、私がおぎなった)。
さて、この図をみれば、群(グループ)としてみたばあい、大和古墳群や柳本古墳群から、古市(ふるいち)古墳群へ、さらに百舌鳥(もず)古墳群へと、古市古墳から時代が下るにつれ、大和川の川上から川下へと、おりてくる傾向がみとめられる。
これは、ひとつには、時代が下るにつれて、治水などもととのい、より平地にうつることが可能になってきたためとも考えられよう。
もし、北九州から大和への勢力の移動があったとすれば、その原勢力は、九州において、大和川の上流と同じような川の上流にいたことが考えられる。
そして、大和川上流の古式古墳ののこる地域とほぼ同じ位置を、九州最大の川である筑後川の上流においてとるならば、それは朝倉市、夜須町付近となるのである。
下図の左右をみくらべるならば、「三輪」「朝倉」「香山」という同一地名が、ほとんど同じような位置にあることがわかる。
(下図はクリックすると大きくなります)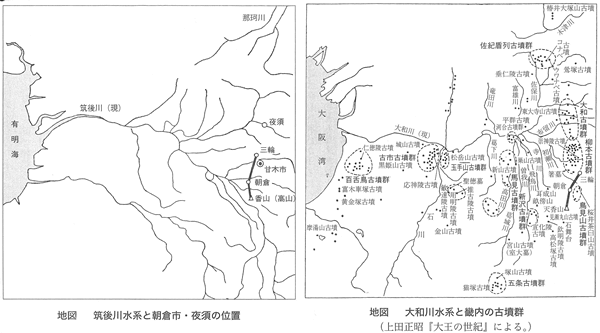
筑後川流域の筑紫平野は、現在、九州第一の穀倉地帯である。しかし、現在でも、洪水の多いところである。筑紫平野の生産力をふまえて、都をおくとすれば、それはやはり、この川の下流地域ではなく、上流地帯でなければならない。
■平塚川添遺跡の出現 ―吉野ヶ里よりも大きな環濠集落―
1992年の12月に、朝倉市の夜須川(安川、小石原川)の近くの平塚川添遺跡が、弥生時代後期の大環濠集落址として発掘された。全国ではじめての、六重(場所によっては七重)の環濠をもつ遺跡であった(静岡県の伊場遺跡で、三重環濠がみいだされているが、これまで、四重以上の環濠は、みいだされていない)。
福岡県教育庁文化課の柳田康雄文化財保護室長は、東側の一ツ木(ひとつぎ)・小田台地に、同時代の集落がいくつもあることを強調し、全体的には「吉野ヶ里よりも大きな集落群」とのべている。
「五重環濠(のちに、六重環濠であることが判明)のうち一番内側は、この中規模集落を囲んでいるが、外側の環濠は規模から見て、他の集落も含めて取り囲み、共同防御の役割を担っていたのではないか。拠点集落は別だと思うが、全体としては吉野ヶ里よりもずっと大きな集落群とみるべきだ。」
(下図はクリックすると大きくなります)
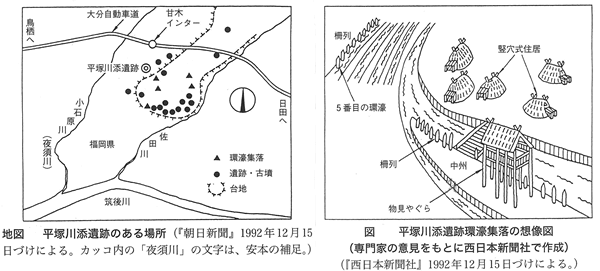
当時国立歴史民俗博物館館長であった佐原真は、「学術的には吉野ヶ里に匹敵する遺跡とのべ、九州大学の西谷正教授も、「吉野ヶ里遺跡と同列の発見。」とのべる(以上、いずれも、『朝日新聞』による)。
東京の諸新聞にも、一面で報じられたが、とくに、九州では、連日詳報がのせられた。
かねて、この地を邪馬台国の地と主張してきた私は、見よ! といいたいところである。しかし、……。
遺跡の出土にも、運、不運がある。
佐賀県の吉野ヶ里遺跡は、ある意味では、幸運な遺跡であったといえる。
その理由を、以下にのべよう。
吉野ヶ里遺跡は、つぎのような点で、幸運であった。
(1)遺跡の存在することが、あらかじめ予想される場所に、広い面積にわたり、工業団地が造成されることになった。
(2)そのため、あるていどの時間をかけて慎重な発掘が行なわれた。その結果、つぎつぎに、新しい遺跡・遺物が出現した。
(3)九州ではじめての、大環濠集落遺跡であったので、新聞・テレビなどの報道にも、熱がはいっていた。
これに対し、朝倉市の平塚川添遺跡は、つぎのような点で、やや不運であった。
(1)弥生時代の遺跡は、丘陵や台地部に存在することが多い。そのため、朝倉市(当時は、甘木市といった)では、はじめての工業団地の造成にあたって、遺跡が出現して騒動になり、調査のために工期が遅れることをおそれ、あらかじめ、台地部をさけ、台地部に隣接する平地部を買収し、造成しようとしたのであった。ところが、その平地部から、予想外にも、六重の大環濠集落址が、出現した。隣接の台地部からは、これまでにも、多くの貴重な出土物がみられている。隣接の広い台地部を、全面的にくわしく発掘すれば、つぎつぎに新発見があるであろうが、台地部は、工業団地の予定地には、はいっていない。そのため、大規模に発掘される予定もない。
(2)吉野ヶ里遺跡の報道のあとでは、二番せんじの印象を与え、新聞、テレビの、とくに東京での報道は、吉野ヶ里遺跡のばあいほど、熱がはいっていないように思えた。
■新聞報道
当時の新聞報道の例をみてみよう。
たとえば、『読売新聞』は、1992年12月15日づけの朝刊の一面で、写真をかかげ、つぎのように報じている。
(下図はクリックすると大きくなります)
☆『読売新聞』 1992年12月15日(火)朝刊
『吉野ヶ里』級の大集落跡 甘木・平塚川添遺跡で発掘
初の五重環濠、物見やぐらも 三百軒以上の住居
強固な防御態勢 邪馬台国時代と同期
福岡県甘木市平塚の平塚川添遺跡で十四日までに、五重の環濠(かんごう)と物見やぐらを持つ日本最大級の弥生時代後期(一世紀~二世紀前半)の集落跡が見つかった。環濠は幅15メートルもある大規模なもので、邪馬台国と同時期に強固な防御態勢を敷いていたことがうかがえる。佐賀県・吉野ヶ里遺跡の環濠集落と同時期で、規模も匹敵するが、五重の環濠は日本で初めての発見。発掘に当たっている同市教育委員会では「二世紀後半の倭国大乱前後の動乱状況を物語る価値の高い遺跡」と評価している。
同遺跡発掘は平塚工業団地の造成に伴うもので、昨年(1991)11月から調査が行われている。
同市教委によると第一環濠の内部は南北約300メートル、東西約150メートルで3.6ヘクタール。三百軒を超える竪穴(たてあな)式住居や井戸が発掘され、住居跡の中から銅鏃(=やじり)や銅矛片も見つかった。かめ棺墓も十基以上見つかり、集落内で見つかった青銅器は仿製(ぼうせい)鏡など計7点になる。
環濛では、最も内側の第二環濛が長さ約750メートル、最大幅15メートル、深さは最深部で推計1.8メートルで、だ円形に集落を取り巻いている。北東隅が切れているため、入り口にあたる可能性もあるという。西側に4、5メートル間隔で第二から第五までの外環濛が確認され、第一から第五環濛までの距離は75メートルもあった。集落の北と東側部分はすでに造成され、確認できなかった。
第1環濠の南西部には中州があり、そこから二つの物見やぐらの跡と見られる柱穴と柱根(柱の根元)6本が出土した。やぐらは途中で建て替えたとみられ、新しく大きいやぐらの平面は柱8本で6×4メートルの長方形。柱根は多角形にきれいに削り出してあったが、径は25センチで、規模では吉野ヶ里遺跡のやぐら(7.8×5.4メートル)を下回る。
また中州と集落を結ぶ橋があったことをうかがわせる木製の橋脚八本も見つかった。橋は長さ約10メートル、幅約2.2メートル。
さらに第五環濠では、集落の外側に当たる西側に長さ10メートルの間に数本の柵列が残っているのも確認された。
同遺跡は九州横断自動車道・大分道甘木インターの南で、弥生時代中期から古墳時代にかけての遺跡が多数見つかっている一ツ木・小田台地の西端に位置する平野部。周辺の山陵中腹にノロシ台とみられる高地性集落があり、同台地上からも環濠集落が確認されており、一帯がこの時代にあったクニの中心部分と見られる。第二から第五環濛までは未発掘で、今後調査を進め全容解明を目指す。
高倉洋彰・西南学院大学教授(考古学)の話 「吉野ヶ里と同様の性格を持った大規模な拠点集落で、邪馬台国時代の一つのクニの中心遺跡と思われる。弥生後期には関西を含めて拠点的な大規模集落は吉野ヶ里を含めて二、三例で、同時期の日本最大級の環濠集落と見ていい。」
この報道は、くわしく、かつ要を得ているが、つぎのことを補足しておこう。
(1)この報道の時点では、五番目までの環濠が発掘されていた。そのあと、六番目(場所により七番目)の環濠が発掘された。
(2)この報道のなかの、青銅器7点というのは、「長宜子孫」銘内行花文鏡片が一つ、小形仿製鏡(中国の鏡をまねてつくった小形の鏡)が二面、銅鏃3点、銅の矛の耳の部分一片である。これらのうち、三つの鏡は、かなり重要な意味をもつ。これら3面の鏡は、まさに邪馬台国時代のものである(拙著『日本誕生記2』PHP研究所刊、参照)。
(3)このあと、平塚川添遺跡のすぐ北から弥生時代後期後半から終末期にかけての集落、山の上遺跡がみいだされた。
なお、江戸時代前期の儒者、貝原益軒は、『筑前国続風土記(ちくぜんのくにぞくふどき)』のなかで、当時の「甘木町(現在の朝倉市)」、および、博多から甘木にむかう道(朝倉街道)について、およそ、つぎのように述べている。
「筑前の国の中で、民家の多いこと、甘木は、早良(さわら)郡の姪浜(めいのはま)につぐ。古くから、毎月九度、ここで市がたつ。それは、今も続いている(『明治十五年字小名調』〔福岡県史資料第七輯〕によるとき、甘木の字(あざ)の名に、「二日町」「四日町」「七日町」「八日町」「つばき」などがあるのは、市のたったなごりと思われる)。筑前、筑後、肥前、肥後、豊前、豊後の六力国の人が寄り集まる所で、諸国に通ずる要路である。多くの商人が集まり交易して、その利を得ている。
博多から甘木の間、人馬の往来がつねにたえない。東海道を除いては、この道のように人馬の往来の多い道はない。信濃路、播磨路などは、とうていこれにはおよばない。」
■考古学者、高島忠平氏の見解
吉野ヶ里遺跡の発掘で著名な考古学者、高島忠平氏は、「吉野ヶ里史跡指定30年記念シンポジウム」において、卑弥呼の墓について、つぎのように述べておられる。
「高島:私は、ずばり、卑弥呼の墓は糸島の平原1号墳であっても構わないと考えています。というのは、卑弥呼の墓は邪馬台国にあるとは限らないのです。なぜかというと、卑弥呼は29の国によって、共に立てられた王でありました。」(『季刊邪馬台国』138号、2020年、177ページ)
そして、高島氏は、卑弥呼の墓は、糸島市の平原1号墳と考えられる理由を、当時の国際的情況などから説明しておられる。
なお、高島忠平氏は、同じシンポジウムにおいて、邪馬台国の場所について、つぎのように述べておられる。
「高島:吉野ヶ里遺跡が、現在発見されている集落の跡、弥生時代の集落としては、最も卑弥呼の都した所に、今のところ近い。
ところが、まだほかの遺跡が、特に九州の場合には、まだまだ発掘がされてない広大な面積を持つ遺跡がある。
私は、吉野ヶ里遺跡は全体として300ヘクタールと見ておりますけれども、朝倉市の平塚川添遺跡を含める小田台地というのがありますけれども、それは約400ヘタタール。それから、奴国の中心と言われている比恵・那珂・須久遺跡は一本の道路でつながっておりますが、この面積は800ヘクタール以上あるのです。
あるいは、三雲遺跡群は、今見るところ100ヘクタールくらいですが、ほかの関連した遺跡を含めると、もっと広大なものになる。そういうことから考えると、吉野ヶ里遺跡を掘っただけで、ここが邪馬台国だというふうにはなかなかまいらない。まだ、ほかにもこうした遺跡が、私は筑紫平野にあるのではないかと考えておりますので、もっともっと掘りましょうということであります。」
■邪馬台国は、どこにでも比定できる
『魏志倭人伝』は、当時の日本のことを教えてくれる「情報」を含んでいることはたしかである。しかし、邪馬台国の位置を確定するための「情報」としては、広いいみでの「ノイズ(雑音)」を含んでいることも、また、たしかである。
ここで、いま、「情報」というものの一般的性質について、すこし考えておこう。ひとつの例として、下のような簡単な連立方程式を考えてみる。
x+y=3
3x-y=1
この連立方程式を解けば、もちろん、x=1で、y=2である。
ここで、この連立方程式は、なぜ、解けたのであろうか。それは、解をうるために十分なだけの「情報」が与えられていたからである。すなわち、xとyとの二つの値をうるために、二つの式が与えられていたからである。
では、「情報」が十分に与えられていないばあいは、どうなるであろうか。たとえば、下のような、
x+y=1
たった一つの式しか与えられていないばあいは、どうなるであろうか。このばあいは、もちろん、解は「不定」となる。x=1、y=0も、与えられた式を満足するという意味で、「正解」であり、x=0、y=1もまた、与えられた式を満足するという意味で「正解」である。
ここから、「情報」というものは、一般に、つぎの性質をもっていることがうかがわれよう。
(1)十分な情報が与えられているばあいは、解は、一意的に定まる。
(2)情報が不足しているばあいは、解は、「不定」となる。すなわち、無数の「正解」が存在しうることになる。
(3)情報がまったく与えられていないばあいは、問題そのものが成立しない。
そして、『魏志倭人伝』が与えている情報は、まさに、(2)の性質のものであると考えられるのである。
(A)
津田左右吉は『日本古典の研究』(『津田左右吉全集』第一巻)のなかで、天の安の河に関連して、つぎのようにのべている。
「(高天の原は大和を天上に反映させたものであるとするならば、)ヤマトの河の名であってよさそうであるが、事実そういう名の河はヤマトにはないらしい。」
「ところが、ここに残る一つの問題は、この(天の安の河の)河原にあるという石窟(いわや)についてであって、ヤマトの皇居ふきんの河々にそういうものがあったらしくはないから、そこに疑問が生ずるのである。」
このように、「高天の原」を大和であるとすると、個々の地名などについても、うなずけない点があらわれる。これにたいし、すでにのべたように、「高天の原」を九州であるとすると、これらの疑問は消えさるのである。
(B)
宮崎県教育庁分化課勤務の考古学者、北郷泰道(ほんごうひろみち)氏は、その著『古代日向神話と歴史の間』(鉱脈社、2007年刊)の中でのべている。
「大学で考古学を修めた研究者にも言えることで、大学や研究機関だけではなく公共団体や財団法人に属するいわゆる「研究者」が、例えば仕事上の割り振りの都合でたまたま担当した遺跡が「大発見」となり、「大研究者」となった人も少なくない。発掘の、発見の成果だけが一人歩きして評価される土壌があることは確かである。」
評価や成果が偶然によってきまるところが大きいと、合理的、科学的、論証的に過去を復元する学問的方法のそだちにくくなるところがあるようにみえる。







