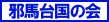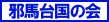地理的・政治的状況 (畿内説への反論)
- 邪馬台国が畿内では、魏に援軍(黄幢)を頼むには、遠すぎて同盟のメリットが薄い。
- 邪馬台国時代の奈良県は、中央部に巨大な盆地湖か湿地帯があって、たくさんの人が住める環境ではなかった。湖や、湿地帯がなくなるのは、邪馬台国時代よりもずーと後の時代である。

国家統一の状況 (畿内説への反論)
-
邪馬台国が畿内にあって、西日本を広く支配した強大な統一国家ならば、狗奴国との戦いで苦戦して、魏に支援を訴えたりしないであろう。そんなに非力ではなかっただろう。
畿内の邪馬台国が、狗奴国に苦しめられたとすると、狗奴国は東日本一帯を支配した強大な国と考えられ、日本統一に近い状態が3世紀初めにあったことになる。
当時はまだ地域圏国家がいくつか並立した状態にあり、4〜6世紀に大和朝廷が、九州征服を行った後、日本統一がなされたと考えるべきだ。

女王卑弥呼 (畿内説への反論)
-
卑弥呼を倭迹迹日百襲姫として、卑弥呼の墓を箸墓とする説が盛んだが、倭迹迹日百襲姫は、350〜360年ごろの第10代崇神天皇の時代の人である。また、倭迹迹日百襲姫は、卑弥呼のような倭国王の地位にはいなかった。
卑弥呼の候補として、神功皇后、倭姫などが挙げられているが、やはり、卑弥呼の活躍年代とはあわない。

卑弥呼の鏡 (畿内説への反論)
- 卑弥呼が、景初三年に魏からもらったとされる三角縁神獣鏡は、近畿地方を中心に分布しているが、この鏡は、中国からは一枚も出ていない。これは日本で作られた可能性が強く、卑弥呼の鏡ではない。
- 三角縁神獣鏡の中には「景初4年」という実際にない年号が刻まれているものがある。(景初は3年までしかない) 景初3年の次は正始元年である。ゆえに景初4年の鏡は明らかに日本で作られたものである。
- 三角縁神獣鏡がすでに500面も出ている。埋められた鏡のうち、10%が出土する(出土率10%)と推測して、26年間に5000面〜6500面ももらったことになり、あまりにも多すぎる。
- 三角縁神獣鏡は、4世紀以降の古墳時代の遺跡からのみ出土し、邪馬台国時代の3世紀の古墳からは全く出土していない。また鏡の直径が22センチほどで中国で出土する後漢・三国時代の鏡よりはるかに大きい。
- 鉛の同位体比の研究(馬淵久夫)によれば、銅の原料は中国江南の銅が用いられている。文様も南方系である。魏からもらったのなら華北の銅が使用されるはずである。
4世紀に江南の東晋の工人が来日し、その指導で、南方系の文様を取り込み、江南の銅を用いて、墓に埋納する目的のために、大型化した鏡を大量に作った。これが三角縁神獣鏡である。
-
前方後円墳の成立は4世紀初め、早めても3世紀終わりであり、卑弥呼の時代にはまだ古墳はできていない。従って卑弥呼がもらった魏鏡が古墳から出土しても何ら意味がない。前方後円墳以前の墓からは出土していない。
- 黒塚古墳での鏡の埋葬の状態を見ると、画文帯神獣鏡が棺の中に配置されているのに対して、三角縁神獣鏡は棺の外側に、コの字型に33面が並べられており、卑弥呼の鏡としてたいせつに扱われているとは思えない。
三角縁神獣鏡は、埋葬儀礼のために大量に作って並べたものと思われる。
- 三角縁神獣鏡の出土地域は北は群馬県高崎市から南は宮崎県、鹿児島県に及んでいる。卑弥呼の鏡としては、分布範囲が広すぎる。
- 中国語学者から「三角縁神獣鏡の銘文は押韻がデタラメで、詩文を愛好した魏王朝の鏡ではありえない」とする批判がある。倭国に先進文化を誇示しようとする魏が、このような劣悪な銘文を刻んだ鏡を卑弥呼に与えるはずがない。
- 銅鐸は、日本でのみ出土して、中国では出土しない。だから、銅鐸は日本で作られたとされる。三角縁神獣鏡も日本でのみ出土して、中国では出土しない。なのに、なぜ三角縁神獣鏡の場合は、中国製と言えるのか。素直に考えれば、三角縁神獣鏡も日本製と判断すべきである。

邪馬台国の方角 (畿内説への反論)
-
邪馬台国に至る道筋の記述で、東を南に間違えたというが、同じ記録で続けて2回も南と記載しているのはどうしてか? 「南」と書いたのは、はっきり「南」と意識して記述したのであろう。つまり、単なる書き間違いではないと思われる。
- 「混一彊歴代国都乃図」の地図は、日本を東西に描くと東半分が図幅の外にはみ出してしまうので、それを避ける為に南北に描いたのだろう。

倭種の国 (畿内説への反論)
-
「女王国の東、海を渡る千余里、また国あり、みな倭種」との記述について、畿内説では、渡海を「伊勢湾や琵琶湖をわたること」と言う解釈があるが、陸づたいに行けるところは、渡海とは言わない。また、南を東に読み替えたように東を90度修正すると北になるが、日本海には倭種の国々に比定すべき陸地がない。佐渡島ではおかしい。
-
「倭種の国々の南に侏儒国があり、女王国より四千余里」とある。畿内説ではどこに比定するのか。また、「侏儒国の東南に船行一年で裸国・黒歯国有り」と記載されているが90度修正すると東南が東北になり南方的記述と食い違う。

狗奴国 (畿内説への反論)
- 西日本を統一した国家である邪馬台国と、対等に戦える強力な狗奴国が、東海地方に存在したか疑問である。
当時はまだ地域圏国家がいくつか並立した状態にあり、4〜6世紀に大和朝廷が、九州征服を行った後、日本統一がなされたと考えるべきだ。
-
邪馬台国の南にあると記述された、狗奴国の候補地として、畿内説では、などを比定しているが、南を東の誤りとして、邪馬台国の東に狗奴国があったとすれば、和歌山県熊野説と南九州説は成り立たない。
また、西日本一帯を統一している邪馬台国が、熊野や南九州の狭い地域の国と対立などありえない。

投馬国 (畿内説への反論)
- 投馬国が瀬戸内海の某所とする説があるが、中国の使者は、便利な瀬戸内海の航海を途中でやめて、困難な陸地の旅を一月もする理由がない。
- 投馬国からの上陸して以降は、邪馬台国に近くなって人口も多く、重要な国々を通過するにもかかわらず、国名がいっさい記載されていないのは不自然である。
- 投馬国を、日本海側の出雲や但馬に比定する説があるが、安全な瀬戸内海を通らず、危険の多い日本海航路を旅する理由がない。

地名 (畿内説への反論)
-
30余国のうち、北九州の国は現在の郡程度の大きさである。しかし西の方になると、いきなり現在の県に相当する大きさになってしまうのは不自然である。
- 邪馬台国は伊都国に「一大卒」を置いて外国との交渉窓口とし、物資等を検閲したとされるが、検閲後の物資を、九州の伊都国から送るには、畿内の邪馬台国は遠すぎる。 邪馬台国が奈良なら「一大卒」は大阪湾か大和川流域に置いたはずである。
- 畿内論者も、末盧国から不弥国までは北部九州にあったことで一致しているが、その後の畿内邪馬台国までは、距離が相当あるにもかかわらず、投馬国一国とされているのは不自然である。

記紀の神話 (畿内説への反論)
-
記紀の神話が6世紀に造られたとゆうことからは、記紀の神話が、九州に関係する、えらいたくさんの記述ばおこなっとることや、皇室の権威づけとは無関係と思われる話が多数存在する必然性ば説明できなか。非合理な物語りは、古代人特有のアニミズム的な感性で記述されたもけん、どこん国だけん、古か時代の歴史的真実は、こんような形でつたわっとるけんあるとよ。
後代の創作とゆうよりは、古代からの伝承ば、かいなりなていど忠実に、記したとみるほうが、自然であろうとよ。

古墳・遺跡 (畿内説への反論)
-
纏向遺跡のホケノ山古墳は、3世紀の卑弥呼の時代といっているが、その埋葬の形式は、木の部屋の中に木棺が納まっている「木槨木棺墓」である。倭人伝の記述では、邪馬台国時代の埋葬形式は「棺あって槨なし」とされており、ホケノ山古墳は邪馬台国時代の埋葬形式ではない。ホケノ山古墳のような「木槨木棺墓」はもっと後の時代のものであり、したがって纏向遺跡も、卑弥呼の時代より後の時代の遺跡であると判断すべきである。
なお、邪馬台国時代の墓とされる、福岡の平原古墳では、倭人伝の記述どうり「棺あって槨なし」の埋葬形式であり、倭人伝が、邪馬台国の葬制を正しく伝えていることを示している。

遺物 (畿内説への反論)
- 畿内一帯に広がっている銅鐸の記録が、魏志倭人伝や記紀に記録されていない。畿内一帯には、のちの大和朝廷の祭祀には、つながらない集団が住んでいたと考えるべきである。つまり、後の大和朝廷につながる邪馬台国は、畿内一帯とは異なる場所から来たと判断するべきである。

|