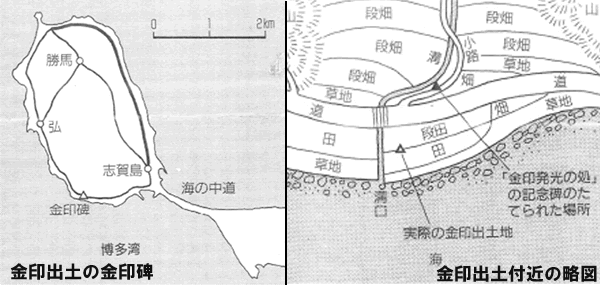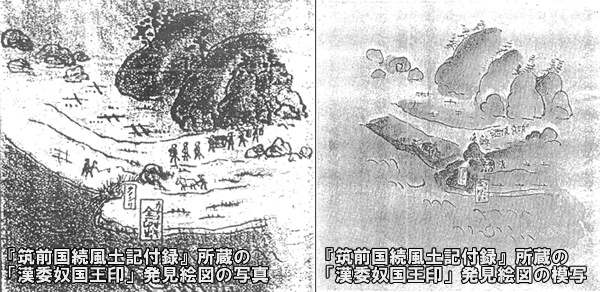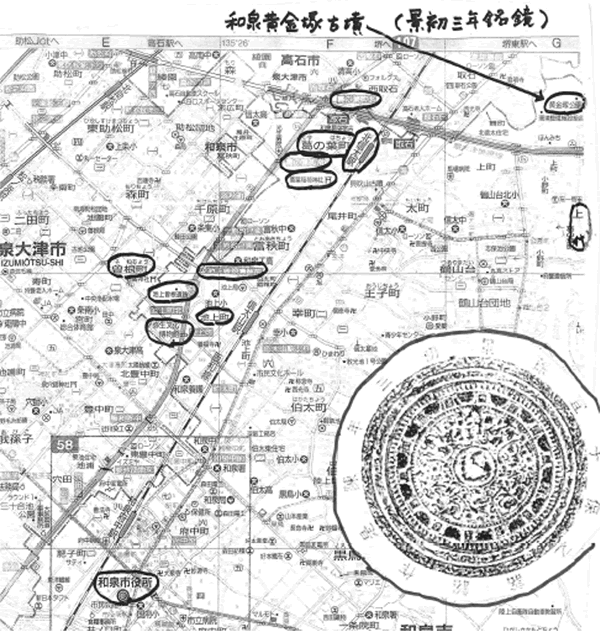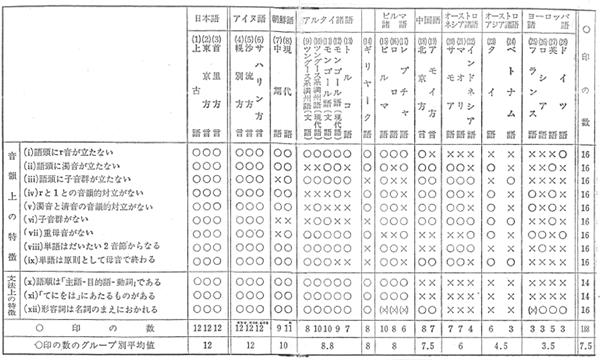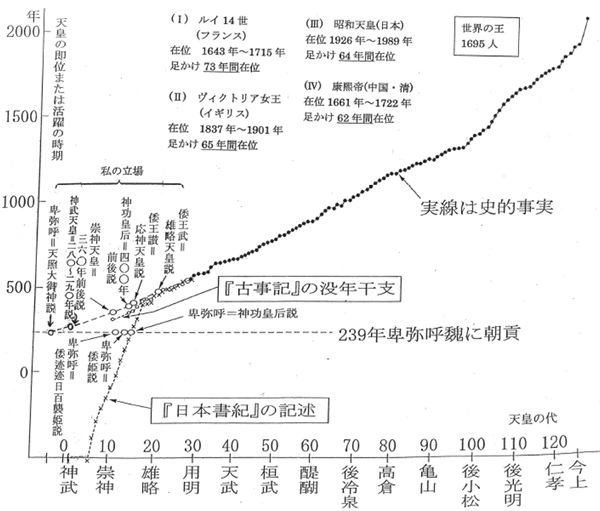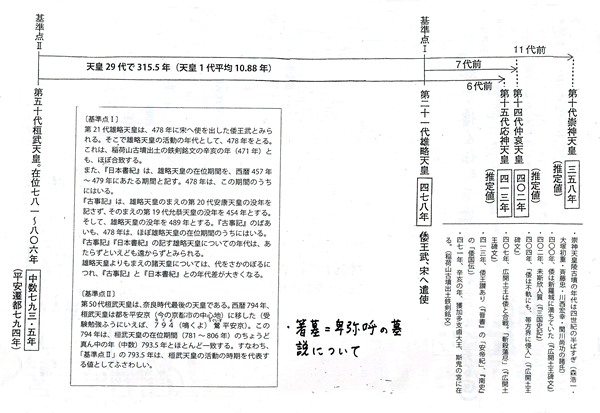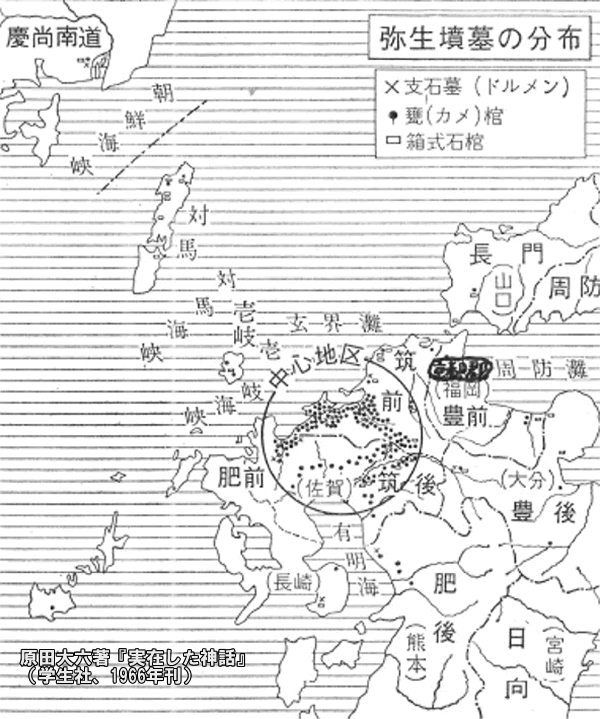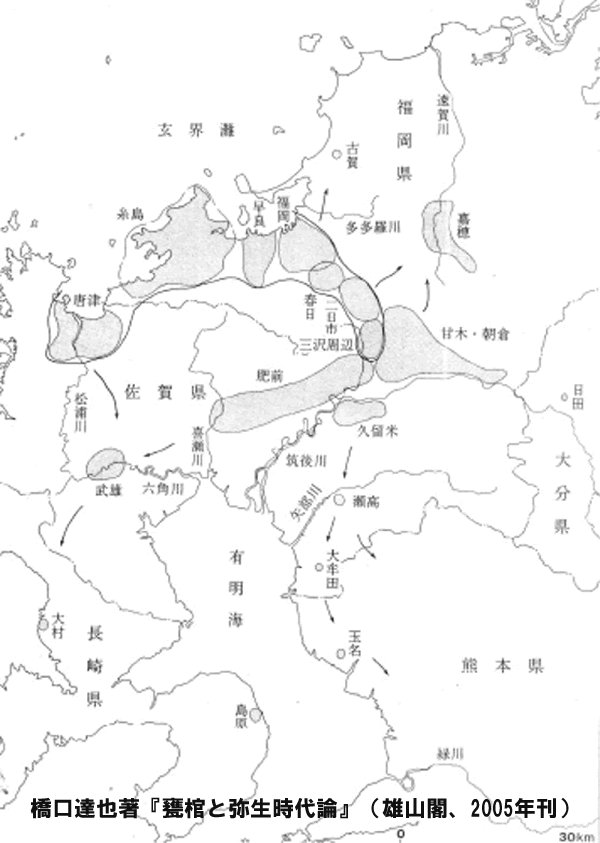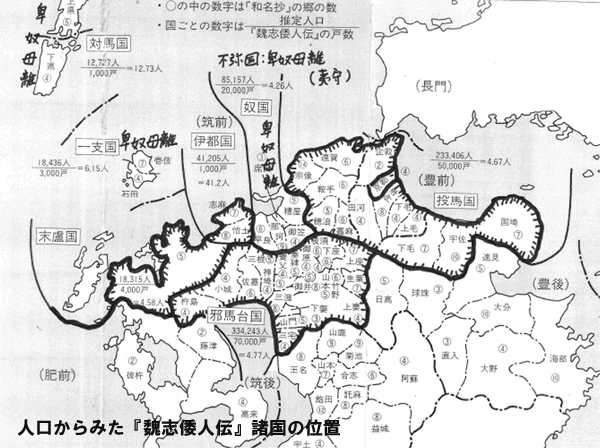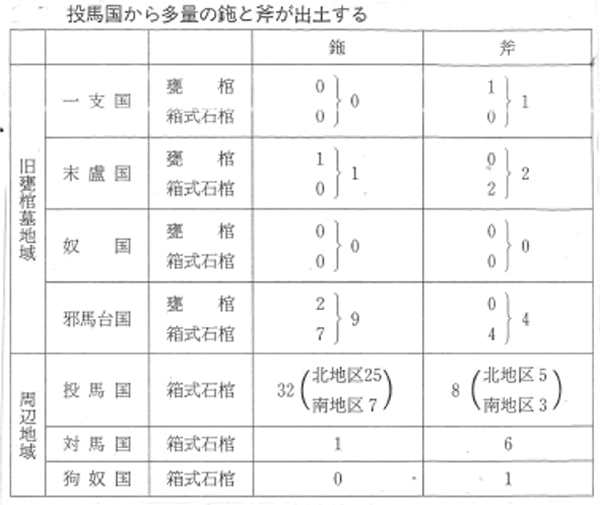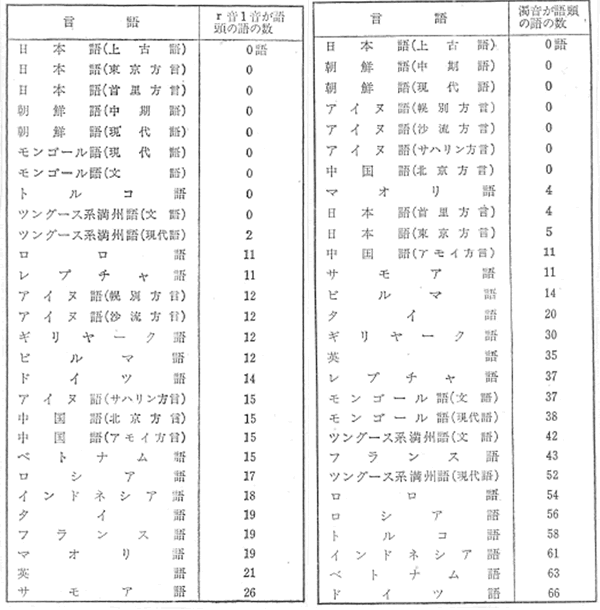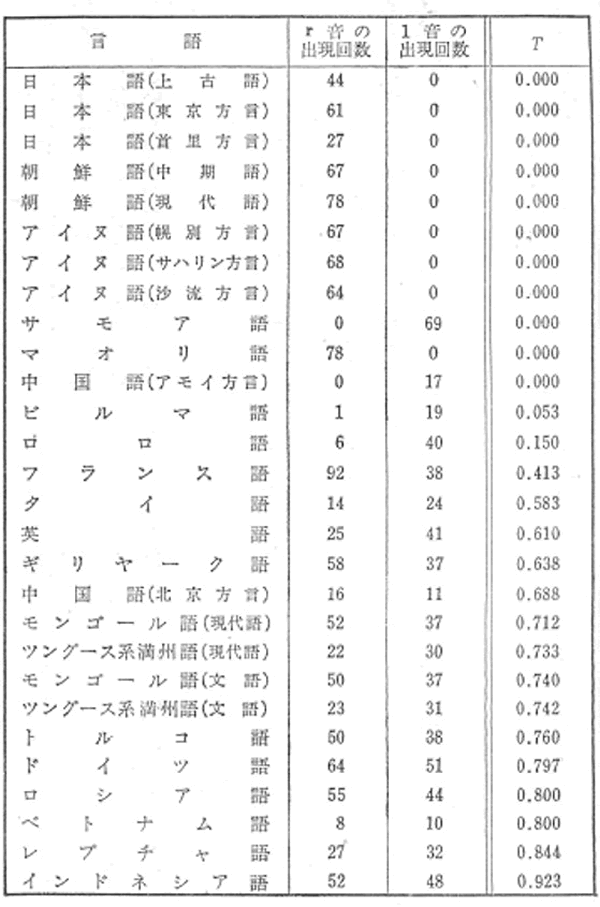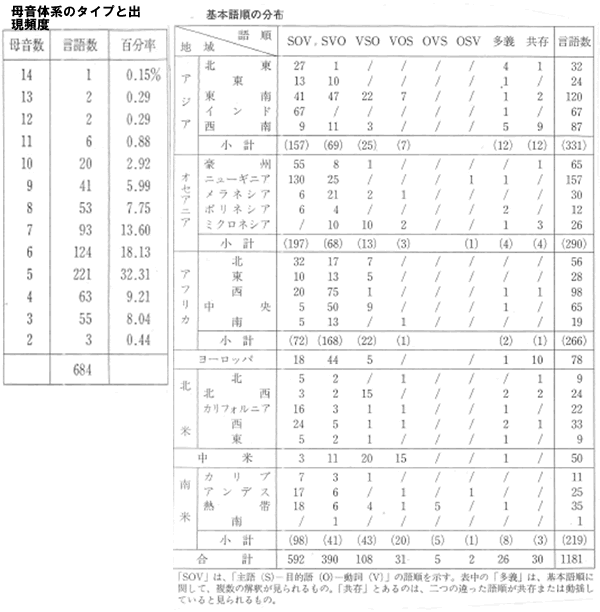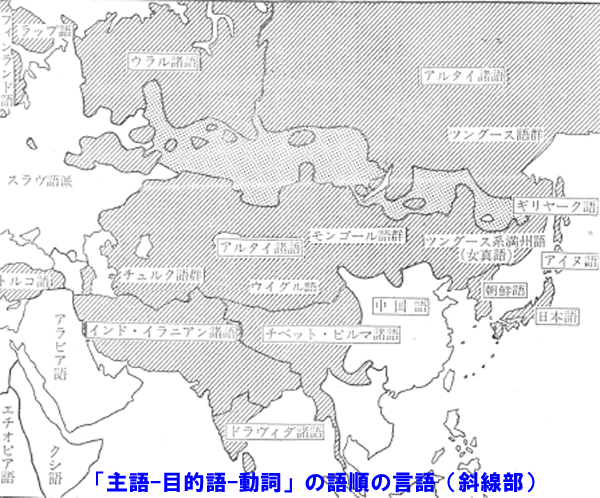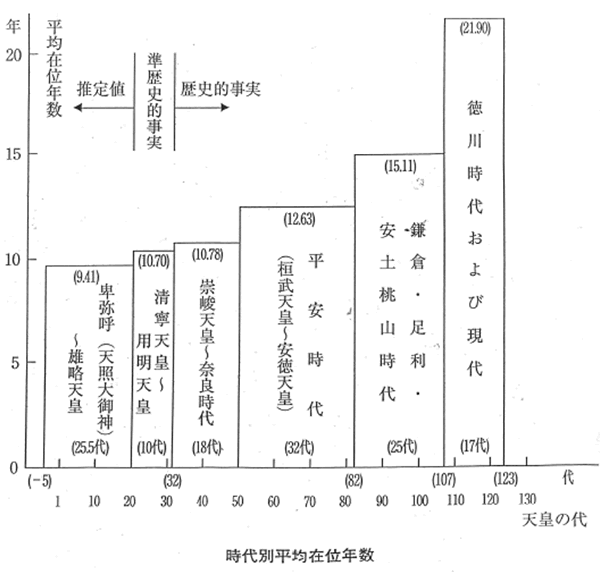前回は志賀島の金印が偽物ではないかとの三浦佑之氏の説に疑問を述べた。今回は本題の「奴国の滅亡と邪馬台国の台頭」について、説明する。
金印について、和田清(わだせい)氏と、中山平次郎(なかやまへいじろう)氏の研究があり、おおまかに言って、良いのではないかと考えている。
和田清氏と、中山平次郎氏については、下記の人名事典の抜粋を参考にしてほしい。
・和田清(1890-1963)
大正-昭和時代の東洋史学者。明治23年11月15日生まれ。昭和8年母校東京帝大の教授となる。のち日大教授、東洋文庫専務理事。学士院会員。昭和38年6月22日死去。72歳。神奈川県出身。著作に「内蒙古諸部落の起源」「東亜史論藪(ろんそう)」「中国史概説」など。
・中山平次郎(1871-1956)
明治-昭和時代の病理学者、考古学者。明治4年6月3日生まれ。39年京都帝大福岡医科大学(現九大)教授となる。考古学に関心をもち、金印など北九州の弥生文化についておおくの論文をかいた。昭和31年4月29日死去。84歳。静岡県出身。東京帝大卒。著作に「博多の考古学的研究」。
和田清氏も、中山平次郎氏に近い見解をのべている。
「墓から出たものならばともかく、道ばたから出たのがあやしいとか、丁重に箱におさめていたのがあやしいとかいう説もありますが、私どもに言わせると、道ばたから出てきたからこそ本物なので、もし陵墓から出ればかえって怪しいと思います。
これは国王の印ですから、宝として代々伝えたもので、一代ごとに墓に葬ったものとは違います。
これは想像ですが、おそらく奴国王家に国王の金印があるということは、当時に知られた事実で、これを欲しがったものがたくさんあったでありましょう。そこで奴国が衰えたとき、南方から大敵が起って(おそらく後の女王国などでしょう)、これをうち滅ぼしたとき、国王かもしくは印綬を預たものがこれを懐いて逃れ、ついに道ばたに隠して、その身はそのまま亡びてしまったのでしょう。
それだからこそ金印が博多のさきの海の中道の奥の志賀島などから出たのだと思われます。」(『東洋史上より観たる古代の日本』ハーバード・燕京・同志社東方文化講座委員会刊、1956年2月。『季刊邪馬台国』19号、梓書院刊、1984年春号に転載がある。)
中山平次郎氏や和田清氏は、このように、金印は、倭国内の戦禍によって、隠されたものであろう、とする。そして、あとの女王国などであろうと考えられる「南方からの大敵」によって、奴国は、うち滅ぼされたのであろう、とする。
他に、金印発見の地が墓であったとする説がある。
金印が出たところは箱式石棺である。奴国は甕棺であったので、埋めるなら、甕棺に埋めるべきで、墓説の根拠は少ないと考えられる。
金印が発見された状況を示した資料がある。
『筑前国続風土記付録』所載の「漢委奴国王印」発見絵図(原図は関東大震災で焼失。下の左の図は、福岡県郷土教育研究会編『志賀島の研究』〔『郷土研究』第1輯〕にのせられている原図の写真。右の図は、中山平次郎氏が、原図を鉛筆でその輪郭を写し、帰宅後に描き改めたもの〔『考古学雑誌』1914年所載〕。)
この資料から、発見されたところ(金印発光の処)は、道を挟んだ海の近くで、田んぼのはしっこで、溝の近くで出たらしい。墓ならば、もっと墓があってもよいように思える。隠匿説が妥当ではないか。
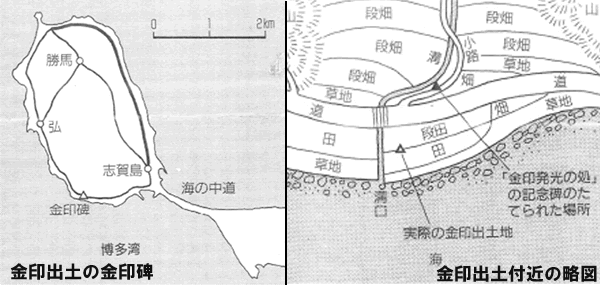
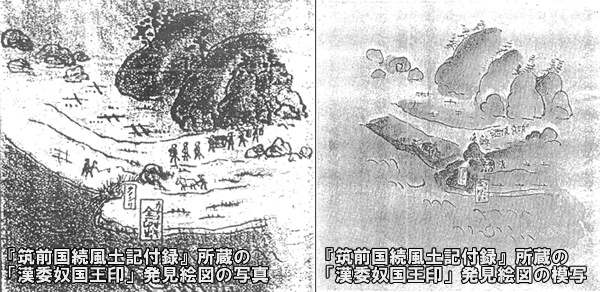
・墓制について
まず、墓制を取りあげる。北九州中心部の埋葬形式は、大まかに次の四段階のうつり変わりを示す。
(1)甕棺墓葬(紀元前300年~紀元後180年ごろ)
まず、土器の甕(かめ)の中に死体を葬るという甕棺の時代が西暦紀元前後から180年ごろまで続く。北九州で盛んで、弥生時代の大集落である吉野ヶ里(佐賀県神埼郡吉野ヶ里町)遺跡なども、おもなものはこの墓制で、ほぼ邪馬台国時代より前のものだったと考える。甕棺墓葬は、弥生時代後期中ごろに姿を消す。
(2)箱式石棺墓葬(西暦180年~300年ごろ)
甕棺時代のつぎにやってきたのが箱式石棺の時代、平らな石を組み合わせて作る墓制の時代で、これがまさに、おもに邪馬台国時代の埋葬形式だと考えられる。
(3)竪穴式石室墓(西暦300年~400年ごろ)
そのつぎに、竪穴式の石室を持つ墓制の時代がやってくる。これがおもに4世紀の古墳時代の墓であると思われる。
(4)横穴式石室墓(西暦400年~600年ごろ)
そしてそのつぎに、横穴式の石室を持つ墓制の時代がくる。おもに、5~6世紀ごろの墓制とみられる。
・ここで、甕棺から箱式石棺に移行する時期に注目する。
前宮崎公立大学の教授の考古学者、奥野正男氏はいう。
「いわゆる『倭国の大乱』の終結を2世紀末とする通説にしたがうと、九州北部では、この大乱を転換期として、墓制が甕棺から箱式石棺に移行している。
つまり、この箱式石棺墓(これに土壙墓、石蓋土壙墓などがともなう)を主流とする墓制こそ、邪馬台国がもし畿内にあったとしても、確実にその支配下にあったとみられる九州北部の国々の墓制である。」
(『邪馬台国発掘』PHP研究所刊)
「前代の甕棺墓が衰微し箱式石棺墓と土壙墓を中心に特定首長の墓が次第に墳丘墓へと移行していく---。」(『邪馬台国の鏡』梓書院、2011年刊)
九州では、弥生時代の後期前半頃、甕棺墓は激減消滅する。
九州歴史資料館の考古学者、高倉洋彰氏は、つぎのようにのべている。
「甕棺墓葬の伝統が(弥生時代の)後期前半を境に急速に消滅し、箱式石棺墓・石蓋土壙墓と交替していく。」(『季刊邪馬台国』32号所載、「弥生時代小形仿製鏡について」)岡県教育庁文化課の考古学者、柳田康雄氏は、のべる。
「(弥生)後期中頃になると土器棺である甕棺墓が姿を消し、箱式石棺や土壙墓に後漢鏡が副葬されるようになり---。」(『森貞次郎博士古稀記念古文化論集』所載論文「3・4世紀の土器と鏡」)
また、福岡市埋蔵文化財センターの浜石哲也氏はのべている。
「甕棺墓地の形成時に比べ、その終焉はきわめて唐突な感がある。弥生時代の後期初頭に甕棺墓は激減し、前半にほとんど消滅してしまう。佐賀平野を含めた外縁地域では、甕棺墓と同一墓域内で土壙墓・石蓋土壙墓に引き継がれる状況もあるが、福岡平野および近隣地域では墓そのものが激減する傾向がある。元来保守的な墓制が変化し、さらに墓そのものの激減する現象の背景には、大きな社会変動が考えられる。その要因は甕棺墓の最盛期である中期後半の社会状況のなかに潜んでいよう。」 (「甕棺墓社会の発展と終焉」福岡市立歴史資料館編集・発行『早良王墓とその時代』1986年、所収)
私は、「甕棺墓の時代から、箱式石棺墓の時代へのうつり変わりは、奴国隆盛の時代から筑後川流域の邪馬台国隆盛の時代へのうつり変わりに対応するものであると思う。
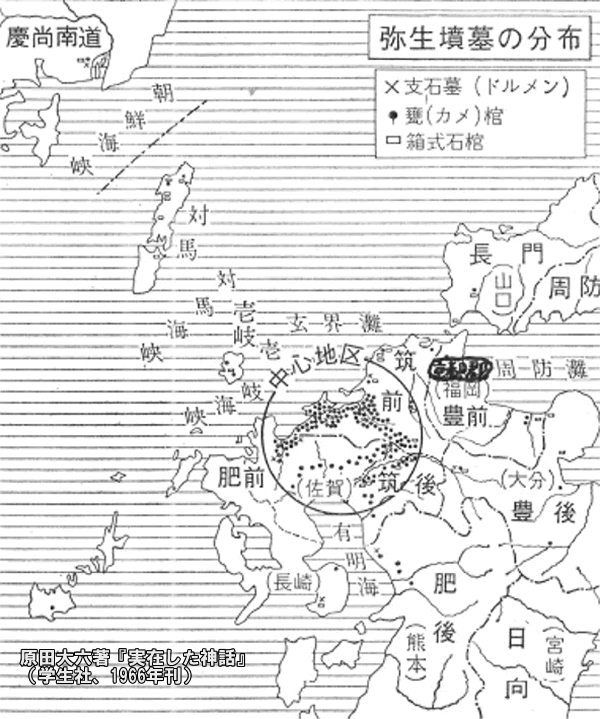
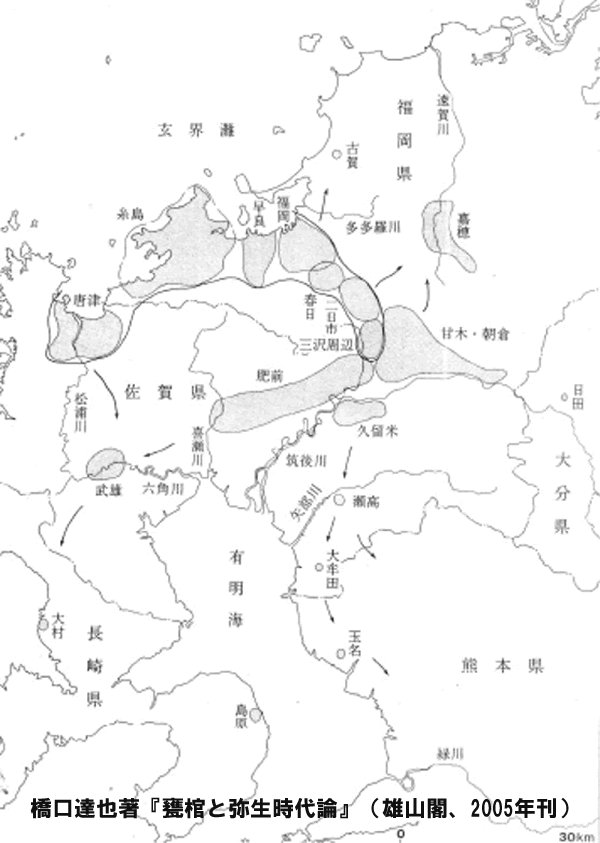
・『魏志倭人伝』
その国は、もとまた男子をもって王としていた。七・八十年まえ倭国は乱れ、あい攻伐して年を歴(へ)る。すなわち、ともに一女子をたてて王となす。名づけて卑弥呼という。鬼道につかえ、よく衆をまどわす。年はすでに長大であるが、夫壻(ふせい)[おっと・むこ]はない。
男弟があって、佐(たす)けて国を治めている。(卑弥呼が)王となっていらい、見たものはすくない。
其國本亦以男子爲王住
七八十年倭國乱相攻伐
歴年乃共立一女子爲王
名曰卑彌呼事鬼道能惑
衆年巳長大無夫壻有男
弟佐治國自爲王以来少
有見者
・『後漢書』「倭伝」
建武中元2年(光武帝、57)、倭の奴国が奉貢朝賀した。使人はみずから大夫と称した。倭国の極南界である。光武(後漢第1代、25~57在位)は賜うに印綬をもってした。
安帝(後漢第66代、107-125在位)の永初元年(107)、倭の国王帥升(師升、倭面土ヤマト説、九州イト説、委面説などがある)らが、生口160人を献じ、請見を願うた。
桓(後漢第11代桓帝、147-67在位)・霊(同第12代霊帝、168-88在位)の間、倭国が大いに乱れ、かわるがわるたがいに攻伐し、歴年主がいなかった。一女子があり、名を卑弥呼といった。年が長じても嫁にゆかず、鬼神の道につかえ、よく妖をもって衆を惑わした。
そこで、共に立てて王とした。
『魏志倭人伝』の
本亦以男子爲王住
七八十年倭國乱相攻伐
歴年
について、いろいろな読み方がある。
つまり「住」には二つの意味がある
①住(す)む。住(とど)まる
②住(ゆ)く。
そして、「七・八十年」について、二つの解釈ができる
a.永初元年(107)から、七・八十年。「男子が王である状態に住(とど)まること七・八十年。」「住(ゆ)くこと、七・八十年。」
b.「魏の使が日本に来たとき(247年~250年ごろ)から住(ゆ)くこと(さかのぼること)七・八十年。」
どちらにしても『後漢書』「倭伝」の話とつじつまがあう。西暦170~180年頃倭国が大いに乱れた。これが、墓制の変化に合っており。この変化が奴国から邪馬台国へ移っていた時期であろうとするものである。
・更に甕棺と箱式石棺について
甲元真之・山崎純男共著の『弥生時代の知識』(東京美術刊)には、次のように述べられている。
「弥生時代における箱式石棺墓の分布をみますと、広島県、大分県、熊本県を結ぶ線の西側
に限られています。おもしろいことに弥生時代の前期には、佐賀県、福岡県、山口県西部の、甕棺墓地からはずれた周辺地域の、海岸砂丘上に多くみられ、中期になると、長崎県対馬や、広島県、熊本県などに分布が拡大する一方、福岡県や佐賀県の甕棺墓地群の外縁部にみられるようになります。後期になりますと、かつて甕棺地帯であった地域にまで墓群をなして”進入”する勢いをみせています。」
国立歴史民俗博物館の考古学者、白石太一郎氏はのべる。
「北九州地方は、弥生時代を通じて支石墓、箱式石棺、土壙墓・木棺墓・甕棺墓など各種の葬法や墓制が複雑に展開した地域である。まず前期には土壙墓や木棺を土壙におさめた木棺墓が一般的であったようで、西北九州では箱式石棺墓も少なくない。ところが前期の中頃から甕棺墓が出現、中期には福岡・佐賀両県を中心にこれが盛行し、土壙墓や木棺墓も共存するが、いちおう甕棺葬がもっとも普遍的な葬法となるのである。ただ周辺の大分、熊本、長崎県などでは、甕棺はそれほど多くはみられず、大分、熊本県では土壙墓・木棺墓が、長崎県などでは箱式石棺墓がより一般的な墓制であった。」
二世紀後半から三世紀、すなわち弥生後期になると、支石墓はみられなくなり、北九州でもしだいに甕棺が姿を消し、かわって箱式石棺、土壙墓、石蓋土壙墓、木棺墓が普遍化する。
ことに弥生前・中期には箱式石棺がほとんどみられなかった福岡、佐賀県の甕棺の盛行地域にも箱式石棺がみられるようになる。」
「九州地方でも弥生文化が最初に形成された北九州地方を中心にみると、(弥生時代の)前期には、土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓が営まれていたのが、前期の後半から中期にかけて大型の甕棺墓が異常に発達し、さらに後期になるとふたたび土壙墓、木棺墓、箱式石棺墓が数多くいとなまれるようになるのである。」(以上、「墓と墓地」学生社刊『三世紀の遺跡と遺物』所収)
卑奴母離の存在は、卑奴は田舎の意味であり、邪馬台国を囲んだ周囲にあると考えられる。
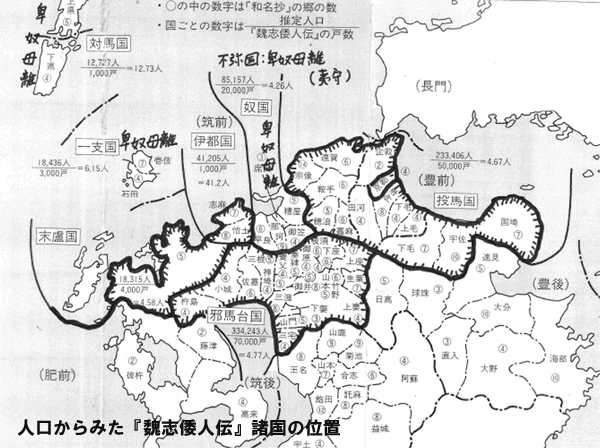
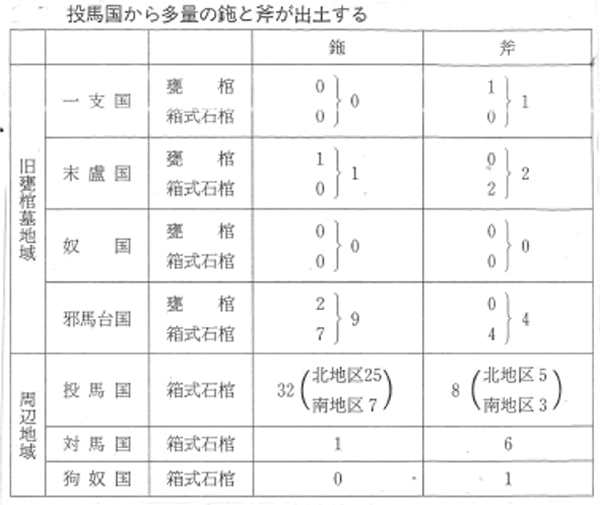
箱式石棺の勢力が甕棺の勢力を滅ぼしたと考えられる。
この図で投馬国の「京都郡(みやこぐん)」あたりから勃興して、奴国を滅ぼしたのではないか。奴国では甕棺であり、投馬国は箱式石棺であった。
壱与の時代に、また豊前、豊後の方に都を戻したのではないか。