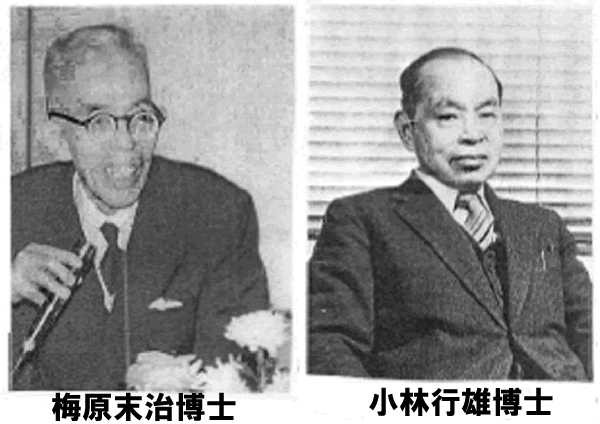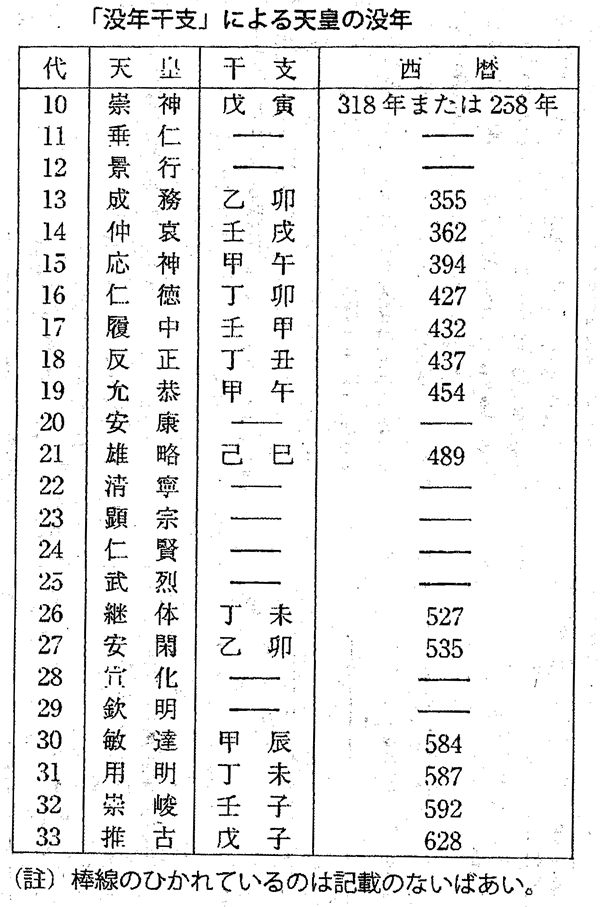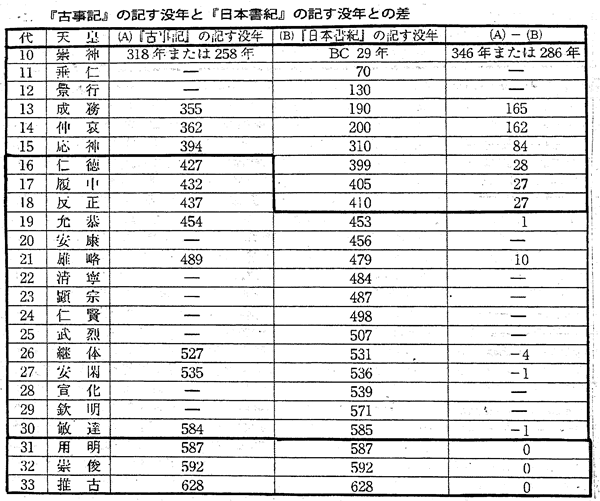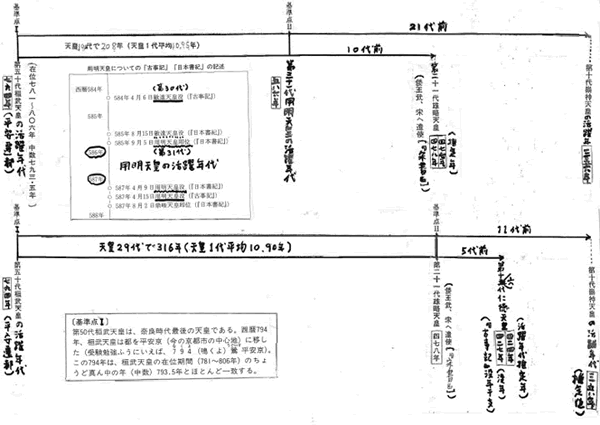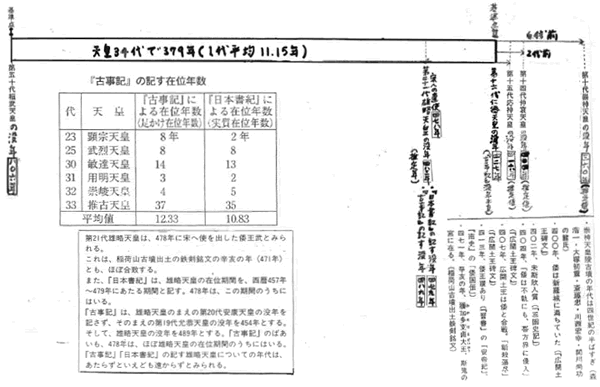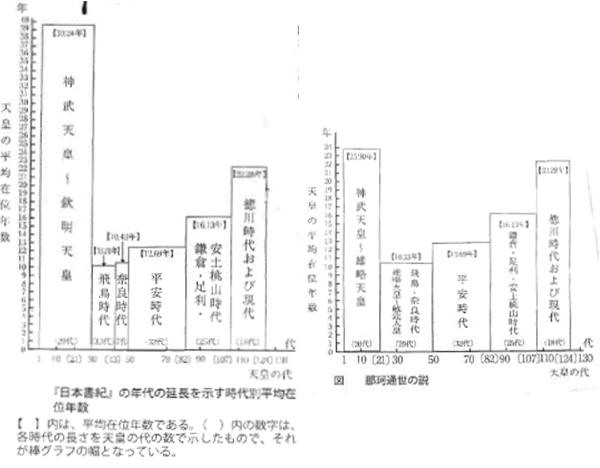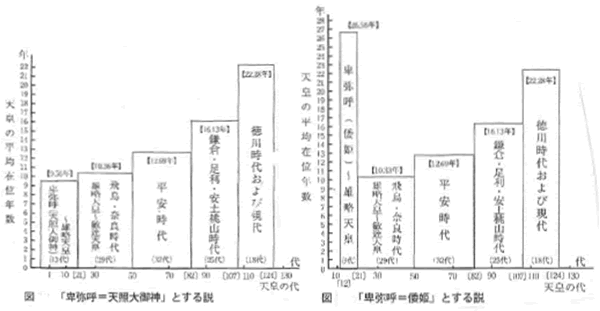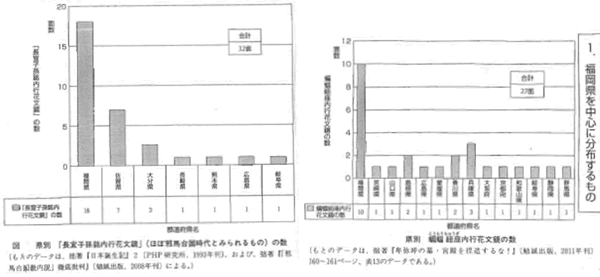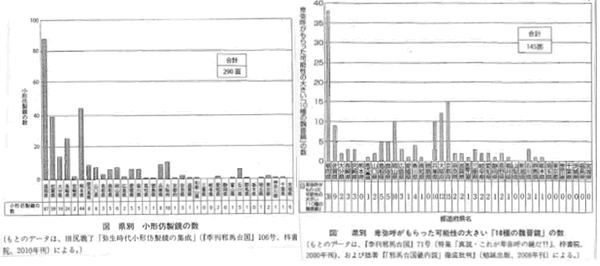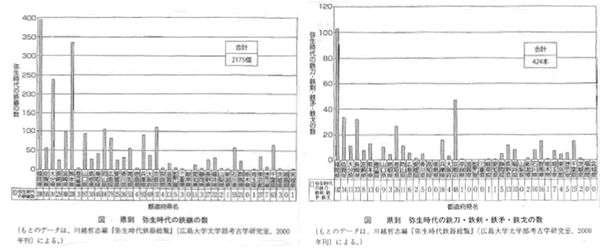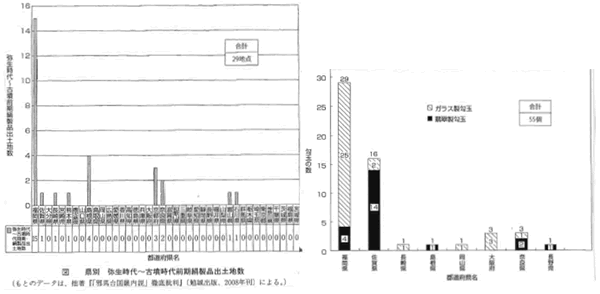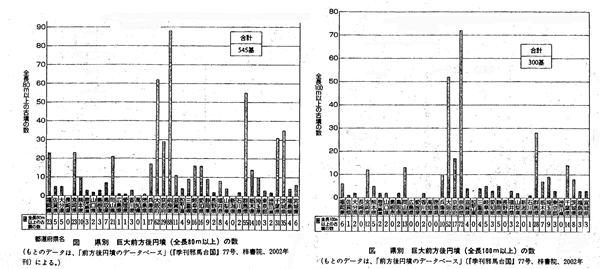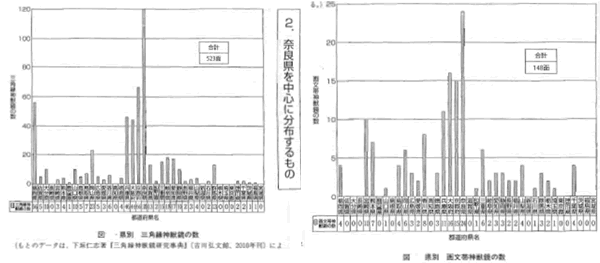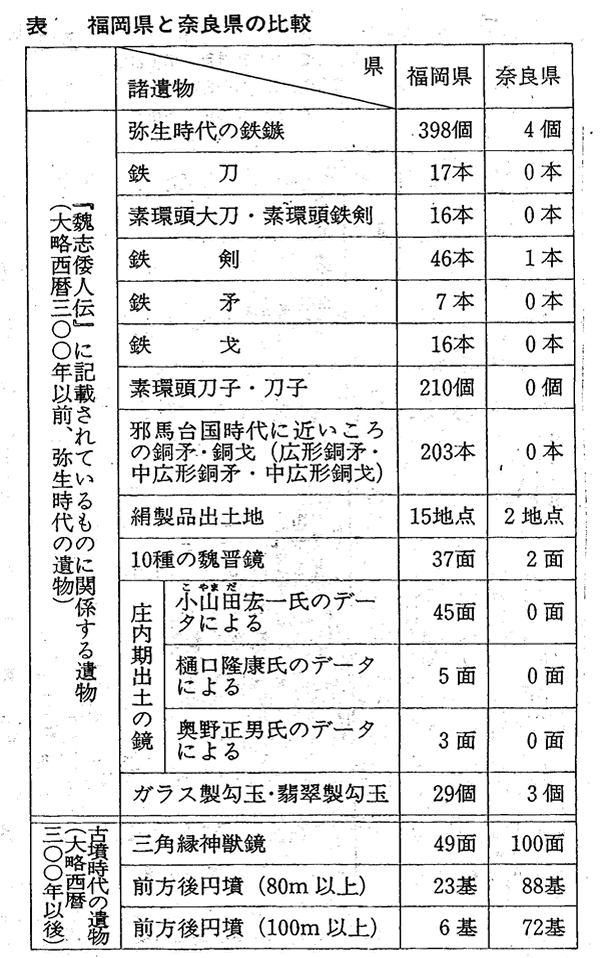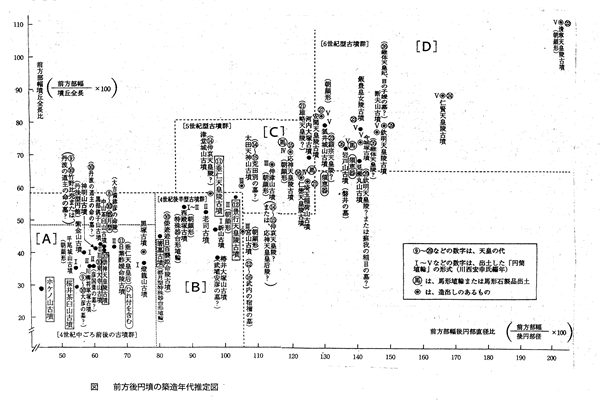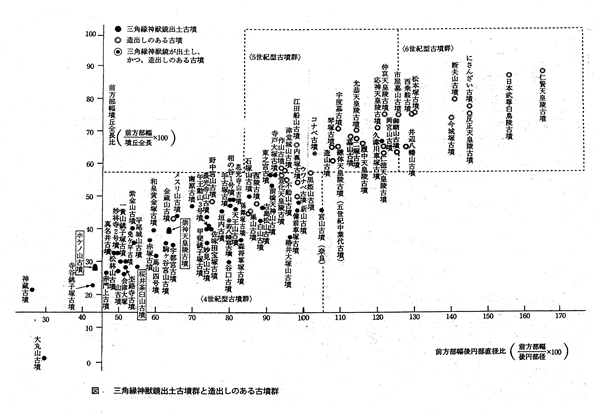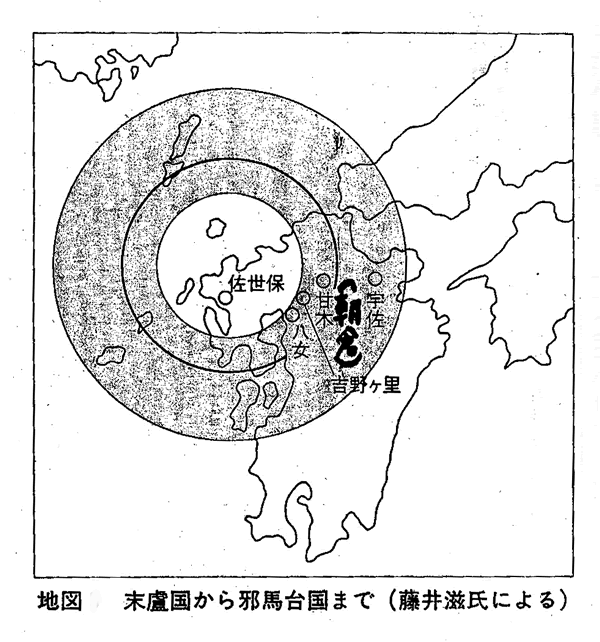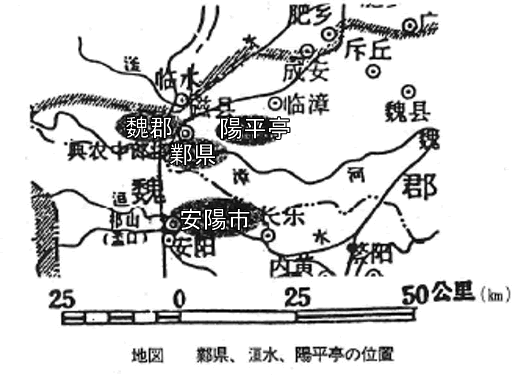■干支
まず、十干と十二支についてのべる。
十干とは、つぎのようなものをさす。
甲(こう)、乙[おつ(いつ)]、丙(へい)、丁(てい)、戌(ぼ)、己(き)、庚(こう)、辛(しん)、壬(じん)、癸(き)
これを、中国の原子論、五行説の五元素(これは、五つの遊星とも対応する)
木、火、土、金、水
に配して、おのおの陽すなわち兄(え)と、陰すなわち弟(と)にわけた。すなわち、
甲 きのえ 木の兄 乙 きのと 木の弟
丙 ひのえ 火の兄 丁 ひのと 火の弟
戊 つちのえ 土の兄 己 つちのと 土の弟
庚 かのえ 金の兄 辛 かのと 金の弟
壬 みずのえ 水の兄 癸 みずのと 水の弟
と名づけた。
また、十二支とは、
子(し)、丑(ちゅう)、寅(いん)、卯(ぼう)、辰(しん)、巳(し)、午(ご)、未(び)、申(しん)、酉(ゆう)、戌(じゅつ)、亥(がい)
をさす。これは、ふつう、
ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い とよばれている。
干支による紀年法では、いま、最初の年を甲子(きのえね)の年とすれば、翌年は、乙丑(きのとうし)の年となる。その翌年は丙寅(ひのえとら)の年である。
(十 干)甲乙丙丁戊己庚辛壬癸甲乙丙丁戊…
(十二支)子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑寅…
このような組みあわせを一回おこなうと、とうぜん、十干のほうは終わってしまっても、十二支のほうは二つあまる。そこで、十干をもう一度はじめからくりかえして組みあわせて行く。十二支のほうも終りまでくれば、またはじめからくりかえす。同じようにしてつづけて行くと、十と十二の最小公倍数である六十年目で、いちばんはじめの甲子の年がもどってくる。
なお、干支による紀年法は、中国の戦国時代(紀元前476年-紀元前221年ごろ)にはじまったものらしく、殷の時代にはない。殷代には、年は、何何王の何年というように記されていた。ただ、殷代には、日々に六十干支をふっていく記日の方法はあった。
干支のよみかたは、たとえば、丙午「ひのえうま」という仮名の訓でよむよりも、「へいご」と音でよむほうがよいと思われる。しかし、ここでは、いちおう仮名の訓でよんでおいた。なお、干支は、方角や時の名前としても用いられる。たとえば、北を子、南を午としたので、現在でも南北の線を子午線(しごせん)よんでいる。
なお、暦のばあい、「乙」は、ふっう、「いつ」と読む。たとえば、645年、「乙巳(いつし)の年」に、中大兄(なかのおおえ)の皇子(おうじ)と中臣(なかとみ)の鎌足(かまたり)とによって、蘇我(そが)の入鹿(いるか)が誅滅される、大化の改新がはじまる。645年のときの変事を、「乙巳(いつし)の変」という。「乙巳(おつし)の変」とはいわない。
干支の読みを下記に示す。
| |
干支 |
訓読み |
音読み |
|
干支 |
訓読み |
音読み |
| 1 |
甲子 |
きのえね |
こうし |
31 |
甲午 |
きのえうま |
こうご |
| 2 |
乙丑 |
きのとのうし |
いっちゅう |
32 |
乙未 |
きのとのひつじ |
いつび |
| 3 |
丙寅 |
ひのえとら |
へいいん |
33 |
丙申 |
ひのえさる |
へいしん |
| 4 |
丁卯 |
ひのとのう |
ていぼう |
34 |
丁酉 |
ひのとのとり |
ていゆう |
| 5 |
戊辰 |
つちのえたつ |
ぼしん |
35 |
戊戌 |
つちのえいぬ |
ぼじゅつ |
| 6 |
己巳 |
つちのとのみ |
きし |
36 |
己亥 |
つちのとのい |
きがい |
| 7 |
庚午 |
かのえうま |
こうご |
37 |
庚子 |
かのえね |
こうし |
| 8 |
辛未 |
かのとのひつじ |
しんび |
38 |
辛丑 |
かのとのうし |
しんちゅう |
| 9 |
壬申 |
みずのえさる |
じんしん |
39 |
壬寅 |
みずのえとら |
じんいん |
| 10 |
葵酉 |
みずのとのとり |
きゆう |
40 |
葵卯 |
みずのとのう |
きぼう |
| 11 |
甲戌 |
きのえいぬ |
こうじゅつ |
41 |
甲辰 |
きのえたつ |
こうしん |
| 12 |
乙亥 |
きのとのい |
いつがい |
42 |
乙巳 |
きのとのみ |
いっし |
| 13 |
丙子 |
ひのえね |
へいし |
43 |
丙午 |
ひのえうま |
へいご |
| 14 |
丁丑 |
ひのとのうし |
ていちゅう |
44 |
丁未 |
ひのとのひつじ |
ていび |
| 15 |
戊寅 |
つちのえとら |
ぼいん |
45 |
戊申 |
つちのえさる |
ぼしん |
| 16 |
己卯 |
つちのとのう |
きぼう |
46 |
己酉 |
つちのとのとり |
きゆう |
| 17 |
庚辰 |
かのえたつ |
こうしん |
47 |
庚戌 |
かのえいぬ |
こうじゅつ |
| 18 |
辛巳 |
かのとのみ |
しんし |
48 |
辛亥 |
かのとのい |
しんがい |
| 19 |
壬午 |
みずのえうま |
じんご |
49 |
壬子 |
みずのえね |
じんし |
| 20 |
葵未 |
みずのとのひつじ |
きび |
50 |
葵丑 |
みずのとのうし |
きちゅう |
| 21 |
甲申 |
きのえさる |
こうしん |
51 |
甲寅 |
きのえとら |
こういん |
| 22 |
乙酉 |
きのとのとり |
いつゆう |
52 |
乙卯 |
きのとのう |
いつぼう |
| 23 |
丙戌 |
ひのえいぬ |
へいじゅつ |
53 |
丙辰 |
ひのえたつ |
へいしん |
| 24 |
丁亥 |
ひのとのい |
ていがい |
54 |
丁巳 |
ひのとのみ |
ていし |
| 25 |
戊子 |
つちのえね |
ぼし |
55 |
戊午 |
つちのえうま |
ぼご |
| 26 |
己丑 |
つちのとのうし |
きちゅう |
56 |
己未 |
つちのとのひつじ |
きび |
| 27 |
庚寅 |
かのえとら |
こういん |
57 |
庚申 |
かのえさる |
こうしん |
| 28 |
辛卯 |
かのとのう |
しんぼう |
58 |
辛酉 |
かのとのとり |
しんゆう |
| 29 |
壬辰 |
みずのえたつ |
じんしん |
59 |
壬戌 |
みずのえいぬ |
じんじゅつ |
| 30 |
葵巳 |
みずのとのみ |
きし |
60 |
葵亥 |
みずのとのい |
きがい |
『古事記』の「没年干支」によるの古代天皇の没年を下記に示す。
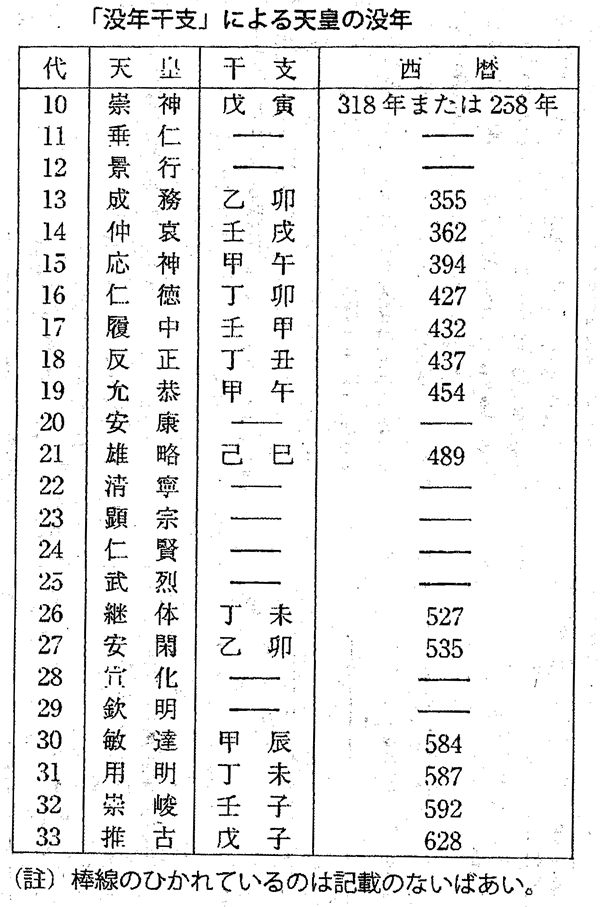
■『古事記』の記す没年と、『日本書紀』の記す没年との差
第31代用明天皇以降では『古事記』と『日本書紀』の記す没年が一致している。しかし用明天皇より古くなるとズレが生じ、古くなるほどズレが大きくなり、第1代崇神天皇の時代では300年近くの差が出る。
『古事記』と『日本書紀』を比較すると、仁徳天皇の没年は『古事記』の記した427年が、ほぼよいのではないか。
下図において、棒線の引かれているのは、『古事記』に記載のないばあい。『古事記』は、崇神天皇の没年月を、戊寅の年12月とする。ふつう、この戊寅の年は、西暦318年または258年にあてる。しかし、この年の12月は、西暦319年および259年の1月にあてられる可能性も、かなりある。
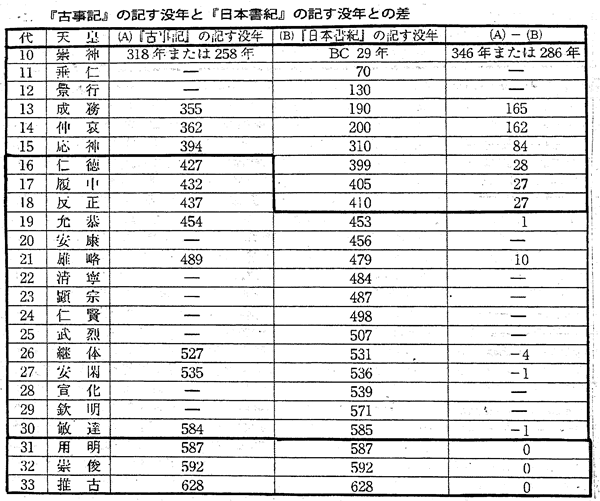
■崇神天皇の没年の推定
下図で基準点Ⅰを第50代桓武天皇の794年(平安遷都)とし、基準点Ⅱを第31代用明天皇の586年(『古事記』、『日本書紀』と没年が一致する)とし、用明天皇から桓武天皇までの天皇19代で208年となり、天皇1代平均は10.95年となる。用明天皇から10代さかのぼると、第21代雄略天皇477年となる。宋書の記載478に近い年代となる。そして用明天皇から21代さかのぼると、第10代崇神天皇となり、崇神天皇の活躍年代は356年と推定できる。
ところが、このやりかたでは、基準点Ⅰと基準点Ⅱの間が短く、そこから崇神天皇を推定すると、確かな年代が短く、推定の期間が長いということになる。そこで、下図の下にあるように基準点Ⅱを、『宋書』記載の倭王武を雄略天皇として再計算する。そのように計算しても崇神天皇の活躍年代は356年となりほぼ同じ結果となる
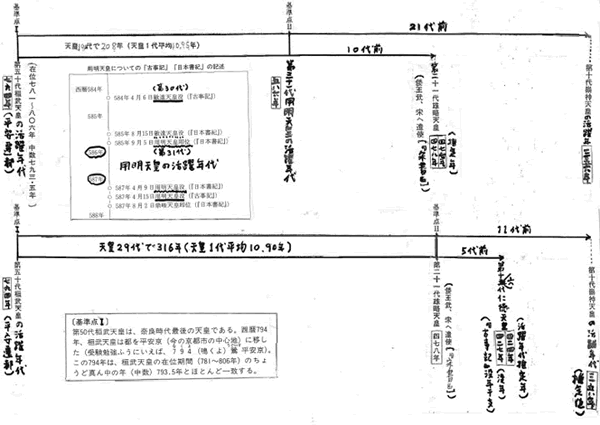
下図は没年を中心として、再計算する。基準点Ⅰの桓武天皇806年(没年)、基準点Ⅱ仁徳天皇427年(古事記没年)とすると、天皇平均在位年数=11.15年となる。この数字を使って、雄略天皇の没年を推定すると、483年となり、古事記の没年489に近い。また、仲哀天皇の没年は404年となり、『三国史記』の未斯欣が人質として倭に来た402年とほぼあう。更に崇神天皇の没年を推定すると、360年となる。
この結果から、『日本書紀』の崇神天皇の没年の年代とするBC29年にはまったく合わない。『古事記』の崇神天皇の没年の年代は318年あるいは258年とされており、笠井新也氏などは258年として、崇神天皇時代の倭迹迹日百襲(やまとととひももそ)姫が卑弥呼とし、箸墓古墳が卑弥呼の墓とする説を唱えるが、この方法で崇神天皇の没年を推定すると360年になり、258年は否定される。箸墓古墳は4世紀の墓となるので、卑弥呼の墓とは言えない。
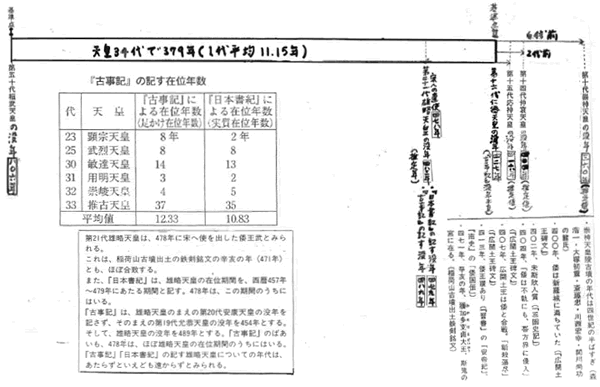
■古代史メモ 世数と代数
古代の天皇の活躍年代(あるいは、即位年代、在位年代など)を推定しようとするばあい、天皇の「代数」を基本的な変数(独立変数)と考える立場と、天皇の「世数」を基本的な変数と考える立場とがある。
たとえば、下の系図のようなばあい、第24代仁賢天皇は、第16代仁徳天皇から数えて「8代目」の天皇である。しかし、世数からいえば、「3世目」の天皇である。
「世数」では、親子関係によって、何世目かを数えるわけである。
系図 「世数」と「代数」のちがいを示すための例
(16)仁徳天皇-(17)履中天皇- 市辺押磐皇子-(24)仁賢天皇
└(23)顕宗天皇
┠(18)反正天皇
╓ (20)安康天皇
└(19)允恭天皇 -(21)雄略天皇-(22)清寧天皇
これを世数でみると、第22代清寧天皇は仁徳天皇から3世となる。このようにすると、仁徳天皇から、清寧天皇まで天皇の代数間は短いが、世数では長くなる。この長くなった世数による年数を使って、天皇の代の間に当てはめて、神武天皇の時代を推定すれば、時代を古くすることができる。
このように世数から計算することは那珂通世氏が唱え、笠井新也氏へと引き継がれてきた。
すでに、慶応大学の教授であった橋本増吉は、大著「東洋史上よりみたる日本上古史研究」(東洋文庫、1956年刊)のなかで、つぎのようにのべている。
「父子直系のばあいの一世平均年数が、ほぼ25.6年ないし30年前後であることは、那珂博士の論じられたとおりであろうけれども、わが上代のおよその紀年を知るために必要なのは、父子直系の一世平均年数ではなく、歴代天皇のご在位年数なのであるから、那珂博士算出の平均世年数をもって、ただちに上代の諸天皇の御在位平均年数として利用すべきでないことは、明白なところである。
下図は『日本書紀』と那珂通世氏の説による、天皇1代の在位年数を示す。
天皇1代の平均在位年数は徳川時代および現代(18代)で22.28年、安土桃山時代・鎌倉・足利時代(25代)で16.13年、平安時代(32代)で12.69年、奈良時代(7代)で10.43年、飛鳥時代(13代)で10.20年[飛鳥・奈良時代雄略天皇~敏達天皇(29代)10.33年]と古くなるにつれ、短くなる。
『日本書紀』では、神武天皇~欽明天皇(29代)の天皇1代の平均在位年数が39.24年と長くなってしまう。
那珂通世の説でも神武天皇~雄略天皇(20代)が23.90年とまだ長い。
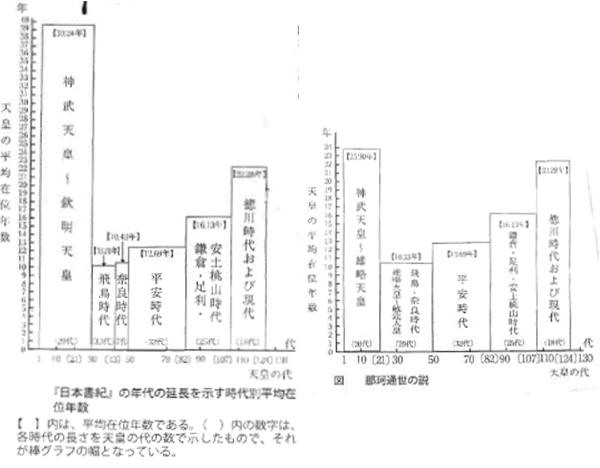
下図は卑弥呼=天照大神説と卑弥呼=倭姫説による、天皇1代の在位年数を示す。
卑弥呼=倭姫説では卑弥呼~雄略天皇(9代)が26.56年と長くなってしまう。
この結果から、卑弥呼=天照大神説がグラフ上整合性があることが分かる。
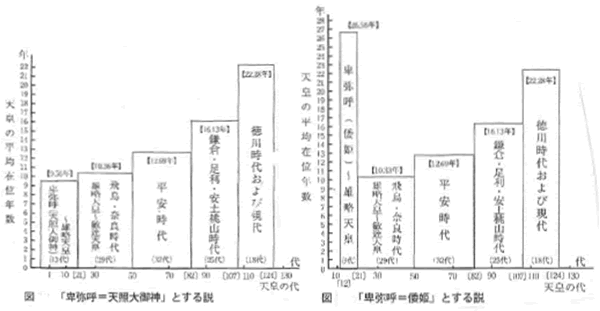
■古文献についての三つの立場
(1)古典信奉主義
年代をふくめ、『古事記』『日本書紀』に記されていることは、なるべくそのままうけとろうとする立場。
本居宣長などの立場だが、『古事記』と『日本書紀』で天皇の没年が違う場合どちらを信ずべきかの問題がある。
(2)半実半虚主義
『古事記』『日本書紀』などに記されていることは、実と虚とがあいまじったものと考える立場。安本説はこれに近い。
(3)抹殺博士主義
『古事記』『日本書紀』に書かれていることで、すこしでも疑わしい記述は、否定し、史料としてみとめない立場[重野安繹(しげのやすつぐ)]
■(2)の半実半虚主義がよいと考える
江戸時代に、故実家の伊勢貞丈(いせさだたけ)(1717~1784)はのべている。
「語り違へもあり、聞き違へもあり、忘れて漏れたる事もあり、事を副(そ)へたることもあるべし。百年五十年以前の事だにも、語り違へ聞き違へて、相違一決せざる事あり。……和漢ともに、太古の事は太古の書籍はなし。古(いにしえ)への語り伝へを後に記したるものなれば、半実半虚なりと思ふべし。」(『安斎随筆』)
・黒板勝美(くろいたかつみ)の神話伝説へ論文
1932年に、日本古文書学を確立した東京大学の黒板勝美(1874~1946)の大著『国史の研究 各説』の上巻が、岩波書店から刊行されている。これは、当時の官学アカデミーの中心に位置した黒板の代表的著作といってよい。
「国史の研究」が刊行された当時、岩波書店は、この本を、「学界の権威として、洛陽の紙価を高からしめたる名著」とし、「わが国史に就(つ)きての中正なる概念を教示する」もので、一般人士はもちろんのこと、「専門研究者も座右に備ふるべき好伴侶たるを失はない」とのべている。
黒板勝美は、『国史大系』などの編集者であり、他の説の批判や自説の主張においては、つねにその根拠を、くわしくのべている。黒板は、津田左右吉の日本神話作為説を「大胆な前提」から出発した研究とし、それを「余りに独断に過ぎる嫌がある」と批判する。そして、黒板は、神話伝説は、むしろ長い年月の間にだんだん作られて来たとする方が妥当であり、はじめはひとつのけし粒であっても、ついに金平糖になるようなものであり、しだいに立派な神話となり伝説となるところにやはり歴史が存在するのではあるまいか、とする。
黒板は、『国史の研究 各説』上巻の冒頭で、およそつぎのようにのべて、「国史の出発点を所謂(いわゆる)神代まで、遡(さかのぼ)らしめ得る」と説く。
「史前時代と有史時代との境目を明瞭に区別しにくいことは、世界の古い国々みなそうである。その太古における物語は、霊異神怪や荒唐無稽の話に富んでいて、神話や伝説などのなかに歴史がつつまれているといえる。
わが国の神話伝説のなかから、もしわが国のはじまりについての事がらを、おぼろげながらでも知ることができるのであれば、私たちは、国史の出発点を、いわゆる神代まで、さかのぼらしめ得るのであり、神代史の研究がまた重要な意義を占めることになるであろう。
もっとも、神武天皇が始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)という尊称をもち、大和に都をひらいた第一代の天皇であるという古伝説にしたがって、あるいは、わが国の歴史の発展を、神武天皇から説明するにとどめようという人があるかも知れない。しかし、わが国のはじまりが、どのようであったかを、いくぶんでも知ることができるとするならば、従来神代といわれている時代に研究を進めることは、また緊要なことといわなければならない。」
ついで、黒板は、天照大御神よりもまえの神々は、皇室の祖先として奉斎(ほうさい)されていないことなどから、実在性はみとめがたいが、天照大御神は、「半ば神話の神、半ば実在の御方」と説く。
「天照大御神は、最初から皇祖として仰がれた方であったからこそ三種の神器の一つである八咫鏡(やたのかがみ)を霊代(たましろ)をして、やがて伊勢に奉斎され、今日まで引きつづき皇室の太廟として、とくに厚く崇祀(すうし)されているのである。
元来史話なるものは、截然(せつぜん)と神話に代るものではなく、その境界は、たがいにいりまじって、両者をはっきりと区別することがむずかしい。これが、天照大御神の半ば神話の神、半ば実在の方として古典に現れる理由である。
神話がほどよく史的事象を包んでおり、史的事象がほどよく神話化されている。したがって、須佐の男の命に関する古典の記載なども同様であるが、天照大御神の御代に皇室の基礎が定まり、わが国は天照大御神の徳によってはじまったことは、おぼろげながらみとめられなければならない。