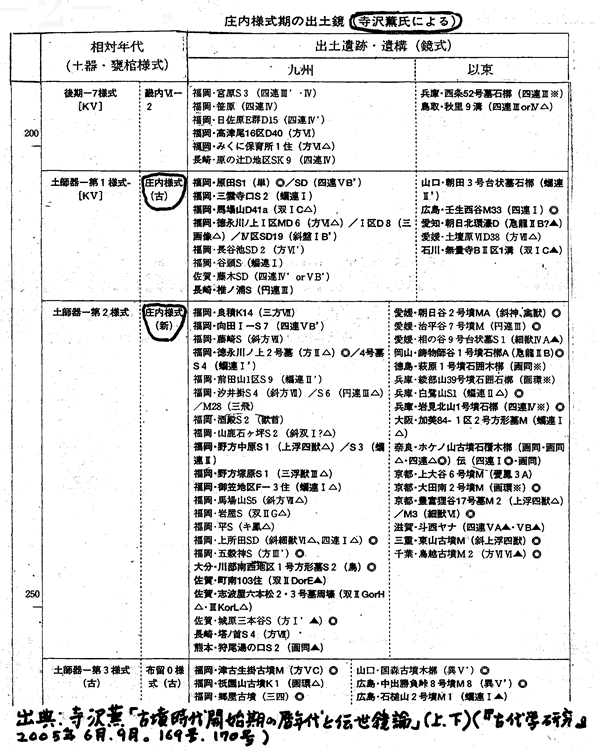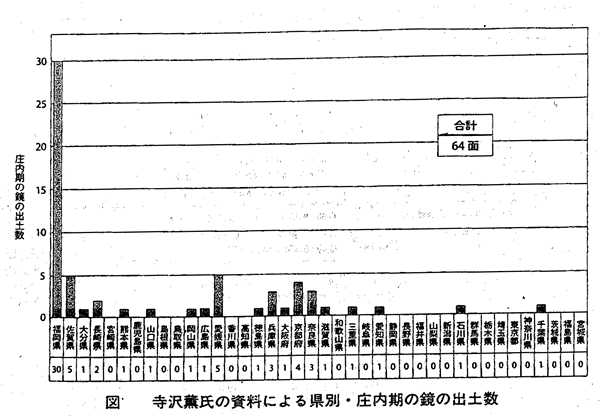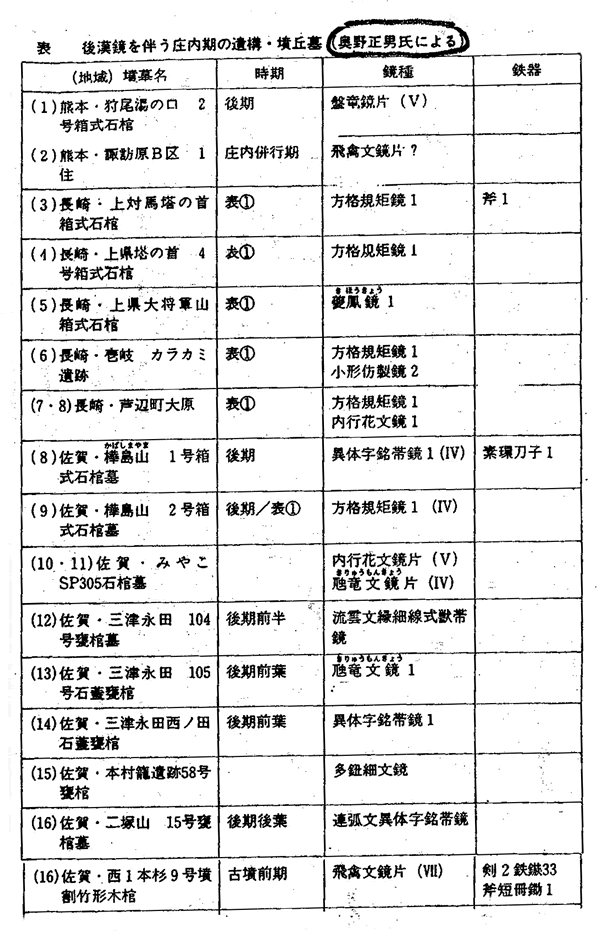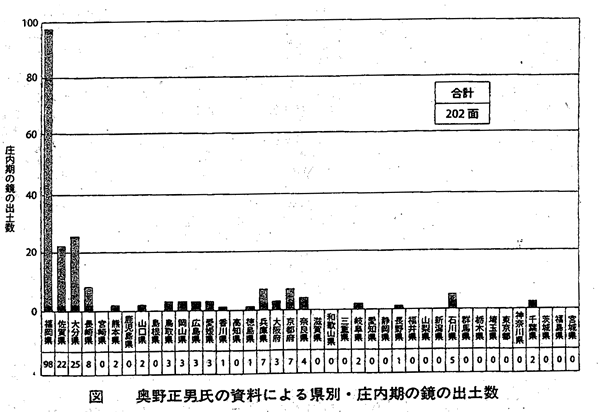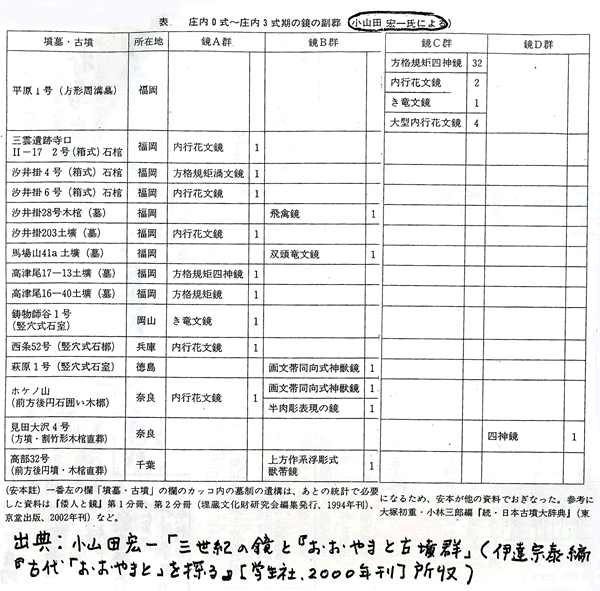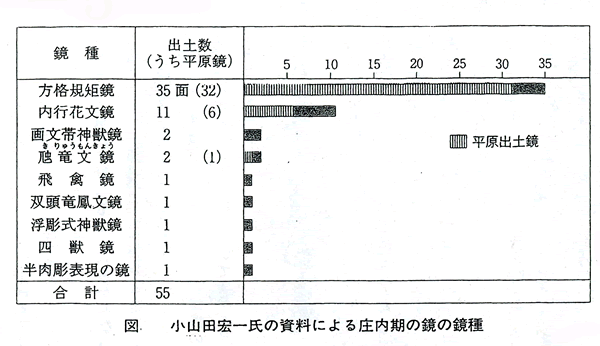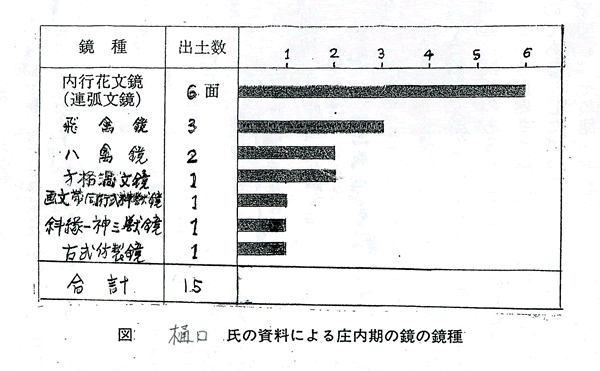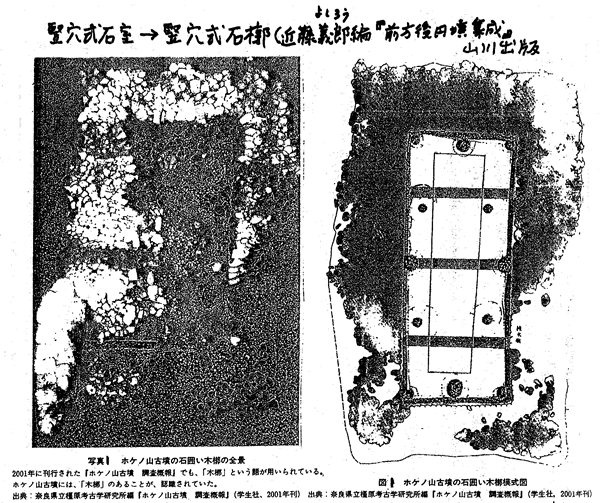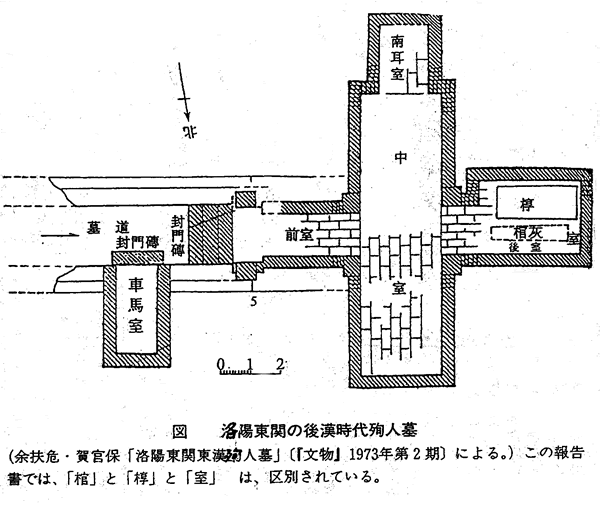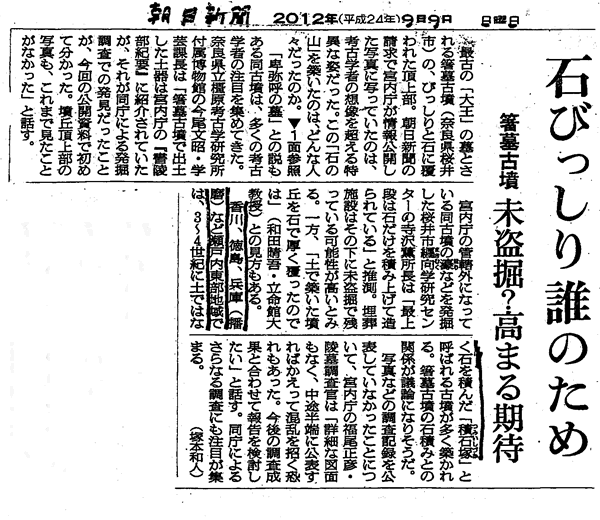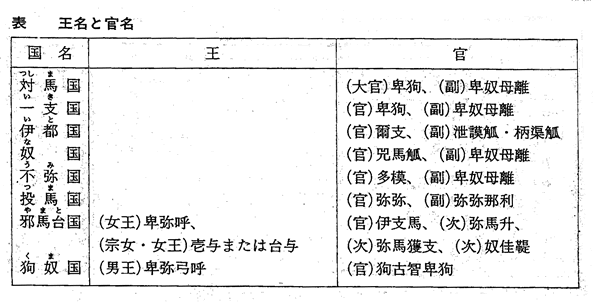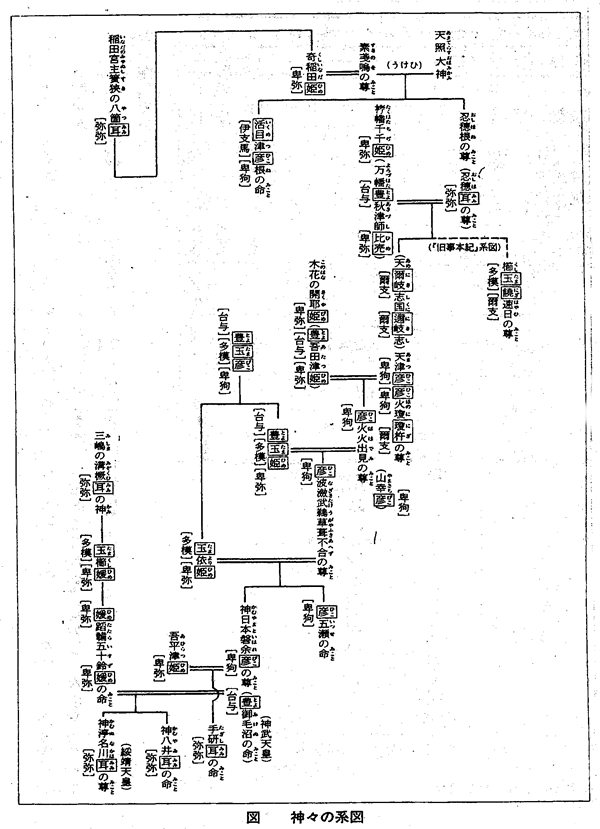■『朝日新聞』大阪本社版2012年9月12日に奈良・箸墓古墳の宮内庁調査資料についての記事がある。

ここで今回の資料から問題になるのは、箸墓古墳には槨があることが分かったことである。箸墓古墳より古いとされるホケノ山古墳では木槨が出土していおり、箸墓古墳も槨があることが考えられていたが、明確になった。
『魏志倭人伝』には、倭人の墓制が記されている。そこには「棺あって槨なし」とある。北部九州の「甕棺」や「箱式石棺」、あるいは「木棺直葬」などは、「棺あって槨なし」の記述に合致する。ホケノ山古墳や箸墓古墳は槨があり、これは『魏志倭人伝』の「棺あって槨なし」の記述に合致しない。槨のある墓制は、時代的に、邪馬台国よりものちの時代の墓制ではないか。
■箸墓古墳出土の「石槨」やホケノ山古墳(庄内3式期)出土の「木槨」は、『魏志倭人伝』の記述「棺あって槨なし」などにあわない。
いわゆる邪馬台国論争は、『魏志倭人伝』という中国の文献から発している。
ここでは、『魏志倭人伝』に書いてある具体的な事実、「棺あって槨なし」という墓制について議論してみたい。
・箸墓古墳(布留0式期)出土の「石槨」、庄内3式期といわれるホケノ山古墳の「木槨」をとりあげる。
まず、下図をご覧いただきたい。この図と写真のホケノ山古墳の「木槨」は、『魏志倭人伝』の記述にあわない。
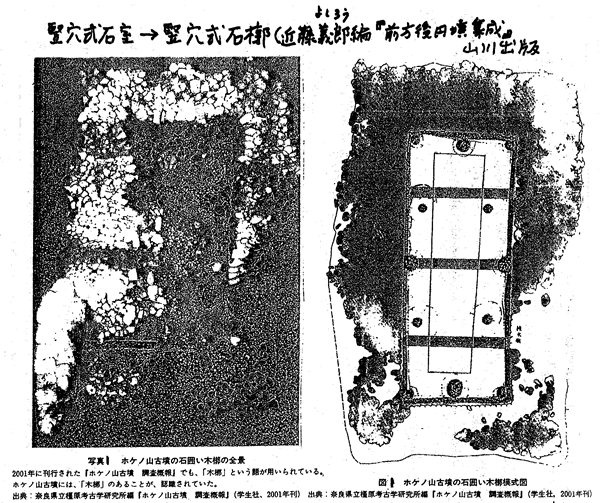
奈良県立橿原考古学研究所編『ホケノ山古墳 調査概報』(学生社、2001年刊)によれば、ホケノ山古墳においては、「木槨木棺墓がみつかった」「木の枠で囲った部屋があり、その中心に木棺があった」「栗石槓みの石囲いに覆われた木槨と木棺があった」という。『魏志倭人伝』には、倭人の葬制は「棺あって槨なし」と記されている。
ホケノ山古墳では、木槨の中に木棺があり、『魏志倭人伝』の記述にあわない。
『三国志』の筆者は、葬制には関心をもっていた。つぎのように各国ごとに、いちいち書き分けている。
『韓伝』……「棺(内棺)ありて槨(外箱)なし。」
『夫余伝』……「厚葬(贅沢な埋葬)にして、槨ありて棺なし。」
『高句麗伝』……「厚く葬り、金銀財幣、送死に尽くす(葬式に使い果たす)。石を積みて封(塚)となし。松柏を列べ種(う)う。」(この記述は高勾麗の積石塚とあう。)
『東沃沮(とうよくそ)伝』……「大木の槨を作る。長さ十余丈。一頭(片方の端)を開きて戸を作る。新たに死するものは、皆これに埋め、わずかに形を覆(おお)わしむ(土で死体を隠す)。」
[倭人伝]……「棺あって槨なし。土を封じて冢(つか)を作る。喪(なきがら)を停(とど)むること十余日(もがりを行なう)。」
このように、倭人の葬制は「韓」とは同じであるが、 「夫余」「高句麗」「東沃沮」と異なっていることを記している。
・日本で「もがり(死者を埋葬する前に、しばらく遺体を棺に納めて弔うこと)」が行なわれたことは、『古事記』『日本書紀』に記述がみえるし、沖永良部島では明治のころまで行なわれていた(斎藤忠『古典と考古学』学生社、1988年刊)。
畿内のばあい、「木槨木棺墓」も「竪穴式石室墓」も、時代のくだる「横穴式石室墓」も、一貫して『魏志倭人伝』の「棺あって槨なし」の記述にあわない。
邪馬台国がかりに畿内にあったとすれば、魏の使いはそれらの葬制を見聞きせずに記したのであろうか。
時代のくだった『隋書倭国伝』は、「死者を斂(おさ)めるに棺槨をもってする。」と記す。隋の使いが畿内に行ったことは、『日本書紀』に記されている。西暦600年ごろ、日本の墓には棺槨があったのだ。中国人の弁別記述は鋭い。
いっぽう、九州の福岡県前原市の平原遺跡からは、40面の鏡が出土している。平原遺跡では、土壙(墓穴)のなかに割竹形木棺(丸太を縦二つに割り、それぞれの内部をくりぬいて、一方を蓋、一方を身とした木棺。断面は円形)が出土した。
平原遺跡の割竹形木棺は、幅1.1メートル、長さ3メートル。ここでは、「木の枠で囲った部屋」などはない。『魏志倭人伝』の「棺あって槨なし」の記述に合致している。
平原遺跡の時期は、1998年度の調査で周溝から古式土師器(はじき)が出土し、また出土した瑪瑙(めのう)管玉、鉄器などから、「弥生終末から庄内式(時代)に限定される」(柳田康雄「平原王墓の性格」『東アジアの古代文化』大和書房、1999年春・99号)。これこそ三世紀の邪馬台国時代に相当するといえよう。また、平原遺跡出土の仿製鏡の製作年代は、西暦200年ごろと考えられている(前原市文化財報告書の『平原遺跡』「前原市教育委員会、2000年刊」)。
北九州で大量に発見される「甕棺墓」や「箱式石棺墓」なども一貫して、「棺あって槨なし」の記述に合致するといえよう。
九州では、古墳時代初頭の土師器の出土した福岡県福岡市の那珂八幡古墳なども、割竹形木棺が直葬されていた。
九州でも時代が下り、竪穴式石室や横穴式石室が行なわれるようになると、「棺と槨」とがある状態となる。このことは、「棺と槨」とがある葬制は時代がやや下るのではないかという疑いをもたせる。
・中国の「槨」は棺の外箱である
以上述べてきたような疑問を、2008年6月22日の「邪馬台国の会」に考古学者石野博信氏をお招きして、討論会「邪馬台国は畿内か九州か」を開いたさい、私は石野氏にぶつけてみた。
石野氏の答えは、つぎのようなものであった。
「『槨』ですけれども、ホケノ山を掘って橿原考古学研究所が木槨と発表したときに、講演会で会場からの質問がありました。『邪馬台国が大和でないことがこれで決まったのですか』という質問でした。
私はそのときにつぎのように答えました。『魏志倭人伝』で『棺ありて槨なし』と書いているときの『槨』は漢墓を参考にしますと、学校の教室くらいの大きさがあります。部屋を三つも四つも連接しているものもあります。それを『木槨』と呼んでおります。魏に使いに行った倭人が倭の墓の構造を説明したか、倭に来だ魏の使者が倭人の墓を見て、棺を囲む施設があっても、そんなものは『槨』ではないと思ったのではないか、と。
ホケノ山古墳の木槨は、2メートル70センチ×7メートルですから、そんなものは『槨』とは呼べない。だから『棺ありて槨なし』と言ったのではないか、と考えています。」(「季刊邪馬台国」100号、2008年刊)
石野氏にやや近い見解を、桜井市教育委員会の橋本輝彦氏や、考古学者の萩原儀征(よしゆき)氏も述べている。石野博信氏『大和・纏向遺跡』(学生社、2005年刊)に、つぎのような座談会記録が載っている。出席者は石野氏のほか、寺沢薫、橋本輝彦、萩原儀征の三氏である。やや長い引用になるが、紹介してみたい。
「寺沢 卑弥呼の墓は『棺ありて槨なし』で考えるでしょう。
石野 そうそう。だから、ホケノ山古墳の石囲い木槨が新聞に載ったときに問い合わせがあった。『魏志倭人伝』では邪馬台国の葬法は『「棺ありて槨なし」だから、邪馬台国は大和じゃないということがわかったのですか』という質問でした。
寺沢 あの『棺ありて槨なし』の「槨なし」というのは、中国人的な目で見た槨がないということですね。だから、卑弥呼が大和にいたという前提で物を言えば、逆にホケノ山のものは「槨」じゃないのでしょうね(笑)。
石野 中国の槨は学校の教室かそれ以上の大きな部屋だからね。
寺沢 ぼくは日本のこの時期の木槨というのは土留めだと思っているから。
橋本 『槨』という用語をわれわれが使ったから、一般の人が誤解しちゃったのかもしれないですね。
石野 竪穴式石槨なんて言うのも恥ずかしいよ。むしろ今の日本語だったら石室、木室でいいだろうと思う。
寺沢 でも中国でいう室は、あとで追葬可能な機能をもった構造の大ぎさですから、どちらかといえばやっぱりあれは槨なんでしょうね。
萩原 二重木棺みたいなものですね。
橋本 中国人が見るとちゃんちゃらおかしかった、ということなのでしょうけれどもね。」
2008年6月22日の「邪馬台国の会」では、時間切れで「槨」の問題について、それ以上、石野博信氏と討論できなかった。いつか石野氏とさらに議論を重ねる日がくればと願っている。
石野氏は「槨」を「学校の教室くらいの大きさがあります」「中国の槨は学校の教室かそれ以上の大きな部屋」と述べている。
しかし、そのように大きなものがあるとしても、それは中国の「槨」の本質なのだろうか。
・『中国古典』の「槨」の記述
まず、『三国志』の範囲でみてみる。『三国志』の『魏志』の「文帝紀」に、つぎのような文がある。
「棺槨(内棺と外棺)は、骨を朽ちさせ、衣衾[衣服と褥(しとね)]は肉を朽ちさせるだけのもので充分と考える。」(世界古典文学全集『三国志I』筑摩書房、1977年刊)
この文で、「三国志Ⅰ」の翻訳者は、「棺槨」を「内棺と外棺」と訳している。要するに「槨」は「外棺」で、「大きな部屋」のようにはみえない。
藤堂明保編の『学研漢和大字典』(学習研究社、1980年刊)にも、「椁(=槨)」は「うわひつぎ。棺を入れる外箱。外棺」とある。
諸橋轍次編の『大漢和辞典』(大修館書店、1980年刊)でも、「ひつぎ。うわひつぎ。棺を納める外ばこ」とある。
『後漢書』の「孝明(こうめい)帝紀」(第二代明帝の紀)につぎのようにある。
「帝、初め寿陵(じゅりょう)[生前に建てておく墓]を作るや、制して水を流さしむるのみにして、石槨の広さは一丈二尺、長さは二丈五尺、墳を起つる得ること無からしむ。」
後漢時代の1尺は23センチほど。1丈は2.3メートルほどである。石槨の幅一丈二尺は2.8メートルほど、長さ二丈五尺は5.75メートルほどである。ホケノ山古墳の木槨、2.7メートル×7メートルよりも小さい。後漢の帝王の「槨」でも、学校の教室ほどはないようにみえる。
中国の周の末から秦・漢時代の儒者の古代の礼についての説を集めた『礼記(らいき)』の「檀弓(だんぐう)編」の「上」にはつぎのようにある。
「天子の棺は四重。(中略)もっとも外側に柏(ひのき)の椁(槨)をかぶせる。これは柏の根もとの部分でつくり、槨の長さは六尺(約1.35メートル)である。」
「斉の国子高がいった。衣服が死者を包み、棺が衣服を収め、椁が棺を収め、墓土が椁を収める。」
ここでは、「棺が衣服を収める」のと同じように、「椁が棺を収める」ものであるといっている。長さ六尺(約1.35メートル)では、ホケノ山古墳の木槨、長さ7メートルほどよりも、かなり小さい。
さらに『晋書』の第三十三の、「王祥(おうしょう)伝」(二十四孝の一人。継毋につかえて孝であったことでしられる)などでも、王祥は、子孫に遺訓をのこし、「槨は棺を容(い)るるを取れ(槨取容棺)」と述べている。「槨」は「棺」が、はいるていどのものを用いよ、と述べているのである。
・現代中国考古学者の「槨」の記述
現代の中国の考古学者も、槨を教室のように大きなものとは、考えていないようである。現代中国で出ている『文物』という雑誌の1973年、第2期に洛陽の、東関の地で出た後漢時代の墓についての報告がのっている。
そこに、出土した墓の「室」と「槨」と「棺」についての、記述がある。これを、私なりに、日本語に訳したものを、下に示しておく(「文物」記載の文章の日本語訳)。
ここでは下図のような墓の図が掲載されている。「室」と「槨」と「棺」とは区別され、「槨」については、つぎのように記されている。
「槨の長さは、1.6メートル、幅1メートル、高さは0.5メートルであった。」
「棺の壁と槨の壁とのあいだのへだたりは3センチメートルほどであった。」
このていどが、帝王でない人の墓の「槨」の大きさではないか。
これらにくらべれば、ホケノ山古墳の木槨は、十分立派な木槨のようにみえる。
ホケノ山古墳の木槨は、『魏志倭人伝』の記す「棺あって槨なし」の記述とあわない。
槨のあるホケノ山古墳は、時代的に、『魏志倭人伝』の時代、邪馬台国時代よりも後のもののようにみえる。
・「文物」記載の文章の日本語訳
墓の中から棺三つが、ともに見いだされた。後室の中から二つ、南耳室(耳のようにつきでた室)から一つの計三つである。人骨とそれをおいた台は、すべて、すでに朽ちそこなわれていた。
後室の中の二つの棺は、南北にならべておかれていた。頭を西にし、足を東にしていた。南がわの棺の外に槨があった。棺の壁と槨の壁とのあいだのへだたりは3センチほどであった。棺はすでにくさりくずれて灰になっていた。
槨のほうは、かえって、保存がよく、比較的安全といってよいほど、ととのっていた。ただ、槨の蓋は、盗掘者によつて、打ちこわされていた。槨は、長方形をしており、底部の中ほどが内むきにくぼんでいた。前後の両端は円い孤になっていた。角のところは、およそみな、内がわは円く、外がわは方形になっていた。槨の長さは2.6メートル、幅は1メートル、高さは0.5メートルであった。槨の蓋の厚さは2センチ。槨のつくりは、相当に堅くしっかりしており、きちんとしていた。蓋と壁とをくっつけ縫ったあとは、見出すことはむずかしかった。この一つの遺体については、特別あつかいしているようにみえた。槨の外は布でつつみ封じ、漆の朱い絵がかかれていた。ただ、脱落がかなりはなはだしかった。えがかれている紋様や飾りは、はっきりしていない。重さは、一般の木槨にくらべ、軽いものであった。槨内の棺の木は、すでに朽ちていた。ただ、(中の棺を守るべき)槨はかえって、このように久しくよくたもたれていた。槨が堅くしっかりしていることと、防腐性が比較的高かったことを示していた。これは、特殊な材料を用い加工し、作ったものであることを示していた。
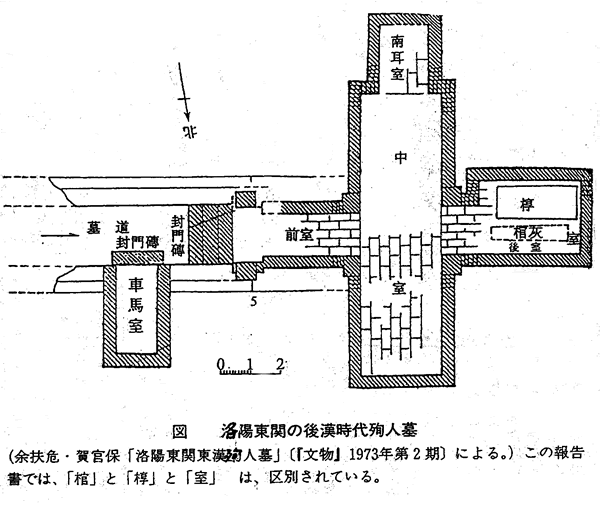
とすれば、ホケノ山古墳よりも、さらに新しいかとみられる箸墓古墳は、当然、ホケノ山古墳よりも時代が下るとみられる。
現在の考古学の主流派は、白石太一郎氏(大阪府立近つ飛鳥博物館館長)らに主導されて、箸墓古墳の築造年代などを百年ほど、古くみつもっている可能性が大きい。この百年の違いは、きわめて大きな違いである。
そして、白石太一郎氏らの理論の主要な根拠は、考古学的事実にもとづくものではない。白石太一郎氏の年代論の主要な根拠は、考古学的な年代論ではなく、笠井新也氏による「古事記の記す天皇の没年」にもとづく文献的な年代論なのである。そして、文献的な年代論にもとづけば、第10代崇神天皇の没年は、西暦360年前後とみられ、箸墓古墳がきずかれたのも、せいぜいその10年前後ていどとみられる。
■『朝日新聞』の予期せぬ新情報
箸墓古墳について、その中は竪穴式石室とみられる。
『朝日新聞』東京本社版2012年9月9日は宮内庁発の1次情報が減って、2次情報が増えている。竪穴式石室の記事がない。
1面

33面
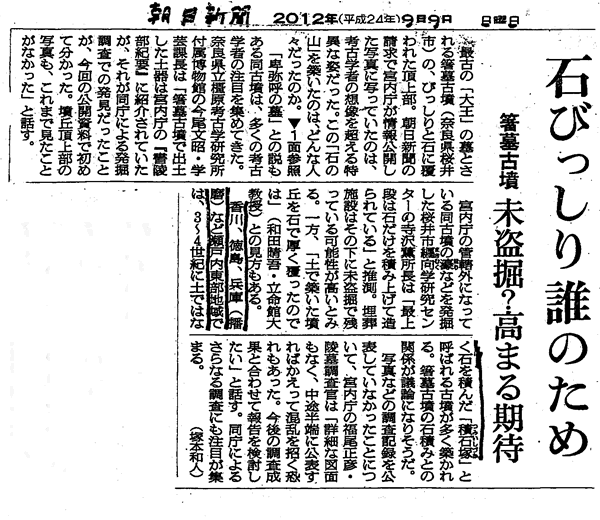
『朝日新聞』大阪本社版2012年9月9日
1面

・地下式板石積石室
箸墓古墳の竪穴式石室について、
九州の川内市には邇邇芸命の墓ではないかと言われているお墓がある。このお墓は「地下式板石積石室墓」という平らな石を積むお墓である。しかし地下に置かれており地面に出てこない。九州の北の方では地面の上の方に土を盛ってお墓とし、割型木棺や箱式石棺を埋めるお墓がある。近畿の箸墓古墳などはこの両方が合わさったようなお墓ではないか。
今回は時間がないので、詳細については別の機会に説明する。