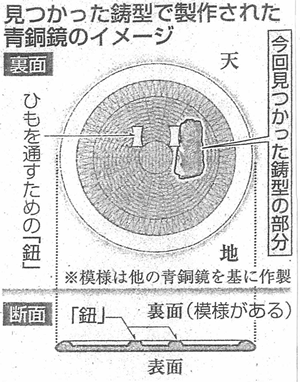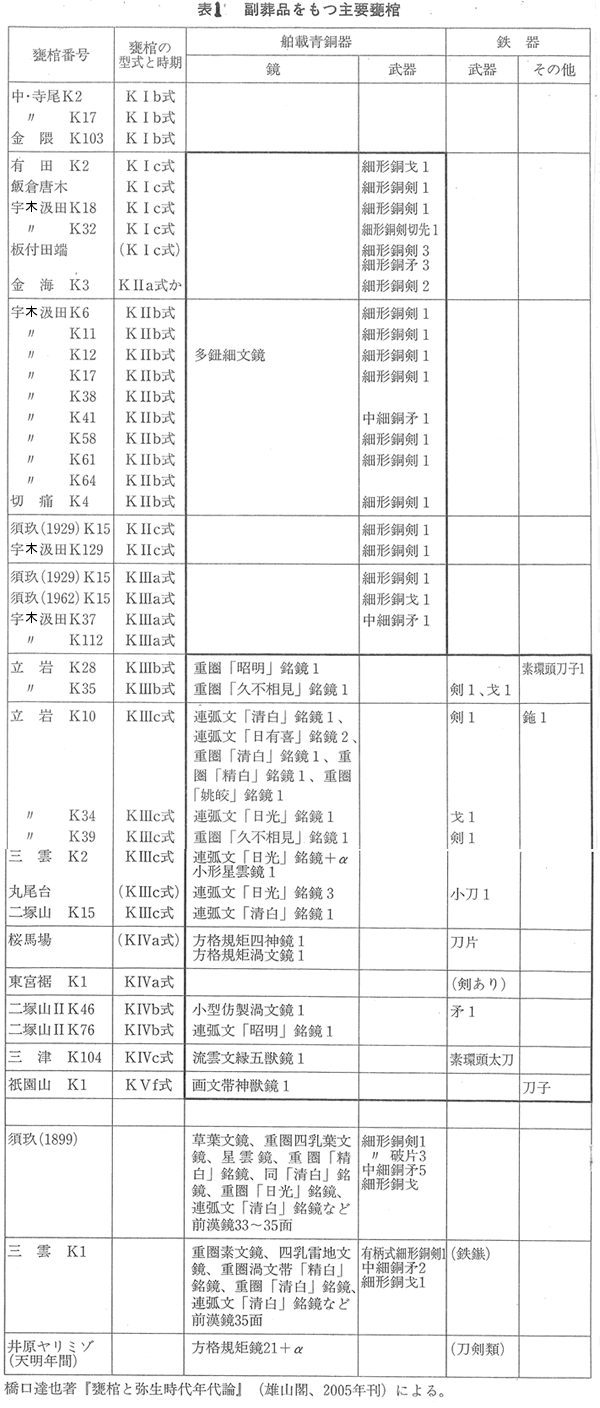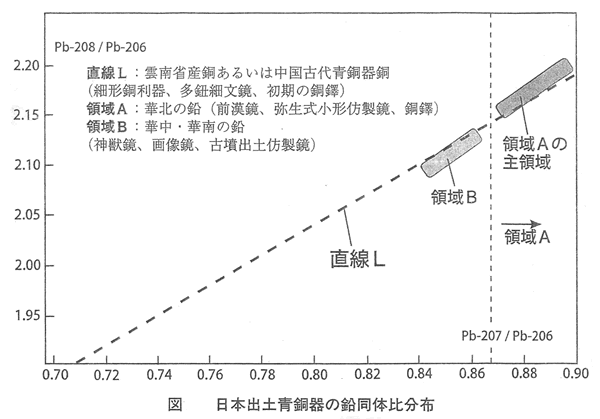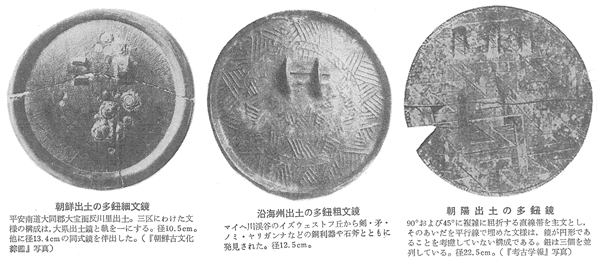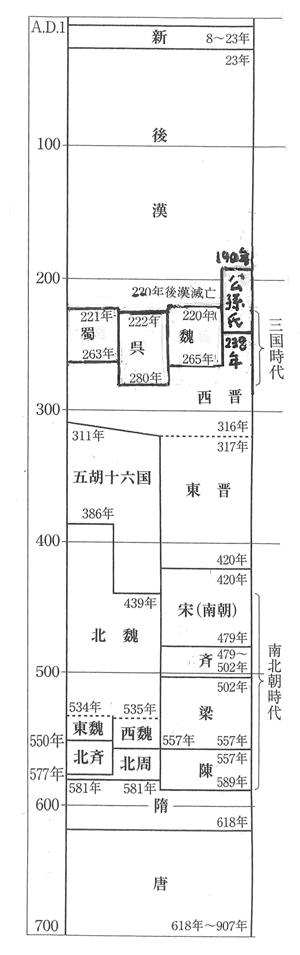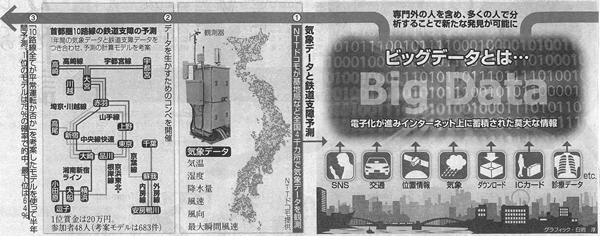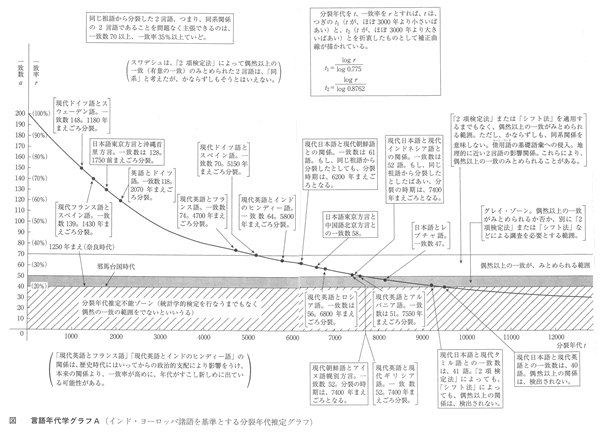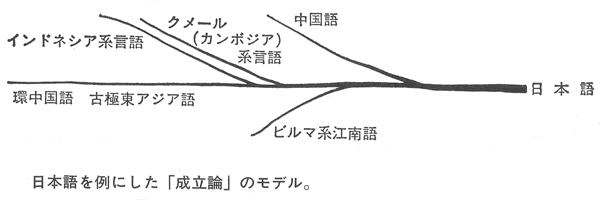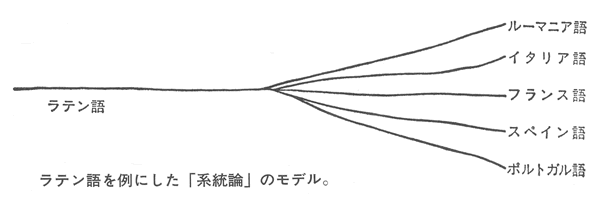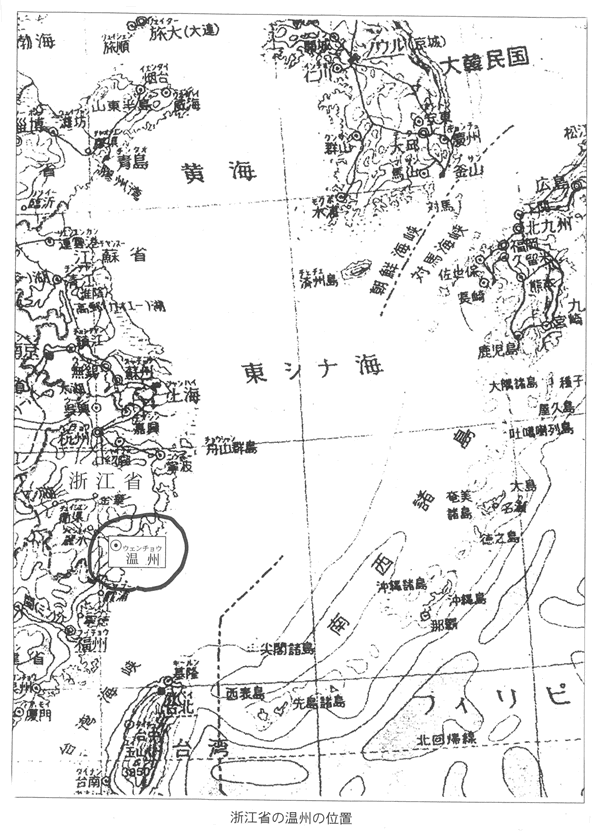■『毎日新聞』2015年5月28日(木)朝刊の「国内最古の青銅鏡型が福岡で出土」記事
(下図はクリックすると大きくなります)

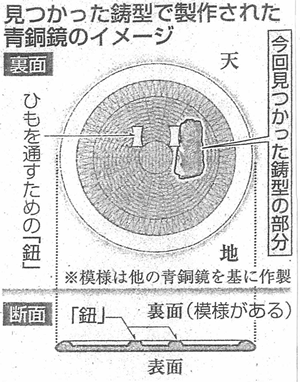
福岡県春日市須玖(すく)タカウタ遺跡で「多鈕(たちゅう)鏡」の鋳型が出土した。
文様の線が細かい「細文鏡(さいもんきょう)」であるという。
石材は朝鮮半島製とみられるが、「重弧文」は日本の弥生時代にほどこされている文様のため、渡来人ではなく倭人が鋳型を作った可能性があるという。
多鈕細文鏡は初期の銅鏡で、海外からの移入のみと、考えられていたが、今回鋳型が見つかったことから、日本でも作られていたと考えられる。
この記事について、『東京新聞』2015年5月28日(木)夕刊の鋳型図が分かり易い。
橋口達也著『甕棺と弥生時代年代論』(雄山閣、2005年刊)より、多鈕細文鏡は古い甕棺の中から出土することが分かる。前漢鏡の「清白」や「日光」や「日有喜」より古いことも分かる。
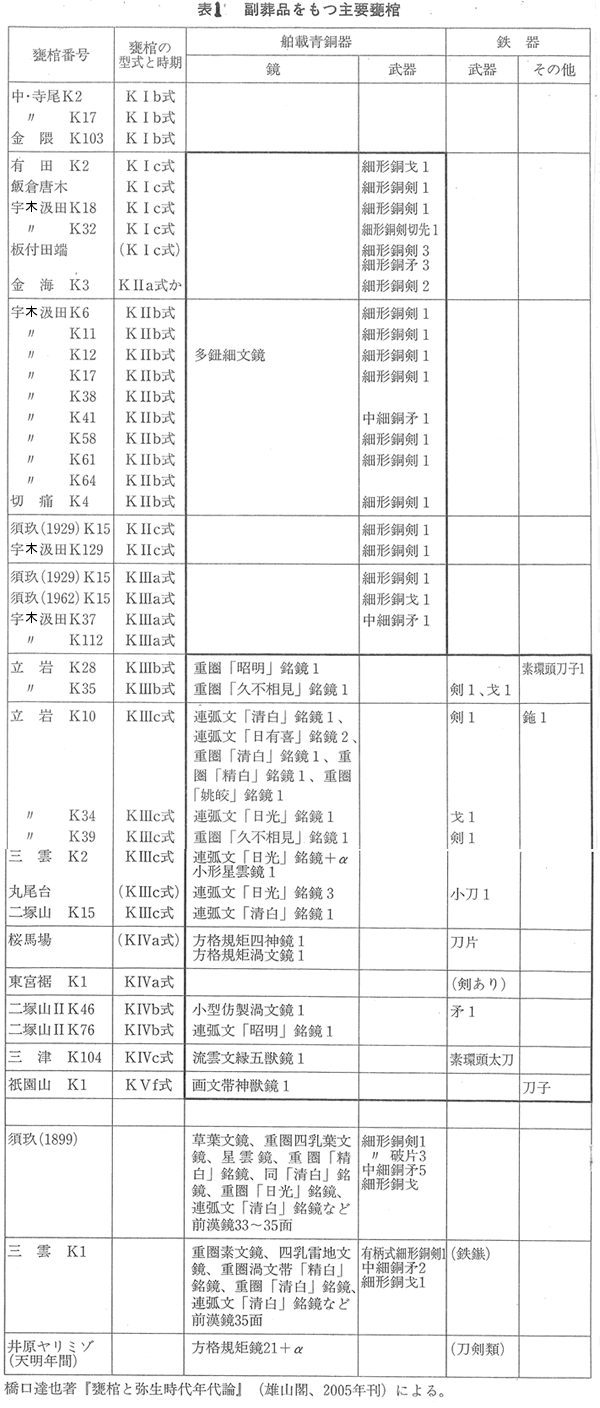
多鈕細文鏡の鉛の同位体比は細形銅利器(銅剣、銅矛、銅戈など)と同じ鉛同位体比である。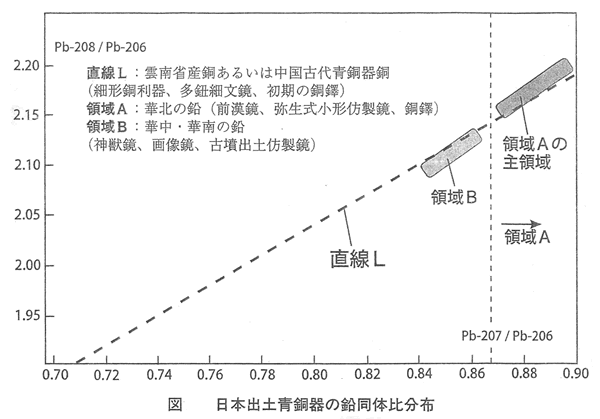
多鈕細文鏡は日本で12面出土している。そのデータを下記に示す。また鋳型の例のデータも示す。
(下図はクリックすると大きくなります)

多鈕細文鏡の例を3例ほどを下記に示す。
これは日本のものではなく、朝鮮、沿海州(現在のロシア)、遼東半島の朝陽(ちょうよう)からの出土品である。(下図はクリックすると大きくなります)
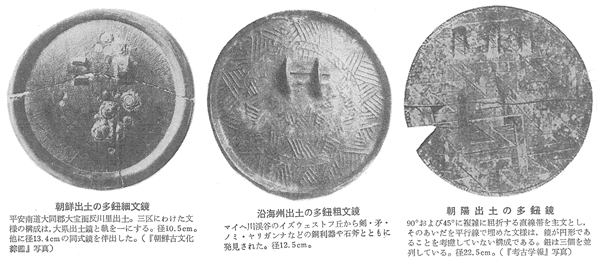
■燧(すい)と鑑(かん)
古代の中国では、凹面鏡と凸面鏡とのちがいを、燧と鑑という文字を用いて区別していた。紀元前につくられたと信じられている『周礼(しゅらい)』という書物には、
「司恒(しこう)氏は夫遂(ふすい)を用いて日から明火をとり、鑑を用いて月から明水をとることを掌(つかさど)る。」
と書いてある。これだけでは意味がよくわからないかと思うので、すこし説明をくわえておこう。鑑というのは、本来は静止した水面に姿をうつす「水かがみ」の意味の文字であったが、しだいに金属製の鏡と混同され、一方では、水をいれる容器の名称として残された。もう一方の夫遂の方は、べつの書物では陽燧(ようすい)ともよんでいるもので、宋の馬縞(ばこう)という学者の説明によると、
「燧は銅でつくった一種の鏡であって、形は鏡と同じようであるが、物の影がさかさまにうつる点がちがう。これを日に向けると火を生じ、その火をモグサでうけて使用することができる。」
という。また、「陽燧は面がくぼんでいる」と明記した書物もある。したがって、燧が凹面鏡であったことには、まちがいはない。
凹面鏡ならば、太陽光線を焦点にあつめて、火をとることができるというのも不思議ではない。しかし、鑑を用いて「月から明水をとる」というのは、はたして、どういう方法によったものか、もう一つはっきりしない。それが、日と月と、火と水とを組みあわせた文飾でないとすれば、月の明るい晴夜に。銅鏡を屋外に放置して冷却し、空気中の水蒸気が水滴となって付着するのを集めるという可能性はあろう。水滴をにがさぬためには、あるいは凹面鏡の方が便利ではないかとも思われるが、そこが中国流の合理主義で、凹面鏡と凸面鏡との機能の相違を、こういうふうに区別して説明したのであろう。
■弥生時代の凹面鏡
さて、前口上が長くなったが、日本で使用してきた鏡のなかでは、弥生時代に輸入されて凹面鏡が、おそらく、もっとも古いものであったらしい。どうして、凸面鏡より凹面鏡の方がさきにはいってきたのであろうか、こういう重要な問題については。まだ、満足な説明はあたえられていない。まず、その謎から解いてみよう。
日本で弥生時代の遺物として発見される凹面鏡は、その裏面に、細線によって表現した幾何学的文様が鋳出してあり、円鏡の中心から一方にかたよった位置に、紐(ひも)をとおす孔(あな)をもった長方形平面の鈕(ちゅう)が、ふつうは二個つくりだしてある。この鏡にたいして、考古学上の用語として、多鈕細文鏡(たちゅうさいもんきょう)という名称があたえられることになったのは、鈕が一つでなく、文様は細線で表現しているという意味からである。この名称は、当然、このほかに一個の鈕をもった鏡があることを前提としているが、そのことは、もうしばらくあとまで、説明を保留しておきたい。
さて、多鈕細文鏡は弥生時代の遺物であるといったが、いままでに日本で発見された数は。わずかに四枚にすぎない。それを西の方からかぞえあげると、佐賀県唐津市宇木汲田(うきくんでん)の甕棺[かめかん](弥生式土器の甕を棺とした墓)から一枚、山口県下関市梶栗浜(かじくりはま)の箱式石棺(板石を長方形に組みあわせて、板石の蓋をした墓)から一枚、大阪府柏原(かしはら)市大県(あがた)の山中から一枚、奈良県御所(ごせ)市長柄(ながら)の山麓から一枚ということになる。
弥生時代の日本には、青銅でつくった器物として有名なものに、銅剣・銅矛(どうぼこ)・銅戈(どうか)の類と銅鐸(どうたく)との二種があり、その分布も、銅剣・銅矛類は北九州地方を中心とした地域に、銅鐸は近畿地方を中心とした地域に集まっているということは、中学生でも知っている事実である。
そのうえ、瀬戸内海の中央部の諸所では、銅剣と銅鐸とが同じ場所から発見されたという遺跡が、すでに四ヵ所ほどわかっている。それは、同じ弥生時代といっても、北九州地方と近畿地方とでは、多少ちがった風習があったことを、また、瀬戸内海の中央部は、その両方からの影響をうけた地域であったことを想像させる原因になっている。
ところが、多鈕細文鏡だけは、その両方の地域から、二枚ずつ発見されていることになる。しかも、佐賀県宇木汲田と山口県梶栗浜とでは、海岸に近い場所につくった弥生時代の墓の中に、この鏡が銅剣銅矛類と一緒に埋めてあった。それにたいして、大阪府大県と奈良県長柄とでは、山腹あるいは山麓の、墓とは思えないところに鏡が埋まっていた。とくに奈良県長柄では、鏡と一緒に一個の銅鐸も埋めてあった。
そうなると、弥生時代の日本を、銅剣銅矛類と銅鐸とを代表として、二つの地域にわけたことは、そのどちらにも多鈕細文鏡があるという点からいえば、結局は、二つの地域の風習には共通性もある、という説明ができることになってくる。
そのばあいの共通性を、もうすこしくわしく考えてみようとすると、多紐細文鏡が凹面鏡であるという事実が重要になってくる。多鈕細文鏡は凹面鏡であるから、顔をうつせば倒立してうつったであろう。それでは、姿見としての役にはたつまい。ただし、凹面鏡とはいうものの、その曲率はかなり大きいから、太陽光線を焦点にあつめて火を採ることができたかどうかは疑わしい。しいていえば、太陽光線を反射させて、人を驚かすことができたていどではなかったかと思う。
多鈕細文鏡が尊重された弥生時代の中期は、日本人がまだ石器を使用していた時代であることを、まず思いだしていただきたい。青銅や鉄などの金属製品は、すこしは用いられていたが、ふつうの生活には縁のすくない貴重品であった。
したがって、現代の子供なら、だれでも経験をもっているような、ガラスの鏡で太陽光線を反射させて、人をまぶしがらせるという種類のいたずらは、弥生時代の日本人には想像もつかぬことであった。弥生時代にはガラスの鏡がなかったはずではないかと、あげ足をとってもらっては困るので、よく磨いた金属の表面でも、同じように太陽光線を反射できることを思いだしていただきたい。その金属製品が凹面鏡ならば、なおさら好都合だということになる。
太陽崇拝 こういうふうに考えてくると、私には、弥生時代の日本人が、多紐細文鏡をどのように使用したかということが、ほぼ想像できるように思われる。
すなわち、まず鈕が鏡の中心からかたよった位置に二個あるから、紐をとおしてさげると、鏡の表面は、だいたい垂直に近くなる。それを榊(さかき)の枝にとりつけて、一入の女性が人々の前に姿をあらわしたとしよう。
それは、よく晴れた日でなければならない。待ちかまえた人々は、おそるおそる巫女(みこ)の姿をあおぎ見、つぎに鏡に眼をうつしたことであろう。その時、巫女が榊の枝を静かに勣かすと、一瞬に、鏡の面に反射された太陽のまばゆい光輝が、人々の眼を射る。はっと驚いた人々は、眼をとじて平伏したであろう。しかし、眼をとじてみても、開いてみても、網膜に焼きつけられた太陽の残像は、あるいは緑に、あるいは紫に変化して、もう一度、いま見たものをたしかめようとしても、ただ不思議な色彩が見えるばかりであったろう。
ようやく時間がたって、あたりの光景を、ふつうの状態に見ることができるようになった時には、巫女の姿は鏡とともに消えている。
こうして人々は、巫女が太陽を自由にするほどの呪力をそなえていることを、確信したにちがいない。太陽を支配するとは考えなかったとしても、人々が太陽にたいして、稲の生育をすこやかにするように、十分な日照りをあたえてほしいと願う時には、その願いを太陽につたえてくれるだけの能力を、この巫女がもっていることは、信じえたと思うのである。
こう考えてくると、さらに想像をたくましくしたくなることがある。それは、近畿地方では多紐細文鏡を墓には埋めなかったのに、北九州地方ではそれを墓に埋めているという問題についてである。
鏡を墓に埋めてしまえば、鏡による呪術はおこなうことができなくなってしまう。北九州地方では、それほどまでに、鏡をつかって太陽を祭った巫女の呪力が強大であり、しかも、人々の信望をあつめうる適当な後継者がなかったからだとも考えられないわけではないが、私は、もうすこしちがった考え方をしてみたいと思う。
それは、北九州地方の人々は、凹面鏡をつかって太陽を祭るという風習をもっていなかったのではないか、という推論である。
どうして、そのような推論ができるかというと、じつは、これらの多紐細文鏡は、日本でつくったものではなく、朝鮮からの輸入品であるからである。その証拠に、朝鮮では、北の平壌付近からも、南の慶州付近からも、日本で発見されているよりも、はるかに多数の多紐細文鏡が出土しているからである。
したがって、日本の問題としては、北九州地方の人々は、銅剣銅矛類などと一緒に、この鏡を朝鮮から輸入はしたが、それを自分たちの生活のなかにとりいれて活用することを知らなかったのではないか。ただ、外国製の宝物として、所有することに誇りを感じたにすぎなかったのではなかろうか、と考えてみたいのである。
それにたいして、近畿地方の人々は、北九州地方にはない大型の銅鐸をつくって、かれらの農耕生活に欠くことのできない宝器としたように、輸入した多鈕細文鏡にたいしても、その鏡の特徴を生かした用法を体得していたと想像するわけである。
それがあまりに想像にすぎるといわれるならば、しいてこだわる必要はない。日本でも朝鮮でも、多鈕細文鏡という凹面鏡を使用する太陽崇拝の風習が、ひろく古代に存在したというていどにまで、話を簡単にしても、いっこうにさしつかえはない。しかも、それならば、文様は日本や朝鮮のものとはちがっているが、同種の凹面鏡の分布範囲は、鴨緑江を北にこえて、中国東北部にも、沿海州にもひろがっているという事実を紹介することによって、問題を展開する方法があるからである。
天照大神が扉をすこしあけてのぞき見をした時に、「私が天岩戸の中にかくれたのに、神々はどうして楽しそうに笑っているのか」と尋ねられたら、「貴女よりも、すぐれた神があらわれたので、一同で喜んでいるのです」と答える計画になっていた。天照大神はこの返事を聞いて、どのような神が出現したのかと、さらに扉をあけて顔をのぞかせた。その顔の前に、かねて用意の鏡をさしだしたのである。天照大神は、鏡にうつった自分の顔を、新しい神の姿と思いこんで、まんまと天岩戸からつれだされたという説明もつけくわえてある。
ただし、この神話をそのままに生かそうとすれば、この時につくった鏡は、人の姿がそのままにうつる鏡であったことになり、もはや多紐細文鏡のような凹面鏡では理屈がとおらない。ところが、日本の古代には、姿をうつすための凸面鏡もまた弥生時代にすでに、中国から輸入されていたのである。この中国鏡は凸面鏡であると同時に、背面の中央に一個の紐をもつことを特徴としていた。
■青銅材料は燕から来た
以前話した淡路島から出土の菱環鈕式銅鐸と多鈕細文鏡とは同じ鉛の同位体比で、燕の国から来た銅を使っていたと考えられる。
・『山海経』のなかの倭
中国に『山海経』という文献がある。
『山海経』は、古代中国の神話と地理のことを書いた本である。山や海の動植物のことや、金石のこと、また、怪談などを記す。十八巻からなる。
著者は不明である。古代中国の伝説上の聖王であった禹(う)が書いたともいい、また、禹の治水を助けた伯益(はくえき)が書いたともいう。もともと、ひとりの人が、ある特定の時代に書いたものではないとみられる。
『史記』を書いた司馬遷が読んでいる。前漢時代の学者の劉款[りゅうきん](紀元前53~紀元後21)が校定し、叙録(じょろく)(大まかな内容を記したもの。解説文)を書いている。
したがって、漢代にはすでに存在していた。戦国時代~秦・漢代の著述とみられる。
その『山海経』の第十二の「海内北経」のなかに、「倭」についての、つぎの文がある。
「蓋国(がいこく)は鉅燕(きょえん)の南、倭の北にあり。倭は燕に属す。」 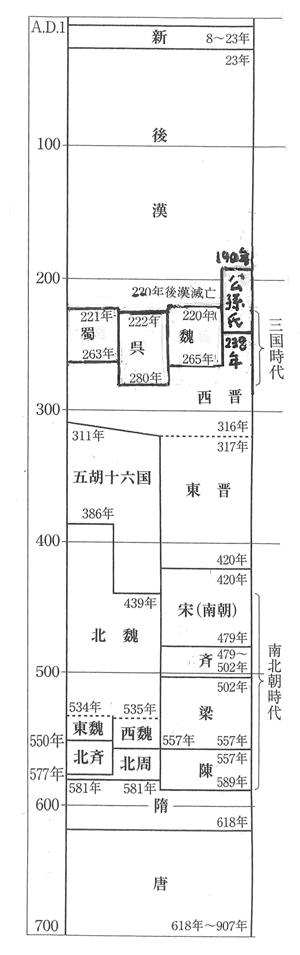
・『漢書』「地理志」のなかの「倭」
『漢書』は、前漢の歴史を記した本である。後漢の班固の撰。西暦82年ごろに成立した。
『漢書』の「地理志」の下の巻の燕地の条に、つぎのような文章がある。
「楽浪の海のかなたに、倭人がおり、百余国に分かれ、歳時(季節)ごとに来て、物を献上し見(まみ)えた[見(まみ)える]、という。(楽浪海中有倭人分為百余国、以歳時来献見云)」
この文章の問題点は、二つある。一つ目は「燕地」の条に記されていること、二つ目は、おしまいが「云う」と伝聞になっていることである。
したがって、「献上し見(まみ)えた」対象が、「燕」であるとも「漢」であるとも読めることである。
すなわち、つぎの二とおりの読み方が成立しうる。
①かつて、倭は燕に属していた。そのころ倭人は、百余国に分かれていた。季節ごとにやって来て、物を献上し、燕に見(まみ)えたという話だ。
②かつて燕のあった地の楽浪の海のかなたに倭人がいる。百余国に分かれ、季節ごとに、(漢の武帝が、紀元前108年に今の平壌ふきんにおいた楽浪郡の官庁に、)やって来て、漢に対して物を献上し、見(まみ)えると聞いている。
ただ、『後漢書』の「倭伝」の最初のところに、つぎのように記されている。
「倭は、韓の東南大海の中にある。(倭人は、)山島により居(すまい)を為(つく)する。およそ、百余国である(あるいは、百余国であった)。(前)漢の武帝が[衛氏(えいし)]朝鮮を滅ぼしたのち、漢に通訳と使者を派遣してきたのは、三十力国ほどである。」
また、『魏志倭人伝』の冒頭には、つぎのように記されている。
「倭人は、(魏の)帯方郡の東南、大海のなかにある。山島(しま)のなかに国ができている。旧(もと)百余国(むかしは、百以上の国があった)。漢のとき、来朝するものがいた。今、使者と通訳とが往来しているのは、三十力国である。」
これらの記事をまとめると、「漢以後には、使者と通訳とを派遣しているのは三十力国ほどで、それよりもむかしには百余国あった。」ということであるようにみえる。
つまり、さきの『漢書』「地理志」の倭についての記事は、燕の時代のことの伝聞のようにみえる。
もともと、『漢書』の「地理志」の燕地の条の記載は、各地の伝統的風俗を述べている部分の一つとして、がっての燕の地で行なわれていたことを述べている部分に記されているものである。
・公孫氏との倭
公孫氏について、『東洋史辞典』(東京創元社刊)の記述に下記がある。後漢末から三国時代に活躍した遼東の豪族。はじめ公孫度(字は升済)が郡吏に任じられ、のち遼東の太守となった。
彼は東は高句麗、西は烏桓、南は東莱の諸島を討って大いに領土をひろげ、 190年(初平元)自立して遼東侯・平州牧となり、強力な地方政権を樹立した。度の死後子の公孫康が位を嗣ぎ、207年袁紹を斬って魏の曹操に献じ、襄平侯に封じられ、左将軍を拝した。康の死後、弟の恭が衆に押されて嗣立したが、康の子の公孫淵が成長すると恭を脅かして位を奪った。その後、魏は淵に来朝を命じたが、淵はこれに応ぜず、自立に燕王と称し、百官を設けた。238年、魏は司馬懿を遣わして公孫氏を攻め、淵父子を斬ってその政権を倒した。
つまり、後漢の末ごろ、公孫氏という豪族が昔の燕の国の地域に起こり、卑弥呼が魏に使いを出す前の年に魏によって滅ぼされた。年表参照。
このように、倭に関して、燕に属していた。次に前漢、次に新、次に後漢、次に公孫氏、次に魏、次に西晋に属していた。そして、次に東晋へと使いを出した。と考えられる。
また、新にも属していたと考えられるのは新の方格規矩鏡が出土していることによる。
倭と中国の国々との関係について、全て歴史書がある訳ではないが、下記の倭伝が考えられる。
①燕史倭伝
②前漢史倭伝
③新史倭伝
④後漢史倭伝
⑤公孫史倭伝
⑥魏志倭人伝
今日は『燕史倭伝』の話をしたが、今後順を追って、各倭伝としての話をしていく。