| �@ |
|
TOP>�����L�^>�u����>��Q�O�Q�� | �ꗗ | ���� | �O�� | �߂� | �@ |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
�@ |
��Q�O�Q��@�u�����i2002.5.12 �J�Áj
|
||||
�@����̑�֓`���Ɛ��S�̊W
|
�P�D�u����̑�֓`���v�����S�ƊW����Ƃ��鏔��
�@���@�_�b�w�҂̑�ё��ǎ��̐�
���}�^�m�I���`�_�b�ɂ�����o���Ƃ����v�f�͏o�_�n�������̎�v�ȓS�Y�n�ł���A�������o�_�Y�ł���Ƃ����Â��`���A���邢�͐_�b�Ҏ[�҂̓��ɂ������Œ�I�ϔO�̔��f�ł��邱�Ƃ́A���łɑ����̊w�҂��l���Ă����B
��̉͂̏㗬�A�����i����j�̕��y�Ɨ��j�A������l�@����ƁA�_�b�̔w�i�ƈӋ`������w�N���ɂȂ��Ă���悤�ȋC������B
�S�ɂ��Ď��̎O���čl����K�v������B
�������E�E �@ �@���@���S�͓�����H �S�̐��ƂŁw�S�̍l�Êw�x�i�Y�R�t�o�Łj�̒��҂ł���E�c���Y�����玟�̂悤�Șb�����B �S�z����S������̂ɂ́A�����Z�p��K�v�Ƃ���ƍl����ꂪ���ł��B�������A���Ȃ炸�����A�����Ƃ���͂����Ȃ��̂ł��B�S�z��Ԃ��M���āA�_�f���Ƃ�A�ӂ��U��Ȃ��悤�ɁA�����ƍ��C�悭�������Đ̕������Ƃ��čs���A�X�O�O�x���炢�ł��A�S�͂ł���̂ł��B�@ �܂��A�R�{�����͒����w�Ñ�̐��S�x�i�w���Ёj�̂Ȃ��ŁA���̐��B�ɂP�P�O�O�x�̉��x���K�v�Ȃ��ƂȂǂƔ�ׂāA���S�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ�B
�E�S�z����S�𒊏o������@�́A���z���瓺�𒊏o������ȒP�ł���B �͌��ɂ悭���������S���U�O�Z���`�قǐςݏグ�A���̏�ɑ�ʂ̐d���̂��ĉ������R�₵�����A�����ɂȂ��ēS����E���W�߂Ă����B�@�i�w��������{�×��̐��S�Z�p�x�@�ʐ��w�o�ŕ�1976�N���j ���ɊȒP�A�����n�I�ȕ��@�ɂ���Ă��A���S�͂ł���̂ł���B�@ �@���@���S�̍s��ꂽ�̂͂U���I���炩�H �L�����O���s�������̏��ۈ�Ղ���O���I�̐��S�F����������i1995�N1��13�������V���[���j�A���S�͖퐶����̌������s���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ����B
�P�X�X�T�N�P���P�R�������V���[�� �R�D�u����̑�֓`���v�ɂ��Ă̑��̉��� �@���@���u�i�����j�̔���̑�ւƂ����L�q�ɂ���
����̑�֓`�������S�ɊW����Ƃ�����ɂƂ��āA���߂ɍ���L�q������B �u�I���`�v�́u�I���`�����v�ƊW������Ƃ��āA�u����̑�ցv�B�⍕���]����A���C�B���ʂɏZ�ރc���O�[�X�n�́u�I���`�������v�ƌ��т����������B �@���@����̑�ւ́A�z�ɏP�����Ă����l�T�i�݂��͂��j���B�w���{���I�x�̋Ԗ��V�c�T�N�i544�N�j�̏��ɁA�u�z�̍����猾�オ���荲�n�̍��ɏl�T�i�݂��͂��j�����Ă���B�v�Ƃ���B�܂��Ė��V�c�S�N�i658�N�j�ɂ��A�u���̔N�A�z�̍���̈������c�b�䗅�v�͏l�T�����v�Ƃ���A�l�T�́u�z�v�Ɏ��X�o�v���Ă����B�w�O���u�x�̂Ȃ��̏l�T�̋L�q�̒��ɁA�C�̓��ɍ��i�`�j������A���N�V���ɓ����������тɂȂ�Ƃ����b���łĂ���B���N�A�����������ɂ��ɂȂ�_�ł́w�Î��L�x�̋L�q�Ǝ��Ă��镔��������B���邢�́A���N�A�l�T���u�z�v�ɂ��āA������D���Ă������B����̑�֓`���́A�����f���j�������s�����b���Ƃ�����ł���B �@���@����̑�ւ́A��C�̗�i���j�̂��Ƃł���B���Ƃ��ƁA�u��C�v�Ƃ����n��������A���́u��C�v�̒n�́A�u��i���j�v�i�_��I�ȗ͂������́B�e���˒q�i�������F�̐_�j�A�v�v�\�q�i�����̂��F�̐_�j�Ȃǂ̗Ⴊ����B�j�ł���I���`����������B �@���@�����ގ��`����r�_�b�w�̗��ꂩ��́A�M���V���_�b�̉p�Y�y���Z�E�X�����h�b�T��ގ�����ȂǁA���E�e�n�ɕ��z���鈫���ގ��_�b�̈�ό`�Ƃ��݂���B ���낢��Ɖ��߂����邪�A�u���u�v�ȂǁA�������ɍ���Ƃ����������̂́A�S�̓I�Ɍ���u����̑�֓`���v���A���S�ƌ��т�����́A���̐��̔�ׁA�L�͂ł���悤�ɂ݂���B |
�@����̌��́A�S������
|
|
����̌��i�����Ȃ��̂邬�j�́A�����S���A�Ƃ����c�_������B
�勝�R�N�i1686�N�j�M�c�_�{���C�����ꂽ�Ƃ��A�_��l��������������ł��鑐��̌��������B���̂Ƃ��̓`���ɂ��ƁA����̌��́A
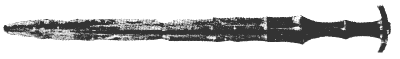
����̌��ɂ��ẮA�M�c�̔����̘A�̌����`���Ƃ��āA�����Ƃ̐��蠁i�킽��j�����A�����w���{�����S�j�x�̂Ȃ��ł��̂悤�ɏq�ׂĂ���B ��_�͈̂�ڔ������A���n�ɂ��Č��Â���ƂȂ�A�M����ĉ���Ȃ��A�䕿�͒|�̐߂̔@���ܐ߂���A�[�����тꂽ��B ���낢��̏������������Ă݂�ƁA�S���Ƃ��Ă���Ȃ��̂́A�u�F�́A�S�̔����Ƃ����v�Ƃ����_�ł���A�����Ƃ��č���Ȃ��̂́A�u������ڎ��A�����v���邢�́u��ڔ����v�Ȃǂ̒����ł���B�S���Ƃ݂Ă��A�����Ƃ݂Ă���△���ȓ_������B�����A�F�����A�����̕����A�ώ@�̑ΏۂɂȂ�₷���悤�Ɏv����B�����̂ق��ɏd�_�������A���A����I�w�i�ȂǁA�S�̂����Ă���A����̌��̓S�������A�Ȃ�����������悤�ɂ݂���B 
 |
| �@ |
|
TOP>�����L�^>�u����>��Q�O�Q�� | �ꗗ | ��� | ���� | �O�� | �߂� | �@ |