『魏志倭人伝』は次のように記す。
(帯方郡から)七千余里にして、はじめて一海をわたり、千余里で対馬国にいたる。その大官を卑狗(彦)といい、副(官)を卑奴母離(夷守)という。いるところは絶島(離れ鳥)で、方(域)は、四百余里ばかりである。土地は、山けわしく、深林多く、道路は、禽と鹿のこみちのようである。千余戸がある。良田がない。海(産)物をたべて自活している。船にのり、南北に(出て)市糴(米をかうこと)をしている。
原文「七千餘里始度一海千餘里至對馬國其大官曰卑狗副曰卑奴母離所居絶島方可四百餘里
土地山嶮多深林道路如禽鹿徑有千餘戸無良田食海物自活乗船南北市糴」
■7000里の解釈
普通は帯方郡から7000里で狗邪韓国に到着したと解釈する。
しかし、中国語学者の藤堂明保氏などは、帯方郡から7000里行ったところで沿岸航路を離れて海を渡ると解釈し、狗邪韓国には寄港しなかったとする。
潮流を考えると、金海(狗邪韓国)に到る前に南に向かうほうが現実的である。金海を出て対馬に渡るには、対馬海流に逆らって航行することになる。
以前、手こぎの船・野生号で倭人伝の航路の実験航海が行なわれたが、金海に寄港した野生号は、海流に流されて自力では対馬に到達できなかった。
■倭人伝の一里の長さ
現在の日本の「一里」は約4kmだが、中国ではどの時代でも一里は約400m強であった。
長さの単位の時代別変遷(『角川漢和中辞典』による)
| 時代 | 周・春秋
戦国・前漢
前10-
前1世紀 | 新・後漢
1-3世紀 | 魏
3世紀 | 隋
6-7世紀 | 唐
7-10世紀 | 宋・元
10-14世紀 | 明
14-17世紀 |
分
(cm) | | 0.2304 | 0.2412 | 0.2951 | 0.311 | 0.3072 | 0.311 |
寸
(cm) | 2.25 | 2.304 | 2.412 | 2.951 | 3.11 | 3.072 | 3.11 |
尺
(cm) | 22.5 | 23.04 | 24.12 | 29.51 | 31.1 | 30.72 | 31.1 |
丈
(m) | 2.25 | 2.304 | 2.412 | 2.951 | 3.11 | 3.072 | 3.11 |
歩
(m) | 1.35 | =6尺
1.3824 | =6尺
1.4472 | =6尺
1.7706 | =5尺
1.555 | =5尺
1.536 | =6尺
1.555 |
里
(m) | 405 | =300歩
414.72 | =300歩
434.16 | =300歩
531.18 | =360歩
559.8 | =360歩
552.96 | =360歩
559.8 |
ところが、『魏志倭人伝』記載の「一里」は、実測すると、平均して100メートル以下にしかならない。
| | 魏志倭人伝の記述 | 実際の距離
(中数) | 一里は何メートルか |
帯方郡→狗邪韓国
(京城・沙里院) (巨済島・金海) | 7000余里 | 630−710km
(670km) | 96m弱 |
狗邪韓国→対馬国
(巨済島・金海) (佐護・厳原) | 1000余里 | 64−120km
(92km) |
92m |
対馬国→壱岐国
(佐護・厳原) (原ノ辻・勝本) | 1000余里 | 53−138km
(95.5km) | 98m弱 |
壱岐国→末廬国
(原ノ辻・勝本) (呼子・唐津) | 1000余里 | 33−68km
(50.5km) | 51m弱 |
末廬国→伊都国
(呼子・唐津) (井原・平原) | 500里 | 32−47km
(39.5km) | 80m弱 |
伊都国→奴国
(井原・平原) (須玖岡本) | 100里 | 23−30km
(26.5km) | 265m |
奴国→不弥国
(須玖岡本) (宇美町・穂波町) | 100里 | 6−24km
(15km) | 150m |
| 合計 | 10700余里 |
989km |
93m弱 |
『魏志』の「倭人伝」「韓伝」に記されている次のような「里数」は、400m強の中国の標準里では説明がつかない。
- 韓−−−方可四千里
- 帯方郡→狗邪韓国−−−−七千余里
- 狗邪韓国→対馬国−−−−千余里
- 対馬国・・・・・方可四百余里
- 対馬国→一大(支)国・・・千余里
- 一大(支)国・・・・・方可三百余里
- 一大(支)国→末盧国−−−−千余里
- 末盧国→伊都国−−−−五百里
- 伊都国→奴国−−−−−百里
- 奴国→不弥国−−−−−百里
- 帯方郡→女王国−−−−万二千余里
100m以下となる「実測里」と400m強となる「標準里」との大きな違いはなぜ生じたか。これについては次のようなさまざまな説が提出されている。
- 標準里説
倭人伝、韓伝記載の里数は中国の標準里で説明できるとする説。
例えば、韓の「方可四千里」、対馬国の「方可四百余里」、一大(支)国の
「方可三百余里」などについては、「一辺の長さ」ではなく「周の長さ」を示していると考える。
また、郡から狗邪韓国への7000里や女王国までの12000余里については、出発点を「洛陽郡」とし「帯方郡」は経由地と解釈する。
さらには、朝鮮半島西側のリアス式海岸の実際の航行距離は、地図上での概算に比べ遙かに大きくなるとする。
しかし、4倍もの距離になるというのは、自然な説明とは言い難い。
- 誇張説
白鳥庫吉が論文「卑弥呼問題の解決」で詳しく述べた。
誇張の理由は、「魏使が重い恩賞にあずかろうとする下心から、ことさらに、倭国を遠隔地の地に置こうとした。」
あるいは、「当時、魏は公孫氏や高句麗を討ち、楽浪、帯方の二郡を置いて勢いが盛んであり、魏の中央政府が倭国征討を唱えようとしていた。戦乱を嫌う地方(帯方郡)の役人が、この動きを封じるため、倭は遠隔の地であると報告した。」というもの。
しかし、この説には実証的な根拠がまったくない。
- 地域的短里説
山梨大、立命館大の教授だった地理学者の藤田元春は『上代日支交通史の研究』のなかで、魏志倭人伝の道里について述べ、「魏略時代に書記された多くの倭韓の里は古周尺の尺度による」としている。すなわち、実際に当時おこなわれていたモノサシによるものであろうとした。
藤田氏は、わが国においても、地域によって、一里が36町であったり、50町であったり、42町であったり、5町であったり、6町であったり、不定ではあるが、それなりの標準があったことを述べ、『魏志倭人伝』の道里もそれほど不確実なものではないであろうとする。
更に、藤田氏は、「道里というものは、いったん定まると容易にかわらないといえる。したがって、『魏志』の道里なども無闇に記したものではなく、おそらく魏以前のよほど古い時代の言い伝えではなかったかと考える。
漢代の一里は、およそ400メートルである。しかし、日本は遠い国であって、漢代では中国本土の尺よりも、さらに古い尺を用いていたのではなかったか。漢尺よりも古い尺は周尺である。」
と述べる。そして、いくつかの仮定をおいたうえであるが、藤田氏は次のように結論を述べる。「魏略時代に書き記された多くの倭韓の里は、すべて今の日本里(一里=約4km)の1/40という古周尺の尺度(一里=約100m)で、全部明瞭に説明がつく」
安本先生も著書『邪馬一国はなかった』の中で、周・春秋・戦国時代の「短里」が残存した可能性について次のように述べた。
千数百年前、日本より広い中国で、時代的、地
域的にさまざまなモノサシが用いられた可能性がある。陳寿は、もとの資料にあった
「里数」を尊重し、それをそのまま『三国志』にのせた可能性が大きいと考えられる。
陳寿が、どの地方でどのような里制が行われていたかを正確に知り、それらを統一的に換算することは、困難であったろうと思う
そして、周・春秋・戦国の時代に(ある地域で)行われていた「短里」が、三国時代においても、朝鮮半島南部を中心とする中国周辺で、地域的に行われていた可能性が大きい。
なお、中国最古の天文算術書といわれている『周髀算経』にのっている「里」の一里が、約76〜77メートルになることについて谷本茂氏の論文がある。(季刊邪馬台国35号)
- 魏晋朝短里説
『三国志』全体が「短里」で書かれたとする。古田武彦が『「邪馬台国」はなかった』
で主張した。
この説は現在ほぼ否定されている。篠原俊次による詳細な研究によれば、『三国志』のなかの「韓伝」「倭人伝」以外の中国本土の距離の記載は、すべて標準里によって説明される。
- 日数換算説
謝銘仁の『邪馬台国・中国人はこう読む』によると、中国では、古代から近世に至る
まで、行程の測定にあたって、水路、海路の場合は「更(庚)」を基準とし、陸路の場合は「亭」「置」「伝」などを基準とした。
海路の船旅で、更を測るために線香や水時計を用い、線香を焚いて、その消費した本数や残る長さで時間を計っていた。
「亭」「置」「伝」は一里塚のように一定距離ごとに目印の樹木や施設が置かれたもので、陸路を行く場合は、その数で道のりを求めていた。
さまざまな事情でこうした方法が適さない場合は、日程をもって表記するのが普通のしきたりであった。倭人伝の里程は、このように時間や日数で測った記録を、陳寿が机上で里数に換算したのではなかろうか。
リアス式海岸の航行や、険しい道の歩行、あるいは港での潮待ちなどで、予想外に日数がかかった場合も、旅の日数として一定の換算率で里数に換算された可能性があり、これが、長大な里数になった理由ではないだろうか。
- 類ハッブル定律現象説
天文学では、地球から離れるほど、星雲の遠ざかる速度も大きいという、『ハッブル定律』がある。
同じように、都から離れるほど里数は感覚的に増えていくものらしい。尾崎雄二郎は、「古代の里程記事において、類ハッブル現象が見られるのではないか」と考えた。
『魏志倭人伝』のもとの記事が正確と考えるより、やや
漠然と考える方が、かえって真をついているかもしれない。




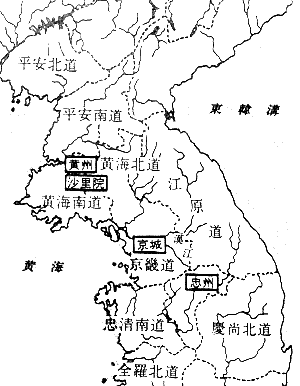 これについては次の三つの説がある。
これについては次の三つの説がある。
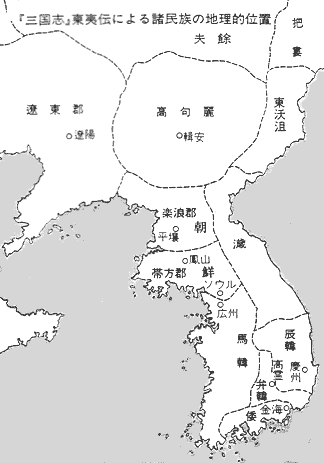 ■「其北岸」の解釈
■「其北岸」の解釈 」の銘が発見された。帯方太守の墓があるのだから、この地が、帯方郡治のあった場所とする。根拠がうすいとの反論もある。
」の銘が発見された。帯方太守の墓があるのだから、この地が、帯方郡治のあった場所とする。根拠がうすいとの反論もある。