| TOP>活動記録>講演会>第264回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第264回 特別講演会(2007.12.16 開催) | ||||
高松塚古墳とキトラ古墳(その国際性と独自性) 佐古和枝先生 |

高松塚古墳とキトラ古墳は7世紀後半から8世紀初頭の古墳。7世紀がどのような時代か見てみる。 ■ 3世紀末〜6世紀 「古墳時代」 7世紀を古墳時代に含める研究者がいる。しかし、古墳時代とは前方後円墳の時代と考えるので、前方後円墳の築造が極端に減る7世紀は古墳時代に含めず、6世紀までを古墳時代と考える。 ■ 7世紀前半 「飛鳥時代」 推古朝 蘇我氏全盛期 推古天皇・聖徳太子・蘇我馬子の時代 新しい国造りをめざして、中国との外交を開始。 従来の外交相手はもっぱら朝鮮半島であったが、この時代から遣隋使・遣唐使を中国に送り、外交相手が中国へシフトして行く。 中国との交流によって国際社会を意識したとき、日本固有の墳墓の型式であった前方後円墳の築造をやめ、中国で広く行われていた円墳などの形式で墳墓が作られるようになったと考える。 645年に、大化の改新。蘇我の本家を滅ぼすクーデターが起こる。改新の詔の中にのちの大宝律令の内容が含まれていたりすることから、「大化の改新」はなかったという議論が続いている。 このころ朝鮮半島では王と家臣との間で事件が頻発主な出来事
■ 7世紀後半 「白鳳時代」 天智・天武朝 朝鮮半島情勢の緊迫
天武天皇は、厳しい国際環境の中で生き残れる強力な国家を作るため、つぎのようなさまざまな施策を実行し、律令国家の基盤を作った。
天武天皇の時代は遣唐使が中止されていたが、唐の制度を取り入れていた新羅からの使者によって、新羅経由で唐の情報が入っていたのであろう。 |
2. 終末期の古墳 |
|
■ 終末期の古墳
 ■ 高松塚とキトラ古墳
■ 高松塚とキトラ古墳 高松塚とキトラ古墳は、次のように多くの共通点がある。
|
| 高松塚古墳 | キトラ古墳 | |
| 墳形 | φ=18m H=5m | φ=14m H=3.3m |
| 石槨 | L=265.5cm、W=104cm、H=113.4cm 9×3.5尺 平天井 |
L=240cm、W=104cm、H=124cm 8×4尺 刳り天井 |
| 壁画 | 人物像、四神図、日月図、天文図 | 四神図、獣頭人身十二支像、天文図 |
| 骨歯 | 熟年男性(40〜60歳) | 熟年から老年男性 |
| 遺物 | 棺金具、海獣葡萄鏡、銀荘唐様大刀関係、 ガラス製粟玉、ガラス製丸玉、コハク製丸玉 |
棺金具、木棺片、コハク玉、ガラス粟玉、 微小ガラス玉、金象嵌鉄刀装具、 銀製金具、金銅板片 |
| 備考 | 木芯乾漆棺、外面に金箔 |
|
■ 高松塚古墳
|
3. 壁画について |
|
高松塚壁画の人物の服装については、当初から、中国系、朝鮮系、あるいは、日本独自のものとする議論があった。女性の服装は、衿が左前になっていて裾が長い。 ■ 中国
《高句麗》 壁画古墳の集中地
《新羅の壁画古墳》 2基 6世紀から7世紀初頭 ■ 日本 《高松塚》
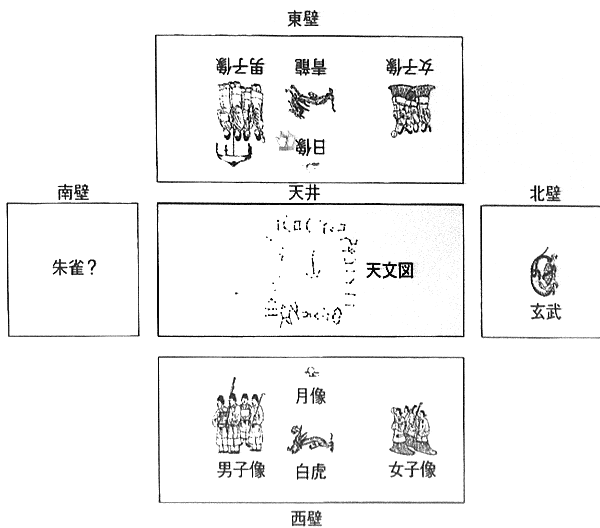 《キトラ古墳》
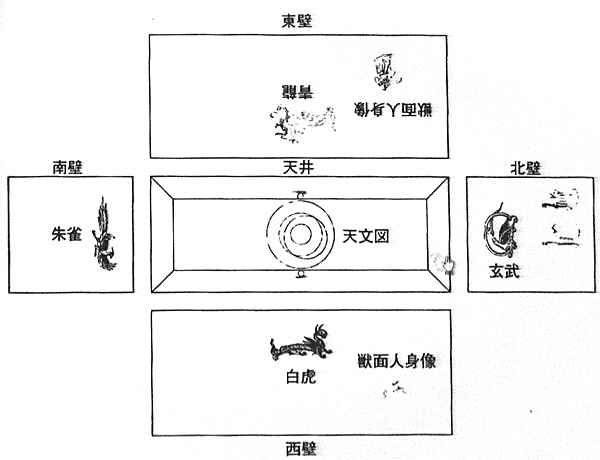 ■ 類似の図 キトラ古墳の玄武、高松塚古墳の青龍は、中国、朝鮮のものより、薬師寺金堂の薬師如来台座描かれたものに似ている。薬師寺金堂は高松塚やキトラ古墳と同じような時期に建立。 |
4. 被葬者について |
|
■ かなり高位の人物
■ 高松塚の築造年代の目安
|
高松塚古墳被葬者論争の現在 安本美典先生 |
|
■ 高松塚古墳の被葬者被葬者の有力候補は下記の3名に絞られる。
■ 壁画からの時代推定
■ 遺物からの時代推定
平城京遷都(710)以降は、身分の高い人は平城京の近くに墳墓を築き、藤原京の近くには埋葬されなかった。従って、藤原京近くの高松塚の被葬者は、平城京遷都の前になくなった人物であるというのが学会の大勢であった。そうすると遷都前に没した忍壁親王が有力になる。 しかし、石上朝臣麻呂は、藤原不比等によって藤原京留守司とされたため、平城京遷都後も平城京に入れなかったので、藤原京の近くに埋葬されてもおかしくない人物である。 ■ 官位 壁画の蓋(きぬがさ)が深緑色である。大宝令によれば、これは被葬者が一位の人物であることを意味する。当時一位の人はいなかったが、石上朝臣麻呂は、没後に従一位を追贈されているので、有力な候補である。 なお、王仲殊氏は、当時、有力者の墓は生前に造らる寿陵であったので、没後に昇進しても対応は難しいのではないかと述べる。しかし、殯(もがり)の期間を考えれば変更できる可能性があるとも考えられる。 また、深緑色は青の範疇に入る色であることから、壁画は青い蓋を描いたものであるとし、唐のころには青蓋は皇族がつかうものといわれることから被葬者は皇族の忍壁親王とする説がある。 しかし、高松塚の壁画は細部にわたり大宝令に従ったように見えるので、一位の人物であったと考える方が妥当とも思える。 ■ 年齢 発見された歯の分析では、被葬者は壮年という結果が出ているので、78才で没した石上朝臣麻呂は除外される。いっぽう、忍壁親王は年齢不詳だが、壬申の乱のとき幼少であったという記録があり、没年は40歳ごろと推定できる。そうすると、歯の分析結果は被葬者が忍壁親王であることを支持している。 しかし、歯によって年齢を正確に判定するのはかなり難しいと考えられるので、石上朝臣麻呂の可能性もある。 ■ 結論 85%程度の可能性で、石上朝臣麻呂が被葬者であると考えている。昔は90%ぐらい確信を持っていたが、青蓋の説など、忍壁親王説を支持する情報がいくつか現れたので5%ほど遠慮した。 |
| TOP>活動記録>講演会>第264回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |