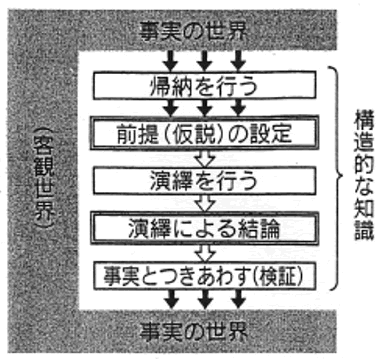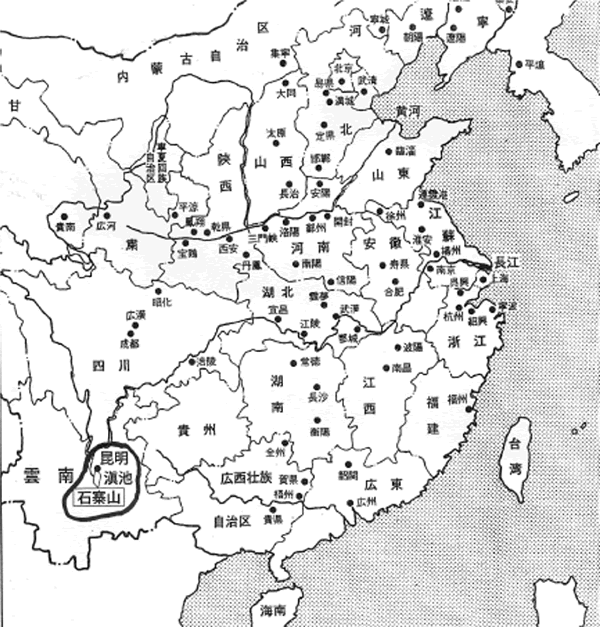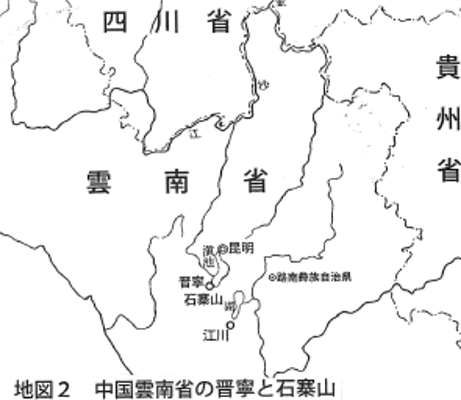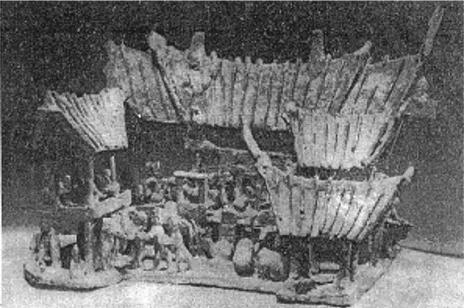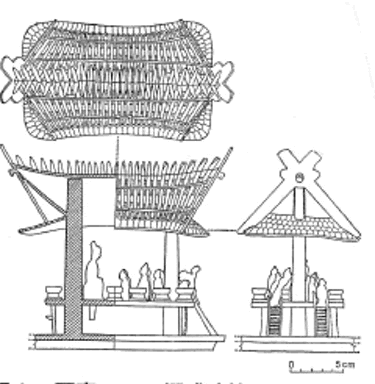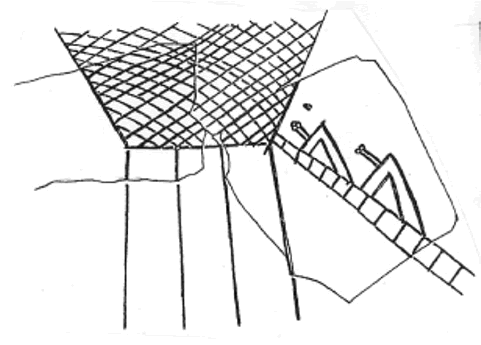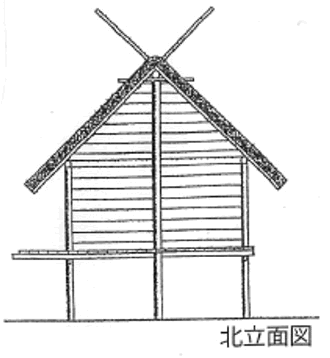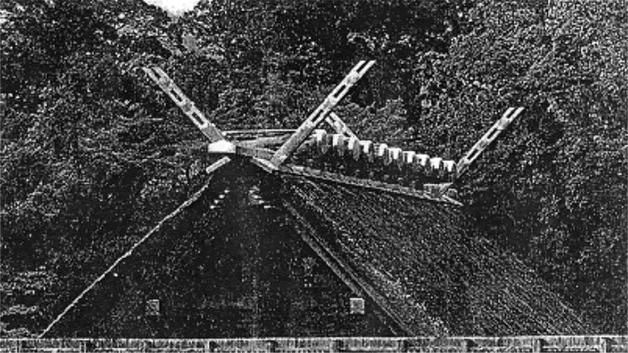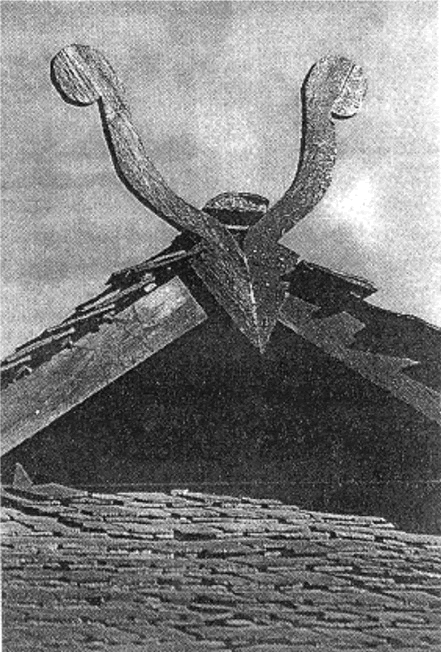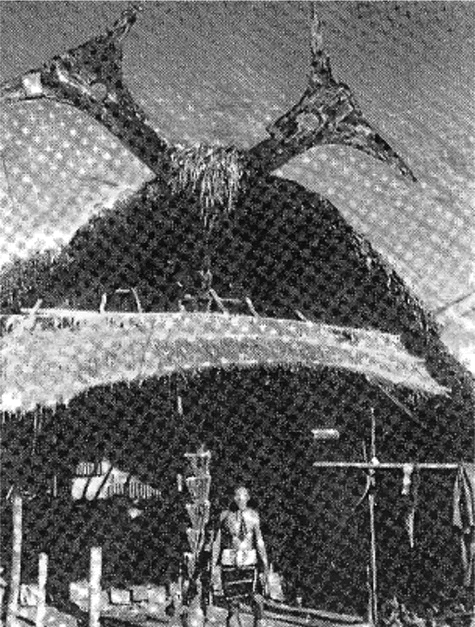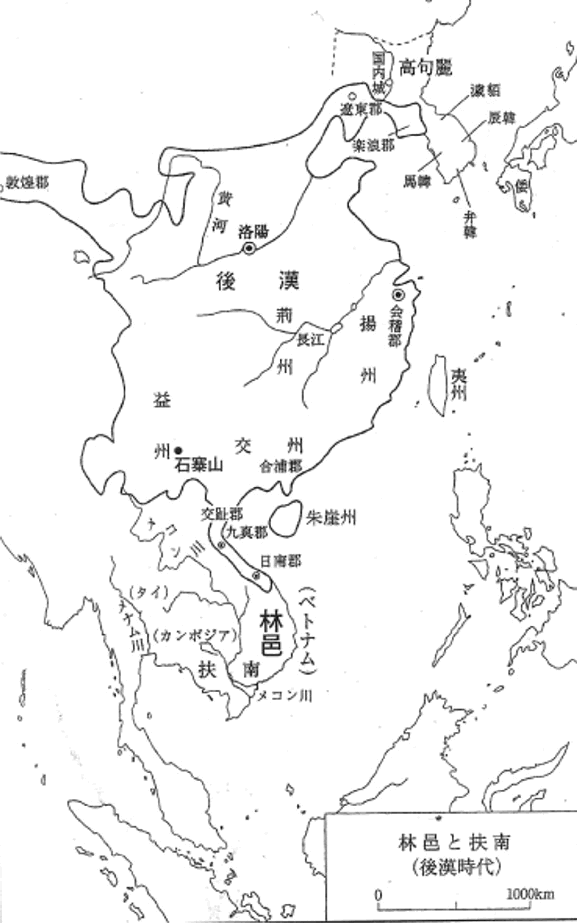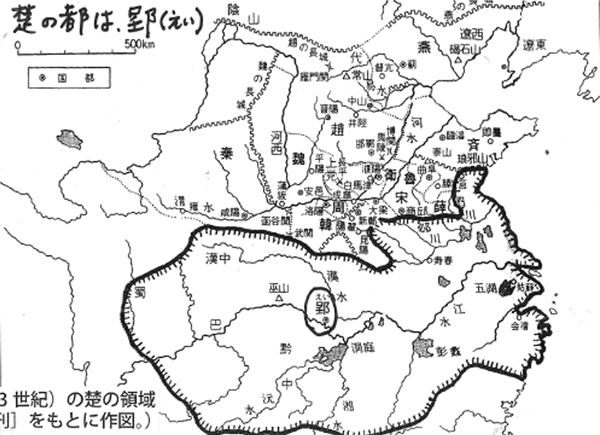昨年10月に「探究の基礎構造」を講演した時に、講演が途中で終わったので、今回はその続きを話す。
■10月の講演
・認識論
・科学とは何か
・「数字」や「数学」で表現する意味
・正確な地図
・事実による説得
・演繹型と帰納型
・前提の設定
10月の講演の続きとして、
■パスカルとヒルベルト
フランスのパスカルは、演鐸型の論理をとりあげている。パスカルは、すでに17世紀に、その著『幾何学的精神』の第二部「説得術について」という文章のなかで、論理による説得、あるいは論証の基本的な方法などについて、明快に説明している(吉田洋一・赤摂也共著『数学序説』[培風館刊]参照)。
パスカルは、まず、「定義」について、次の三つの規則をあげている。
①それよりもはっきりした用語がないくらいあきらかなものは、それを定義しようとしないこと。(すべての言葉を定義するのは不可能なため。)
②いくぶんでも不明、もしくはあいまいなところのある用語は、それを定義しないままにしておかないこと。
③用語を定義するにさいしては、完全に知られているか、または、すでに説明されていることばのみを用いること。
次に、パスカルは、「公理」について、二つの規則をあげている。公理というのは、議論の出発点、または前提ともいわれるものである。
①必要な原理は、それがいかに明晰(めいせき)で、明証的--つまり一見してだれでもが納得できるような形であっても、けっして、承認されるか否かを吟味(ぎんみ)しないままに残さないこと。
②それ白身で完全に明証的なことがらのみを、公理として要請すること。
さらにパスカルは、「論理」について、三つの規則をあげている。
①それを証明するために、より明晰なものを探してもムダであるほど、それだけで明証的であることがらは、これを論証しようとしないこと。
②少しでも不明なところのある命題は、これをことごとく証明すること。そして、その証明にあたっては、きわめて明証的な公理、またはすでに承認されたか、あるいは証明された命題のみを用いること。
③定義によって限定された用語のあいまいさによって誤らないために、つねに心のなかに、定義された名辞の代わりに、定義をおきかえてみること。
以上のパスカルの方法をまとめてみると、「自明のものをのぞく、すべてのことばを定義し、また自明でないすべての命題を証明しつくす」ということになる。
このパスカルの論証の方法というのは、ギリシア人が幾何学を築くのに用いた方法にほかならない。すなわち、ある「公理(前提)」といったものを設定しておいて、そこからひじょうに多くの「定理」といったものを導きだす、という方法である。きちんと決めた前提から、さまざまなものを、正しい論理に従って導きだす、ということである。だからこそパスカルは、自分の書物を『幾何学的精神』と名づけた。
ところで、以上のような方法論は、19世紀以来の自然科学のめざましい発展とともにさらに洗練されてきている。「幾何学的精神」の代表的な形としては、「公理主義」といわれるものがある。ある理論において、ほかの命題の前提となる基本的な命題の体系--これを公理系という--をあきらかにし、その公理系と、特定の推論規則から演鐸的に理論をくみたてることを、公理論的方法または公理論と呼ぶ。ユークリッド幾何学は、不完全なものであっても、その適切な例であるといえる。また、すでに述べたパスカルの方法は、公理主義の原初的な形といえる。
現在の公理主義が、パスカルの説いた方法と根本的に異なる点は、主として公理というものについての考え方にある。パスカルにおいては、公理というのはそれ自身、完全に明証的なことがらで、すべての人に承認される明晰なことがらでなければならない、と考えられた。
ところが19世紀のはじめに、万人に承認されたとはいえない公理をもとに、完全に矛盾のない非ユークリッド幾何学(リーマン幾何学など)が建設された。このために、パスカルが述べたような意味での公理に対する考え方が、大きくゆらいだ。そして、ドイツの大数学者、ダヒト・ヒルベルト(1862~1943)によって、公理の考え方についての大転換が行われた。
一言でいえば、ヒルベルトは、公理は、なんら自明の真理である必要はなく、たんに、明確に定められた仮定で十分である、としたのである。すなわち、いくつかの仮定をおき、そこから形式的に結論を導いて、そこに矛盾を生じなければよい、としたのである。ヒルベルトは数学の基礎として、自分の考えを述べた。しかし、その考え方は、やがて自然科学全体に、そして社会科学の分野にも、きわめて広範な影響をおよぼすことになった。
オーストリアに生まれ、のちアメリカに渡った、物理学者で科学哲学者、ルドルフ・カルナップ(1891~1970)らは、この方法(公理的方法)だけが科学的方法であり、すべての科学は公理論的に構成されるべきであるとして、公理主義をとなえた。さらにカルナップらは、それまで主として、数学を基礎づける道具として発達してきた記号論理学を、広く諸科学を分析し、基礎づける道具として用いることを主張した。西欧の現代哲学である分析哲学では、公理主義が深く根を下ろしている。
一つの例をあげよう。
太陽と地球との関係について、地動説と天動説と呼ばれるものがある。きわめて多くの人が自然に認めることがらに立脚すれば、天動説のほうに分かある。すなわち、太陽は東から昇って、西に沈む、というのは、私たちが直接目にする事実である。明証的な事実であるといえそうである・しかし、天動説のほうが正しいとはいえない。
地動説は、太陽は動かず、地球がそのまわりをまわっているのだと主張する。地動説のほうが正しい、ということになったのは、この立場に立ったとき、ひじょうに多くのことが、矛盾なく、うまく説明できるからである。すなわち、地動説の仮定に従ったほうが。多くの観測事実を、矛盾なく説明できるのである。
いま一度まとめてみよう。
議論を行うばあい、パスカル的な方法は、だれもが認めることを前提として、議論を進めていき、だからこの結論は正しいのだということを、認めさせるやり方である。
これに対して、ヒルベルト的方法では、前提はだれもが認めるようなものでなくてもかまわない、ということになる。そして一応の「仮説」として、あることがらを前提にし、それによって多くのことがらが矛盾なく説明できれば、もとの仮説を正しいものとして受けいれよう、ということになる。
私たちの日常生活においては、あるいは社会科学、人文科学などの分野においては、だれもが認める事実というものは案外少ない。けっきょく、「まあここらあたりが、だいたい正しいところかな」ということがらを前提にして、議論を展開しなければならないことが、しばしばある。
パスカル的なやり方は、論証としてはスマートだが、柔軟さにおいては、ヒルベルト的方法のほうが、すぐれていることが多い。
■論理による説得の手つづき
論理による説得、論証による説得というのは、一般に若い人が得意とする説得の方法である。まず自明のように思われることを、相手に認めさせる、そして、相手がひとたびそれを認めればシメたものである。こうだからこうだ、だからこうだ、と論理を展開して結論を出し、それを相手に認めさせる。相手は前提を認めた以上、結論も認めざるをえない。
ところが、このような論理展開を行ったばあい、なるほど、理屈はそのとおりだ、しかし、結論がどこかおかしい、という疑問を抱かせることがしばしばある。西洋の中世のスコラ哲学(おもにキリスト教の教義を、アリストテレスの哲学などによって体系づけ、説明しょうとするもの)にしても天動説にしても、論理的にはきわめてととのったものだった。しかし、それは、対象を説明しうる唯一の説明体系ではなかった。対象をもっと適切に説明しうる体系が、ほかにあった。論理的にととのっているということだけでは、その説明体系がもっとも妥当なものであるという保証には、かならずしもならない。
論理による説得は、論理的にととのっていれば正しいという態度を、しばしば生みがちである。論理的に導きだした結果が、現実とよく合致しているかどうかを、もう一度よくチェックしてみる必要がある。そのチェックが落ちていると、論理的にはととのっているが、現実や事実と合わないというようなことが、しばしば起きる。「理路整然と間違っている」というようなことになるのである。
そのような問題はあるにしても、論理による方法は、ほかの方法にくらべて、きわめて体系的で、構造的な知識をもたらすことも事実である。
論理による説得を行うには、一般的に、どのようなことに気をつければよいのだろうか、
論理による説得は、次のような手つづきによって行われると考えられる。
①具体的な多くの事実やデータから、比較的わずかな、いくつかの前提(仮説、仮定)を導きだす(いわゆる「帰納」を行う)。
②そのいくつかの前提を出発点として、形式的にととのった、落ちのない議論を展開し、結論を導きだす(「演鐸」を行なう)。
③その結論を、具体的な事実やデータと、いま一度照らしあわせて、矛盾することがないかどうかを調べる(事実とつきあわす)。
④矛盾したぱあいは、いま一度前提を検討し、前提を修正するか、あるいは、ほかのもっと適切な前提を選ぶ。新たな前提によって、②以下の手つづきをくりかえす。
⑤このようにして、矛盾なく対象を説明する体系がえられたならば、他を説得しうるものとして、提示することができる。
この流れを図に示せば、図のようになる。
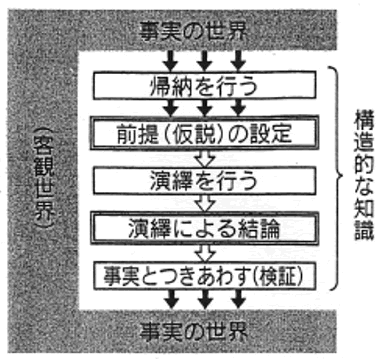
論理による説得を行うばあいには、適切な前提を選ぶこと、結論を具体的世界の事実やデータと、いま一度照らしあわせて、矛盾がないかどうかをよく検討すること、などが大切である。
政治的なある立場や、ある種のイデオロギーにもとづく議論などにおいて、途中の議論そのものはきわめて論理的なのだが、適切な前提が選ばれているかどうか、えられた結論が、現実の社会によく合致しているかどうかという検証が脱けおちていることがよくある。
■パラダイムの変換
すでに述べたように、現代の科学方法論では、議論の出発点となる仮説の任意性が主張
されている。
そのため、仮説の設定の仕方によって、ものの見え方、考え方が大きく変わってしまうことがある。
これを、「パラダイム・シフト」という。
例:図を見ると、若い女性に見えるし、お婆さんに見える。見方によって変わるのである。

「中世のヨーロッパでは、太陽が地球のまわりをまわっているという天動説が、当時の宇宙論を支配していた。ところが、16世紀にはいると、コペルニクスが、地球が太陽のまわりをまわっているという地動説を提唱する。このコペルニクスの地動説は、当時容易には受けいれられなかったが、一世紀にわたって議論が行われ、現在では、常識的な知識の一つとなっている。
そして、この転回に端を発して、科学的な概念の枠組みが大きく変わった。みえている世界や宇宙には、なんの変化もなかったが、われわれが宇宙をみるときの姿勢や考え方にとって、この転回はきわめて劇的なものであった。
このような新しい概念、パースペクティブの転換や創造を、科学者は、”バラダイム(新しい世界観)の創造”と呼んでいる。
この”パラダイム”いう言葉は、アメリカの科学史家であり、哲学者でもあるトーマ
ス・クーン(Thomas.S.Kuhn 1922~1996)が、1962年、その著書『科学革命の構造』(みすず書房刊)で、はじめて提唱したものだ。パラダイムは、ギリシア語で、パターンを意味する”バラディグマ”に由来しており、クーンは、これを特定の科学の基礎となっている支配的な論理的枠組み、あるいは、一連の仮説という意味で用いた。」
■学説の優劣を判断するための基準
①議論を行うための前提(公理、仮説)は、よく整理されているか。
例:私(安本)の仮説系
【前提1】
『古事記』『日本書紀』に記されている天照大御神以下の五代、および、歴代の天皇の存在。および、その順序は、一応信じられるものとする。すなわち、「代の数」は、信じられるものとする。
【前提2】
「父子継承」記事は、信頼できないものとする。そして、用明天皇以前においても、継承関係がほぼ確かな、用明天皇から桓武天皇におけると、あまり変わらない形で、継承がおこなわれたものとする。したがって、古い時代の諸天皇などのだいたいの活躍の時期は、活躍の時期がはっきりしている諸天皇の、一代平均の在位年数をもとに、推定しうるものとする。
②その理論はシンプルか。
例1:福永伸也(大阪大学)の『三角縁神獣鏡の研究』
福永氏は本のなかでも『三角縁神獣鏡の研究』複雑でむずかしと書いているが、その本は非常に複雑であり、分かりにくい。やはり理論はシンプルでなくてはいけない。
例2:村上斉(ひとし)『宇宙はなぜこんなにうまくできているのか』(集英社2012年)
「科学の理論はシンプルなほうがよい、という話をしました。その意味では、この統一も非常に重要です。さまざまな現象をいちいち別の理論で説明するのは、話が複雑になりますし、美しくもありません。ひとつの法則で多くのことを説明できたほうが、より深い原理に近づいたことになるでしょう。
そのため、大昔から現在にいたるまで、物理学者たちはさまざまな理論を統一する努力を続けてきました。物理学の歴史は統一理論の歴史だといっても過言ではありません。この世に起こるすべての現象をひとつのシンプルな理論で説明したい--それが、私を含めた全世界の物理学者の夢なのです。ニュートンの万有引力の法則は、そんな統一理論の先駆けとなるものでした。」と書いている。
③その理論は統一理論化か。
議論で統一性がある方が優れている。邪馬台国論争を例にすれば、
例:私(安本)の理論
上記仮説前提から、第31代の用明天皇から第50代の桓武天皇までの天皇の1代の平均在位年数が10.88年となる。用明天皇からさかのぼり、神武天皇まで計算すると神武天皇は卑弥呼の年代に届かない。更に5代さかのぼり、天照大神とすると、卑弥呼の時代と合う。『古事記』『日本書紀』のなから、天照大神は九州に居たと考えられる。などと理論が展開でき、『魏志倭人伝』など中国、朝鮮文献、『古事記』『日本書紀』など日本文献、更に考古学的事実も調べその中で、矛盾がない理論となる。
例:畿内説の多くは
鏡だけを調べる、または土器だけを調べる。これではあぶない。