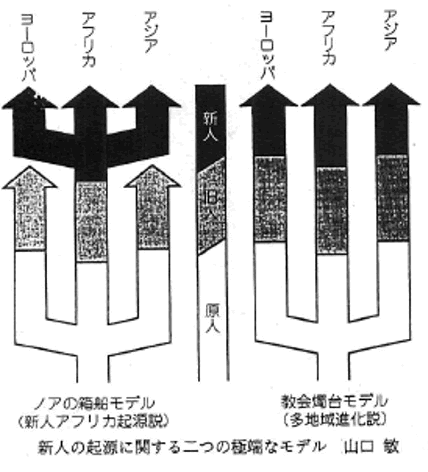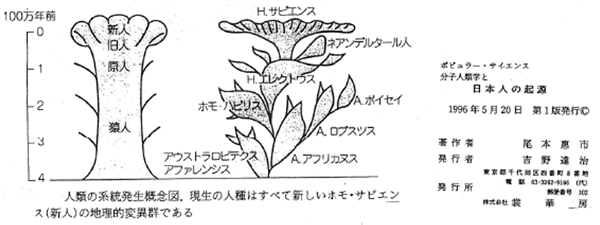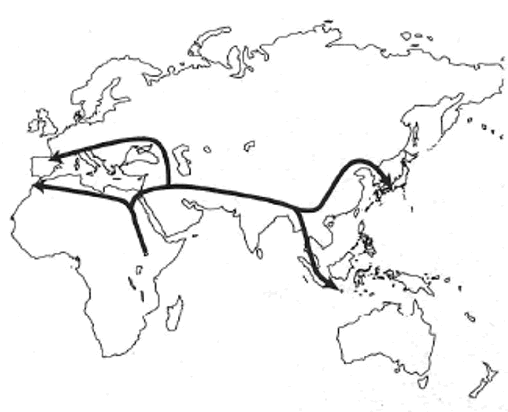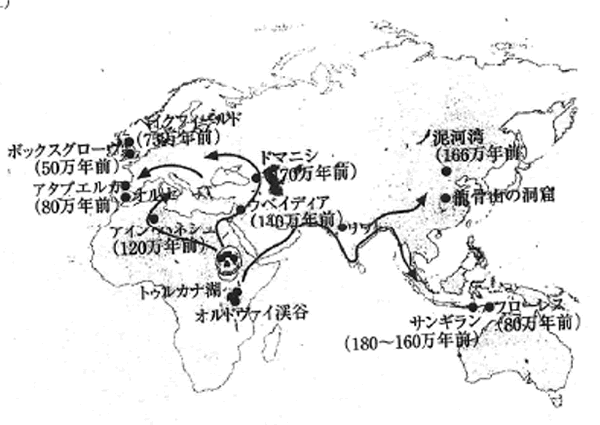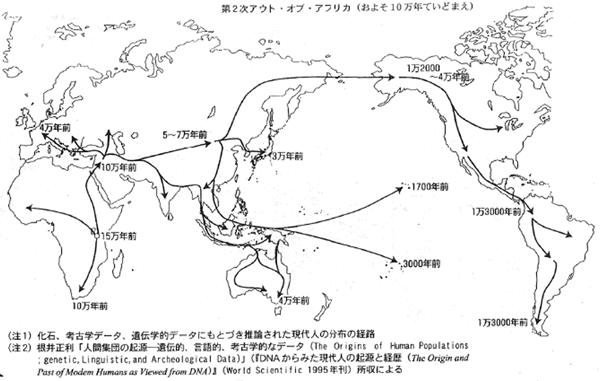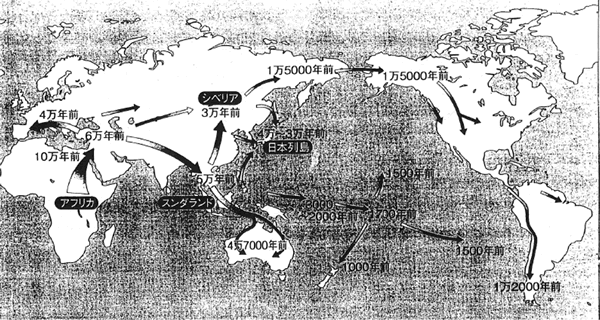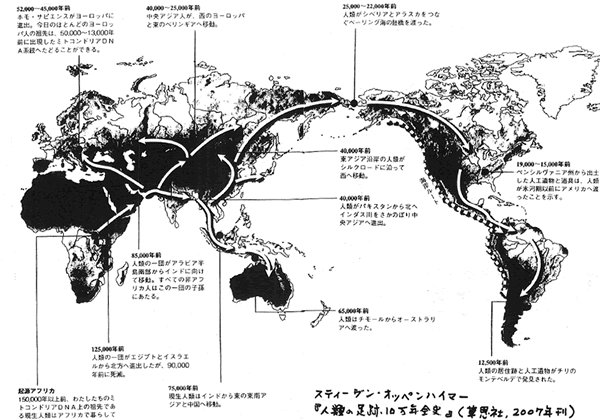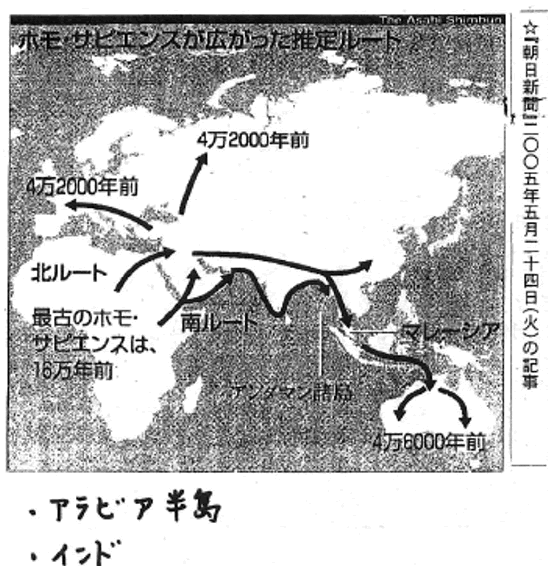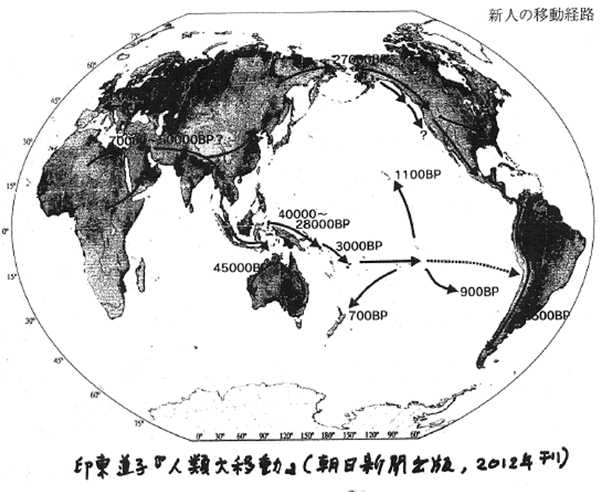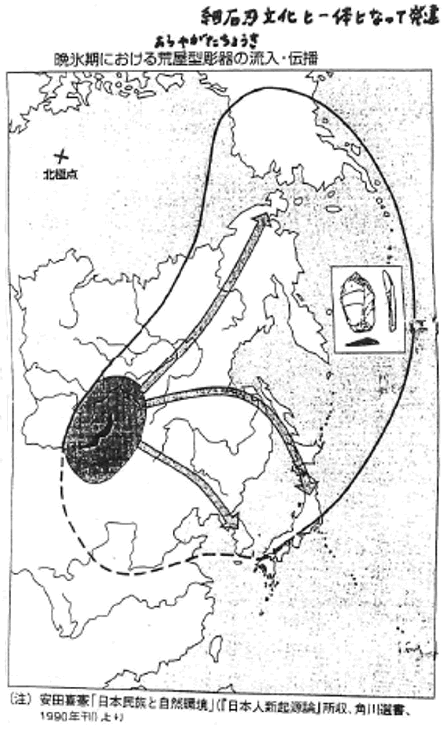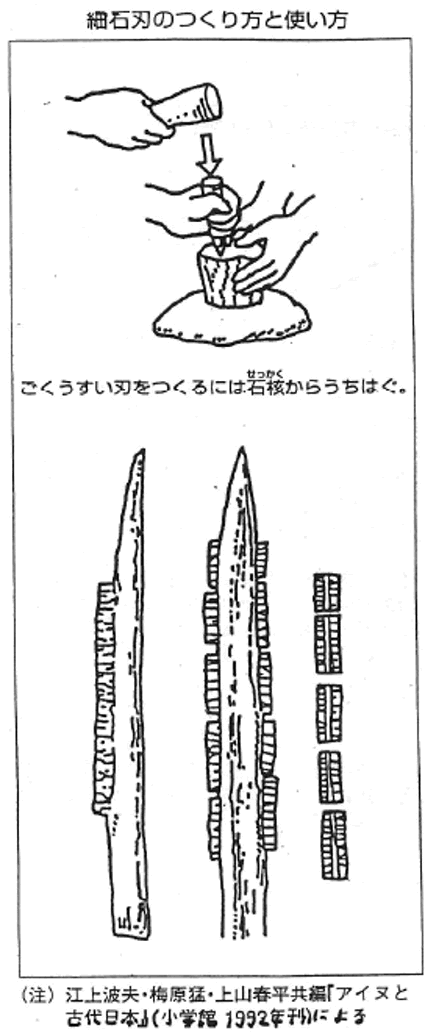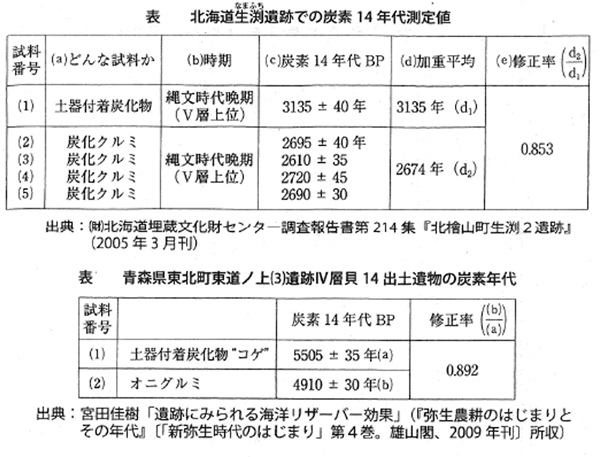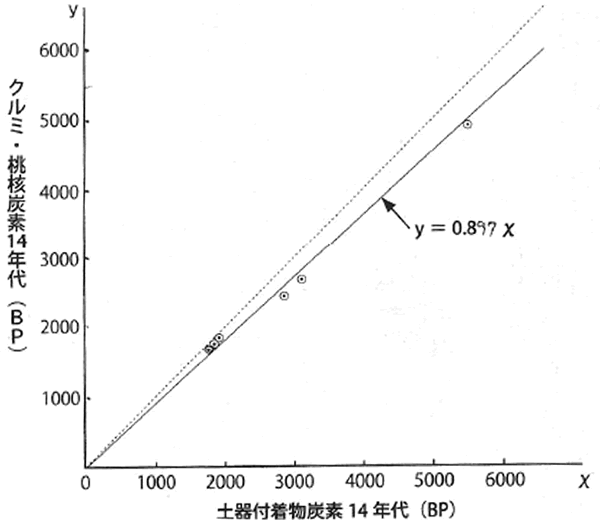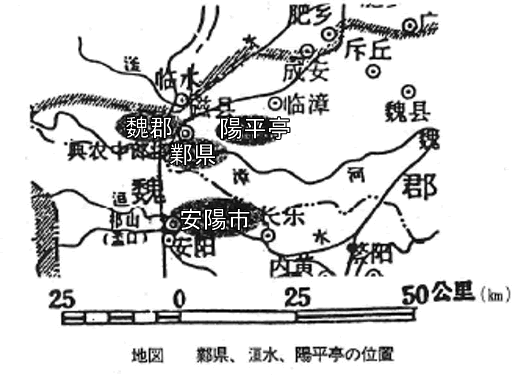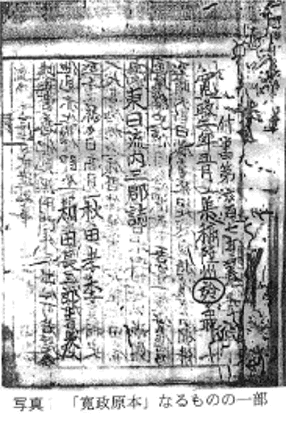| TOP>活動記録>講演会>第308回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第308回 邪馬台国の会(2012.4.22 開催)
| ||||
1.原人たちの移動
|
■原人、旧人、新人 その他の資料 ・スティーブン・オッペンハイマー著『人類の足跡・10万年全史』(草思社、2007年刊)
・『朝日新聞』2005年5月24日(火)の記事
・印藤道子著『人類大移動』による新人の移動の説明。
これらでの違いのポイントは ■細石器文化
もし、縄文時代の年代を繰り上げた場合、その前の細石器文化の年代はどうなるのか、そのことには触れていない。 しかし、ここでも、土器付着炭化物が、年代決定の主要な試料とされている。土器付着炭化物は軒並み、古い年代となることが分かっている。 土器付着炭化物とクルミ・桃核が同じ年代だとするなら、45度の直線(y=1)となるはずだが、測定値から、y=0.897となる。
このことから補正すると。 もっとも若いもての----13000年 となる。 おおまかに言って古くても14000年前とすれば、細石器文化とつじつまがあうのではないか、16500年前は古すぎる。
|
2.古田武彦説の検討
|
前回は本居宣長について述べたが、本居宣長は卑弥呼は九州の女酋であるとした。古田武彦氏は本居宣長の流れをくんでいるので、その考えを更に進め、九州に王朝があったとしている。また、東北にも王朝があったとしている。 古田武彦説の主張を検討してみる。 しかし現存版本は12世紀に成立したもので、それ以前のテキストでは「臺(台)」であった。例えば、『翰苑』がよい例である。『翰苑』は唐の張楚金の撰で、、雍公叡の注である。大宰府天満宮にあり、平安初期9世紀に書写され、そのまま今日に伝来した。 このことは、原文を対照してみればすぐわかる。 さきの引用文は、はじめ『後漢書』の文を引き、後半においては、「魏志倭人伝」の文を引いている。そして、『翰苑』の文をよく見られよ。そこでは、現存版本の 「魏志倭人伝」には、「壹與(壱与)」とある卑弥呼の宗女の名が「臺與(台与)」と記されている! それ以外にも『魏志倭人伝』の「対馬国」「一支国」についても、現存の版本の『三国志』「魏志倭人伝」にあるように「対海国」、「一大国」が正しいとするが、『翰苑』では、「對馬国(対馬国)」、「一支国」となっている。 (b)魏晋朝短里説
これらの値は、直線距離によって求めたものであるが、1里を434メートルとする標準里で、十分説明できる。直線距離のように、小さめの値ででるような測りかたでも、1里は、100メートルていどには、とうていならない。道路の屈曲その他を考えれば、1里を、実測値よりも長めにすることは可能であるが、直線距離で求めたものよりも、短かめにすることはできない。
(c)『東日流外三郡誌(つがるそとさんぐんし)』 しかし、これらの古文書は全くの偽物と考えられる。 これは、「自説は正しいのであるから、少々の不正は許される」とする感覚で、現代は諸種の情報が野ばなしの状況なので、情報の質を検討する力が必要である。 「東日流外三郡誌」論争について、安本先生と古田武彦氏+和田喜八郎氏の対談の形式で、1993年にNHKのナイトジャーナルでテレビ放映された。第308講演会では、その録画を観賞した。 「東日流外三郡誌」について調査し、本を書いた斎藤氏の記述。 ・和田喜八郎氏のいとこ:和田キヨエさんの証言
|
3.『魏志倭人伝』を徹底的に読む
|
①道順が、「(帯方)郡から倭に至るには」となっている。対馬国→一支国と、むこうから、こちらに来たかたちになっている。「倭から、(帯方)郡に至るには」となっていない。魏から倭にきた使が書いたから、こうなったのであろう。 |
| TOP>活動記録>講演会>第308回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |