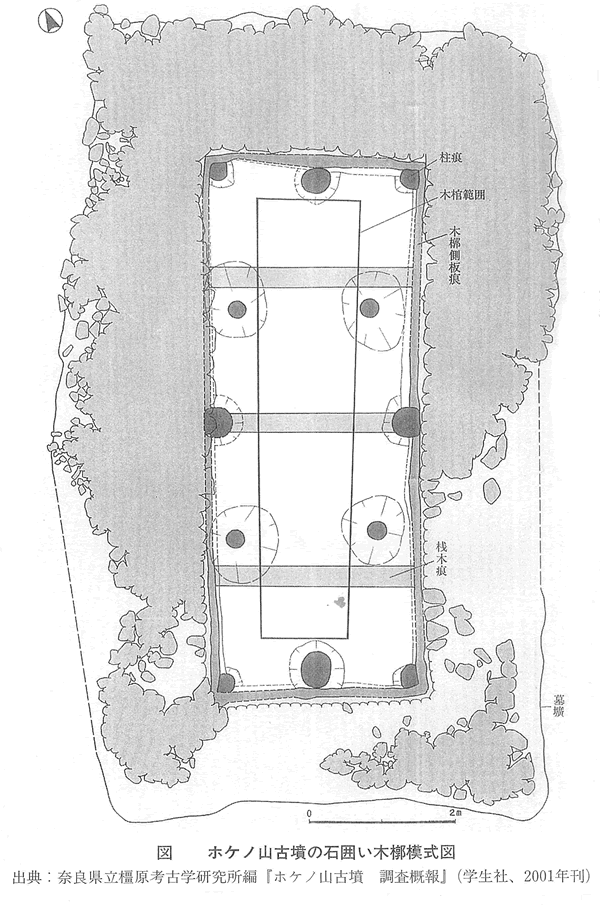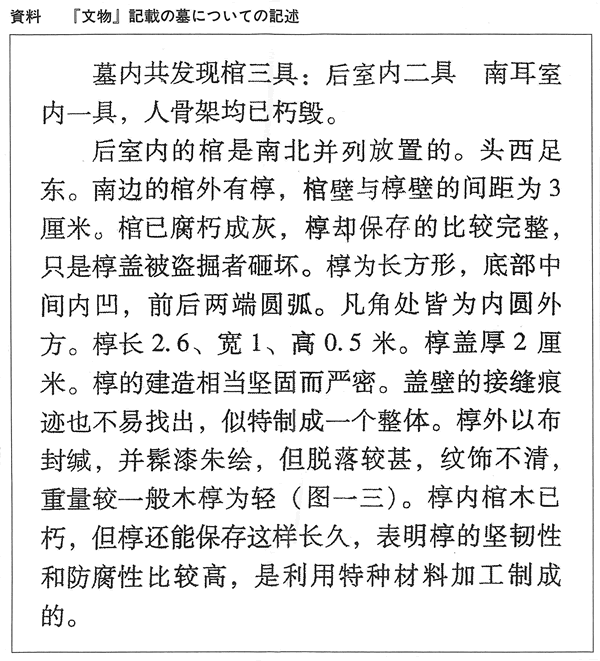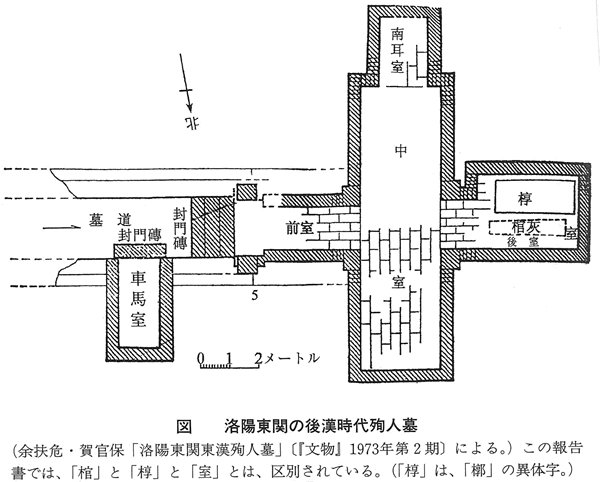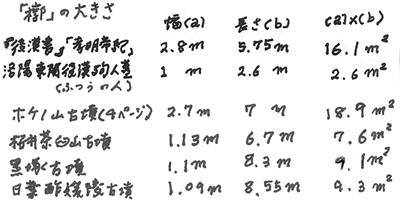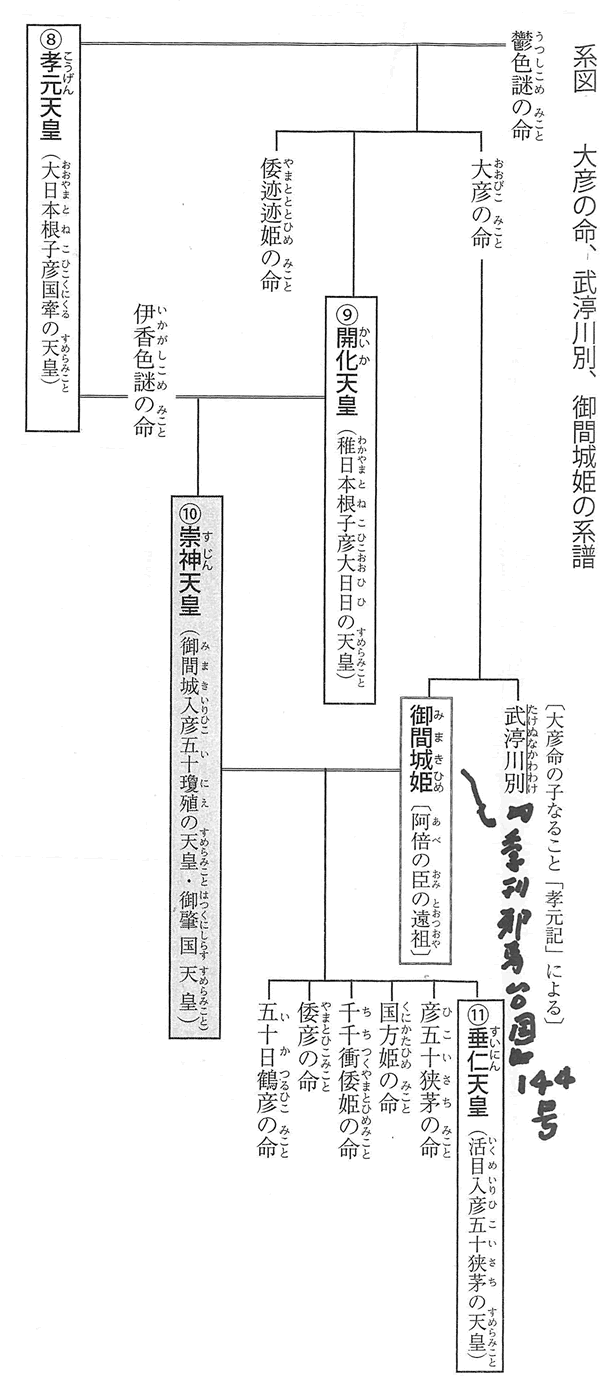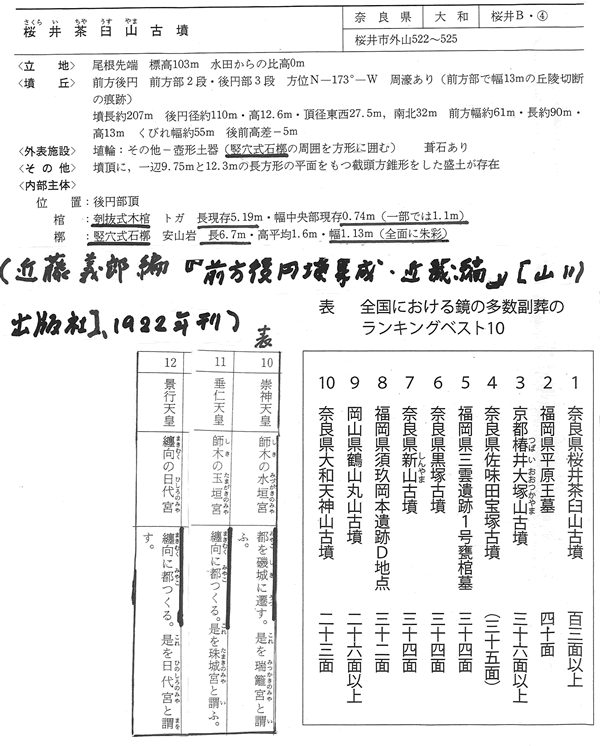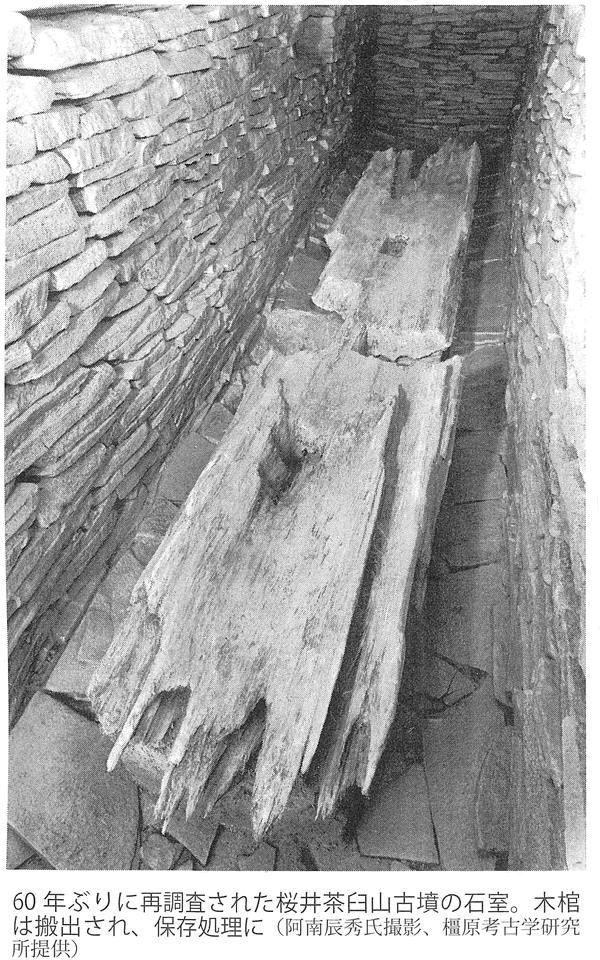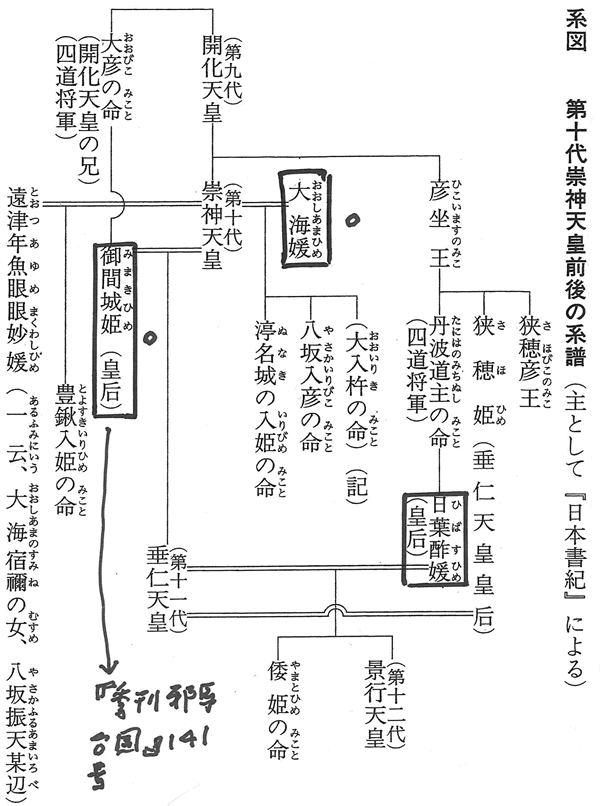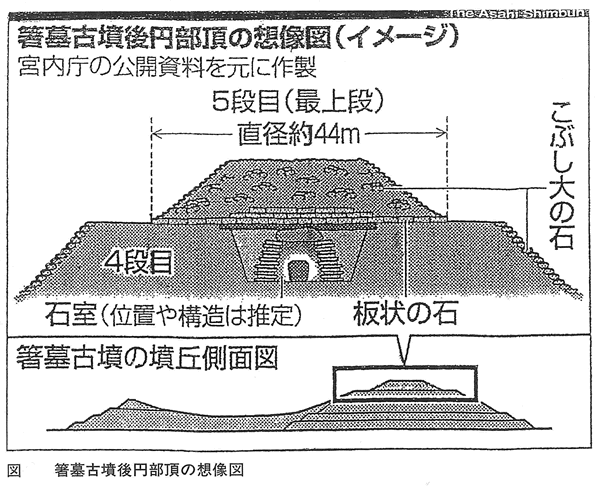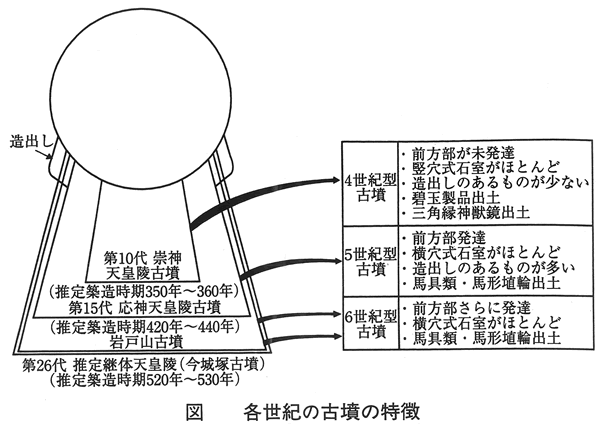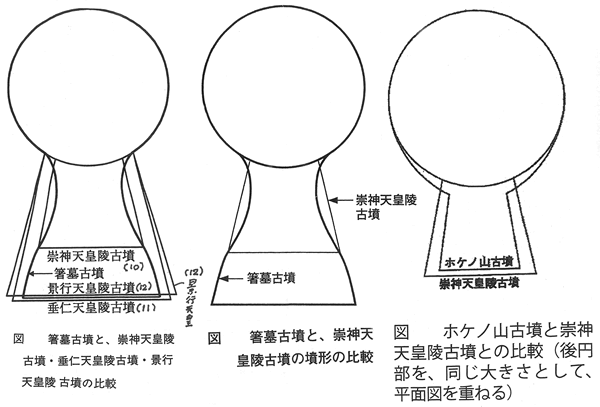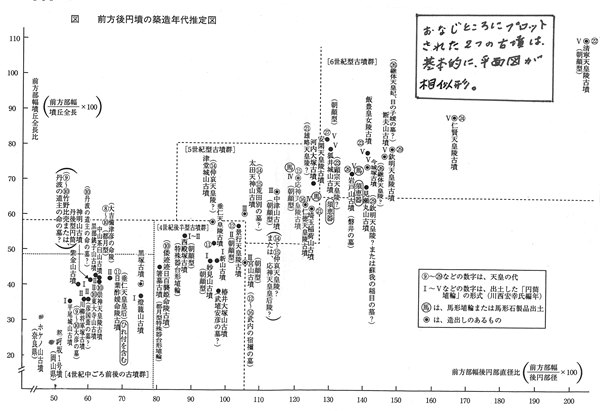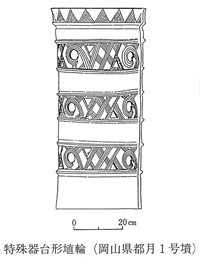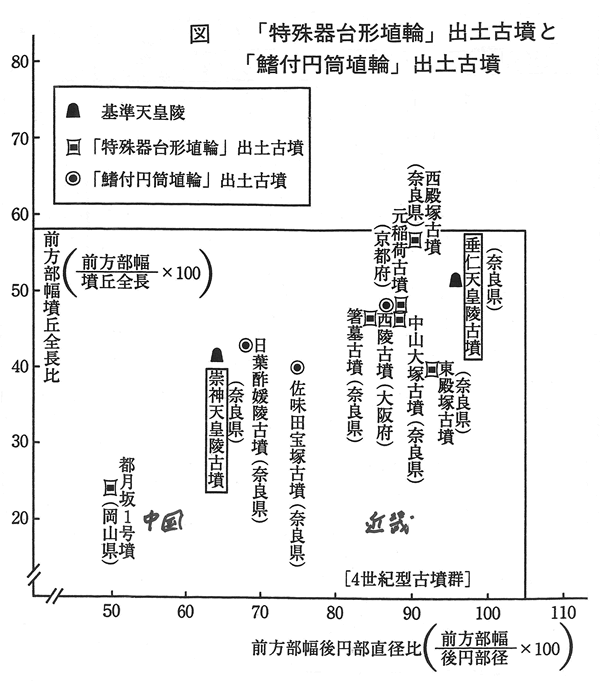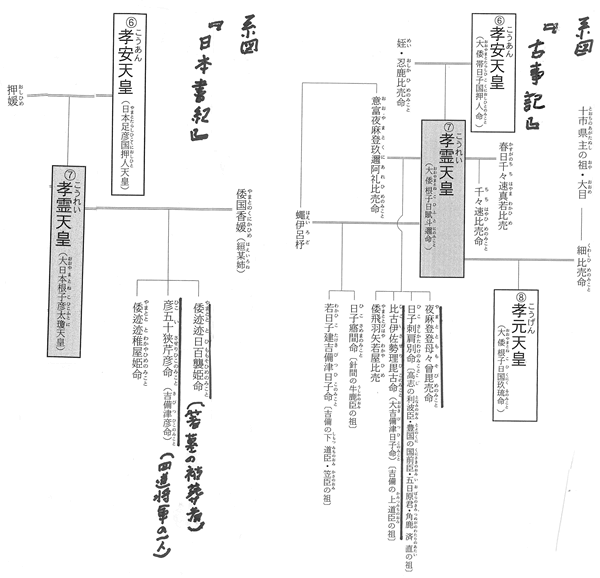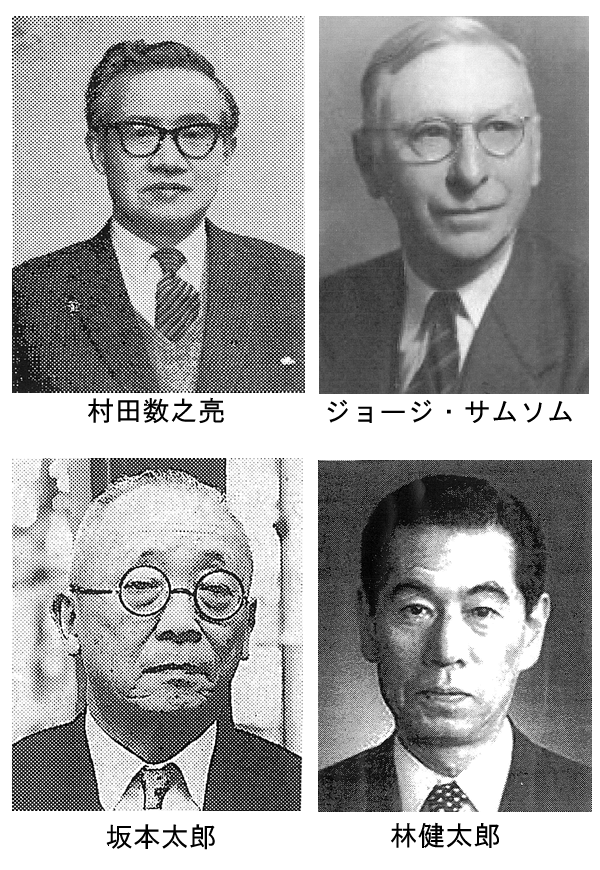| TOP>活動記録>講演会>第424回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
Rev3 2025.7.2 |
第424回 邪馬台国の会(2024.10.27 開催)
| ||||
1.「邪馬台国北部九州説」七番目の証明 |
「棺あって槨なし」による証明の詳論 「棺あって、槨なし」問題については、前回の9月の第423回の「邪馬台国の会」で取り上げた。この問題は「邪馬台国北九州説」の第7の証明としてもよいように思えてきたので、今回すこしくわしくのべる。 ■「棺あって槨なし」が示す年代 庄内3式期といわれるホケノ山古墳の「木槨」をとりあげる。
この図と写真のホケノ山古墳の「木槨」は、『魏志倭人伝』の記述にあわない。 奈良県立橿原考古学研究所編『ホケノ山古墳 調査概報』(学生社、2001年刊)によれば、ホケノ山古墳においては、「木槨(もっかく)木棺墓がみつかった」「木の枠で囲った部屋があり、その中心に木棺があった」「栗石積みの石囲いに覆われた木槨と木棺があった」という。 『三国志』の筆者は、葬制には関心をもっていた。つぎのように各国ごとに、いちいち書き分けている。(「倭人伝」以外は、棺のある記述になっていない。) 『韓伝』……「棺(内棺)ありて槨(外箱)なし。」 『夫余伝』……「厚葬(贅沢な埋葬)にして、槨ありて棺なし。」 『高句麗伝』……「厚く葬り、金銀財幣、送死に尽くす(葬式に使い果たす)。石を積みて封(塚)となし、松柏を列(なら)べ種(う)う。」(この記述は高句麗の積石塚とあう。) 『東沃沮(とうよくそ)伝』……「大木の槨を作る。長さ十余丈。一頭(片方の端)を開きて戸を作る。新(あら)たに死するものは、皆これに埋め、わずかに形を覆(おお)わしむ(土で死体を隠す)。」「皮肉尽きれば、すなわち骨を取りて、槨中に置く。」 『倭人伝』……「棺あって槨なし。土を封じて冢(つか)を作る。喪(なきがら)を停(とど)むること十余日(もがりを行なう)。」 このように、倭人の葬制は「韓」とは同じであるが、
「夫余」「高句麗」「東沃沮」と異なっていることを記している。 日本で「もがり(死者を埋葬する前に、しばらく遺体を棺に納めて弔うこと)」が行なわれたことは、『古事記』『日本書紀』に記述がみえるし、沖永良部島では明治のころまで行なわれていた(斎藤忠『古典と考古学』学生社、1988年刊) いっぽう、九州の福岡県前原市の平原(ひらばる)遺跡からは、40面の鏡が出土している。平原遺跡では、土擴(墓穴)のなかに割竹形木棺(丸太を縦二つに割り、それぞれの内部をくりぬいて、一方を蓋(ふた)、一方を身とした木棺。断面は円形)が出土した。 北部九州で大量に発見される「甕棺(かめかん)墓」や「箱式石棺墓」なども一貫して、「棺あって槨なし」の記述に合致するといえよう。
■中国の「槨」は棺の外箱である 石野氏にやや近い見解を、桜井市教育委員会の橋本輝彦氏や、考古学者の萩原儀征(はぎはらよしゆき)氏も述べている。石野博信編『大和・纏向遺跡』(学生社、2005年刊)に、つぎのような座談会記録が載っている。出席者は石野氏のほか、寺沢薫、橋本輝彦、萩原儀征の三氏である。やや長い引用になるが、紹介してみたい。 2008年6月22日の「邪馬台国の会」では、時間切れで「槨」の問題について、それ以上、石野博信氏と討論できなかった。いつか石野氏とさらに議論を重ねる日がくればと願っている。
■『中国古典』の「槨」の記述 藤堂明保編の『学研漢和大字典』(学習研究社、1980年刊)にも、「椁(=槨)」は「うわひつぎ。棺を入れる外箱。外棺」とある。 諸橋轍次編の『大漢和辞典』(大修館書店、1960年刊)でも、「ひつぎ。うわひつぎ。棺を納める外ばこ」とある。 (注:確実な魏の時代の墓で、発掘されて知られているものは、一例のみ) 中国の周の末から秦・漢時代の儒者の古代の礼についての説を集めた『礼記(らいき)』の「檀弓(だんぐう)編」の「上」にはつぎのようにある。 さらに『晋書』の第三十三の、「王祥伝(おうしょうでん)」(二十四孝の一人。継母につかえて孝であったことでしられる)などでも、王祥は、子孫に遺訓をのこし、「槨は棺を容(い)るるを取れ(槨取容棺)」と述べている。「槨」は「棺」が、はいるていどのものを用いよ、と述べているのである。 ■現代中国考古学者の「槨」の記述
これを、私なりに、日本語に訳したものを、下の資料に示しておく。 ---------------------------------------- 墓の中から棺三つが、ともに見いだされた。後室の中から二つ、南耳室(耳のようにつきでた室)から一つの計三つである。人骨とそれをおいた台は、すべて、すでに朽ちそこなわれていた。
-------------------------------------
ここでは上の図のような墓の図が掲載されている。「室」と「槨」と「棺」とは区別され、「槨」については、つぎのように記されている。 「槨の長さは、2.6メートル、幅1メートル、高さは0.5メートルであった。 後漢の孝明帝などの中国「槨」と日本のホケノ山古墳の「槨」の大きさを比較すると下の表のようになる。
ここで、桜井茶臼山古墳は、鏡の副葬枚数が全国で1番である。御間城姫の墓ではないかと思われ、崇神・垂仁天皇の時代的にと考えられる。
桜井茶臼山古墳は石槨の長さが6.7メートルである。
奈良大学教授であった考古学者の水野正好(みずのまさよし)氏(邪馬台国畿内説)は、黒塚古墳の被葬者を崇神天皇の妃(みめ)大海媛(おおしあまひめ)などであろうとする。(『卑弥呼の鏡』毎日新聞社、1998年刊)。黒塚古墳のすぐ西、JR柳本駅に接して、「大海(おおかい)」の地名があるからである。
大塚初重・小林三郎 他編『日本古墳大辞典』(東京堂出版、1989年刊) 「槨」問題から言えることは、 2013年になくなった考古学者の森浩一氏は、つぎのようにのべている。
■箸墓古墳は、「竪穴式石槨」をもっている?
この図のどこが、興味をひくか。 もちろん、箸墓古墳は、現在、発掘されていない。上の図は、あくまで、「想像図」にとどまるものであろう。 しかし、この記事のなかにも、「竪穴式石室が盗掘された時に転落した石材だろう」などの文がある。 ・ホケノ山古墳は4世紀中の時代である。
下の図から、箸墓古墳は崇神天皇陵古墳より前方部が発達していて、新しいことが分かる。
これを全体に示すと下の図のようになる。
ローマ数字は円筒埴輪の時代変化を示したもので、
日本の古墳の「槨」は後漢時代の中国の皇帝の「槨」の大きさとさほど変わらない。
これをプロットすると下図のようになる。
これは、崇神天皇、垂仁天皇の時代である。記紀の系図で示すと下記となる。
徳島大学の教授であった考古学者の東潮(あずまうしお)氏は、その著『邪馬台国の考古学』(角川学芸出版、2012年刊)の中で、「(倭の)棺はあるが槨はない」についてふれ、つぎのようにのべる。 「東夷伝の棺槨の構造、陳寿の認識はさまざまで、墓葬観念にもちがいがある。したがって棺槨の有無などの表現は絶対的なものではない。」 |
2.邪馬台国問題は、なぜ解けないか |
病根の所在 「邪馬台国論争」は、いま、いかなる状況にあるのか。それを考えてみよう。 「情報」というものの一般的性質について、考えてみる。ひとつの例として、下のような簡単な連立方程式を考える。 この連立方程式を解けば、もちろん、x=1で、y=2である。 このばあいは、もちろん、解は「不定」となる。x=1、y=0もまた、与えられた式を満足ずるという意味で、「正解」であり、x=0、y=1もまた、与えられた式を満足するという意味で「正解」である。 (1)十分な情報が与えられているばあいは、解は、一意的に定まる。 (2)情報が不足しているばあいは、解は、「不定」となる。すなわち、無数の「正解」が存在しうることになる。問題が解けない「不能」になるのではなく、「不定」となるのである。 (3)情報がまったく与えられていないばあいは、問題そのものが成立しない。 「邪馬台国論争」はつぎのどの状況にあるのであろうか。 (B)情報が不足しており、解は「不定」となる。すなわち、無数の「正解」が存在しうる。(それにもって行く) (C)情報は解をうるために十分に与えられているのであるが、どの解も、どこか矛盾を生じ、解くことは「不能」な状況にある。このばあいは、「解けないこと」「不能であること」じたいが、証明されなければならない。 (D)問題は、例えば「邪馬台国は北部九州に存在した」という形ですでに解けているのであるが、解くのに、数学などを用いているので、数学という言語を、忌避する人たちには、うけいれられない。あるいは「邪馬台国は畿内にあった」という前提にたつ人たちにはうけいれられない。 以上のようなことを、よく検討しておかないと、すでに解けているものが解けていないことにされたり、解けていないものが解けていることにされたりすることになる。議論が混乱する。 邪馬台国問題は、「解けない」問題ではなく、なにが「解けた」という状況をさすのか、それをわかっていただかなければならない状況にあるようにみえる。 すなわち、私は邪馬台国論争は、先に述べた(D)の状況にあると考える。 考古学関係の方は、すでに、「棺あって槨なし」問題でみたように、文献的事実は、それが事実であっても、言葉による記述は言葉による「解釈」しだいで、なんとでもなるとする方が多い。つまり、「文献軽視」の傾向が強い。文献的記述との矛盾を「解釈」によって矛盾としない傾向がかなり強い。 しかし、邪馬台国問題は、もともと文献における記述から出発している。文献記述と、矛盾する理論や学説よりも、文献記述とも矛盾しない理論や学説のほうがよりよいことはあきらかである。 日本の考古学は、独自な傾向を発達させ、世界基準の考古学とかけはなれている。世界基準の考古学は、ギリシャ・ローマの考古学や『聖書』の考古学が母体となっている。その考古学は神話・伝承といったものにみちびかれたものであった。しかし、日本の考古学では神話・伝承を排除する傾向が強い。 一連の問題を考えるにあたって、まず検討しなければならないことは、「世界基準の考古学、文献学、そして歴史学」と、「わが国で現在、かなり発言力をもつ一群の学者、研究者の主張する考古学、文献学、そして歴史学」とは、その意味内容に、かなり大きなへだたりがあり、ほとんど異質のものといってよいほどのものであることである。そこには、「地動説」と「天動説」との対立に近い、といってもよいほどの対立がみられる。 日本考古学は、独自で特異な傾向を発達させ、世界基準の考古学とは異質のもので、孤立したものとなっている。 (A)文献資料を用いない。『魏志倭人伝』はわが国の古代のことを記した文献である。わが国には、わが国の古代のことを記した文献として、『古事記』『日本書紀』をはじめとする諸文献がある。 いっぽう、現在の世界で基準となっている「考古学」は、ギリシャ、ローマの考古学や、『聖書』の考古学などが母体となったものである。その考古学は、神話、伝承といったものにみちびかれて成立したものであった。このことを忘れてはならない。 (B)総合の論理と方法とを発展させていない。(A)で、のべたこととも関係するが、「歴史」を復元するには、文献学、考古学、言語学、民俗学などによる諸成果を組みあわせ、相互にチェックし、「総合」する必要がある。とくに、「文献学」と「考古学」とは、「歴史」を復元させるための、大きな両輪である。 また、考古学の分野の中でも、個々の遺物や遺跡を、できるだけ詳細に記述する「記述考古学」や出土品などの目録をつくる「目録考古学」の傾向が強い。 考古学者の細谷葵(ほそやあおい)氏(女性。1967~2019)は、お茶の水女子大学の特任准教授をされていた方で、若くしてなくなられた。 細谷葵氏は、外国留学の経験のある方で。1966年当時、ケンブリッジ大学留学中に、『理論なき考古学-日本考古学を理解するために』という報告文を発表されている。 (C)属人主義的傾向が強い 猫は、観察力や記憶力などを持っていても、「歴史」を知ることはできない。百年前のことを知ることはできない。 英語で、「ヒストリイ(history)」といえば、まず、「歴史」のことである。ただ、英語の「ヒストリィ」は、「物語」という意味ももっている。フランス語で、英語の「ヒストリイ」と語源を等しくすることばは「イストワール(histoire)」である。フランス語の「イストワール」は、おもに、「物語」という意味である。これらの言葉は、ギリシヤ語やラテン語の「ヒストリア(historia)」からきている。 言語情報を排して、「歴史」は成立しえない。出来事や遺物を、年代という時間の軸の上にならべることによって、「歴史」も、「物語」も成立する。 世界基準の考古学 シュリーマンは、神話伝説で語られてきた古代ギリシャ文明が、考古学の対象となりうるものであることを示した。 「なぜ、わが国では、伝承がすべて虚構だとしりぞけられるのかと、ギリシアのばあいとくらべて、その拒否反応というか潔癖というか、そんなものの強さが、私には異常なような気がしております。ギリシアのばあいとは、伝承の成立が異なるにしてもなぜ伝承のなかになにか真なるものを探ろうとする態度が認められないのかと、日ごろ感じておりました。」 (2)サンソム卿の見解 「かつて英国の駐日商務参事官として永らく日本に在留し、いまはアメリカのスタンフォード大学にいられるジョージ・サンソム卿が畢生の著述として、『日本史』三巻を計画し、その第一巻を出版されたことは、かねて聞き及んでいたが、このたびその書物を読む機会に恵まれた。 「神武東征、日本武尊の遠征などの物語は、こまかに委曲を叙述して、それが歴史事実の反映であることをみとめる。九州にあつた邪馬台国の勢力が東に進んで、畿内の大和の勢力となった。その東遷の事実が、神武天皇東征の物語となって伝えられたというのである。神代の物語も、『国民、その風俗、信仰』の条で、こまかに取り上げられ、日本歴史を動かした基底の力がそこにあることに注意する。要するに、神話・伝説はおちなく紹介され、合理的に解釈せられて古代史の初めを飾っているのである。」 このように、サンソム卿は、邪馬台国東遷説の立場をとり、神武東征の時期が、邪馬台国の時代のあとであるとするのである。 (3)林健太郎氏の見解
「考古栄えて記紀滅ぶ」ということばがある。 「後藤(守一)先生は「三種の神器の考古学的検討」という論文を雑誌『アントロポス』に発表し、翌年には『日本古代史の考古学的検討』(山岡書店)という冊子風の単行本にその論文を収めた。先生の知識の豊かなことや自由な発想に、当時十八歳の僕は驚嘆した。もちろん先生の勇気にも感心した。
|
| TOP>活動記録>講演会>第424回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |