| TOP>活動記録>講演会>第278回 | 一覧 | 次回 | 前回 | 戻る |
 |
 |
 |
 |
|
第278回 講演会(2009.3.22 開催)
| ||||
1.トピックス『纒向遺跡の建物跡』
|
 ■ 纒向遺跡の建物跡が卑弥呼時代の建物?
■ 纒向遺跡の建物跡が卑弥呼時代の建物?
2009年3月21日の新聞(読売、毎日、朝日は夕刊)で「奈良県桜井市の纒向遺跡で、 計画的に建てられたとみられる3世紀前半〜中頃の3棟の建物跡が確認された。」ことが報道された。 纏向遺跡は、邪馬台国畿内説を採った場合、都の最有力候補とされており、桜井市教育委員会は、卑弥呼の時代の遺跡中枢部の一端が明らかになったとしている。 この報道についていくつかの論点がある。 ■ 本当に3世紀前半〜中頃という年代なのか この年代は庄内式土器によって判断されたものである。庄内式土器の年代の決め方については、石野博信先生と昨年対談した時に話題としたが、石野先生は年代を次のように決めていると解説された。 まず、古い方は王莽の新の時代(8〜23年)の貨泉で決め、新しい方は5世紀ごろに現れた須恵器で決めると言うことであった。そして、その間に土器の型式がいくつあるかを調査し、年代を割り振る。そうすると、庄内式土器の時期がおよそ250年代になり、纏向遺跡の年代も決まってくる。 これに対し、安本先生は、古い方は洛陽の焼溝漢墓(190年頃)で決め、新しい方は 洛陽晋墓(300年頃)で決めるとする。 これらの墓からは、多くの鏡が出土するので、鏡の年代が決まる。蝙蝠鈕座内行花文鏡は両方の墓から共通に出土する鏡であり、190〜300ごろの邪馬台国の時代に中国で盛んに用いられた鏡である。 邪馬台国時代の蝙蝠鈕座内向花紋鏡が、日本では九州から多数出土する。この時代の鏡の分布の中心は九州に在ったと言うことである。 石野先生の方法と安本先生の方法を比べると、焼溝漢墓と洛陽晋墓で年代を押さえたほうが、年代幅が狭いし、両墓とも墓誌が出いるので年代がはっきりしている。 貨泉は日本に来るまでの時間が判らないので年代を明確に決められない。 安本先生は庄内式土器の時代は卑弥呼の時代よりも少しのちの時代と考えている。  ■ 建物と「王権」「都」とは結びつくのか
■ 建物と「王権」「都」とは結びつくのか
『魏志倭人伝』には、「宮室、楼観、城柵、おごそかに設け」と記されているが、中国人のいう城柵とは吉野ヶ里のように一定の地域を囲うものと考えられるので、今回発掘された柵は城柵とは言えない。 また、楼観もないようなので、立派な建物があったという程度のものである。 これを「王権の中枢施設の一角(毎日新聞)」というように、すぐに王権と結びつけたり、「卑弥呼の宮殿か(産経新聞)」などとするのは解釈の行き過ぎである。 ■ 『魏志倭人伝』に記されている事物が出土したわけではない。 畿内説を説く研究者の共通の欠点は、『魏志倭人伝』から離れて議論をすることである。 今回の発掘でも、鉄の鏃や中国北方系の魏代の鏡などが出土したわけではない。建物があったとか土器があったとかは間接証拠、状況証拠でしかない。これらは『魏志倭人伝』の記述に直接結びつくわけではない。 『魏志倭人伝』に記されている事物でみれば、ことごとく九州のほうが多く出土する。近畿からの出土は非常に少ない。この事実を畿内説の学者はまったく考えていないのではないか。 間接証拠を並べて解釈を重ね、新聞報道すれば良しとしている。
■ 土器の年代 下図に示すように、1970年頃は、石野博信氏や佐原眞氏、都出比呂志氏などは、庄内式土器を西暦300年以降の土器と見ていた。布留式土器はそのあとの古墳時代の土器と見ていた。 ところが、1980年代になると、庄内式土器は200年代前半にまで遡り、都出氏は布留式土器も3世紀後半にまで古くした。 この間、考古学的には特に新しい発見があったわけではないが、「年輪年代法」の登場で、遺跡から出土した木材の年代が大変古く出たことで、一斉に年代の前倒しが行われたように見える。 しかし、「年輪年代法」で測定した年代を遺跡の年代とするには疑問が残る。木材を伐採した年代と使用した年代とは異なるからである。 木材は伐採した後、長期間寝かせることがある。また、再利用や、風倒木の利用などでも、使用年代と年輪年代が大きく違ってくる。 また、最近では、土器付着物の炭素14年代測定が盛んに行われ、これによって庄内式土器の年代もかなり古いという主張がある。 しかし、桃の核やクルミの殻などの分析と比較すると、土器付着物は100年あるいはそれ以上古い値が出るという事例が数多く報告されてきているので、予断を持たずに公正な立場から正確に分析すべきである。 邪馬台国畿内説は、「はじめに畿内説ありき」の立場に立つ考古学者たちの、遺跡・遺物の恣意的な解釈とマスコミ宣伝によって成立している。 実証によって成立しているのではない。 < 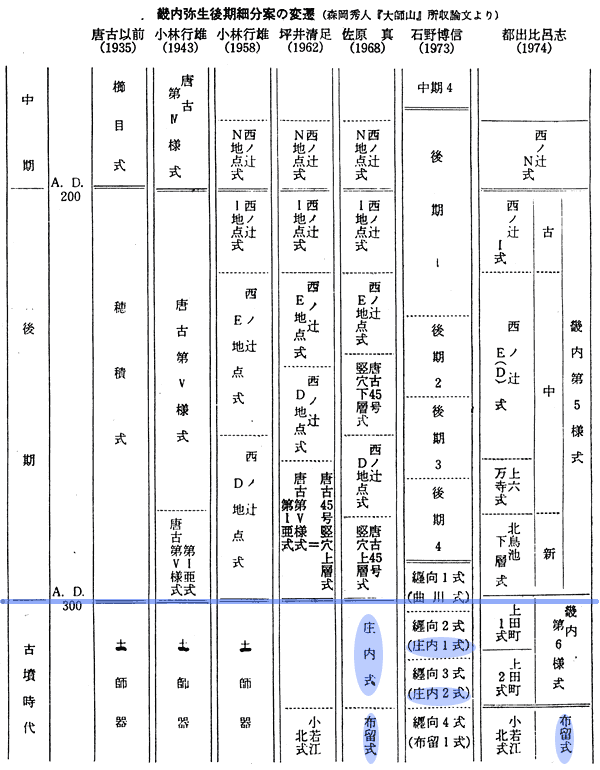
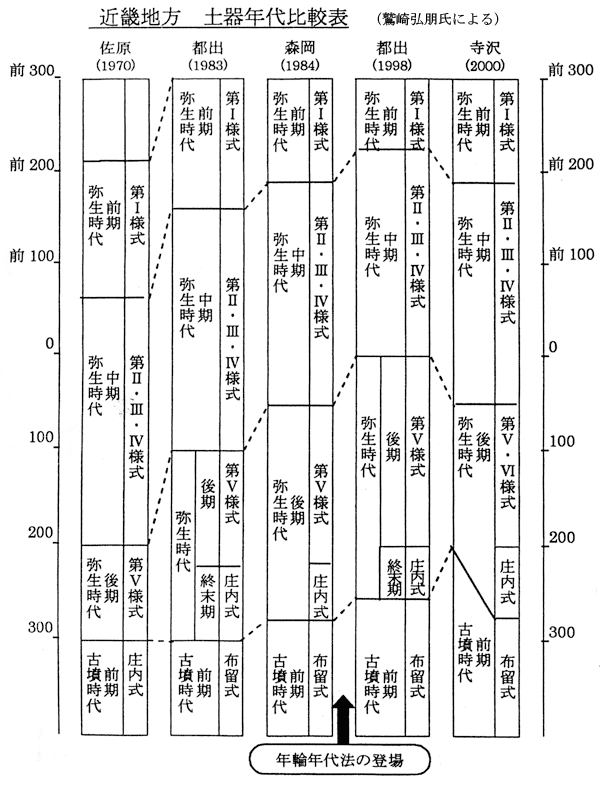
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.古代史探求の方法
|
■ 歴史とは何か
イギリスの外交官で国際政治学者のE.H.Carr(カー)が書いた古典的名著『歴史とは何か』で、カーは「歴史とは現在と過去との対話である。歴史とは現在から過去を投影し、同時に過去から現在を投影するものである。」とし、「客観性」のみで歴史を記述しようとした近代歴史学を否定した。 司馬遷の『史記』は、例えば、項羽の最後の場面などを見ると、表現に迫力があり、現代の我々の感情を揺さぶる。カーの述べるように現在と過去が対話が成立している描写である。 中国の陳凱歌が映画化した『覇王別姫』(京劇の『覇王別姫』を演じる2人の役者 の愛憎を50年に及ぶ中国激動の時代を背景に描いたもの)などはまさにカーが述べる 過去との対話である。 しかし、このように、「歴史とは現在と過去との対話である」とし、現在の我々が 生きるための希望とか慰めを歴史の中に求めるなら、歴史ではなく小説でも良いことになる。 「恋しくばたずね来て見よ、和泉なる信太の森のうらみ葛の葉」などみずから身を引く つらさを、象徴するような物語の「葛の葉」の話は、狐が娘に化けるなど現実にありえ ない話を加え、面白く作られている。このような架空の話でも我々の感情に影響を与え、いわば、我々と対話することが可能になってしまう。 安本先生はこのような立場を取らない。 ■ 19世紀的文献批判学 19世紀に実証主義的文献批判学が盛んになる。「不合理なものは信じない」という立場である。 江戸時代の山片番桃はこの立場から、『古事記』は応神天皇以降のみ信頼できるとし、それ以前の記述を否定した。 津田左右吉の主張も山片番桃の系列の学説である。 明治時代でも、東京帝大教授の久米邦武は、それまで史書として広く読まれていた『太平記』を、前近代の巷談俗説として批判した。 しかし、その後の研究によって、『太平記』の記述には、史実の誤認や実在の定かでない人物の活動など、誇張や曲筆はあるものの、時代の本質をよく伝える部分も少なくなく、この時期の社会や思想の動きを考える上でかけがえのない豊かな内容を持つ文献であることが認められてきた。 また、帝大教授の重野安繹(やすつぐ)も、太平記で後醍醐天皇の救出に努力した忠臣児島高徳について、『太平記』以外に名前が記された確実な試料がないため、その存在を否定したが、近年の研究で、太平記の記述の傍証となる資料が発見され、児島高徳は備前邑久郡地方の土豪であったことがほぼ確実とされている。 19世紀的文献批判によって、ギリシャ神話はお伽噺とされていたが、シュリーマンの発掘によって現実の話であることが明らかにされた。 中国でも、清の康有為は、19世紀的文献批判によって、夏・殷などは架空の話と主張したが、その後の発掘によって存在が認められるようになった。 日本では、戦前に『古事記』『日本書紀』が皇国史観の拠り所にされたこともあって、戦後に津田左右吉の文献批判学が中心となり、史書としての『古事記』『日本書紀』は全面的に否定された。そのため、邪馬台国問題を考える場合も『古事記』『日本書紀』が使えない状態になっている。 だから考古学だけで話をつけようと言うことになる。そうすると、少数の人がわずかな史料で突っ走ってしまうという弊害が出ている。 やはり、考古学も文献学も活用しないといけないと思う。 安本先生の立場は、津田左右吉のように、何でもかんでも疑ってかかりましょうというものでもない。 ■ 探求の構造
 ■ 認識について
■ 認識について
■ 「数字」で表現する方法 数字で表現する方法は地図を正確に描くための有用な技術である。 人文科学関係の人が、しばしば述べる数についての誤った意見がある。
温度にしても、速さにしても、明るさにしても、それはもともと質的なものである。それを今日、数字で表現して、量的処理を行って、だれしもあやしまない。 数量的概念は、対象に数を適用するという人間の積極的な行為によってはじめて生じている。 質的なものと、量的なものとの違いは、私たち概念体系のなかでの違いである。 これは私たちの言語のなかでの違いであると、ということができる。 ■ 事実と意見を分けること 事実による説得の方法について考えるとき、「事実」と「意見」を分けて考える必要がある。私たちは、日常の議論などで、事実と意見とをしばしば混同する。 たとえば、「あの娘は美人だね」と言った場合、そこには事実以外の個人の意見、判断がはいりこんでいる。そのため、美人であるかどうかを議論しようとすれば、しばしば意見の不一致が起きる。 これに対し、その女性が二重まぶたであるかどうかといった事実にもとづく議論をすれば、意見の不一致はおきない。 私たちが客観的な議論をする場合は、できるだけ、事実にもとづく議論をする必要がある。 事実による説得、あるいは、事実と言葉との関係を研究する学問がある。一般意味論といわれるものである。 一般意味論では、意見がくい違ったときには、言葉の段階での話し合いをやめ、具体的事実の検討に移れ、といわれる。ここで、事実というのは観察されたことがらを指す。 アメリカの一般意味論研究所の所長であったコージプスキーは、ことばを専門用語と非専門用語に分け、専門用語で90度とかH2Oとか書けば誤解なく議論を進められるが、非専門用語は誤解を招く言葉であると述べている。 この90度とかH2Oのような表記は、意味するところは一義的である。学問などを進める際に用いられる言葉は、明確な定義によって限定され、可能な限り一義的であることが望ましい。 邪馬台国問題についても、水掛け論になるような所から議論を始めてはいけない。だれがやっても一義的に定まるところから議論を始めるべきである。 そのためには数値などで表したデーターから議論を始めるのがよい。 下図のようなデータは、畿内説の学者が調べても九州説の学者がやってもほぼ同じ結果になる。このような情報に基づいて議論を始めるべきだと考える。 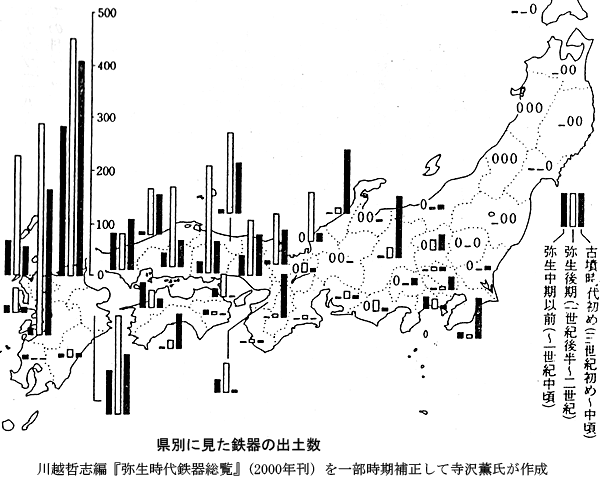 ■ ニュートンの方法(演繹法)とダーウインの方法(帰納法) 科学上の業績などを観察すると、その結論に至る方法は大きく見ると演繹型と帰納型の2つのタイプに分かれる。 演繹型は、ニュートンの『プリンキピア』やユークリッドの『幾何学原論』なのどの 業績がその典型で、確実な少数の事実から出発して、自己完結的なほぼ完璧な体系 をつくりあげる。それは堅牢で閉じられた体系であり、ひとたび成功したならば、容易に破壊されない。 帰納型は、チャールズ・ダーウインの『種の起源』などの業績がその典型であり、現実に 密着して、客観的な事実を徹底的に収集し、そこから帰納的な方法で、それらの諸事実 を説明する一般法則を仮説として導き出すというやり方である。 一般社会、あるいは人文科学、社会科学の分野においては、自然科学に比べて多くの場合対象が個別的な性質を持っている。演繹的な方法による説得よりも、帰納法的な方法のほうが適している場合が少なくない。 ■ パスカルとヒルベルトの公理についての考え方
■ パラダイムの変換 前提は何でも良いということから、現代の科学的方法論では、議論の出発点となる 仮説の任意性が主張されている。 そのため、仮説の設定の仕方によって、ものの 見え方、考え方が大きく変わってしまうことがある。これを「パラダイムシフト」 という。 良い例が、天動説から地動説に変換したことである。この転回に端を発 して、科学的な概念の枠組みが大きく変わった。 見る世界や宇宙にはなんの変化もなかったが、われわれが宇宙をみるときの姿勢や考え方にとって、この転回はきわめて劇的であった。 ■ 安本先生の古代史についての仮説系 安本先生は、ヒルベルトの考え方に従って、古代史を考える上で次のような仮説系を置いている。この仮説から出発することで、従来のさまざまな議論に比べ、より多くのこと説明することができる。
しかし、安本先生の記紀についての考え方は仮説である。仮説が批判されていることになる。 ヒルベルトの仮説論(新しい公理主義)によれば、仮説自体はどんなものでも良いとされているので、このように仮説を批判するのは、批判のやり方としては誤りである。 仮説(仮定、前提)から結論に至る道筋のどこに誤りがあるか、導き出した結論を客観世界の示す事実(データ)と照合するとき、どのような矛盾が生じているかを指摘しなければ、批判をしたことにならない。 ■ 論理による説得の手続き 西洋の中世のスコラ哲学にしても、天動説にしても、論理的には整ったものだった。しかしそれは、対象を説明しうる唯一の説明体系ではなかった。地動説は、天動説よりも、対象をもっと適切に説明しうる体系であった。 論理的に整っているということだけではその説明体系が最も妥当なものであるという保証には必ずしもならない。理路整然と間違っている可能性があるのである。 このような欠点があっても、論理による方法は、ほかの方法に比べてきわめて体系的で構造的な知識をもたらすことも事実である。 論理による説得を行うときに、次のような手続きによって行われる。
|
| TOP>活動記録>講演会>第278回 | 一覧 | 上へ | 次回 | 前回 | 戻る |
 すなわち、いくつかの仮定をおき、そこから形式的に結論を導いて、そこに矛盾
を生じなければよいとする新しい公理主義である。
すなわち、いくつかの仮定をおき、そこから形式的に結論を導いて、そこに矛盾
を生じなければよいとする新しい公理主義である。