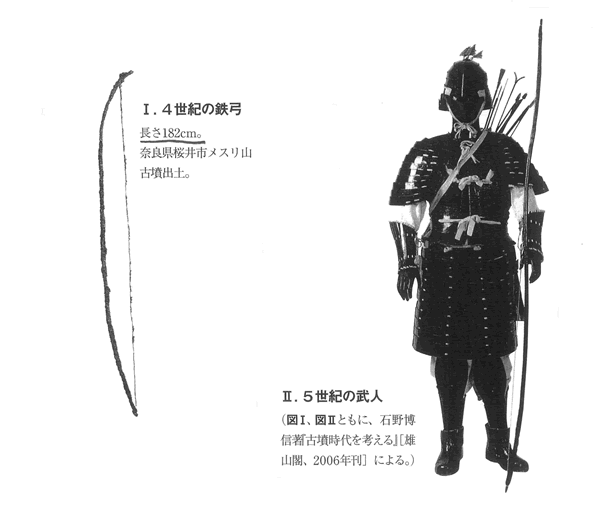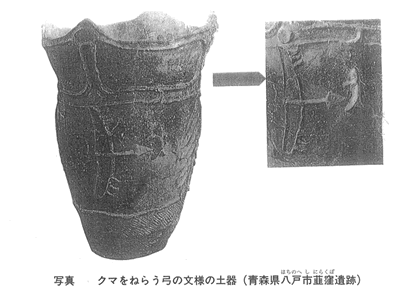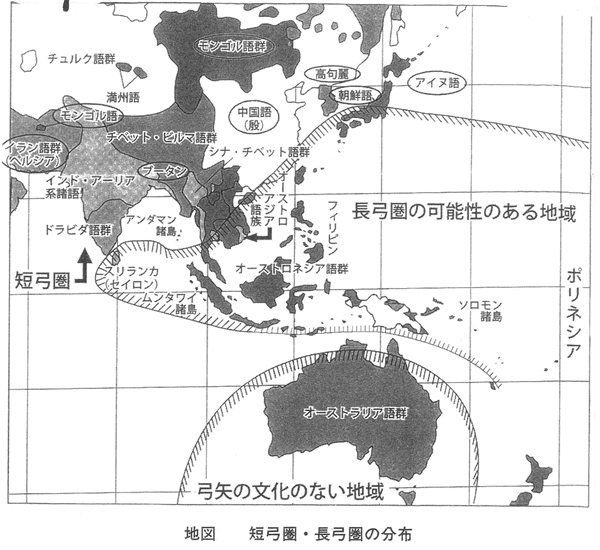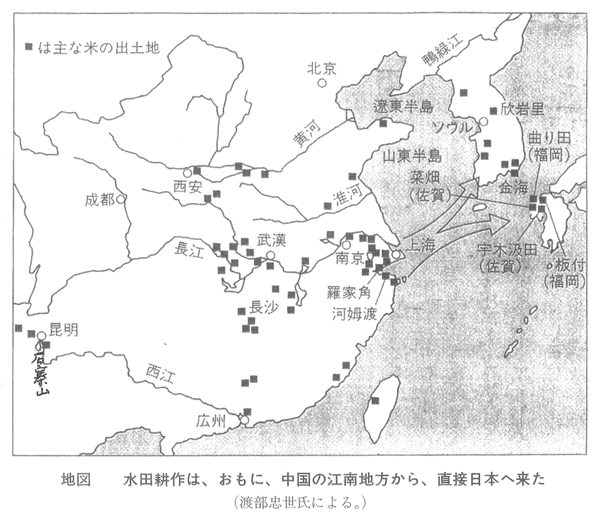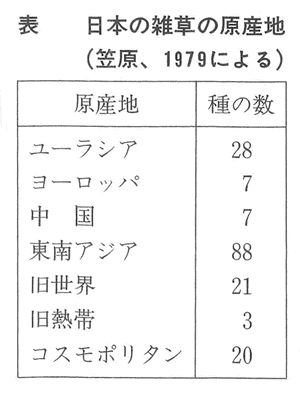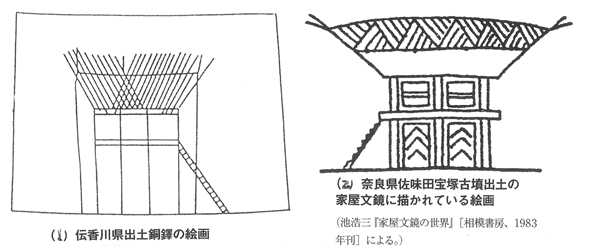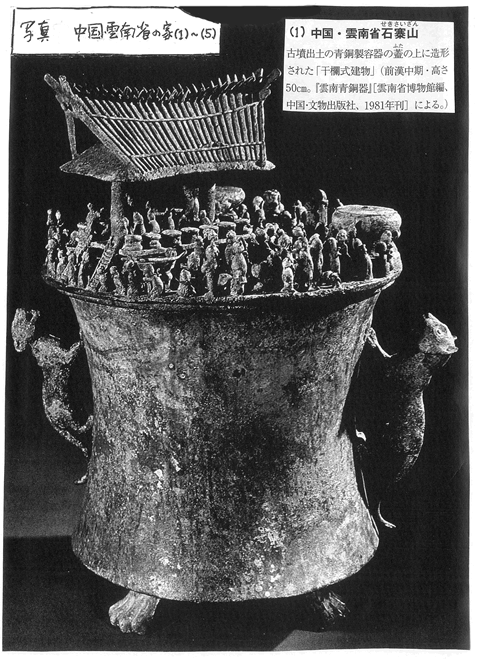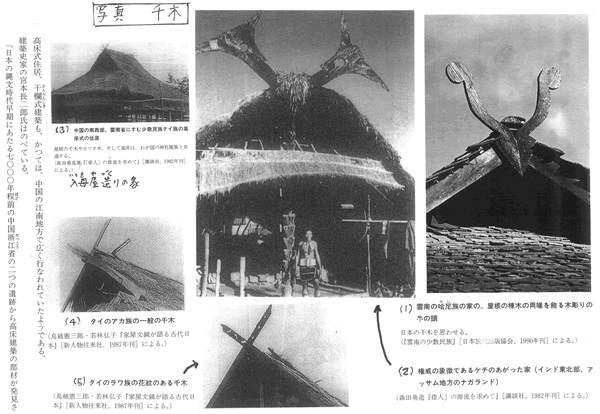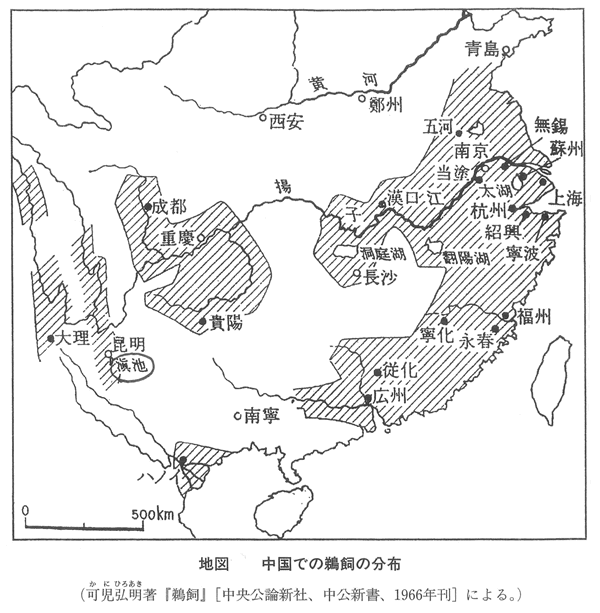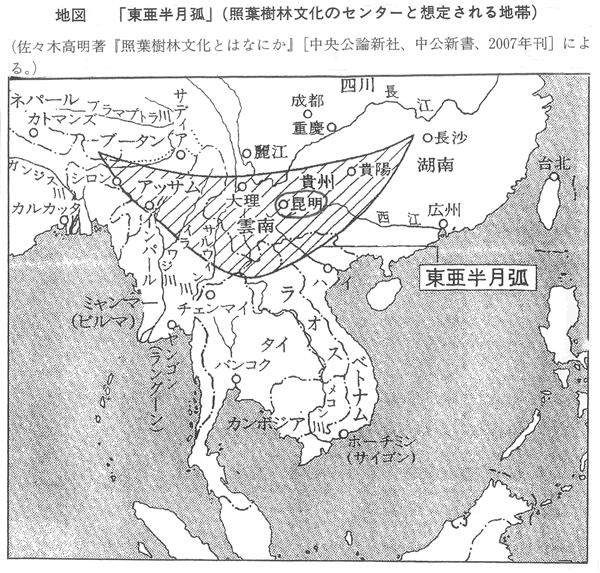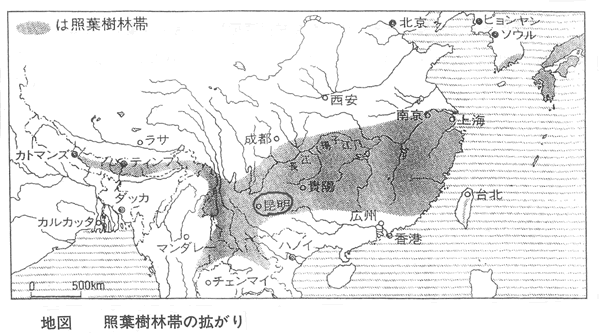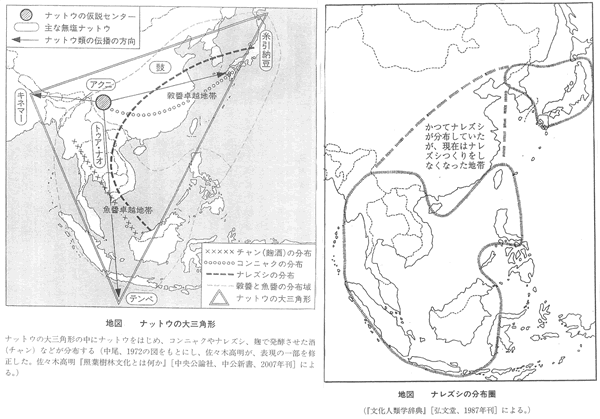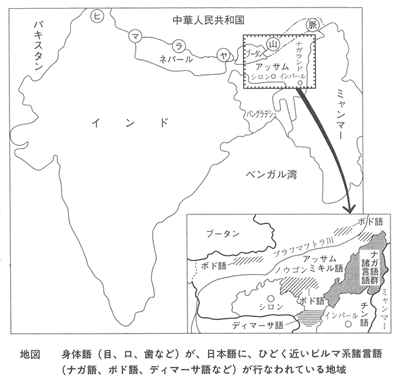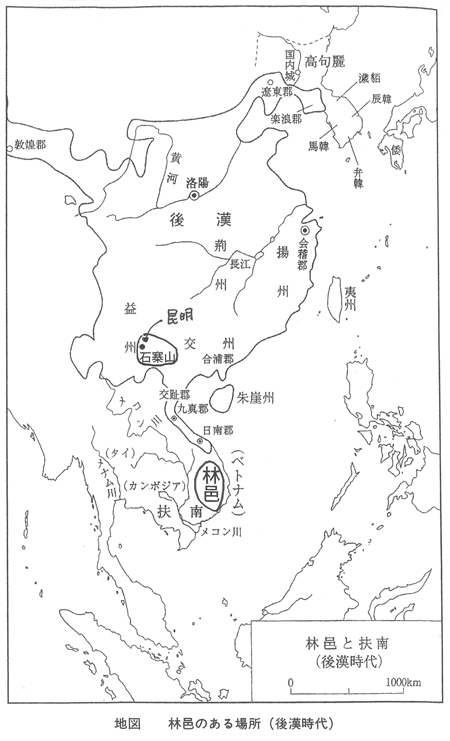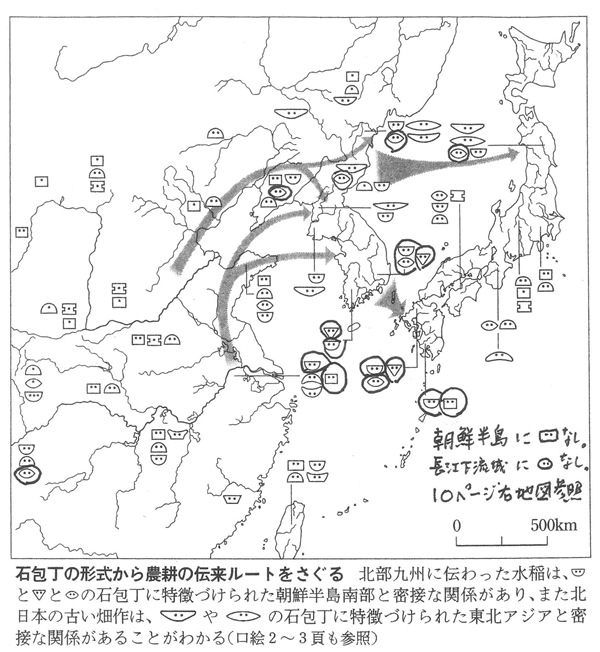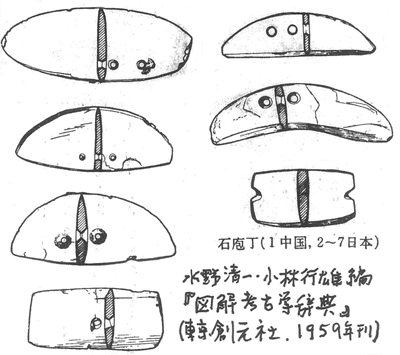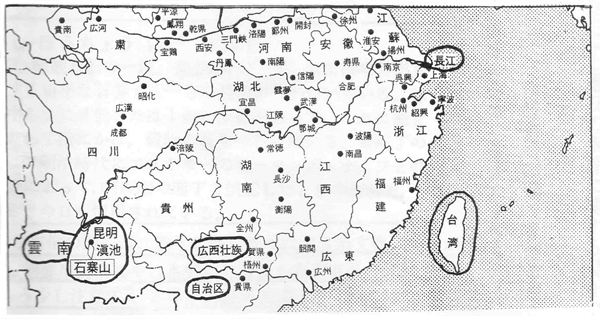■倭人の弓
・日本の弓は長弓
『魏志倭人伝』は記す。
「(倭人の弓は、)下に短く上に長い。」と。
倭人の弓は、伝統的に、身長を、しばしば大きくこえる「長弓」であった。
このような長弓は、ユーラシア大陸東部、南部では、まず見かけない。
この長弓の伝統は、どこから来たのか。
4世紀、5世紀の日本の弓(下図参照)
Ⅰ.4世紀の鉄弓
長さ182cmのものが、奈良県桜井市メスリ山古墳から出土している。
Ⅱ.5世紀の武人の弓も身長を超える。
(Ⅰ、Ⅱは石野博信『古墳時代を考える』[雄山閣、2006年刊]による。)
図から日本の弓は長かったことが分かる。
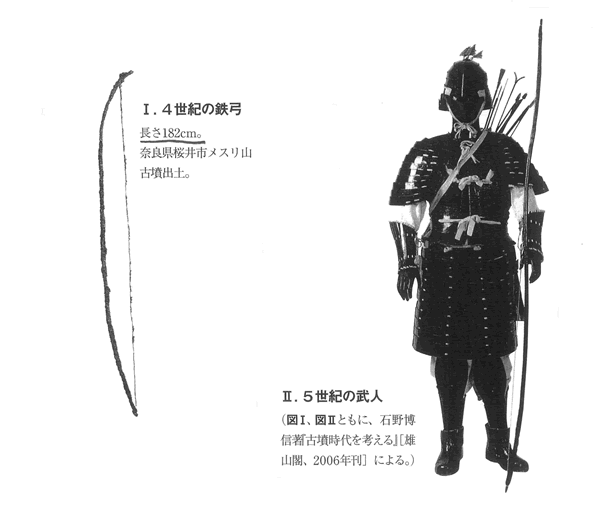
それに対し、高句麗、匈奴など中国北方や中国は短弓であった。
Ⅲ.高句麗壁画の弓
高句麗の弓は、アーチェリー型の短弓であった。
高句麗は、4世紀から6世紀ごろ栄えた。668年に、唐と新羅との連合軍によって滅ぼされた。(薬水里古墳、5世紀初、朱栄憲「高句麗文化展図録」)
(石野博信『邪馬台国と古墳』[学生社、2002年刊]に引用されたものによる。)
Ⅳ.匈奴(きょうど)の弓
紀元前4世紀末から、ほぼ5世紀間、モンゴルを中心に繁栄した騎馬民族、匈奴の弓は、下図にみられるように、アーチェリー型の短弓であった。
内蒙古自治区出土。青銅製とみられる。
(『世界考古学事典上』[平凡社、1979年刊]による。)
Ⅴ.中国の弓
中国の弓も、伝統的にアーチェリー型の短弓が主であった。図は、中国河南省北部の山彪鎮(さんびょうちん)西の墓から出土した銅の鑑(かん)[大きな鉢(はち)]に描かれた画象文。墓は、春秋時代後期後半の晋末期の貴族のものとみられている。
[『世界考古学事典上』(平凡社、1979年刊)による。]
(下図はクリックすると大きくなります)

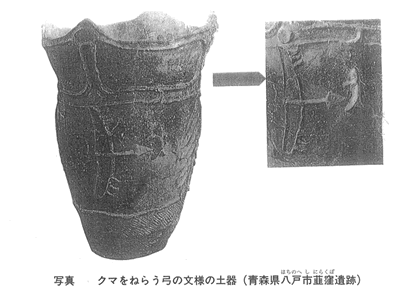
・縄文時代の弓
2010年の8月に、北海道中部の恵庭(えにわ)市和光町のユカンボンE11遺跡から、縄文時代中期の、木製の矢柄(やがら)数本が、黒曜石の鏃とともに出土している(『千歳民報』2011年5月31日刊)。
新聞の報道では、約4700年まえのものとされている。
矢柄は、長さ五十~六十センチのものとされている。その長さが、長くないところからみて、短弓に用いたとみられる。
これは、わが国で、もっとも古い矢の例とみられる。
出土した場所からいって、アイヌの祖先にあたる人たちが用いた可能性がある。
また、福島大学教授の、工藤雅樹氏の著書『古代の蝦夷』(河出書房新社、1992年刊)に上図のような写真がのっている。
写真はクマをねらう弓の文様の土器[青森県八戸市(はちのへし)韮窪(にらくぼ)遺跡]
縄文後期のもの。2本の樹木を思わせる文様の間に矢をつがえた弓と、クマのような動物が隆線で表現されている。狩猟の表現とも、アイヌ民俗のクマ送りのような儀式を表したものとも見られる。
これは青森県八戸市から出土したもので、縄文時代の後期のものである。
これも、短弓の系統のようにみえる。
青森県八戸市という場所からいって、アイヌの祖先にあたる人たちの用いたものであろう。
北海道小樽市(おたるし)の忍路(おしょろ)土場遺跡出土の、縄文時代後期の弓。
出土した場所からいって、アイヌの祖先にあたる人たちの用いたものとみてよいであろう。
これも短弓の類である。
以上のようにみてくると、アイヌ系の人々の住んだ地域では、数千年にわたって、短弓が用いられてきたようにみえる。
・アイヌの毒矢について
アイヌは毒矢を用いた。
アイヌの毒矢の作りかたについては、ジョン・バチラー著の『アイヌの伝承と民俗』(安田一郎訳、青土社、1995年刊)に、くわしくのべられている。
そのなかで、ジョン・バチラーは記す。
「猟をするとき、アイヌは矢に毒を塗った。そしてある種の毒は、トリカブトの根から作られた。」
「アイヌが狩猟で用いる矢は貧弱で弱い道具のように見える。しかし、非常に強力である。」
1336年(延元元年)1月28日、足利尊氏が、長野県諏訪神社に寄進した『諏訪大明神絵詞』のなかに、北海道のアイヌの毒矢についてふれた文がある。
そこでは、つぎのようにのべられている。
「彼らが用いるところの箭(や)は、魚骨をやじりとして、毒薬をぬる。わずかに皮膚に触れれば、その人は倒れないということはない。」
『文化人類学事典』(弘文堂、1987年刊)では、世界の矢毒の分布を、地理的な分布と、用いられる植物の種類とから、四つにわけている。
その一つに、東北アジアから、アッサム・ヒマラヤにかけてにみられるトリカブト圈をあげる。そしてのべている。
「トリカブト圈において最もよく知られた例はアイヌであるが、彼らはトリカブト(キンポウゲ科)の根を粉にし、マツヤニをつけたやじりにその粉をつけて用いていた。」
毒物学の石川元助氏は、およそ、つぎのようにのべている。
「キンポウゲ科のアコニツム属植物を矢毒につかう伝統は、北海道と沿海州、樺太(サハリン)、アリューシャン、アラスカ半島に、西南へは、中国大陸を通って、雲南、四川、さらに、ネパール、ブータンにのびる。毒矢文化の起源は、ヒマラヤとみられる。毒矢文化を、アイヌ祖先集団に伝えたのは挹婁(ゆうろう)族であろう。」(『毒矢の文化』紀伊國屋書店、1962。『毒薬』毎日新聞社、1965年刊)
『後漢書』や『三国志』の挹婁伝(ゆうろうでん)には、つぎのように記されている。
「弓の長さ四尺(約96センチ)。」(『後漢書』『三国志』同文)
「矢には毒をほどこし、人にあたればみな死ぬ。」(この文は、『三国志』による。『後漢書』は、「鏃(やじり)には、みな毒をほどこし、人にあたれば、即死する。」とある。)
挹婁(ゆうろう)は、「いにしえの粛慎(しゅくしん)」とされている民族で、ツングース族の一種である。ロシアの沿海州(アムール川[黒竜江]下流域、ウラジヴォストークを中心とする地域)から、中国東北地方(旧満州)東部に住んでいた。
下の地図参照
(下図はクリックすると大きくなります)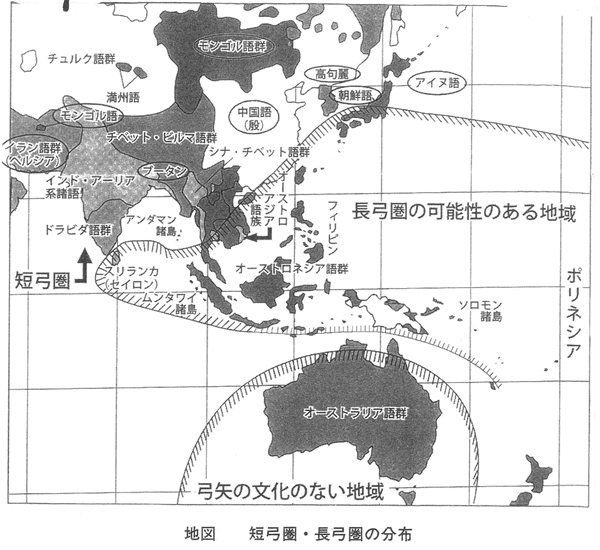
アイヌの弓矢文化が、短弓で毒矢をもつのに対し、倭人の弓矢が、長弓で毒矢を用いないことなど、弓矢、については、文化の系統が異なるようにみえる。
・モンゴルの弓
騎馬によって、欧亜を席巻したことのあるのは、モンゴル族であった。
モンゴル族の弓も、短弓系の弓とみてよい。
やはり、アーチェリータイプの短弓である。
モンゴノ軍も、毒矢を用いた。
鎌倉時代末期の神道書で石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)霊験記(れいげんき)を書いた『八幡愚童訓(はちまんぐどうくん)』のなかに、つぎのような文章がある。
「(文永十一年[1274])十一月二十一日、蒙古(軍)は、船よりおり、馬に乗り、旗をあげて攻めかかる。日本の大将は、少弐(しょうに)[資能(すけよし)入道覚恵(かくえ)の孫の、わずかに十二、三歳のもの[少弐資時(すけとき)。十二歳で出陣]で、矢合わせ(開戦を通告する矢をはなつこと)のために、小さい鏑矢(かぶらや)を射(い)たところ、蒙古軍は、一度に、どっとあざ笑った。(中略)蒙古軍の矢は、短いけども、矢の根に毒を塗っているので、あたったものは毒気を負わないということがない。」(『寺社縁起』「日本思想大系、岩波書店、1975年刊」による)
これは、元寇のときの、文永の役のことをのべているのである。
大阪大学の黒田俊雄氏は、その著『蒙古襲来』(日本の歴史8、中央公論社、1965年刊)のなかで、つぎのように記している。
「蒙古軍は短弓で、矢も短かったが、すばらしくよく飛び、しかも矢じりに毒を塗っていたので、浅い矢傷でもひどく苦痛を与えた。」
矢が短いこと、毒矢であること、強い効力をもつことなど、アイヌの矢と共通している。
・オーストロネシア語族の拡散と長弓の伝播
以前の第355回講演でふれたように、Ⅰ類長大弓の分布と、オーストロネシア語族の拡散域ないしその影響圏との間には、明ちかに有意な関係がある。
岡崎光彦『原始和弓の起源』(『日本考古学』第39号、2015.5.日本考古学協会)
このように、長弓が広がっていったものと考えられる。
■稲作の起源
・稲作の起源はどこか
おもに縄文時代の、狩猟採集を主とする時代と、おもに弥生時代の水稲栽培を主とする時代とでは、生活のあり方が、大きく違う。
「稲作」は、人口の急速な増加をもたらし、新しい時代をもたらした最重要要因である。「稲作」が、自然発生的に、日本で行なわれるようになったということは、まずありえない。日本では、野生種の稲が、まったく発見されていないからである。
野生種の稲では、実が熟すると、穂からパラパラと地面に落ちてしまう。栽培種の稲では、実が熟しても、穂についたままである。また、野生種の稲は、発芽が不ぞろいで、出穂期も不ぞろいである。栽培種の稲は、いっせいに出穂し、いっせいに成熟する。
日本の山野に自然にはえているようにみえる稲は、すべて、栽培種が、野生化したものである。
中国の揚子江流域から、東南アジア、台湾、インドにわたる地帯には、野生種の種がみられる。
たとえば、「オリザ・ペレニス」という種は、「ウキイネ」で、多年生である。雨期に、水たまりになる場所に生じ、雨期に水がふかくなると、池のなかの泥の底の根から、三メートルも上の、水面に浮かんで生育する(右図参照)。
栽培イネ(Oryza sativa)は、インド型(インディカ種)と日本型(ジャポニカ種)とに、大きくわけられる。
最近の研究では、日本型のイネの起源地は、揚子江の中・下流域であろうといわれている。
日本の稲は、栽培種であるから、かならずだれかが、日本にもってきたはずである。
親となる稲がなければ、子となる稲は生じない。したがって、その系譜は、あるていどたどれるはずである。
では、日本の稲作は、いつごろ、どこから来たのであろうか。
・稲作は、江南から直接来た
稲作、とくに水田耕作が、もっぱら中国の江南地方から、対馬海流にのって直接日本に来た、とする考えをのべている人は、樋口隆康氏、渡部忠世氏、松尾孝嶺(まつおたかね)、安藤広太郎などかならずしもすくなくない。
そして、放送大学の渡部忠世教授の、つぎのような見解は、かなり十分な根拠がのべられており、支持できるものとみられる(下の地図参照)。
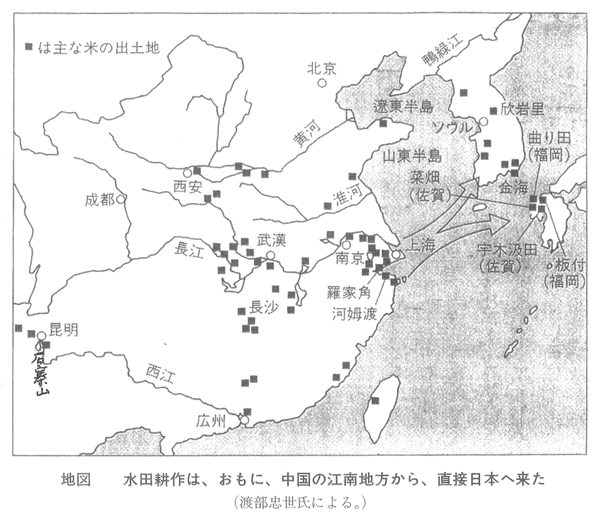
「稲作が、江南から直接日本、特に九州地方へ渡来したとする説は、多くの農学者も支持するところである。その大きなよりどころとなっている研究に、松尾孝嶺の『栽培稲に関する種生態学的研究』の成果がある。アジア各地に栽培される666品種を供試して、精密に形態、生態、生理的分類を行なったところ、日本の水稲に最も近似する品種は(朝鮮半島のものよりも)華中のジャポニカの一群であることなどが証明されている。
さらに雑草学者の笠原安夫の研究なども興味深い。岡山市津島遺跡の水田址で検出された雑草種子89種は、東南アジアから華中にかけて分布する雑草が大半で、長江以北には見られないものが多いという。水田の雑草を稲の隨伴物とみる限り、このことも江南地方以南からの渡来を主張するひとつの根拠となりうるだろう。
朝鮮半島を経由したとする考えは、考古学者のなかに支持の多い説といわれている。しかし、陸路を揚江流域から遼東半島に至って鴨緑江を渡り、文字どおりに半島を南下したとは、農学者や植物学者にとっては容易に賛同し難い推理であろう。遼東半島付近は北緯四〇度、盛岡よりも北である。
日本に渡来した稲がしだいに東方に移り、やがて北上して津軽地方にまで割合と早くに達したともいわれるが、東北の稲作史を正確に調べれば、陸奥(むつ)や陸中(りくちゅう)に比較的安定した稲作が確立するのは十六世紀も末の頃と考えてよかろう。
稲は長い年数をかけて次第に寒さなどへの適応を重ねた事実を考え合わせると、この経路がわが国に稲を伝えた古い道であったとはにわかに首肯(しゅこう)し難い。
半島を経由したケースとして考えられるのは、淮河(わいが)の周辺から黄海(こうかい)を渡り、今日の韓国南部から九州に達した伝播経路であろう。有名な釜山(ふざん)近郊の金海(きんかい)貝塚から出土した炭化米の存在がそのことを証明しているといえよう。しかし、このような場合に、これを朝鮮半島を経由して日本に達したと解釈する必要はないであろう。韓国南部と九州北部へほぼ同じ時期に到着したと考えても誤りはないのではなかろうか。かつて、安藤広太郎が『わが国の稲作は韓国南部とほぼ同じ時代に双方において始まり、わが国と韓国南部との間にはいずれからいずれに伝えたというのではないように思われる。』という説に、私も同意したい。」(「イネはどこからきたか---雲南と江南を経た道のり」『最新日本文化起源論』学習研究社、1990年刊)
この、韓国南部と九州北部の、ほぼ同時期に稲作のもたらされた地域、あるいは稲作をうけいれた地域こそが、「倭人」のいた地域とみられる。なお、金海貝塚から出土した炭化した米粒は、紀元後一世紀ごろのものとみられている。
「南船北馬」ということばがある。中国の南では、船が発達していた。
中国の江南の民のなかには、たまたま、朝鮮の南部や、北九州に漂着したものがおり、数千年のあいだには、往復の方法を見いだしたものもいたのであろう。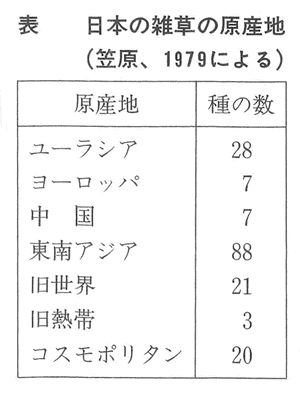
数千年のあいだには、さまざまなルートで稲がはいってくることがあったであろうが、メインになったのは、江南から直接きたルートであったようである。
外来の民族で、現代の日本民族や日本文化の形成に、もっとも古くもっとも大きな影響をもたらしたのは、北方騎馬民族ではなく、南方就船民族であったようにみえる。考古学関係の方のなかには、稲作や弥生文化の到来は、主として朝鮮半島ルートによるものとし、中国の揚子江流域文化や中国南部、さらには、インドシナ半島(ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、ミャンマーなど)との関連を、ほとんど無視する見解がある。
しかし、わが国の言語や文化において、揚子江流域以南の言語や文化の影響は、あきらかにみとめられる。
それを無視、または、軽視することはできない。
京都大学の教授などであった池橋宏氏は、その著『稲作の起源 イネ学(がく)から考古学への挑戦』(講談社、2005年刊)のなかで、さきのような考古学者の見解を、くわしく根拠をあげて批判している。
池橋宏氏は、まず、笠原安夫の「雑草の歴史」[沼田真編『雑草の科学』(研究社、1979年刊)所収]により、右上表のようなデータを紹介したうえでのべる。
「根栽農耕や水田農耕を通じて、日本が華南からインドシナ半島までと深いつながりをもっていることが、あらためて理解される。」
そして、池橋宏氏は、自説をまとめた部分の文章のなかで、つぎのようにのべている。
「長江中・下流域で長い年月をかけて工夫された漁撈と水田農耕を営む人々が、戦国時代末期から、越の滅亡などの社会的動乱のなかで新たな活路を求めて、東や南に移動したという歴史の背景を説明した。
民俗学者は古くからその見方を支持していたのに対し、考古学者は朝鮮半島からの文物の伝来を重視してきたが、後者は稲作民の移動の背景の説明がかならずしも一貫しない。それには『短粒のコメが長江流域から伝来しないはずである』という誤解も関係したことを指摘した。」
「越で発達した水田稲作が漁撈をともなう効率の高いものであり、それが朝鮮半島南部を経由して九州に伝来して、弥生時代の幕を開け、交通の不便な古代にあっても、それが急速に日本各地に普及した。」
「水田稲作が単なる灌漑農地ではなく、農耕の施設として、高い生産力を示したことが注目される。
イネは当初から水田で栽培化され、水田および漁撈は一体として伝来したという本書の見方の方が、『稲作の焼畑起源説』よりも、筋の通った説明を与えられたのではないだろうか。また、古代のイネの栽培で直播き栽培が確認できないということは、イネは水田で苗代と田植えと一体となって起源したとする本書での主張とも両立する。」
池橋氏ののべておられるところと、私がここでのべているところとは、大略において矛盾しない。
池橋氏は、別著『稲作渡来民』(講談社、2008年刊)のなかでものべている。
「一つの鍵は中国の史書に現れる『倭』という集団がどこにいたかという問題である。三世紀ごろまでの『倭』は、朝鮮半島南部と九州北部にいた稲作民を指しているのではないかという可能性は検討に値する。」
・二日と八時間で、会稽へ---『日本書紀』の記事
日本と江南とのルートを示す記事が、『日本書紀』に記されている。
縄文、弥生時代と、七・八世紀ごろとでは、船の構造の違いもあるとみられるが、参考になると思われるので、以下に紹介してみよう。
『日本書紀』の「斉明天皇紀」の五年(659)七月の条に、つぎのような文がある。
「伊吉連博徳(いきのむらじはかとこ)の書によると、この天皇(斉明天皇)の御世に、小錦下坂合部石布連(しょうきんげさかいべのいわしきのむらじ)・大仙下津守吉祥連(だいせんげつもりのさきのむらじ)らの二つの船が、呉唐(くれもろこし)の路(中国江南へ直行する南路)に派遣された。己未(つちのとひつじ)の年(斉明天皇五年・659年)の七月三日に難波の三津浦を発し、八月十一日に筑紫の大津の浦(博多港)を発した。九月十三日に百済の南方の島に着いたが、島の名ははっきりしない。十四日の寅(とら)の時(午前四時ごろ)に、二船あいそろって大海に乗り出した。十五日の日入(とり)の時に、石布連の船は横からの悪い風を受け、南海の島に漂着した。島の名は爾加委(にかい)という。そこで島人に殺害されたが、東漢長直阿利麻(やまとのあやのながのあたいありま)・坂合部連稲積(さかいべのぬらじいなつみ)ら五人は、島人の船を盗み、それに乗って逃げて浙州(せっしゅう)[浙江省麗水]に着き、州県の官人が洛陽(らくよう)の京に送りとどけた。十六日の夜半の時に、吉祥連の船は、越州の会稽県(かいけいけん)の須岸山(しゅがんさん)[舟山列島の須岸島か]に着いた。東北(うしとらのすみ)の風が吹き、大変強かった。二十二日に余桃県(よようけん)[浙江省余桃]に着き、乗ってきた大船と諸種の備品とをそこに留めた。閠(うるう)十月の一日に越州の州衙(州役所)に着き、十五日に、駅馬に乗って京(長安)に入った。二十九日に、さらに馬を走らせて東京(とうけい)[洛陽]に到った。天子(高宗)は東京におられた。三十日に、天子は謁見した。」
この記事で注目されるのは、九月十四日の午前四時ごろに大海に乗りだし、十六日の夜半には、中国の江南の会稽県についていることである。
二日(二昼夜)と八時間ほどで東シナ海を渡っていることになる。
■倭人の家
「干欄式建物(かんらんしきけんちく)」とよばれる高床式建物(たかゆかしきたてもの)の形式がある。
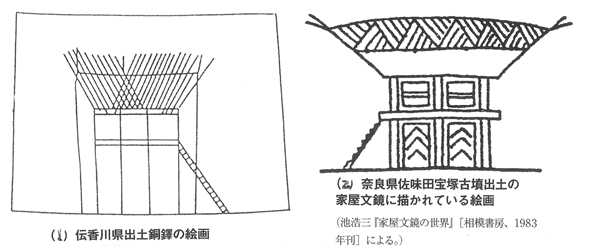
屋根の一番上の、棟(むね)の長さが長く、下の、軒(のき)の長さが短い。そのため、屋根を真横から見るとき、逆さの台形に見える。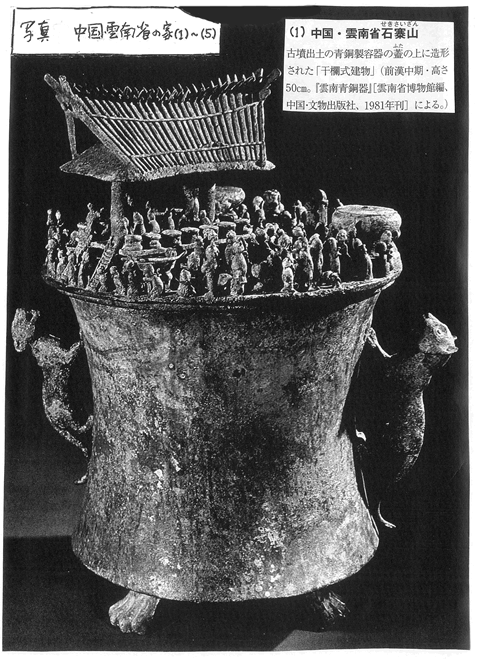
このような「干欄式建築」は、日本から遠くはなれた中国の雲南省の石寨山(せきさいざん)古墳出土の青銅製の容器の蓋(ふた)の上の飾りなどに造形されている。
また、中国の江西省清江県営盤里出土の家形土製品に見られる。
いずれも、長江流域およびそれ以南の地である。
いっぽう、わが国でも、「干欄式建物」は、弥生時代の銅鐸に描かれた絵画、古墳時代の鏡の上に描かれた絵画に見られる。また、「干欄式建物」の家形埴輪が出土している。
なぜ、遠くはなれた中国雲南省と日本の地で、同じ形式の建物が見られるのか。
日本では香川県出土銅鐸の絵画や奈良県左味田宝塚古墳出土の家屋文鏡に描かれている絵画、池上曽根遺跡の大形建物の復元、登呂遺跡復元高倉など日本の弥生時代の家は「干欄式建物」である。
それに対し、中国の雲南省の家の例がある。
更に中国以外の国にの「干欄式建物」の下記の例。
(1)雲南の哈尼(はに)族の家の、屋根の棟木の両端を飾る木彫りの牛の頭
(2)権威の象徴であるケチのあがった家(インド東北部、アッサム地方のナガランド)
(3)中国の南西部、雲南省にすむ少数民族タイ族の高床式住居
(4)タイのアカ族の一般の千木
(5)タイのラワ族の花紋のある千木
などである。
高床式住居、干欄式建築も、かつては、中国の江南地方で広く行なわれていたようである。建築史家の宮本長二郎氏はのべている。
「日本の縄文時代早期にあたる7000年程(ほど)前の中国浙江(せっこう)省の二つの遺跡から高床建築の部材が発見された。余姚(よよう)県河姆渡(かぼと)遺跡と桐郷(とうごう)県羅家角(らかかく)遺跡である。」
「(河姆渡遺跡の)堀立柱の干欄式(高床)建築はかなり高度な水準を保っていたことを示している。」(以上、宮本長二郎「長江流域から米作りとともに普及」[『日本文化起源論』学習研究社、1990年刊、所収」による。)
(下図はクリックすると大きくなります)

(下図はクリックすると大きくなります)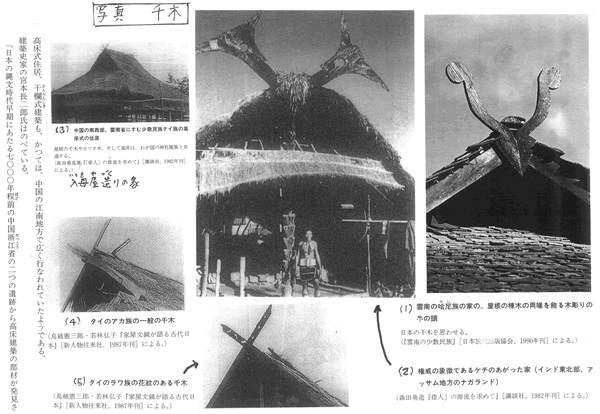
高床式住居については、佐々木高明も、つぎのようにのべている。
「国立民族学博物館名誉教授の周達生(しゅうたっせい)氏によると、かつては長江をはさんで北側の地床式(地面を床にした形式)住居に対し、その南側には高床式の住居が広く分布していたことが明らかになっている。現在では、雲南省の一部など、西南中国の一隅に押しやられた形で残存している高床式の住居が、かつては長江以南の照葉樹林帯に広く分布していたようである。」(佐々木高明著『照葉樹林文化とは何か』[中央公論社、中公新書、2007年刊])
「高倉は雲南から江南地方にひろく分布し、しかも朝鮮半島ではその遺跡が発見されていない。したがって、高床の穀倉は長江下流域あるいは江南地方から直接、水田稲作技術とともに日本列島へ伝来したと考えられる。」[佐々木高明著『日本誕生』(集英社、1991年刊)]
石寨山古墓出土の青銅製の家は、横からみたとき、屋根が上にひろがっているようにみえる[上の「写真(1)中国・雲南省石寨山」参照]。このような特徴のある家の形は、どこかでみたような記憶があるであろう。
そう、わが国の銅鐸や鏡の上に、これに似た形の家が描かれている。また、似たような形をした家形埴輪が出土している。
このようなタイプの建物は、「干欄式建物」による建物である。(「干欄」は「欄干」と同じで、「てすり」のこと。)
「干欄式建築」については、『世界考古学事典、上』(平凡社、1979年刊)に、つぎのように説明されている。
・干欄式建築(かんらんしきけんちく)について
中国の古典に記載されている高床式建築 新石器時代以後現代にいたるまで、長江流域および江南の諸地域、東南アジア、日本などに広く分布している。《梁書》林邑国伝(りんゆうこくでん)、《北史》蛮獠伝(ばんろうでん)《唐書》南蛮伝などに、干蘭・干欄・高欄・閣欄、葛欄の用語がみられるが、その建築様式を示すと考えられるいくつかの遺物が知られる。雲南石寨山(せきさいざん)出土の青銅製貯貝器(ちょばいき)[宝物または貨幣とされた子安貝をいれる容器]蓋(ふた)上にみられる建造物は、長方形の高床式建築で、壁はなく、二本の円柱が切妻造りの屋根を支え、前端に梯子が付く。広東・広西・湖南・四川・貴州省などの後漢墓からは、高床式建築の明器(めいき)[墓の中に埋めるために特製した器物]が出土する。干欄式建築を描いた画象としては、石寨山出土の貯貝器の腰部(胴体の曲った部分)画象や、日本の香川県発見とされる銅鐸の画象、奈良県佐味田宝塚古墳出土の家屋文鏡の高床式建築の例が知られる。湖北省圻春県(きしゅんけん)毛家嘴(もうかすい)の西周の遺跡では、二列または三列に配列された柱、木板、木製梯子を有する高床建築の遺構が発見されている。日本においても静岡県登呂遺跡で高床式建築址と考えられる遺構が発見されている。[文献 安志敏(あんしびん)(『考古学報』1963-2)。(飯島武次)]
「干欄式建築」ということばを、広く「高床式建築」一般の意味で用いているようにみえる論文もある。
しかし、論文「”干欄”式建築的考古研究」(『考古学報』1963年第2期)をあらわした安志敏氏は、「干欄式建築の基本特徴」としてつぎのようなものをあげている。
①「長脊短檐(ちょうせきたんえん)[長い脊(せ)、短い檐(ひさし)」の屋頂。
②大きな柱を土中にうちこんでたて、高床にする[摏柱的底架(とうちゅうてきていか)]。
そして、安志敏氏は、これらは濃厚に、地域的色彩をもち、黄河流域の建築と、風格が異なっているとのべている。
安志敏氏はいう。
「周や漢の時期いたって、この種の建築様式は、長江流域およびそれ以南の地区のいくつかの地点の建築において、なお、一定ていど保持された。中原文化のたえざる影響によって、しだいに改変され焼失していったものである。」
安志敏氏は、また、つぎのようにものべる。
「干欄式建築は、湿潤な沼沢地区に適している。」
■倭人の鵜飼(うかい)
・中国での鵜飼の分布
慶應義塾大学名誉教授の可児弘明(かにひろあき)氏の著書、『鵜飼』(中央公論社、中公新書、1966年刊)に、中国での鵜飼の分布図がのっている。
下図のようなものである。
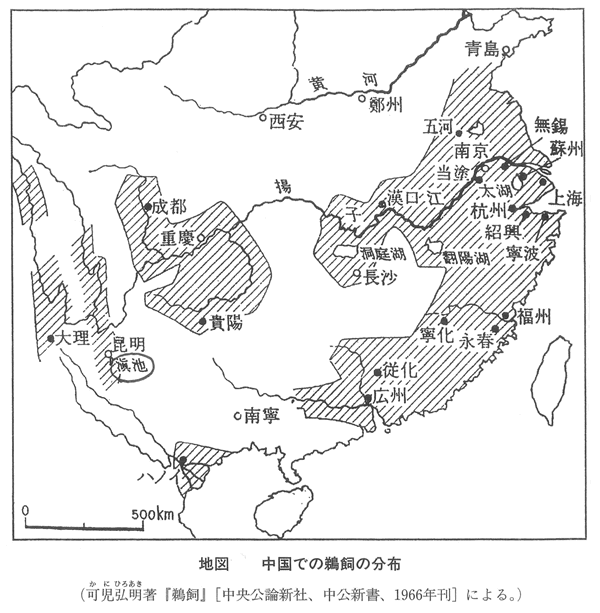
地図をみると、「倭人の家」でのべた「干欄式建物」の青銅器の出土した雲南省昆明の近くの滇池(てんち)の付近も、鵜飼の分布域のなかにはいっていることがわかる。
可児弘明氏は、『鵜飼』のなかでのべている。
「鵜飼の歴史的慣行地のひろがりは、原住民国家のうち楚の国と、それに文化的に密接な関係をもつ故地とよく合致している。楚の国は今の湖南、湖北に中心のあった国家であるが、戦国時代(前475~前221)、あるいはそれ以前における楚の文化は四川・雲南方面の土着文化と密接な関係をもち、さらに四川・雲南の土着文化は、広東・広西の土着文化とつながるからである。」
「中国で鵜飼にたずさわるのは、中国人ばかりでなく、中国西部の少数民族、たとえばロロ族がある。
このことがわかったのは、1900年、雲南から金沙江(揚子江上流)をこえて四川に入った英人デービスが独立ロロ族の住む建昌渓谷を踏査し、ウをつれた漁夫の写真を記録してくれたおかげである。」
「華南と日本の稲作地帯にかぎってみると、鵜飼ががんらい、私たちにはまだ未知の、ある稲作民族の文化複合につながる可能性を強く予測することができるのである。」
昆明の近くの滇池(てんち)ふきんの石寨山の、「干欄式建物(かんらんしきたてもの)」については、すでに、前の「倭人の家」においてのべた。そして、石寨山ふきんの滇王国の文化のにない手が、ロロ族である可能性がある。
かりに、「鵜飼」と「干欄式建物」とが、可児弘明氏のいう「ある稲作民族の文化複合」につながるものであるとしよう。すると、石寨山古墓は、前漢の初期から後漢の初期、つまり、紀元前202年ごろから紀元後100年ごろには、その文化複合が、蜀の地の石寨山ふきんまで、およんでいたことを示していることになる。
・わが国での鵜飼
山口県下関市の土井ヶ浜(どいがはま)遺跡(弥生時代の前期・中期を主体)から、総数243体にのぼる遺存状態良好な弥生人骨が発見された。
そのなかに、鵜を抱いている女性の人骨が出土している(写真)。鉄製品が、副葬されていた。

土井ヶ浜一帯には、現在でも、鵜が群れているということから、この鵜が、たまたま、とらえられたものか、鵜飼のために飼われていたものであるかは、わからない。
鵜は魚食の鳥なので、鵜そのものの肉はくさくて、食用に適さないという。
『古事記』の「神武天皇記」には、奈良県の吉野川の下流で、神武天皇軍が贄持(にえもつ)の子という国つ神(くにつかみ)と出あうが、この贄持の子は、鵜飼部(うかいべ)の祖先とされている。
また、『古事記』の「神武天皇記」には、神武天皇軍が「鵜飼で漁をする人々よ、助けに来てほしい」という歌もみえる。
さらに、『隋書』の「倭国伝」に、わが国の七世紀ごろの鵜飼のことを記した記事がみえる。
すなわち、つぎのような記事である。
「首に小さい輪をかけて、ひもをつけた鵜を水にもぐらせて、魚を捕らえさせる。一日に、百余匹もとる。[小環(しょうかん)をもって、鸕鷀(ろじ)のうじなに挂(か)け、水に入りて魚を捕らえしめ、日に百余頭を得(う)。]」
八世紀成立の『万葉集』では、鵜飼のことが、かなり多く歌われている。
『万葉集』の4011番の歌で、越中の国(現在の富山県)の鵜飼たちのことが歌われている。4156番にも、富山県の辟田(さきた)の川で、「鵜飼をする歌」がのっている。
4185番にも、「鮎が躍るころになったら、辟田川(さきたがわ)で、鵜をいっぱい使って川瀬を探って行こう。」という意味の歌がある。
4187番の歌にも、福井県の叔羅川(しくらがわ)の「早瀬で、鵜をもぐらせて」とある。なお、可児弘明氏は、さきの『鵜飼』のなかで、「朝鮮半島に鵜飼がひろまった痕跡はみつからない」と記している。
・照葉樹林文化と重なりあう
以上のようにみてくるとき、思いおこされるのは、「照葉樹林文化」という文化概念である。
照葉樹林というのは、カシ、シイ、クスノキ、ツバキ、サザンカなどを代表する常緑広葉樹を主とする樹林である。さきのような照葉樹では、葉が比較的厚く、テラテラとした光沢がある。
照葉樹林文化は、共通の文化的要素によって特徴づけられる。
イモ類、アワ、ヒエ、キビなどの雑穀類の栽培、稲作、絹の製造などを大きな特徴とする。モチやナットウ、スシを食べ、絹や、漆(うるし)を利用する。麹(こうじ)で酒をつくり、高床の家にすむ。歌垣(うたがき)や鵜飼の習俗がある。
照葉樹林文化は、ヒマラヤ山麓から東南アジア北部山地、南中国、日本西部にかけての東アジアの温暖帯に分布する。
国立民族学博物館の館長などであった佐々木高明は、その著『照葉樹林文化とは何か』(中央公論新社、中公新書、2007年刊)のなかで、「照葉樹林文化のセンターと想定される地帯」として、地図のような「東亜半月孤」を示している。
佐々木高明によれば、この「東亜半月孤」は、「雲南高地を中心に、ブータン・アッサムから中国の湖南省に至る。」という。
下の地図をみれば、石寨山の近くの昆明などが、「東亜半月孤」の、ばぼ中心の位置にあることがわかる。
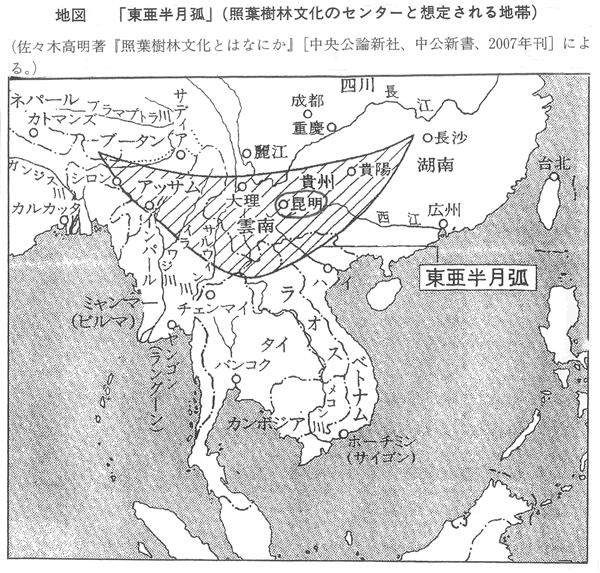
佐々木高明は、また、同じ著書で、「照葉樹林帯の拡がり」として、下の地図も示している。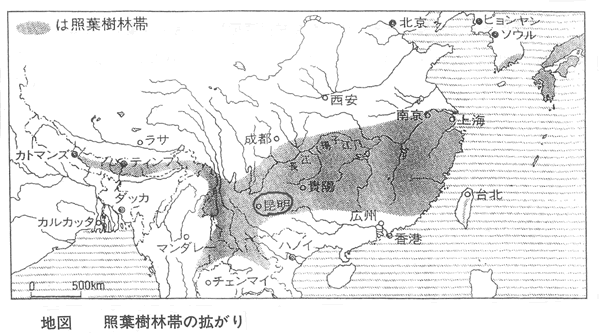
なお、『後漢書』の「西南夷伝」を読むと、つぎのような表現がある。
「[日南(現在のヴェトナム領)の南の黄支国(こうしこく)では、]長幼の別なく、項髻徒跣(こうけいとせん)し[髻(もとどり)を項(うなじ)のうえにつくり、はだしで)、布をもって頭に貫いて、これを著(き)る。」
「[哀牢(あいろう)の夷人(現在の、雲南省西南部地方に国をたてていた民族)の邑(むら)の豪(かしら)は、]歳ごとに、貫頭衣二領などをさしだしそれを賦(みつぎもの)とした。」
これは、『魏志倭人伝』に、「(倭人の)作った衣は一枚の布のようで、その中をうがち(まん中に穴をあけて)頭をつらぬいてこれを衣(き)る(中央貫頭衣)。」と、いわゆる「貫頭衣」のことが記されているのと通じている。
・ナレズシやナットウの分布
『文化人類学辞典』(弘文堂、1987年刊)の、「すし鮓」の項に、下の地図のような、ナレズシの分布図がのっている。
(下図はクリックすると大きくなります)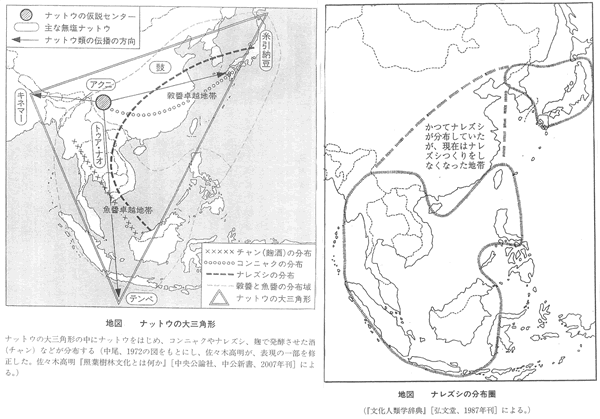
「ナレズシ」は、現在の、握り鮨の原型といえるものである。「ナレズシ」については、佐々木高明著『日本史誕生』(集英社、1991年刊)に、つぎのように要領よく説明されている。
「スシのもっとも古い形はナレズシとよばれるもので、魚を開いて軽く塩をしたのち、炊いたり、蒸したりした米の上に置き、魚肉(獣肉でもよい)と米とを桶(おけ)や甕(かめ)の中に交互に積み重ね、漬け込んだものである。いく日かすると米が乳酸発酵するのですっぱくなるが、その乳酸菌で他の雑菌の発生が抑制されるので、魚肉(獣肉)をかなり長期に保存できる。このようなナレズシは、いまもわが国では琵琶(びわ)湖畔などでつくられるフナズシに、その姿をよく留めているが、実はきわめて古い食品なのである。
たとえば中国の三世紀ごろの古い辞書の中には、長江より南の江南の地にナレズシがひろく存在していたことが記されているし、現在でも、湖南省、貴州省や雲南省の少数民族、特に苗(ミャオ)族や侗(トン)族などのもとではナレズシが日常的につくられている。1980年の秋、私も貴州省台拱県施洞区の苗族の村でナレズシをたくさん御馳走になったことがある。十三世紀ごろ以後、中国人(漢族)の中では失われてしまった古い食習慣が、少数民族の中でよく保持されてきたということができる。いずれにしてもナレズシは大へん古い食品である。おそらく、それは稲作農業とともに長江の下流あたりから、九州へ伝わったものと考えられている。
現代、日本の食文化を代表するスシは、国際化の波にのってアメリカやヨーロッパに輸出され、人気を博しているが、その握り鮨の伝統はせいぜい近世(江戸時代)後期ごろにまで遡りうるにすぎない。」
このように、「ナレズシ」は、かつては、日本から中国の江南、そして、雲南省の少数民族へと、大略、照葉樹林帯にそう形で、あるていど連続的に分布していたとみられる。しかし、前の地図をみれば、照葉樹林帯の外周部へと、波紋のようにひろがっていって分布しているようにみえる。「上に長く、下に短い弓」なども、かつては、ユーラシア大陸東南部で行なわれていたものが、もとの地では失われ、「ナレズシ」の分布圏にあるていど重なる形で、細々と存在しているのではないか。
・『魏志倭人伝』の風俗記事が、南方的である
東京大学の民族学者、大林太良(たりょう)の労作『邪馬台国-入墨とポンチョと卑弥呼-』(中公新書)において、『魏志倭人伝』の風俗記事が、南方的であることを、ややくわしくのべている。『魏志倭人伝』には、わが国の、弥生時代後期の風俗習慣が記されている。大林太良は、「倭人の文化は《北方的》要素が少なく、圧倒的に《南方的》要素からなっていた」として、つぎのようにのべる。
「『魏志倭人伝』に描きだされた倭人の文化は圧倒的に南方的であって、中国南部から東南アジアにかけての文化、ことに江南の古文化と密接な親縁関係をもっている。」
「倭人伝に現れた服装が、採集狩猟民的な文化に遡る可能性は少なく、農耕とともに、おそらく弥生時代あるいは縄文後・晩期ごろから、中国の中・南部から入ってきたと考えるのがよいと思われる。」
「倭人の生活様式に関する記事の大部分は、華南から東南アジアに類例をもつものだ。このことは、すでに『魏志』を書いた陳寿自身が注目し、『有無する所、憺耳(たんじ)朱崖と同じ』と述べて、海南島との生物・文化の類似を強調している。」
「東夷伝の諸民族のなかで、倭人だけが著しく江南的・東南アジア的な習俗をもっていると描きだされている。」
大林太良は、「水中の動物からの危害を受けるのを防ぐ」という目的のために入墨をする習俗は、中国南部、ことに、江南の地を中心に、東は倭人から、西はラオスに至る地域に、ほぼ連続的に分布していること、貫頭衣、つまりポンチョ式の服装は、北方ユーラシア東部にはほとんど知られておらず、中国南部から東南アジアにかけての地域に多いこと、横幅衣も、東南アジア的な服装であること、などを指摘する。
・日本語の語彙が、南方的要素をもつこと
日本語の「私は、本を、読む。」などの語順は、北方的特徴をもつのにたいし、語彙は南方の諸言語と親近性をしめす(これについてくわしくは、拙著『研究史 日本語の起源』「2009年刊」、参照)。計量言語学的な方法で、言語と言語との近さの度合を、数字で測定してみると、つぎのようなことがわかる。
日本語は、インドネシア語、カンボジア語、台湾の高砂族のアミ語やパイワン語、ビルマ系の諸言語など南方的な諸言語と、「基礎語彙」において、確率論的に、しばしば、偶然以上の一致をしめす。
これに対し、朝鮮語、アイヌ語は、南方的な諸言語と、「基礎語彙」において、偶然以上の一致を示さない。日本語、朝鮮語、アイヌ語の三つの言語の「基礎語彙」は、確率論的に、相互に偶然とはいえない関係を示しながら、このうちの日本語の「基礎語彙」だけが、南方の諸言語とも親近性をもつ。
これは、「東夷伝の諸民族のなかで、倭人だけが著しく江南的・東南アジア的な習俗をもって描きだされている」ことと、軌を一にしている。
とくに、「ビルマ系の諸言語」のなかには、日本語の身体語とかなり近い形をしているものを、多数ふくんでいるような言語がある。
(下図はクリックすると大きくなります)
上の表は、グリアソン監修の『インド言語調査(Linguistic Survey of India)』により、インド北東のアッサム州の、ヒマラヤ山脈東端の南麓、ミャンマーの北西、ブータンの東の、ナガランド付近の「ビルマ系諸言語」(下の地図参照)のなかのいくつかの言語の身体語と、日本語の身体語とを比較したものである(グリアソンの『インド言語調査』には、身体語は、十二語とりあげられている。ここでとりあげた身体語は、グリアソンのとりあげているものにあわせた)。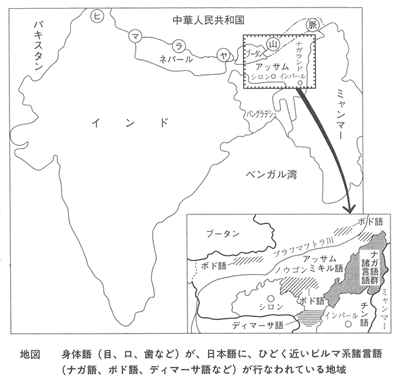
「ビルマ系諸言語」のなかの、「ボド語群」の身体語では、日本語、あるいは琉球語と、十二語のうち、六~九個までの語頭の音が一致する。確率計算を行なえば、この一致率は、偶然による一致の範囲をこえる。
同一系統の言語では、むかしの音が変化しないでのこる傾向は、とくに、単語の語頭の音においていちじるしい。
「ボド語群」の言語と「日本語」との身体語の語頭の音の一致の度合は、「英語」と「フランス語」との一致の度合よりも、「英語」と「ドイツ語」との一致の度合に近い。
「ビルマ系諸言語」のなかには、「歯(tooth)」が日本語と同じく、「hā」であるものも多い(「クキ・チン語群」では、「tooth」はだいたい「hā」である。「hā」は、「はー」であるが、「日本語」でも、沖縄の「首里方言」では、表に示したように、「はー」である。「ボド語群」のなかには、「hair」が、「kamai」であるものもある。これは、「日本語」の「かみ」に近い。また、「舌 tongue」が、「sila」であるものもある)。
「ビルマ系諸言語」のなかには、身体語ばかりでなく、数詞や代名詞、植物関係の語などにおいても、「日本語」と偶然以上の一致を示すものがある。
ところが、身体語、数詞、代名詞、植物関係以外の基礎語彙(たとえば、「水」とか「雲」など)においては、それほどよく一致していない。この点、英語とドイツ語とが、一般の基礎語彙においても、よく一致しているのと異なっている。
身体語、数詞には、若干文化的な色彩かあるが、どちらかといえば、基礎語彙のなかでも、文化的な色彩をもつ語彙においては、日本語と比較的よく一致する言語を、「ビルマ系諸言語」のなかに見いだすことができる。
ヒマラヤ山脈から、ネパール、ブータン、中国南部を通って、九州、四国、本州南半部などに続く地域が、いわゆる照葉樹林帯に属し、栽培植物や文化において共通性のあることは、植物学者、中尾佐助の『栽培植物と農耕の起源』(岩波新書、1966年刊)にくわしい。これらの地域は、揚子江流域と、揚子江の延長上とにある。
いまから二千数百年まえ以前には、揚子江以南、あるいは、その流域には、漢民族以外の多くの民族が存在していた。そこでは、ベトナム族、ビルマ族など、現在の中華人民共和国の外につながる民族が、かなり勢力をふるっていた可能性は大きい。
揚子江の下流地方から南の地は、むかしの呉・越の地であった。紀元前五世紀から、紀元前四世紀にかけて、呉・越が滅亡した。戦国時代から、呉・越の戦いのころ、中国南部の非漢民族のあいだで、大きな動揺がおこり、戦火などをのがれて、揚子江下流域地方から日本列島に渡来したものがあったとみられる。また、日本列島に渡来した民族と関係のある民族で、揚子江をさかのぼり、ヒマラヤの方面にのがれたものもあったとみられる。ビルマ系諸言語のなかに、身体語などにおいて、日本語と偶然以上の一致のみられる言語があるのは、その上うな理由にもとづくとみられる。
ビルマ系江南語の日本列島への渡来は、いまから二千数百年まえていどの、比較的近い時期であったと考えられる。
そのように考えられる理由は、つぎのとおりである。
第一に、日本語とビルマ系の「ボド語群」「ナガ語群」「クキ・チン語群」などの、身体語の近さの度合は、英語とドイツ語との身体語の近さの度合に近いことである。そして、英語とドイツ語との分裂の時期は、今から約二千年ていどまえである。おなじインド・ヨーロッパ語族に属する言語でも、英語の身体語とフランス語の身体語とは、かなり異なっている。関係のある言語のばあいでも、長い年月のあいだには、身体語が異なった形になる。日本語とビルマ系諸言語との身体語の近さの度合は、日本語にたいするビルマ系の言語の関与の時期が、それほど遠い昔ではなかったことを示している。
第二に、ふつうの日本語の基礎語は、「やま」「かわ」「とり」など、二音節の語が多いのに、身体語には、「め(目)」「は(歯)」「て(手)」「け(毛)」など、一音節のものが多いことである。「みみ」「ほほ」「もも」なども、「おめめ」「おてて」などというのと同じく、本来は一音節語であったものが、一音節では、日本語として発音しにくいため、音をかさねて、二音節語にしたのではないかと疑われる形をしている。
ほとんどの単語が、一音節からなる言語は、中国語、ビルマ語、タイ語、ベトナム語、チベット語など、大陸に広くひろがっている。
「め(芽)」「ね(根)」「は(葉)」「ほ(穂)」など、やはり一音節語が多い植物関係の語や、身体語、数詞、代名詞などは、どうやら、中国南方の一音節語の地域からもたらされたもののようである。
これらの語は、「やま」「かわ」「とり」などのふつうの日本語の基礎語彙のうえに、ちょうど、油が水に浮くように浮かんでいる。ビルマ系の言語からもたらされた語彙は、なお、日本語のなかに、十分うまく溶けこんでいないように思われる。このようなことも、ビルマ系の言語が日本列島にわたってきた時期は、それほど古くないことを示していると思われる。
ビルマ系江南語は、おそらく、その人口は、かならずしも多くなかったであろうが、稲作などをともなう文化的優位性のゆえに、そして、おそらくは、政治的な優位性のゆえに、基礎語彙のうちの、より文化的な部分をもたらしたと考えられる。
ビルマ系江南語は、おそらくは、はじめ、北九州に上陸したであろう。そして、すでに北九州に存在していた朝鮮語祖語との関連をもっていた古極東アジア語の系統をひく言語(原倭人語)とむすびつき、日本語祖語(倭人語)を形成したと考えられる。
おそらく、稲作がかなりなていど行なわれ、生産性があるていど高くなった段階で、江南方面から来て、租税制度と国家概念をもたらし、支配勢力となった勢力があったのであろう。
基礎語彙のなかでも基礎的なものとみられる身体語への影響は、そのことをうかがわせる。
もし、倭が呉の太伯の子孫であったとすれば、それは、倭人の全体がそうであったという意味ではなく、支配者階級がそうであったという意味であろう。
なお、現在でも、ビルマ系諸言語の基本的な語順は、日本語などと同じく、「私・本・読む」式の語順である。
ビルマ系諸言語は、語順などからいって、「原倭人語」と結びつきやすい面があったとみられる。
・弥生文化成立期の、倭人の為政者の言語・文化は、長江流域からきた
成立期の倭人の為政者の言語・文化は、長江(揚子江)流域諸語、および、長江流域文化と結びついている。
それにくらべ、朝鮮(韓)民族の言語・文化は、長江(揚子江)流域諸語、および、長江流域文化の影響は、ほとんどみとめられない。
干欄式建築、高床式建築、千木、カツオ木などは、現在も、神社建築の様式として残る。これは、倭人の為政者の宮殿や庫などの建築様式であった。
その建築様式は、長江の延長上に、日本と、遠くはなれたヒマラヤ山脈のふもとまでに残る。
おそらくは、長江流域の、呉・越・楚などが滅亡する動乱のさいに、長江の延長づたいに、日本列島にわたってきた人々と、長江を、そのはてのほうまでさかのばった人たちがいたのであろう。かくて、長江のほとんど両端の延長上の地に、共通の文化、共通の言語の影響が、残ることとなった。
鵜飼や歌垣の文化なども、同じく、長江の流域と、その延長上に残ることとなった。
『魏志倭人伝』に記されている租税制度(租賦をおさむ)なども、おそらくは、呉・越・楚などの長江流域国家からもたらされたものであろう。
長江流域文化は、また、稲作文化と重なりあうものであり、それが、わが国における弥生文化の成立、倭語(日本語祖語)の成立と結びつくものであるとみられる。
日本語祖語においては、ビルマ系諸語(ボド語・ナガ語)、インドネシア系諸語、クメール系言法(カンボジア語)などの影響がみとめられる。このうち、ビルマ系諸語は、現在、長江上流、および、その延長上に分布する。おそらく、かつては、長江下流地域にも存在したのであろう。
ビルマ系諸語は、とくに、その身体関係語において、日本語とかなり強い関係がみとめられる。おそらく、この言語が、長江流域の言語のなかでは、もっとも新しく、日本語の成立に影響したものであろう。
成立期の、日本語文化、弥生文化の為政者の文化と結びつくものではないか。
インドネシア系諸語は、現在、太平洋東南諸島に多くは分布するが、かつては、中国の南部地域に存在したとみられる。現在でも、インドネシア諸語の一つであるチャム語は、ベトナムの奥地やカンボジアなどに存在する。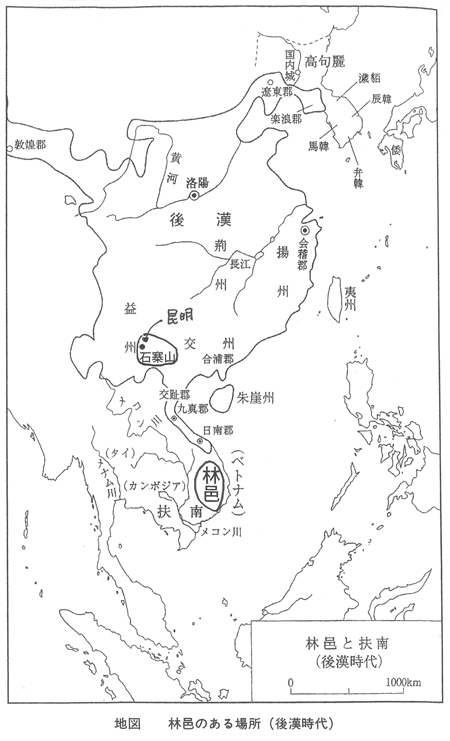
・「林邑(りんゆう)国伝」のなかの「干欄式建築」についての記事
なお、『梁書』の「諸夷伝」のなかの「林邑国伝」に、干欄式建築について、つぎのように記されている。
「その国の(風)俗では、居処に、閣をつくり、名づけて干欄(かんらん)という。門戸をみな北にむける。」
西暦二世紀の末のことである。インドシナ半島の東南海岸地域にチャム(cham)といわれる種族が国家をたて、チャンパと称した。
中国では、この国のことを林邑(りんゆう)と呼んだ(右の地図参照)。
チャム族は、オーストロネシア語派のインドネシア語派の言語を用いた。つまり、インドネシア系言語を用いる人たちが、インドシナ半島にいたのである。現在、太平洋上にひろくひろがるインドネシア、ポリネシアの民の原郷が、中国の南部や、インドシナ半島であることを思わせる事実があるのである。
・弥生文化の南方方面的要素は、いつ、どこから、どのようなルートできたことになるのか。
石包丁は、稲の穂をとるだけのものではない粟(あわ)にも使う。
弥生文化の基本的南方性
これら、農学者の南方伝来性説に対して、考古学者は水稲の朝鮮半島からの伝来説を主張する。
寺沢薫著『王権誕生』(講談社、2000年刊)
「縄文晩期後葉、玄界灘沿岸地域に最初に伝来した水田稲作が、おもに朝鮮半島南部から渡来した人々によってもたらされたことは間違いない。つまり朝鮮半島から北九州に来たルートだ。こと最初の水稲に関する限り、他のルートは可能性が薄いといってよかろう。」
「朝鮮半島南部こそが弥生農業の直接の故郷だと断定する理由である。」
石包丁の形式から農耕の伝来ルートをさぐる。北部九州に伝わった水稲と石包丁の関係の下図。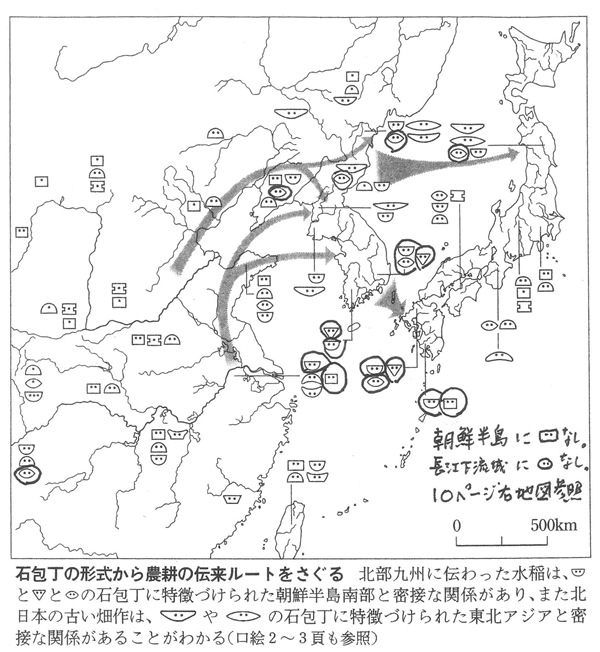
注:石庖丁(いしぼうちょう) [『図説考古学辞典』水野清一・小林行雄編、東京創元社1959年刊]
磨製石器の一種。長方形、楕円形、または半月形を呈する扁平な石器で、一方の長辺に刃がついている。体の中心部に2個または1個の穿孔があって,これに紐をとおして指にかけ,穀物の穂をつむに用いる。石庖丁の名は。明治時代にエスキモーのウーマンズ・ナイフとの比較によって、調理用の庖丁と誤認したときの命名で、そのまま今日も慣用されている。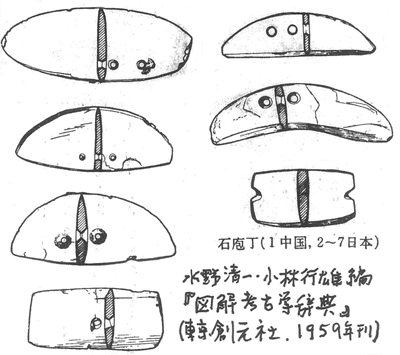
・「直接伝来」説と「海上の道」説
寺澤氏は更に述べる。ここで、直接伝来ルートについて少しふれておこう。考古学者のなかには、外湾刃半月形(がいわんばはんげつけい)石包丁や抉入(えぐりい)り柱状片刃石斧(ちゅうじょうかたはせきふ)を、長江下流域に起源するものだと考える人もいる。たしかに、長江下流域にもこの型式のものはある。しかし、長江下流域の前一千年紀の湖熟(フーシュ)文化の石包丁には、外湾刃半月形のほかに、
内湾刃半月形、舟形、長方形、翼形とじつに多様な形式があり、直接伝来したのであればこうした形式も一緒にもたらされるはずだが、北部九州では発見されていない。
また、湖熟文化の水稲農耕には、収穫具として多数の石鎌や貝製の鎌、耕作のための石犂(いしすき)や除草のための転田(うんでん)器、そして青銅や鉄製の鎌、鋤(すき)、犂(すき)もすでに存在するけれど、そうした農具も北部九州には見られない。今のところ直接伝来説は、海流による伝来の容易さやイネの生育環境の類縁性、といった推察の域をでるものではない。
このように、朝鮮半島を北から南に降りて、日本に伝わったとしていて、直接江南から日本に伝わったことの可能性の低さを示している。
この稲作は朝鮮半島を北から南に降りて日本伝わったする説に対し、前述した稲作は江南から直接日本に伝わったとする説があるが、補足として下記の徐福伝承と呉越の話を加える。
・徐福伝説は何を物語るか(池橋宏『稲作の起源』講談社、2005年刊)
さてここに登場するのが、不老不死の術を行う「方士(ほうし)」、徐福(じょふく)という人物である。以下は、伊藤清司の「呉越文化の流れ」を参考にして、その話を紹介する。『史記』によると、始皇帝はかれと山東で出会い、東方海上にある蓬莱(ほうらい)など神仙(しんせん)の住む島の話を聞いた。そこで不老不死の薬を手に入れるために、徐福に命じて数千人の童男童女を率いてそこへ向かわせた。徐福の話は『史記』の別のところにもあり、最初蓬莱を目指して出発したが、失敗し、二度目に皇帝に謁見して三千人の童男女と百工(技術者集団)をつれ、五穀の種子を携えて出発したとなっている。別のところには、徐福は、「平原広沢を得て止まり、王となりて来たらず」とあるという。さらに、『後漢書』の「東夷伝」には、「徐福は、誅罰(ちゅうばつ)を畏(おそ)れて敢(あ)えて帰らず、ついにこの州に止まり、世々相承(あいう)けて数万戸あり、人民時に会稽にいたりあきないす」となっている。会稽はかつての越の都で、越人の本拠地であったことを考えると、なにか意味がありそうである。
その後、前漢と後漢の約420年を経て、『三国志』の時代の呉の記録、「呉志」の「孫権伝」にも、孫権が大部隊をのせた軍船を、徐福の子孫のいるといわれる島に派遣したという。また、徐福について、日本各地に伝説が残っているが、それらははるか後世の作である。それでも、中国の史書に基づく日本の学者の考察によると、「徐福が平原広沢を得て止まり、王となりて来たらず」の記事はある程度信頼性があるかもしれないという。
徐福の伝説に関する長い記述の一部をここに紹介したのは、この話が、稲作の伝来の状況を想像する資料となるからである。伝説であるにしても、技術者集団をつれ、五穀の種子を持って、さらに大勢の児童を連れて、大挙して渡航したというところは示唆に富む。五穀とは、コメ、ムギ、アワ、マメ、キビあるいはヒエといわれている。移住のためにはそういうものが必要と考えられていたのであろう。水田稲作が灌慨網を要する組織的なものであることを考えれば、その伝来には、徐福伝説の物語るように、技術者集団と五穀の種子の準備があったことは当然である。紀元前330年ごろ、敗亡した越の人々は、海上に逃れ「江南の海の浜で暮らした」と記録されているが、徐福の話はそれから100年余り後のことだから、集団移住のことは人々の記憶に残っていたはずである。それが徐福の話のもとにあったのではないだろうか。」
水田稲作の日本への伝来に関連して、中国の戦国時代末期の社会の動乱、紀元前四世紀の越の敗亡から、その水田稲作民の逃避、その一部の日本への渡来という説は注目すべきである。越と日本古代の関係を最初にまとまったかたちで指摘したのは、国際的に活躍した民俗学者の岡正雄(おかまさお)である。
岡は、春秋時代以降の呉・越の抗争期そして越の敗亡期に、江南の民が難を逃れるため、その一部が東シナ海を渡って日本列島に移り、それが、日本の弥生文化の形成に大きいく関与しているのではないかという構想を提出した。古代稲作史を研究した農学者の安藤広太郎はそれより早く『稲の日本史』(1951)の中で同様の見方をしている。中国の歴史と地理、それに稲作の歴史を考えてきた者には、この指摘は今でも新鮮であると思う。(池橋宏『稲作の起源』)
民俗学者には長江流域からの稲作民の渡来を強く指摘する傾向がある。石毛直道(いしげなおみち)は、考古学的遺物としての収穫用石包丁、特に穂刈り用の半月形外彎刀は、長江下流、南朝鮮、北九州にしか分布していないとし、これによって江南渡来説を支持した。考古学的証拠として佐原が指摘したように、高床式倉庫などが長江流域から伝播した可能性を見る必要があろう。民俗学的な調査を重ねた考古学者の国分直一(こくぶなおいち)も江南の稲作民の渡来の可能性をみている。民俗学者の諏訪春雄(すわはるお)『稲を運んだ人びと』という論文(1996)を書いてて、中国の古代稲作遺跡と日本への稲作の渡来を論議し、彭頭山遺跡に見られるように長江流域で栄えた水田稲作が、長江下流域から九州へ海流に乗って渡来した可能性を論じている。
・越の敗亡と弥生稲作の始まり
以上、中国の戦国時代の動乱と越の敗亡が、越の南部への移動をもたらし、またその一部が日本にも渡来したのであろうという、岡正雄や安藤広太郎の説明を紹介した。それの背景としては中国の長江下流域の、呉と越という国の状況を説明しなければならない。
伊藤清司(いとうきよし)の『呉越文化の流れ』(1986)という解説によると、呉越の人びとは独特の習俗や文化をもっていたが、海上交通の可能性についても、優れた船を持ち、潜水漁業にも長けていたことが指摘される。歴史書によれば、紀元前485年に呉の大夫徐承(じょしょう)が水軍を率いて山東半島の斉を攻めた。また、越王勾践は紀元前473年に呉を滅ぼした。
また彼の決死隊8000人、軍船300艘を指揮して山東半島の琅邪(ろうや)[青島付近]に打ってでた。越の全盛の時代である。前にも触れたが、越は楚によって紀元前334年に滅ぼされた。この敗北をきっかけに、本拠地からは逃れて、会稽から北部ベトナムまで、百越といわれる、大小の越の種族の国々が散らばった。そのことは、『閩越国(いまの福建省)』、『南越国(いまの広東)』や『越南(ベトナム)』という名前にも刻まれている。さらに紀元前221年、戦国時代末に秦の始皇帝が中国を統一したが、始皇帝はいくども華南に軍隊を派遣した。そのあとを継ぐ漢帝国に対して、呉や楚の住民は、呉楚七国の反乱(紀元前154)を起こした。漢は江淮(こうわい)の低湿地へ越人を強制移住させた(紀元前138)。
呉や越の住民と北方系の漢人の争いは容易なものではなかったのである。
敗亡した越の人々は、「江南の海の浜で暮らした」といわれるが、実際に閩越国、南越国、越南など、越人のいくつかの王国の中心は、いずれも大きな入江か湾に大河が河口を開いているところを少しさかのばったところにあった。そしてそこに高度の文化を築いた。船で移動する越人はこうした地形に着目し、河川に沿って水田稲作を展開した。朝鮮半島西岸にもそうした適地がある。また日本でも博多湾(その奥に板付遺跡がある)や、有明海(ありあけかい)に注ぐ筑後川(ちくごがわ)、それに島根半島の宍道湖(しんじこ)や中海(なかうみ)に連なる河川などが、越人好みの適地であっただろう。
最後に整理のため寺沢、池上、両氏の主張を並記する。
寺沢薫氏の主張
朝鮮半島出土のコメは日本列島同様、すべて短粒米(多くはジャポニカ種)といわれるコメで、新昌洞遺跡で見つかった炭化米はDNA分析でもジャポニカ種と太鼓判を押された。イネの品種でもⅡのルートは支持される。ちなみに、イネには大別二つの品種群がある。粘り気があり丸みをもった短粒米がジャポニカ、粒が細長く粘り気がなくパサついた長粒米がインディカと呼ばれる亜種である。少し年輩の方なら、内地米と外米と言ったほうがわかりやすいかもしれない。中国では、長江郷流域を境に北に短粒米[中国では粳(コウ)という]、南に長粒米[籼(シアン)]が分布し、流域一帯は両者の混在地帯とされてきた。それはイネの北上と時代が下るにつれて、短粒米を選択する方向に変化していった結果だととらえることができる。
池上宏氏の反論
第一の問題は、イネのモミ型の問題である。
岡崎が江南からの直接伝来説に否定的で、朝鮮経由説に傾いたのは、南朝鮮経由と見られる石器などを理由としているが、もう一つ注目されることは、「北九州から発掘されるコメの形が、短粒の日本型[梗(コウ)]であり、江南伝来であれば、長粒のインド型[籼(シアン)]が出るはずだ』という理屈である。岡崎が、華北に進んだ稲作がすでに前漢時代からあったことを、朝鮮経由の主張の前に強調したのはそのためでもあろう。「板付遺跡の籾は、日本型のコメとされている。淮水以北でもコメの栽培があったことは認められているから(中略)、山東半島より西朝鮮に伝えられ、さらに日本に流入したという考えに私は傾いている。」と岡崎は結論している。新しい資料をもりこんで書かれた寺沢薫(2000)の著書でも、朝鮮半島から出土するコメは日本型であるから、長粒種(籼)があるはずの長江流域からの直接伝来や華南からの伝来は支持されないと述べている。
しかし、そのような論議は今では通用しない。華南の広西の4000年前の遺跡から今日の日本型と同じようなコメが発見されたことは図でも示した。江南でインド型の長粒のコメが優占的になったのは、・・・・ 時代を下って宋(11世紀)のことであり、稲作の起源地では、野生イネは長粒であって、長粒から短粒種の方へ混在しながら数千年かけて変化していたのである。
(下図はクリックすると大きくなります)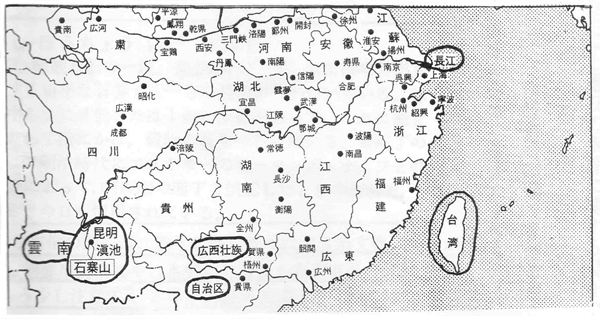
以上のように、日本の弥生時代の文化は干欄式建築とか鵜飼いと南方系文化要素が多くある。これらは朝鮮半島にはない。稲作が直接江南の方から来たと考えてもおかしくない。