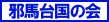 |
TOP > 特集 > 深読み日本史 | 一覧 | 前項 | 次項 | 戻る |
 |
||||||||||||||
 |
 |
 |
 |
|
||||||||||
毎日新聞連載 |
||||||||||||||
「畿内説で決着」でいいのか
|
|---|
 邪馬台国の所在地が畿内(大和)か九州かをめぐる論争は江戸時代から続いている。だが、ここ数年、考古学界を中心に「畿内で決着」とのムードが濃厚だ。昨年出たある論文は「考古学関係者の9割以上が畿内を支持するだろう。九州
説の物的証拠が見当た
らない」と、学界の空
気を表現した。
邪馬台国の所在地が畿内(大和)か九州かをめぐる論争は江戸時代から続いている。だが、ここ数年、考古学界を中心に「畿内で決着」とのムードが濃厚だ。昨年出たある論文は「考古学関係者の9割以上が畿内を支持するだろう。九州
説の物的証拠が見当た
らない」と、学界の空
気を表現した。
だが、畿内説は本当 に確かなのか。 論争の出発点は3世紀の中国の史書、三国志の中の「魏志倭人伝」だ。 帯方郡(ソウル付近)から邪馬台国までの方角と距離が書かれているが、 おおむね方角では九州、距離では畿内と読め、決着が付かない。 それで、「文献からは無理だ」との考古学主導、畿内説優勢 ムードが生まれてきた。 さて倭人伝では、邪馬台国は博多付近の南方にある。畿内説には 具合が悪いから、「南を東」に読み換えるのが普通だ。このため、 邪馬台国の南にあり敵対する狗奴国が畿内の東、濃尾平野に想定さ れたりする。 九州を北に、東北を南に描いた日本列島の古地図もあ り、あながち絵空事ともいえない。 だが、畿内説論者のほぼ全員が口をつぐんでいる一文がある。 ・・・女王国の東、海を渡る千余里、また国あり、皆倭種なり。 女王国東方の海を渡つた所にさ らに別の国がある、ただし、人種は同じ倭人だと言っている。南を東と読む畿内説パターンなら、東は北だ。琵琶湖でも渡り北陸あたりを想定するか。 だが、倭人伝の「海を渡る」は舟でしか渡れない 場合に限定される。これこそ、畿内説では絶対に理解不可能な一文 なのだ。方角の読換えが無理だから、と文献学者は反撃 する。  『九州にある女王国から東に海を渡った所、つまり本州や四国にも倭人
の国があると読むしかない」と、畿内説に否定的
な平野邦雄・横浜市歴史博物館館長は言う。倭人伝の地理的説明は、帯方郡から対馬、壱岐・・・邪馬台国、狗奴国まで、すべて南北の軸線で描かれ
ている。「女王国とは別個の倭人国に触れる時、初めて東西軸を示したのです。著者は倭を東西に分け、東の方は倭人伝では触れな
いと言っているのだと思う」
『九州にある女王国から東に海を渡った所、つまり本州や四国にも倭人
の国があると読むしかない」と、畿内説に否定的
な平野邦雄・横浜市歴史博物館館長は言う。倭人伝の地理的説明は、帯方郡から対馬、壱岐・・・邪馬台国、狗奴国まで、すべて南北の軸線で描かれ
ている。「女王国とは別個の倭人国に触れる時、初めて東西軸を示したのです。著者は倭を東西に分け、東の方は倭人伝では触れな
いと言っているのだと思う」
当時、大和も吉備も出雲も、北部九州同様のまとまった勢力として存在し、互いにに交流していた。 ただし、『倭人伝』記述の対象外だったというのである。 しかも、この一文の意味が後代に生きてくるのだ。唐代に編集さ れた「隋書倭国伝」に次のくだりがある。聖徳太子の時代、隋使・裴世清(はいせいせい)が北九州から瀬戸内海を通って大和に向かった時のこと。 ・・・竹斯(筑紫)国より以東は、 皆倭に属する。 裴世清は大和に行くのだから、 筑紫(福岡県)以東が倭国である のは当たり前のことだ。 なぜ、わかりきったことを書いたのか。中国の史書は前代の史書を踏まえて 書かれることになっている。そこで、最も合理的な説明はこうなる。 「隋書」の著者は「『魏志』は、倭の東方にある国は倭国に属さな いと言っているが、今は状況が変わり、属するようになった」と解 説しているのではないか。 「得手勝手な『倭人伝』の読みで、都合のよい結論を出すようで は困る。(考古学者主導の畿内説が)ここまで進み、反論しておか ないどダメだ」と平野館長。 「畿内で決まり」だとは、とて も思えないのだ。【伊藤和史】 |
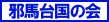 |
TOP > 特集 > 深読み日本史 | 一覧 | 前項 | 次項 | 次回 | 戻る |