|
畿内説の主張 |
様々な研究者の見解を集めたので、邪馬台国は畿内にあったとする点では共通ですが、その他については、同じ項目の中でも、必ずしも意見が統一されてないことがあります。 |
地理的・政治的状況

 国家統一の状況

 倭国の大乱

女王卑弥呼

 卑弥呼の鏡

 邪馬台国への道のり

邪馬台国の方角

 邪馬台国への日数・距離


倭種の国邪馬台国の人口狗奴国投馬国

 地名

 記紀の神話古墳・遺跡

 遺物

 |
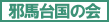 |
畿内説 | 上へ | 親頁 | 戻る |
|
畿内説の主張 |
様々な研究者の見解を集めたので、邪馬台国は畿内にあったとする点では共通ですが、その他については、同じ項目の中でも、必ずしも意見が統一されてないことがあります。 |
地理的・政治的状況

 国家統一の状況

 倭国の大乱

女王卑弥呼

 卑弥呼の鏡

 邪馬台国への道のり

邪馬台国の方角

 邪馬台国への日数・距離


倭種の国邪馬台国の人口狗奴国投馬国

 地名

 記紀の神話古墳・遺跡

 遺物

 |
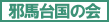 |
畿内説 | 上へ | 親頁 | 戻る |